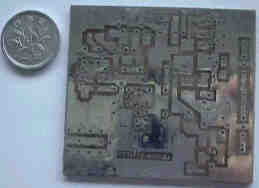 基板
基板  完成
完成 Microwave Handmade
| 局発(ローカルオシレータ) | 1ボードトランスバータ | 検出器(パワーチェック) | beaconの製作 | 失敗のお話 |
順次、それぞれについてupして行きます。
局発(ローカルオシレータ)
手作りのトランスバーターを作るときの心臓部分は、ローカルオシレーターと言って過言ではないと思います。
ここでは、基本水晶発振子からの逞倍で行う局発と、VCO等の発振に基本周波数で制御するPLL方式の局発との2つを紹介します。
特に、PLLの局発については、盛んに出回ったドレークの2GHzのコンバーター(2880 type)を中心にして紹介します。
・基本水晶逞倍式局発の制作
局発(きょくはつ)とは、早い話が発振機です。水晶で無くても良いのですが、安定度や価格その特性から現在の所単純で水晶発振子が1番優れていると思います。後述のドレークのコンバーター等も安価で非常に便利ですが、その特性は、比較すべも有りません。(自励発振は、ご勘弁を・・・・・・(ATVならこれでも良いが・・・)\(^^;)...マァマァ)
水晶発信子の選定。
一般に、2Gや5G・10G等は、どんな周波数の水晶が必要なのでしょうか?
トランスバーターを制作する場合、親に使用するトランシーバーの周波数によって水晶の周波数を選定しなければいけませんが、一例として下記の様に成ります。
| バンド | 2G | 5G | 10G | 24G | 47GHz |
| 144MHz | 1140MHz 2逞倍 |
1123MHz 5逞倍 |
1121.66MHz 9逞倍 |
1137.142MHz 21逞倍 |
1117.142MHz 42逞倍 |
| 430MHz | 995MHz 2逞倍 |
1065MHz 5逞倍 |
1090MHz 9逞倍 |
1123.33MHz 21逞倍 |
1110.23MHz 42逞倍 |
| 1260MHz | 1140MHz |
1120MHz 4逞倍 |
1120MHz 8逞倍 |
1137MHz 20逞倍 |
1040.90MHz 40逞倍 |
| 2400MHz | ------- |
1120MHz 3逞倍 |
1120MHz 7逞倍 |
1080MHz 20逞倍 |
1116MHz 40逞倍 |
上表は、あくまで一例ですが、これらの周波数の局発を制作する事で、それぞれの親機で目的のマイクロバンドのトランスバーターを制作する事が出来ます。
例えば、上表の周波数の局発を制作するとすれば、(1120MHzとする)基本発振が56MHzや46.66MHzの水晶などを選択する事になる訳です。
56MHzの水晶発振子を利用する場合それを40逞倍することで目的の1120MHzを得ることになります。
28MHzの水晶でも1120MHzを作り出す事は可能ですが、逞倍数が多くなり芳しく有りません。
高い周波数を発振出来る水晶で、逞倍数が少ないに越したことはないと思います。
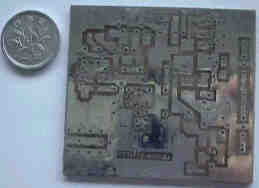 基板
基板  完成
完成
写真の基板は、西新潟クラブのJAφDFR局のデザインした局発基板です。
両面のガラスエポキシ(G10)でも1GHz程度の周波数なら十分に使用出来ますから、このような局発基板を作っておくと、色々な周波数に汎用できてFBです。
ただ、50MHz程度の周波数から逞倍して1Gクラスの局発を制作するには、数段の逞倍・増幅が必要ですから、それに使用する共振回路のコイルやフィルターに何を使用するか考慮しなければなりません。
200MHz程度までなら、FCZのコイル等でも十分ですが、500MHzや1GHzでは、業務用の物が数社から出てますから、それを利用したほうが手っ取り早いでしょう。(東光のコイルなど)
また、これらの増幅には2SC2367や3603などのトランジスタで十分で、上記の局発では、1GHzで50mW以上得る事が出来ます。
制作のポイントは、1段毎に予定の周波数の出力を確認して次段に進む様にする事で失敗のほとんどを防げます、スイッチポンの一発で目的周波数を得る事は困難な事です。
格段のチェックは面倒でしょうが、後々のトラブルで費やす手間を考えれば、絶対に格段のチェックを行なうべきでしょう。
簡単な検出器やカウンターがほしい所ですね。
・VCOをロック・PLL局発(ドレークコンバーター
2880type)の制作
※ドレークコンバーターについての問合せが非常に多くて驚いています。
AO−40が稼動はじめたのが、大きな要因のようです。もう少し詳細を記述したページも用意しましたの参照してください。
誘電体などを利用した発振回路は、そのままでもATVなどには直ぐに利用できますが、ATVに比べ帯域が狭いFMやSSBモードではそのままでは利用できません。
しかし、基準発信機の周波数と比較して制御する事で、安定な局発を制作する事が出来ます。
いきなり高い周波数を発振するVCOは、最近比較的容易に手に入れることが出来るようになりました。
また、その発振周波数を制御する回路もコンパクトに一緒になっている、ドレーク社のコンバーターが近年たくさん出回り、その恩恵をこうむった方も多いと思われます。
そこで、ここでは今も手に入れやすいこのコンバーターでの局発制作についての概要を紹介したいと思います。
改造に際しての、基板などはセプロン電子の基板を利用して行うと、作業が非常に簡単に行えます。
 5GHz用の2段基板
5GHz用の2段基板
コンバータ概要
ドレークのコンバーター(2880typeと言うそうです。)は、小さいダンボールケースの中に入っており、マストなどに取り付け様のUボルトと一緒に梱包されてます。
ケースは水色で塗装されており、12本のビスを外すと蓋が外せます。
防水用のゴムパッキンも当てられています。
シールド用の、アルミ板なども簡単に外せますから、改造する方は外しておきましょう。
改造後は、またシールド出来れば使います(水晶の形状等で使用できない事が有ります。)が、無理に使用することは有りません。
改造手順
1.まず、N型とF型のコネクタを外します。
N型はビス、F型はネジになってますので、基板側のハンダを外した後にそれぞれ順に外します。
F型の方は、コンタクトピンがわずかにハンダ付けされているだけですから、ハンダをはずさなくても、モンキーで回していくと自然に取れてしまいます。
2.基板はビスで止まっています、3端子ICのビスなども外すと、ケースから自然に外れるはずです。
小さいビスも有りますから、良く見てはずしてください。
3.取り外した基板は、2つに切断する必要があります。(そのまま2GHzで改造する方は切断の必要は有りません、後述の水晶取替えだけでもOK)
三端子ICが付いた所を下側にすると、ちょうど半分にした感じに切断しなければなれません。
利用する部分は、VCOとPLLや電源部分ですから、この部分を壊さないように切断します。
(この部分で2GHz帯を直接発振しています。)
基板中心部には、アースラインが有りますが、そこで丁度切ることになります。
セブロン電子などの基板は、ちょうどよい大きさに作って有りますから、裏から切断ラインをケガキ「エイ・ヤ・・・」と切ってしまいます。
コツは、壊れるかと思ってビクビクしないで、思い切って切りましょう。
切断には、普通の金ノコで十分です。
4.切断した、2G部には良く見てみると、利用できるパーツが一杯ついています。
上手になると、全てこの部分からパーツが調達出来ますから、捨てないで下さい。とくに、SFC11等のデバイスは、そのまま外して利用しましょう。
SFC11・103等のチップ抵抗・数十pFのチップ結合コンデンサ・千pF程度のチップバイパスコンデンサは上手に外しましょう。
5.切断して利用する部分は、ヤスリなどで切断面を処理します。また、基板裏の電源ラインのリード線も外してしまいます。
切った部分と改造基板が、ケースにすんなり収まりましたら、元のようにビス止めします。
ただし、改造基板は、切断部分のアースラインと接続するように、ハンダの吸い取り線などを利用してしっかりと接続しましょう。
ここが、しっかりとつながっていないと、異常発振したり・パワーが余り出てきませんのでノウハウの1つでしょう。・・・(^o^)丿
最初に外したN型コネクタもそのまま、再接続します。(SMAコネクタに付替えるときは、タップでネジ切りを行いコンタクトの長いものを利用しないと基板まで届きません。)
F型コネクタの穴からは、電源リード等を入れるようにします。
周波数可変用のリード等も、この穴を利用したほうが良いと思います。
6.ケースインする前にパーツを付けても良いのですが、インしてからで十分OKです。
手慣れた方は、基板を見ただけで、パーツの配置は分かると思いますが、初めての方などは、以前にこの基板を紹介した記事が載っている西新潟クラブの会報等を参考になさってください。
じつは、基板も4480MHzの物と5760MHzの2種類が有ります。4Gの物は1段で、その後フィルターで4Gを得るように成っており、4480MHzで7dbm程度出てきます。(調整によっては10dbmを期待できます。消費電流は110mA程度)
5G用のものは2段構成になっており、調整によっては、5760MHzで20dbm近く得る事が出来ます。(この時の消費電流は150mA程度)
FETに関しては、いずれもゼロバイアスで動作させるようになっていますが、大きな問題は出ないようです。(スタブを立てて調整しますが、深追いするとデバイスが・・・(^人^)ナンマイダァ)
7.水晶についてですが、2Gを1/256の周波数でロックしていますから、4480MHzが必要な場合は、1/2の2240MHzの1/256の8.75MHzの水晶発信子が必要になります。
水晶選定の一例
1140MHz 1920MHz 2002.083MHz 2240MHz 2274MHz 2425MHz 2560MHz 4.4532MHz 7.5MHz 7.821MHz 8.75MHz 8.8829MHz 9.4727MHz 10MHz 2G osc 5G beacon 24G beacon 5・10G osc 24G osc 2G beacon 10G beacon
oscとあるのは、局発に利用した場合の水晶選定の一例で、beaconとあるのは、そのままそのバンドの送信機とした場合の水晶選定の一例です。
※ 2G帯から外れた周波数を発振させる場合は、VCO回路の発振回路を微改造する必要が有ります。LとCの値を触ります。
上表で10GHz(10240MHz)が2560MHzの4逞倍で、丁度得られる事が分かります。10MHzの水晶なら特注しなくてもお持ちの方は多いでは・・・・・φ(.. )メモメモ
7.5MHzの区切りの良い水晶でも、1920MHzの3逞倍で5GHzのビーコンが作れますね。
北陸マイクロの管理する10GHzや5GHzビーコンは、この方式です。
元々付いている水晶は、少し高さが低い水晶がついていますから、通常の物をそのままつけると蓋が閉まらなくなってしまいます。
足を長くして曲げるか、水晶の頭を削って低くするかの工夫が必要です。
さらに、この回路では少し高めの周波数でロックが掛かるようで、特注の水晶を注文する場合は注意しましょう。
回路に入っているトリマでも周波数を可変できますが、更に数pF〜数百pFをパラレルにする事で、1MHz程度の周波数を下方に変化できるでしょう。この変のテクニックは、ビーコン作成のときなどには有効です。
しかし、余り下げすぎると、発振が止まりますから欲を出さない事です。
(この作業は、電源をon・offを繰り返し間違いなく発振する周波数に留めてください。電源onで調整時は発振していても、いったんoffし再度on時に発振が止まる事が有ります。)
有効な方法として、数pFのエアトリマ(バリコン)を入れることで、VXO(CXO)的に出来ますから、トラスバーターの局発に利用するときは、入れてみましょう、数KHz〜数十KHz可変できることは非常に便利で、その安定度の良さに驚かされるかもしれません。・・・空気は馬鹿に出来ません・・hi
8.作った物をスペアナ等で見ると、やはり水晶での局発とは、特性が比べ様も有りませんが、意外にきれいで、10GHz程度まではSSBでも使用できそうです。通常は信号とノイズのレベル比が45dbは取れます。
さらに、シールドを施す事でスプリアス特性も改善できますから、最近では75GHzでもこのドレークの局発を利用している方を見かけます。また、電源の三端子を10Vから8Vに交換する事で電源三端子からのノイズや異常発振を防げますから、安定な局発として利用する方はこの対策も必ずしておいた方が良いでしょう。
 完成した4480MHzのドレーク局発
完成した4480MHzのドレーク局発