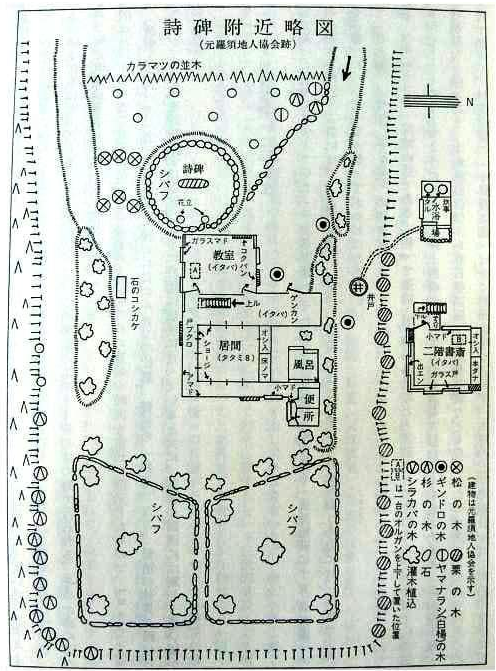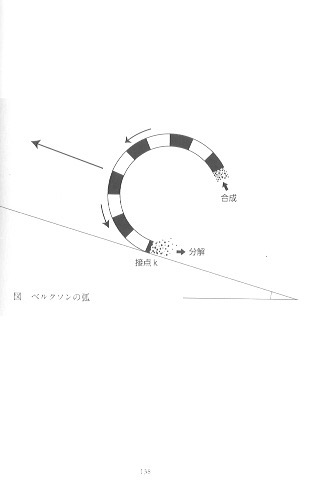「姿勢とは、私がこの世界に存在し、世界に触れている、その形である。
これは、主に人間関係における、いわば水平方向における身構えの形
の一つだが、人にはもう一つ垂直方向に立ち上がってゆく力における、
さまざまな在り方がある。」(竹内敏晴)
故郷に立ち返るお盆の墓参り。1972(昭和47)年の暮れに小矢部市埴生から富山市高屋敷に引っ越して以来、平成の夏の台風の豪雨で一度見合わせたくらいだったのに、令和元年の猛暑が年老いた夫婦の外出をためらわせた。
庭の雪吊も要らなかったような春先、天気が良ければ彼岸をえらんでお参りしてこようか。夫婦いずれからともなくこと葉を交わしていたところへ、巷では新型コロナウィルス感染騒ぎによる外出自粛の足止めをくらいそうな雰囲気が。
富山駅を西に向かう列車に乗り込み、神通川、庄川、小矢部川と車窓を三枚めくって富山県西端の石動駅で下りる。目前を横切る県道の向こうのT字路を横カバンに厚歯下駄を履いて中学通いをした旧目抜通りまで行かず、駅前からすぐ西南へ向かい、嘗て福野高校へ通った加越能鉄道の廃線跡でもある道を野端に抜け、幼少期の遊び場の一つだった製材所を右の山側に入るように折れ、少し上った先で左に雑木林を抜け登った頂が吉田家二代の墓所だ。
1年分の落ち葉をかき分けるように耳をすませば、半世紀を超えて身体を吹き抜けた風の来し方行く末を俯瞰するような鳥の冴えずり。雑木に覆われ南東に広がる散居村の向こうの立山連峰も見通せない。陽当たりが良かった斜面の畑や山間の水が冷たかった田んぼへの曲がりくねった道筋も朧げな景観のはるか向こうへ往時の暮らしぶりとともにかき消されそうだ。
石動町の西へ、埴生護国八幡宮前でL字型に折れる街道を挟んで民家が並ぶ埴生の入り口の製材所から新しくできた小矢部福光道との分岐点を右に旧街道を入ってすぐ右にカーブする手前左側にわが家、その数軒手前右側に家業の精米作業場があった。グーグルマップでズームインしてもその痕跡すら見分けられない。手作りの仮想ドローンでも飛ばしながら遡行してみたくなる。
祖父の直次郎(1879[明治12]年7月31日〜1975[昭和50]年7月25日)にその妻(生没年も名前も不詳)、そして母の友栄(1920[大正9]年4月18日〜2010[平成22]年4月12日)と父の正作(1912[明治45年・大正元]年〜1945[昭和20]年4月18日歿、享年33歳)が眠る墓石には1922[大正11]年と刻まれている。おそらくその年に43歳で祖父は妻を亡くしたのだろう。姑と一緒に暮らしたことのなかった母が聞き知った近隣住民の噂話では、髪を結った着物姿でキセルタバコを嗜み、料理や家事などすべて祖父任せだったらしい。祖母の姿形や氏素性もはっきりせず、家政の切り盛りに疎かったのかあるいは病弱だったのかよくわからないなりに祖父から大事にされていたらしい。
とっくに廃校になった埴生小学校から帰ったある日こと、いつも祖父さんが座っていた囲炉裏の上座に女の人が座っていた。“瓦山”といって登り窯が珍しく遊び場の一つでもあり、家ぐるみ貰い風呂したような仲だった瓦職人の家のおかみさんだった。なんでも離縁されたとかで、とりあえず貧乏我が家に身を寄せたらしかった。元芸者だったらしく眼を泣きはらしてキセルタバコを燻らしながら時おり愚痴をこぼす姿が見えなくなるまで、当たり前のように居候させる祖父の姿に亡き祖母の人となりが気になったりしたが、いつの間にか“瓦山”のおばさんが行方知らずになったように、祖父の口から語られたことは一度もなかった。
家風呂は未完な家族の象徴のように壊れたままに放置され、精米作業場の裏手に小川を挟んで建っていた村の共同風呂は利用したことがなく、近所の遠い親戚の子どもが夕方近く風呂においでと誘ってくれる両家の釜風呂を交互に家族ぐるみで使わせてもらう習わしになっていた。貰い風呂が立ち消えになった瓦職人夫婦は子持たずだったようだが、なんで離婚に至ったのかなんて幼い耳では知る由もなかった。
いつもの近所の二軒の貰い風呂上がりには兼業と専業百姓家族それぞれの子どもらと遊んでから夜道を家族一緒に帰ったが、昼日中につるんで遊んだ子どもらは違う家の家族だった。とある昼下がりに兼業農家の子どもの家の裏手で遊んでいて、いかにも勤め人の父親を誇らしげに語る様子になじめない自分を見つけた。虚弱児の貧乏暮らしなんて当たり前で気にもならないのに「父」がいない片親暮らしの何が不足なのかわからないまま、帰った家の囲炉裏端を煙管で叩きながら煙草を燻らし胡座をかく祖父の緘黙が匂った。
1941[昭和16]年2月に里帰りした高儀の母の実家で生まれた姉はおぼろげながらも京城から引き揚げるまで住んでいた朝鮮総督府の官舎で父に抱っこされた胡座や無精髭の感触を話せたが、京城生まれで2歳下の弟にはそんな体感記憶のかけらもなかった。3歳でようやく掴まり立ちさせてもらった引き揚げ先の埴生の縁側から覗いた富山大空襲の夜空や、父や祖母の月忌参りに訪れた僧侶の胡座の心地のほか思い出せない。立って歩けるようにならないと幼児の体感記憶は残りにくいのだろうか。
就学前の体感記憶といえば何と言っても5歳になった誕生日の晴れた夕刻の[福井県の]大地震。家の前の街道のカーブのところで歩けず立ちすくんだ背後からしっかり抱きかかえられた。あやすような声とぬくもりから数軒右隣のまだ腰の曲がらない婆さんとわかった。おそらく買い物か何かで出かけた母は荒物屋の前で歩きにくくなり竿竹に陳列した薬缶など金物商品がぶつかり合う音を警鐘のように聞いていたようだ。そのとき祖父さんや姉さんはどうだったか憶えていない。
家の中でびっくりしたのが日にちまで覚えていないが、鉄瓶が懸かった囲炉裏に落ちて灰神楽になったこと。左肘のあたりにいまでも火傷の跡が残っている。下腹にもあるが母によれば寝間着がはだけた肌に直に“湯たんぽ”が当たった際のものらしい。幼児期の火傷体験は身体的な混沌として我が身に残っている。あのとき、水で冷やすより、熱いお湯で温めるべきではなかったのか?
その頃で身体生理的に忘れられないのが祖父の癇癪というか打擲だろうか。自分のことは覚えがないが、素っ裸で雪の庭に放り出された幼い姉さんのこと、とりわけ火吹竹が割れるまで殴られながら頭や顔をかばって紫色に腫れあがったた母の二の腕の痛々しさ。いつの間にか腫れ物に触るかのように祖父の機嫌をうかがう日々、野良仕事から帰った祖父が背戸の戸を開ける音にビクつき、小言が聞こえたりしたら母子三人“低気圧”が近づいたかのように目配せしあった。そして暴発したらとにかく鎮まるまでやり過ごすしかなかった。小言は多めでも普段はいばりちらすなんてことも無かったのにあの豹変ぶりはどこからやってきたのだろうか。今風の「虐待する祖父」という存在だったら孫の自分も同様に振る舞われていたに違いなかっただろうが、当時の祖父の「暴力行為」の風当たりは家族間の性差によって違ったものになっていた。
引き揚げ先が違っていたらとか父が生き残っていたらなど逃げ腰になったり、生前の祖母や父も「折檻」されたんじゃないかという疑問も芽生えたりした。朝夕のお勤めを欠かさなかった祖父は、「おぼくさん」を供えた仏壇の前で孫二人も合掌してからでないと朝飯を食べさせてくれなかったが、妻を亡くすまでの10年余りで授かった一人息子の場合はどうだったんだろう。息子の嫁にしたように妻も打擲したんだろうか。明治末30歳頃に埴生の地で所帯を持つまでの足取りがまるで謎だが、40歳で10歳の息子と暮らすことになった戦前の父子家庭の毎日から、その後の息子の朝鮮行きが芽生えたのだろうが、そんな経緯がわかりそうな手がかりひとつ残されていない。
還暦も過ぎ越した敗戦の数ヶ月前に埴生の住いに京城で殉職した息子の遺族を迎え入れ養うことになった祖父と、夫を失い暮らしの場が外地から「敗戦」をはさんで内地に急変した母子が協働して営む暮らしに生じた「違和」も祖父の老いとともに薄らぎ「好好爺の家族」にさまがわりしていったようだった。地元の農作業環境の変化によって精米業もたたんで三反百姓仕事にいそしむだけになったていたとある日、大学の附属図書館で働きながら経済学部に併設されていた夜間短大に入学してできた男女数人の学友が訪れたなかには、祖父をニコニコした老人の置物みたいだったと評した者もいた。
訪問者のひとりだった女子学生Dと仲良くなり山沿いと海沿いそれぞれの家を訪れたりするほどになっていた仲が破談になる出来事があった。もう結婚など縁がないと思い決めていた数年後に学友じゃない文通知人だったEと川沿いの建売団地で暮らすようになってから、結婚前にDから呼び出された喫茶店で「結婚」を思いとどまるよう諭されていたことを知った。
当時の祖父の居住まいや暮らしぶりから何を感じ取っていたのか、とにかくあのような爺さんを抱えた家に嫁ぐべきじゃないと言わせるような事由があったのだろう。偏屈で意地悪な存在として映るような事があったのだろうか。それぞれが訪れた際には、田舎の老人特有の笑顔で眺めるだけで、ことさら言葉をかけるでもなく、付き合っているのを分かっていたようで、採れた野菜や花などをDの勤め先に持って行かせたりした。
Eの父がアル中で自宅療養していたのを見計らい、双方の片親姉妹が顔合わせしただけの簡素な結婚の次第を祖父は問いただしたりせず、週末に訪れたEに柿やイチジクや栗など庭の産物を持って帰らせたりしていた。
Dが住んでいた海沿いの砂丘の集落の二階家をはじめて訪れ、居間の長押をぐるっと賞状が取り巻いていて唖然としたというか、なんだか額縁で鉢巻されたような心地だった。同居の兄は独身で身体障害があり父は病がちで娘の結婚を機にどう家を継ぐかが切実というより具体性をおびたりするうちに交流は途絶えた。
Dと同じ高校を卒業していたEのお袋さんの弔問で訪れた借家も、父親の仕事の都合で17回目の引越し先となった団地の建売住宅いずれも平屋で、上がりこんで見回した長押には飾り物ひとつなく、目についたものは生花だけだで、アル中の治療で病院と自宅を行ったり来たりの父親と妹の三人家族の家政の切り盛りで手いっぱいの様子だった。
そんなEとの出会いからお互いの職場に通勤可能な富山市内の土地を探し家を構えるまでに数年の歳月を要した。おそらく母の同意は得られるとしても、狭い山林を見捨て、埴生の宅地や田畑を売り払い富山市の郊外に生活の場を移す事を祖父が納得しれくれるかどうか身構えざるを得なかった。背戸の庭木の松を根切りして移植の準備が整ってきた頃合いに、「この歳になっては孫についていくしかない」と97歳の祖父が同意してくれた。あとは新築と引越しに必要な諸経費をどう賄うかが問題だった。(2021年1月27日公開)
続・本の一言:街道と民家(2)祖父と巾着
「まあ、どのような病や怪我でも上手く経過させてゆくこと、
それも自然に経過させてゆくことが何よりである。」
(光岡英稔@ツイッター)
祖父が生まれた1879(明治12)年といえば日本全国にコレラが大流行[約10万人死亡]したようだが、埴生からほど近い松永でおそらく農家の次男として芽生えた「我」の容れ物として、身体的に両親や兄弟からどのように揉まれ[躾け、仕置き、しごき、折檻などにさらされ]ながら育ち、尋常小学校を経てから、大阪で如何なる丁稚奉公をしていたのか、詳しい話は聞いた覚えもない。口癖のような「公界をわきまえろ」という矜持が祖父の大我と小我を行き来するうちに「来し方行く末など語るほどのことでもない」に収斂したのだろうか。
昭和のはじめごろの東京では丁稚奉公制度に反対して「殴らないこと」名前に「どん」をつけないことなどを要求した42名の少年店員による争議があったようだが、明治中期の大阪での祖父も「直どん」呼ばれてぶん殴られたりして良い思い出などあったのかどうか、1912(明治45・大正元)年に息子(正作)を授かるまでの暮らしの足取りなどまるっきりわからない。
互いに家族の誕生日を祝って囲炉裏端で一家団欒など稀な埴生で、引き揚げ母子家族が棲みついた小作りな家構えは百姓家というより商家向きだった。近隣の住人からは「直ま」と呼び慣わされていたようだが、子ども心には愛称というより蔑まれているように響いた。ほかに「〜さ」の誰それなどと言い習わされたりしている家もあったりして、小学六年頃からはじめたヤクルト配達で知った屠殺や廃品[鉄屑]回収業者の集落を蔑むような物言いに同調しているように感じた。集金の際などに垣間見た暮し向きを感じさせないそんな集落の家の対応には風評とは相容れない柔らかな奥行きがあった。
街道に面した埴生の我が家は土足のまま背戸に通り抜けられる風通しの良さがあった。
玄関の内開きの大戸の左端に拵えた引き戸をくぐると土間の左手が小さな商品棚を置いた板の間と記帳場になっていて、そこを細かい縦桟の障子戸で仕切った奥が母の居間になっていた。反対側の板壁を隔てて納戸があり、続く茣蓙を敷いた板の間[兼食事処]の障子戸を挟んで、竃と井戸と流しが並んだ板の間の背中側には食器棚の隣に米や味噌の甕が並ぶ台所だった。そこを下りた狭い土間が焚き口になった風呂と脱衣場の隣が大小便所だった。背戸の引き戸を開けた左手に手水鉢があり、祖父が剪定する庭木や植え込みを囲い込むように傾きかかった小さな納屋と鶏小屋が連なっていた。納屋の土間には薪が積まれ、漬物樽や農作業や大工道具などで足の踏み場もない狭さだった。
百坪足らずの敷地の小柴垣で仕切った西南側には榛の木や栗の木や桐の木などが並び立ち、午後の日差しを遮る下が薪割り作業場になっていて、中学生になると薪割りを祖父に手伝わされた。薪材を相手に見よう見まねで斧や鉈の使い方を覚えさせられたが、ルリボシ以外のゴマダラその他のカミキリムシとのたまさかの遭遇ぐらいが楽しみで、なかなか道具と体との相性の良い使い方がのみこめず、指が擦り剥けたり腰がギックリしかかったり虚弱な我が身の自覚が部活の剣道部へ向かわせることになった。寒稽古や暑中稽古も休まなかったが、当時130cm30kgの体が少しは大きくなった程度で、肝心の技の上達にはおよばなかった。ただ力まかせに斧や竹刀を振りまわしていては、やたら疲れるだけで、会得すべき事柄から遠ざかるばかりだった。
背戸の庭の東南側に広がる他所さまの田畑との境界に植えられ無花果や柿の木のあたりは花菖蒲や仏壇用の花などが咲き乱れていた。祖父は寝所にしていた座敷の床の間に常置した息子の遺影の前の台座に「仁清」の香炉を据え、明かり障子の傍の「木米」の花瓶には花を絶やさにようにしていた。ほかに青瓷の水指や花瓶などの蒐集品が飾られたり、古九谷の揃いの食器など祭りの御膳限定だったが、晩酌用の酒器だけは普段使いされていた。お気に入りの蒐集品を手にした祖父の講釈を聴き分けられる耳も目も縁がなかったようだった。とある独り居の日中に訪ねてきた骨董屋らしき御仁に、祖父さんが持ってるはずの刀の鍔を是非見せて欲しいと迫られ、父の遺品の「軍刀」一振りしか知らない孫は応対に困り果てた。
手にした小金をすぐ株券に換えて母を困らせていた祖父は、金になるものならなんでも投機の資金繰りに充てる癖があったようだ。道理で埃だらけの納戸にはガラクタばかりしか残っていなかった。月忌に訪れていた檀家の住職は残った数少ない骨董品を愛でていたようで目敏く、床の間以外で飾ったりなどもってのほかだった。祖父の供養になるよう夏の通夜の祭壇に前述の香炉を使ったときなど真っ先に片付けさせられた。前年の秋にさりげなくLPを聴いていた部屋に入って来て、いかにも安心したように飾り棚の愛蔵品を指差し、よろしく頼むと言われていた骨董のひとつだった。同じ頃に盆栽など鉢植えの植え替えのお世話はできませんとお断りした妻には、そうかと頷いて無理強いすることもなかった。
お年玉以外に小遣いなど縁がなく、小学校へ収める現金に事欠いたりしがちな家計の足しというより小遣い欲しさに雑木担ぎや山菜採りや酢の瓶詰め作業などもやった。夏休みの古綿打ち直しの収集アルバイトは近所の店の主人が業務用自転車を貸してくれたが、町のヤクルト配達業者はそうはいかなかった。
早朝アルバイトにあまりいい顔をしなかった母の口利きが功を奏したのか、晴れた学校帰りの午後に足を踏み入れた玄関の土間の左手の板の間に、祖父が手配したのであろう村の自転車屋が部品を寄せ集めて組み立てた一台に小躍りした。祖父に手を引かれて出かけた石動町の祭礼で、ブリキ製の舟の玩具“ポンポン蒸気”を買ってもらった喜びに勝ったようだった。
代金領収も配達担当ということで祖父は集金用に「巾着」をくれた。落としたりひったくられたりしないようにとの気遣いからだったろうが、複数だった配達集落が地元の埴生だけになった頃に集金済みの巾着袋を失念したことがあった。薄暗くなるまで集金先の道筋をたどりなおしても見つからず、家に居合わせた誰かに尋ねるより数少ない部屋という部屋を探し回ったあげくに母の部屋のミシンの上で見つけた。集金から帰宅後に家のどこかでうっかり落としたか置き忘れたのを見つけた家人が何気なくそこに置いたらしく、安堵の思いで握りしめたら祖父手製の巾着ではないのに使い古された祖父の手触りに見いだされた気がした。
鍋敷きや盆などの木製品から屋根や家屋の修繕まで、祖父は日頃から集めておいたそのうち使えそうな「ガラクタ」類を利用してなんでもやってのけようとしがちだった。たまに手伝わされたが上手くいった時などけっこうご機嫌だった。魚や鳥などの食材の扱いだけでなく、木の根っこや瘤などに手を加えて飾り物に拵えあげた一品などいまだに残っている。
祖父から明治後半期に大阪で奉公していた頃の話だけでなく年季が明け帰省した埴生で家を構え田畑を耕しながら精米業を営むにいたった経緯など一言も聞いた覚えがなく、とにかく老齢で受け入れた引き揚げ母子家族ともども戦後を生きのびるのにせいいっぱいだったのだろう。明治末期に奉公先の大阪から出戻った埴生で所帯を持ち、長男を授かったのが1912(明治45・大正元)年、祖父33歳の頃の田舎での暮らし向きを振り返ったりなど、埴生から高屋敷に引っ越してからの3年間もとにかく昔語りに縁のない老人だった。ただ一度だけ「埴生の家に帰してくれ」と喚かれて往生したことが忘れられない。たまたま我が家でアル中療養中だった義父と家族で囲んでいた麻雀卓をひっくりかえされたときのことだった。すべて売り払ってきた経緯をなんとか納得してもらえて良かったが、年老いて住み慣れた土地を離れさせたことの重大さを思い知らされた。
1890(明治23)年前後の経済恐慌で米価が高騰して大阪でも餓死者が出たり、濃尾大地震(M8.4)で14万2177戸が全壊して7237人が亡くなっただけでなく、震災後の岐阜県を中心に農民騒乱が起こったり、日清戦争の影響で活性化した景況下で従軍兵士によるコレラの国内感染拡大に続いて、麻疹、天然痘、赤痢、腸チフスや肺結核の感染流行による死者も多かったようだ。1896(明治29)年6月の三陸沖地震(M7.6)による大津波で1万390戸が倒壊し2500余戸が流失して2万7122人が亡くなり、翌7月の新潟の大洪水では1万余戸が流失破壊され2500戸が浸水して78人が亡くなっている。
おそらく『大阪毎日新聞』が大阪で奉公していた頃の愛読紙であったろう祖父は埴生の地でも『毎日新聞』以外は見向きもせず、地方紙との併読などもってのほかだった。どうせ「株式欄」しか用がないのにという母の常套句だったが、朝刊が祖父の手を離れてから回し読みする習いだった。埴生の家庭のほとんどが地元紙しか読んでいなかったのに祖父がそのこだわりを手放したのは晩年に高屋敷へ引っ越してからだった。おそらく十数年に及んだであろう祖父の大阪での生活環境と共棲した青少年期に、当時の〈新聞〉をとおして世相を見聞きし感じた〈反響〉のような何かを、出戻った埴生での生活を律する内部の〈声〉のように大阪弁で響かせることはなかった。
富山弁で叱られたり、小言の多かった祖父の声から遠ざかった今なお読経の響きだけは、埴生の家から持ち越した仏壇を置いた四畳半に残っているような気配がしたり。日々めくりにめくって表表紙や和綴じ半ばのページがボロボロに千切れかかった小本『眞宗 在家勤行集 全』の奥付に富山市の守川聚星堂は編集兼発行�1918[大正7]年3月20日発行とあるが、その数年後に妻を亡くしたあたりから勤行が習慣になったのであろうか。ちなみに1964[昭和44]年に買い直されたであろう同書型の『寺院兼用 眞宗改定 在家勤行集 全』も裏表紙やページ半ばに指跡の穴が開いて縁が擦れたりしている。
朝に朝刊を、夕べに経典をめくるまでの日々の農作業などで働き続けてきた関節痛で曲がった手指で囲炉裏の縁や畳や箱御膳そのほか、手じかなものを叩きながら諭すような語り口も遠い存在になってしまった。
村人との寄り合いというか宴席で諍いになり、近所の人に宥められながらも激昂おさまらず褌一本で帰ってきた祖父の姿。夜半に精米所の鍵をこじ開けられ、精米が済んで預かっていた近隣者の叺が盗まれた時など、残りの叺を盗りに来るのを予想して村の駐在さんと張り込んだ捕物譚をひた隠しにした祖父の立ち居振る舞い。柿の木から落ちて1年半ほど寝込んだ時も頑なに医者にかかろうとしなかったり。70歳以上無料の老人医療費制度には無縁だったけど、痛いだの痒いだのどこか病あぐらしそうながらも病院嫌いを通した老半生(青壮年期は分からないが)。高屋敷に越して3年目に寝込むようになり、急遽往診に来てもらった女医さんは、高齢男性にしては珍しく消化器系も循環器系も問題が見当たらないようで、普段の祖父の食事内容などを家族から聞き取って帰られた。
虚弱な孫には何かと滋養強壮になりそうな物をあれこれ工夫して食べさせたように、祖父は好き嫌いなく家人が食卓に並べた和・洋の料理をことごとく入れ歯で食べ、酒は言うまでもなく魚や昆布などをとくに好んだ。
体調が不良な祖父の場合はとにかく寝て身体を休めること。春夏秋冬の昼寝は欠かさず、馴染みの行商の売薬を服用することはあっても往診医の診断を頼らず、医療に対して臆病なのか無頓着なのか、灸で関節痛を鎮めようとしたほかいわゆる生活習慣病[の区別も分からないが]には縁のない暮らしぶりをまっとうした。
母の介護暮らしを担当してくれたケアマネらは時系列で係累の病歴などを聞き取った際に、祖父のことを充分でない医療時代を生き抜いた「スーパー老人」として一様に評しただけで、人それぞれ社会的な構成力、人間関係の場を生きる〈病〉の問題に言及しなかった。戦争に駆りだされるような権力とは縁が薄くても、祖父の両肩には成人期や老人期を生きぬく重力が働いたであろう。なのに「老人病」や「成人病」などに悩まされずに済んだのはどうしてだろう。(2021年3月2日公開)
続・本の一言:街道と民家(3)引き揚げて
「『ですから、いま新興の団地が日本のそこここ
に生まれているように、そしてまた団地の中に
学校もマーケットもあるように、日本中の小都
市とすこしも違わない日本人の町が朝鮮中に出
来ていたのです。そして、そこで生まれ育った
子どもたちは自分が暮らしている所は日本であ
ると認識していました。おまけに肉体労働はみ
んな被支配民族がしていましたから、開拓はお
ろか、買い物も配達してもらい、掃除もお手伝
いさんがし、学校帰りがおそくなれば迎えに来
てもらいました。罪深さにおいては、移民や開
拓団の比ではありません』」
(森崎和江)
街道を挟んで数軒筋向いの精米作業場の裏手の畑のほかに、くねる畦道を上り下りした山際にも田んぼや畑があり、家族ともども農作業に通う曲がりくねった道筋は、独り遊びの子どもにとって街道を外れて「探検」に向かう未知の歩みのとば口でもあった。山菜を採りに裏山の奥へ入ったり、農道を抜けて川魚を釣りに河原に下りたりする上空を爆音響かせ飛び交う星のマークの飛行機の行き先で始まった「朝鮮戦争」が茶の間の話題になったが、昭和20(1945)年4月の父の殉職後に京城の住まいを後にするまでの四方山話から「オモニ」か「ネエヤ」か定かでないお手伝いさんがいたことなど聞き及んで、まったく記憶にない朝鮮総督府の官舎での家族四人の暮らし向きが引き揚げて居着いた埴生でのそれとはかけ離れていたのを知った。
冬場を迎え祖父が畑から採ってきた白菜で母が作ってくれた朝鮮漬けに朝鮮植民地暮らしの時間が仕込まれていることに気づいたのはずいぶん後のことだった。丼に盛って訪れた客人のお茶請けにふるまったりしていたが、祖父手作りのカブラ寿しともども、いつのまにか囲炉裏端やちゃぶ台から消えてしまった。
また家族が食前に仏壇にむかって拝むような「食」と「祈り」にまつわる古くからの民間信仰みたいな伝統も薄らぐなかで、家人がそれぞれの願望を祈願するという習慣も生まれず、さりとて「神仏のおかげ」や「村民の営為のおかげ」にとってかわるような朝鮮植民地生活の〈共同性〉の面影みたいなものもなかった。ことさら引揚者意識はなかったものの埴生でくらすようになって「よそ者」扱いを感じるたびに三歳までの出生地が〈空白〉としてせりあがり、子ども心に「父の不在」が「殉職」と「戦死」のあわいで揺らめく影のように見え隠れした。
その後のことだが、どこからともなく囁かれるようになった「人さらい」に逢わないようにという村の噂話が近所の子どもらの遊びの合間で交わされたりしていたが、やがて世間で「拉致問題」が話題になるに及んで、少年期の“まさか?”の出来事がひっくり返った気がした。
富山市の郊外に移り住んだ村共同意識の希薄さの彼方に、村意識が残存する埴生でとぼとぼ歩き去る老人の後ろ姿が焼きついた25年間があり、その先に日本統治下の京城での植民地暮らしがあったことを思い起こさせられた。引き揚げ後の埴生とは違って、都市ガスや風呂や電話も普及していたようだ。殉職時の父の本俸は幾らか分からないが、住宅及び家族手当があり、恩給受給期間の1年が2年半分に計算されたらしい。母が持ち帰った父の遺品が朝鮮での生活を支えた象徴のように思えてきた。
なんでも「犯人」逮捕の際に格闘になった相手からもらった急性感染症で亡くなったこと以外はあまり語りたくないような母の口ぶりで、それ以上朝鮮植民地政策下の警察官としての生活実態に触れてほしくないようだった。父の人となりについてはいつも「いい人だった」でその先が聞けなかった。
高校三年生の半ばだったか、学費の見通しの立たない進学より就職に傾きかけていたら「警察官だけはやめて」と母からダメだしされたことがあった。理由を聞いたら「占ってもらった」ということだった。ちょっとした紆余曲折を経て就職した大学図書館の目録システム地域講習会の打ち上げで懇意になった韓国出身のK講師から「お母さんが元気なうちに」と水を向けられた訪韓のお誘いにも母は気乗りしないようだった。
『日本人物情報体系第8回朝鮮編』によれば、朝鮮在留日本人の始まりは明治9(1876)年の釜山港開港以来、日本政府の保護・補助策もあって西日本各地から商人層を中心に多くの日本人が渡航しているが、明治43(1910)年の併合を機に韓国警察事務を日本に委託した「日韓両国政府覚書」に基づいた日本政府による朝鮮総督府の業務に就くという何らかの縁が父を祖父から引き離したにちがいない。
父母が結婚生活を始めた昭和15(1940)年の在朝日本人数は689,790(女333,564内数)人とピークにあったようで、都市別では京城の日本人人口は124,155人で他を抜きんでていた。職業別の日本人人口割合(昭和5[1930]年)は公務・自由業が31.8%ともっとも多く、次いで商業が25.7%、工業が17.6%とつづき、農業は8.7%だったのに対し、朝鮮人のそれは1.2%、5.1%、5.6%、80.6%となっていた。植民地支配を推進するうえで総督府や地方庁の官吏が数多く在留し、工業化も推し進められたのだろうが、農業中心の朝鮮人との就業人口構成との落差が大きかった。官舎での家庭生活に朝鮮人のお手伝いさんが加わるなど、当時の埴生での平均的生活よりいい暮し向きだったらしい。母が持ち帰った二組の「京城観光絵葉書」セットに写っていない京城の町並みや家並みにどんな物語が隠されていたのだろうか。
家のまえの街道を行きする草鞋履きの老人を見かけるたびに、どこから来てどこへ行くのか、人の生き死にが気がかりでならなかった中学時代を過ぎる頃には、祖父と兵役の関心は薄らいだようだった。ただ夜の読書を見咎められるようにっなって電灯の傘を風呂敷で覆った下で隠れて本を開くなどしたが、ことごとく家計の切り盛りに口を挟まずにいられない祖父の日常暮らしの端端から孫にはなんとなく戦時中の窮乏生活の名残がうかがえるようだった。
富山は石川、福井、岐阜の各県を徴兵の管区とする第九師団として、第11師団[高知、香川、徳島、愛媛の四国4県]とともに、第三軍に属して旅順攻囲戦に参加して多くの犠牲をだし、男子人口(本籍地人口)千人あたりの戦没者字数は6.04人で全国6位[1位は高知県の7.72人](大江志乃夫『兵士たちの日露戦争』)ということだが、ときたま村の年長者と場を同じくした世間話から出征体験や満州での開拓生活などを聞きかじったりしたが、祖父にまつわる聞き覚えはまるでない。
昭和4(1929)年に開設された石動図書館はほとんど利用したことがなかったが、祖父の没後に富山市立図書館で手にするようになった郷土資料の抜刷り広瀬誠「戦時下および戦後の石動・津沢ーー北陸の町と大東亜戦争ーー」によれば、大正13(1924)年11月3日に摂政宮裕仁親王が陸軍大演習御統監のため埴生の御野立所を訪れている。
昭和7(1932)年1月5日に石動青年団満州時局部が新設されてまもなく第1次上海事変となった翌2月2日に第九師団出動命令が出され、同月7日に富山連隊が石動駅を通過[青年団壮行]した。同年5月4日から31日にかけての軍人帰郷後も非常時が慢性化したようだ。
昭和10(1935)年6月14日暁闇の埴生護国八幡宮で武運長久祈願祭が行われ、翌年の11月2日に石動町愛国婦人会・婦女会・国防婦人会が北満の山岡部隊の同町出身者30余名に慰問袋を送り、一個1円20銭相当[送料60銭]として各町村でも同様に行われた。支那事変に郷土部隊の第一陣が出征したのは昭和12(1937)年8月21日だった。
昭和13(1938)年2月の満州開拓移民第1次先遣隊募集に97名、5月の第2次に100名あった富山県内応募者に埴生村からの入所者が含まれ、6月23日の政府による非常時国民実践事項による衣食住の制限を受け、12月の第2回国民精神総動員運動に際して石動町週間行事として第1:建国精神昂揚の日、第2:生活刷新の日、第3:心身鍛錬の日、第4:非常時経済協力の日、第5:将兵へ感謝及銃後後援の日、第6:廃品供出の日、第7:勤倹力行の日の実施が設けられた。
昭和14(1939)年4月に各種軍事援護団体を一本化し、各市町村単位に銃後奉公会が結成され、7月7日に愛宕神社で支那事変勃発二周年記念式典が執り行われ、7月9日以降毎月一日を興亜奉公日として一行事、神社参拝、一日禁酒、青年学校生徒による境内剣道試合、花街は一日休業、禁煙、町内各戸では代表一人神社参拝戦勝祈願の実践が掲げられた。
挙式を済ませた母が父の勤め先の京城で暮らしはじめた昭和15(1940)年の石動[や津沢]では6〜7月に「贅沢は敵だ」の街頭標語が掲げられ、9月には、常会(町内会・部落会)が結成され、隣保班が作られ、回覧板の利用がはじまり、翌10月に天田峠で皇紀二千六百年奉祝文継走行事が行われ、あい前後して大政翼賛会のもとに西礪波郡支部第一回協力会議や石動支部発会式があった。
里帰り先の高儀で姉が生まれた昭和16(1941)年の9月27日に石動国民学校校庭で地域の大小工場から六百余名の男女従業員を集めた大日本産業報国会第一回体育大会が開催され、12月8日の開戦以降毎月八日を大詔奉戴日とする戦時下の生活の物資統制が日々強化されるようになった。
小学校時代は三日にあげず休むほど弱かった母が引き揚げ後の生活で、嫁ぎ先の祖父の精米業を引き継ぐほどの体調を維持できるまでになったのには、実家の母の弟妹も驚いていた。米の収穫繁忙期など、早朝から深夜まで精米機を動かし、米俵や叺を扱っていて子どもに手伝わせることなどなかった。
祖父が体得していたように斧で薪を割るなど道具を使う前に、力と感覚を転倒させるような身体操作法を体感しないことには、ほんとうに道具を使いこなせるようになれなかった孫にとって、祖父や母の日々の作業姿が、小、中、高校期のアルバイトを続ける体力維持の励みにもなっていた。
中学生になって肥桶の片棒を担がされて祖父との歳の差に気づいたのだが、それまで祖父は一人で住居の裏手の汲み取り口から山間の畑まで天秤棒を担いで往復し続けてきたのだ。
冬場の家の雪囲いや庭木の雪吊りなど、祖父から教えられた縄の結び方などすっかり忘れてしまった。
砺波平野を走る城端線の高儀駅の近くの旧地主の長女として育ち、廃線になった加越能鉄道(津沢駅)沿線にあった砺波高等女学校を出て勤めた銀行でタイプ仕事などこなすうちに、母はいかなる縁で埴生の父子家庭の一人息子との縁談がまとまったのだろうか。昔語りのほか和裁が得意だった高儀の実家の祖母が仕立てた着物の納品先のひとつだった石動町の呉服屋あたりを介して地縁的な縁故を想像できない事もないが真相はわからない。昭和15年の9月に母の母校で行われた「大陸の花嫁」奨励[候補者50名、2週間]講習会とはおそらく無縁であったろう。
「日独伊三国同盟」で南方進出の国策が決定した昭和15年に、20歳で8歳年上の外地[京城]勤務を選択していた父と結婚生活をはじめて5年目、沖縄本島では米軍が上陸し始めた春に突然の殉職で夫を亡くした母は、とにかく“いい人だった”というだけ、「御前会議」が本土決戦方針を採択した昭和20年6月に埴生に引き揚げ棲みついた当時も、そしてその後も多く語ることはなかった。
あわただしく殉職葬が執り行われ、取るものもとりあえず京城の官舎を引き払い釜山から船で不安に揺られ、下関から乗り込んだ列車も窮屈で果てしないものだったらしい。内地へまとめて送った家財などすべて消え失せたとのこと。敗戦の2ヶ月前だったというが、まだ歩けない3歳の長男をおんぶし、5歳の長女の手を引きながら、持ち帰った遺品の幾つかが今も身近に残されてある。
祖父が埴生で寝室にしていた座敷の床の間に飾られた遺影の写真でしか会ったことのない父がかぶっていた制帽をひっくり返すと「京城鍾路警察署勤務/朝鮮総督府京畿道警部補 吉田正作」なる名刺が縫いつけた透明ケースに入っていた。
とにかく朝鮮総督府の警察官だった父が「容疑者」逮捕時に格闘となった[朝鮮人]から感染した伝染病であっけなく亡くなったことがよほど無念だったようで、引き揚げ後の暮らしでときおり漏らす母のため息がおさな心に響くのを紛らすように、幾つか軍歌や『異国の丘』などを歌い覚えた西陽射す母の居間でのひと時が忘れられない。
幼い手のひらに余るように大きく艶のあったくるみを喜寿過ぎの皺だらけの手にする感触の落差。「平型體温計一号(柏木型)朝鮮総督府」と銘打ったーー使い込まれて外装が擦れ剥げロックも緩んだーーケースに入った体温計。小さな三枚重ねの虫眼鏡。未使用の「朝鮮観光絵葉書」2セットは二人の子どものためのものだったのだろうか。赤と紫の刀袋に入った軍刀一振り。階級の違う制帽それぞれ一個。遺影大小一組。これらを携え「遺骨」を胸に引き揚げてきた姿を母の命日に拝んだ。(2021年4月12日記/2021年4月14日公開)
続・本の一言:街道と民家(4)軒端の外へ
「人間が太陽の光に包まれ、風に包まれて生き
ているように、かっての日本の人々は、自然に
包まれ、共同体に包まれて存在している自己を
感じていた。だから自分を見つめようとすると、
そのこと自体のなかに自然や共同体が入ってく
る。自然や共同体に包まれて成立した『場』の
ことを風土と呼ぶなら、自己とはたえず風土と
コミュニケイトするなかに成立するものだった
のである。」(内山 節)
新型コロナ禍による外出時の長時間のマスク着用が苦手になってしまい、乗り物での遠出にはかなわないが、グーグルマップのストリートビューによる在宅バーチャル散策や、ご当地風物のユーチューブ探索や見聞などしがちな今日この頃。
2014年撮影の埴生界隈をたどってみると、砂利道が舗装されて道幅が変わっていないような街道を挟んだ埴生の家並みはすっかり様変わりしている。ただかって住んでいた辺りに立っている防火用水標識と精米所跡地の傍にいまも流れる小川の背景にハッとした。曇天を切り取る杉林と山の稜線が幼少期の眺めそのままに見えたのだ。売り払ってきた宅地や田畑や、放棄した山林などの痕跡など定かではないが、航空写真の高度を上げ下げしながら祖父について歩きまわった田畑や山林のルートをはみだすような幼少時の街道につらなる様々な出来事や体験のかけらが埋まっている。
天狗のように見えた八幡宮の杜を舞うむささび。鼻の欠けた老婆や巨大な蝦蟇やカモシカに出会って立ちすくんだ山道。中学生の夏の午後の日課みたいだった川釣りの土手[渋江川]の草いきれ。寝そべって見上げた空には昼日中の星が。あちこち釣り場を変えた坊主の川面の流れに透けて見えた女体の背を隠す長い髪。街道沿いの板塀を背に取り囲んだひとりを痛めつけて去っていった若い衆の後ろ姿。砂利道をかける馬の蹄の響きをかき消す自動車の砂埃。焼け石に水の夏の街道の水撒き。豪雪後に各戸総出で街道の雪割作業。子どもの足で付いて回った冠婚葬祭の列が街道の主役だった日々。
山の端の雑木に覆われた土饅頭のような墓山の眺め。そこに至るまでの街道を山側に枝分かれして入った道の右手にサンマイがあった。嫁入りの列にはあまりついて歩いたりしなかったが、葬列には焼香から火葬場まで一部始終が気になって仕方なかった。井桁に組まれて燃えさかる薪の炎を蹴破るように座棺から火花を散らして躍り立った黒い人影に、出棺時にもらった盛り物を取り落としそうになった。子どもながら近所の長老のように思いなしていた葬儀だった。数日後だったか仄暗い焼き場のあたりから青白い小さな炎が漂っているのを見たときはそんなに驚かなかった。
先の読めない新型コロナ禍の昨今、脳病の後遺症が残ったりする一方で、“ボケ”が治ったりするという風聞に、ボケずに亡くなった祖父のことが想われた。越中上新川郡の野焼き火葬では山芋を入れて焼き、それを食すると脳病が治るという風習があった(高橋繁行『お葬式の言葉と風習:柳田國男『葬送習俗語彙』の絵解き事典』)ようだが、子どもの頃に木陰から固唾を呑んで眺めた埴生での情景にそんな気配はまったくなかった。昔日の火葬で死者の脳をいただいた名残かもしれないが、ほんとうのところはわからない。
そんな村の葬送習俗見聞の対極にあったのが、街道を挟んだ筋向いの農家の牛小屋での湯気の立つような出産の光景。産後すぐに四つ足で立とうとする仔牛の動きや、近所の納屋で押し切りで首を切られたひね鷄が血を滴らせながら背戸から田んぼへ走りまわって倒れる姿など。
我が家の背戸の納屋に逆さL字型に祖父が作り足したみたいな鶏小屋は狭いながらも止まり木や巣箱や砂場もあり、数羽いた白色レグホン種の餌やりや採卵は孫の姉弟の仕事だった。羽目板と土間の隙間を掘って忍びこむイタチの餌食にならないよう祖父と新たに小さな鶏小屋を納屋の軒下で作り直したりしても被害が絶えず、鶏の無残な姿に飼育を続けられなくなった。空き家になった鶏小屋で、祖父が用意してきた原木にシイタケの菌を埋め込む自家栽培を手伝わされたりした。生きとし生けるものをめぐる食の関わり合いを実習させられたような気分だった。
秋から春にかけてのこと、数少ない遊び仲間から新式や旧式の空気銃を貸してもらったことがあった。母の手になるおにぎり弁当を背に山野の独り歩きで狙いを定めても撃てず、習慣化していた川魚釣りのようにはいかなかった。人気のない空が開けた斜面で手頃な標的を仕立てた距離感と当たり外れを確かめたりして家路をたどった。
自然林と人工林が入り混じったような山間で見つけたため池で釣り糸をを垂れたりしたこともあったが、イモリぐらいしか釣れなかった。持って帰ったりしたら祖父さんに黒焼きにして食べさせられたであろう。そんなことより転げ落ちたりしたら泳げず這いあがれそうにない斜面が怖くなって近づくのをやめた。
そんな山際の境を堰き止めた灌漑用水の水場が川や海から遠い夏の子どもらの恰好の遊び場だった。母が用意してくれた黒い三角褌姿で、恐る恐るカッパみたいな村の子どもらに紛れ込んでみたが犬掻きの手前で挫折した。山と違って祖父に連れられて海へ行ったこともなく、中学の夏の林間学校も虚弱なるが故の見学扱いで海に慣れず、その後も夜学や職場で出逢った知人に誘われた海水浴やセーリングの機会があったのに泳げないまま、残念ながら所帯をもって授かった一人娘に教えることもかなわなかった。スキーやバドミントンのように、妻子ともども下手くそながらも上達を楽しめるようなやり方が分からなかったカナヅチは、老の水際で身体操法を稽古してみるしかない。
近所の農家のように牛や豚など飼う余裕も必要もない家内労働たよりの三反百姓で、田植えなど農繁期に近所の親戚の手助けがあったが、祖父から母へと主役交代で維持した精米業の方は、個別農家の脱穀/籾摺り作業の機械化導入で需要がなくなり廃業するしかなかった。現金収入がなくなって母子ともども働きに出るようになり、田んぼは近所の農家に収穫の半分を物納するかたちで請け負ってもらい、残った畑作作業は祖父がやってくれた。犬や猫を飼う事を好まなかった祖父だったが、鼠除けにとかなんとか母と懇願して飼わせてもらった拾い猫が交通事故で亡くなった際、仏壇に向かって涙声でお経を唱えてくれたのには驚いた。祖父の指図で庭の片隅に穴を掘って埋めた場所はグーグルマッップでも見当がつかない。
祖父は食にともなういのちをいただいてもむやみな殺生をするもんじゃないというのが口癖だった。米と野菜は家族四人がなんとか食っていける田畑からの収穫がほとんど、鶏小屋の数羽による日々の産卵のほか動物性の食材を山野に求めるようなことはなかったが、向こうからやってきた食べられそうな生き物は何であれ捕らえて調理する癖があった。囲炉裏端の間食で付き合わされた蛇や蛙の蒲焼や雀や鶫などの焼き鳥や昆虫食なども多分そういうことだったのだろう。夏休みの日課みたいだった孫の釣果の雑多な川魚それぞれに見合う前処理と調理法で夕食に供された。働かざるもの食うべからずというより、働きかつ食らうものとしてのいのちの働きからなる公界を実践して見せてくれていたのだろうか。
今となってはグーグルマップの航空写真でどこからどこまでが山崎町か宮崎町だったか定かじゃないが、町内の獅子方若連衆の踊り子の一人を勤めさせられた時期があった。とりあえず目立つのさえ我慢さえすれば春の祭礼当日に小学校を大っぴらに休めるという具合だった。おそらく祖父の差し金と母の賛意に背を押されたのだろうが、例年巡っていくる夜毎の稽古初め、中入り、打ち上げまでの通いは短期で終わった算盤塾より馴染めた。八幡宮に奉納した後の獅子舞の戸別訪問は祭りの出し物という感じなのに、なんとか踊り子の勤めを終え隊列を組んで帰る夕暮れの道中を飾る笛や太鼓がなんだか村の通過儀礼のように踊り疲れた身体に響いた。性に目覚める中学生半ばで抜けてしまい、祭礼の打ち上げ後に未婚・既婚の若衆が習慣化していたような花街通いを体験するまでにはいたらなかった。
石動町を流れる小矢部川の近くに村人が訪れる婚外性交公認の場があるのを知った中学生半ばで「赤線防止法」なるものができた時には、なんとなく家業の精米所で捕まったゲタ履き米泥棒のことが思いかえされた。遊興費欲しさの再犯を予想して精米所で待ち構えた祖父と駐在巡査に捕まった愚かさより、長男でないと嫁をもらって家族を営み難い村の次男坊以下の性生活の切実さがあからさまだった。祖父にとっては夜半前にゲタ履きでやってきたような近所の男の若気の至りといったところだったのだろう。山間の農家の次男坊として育ち、尋常小学校を終えたら奉公に出されざるを得なかった祖父にとっても、故郷に出戻って嫁を娶り家を構えるなんて並大抵のことではなかったであろう。
大阪での奉公の年季明けUターン先を山深い松永の実家より里寄りの親戚筋が住む埴生を永住の地として暮らし始められたのは、村人からの有形無形の生活上の協力や便宜などに恵まれてのことだろうが、新しく家を成す縁談はどのように祖父の元へ運ばれたのてきたのだろう。嫁の出自はとにかく、新婚夫婦には家作料や宅地や田畑となる耕作地など借用の便宜を図ってもらったことだろう。だが村に根を下ろして子孫を絶やさず、家を維持・継承していく営みも、まだ幼い一人息子を残して逝った嫁の死で中折れしたようで、仲人を立てた婚姻を正式とする当時の婚姻規制に棹さすような「馴れ合い夫婦」の影を匂わせながら、その後を生きとおしたようだ。
囲炉裏端での家族の噂話などから「朝鮮生まれ」を聞き知ったのであろう村の悪童から“ゲイシャの子”などと揶揄されたりして合点がいかないこともあった。後知恵で植民地を女性に喩えたりする「宗主国」の風習から朝鮮生まれを言挙げされたのに気づき、祖父の亡妻が芸者あがりだったことも考えあわせ、幼少期の父が京城へ移住して殉職する前の埴生で受けたかもしれない“イジメ”をより身近に感じた。また若い未亡人として引き揚げ住み慣れたはずの母が時おり晒される村の男衆の視線が気になりはじめ、「父性」の不在と相まって「母」と「女」のあいだで揺らぐ「母性」の実在が陰るようだった。
年を取ってからの出産を恥じるような村の風習のなかで、男やもめとなった祖父は朝鮮総督府勤務の一人息子の縁談をまとめあげたわけだが、なぜか年頃になった孫二人の縁談などこ吹く風のようだった。それでいて孫に訪れた男女の縁は何も言わずに受け入れ、姉の結納の義には同席しても結婚式には出なかった。結婚前の息子が京城で花街通いをしたりしていたとしても祖父は何の咎めだてもしなかったであろう。孫が話した山中で出会った鼻欠け老婆については「おそらく梅毒にやられた夜鷹の婆さんだったんだろう」と事も無げだった。
祖父は毎年歩いて出かけていた実家の松永のお祭りには、家族の誰一人として誘うことはなかった。覚えているのは、お正月の和倉温泉や、春の石動町の祭礼や、諏訪神社での鏡里が横綱だった頃の大相撲巡業など。近郷で素封家の家財が売りだされる市にも同行させられたが、姉や母はいつも蚊帳の外だった。埴生の祭りには松永の祖父の実家だけでなく、母の高儀の実家からも客人を迎えていたのに、高儀のお祭りに出かけるのはいつも母子三人だけで祖父が加わることはなかった。田舎料理が上手で「昔話」の宝庫みたいだった高儀の婆さんとの添い寝の記憶が、訪れることも途絶えた母亡き後の実家を象徴するようだ。
お祭りの御膳ともなると、赤飯から何から何まで祖父が腕をふるって采配し、母はもっぱら手伝いに終始していた。家の外でも冠婚葬祭の仕出し料理を頼まれ腕をふるったりしたようだ。また虚弱な孫を気遣ってか、八目鰻の干物や蝮酒のほか、囲炉裏端でイナゴやカエルやモグラそのほか焼いたものなどいろんなものを食わされた。長じて中学生の夏休みの晴れた午後の日課だった川釣りの獲物や、里山で怪我していたのを捕まえた山鳥など祖父は待っていたみたいに調理したり、いつどこで料理の腕を磨いたのか疑問だった。とにかく食べて、消化して、排泄して暮らす老・幼がお互いの存在を認めあっていたような炉端での場面のあれこれが埋まった囲炉裏の灰も、我が家の糞尿とともに行き来した輪作田畑に撒かれ、鋤き込まれ、分解してしまったようだ。(2021年7月26日公開)
続・本の一言:街道と民家(5)本と昔語り
《陽が照って鳥が啼き
あちこちの楢の林も
けむるとき
ぎちぎちと鳴る汚い掌を
おれはこれからもつことになる》(宮澤賢治/春)
玄関を入った土間が茶の間の所で狭い通路となり、囲炉裏や座敷や縁側を右手に土足のまま背戸まで抜けられるようになっていたが、家屋の老朽化が目立ってきた1970年代のはじめに床や梁などの補強修繕の際に用済みで塞がれ、縁側の手前まで板張りの廊下になり、囲炉裏横の薪入れ箱の置き場所が消滅したあとあとまでモヤモヤくすぶり続けた出来事があった。
夕食後の囲炉裏端、祖父に薪で殴りかかった中学生の自分を、背後から叫びながら締めつける母の腕力で抱きとめられたことがあった。その時にかぎって、いつもの母に対する打擲に我慢がならず、とっさに身近な薪箱から掴み取ったのだろう。「それだけはやめて!」の叫びに我が身が金縛りになって身動きならず、震える眼前から瞬きもしない祖父の眼が望遠レンズのように遠のいた。後先のことも忘れてしまうほど一瞬の出来事だったろうに、まるでスローモーションの光景のように記憶に残った。いじめっ子に向かって履いていた下駄をひっつかんで振り上げた場合と違って、祖父と一緒に薪割りした一本を凶器に、狂気の沙汰におよんだ事態から引き離された自分に茫然自失した。祖父に何を言われ、どんな反撃を食らったか、前後のことはまったく覚えがないのに、取り返しのつかないことをやって我にかえった違和感が寝つかせてくれない夜になってしまった。
部活で剣道を始めた頃だから、竹刀だけでなく木刀や軍刀も茶の間にあったはずだが、「殺意」どころか何の見境もない行動をやってのける自分に出会った驚き。中学校の廊下の陰で苛めっ子から血が出るくらい殴られても、「肥後の守」の折り込まれた刃を伸ばし布切れと針金で巻いて隠し持ったまま何の手出しもでき[し]なかったののとは違う。
老いたりとはいえ田畑仕事や山仕事を生き抜いた持ち前の技で虚弱な中学生の孫の不意の仕掛など一捻りだったろうに。山道で遭遇した蝮など、素早く拾った棒で一撃し、素手で引き裂いて持ち帰ったり、登っていた柿の木の枝折れで落ちる躰が串刺しにならないよう捻りながら杭と杭の間のぬかるみで躱したこともあった。鎌や鋤や鍬や斧や鉈だけでなく、大工道具などの扱いに力みがなく、長時間働いても疲れを見せないのが不思議なくらいだったが、そのうちまる一日働いたら翌日寝込んだりする老い姿を見せはじめた。祖父亡き後に晩年の母が庭の草むしりに入れ込みすぎたみたいに玄関に倒れこんで這い上がる姿に、我が家の〈老い〉の解体と再生に居合わせる思いがした。
囲炉裏端での出来事から10年ほど経った半ドン上がりの図書館を後に、バリケード封鎖された富大正門脇を出たところでの「交通事故」体験。青信号T字路交差点の横断歩道上で右折車に撥ねられた一瞬も、その場にいない〈母〉に呼び止められた記憶として残っている。
とっさに避けようも無く跳ね飛ばされ倒れこむまでに、走馬灯のように幼児遡行記憶が渦巻く渕を「お母さん!」が木霊す響きの漏斗に墜ちたようだった。呆然としているうちにぶつかってきた乗用車で近くの整形外科に運ばれ診察を受け、打撲と擦過傷で済んでよかったねと言われた。メガネは行方知れずのまま、頭に傷はなく左胸に腕時計の跡が痣になって残っていた。対向車線側へ逃げたみたいに、ちょうど赤信号で止まったトラックの前で左腕を胸の下に、右手で頭を抱えるように転がったのだろう。右手が外へと向かい、左手が内を守るように、とっさに心臓と脳を守るかのような身のこなしができていたのは、潜在的に身体が受け継いできたものの発現だったのだろうか。それまで虚弱で運動オンチの自分しか知らなかったのに。ぶつかる肉体意識が薄らぎ、無意識が身体から飛び出したような状態だったからこそ、あんな防御姿勢になったのだろうか。柿の木から落下した祖父が杭を避けて当たりどころを変えたような身の躱しとは次元が違うが。
座敷で昼寝から覚め、タバコ盆を傍にあぐらをかいた祖父が煙管タバコを燻らしながら、縁側に広がる庭越しに何を眺めていたのだろう。なんとなく近づきがたかったあの後ろ姿の感触からかなり遡った母の実家の夏の縁側での母方の祖母との昼下がりの添い寝の感触まで。田舎暮らしのエアポケットにはまったみたいな〈異界〉体験が語り種になったり。男と女の距離感の違いなのか、祖父の語りは黙したままで祖母の語り口だけが懐かしい響きで谺すことがある。時と所を隔てて、夏場を過ごす祖父のほとんど裸に近い普段着姿と呉服屋から頼まれた着物を縫う母方の祖母の和裁姿が、幼少時に行き来した田舎のイエの対になった情景の一つだった。
母の実家の泉水と築山に面した座敷の縁側ではなく、居間の縁側に茣蓙を敷き、青田を渡り屋敷森を抜ける風が、腰巻き姿の母方の祖母の昔語りの頁をめくるうちに、二人とも昼寝に落ちた夏休みの昼下がりのひととき。
母方の祖母の物語を強請れない時など、庭でトンボ釣りをしたり、魚を捕まえたり、雨の日は埃まみれの古道具屋の物置きみたいな2階で薄暗闇を探検して見つけたSP盤を片っ端から手回し蓄音器に載せて聴いてみたり。とにかくなんにもなかった埴生の我が家とはケタ違いで暇つぶしのネタに困らなかった。手に馴染むような本は見つからなかったが、母方の家族が時々読んでいた『キング』や『リーダーズ・ダイジェスト』が雑誌の読み始めになった。
はじめての本といえば埴生の茶の間で手にした松田甚次郎編『宮澤賢治名作選』(羽田書店)の上・中2冊だ。母が京城から持ち帰ったものではなく、奥付には昭和21年7月発行とあるから引き揚げ直後に石動町の本屋で子ども二人が喧嘩しないよう買い与えてくれたのだろうか。祖父の手擦れ跡を残す和綴じの『経典』ほどの破損はないが、数度の引越しを経て座右の賢治本となっている。帽子をかぶり手をコートのポケットではなく後手に組んで俯き加減に野に立つ姿が際立つ上巻の目次の「やまなし」「貝の火」「オッペルと象」、そして歩行感を留めた「岩手公園」で終わる中巻の目次の「風の又三郎」には当時の鉛筆でつけた印が残っている。「童話」や「詩」にとどまらず「劇」や「歌」まで、盛り沢山に〈心象スケッチ〉なる電信柱に連なった列をたどり歩いた勢いが、手元にない『下巻』探しではなく、小学校の「図書室」へと向かわせたようだった。
埴生の神社や寺の境内や小学校の講堂で、秋祭りの余興の芝居小屋が掛かったり、映画が上映されたりしていた秋祭りの晩に不思議な体験があった。邦画の現代物の筋が分かりづらいつまらなさから、一緒に見ていた母や姉を後に先帰りした。家並みに挟まれ街灯のある街道ではなく、通学路として通い慣れた農道の暗闇をたどって我が家近くの街道に出たらなんだか辺りが暗くシーンとしていた。手探りで潜り戸を開け、おそるおそる家の闇に忍び込むように下駄を脱いだ。留守番の祖父や祭りで訪れていた母方の祖母の気配がどこにもない暗闇をかき分けるよに手を前に伸ばし、足元を確かめるように奥へと入るほどに、何が何だかワケが分からず、何度も「おばあちゃん!」と叫んだようだ。目を凝らしても何も見えず、だんだん怖くなってきたらいきなりパッと明かりがついて、祖父は座敷で、祖母は茶の間で何事もない様子だった。
その場でへたり込んでしまって、二人に何をどういったか覚えがない。なんで「じいちゃん」ではなく「ばあちゃん」を連呼したのか自分でもわからなかった。帰った母や姉に何を言っても、チンプンカンプンだったろう。「神隠しにあったんじゃ」が祖母の感想だった。
我知らず闇を弄っていたいた自分の姿勢が、なんだか獣みたいな四つ足歩行から立ち上がったみたいな感じだった。上半身の前方に両手を泳がせた手触りはなんだったのだろう。何かを見透かそうとしている目玉の感触だったのだろうか。明るさのもとではやったことのない動きをしていたようだ。発育不良で四つん這いから立ち上がるのが遅かったようだが、二足歩行になっても頭では考えられない動きの姿勢が発現する場に居合わせた気がした。目に頼れない状態での手足の動きは、そうでないときの運動条件と異なって、より動物的にならないと通用しないようだった。
小学校低学年の「体操」の授業で、輪になった左回り歩行行進の列からつまみ出された何人かと一緒にグランドの中ほどを歩かされたことがあった。先生が外側の列に向かって何を説明しているのかわからず、自分も手足がバラバラになったぎこちなさで歩きを見失いそうだった。運動会でもお手本になるような動きは何一つできない生徒だったが、外周と内周とに分けられて歩かされた差異から自分では意識し[でき]ていない身体/肉体の動きの違いを考えさせられたようだ。「虚弱児」にも「健康優良児」にも行き着かない〈身体性〉を認識したり、把握したり、その区別もできないままに。
身近な歩きや身のこなしのお手本といえば祖父の日々の姿であり、天秤棒をしならせるように水桶や肥桶を運び歩く拍子についていくのが面白かった。畦道や山際の上り下りを半身になって、ときにわ左右の肩を入れ替えたりして、いかにも身のこなしと歩きが一体になっていて、とても真似など出来ないと思わされた。「ナンバの身のこなし」など知る由もなかったのだが。
とにかく体操の授業時間より、樹木が伐採され運び込まれた原木を加工する製材所を覗きこんだり、製材を大工さんが加工したり、職人が機械や道具を自在に操る身のこなしが面白く、見飽きることがなかった。おぼろげながら西洋式の歩き方と日本古来のそれとの違いに気付かされたのもその頃だった。中学で入った剣道部での構え方は、半身になって鍬や斧を使う身構えと地続きに思えたが足捌きだけは違うようだった。
匍匐から立ち上がって掴み取れない何かを把握しようとしていた暗闇と、祖父と母方の祖母を見つけた明るさの落差のもとでくらくらしている自分の身体に出会いながら、その場の明/暗を感受した自分自身を家族に説明できないもどかしさは何だったのだろう。祖母の言う「神隠し」が、何を何から隠すというのか見当もつかなかった。祖母から聞いた寝物語のほとんどが物の怪に「化かされたり」すことであったり、何者かから逃げて「迷子になったり」という、そんなふた色の主調音が幼ごころに巣くった〈あてどなさ〉に共鳴したようだった。家屋から畳や建具が取り払われて柱だけになった夏の大掃除の吹き曝し感が裏返ったような床下に迷い込んだ軒遊びの行き場のなさ。やがて民家の縁の下から神社の縁の下へと遠出をしたり、山に入ってコウモリ洞窟を見つけるなど、薄暗闇の手前で遊び途絶えたその先に街道を外れた祖父との里山歩きや母方の祖母と列車で訪れた門前町歩きが待ちうけていた。
砺波平野に広がる散居村の西のはずれの母方の祖母の実家の前には生活用水の川が流れ、田畑を区切って伸びる農道に木の橋がかかっていたり祠があったりするその先はどこの街道に続いていたのだろう。埴生のような街道沿いの家並みの村とは異なる生活空間の広がりの山と里との間に寝物語で聞いた狢や狐や狸などの姿に託され語り継がれた跡が潜んでいたのだろうか。街道の主役だった馬や間道の主役だった牛が交差するような絵物語の世界から、義仲が戦勝祈願したという埴生八幡宮の佇まいや、牛の角に松明を点けて戦った倶利伽羅の源平古戦場の跡まで、語り継がれた物語から山川草木に分け入って植物や昆虫を採集したりする少年期の活字離れが、読むことから聴くことへ向かわせたようで、鉱石ラジオの組み立てから始まり、アンプやスピーカーの自作を通して放送やレコードに耳を傾けるようになった。
祖父の小言めいた説教話や母方の祖母の昔語りにも間が置けるようになったが、それぞれが何気ないときに漏らす「なマンダブナマンダブ」や「南無阿弥陀仏‥‥‥」が身にまとわりつくように響いてきた。誰かに触れるとか、何かに触るというのでもなしに、生きつつある事を確かめつつあるように聞こえてきた。己の生き死にの前にも後にも世間は続いているという風に。若すぎて言葉以前の体験のなさと当てどなさをもてあますしかなかったが、それぞれ違った環境で育った二人がいつの間にか似た様な呟きを漏らしたりする土地柄に依存する環境とは何だったのだろう。
小作農家生まれの幼少期を過ごした田舎娘が嫁いだ先の地主の家柄や家訓に馴染むように暮らしを重ねるうちに夫や長男を亡くしたようだが、二人の「遺影」を飾った部屋もなく、苦労噺の翳りを感じさせない母方の祖母の語り口に病死した家族のことだけでなく、親戚の大学生の冬山での遭難死や高校生の入山自死を悼む思いも溢れるようだった。父は埴生で生まれ京城で死んだように、人は誰しもどこかで生まれ早かれ遅かれどこかで死ぬ。幼少の頃から街道を歩いている老人の背後がなんであんなに気になって仕様がなかったのか。
呼吸か念仏かもわからないように聞こえた呟きは老人の動作でも肉体でもない頭上の気配のようだった。それでいて足腰のしっかりした身体観を伴う日常の作業姿があった。真っ新な反物を裁断して縫い上げた和服も着古したら解いてそれらの布切れを合わせて新しく縫い上げて別物に作り変えられるのも、木造古民家の“再生”の仕事とに通っているように思えた。工芸品を新しく作るだけでなく、壊れた骨董品を繋ぎあわせたり、使い物にならなくなった別個の部品を寄せ集めて新たな一つの中古品にしたり、祖父も再生手作業が生活の一部になっていた。
家の外での農作業だけでなく、日頃から庭と同じように里山でも手を入れて活かす自然の寄り道が生と死を繋いでいたのだろうか。その途上をいかようにも輝かせる命の働きを宿した身体の後ろ姿を街道で探していたようだった。(2021年10月24日公開)
続・本の一言:街道と民家(6)童話と山歩き
「義母がとめにはいってくれなければ、私はなに
をしていたかわからない。しかし義母がとめに
はいった瞬間に、急に祖母が小さな老婆にかわ
り、すべてが散文的に白茶けて、そのなかでい
きり立っている自分がみじめに見えはじめた。
義母は祖母にとりすがって必死に詫びながら、
私にむかって『自分がなにをしようとしている
かよく考えてみなさい。どうしても切るならわ
たしをきってからになさい』というようなこと
をいった。そういうせりふも私はなにかで読ん
だことがあるような気がした。こういうグロテ
スクな場面もどこかで見たことがあるようであ
った。私は吐き気を感じて刀をほうり出し、自
分の部屋に走って行って泣いた。尊属殺人未遂、
傷害、感化院、というような言葉が頭のなかで
ぐるぐるまわっていたが、そのとき私は自分に
おびえていたというだけではない。なにをしよ
うとしても自分の外側に網をはっている死んだ
言葉にからめとられて、自分を理解させられな
いことに絶望していたのである。」(江藤淳)
学童期の夏休みに訪れた母の実家のお盆に、田んぼの一画にあった墓参りに連れ出されたりしたが、仏壇や神棚と同じように、埴生の我が家のものとは違って大掛かりな感じだった。一度も連れて行ってもらえなかった祖父の実家との違いなど知らず終いだったが、よそ様を訪れた際には仏壇に手をあわせる習慣みたいなものとして浄土真宗の雰囲気に馴染まされたような気がした。朝晩のお勤めを欠かさなかった祖父と一緒にお寺参りした記憶はないが、母の実家の祖母と訪れた別院の大きなな佇まいと親鸞法要など法会の声明や、手の込んだ巨大な木造建築を目の当りにした耳目の残渣に引きずられたみたいな様変わり。月忌参りに訪れる坊さんの話や忘れた頃にやってくる売薬さんの話がいつの間にやら聖と俗がごっちゃになったみたいに響く場違いな感じが面白かった。
「いつも鼻柱にお天道様の陽が当たると思うな」などと祖父は、いったい孫に何を言いたかったのだろう。「天道」とは何か、誰の「鼻柱」なのか、両者が関わるとはどういうことなのか。祖父に問い返すこともできなかった。
「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」、『宮澤賢治名作選上』の「序」と「目次」の間に挟み込まれたひとくだりを「世界ぜんたいが‥‥‥」と読み間違えたまま、収録作品の頁をめくっていった。虚弱に生まれついた日頃の身体感覚を揉み消すような初読の手触り。
二疋の蟹の子供の「クラムポン」会話から始まる五月と十二月の谷川の底の心象風景が二枚の幻燈に映しだされた「やまなし」。急降下したかわせみが魚を捕える一瞬の音にはじけたり、落ちて流れて沈んで醗酵するやまなしの分解作用に寄り添ったり、〈蟹の泡〉が自然現象を繋げて点滅する心象風景。
祖父と家族・親戚ぐるみでやった山田の田植えの合間に近くを流れる川底の石をめくって沢蟹を捕まえてみたり、見つけた木苺を片っ端から採ったり、里田と山田の感触の違いを足裏で感じたり、身体感覚の自然が賢治童話に溢れているようだった。
小兎のホモイが溺れかかったひばりの子を助けたお礼に、ひばりの親子から宝珠を贈られて家宝としたが、ホモイの日頃の行いをめぐって明滅する「貝の火」を見護って一喜一憂、交叉する兎の親子の擬人化された視線の先に見えたものと見えなかったもの。
「オッペルと像」では六台の稲扱機械の響きが、母方の祖母が寝物語に語る民話でも聞こえていたようで、働き詰めの像が繰り返し呟く「‥‥‥、サンタマリア」など、祖父や母方の祖母が漏らす「ナマンダブナマンダブ」や「南無阿弥陀仏‥‥‥」そのものに聞こえた。
初読のざわつき感が忘れられない「風の又三郎」の嘉助は仲間とはぐれた山中の草むらで眠り込んでしまい、夢見の又三郎がガラスのマントと靴の出で立ちでキラリと空に飛び上がったところで目が覚める。
連れだって水遊びや鬼ごっこに戯れているうちに空がにわかにかき曇り、降ってきた雷鳴混じりの夕立に急かされるように水から上がってねむの木の下に逃げ込んだが、逃げ遅れた三郎の耳に「どつどど どどうど どどうど どどう」ではじまるどこの誰ともわからない叫びが響きわたる。
宮澤賢治の心象中に実在した「イーハトヴォ」ではあらゆる事が可能で、「人は一瞬にして氷雪の上に飛躍し大循環の風を従えて北に旅することもあれば、赤い花林の下を行く蟻と語ることも出来る。罪やかなしみでさへそこでは聖くきれいに輝いてゐる。」ような「ドリームランドとしての日本岩手縣である。」と記された「序」の前頁を飾る外出着の賢治が見ているのは街道ではなく耕作地のようだ。『宮澤賢治名作選』の下巻を母に求めたりしなかったが、その後も賢治本を手にするのを待ってたかのように、帽子に襟を立てたコート姿の宮澤賢治に立ち戻らされることとなった。
街道の立ち姿といえば杖を手にしてマントに中折れ帽の祖父の出で立ちや、縫い物などの風呂敷包みを背に腰を曲げ加減で歩いていた母方の祖母から聞いたのだが、五街道に準ずる加賀街道にまつわる難所[親知らず・子知らず]を行き来した旅人話が忘れられない。母が語ってくれた家族三人引き揚げ時に制空制海権を失った対馬海峡西水道を航行中の揺れる連絡船室内の怖さにも通じるものがあった。
亡夫の故郷の埴生村で祖父が稼業にしていた精米作業に勤しむ前の母については、まだ歩けない三歳男児を背に五歳の娘の手を引き、父の遺骨を胸に敗戦直前の植民地朝鮮からの引き揚げ旅姿。姉と違ってまったく憶えがないはずなのに強い印象として残っている。着の身着のまま京城の朝鮮総督府の官舎から持ち帰った父の遺品には制服・制帽だけじゃなく軍刀まで含まれていた。
仏壇に置かれた小さな遺影では、制服・制帽に白手袋の父が手にしているのはサーベルだ。「父さんの左足の靴の踵が片減りしてしょうがなかった」と母が語ってくれたが、朝鮮総督府に勤めていた生前の父には左腰に吊るしたサーベルの鞘を振り放つような歩き癖があったのだろう。ちなみに朝鮮語の使用が禁止された統治時代を描いた韓国映画の『マルモイ:ことばあつめ』[2019年製作の作品の背景は1941年前後の京城]で朝鮮総督府の警官が携行していたのは警棒や拳銃や小銃だった。
サーベルは殉職時に朝鮮総督府に返納させられたのだろうか。当時の植民地朝鮮は昭和天皇の直轄だったから、おそらく下賜品だったが故にかけがえのない遺品として母が持ち帰ったのは、日本刀を作り直した「式刀」ということだった。剃刀のようには紙も切れない刃先の仕立てだったが、鞘から抜いだ「軍刀」は本物そのものの見応えがあった。錆のきていない刀身の波模様が晴れた日の埴生から見渡せる立山連峰のシルエットみたいだった。刃文に天皇制の影がまとわりつくような代物に思えなかったが、埴生に引き揚げておちついた母を村の婦人会による立山[雄山神社参拝]登山や皇居の勤労奉仕に行かせたりした祖父の姿が普段とは違うように感じた。
入学時に130cm、30kgに満たなかった中学生が剣道部に入って初めて竹刀を握った。軍刀を抜いて構えたりしたことのあった身体には奇妙な違和感が先だったようだ。ほどなく小遣いで買った木刀を振ったりするようになったが、長さや形が「軍刀」にそっくりなのに刀身が抜き差しできないからといって、抜刀や納刀を試そうにも非力な中学生に「軍刀」はとにかく重すぎた。とても斧や鉈のように扱える気がしなかった。どんな儀式に使われたのか分からないが、刀身も外装も「式刀」にふさわしい美品のようで、刀身を鞘に収めたときにカチッと駐爪がロックする音がたまらなかった。透かしがない金鍍金の鍔が綺麗なのに、なぜか鉄鞘の感触に馴染めなかった。50年前に28年間住み慣れた埴生から高屋敷へ引っ越しを任せた母が父の遺品の軍刀だけじゃなく、息子が使い古した木刀や竹刀まで運んでくれるなんて思いもよらなかった。あれこれ調べて刀身には陸軍受命刀匠で大業物の「岡田兼義」なる銘が彫られているのではという見当がついたが、竹刀のようにバラして確かめたことはない。
虚弱なだけでなく体格差もあって身が入らない部活から帰って一人悶々とすることが多くなったとある日の午後、母と諍いになった。いわゆる反抗期にありがちな台詞を吐きだしてしまった後ろめたさ。「産んでくれと頼んだ覚えはない」なんて言うも愚か、この世に存在してしまったからにはどうしようもないことを失念した戯言に母は黙ったままだった。
親と衝突する前にすでに生きてしまっているから「何のために」は不問にされざるを得ず、生身から悔恨を抜き出された鈍刀のようでどこへも切り返せなくなった。振り上げた斧には薪割り、払う鉈には伐採、というように抜き身の身体は存在していない。
揺り籠から墓場までを抜刀と納刀に、抜き身を生涯に擬えていたのかもしれない。「軍刀」を振り上げたら落とすだけなのにその前後が気になって身動きならない。抜刀から納刀までの身体の捌き方が刀の通り道を創りだすのであって、刀がどう身体を動かせば良いかを教えてはくれはしない。部活では竹刀を、家の裏庭では木刀など、振れば振るほど〈素振り〉の意味が分からなくなったようだ。剣道部員が少なくて団体戦の先鋒か大将のいずれかで対外試合に臨まされたが、小手で一本取ったら場外にならないよう勝ち逃げ狙いも外れてばかり。個人戦でも小手一本槍だったが、ほとんど負けてばかり。それでも部活はサボらず、暑中稽古や寒稽古では稽古参加者が自発的に、学校裏の夏草を刈ったり校門前の通学路の除雪までやったりした。
埴生を抜けて石動町と結ばれた街道を数キロ歩いて中学校に通ったが、雨風や吹雪のときの途中で家並みが途切れた通り抜けが小柄な体に厳しかった。雪に埋まった下草径を探すような藁で編んだ深履の感触がやがて汗ばむゴム長にとって変わった頃、履物がどんどん変わっても「道」はそんなに変わらないようだった。街道の両側の建物や土地の所有権がめまぐるしく変化しても、そんな風景をつなぎとめる「道」があって、そこを歩く人の様子は「昔ながら」をくりかえしていたのだろうか。立ち上がって「歩く」をくりかえしくりかえししながら、人は古人の生を追体験しようとする。古文書や古民家を見て在りし日を思いめぐらすのとはちがい、同じ道を〈同じように〉歩くことをつうじて、人はその時代の通り道を一人歩きできるようになるのではないか。祖父の「天道を知るには本など読むな」とは、人間を含めたこの世界の自然全体を掴めと言いたかったのだろう。古きを尋ねて新しきを知るように生を活かす暮らしそのものが稽古じゃないかと気づかされた。
いじめっ子が志望しないのを見越してだが、母の実家に近い駅から一駅手前の総合高校の普通科への進学後も剣道を続けようと思ったが担任から止められた。文武両道どっちつかずの生徒にしか見えなかったらしい。山岳系の部活など母はもってのほかだった。たまたま同校のラグビー部員だった農業科の先輩の弟から県西部の低山登山に誘われ、なんとなく家族の目には里山や裏山歩きの拡張みたいに映った山歩きが剣道を遠ざけたようだ。ただ〈何か〉を〈稽古〉したいという気持ちは消えなかった。
田舎の街道を離れて知らない道をたどって高山を目指す物珍しさに加え、どの山に出かけても当たり前のように登山道が開かれているのが〈古き〉を辿りながら〈新しさ〉に至る〈稽古〉の身体感覚を下山してからの実生活にどう活かせば良いのか迷い道に踏み込んでしまった。槍から穂高への縦走に出かけた初日の飛騨乗っ越しで動けなくなった昏睡状態から気づいた一瞬、いったい自分がどこでなにをしているのかわからなかった。起こしてくれた同行のSさんによれば、好天で日没にまだ間があったから寝かせたままにしておいて、ひとまず二人分の荷物を槍の肩の小屋まで運んでから迎えに戻ったという。しばしの昏睡で体力も回復し、屈強で優しいSさんに担がれたりせずに槍の小屋までたどりつけた。その後富山市内の五福キャンパスから高岡市内の中川キャンパスへの配置換えから出戻ってSさんを訪ねたらこの世からいなくなっていた。二人で槍穂高縦走途中の悪天候から避難下山してから間をおいてのこと、Sさんは傘をさして雨の帰り道を歩いていて、背後から来た車にはねられ亡くなられたとのことだった。
母方の祖母が哀悼していた親戚の高校生が自死した医王山は経験者と同行したが、同じく大学生が冬山遭難死した赤谷山に至る夏の早月尾根筋歩きに初心者と連れだって出かけて霧に巻かれ迷ってしまった。登山路に沿うように潅木に張られたロープの高さが冬場の積雪を忍ばせ、赤く結び垂れた布切れが安心・安全の目印だったのも束の間、みるみるうちに乳白色の霧がとり囲むように湧きあがってきた。帰り道のために新聞紙をちぎって足もとに撒きながら登るうちに目印どころかお天道様も分からずあやふやな方向感覚に立ち迷うしかなかった。まったく風もなく、登ってきた道を引き返しているつもりがリングワンデリングに嵌ったようで時間の経過も分からなくなってしまった。
夜間短大の同窓生に請われた日帰りトレッキングの初っ端の出来事だったが、とにかく山麓の終バスに間に合うよう聞こえてきた谷川の水音に導かれ、道無き急斜面を膝あたりまで埋まる枯葉を踏みしだき、持ち合わせたナイフが役立たないような藪漕ぎをしてなんとか麓の明かりが見える場所に出られた安堵感が忘れられない。祖父の云う「お天道様の陽」を見失ったような出来事で、水や携行食の不備だけでなく鉈みたいに使えるナイフの持ち合わせなども反省しながら川筋をたどりくだって事なきを得た。帰宅が遅くなったわけを家族の誰にも話さなかったが、濃霧で分からなくなった尾根筋を引き返さずに水の音を聴き分けて下る流域にたどり着けたのは誰かの導きがあったからだろうか。
その後も春から秋にかけての日帰り独峰登山ルートからやがて梅雨明けの縦走登山ルートへ脚を伸ばすようになり、自炊テント泊登山から点在する峰々の山小屋泊まりへと、縦走期間が延びた高所暮らしで下山してからの体調が変わる身体感覚に励まされるように冬場の立山山麓スキーも習慣化した。夏バテ体質で細った食欲が夏山登山で回復する様子に気づいた母は息子の山歩きに良い顔も悪い顔もしなくなったが、続けようにも職場の製本運び中に突発したぎっくり腰による痛みが慢性化して運動どころじゃなくなった。
祖父は手足の関節の痛みをまぎらすように、歳をとらないとわからない痛みがあるからその時々を耐えるしかないというふうだった。飛騨乗っ越しでの体調不良は登山前の食い合わせか何かによる内臓の変調による一過性のものだったろうが、平地での筋骨格系の不具合による慢性的な腰の痛みは体内自然のなせるひとつの不調過程として抱えこむしかなかった。
ひどい時は30分も歩けず、刀どころか箸の上げ下げまでも苦しくなったり、なんとか〈腰痛〉をやり過ごすような体の使い方を探し歩くみたいに、職場の昼休みに近くの整形外科に通うようになり、日によって11時間も続いた小屋から小屋への変幻自在な山道歩きが遠い夢のように思えた。
腰の痛みが治まって直ったようでもいつなんどき身動きならなくなるかわからない原因不明の不安感から身体の予防運動として職場の裏のグランドを走ってみたが一週間と続かなかった。生え抜きの金槌とは知らない医者には水泳を勧められたが、とある日の昼休みにのぞいた職場の横の体育館でバドミントンラケットを握りはじめた。
登山から遠ざかることになった身体的要因が持病化した腰痛のほかにもあった。ときおり排便時に痛みを感じるようになってほどなく、通勤時の列車や職場で座っているのも辛くなり、泌尿器科の診察を受けたら遺伝性の脱肛ということで即入院し手術を受けることとなった。祖父や母に訊いても家系に該当するものはいないとのことだったが、術後も便秘時の排便出血が度重なるような痔主となって、植民地朝鮮で父と死に別れた三歳児の空白のままだった父の面影がなんとなく体質的肌触りをともなうものになった。(2022年1月30日公開)
続・本の一言:街道と民家(7)里山と手伝い
「うまく言えないのだが、私たちはすでに、いのち
と共生しているのではないだろうか。人が生まれ、
そして生き、子を作り、死ぬという変化は、根本的
には、意思や努力や感情といった人間的な事情とは
関係ないところで起こっている。いのちは自然の営
みであり、それと並走することはできても、所有す
ることはできない。生まれるとは、いのちの流れに
ノることであり、死ぬとはいのちに追い越されるこ
となのではないか。私たちはすでに、思い通りにな
らないものとともにある。
(伊藤亜紗/胎盤とバースデーケーキ)
母方の祖母だけでなく祖父も亡くなってからだが、在りし日の立ったり歩いたり座ったりなどそれぞれの立ち居振る舞いが不断の稽古姿みたいに透けて見えたりするのは、それだけ自分が〈老境〉に近づきつつあるからだろう。だからと言って〈死〉が近づいたとも思えない。
おくればせながら歩けるようになった就学前のある朝、あたりがざわついている近所の雰囲気に誘われるように家人の後について入った一軒置いて隣の家の炬燵で生気のない女の子が横たわっていた。思わず頬のあたりに手をだしていたが、何にフれたのか、サワったのか〈実感〉がなかった。引っ込めた指が〈怖さ〉で震えることもなかった。祖父や近所の人が手伝った「葬式」の後になって、伝え聞いていた父や実家の祖母の家族以外の「死」を、はじめて恐れるように身近に感じた。
同級生とつるんで遊んだりすることの少ない中学生だったが、収穫の秋に砺波の大工[棟梁]のおじさんがひょっこり埴生の我が家を訪れ、富山と石川県境の倶利伽羅山あたりに連れ出されたことがあった。あいにく祖父は不在で山葡萄や茸に不案内な孫が同行せざるを得なかった。おじさんが運転する軽四トラックを山道の傍に乗り捨て、たがいに離れ離れになりすぎないように緩やかな雑木林の斜面へ分入った。あれこれ探すうちに眺望が開けた端の潅木に絡むアケビの蔓を見つけるまではよかったが、たわわに熟した実を見上げながら寄せた体がいきなりスポッと沈んだ。左右両脇がヤマツツジの茂みに引っ掛かっただけで足が地についていなかった。こわごわ俯いた足先に地面はなく、落ち込んだ粘土混じりの土砂崩れ跡の先に瓦礫しか見えなかった。助けを求める声も出ず、宙に浮いてるヤマツツジの崖っぷち側の枝をびくびくしないようにそっと両手で引き寄せ、なんとか身を崩れ残った崖っぷちに届かせた。冷や汗と無事に切り抜けられた思いが鎮まってから何気ない振りを装っておじさんに合流したが、何をどれくらい採ったのかもはっきりしない上の空状態で山を降りた。
家に帰っても内心が落ち着かないものだから、ヤマツツジの茂みに引っ掛からなかったらすりぬけおちてどうなっていたか分からなかった事態に気づかなかったおじさん同様、家族にも話せなかった。
低木に両脇が引っ掛かった枝葉の隙間から見えた、真下の赤茶けた土砂が崩れ落ちた底の瓦礫からの高さに、息が止まらんばかりの声にならない身の震えが張りついた光景が夢に現れるようになってしまい、いつの間にか爪先立って縁側から覗き見た三歳児の最初の記憶だった富山大空襲の夜空の夢を見なくなってしまった。
墜落夢から醒めるたび、見下ろした底の瓦礫が柔らかい堆肥みたいな腐葉土だったらとか、命綱を持ち合わせていたらなどなど‥‥‥取り留めのない想念が浮かんでは消えるように、いきなり足元の感覚が取り払われた恐怖に浮いた身体感覚も薄らいでから、ようやく台風の集中豪雨による土砂崩れ跡の茂みに遭遇した吹けば飛ぶような虚弱児の軽さと弱さにも助けられた気がしてきた。
祖父や家族と持ち山への往復で歩き慣れた間道からおじさんと一緒にちょっと逸れただけだったのに、地に足が着いている安心感と倒れたり堕ちることへの不安感の間で揺れ動く小心で臆病でしかない卑小な自分が打ち壊されたようだった。家庭内の祖父の打擲だけでなく家の外でのいじめ体験の裏でもひた隠しにしてきた逃げ道のない行き場のなさが、思い掛け無い〈死への恐怖〉に揺さぶられていっそう道無き道に迷い込んだ気分にとらわれるようになった。道に行き詰って前にも後ろにも進めなくなったら這いつくばってでも横に超えるしかない。小学高学年になるにつれてイジメがきつくなってきた頃だが、休み時間になると理科室だったかの図書コーナーの片っ端の本から手当たり次第に最後まで辿ったりしたが乱読にもならなかったようで『おくのほそ道』の感触しか覚えがない。
街道を旅しながら言葉で景物を接写する老詩人の近寄りがたい姿以上に、軒端や庭の木に網を張る蜘蛛が網を張り上げる糸の順番や粘着糸とそうでない糸の繋ぎ目や、ヤゴや蟻地獄など道から逸れたみたいに変態する虫の姿かたちなどに気を奪われがちだった。
小さい頃から気になった街道をゆく老人の後ろ姿のイメージからかけ離れた優柔不断なぼやけた自画像の前に座り込むような無為の部屋に面した街道の静けさ。砂利道を踏んで往来する村人の動きは少なくても重箱の隅を探るような視線は確実に米櫃の底まで届いている。家長を除けば家屋内での家族の居場所は流動的だったが、箸や食器だけでなく洗面用具なども家族それぞれ個別に使い分けられていた。庭の草むしりや田んぼや畑仕事の手伝いなどから天候だけでなく季節的に変化する身体感覚に目覚めたようで、移ろう遊び事だけでなく性的な関心も芽生えつつあった。たまたまいじめグループじゃない子どもの家の庭で遊んでいて「寝たきり老人」を見かけたりすると元気な祖父を嬉しく思ったが、「寝ていて人を起こ」したりしがちな祖父がなかなか起きてこない朝など、「ひょっとしたら」と案ずる家族の沈黙が晴れるまで気が気じゃなかった。
中学に通うようになってから祖父の許しを得て縁側の戸袋がある片隅を毛布で仕切り、母が買ってくれた机と椅子を置かせてもらった。中古自転車を買ってもらった手前、毎朝のヤクルト配達は続けていたが、夏休みの小遣い稼ぎにやった柴[薪用雑木]担ぎや古綿打ち直し集配や酢の瓶詰めラベル貼りと木箱詰めそのほかはほとんど続かなかった。手にした小金で鉱石ラジ作りから管球ラジオ作成へ、深夜放送の物珍しさなど国内から国外へと受信電波の遠隔化にもすぐ飽きてしまった。英作文の練習相手に少年少女向け雑誌に掲載された海外ペンフレンド登録者数名に手紙を出したら英米独の三名から返事がもらえたのに当方の文通力不足でいずれも立ち消えに終わった。たまたま在日米軍向けラジオ放送で身体に心地よく響く音楽を耳にしたのがジャズの聴き始めだったが、まるで演奏者の身体の一部みたいに奏でられる楽器に興味を持つようになり、手当たり次第に音楽室にあった楽器に触らせてもらったりしたこともあった。
本を手にしても祖父から咎められるようなことはなくなっていたが読書癖にはほど遠かった。息子の同級生に貸本屋の息子がいるのを知った母から指示された本の運び屋に徹して「貸本漫画」には手が届かず、中学卒業までに何冊運んだかわからないが三島由紀夫『美徳のよろめき』の一冊は男と女の関係妄想みたいな手触りがした。
中学時代の自分が自意識から現実世界への潜り戸を跨ごうとしたように、出生地の京城から引き揚げ先の埴生にかけての幼少期に一つ目が、そしてどう思春期をくぐり抜けられるかが三つ目の関所みたいになって意識と無意識の断層が織り上げられたりするのではないかと。
なんとか中学そして高校と歩き抜けてからのことだが、同じ著者の『午後の曳航』で洋装店を営む未亡人と十三歳の息子とその仲間らが母の恋人の航海士をめぐって織り成す不気味な物語を読み、蛹繭のような揺籃期と思春期の狭間で意識の来し方行く末の迷路で蠢く幼虫でも成虫でもない制服を着た爬虫類の変形譚を空想した。
家にテレビはなくプロレスなど近所の農家の数少ない友だちの家で見せてもらえたが,独りで楽しめる小説や漫画など見聞きするものに先行する何故か作り物めいた不自然感が邪魔をしてただの食わず嫌いから抜け出せなかったようだ。
映画館に入る余裕などなかったのに、たまたま『サムソンとデリラ』(1950年日本公開)を観て、小学校の理科室でナトコの映画で観た『オズの魔法使い』以来の感銘を受けた。燻る囲炉裡のように村の暮らしだけじゃなく学校でも逃げ場のない煙たさに辟易しかかっていた自分に風穴を開けられた気分に酔ったみたいな数日が不思議だった。
中学のクラスでのいじめも陰湿だったが、体力や知力を身につけようとして入部した剣道部や放送クラブではいじめが無く続けたられたが消極的な受け身姿勢は相変わらずだった。
滑り落ちそうないじめ関係の隙間で同級の男子生徒と懇ろになったり仲違いしてみたり、学年の違う女子生徒に憧れるようなことをしてみたり、中身と入れ物が合わないような心身の居心地の悪さで姉や母とも衝突しがちだったが、いささか体力が衰えつつある祖父に従う時節の畑仕事の手伝いが日々の和みの句読点にもなった。何事も不潔で窮屈にしか見えない年頃特有の視野の狭まりで昆虫や植物への関心も見失ったように勉強にも身が入らなくなり、祖父の目を盗んで手折った庭木などのスケッチや五七五の真似事を毎晩書き溜めたりしはじめたが破り捨てた感触しか残っていない。
中学通学の行き帰りはおなじ街道筋なのに田舎家が軒を並べる埴生と多様な小商い店が向きあう石動町とでは大違い。貸本屋とおなじ並びの洋品店のハスキーな女子生徒とはたまに登下校が一緒になったりしたが、村中の街道筋でそんなことは起こりようがなかった。奇妙なことに小・中学期あわせて苛める側にまわった女の子には会わなかった。それとなく男子に気取られないように陰になったり日向になったり、見えない傘を差し掛けられるような気配に救われた場面は一度や二度じゃなかった。2歳年上の姉にいじめがあったかどうかはその気配も感じられなかったが、ほんとうのところはどうだったのだろう。
小学校の休み時間に黄色いスカートが似合う転校生から『婦人雑誌』を差し出されたことがあった。埴生の街道筋の駐在所に転勤になった警察官の家庭で、埴生出身で敗戦間際の植民地京城で殉職した警察官とその引揚げ母子家族のことが話題にでもなったのだろうか。戸惑いながらも手渡された雑誌を家に持ち帰って見せた母に喜ばれたまではいいが、受け渡しの現場を見咎めたいじめっ子の格好のネタにもされた。
敗戦後間もなく何らの縁故もなくて都市の引揚者収容所に引揚げてきた家族の子どもらは「外地から転がり込んできた乞食」(李淵植著・舘野皙訳『朝鮮引揚げと日本人:加害と被害の記憶を超えて』明石書店2015年12月刊197頁)と近所の子どもたちから嘲られたり、どこまでも“異種”扱いから逃れられなかったようだ。泣きながら帰ってくる子どもらを見つめる父母たちは植民地暮らしで「現地人を怠惰で、無能で、無知で、不潔で、無謀な抵抗だけに明け暮れる集団と罵倒した。その日本人が、敗戦後祖国に帰ると、同胞から全く同じ罵声を浴びせられたのだった」(『前掲書』201頁)。
敗戦直前に埴生のような田舎に引揚げてきた家族には、「あなたたちは外地で良い暮らしをしてきたのだから、少しぐらい苦しい思いをしても当然だ」(同前)とばかりに、植民地から着の身着のままで本土帰還した普段着姿が地元にふさわしくないと見咎める視線が待っていた。
隠しきれないほどの引っ込み思案だったのに、貸本屋と街道を挟んで指呼の距離にあった写真屋の娘とも同級だったよしみからか、買えもしないカメラを触らせてもらえるようになった。いろいろ教えてもらったりしているうちに貸してくれた白黒カメラで写したのが杖を手に作務衣を着て庭で微笑む祖父の立ち姿だったとは。
母の死後に仏間を掃除していて何気なく開けた仏壇の引き出しの『教典』2冊の下から6×9cmサイズのモノクロ三枚を見つけ、なんとも言えない気持ちになった。中学生の孫が撮った自分のポートレートそんなところに仕舞い込んでいたなんて。戸の桟につかまり立ちして富山空襲を遠望した縁側やその手前の引越移植前の庭木の懐かしさの向こうから幼少時に祖父から受けた払拭しきれない何かが湧いてきて母や父の遺影のように写真立てに飾る気になれなかった。
母とは違って「毎日新聞」と「教典」しか読まない祖父から「勉強しろ」なんて言われたこともなく、中卒間近な孫の就職か進学の岐路では、黙認するみたいに姉の商業科進学も弟の普通科進学も成り行きまかせ。貧乏家庭なのに祖父のような丁稚奉公や流行りの集団就職などは選択肢になく、母は修学資金制度を利用して高校に通わせてくれた。
高校の学校林の下草刈りに駆り出された際、サボって桑の実を食べたりしているうちに迷って山の利賀村側に下りたあたりの農家の天井裏だったろうか。そこで飼われていた「おしなもんさま」の卵が「毛蚕」になって桑の葉を食べながら成長して脱皮し、自然下では育たない幼虫は養蚕家のもとで化蛹し、蛹繭の中で体が作り変わって脱皮した蛹になり、羽化すると自ら繭を破って成虫へ、まるで〈民家〉でうろうろさ迷っていてどこにも辿りつけない〈街道〉を紡ぎだしているような幻想に染まる八乙女山を後にした。
高校へのガソリンカー通学にともない、埴生内の最小範囲に絞った毎朝のヤクルト配達に穴を開けそうになったときなど、近くの自動車学校で働きはじめていた母に配達を頼んで登校するような始末で、やむなく埴生のそれ以外の地域を配達をしていた近所の学生に引き受けてもらった。
持ち山の管理だけだなく田植えから収穫までの年間作業など年老いてきた祖父は近くや遠くの知り合いに任せるようになって家族労働の機会が減少してしまい、日祭日以外は祖父と擦れ違い家族みたいになってしまった。
家族連れで外出した頃の幼い目に焼き付いた北陸線の主要駅や賑わう街頭などで戦争で身体を負傷した“白衣募金者”を見かけなくなったのに、進学した県立高校では戦時中の軍隊で心身を負傷したような体育教師がのさばっていた。幸い担任ではなかったからぶん殴られたりしなかったが、全校集会で生徒に怒鳴り散らしたしたり手をあげたり、なすがままを黙認する校長や教頭をはじめとした諸先生の態度にも虫酸が走った。
石動駅から通学利用していた旧加越線下車駅が乗り換え接続していた福野駅の城端線ホームから一駅と近くなった母の実家へは気の向いた放課後に寄り道することもあったが、その秋の午後はテレビのあった教室で日本シリーズ[大毎vs.大洋/1960.10.12]を観覧していた。いきなり野球中継画面が切り替わって、日比谷公会堂壇上で講演中の政治家[浅沼稲次郎61歳]が下手から駆け寄った若い男[山口二矢17歳]に刺されてよろめき倒れる映像に驚いた。もし体育教師に見つかって「用のない奴はさっさと帰れ!」などと学校から追い出されていたら見逃すところだった。学校が管理する秩序に縛られたような口先だけの自由からどれだけ〈無用の用〉がこぼれ落ちてしまったかだれにもとり返しがつかない。
当時70代の祖父に比べて若く見えた巨漢[大学では相撲部や漕艇部に在籍]があっさり殺られるなんて信じられなかった。凶器の刃物は家にある軍刀の半分位の長さに見えた。握った刀身と一体になって体当たりするまでに17歳の少年はどんな道を歩んできたのかが謎めいて見え、高校の校舎で行き交う生徒たちにまぎれてなんとなく我が道を行く風な存在感を漂わす〈少年や少女〉を探し見るようになった。事件後の少年の自殺のニュース時にはぼんやりとしながらも母の実家で叔父さんに触らせてもらったことのある白木の鞘の抜き身の感触が甦った。
実家の長男が病死して持ち上がりの長男だった三人の子持ちの叔父さんから母は物心ともに配慮してもらっていたようだが、進路を決めかねていた高卒間際の甥っ子の大学の学費の負担をかけるなどもってのほか。出戻った子連れの叔母さんが実家で同居していたから家計にはそれなりの余裕があったのだろうが、実父でもないのに生涯に負担を残すような面倒はかけられなかった。実家の祖母はそんな経緯を知ってかしらずか、昔語りみたいに“起きて半畳、寝て一畳。天下とっても二合半“などと茶化すように和ませてくれた。
いち早く受験しておいた国家公務員の税務職員採用試験に合格していたのにいっこうに採用通知が来ず、縁故就職のあてもなく、クラス担任が勧めた地元の大学の教育学部受験の願書提出にも応じていなかった。戦中戦後の子育て暮らしをやってのけた母の心配とは別に、孫の将来の事など“面々のお計らい”みたいな祖父の存在が何ものかだった。(2022年4月16日記/24日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(8)就職と一人旅
「その時期の友情のことを太宰は〈純粋ごっこ〉
みたいなものだと言ってるんですね。〈純粋ご
っこ〉とは人間と人間がお互いにどれだけわか
るかということで言えば、もう骨の髄までわか
った感じを体験できる時期なんだ、と言ってい
るんです。つまり、世間的、社会的には通用し
ない時期だからこそ〈ごっこ〉なんだけど、で
も、心から自分以外の人をわかった、人間もわ
かったというふうに思えるのはその時期しかな
いんだとね。
僕もそういう感じがしているんです。だから、
この〈純粋ごっこ〉の時期を除けば、結局、こ
の世は全部ひとりだよってことなんです。」
(吉本隆明・聞き手 糸井重里「「友だち」ってなんだ?」/『悪人正機』)
「以上のように、友だちとか友情を結論付けま
すと、「じゃあ、人間は歳とともに、生きると
ともに切なくなるんじゃないか」という意見が
出てくるでしょうが、実は、その切なさみたい
なものは非常に大切なことでね、なくさないほ
うがいい感情なんですよ。
普通の人間っていうのは、たいてい、幼い頃
の友だちの存在を忘れたりとか、薄めたりとか、
利害のことだけが先に来るとかっていうことに
なっていきますからね。
実際、その時期の友だち関係をずっと持続で
きたら、文句なしで、それは本当に本当にたい
したもんなんです。なおかつ、そういう友だち
がひとりでもふたりでもいたり、利害とか生死
とか、そういう際どいものも含めて持続できた
ら、その友だちはその人にとって宝物みたいな
もんですね。」(同上)
総合高校普通科三年の時のクラス担任が卒業後の窮状を見かねて紹介してくれた金沢の税務会計事務所に通い始めたが、不埒な先輩の鞄持ちに我慢がならず、“出勤拒否”で応じた“不始末”の尻拭いを母にさせてしまった。若気の行ったり来たりみたいな紆余曲折を経てありついた大学図書館の仕事にも馴染めず、かといってプー太郎にも戻れない空白を持て余したみたいにラヂオで大学受験講座を聞くなど一年余り朝晩問わず机にかじりついたりした。そんな息子の豹変ぶりを母は持て余したようだったが、夜間の照明を消して回ったりするようになったりしていた祖父からは何のお咎めもなかった。
一回しか貰わなかった税務会計事務所の給料袋はそのまま母に渡したが、それから数千円目減りした毎月の国家公務員「一般職」の給料袋も同様に扱い続け、年間小遣い銭として手元に残る夏と冬のボーナス袋の中身から学費貯金など積み立てる余裕もなく月日は過ぎた。いざ関西の国立大学の願書を取り寄せたり高卒の成績証明をもらいにいったりしているうちに、やっぱり“家計優先”しかなくなり、勤務先の附属図書館本館があった経済学部の併設校舎で授業が行われていた富大経営短期大学部(夜間3年制1959年設置〜1990年廃止)受験に鞍替えすることにした。遠隔地の志望学部受験を断念した余勢でたまたま仕事と両立できる学び舎に踏み入っただけで、特に学びたい学科や科目もなかった後ろめたさから必須も選択も履修できる科目の単位をすべてとったりした。小学校以来の“学校嫌い”だったのに、木造の教室に高校新卒者から中年の社会人まで集まってくる女性が少ない夜間学生がかもしだす雰囲気は悪くなかった。
経営短期大学部入学手続きの際に学務担当から授業料減免手続きを勧められたが、その場でほかの入学生にまわしてくれるようやんわり辞退し、すでに高校の修学資金を一括返済してくれていた母には内緒にした。三年後に大学事務局から割り振られた富大卒業式での経営短期大学部代表答辞はどうあがいても辞退させてもらえなかった。どうにか書きあげた原稿を勤め先の和文タイプライターで清書してくれた母に、もう「答辞」は読んでもらったから来ないようにと断わっておいた当日の式次第は大学固有の序列で塗り固められていた。学長以下各学部長および附属各施設長の席順から図書館長は末席扱いと知った。
埴生からぽっと出の偏見かもしれないが、表向きは“学問の府の中枢”などと言っておきながら、図書館長人事はどう見ても学内の学長や学部長への出世街道から外れた“名誉職”のように見えた。建物は経済学部の間借りだったし旧制師範学校蔵書数なども設置基準に含めた蔵書構成など素人目にも貧弱に映った。
短大卒資格は「司書補講習」受講免除扱いだけで給与に反映されず、現職からの異動や転職ではなく手取り給与の特別昇級狙いで受験した「中級職採用試験」に合格したら、馴染みはじめた整理係での仕事現場にやってきた本部事務局の人事担当係長や出入りの大手書店の支所長から「図書館にいてもうだつが上がらないから」と引き抜き人事勧誘されたりした。
5学部からなる地方の総合大学の図書館が受け入れる図書の整理の仕事は無学者にとって難儀だった以上に、なぜか横書きの学術書に違和感を感じた。図書の整理作業の前提となる横書き印刷された和・洋図書の分類のし難さを差し引いたとしても、判読し難い縦書きの和装本や漢籍にはなんとなく親しみを感じた。受け入れ図書の目録カードも横書きだったが、自分の手書き作成カードの筆跡が複製されて各種閲覧目録カードとして利用者に公開されるのが恥ずかしくて堪らなかった。やがて印刷カードの導入に続くコピー・カタロギングシステムの共同利用によって手書き目録カード作成にともなう気恥ずかしさは薄らぐことになったのだが。
短大在学中の学友会の機関紙や10号ほどで潰れた「同人誌」の編集・発行に携わったりしても“書いたものを晒す”抵抗感から逃れられなかったようだ。数少ない異性との縦書きの手紙のやり取りだけは違和感がなくてよかった。面と向かって目を合わせながら話すのが苦手で、たまたま同じ道の通りすがりに肩を並べて言葉を交わすというような成り行きが気楽だった。
十代から二十代への曲がり角の春先の気ままなローカル線乗り継ぎ一人旅の夕暮れ、岡山駅前の公衆電話から当夜の宿泊予約がどこも満室で断られて途方に暮れそうになっていたのを見兼ねてか、隣合わせの電話ボックスの女性から声をかけられた。真っ先に断られた国家公務員共済加盟宿を除きまだ未確認のホテルなど優しい声で問い合わせてもらったが空室はなかった。電話帳のページを閉じた彼女の指が回したダイアル番号の相手の了解を得て案内された岡山大学男子学生寮の一室に迎え入れられた。
富山からの“風来坊”を紹介し終えた岡山市内在住のT橋さんは帰宅の途へ、一夜泊まりさせてもらえることになった熊本出身のS藤君には先ずは夕食でしょうと夕暮れ迫るキャンパス内の学食へと誘いだされた。路線バスが乗り入れているキャンパス風景がもの珍しかった。まさかの成り行きの宿泊に背中を押されるように宇高連絡船で四国に渡った頃から天候が崩れだし、翌日から予定していた瀬戸内海の船旅を諦め、満室でも断られたことのなかった山小屋旅とは違う都会の旅先での一宿一飯の恩義を土産に引き返えすことにした。折しも北上する桜前線に合わせたみたいにのんびり運行されるローカル列車を乗り継ぎながら。
停車時間が長めの駅構内で特急や急行に追い越されたり、通勤・通学時間帯を外れた客車を出入りする地元の乗降客の会話を耳にしたりしながら、煤けた硬い座席に身を預けた初めての鉄道旅の帰路。山旅の時と同じように借り物の銀塩カメラで何処で何を撮ったかが朧げなように、二泊三日で終わった旅先の人との出会いや風物などは遠ざかるばかり。自分がいま・ここで揺られている鉄道路線を過去に遡った敗戦前、明治生まれの祖父は大阪での奉公生活の年季明けまでに、ともに大正生まれの父と母は海を渡った京城での植民地生活が[父の殉職で]途絶えるまでに、それぞれどんな思いで往復したことだろう。
登ったり下りたりした山歩きがそうだったように今回は貧乏旅をしてみたということだけが取り得だった。働き始めた職場のアフターファイブや、夜学の放課後の酒場など、村では出会わなかったような顔や癖を隠し持った人たちとの付き合いから祖父に言い聞かされた「公界」の裏表を実感させられるような事柄も学ばされた。
腰を落ち着けて「図書館職」をこなすにはどうしても「司書資格」を!ということで白山キャンパスの東洋大学でやっていた二ヶ月間の夏期司書講習に行かせてもらった。200名余の受講生のうち男性は30名ぐらいで夜間短大の講義に続く“特別集中講義”という雰囲気だったが、食欲も減退するような都会の蒸し暑さには参った。駒場で下宿していた大学生の従兄弟のアパートから巣鴨まで電車の定期券で往復した通りすがりに“街道”のイメージはなかった。縦並びでも横並びでもなくせかせかと行き交う人々の流れに右往左往しながら新宿あたりで途中下車してジャズ喫茶を探しては、日を改めて出かけたりした。黒いリボンがかけられたジョン・コルトレーンの肖像額に気づいて、お店の人に確かめたらビリー・ホリデーの命日と同じだった。
司書講習期間中に“ジャズファン”とは出会わなかったが、講義で隣り合わせた山好きな山梨の女子受講生から手作り弁当をご馳走になったり、体操が得意な三軒茶屋の男子受講生に誘われてユニバシアード大会開催中の体操競技[東京都体育館]や陸上競技[国立競技場]を観戦したり、埼玉から通っていた大卒受講生には蕨市の自宅に泊りがけで招待された。壁いっぱいの教育関係の専門書だけでなくマルクスやエンゲルスやレーニンに並んで「吉本隆明」を見つけて話がはずんだが、ほとんど聞き役だった。「60年安保闘争」で吉本さんらと一緒に「敗走」を経験した早稲田の卒業生で、静岡で就職した「高校教師」を辞めてまで「司書講習」を受講する“本気”の人だった。
田舎住まいの家計や生計のために生きる見極めもつかない中学生半ば、〈いま・ここ〉に在る〈自分とは何か〉に居ついてしまったような“自分”という身体を持て余すしかなかった。なんらの手応えも見つからないまま徒歩とガソリンカーで通い続けた木造洋館建ての高校の本館の風情に別れを告げて間もなく、いかにもにわか作りといった感の夜間短大の木造校舎に通い直したりしたが、先の見えない袋小路に迷い込んだようでなんとか生きている〈時・空〉の隅々まで見通せるような立ち位置の分からなさに焦りながら通勤(学)する北陸線の車内が読書の時間になった。
1960年代半ばの吉本著作の全貌も掴みきれていない遅れてやってきた未熟な読者で“ジャズフリーク”の自分には、A面が詩集でB面が批評からなる膨大なレコードのトラックに針を降ろすように吉本さんの声と言葉を聴き漁るしかなく、初読の高鳴りだけでなく読後の隔絶感も伴う縦書き〈文体〉から身体に響いてくる射程の奥行きと広がりに魅せられたように引き込まれる手応え。
〈読み手〉が生きつつある世界[当時の]情況の〈いま・ここ〉を呼吸している〈書き手〉の存在が書き記している先に目指している〈何か〉を追っかけるしかない。当時聞き漁ったジャズ[喫茶]レコードに負けない意気込み。高卒後から読み漁った中原中也や太宰治とは比べようのない惚れ方だった。田舎育ちの手にも目にも余る吉本著作をどこからどう読み込めばいいのか、その表玄関や勝手口もわからないままに。
1966[昭和41]年秋の『文芸』(河出書房新社)11月号から連載された吉本隆明「共同幻想論」の第1回「禁制論」に、春先に亡くなったばかりの“実家の婆さん”から幼い自分が聴き馴染んだ昔語りの幾つかによく似た“山人譚”が引用されていて近親感が湧いたが、翌年4月号までの各「論」そのものの展開についていけず、数年後の雑誌連載を加筆訂正して後半に書き下ろし各論を合わせた単行本『共同幻想論』は、祖父が日夜頁をめくったよれよれの和綴じ『経典』とまではいかないが、布装ハードカバーの背表紙が判読できないほど剥げ落ちた手元の一冊になった。たまたま就職先が属していた日教組系の教職員組合に籍を置くことになった分会活動からはみ出すように夜学で知り合った「活動家」らが主導する反日共系の「街頭行動」にも「秘密裏」で潜り込んでまるで二足のわらじを履くようなだらしない自分の行動に行き詰まり悩んでいた、人間の生涯が逃れられない〈錯綜する三つの幻想的関係性〉について考える糸口が見つかった気がした。
明治大正昭和を生きてきた祖父や実家の祖母には“御仏さん”[浄土真宗]が人生のよすがみたいだったが自分にそのような契機は訪れそうになかった。「人として悟りを開く」とはどういうことか?人とは何か、悟りとは得られるものなのか‥‥‥。毎朝玄関で母から弁当ではなく昼飯代を貰って歩いて[時には自転車で]石動駅へ、北陸線の客車にしばし揺られて降りた富山駅前から満員バスで職場へ通う毎日の繰り返し。
埴生を抜ける街道が北陸線の踏切を渡って石動駅方面へ出る通勤途上で毎朝見かけた一軒家のガラスの入った格子戸や目の粗い木虫籠[きむすこ]を濡れ雑巾で拭いていた“姉さん”の姿。祖父や実家の祖母が言い習わしていたいわゆる村の〈家屋敷〉からほど遠い庭や木立もない平家の一軒家にそぐわない風情でいつも足早に通り過ぎるようにしていた。潜り戸のある大戸に並ぶように目の細かい木虫籠をはめ込んだ村の民家の貌が崩れつつあるように感じたのかもしれない。もっとも大正期に祖父が建てたであろう我が家の木虫籠が子ども心にはよそ様に比べて目が荒く[あるはずのない]正統な民家から外れつつあるように暮らしてきたせいだったかもしれないが。
1970[昭和45]年前後の吉本[46歳]さんんの著書はすでに70冊を超えていたようだが勤め先の大学図書館の吉本本の所蔵は少なく、手にしたのは富山市内の古本屋で買い求めた詩集や評論集などで、もっぱら定期発行されていた『展望』[筑摩書房1964年10月復刊ー1978年]や『文芸』[河出書房新社1962年復刊ー]そのほか数軒の書店の新着雑誌棚から手当たり次第に目次をめくって「吉本隆明」の掲載作品の追っかけで手一杯。「言語にとって美とは何か」や「心的現象論」が載っていた『試行』は同人誌仲間から回し読みやコピーさせてもらっていた。おりしも勁草書房版『吉本隆明全著作集』[全15巻、1968.10〜1975.12]が刊行中、“四十”そこそこで「全著作集」とはなんて凄い詩人であり批評家だろうと読むのに尻込みしそうだった。そんな背中を押されるように読んだのが各巻末の解題(川上春雄)だった。あれから25年過ぎた2000年3月から2019年12月まで継続購読した『吉本隆明資料集』(松岡詳男@猫々堂)の力仕事には自家発行〈表現〉による〈吉本隆明論〉が刻み込まれている。また現在刊行中の晶文社版『吉本隆明全集』各巻末の解題(間宮幹彦)には編集〈表現〉による〈吉本隆明論〉を読む思いがする。(2022年6月27日記/28日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(9)吉本〈初期〉拾い読み
「5億年にわたる土の「変化」は生き物を育むだけでなく、時には生き物
たちを翻弄しながら、現在の自然の姿を形作ってきた。そのひとつが土の
「酸性」への変化であり、アジサイの花が青色に染まる理由も、宮沢賢治
が「雨ニモマケズ」石灰肥料を売り回った理由も土が酸性であったためだ。
土を含む環境の変化に対応して生き物たちが獲得した多様な姿に、「適応」
や「変化」を見出したのがダーウィンであった。」
(藤井一至/大地の五億年:せめぎあう土と生き物たち)
遅まきながら見えてきた吉本著作の書誌的履歴を手繰り寄せるようにあれこれつまみ読み状態のさなかに出会ったのが吉本隆明『初期ノート増補版』(試行叢刊第一集)[試行出版部1970年8月、初版は1964年6月刊行。2006年7月光文社文庫版刊行]だった。
埴生村の民家に住む子どもや老人らが家屋敷の庭から縁側に回って上がりこむような吉本著作世界への手合があったとは!
自らの〈初期〉に祖父から釘を刺されていた読むことの罪障感、それまで気になってしょうがなかった読み・書きの表口や裏口など敷居の高さを感じさせない手触りの装丁本の冒頭の「姉の死など」に引き込まれ、仏壇に手をあわせるように上がり込んでその先を隅々まで読み進めることになった。
海風の赤いぐみのせんせいせんせい
私は何処かで斯んな俳句を聞いた事がある。(吉本隆明/随想(其の一)【第 II 部 戦中篇1少年期】)
くものいとに
息を吹きかけながら
明日の日の
小さな声を
にはとこの
ざやめきに
真実きいた
軒端のくものいと
くもは居ないよ
息ふきかけて
夕焼 小焼(吉本隆明/くものいと【第 II 部 戦中篇1少年期】)
唯自分の考へてゐる処を表現しつくして、その時の何とも言へぬ安心から出発してもっと深い自分を見付けて行くのです。文章は少くとも僕達化学者が(化学をするものは皆化学者です。これ以外に化学者の定義はありません)書く時は、そのような安心立命を得るためと、その安心から出発してもっと深い自分を探して行くためであると思ひます。それだから文章を書いたり、書物を読んだりするだけで、自分の人間をより深いものに導くことが出来ます。それ故文章を書いたり読んだりすると、現実を遊離してしまふなどと考へてゐる人間は問題になりません。又文章を書いたり読んだりしながら現実を遊離してしまひはせぬかと不安に思ふ人はやはり駄目なのだと思ひます。僕はその駄目な人間の一人です。僕は僕達が現在持ってゐる大きな問題や決心については何も言ひません。それは余りに大きく、そして真剣な問題だからです。もっともっと深く考へて、その時僕達は日本人である僕達を心ゆくまで語り合はうと思ひます。(吉本隆明/巻頭言【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)
「幼い思ひ出」への回想に〈身体性〉が息づいている詩作品に次いで、1943[昭和18]年の若き吉本さんが自分の中の駄目な人間とそうでない何者かを腑分けするように、《化学》をするものとして《自分の人間をより深いものに導く》ように読み書きすることの〈初心〉が率直に語られている。当時の日本人が直面していた《大きな問題や決心》について学友に語ることは慎重に先送りされ、翌年5月に編まれた私家版詩集『草奔』を経て、「哀しき人々」および「雲と花との告別:これによって諸氏に告別せむとす 御元気で」[1945年4月、発表誌不明)]の2編が学友に手渡されたようだ。
私は帰省の時と帰校の時と、米沢と東京の間を必ず汽車に乗らなければならない。ところが、舟には決して酔はない私であるが、汽車に乗ると、必ず、私の頭に速度の観念が入って来て生理的に大そうむかついて来る。すると時間の観念が伴って来て、その相対性が甚だ頭を混乱させ、かすんだやうな意識の中から赤血球の運動量の変化が気になってくる。そうすると私はもう青くなって、窓を開けたり風を通したりしなければならない。私を汽車で苦しめるのは何時もこの相対性原理である。(吉本隆明/◯汽車の中【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)
しんしんとした蒼い空の無方にその花を浮べて眺めることなのだ。きっと、無上に美しいに違ひない。或日私は意識の超絶を随分恐れることがある。(吉本隆明/◯白い花【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)
郷愁は論理のない沈黙
こちらには冷たい灯
あちらにはあたたかい灯(吉本隆明/郷愁【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)
静かに風が動いていった(吉本隆明/山の挿話【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)
相対的な寒暖差の灯に包まれた郷愁の大地[東京と米沢]を行き来する際の“乗り物酔い”で、《赤血球の運動量の変化》に気づかせられるるように身体的な〈他者性〉に目覚め、仮定の誰かから贈られた「白い花」を「緑色の花瓶」に挿した机上からあちこち動かすうち、天井から吊るして空中に浮かべるだけでなく、《蒼い空の無方にその花を浮べて眺める》ような〈意識の空白〉を《静かに風が動いて行った》。〈揺れ〉に対して適正にカラダが反応できないことや景色の変化に焦点(視覚と意識)が定まらない心的状態の描写が人ごとではなかった。
小学校に上がる前後の数年だが、新年恒例の祖父に連れられた和倉温泉の行き帰りでの“列車酔い”の初体験以来、中卒頃までなぜか自転・公転する大地を動く乗り物上の自己意識感覚のズレみたいなものが気になってバス旅行にも馴染めなかった。
身体と心は同じもの? 実家の祖母に「心身一如」なんて言われても、そもそも両者の区別がつかず、〈身〉は〈心〉の入れ物というか〈乗り物〉ぐらいにしか思えなかった自分には、揺れや変化にカラダが適正に機能するとはどういうことか見当もつかなかった。同じものを見ているが、視点が違うことに気づけなかった。表裏一体のものかどうか、肉体がないなら精神もないが、身体だけはある。肉体よりなのが身体感覚だとしたら、精神寄りな身体感覚に当てはまるものはなんだろう。何となく考えること、〈思考〉がそうなのかな? と未だに手探り状態、肉体の動きが対象化された身体の感触を張りめぐらしたスクリーンに投影される〈修羅〉の影の行方をどう探るかが謎めいて。
いまにしておもひきはまりぬ
友どちよ
われのいのちに涙おちたり(吉本隆明/序詩@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)
ふう癩病者と紙一重ですが
それ程呑気な患者ではなく
瞋りと気焔を吐き散らしながら
修羅と云ふ表現圏を渡り歩くのです[原文下線部傍点](吉本隆明/原子番号0番@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)
闇色のさびしいマントの襟を立てて
孔雀のやうに拡がった空を見上げるのは
灰色吹雪の街を駆けぬけて
あなたのひと言をしんしんと聴くのは
斯の通りふるへてゐる私の影です(吉本隆明/原子番号一番@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)
《修羅と云ふ表現圏を渡り歩く》宮沢賢治の言葉に聴き入る《私の影》とは、マント姿に二重化された心情の岐路に佇む苦渋の心象風景にほかならない。
私はこれは最後の切り札なのですが
とても苦しい道なのですが
彼らよりももっと一途に青白くなることにより
彼らをむざんに踏みつけることにより外に
どうしてよいか判らないのです(吉本隆明/原子番号二番@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)
ともに戦時下を生きる学友に向けて〈いま・ここ〉にきわまる《おもひ》が涙となって「いのち」を濡らす〈別離〉の深まり。自然的存在からの疎外態「患者」が〈書く〉ことによって生じる表現圏に《道》を求めて渡り歩く心象風景、観念の相対性にさらされ混沌とした原形体が呼吸する〈寂寥〉のとば口を抜けた先の幻想としての〈自然〉を吹き抜ける「第二の風」が作り出した《かぶと山と虚妄列車》。山麓を走り抜ける列車の窓の外では民家も街道も「雲表樹氷の影」に覆われているのだろうか。
一つの定点を離すまいとする人間の寂しさは
厳酷な真意の影がそうさせるので(吉本隆明/銀河と東北@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)
たった一言の真言のなかに
万[角斗]の危機とさびしい諦観と
傾きかけたわたしの心象と影と
細々灯ってゐる道があるのです
瞋りや悲哭もまだとどかない
念々不断の合掌も通はない
修羅のひかりの道があるのなら
何故わたくしは通れないのです
こんなにさびしい月光のきらめきに
わたしはひとりで佇んでゐるのです
わたしはかくれて泣いてゐるのです(吉本隆明/繚乱と春@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)
《たった一言の真言》がもたらす心象風景に《細々灯ってゐる道》があり、万感の想いや不断の合掌も通わない《修羅のひかりの道》があるのに、ひとり佇んでいるのは岐路としての〈惟神の道〉なのだろうか。お盆には仏壇に合掌し、お正月には神棚に手を合わせる人間が「神さながらに生きる」とは、そんな《道》をどこでどのように会得できるのか。
さあれどんな場合でも
人間をはなれて「神様」があったり
人間の外側に「理想」があると思ふのは
インテリと呼ぶメタ人類の
淋しい暗い幻覚なのでせう(吉本隆明/無神論@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)
われら みづからの小さき影をうちすてて
神ながらのゆめ 行かんとす
まもらせよおほきみの千代のさかへ
われら草奔のうちなるいのり
まもらせよ祖国の土や風の美しさ
われらみおやの涙のあと
われはいのりて
ひたすらに 道しるべ たてまつる(吉本隆明/草ふかき祈り@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)
《宮沢賢治は常に最も生々しい現実にゐながら常に遠方に眼を注いでゐた それが遠方を見てゐる時は現実の生々しさを忘れ、現実の生々しさを視てゐるときは遠方を視なかったのではなく、二つの意識が同時に働くと言うことが少なくとも彼の場合には正常であったのである》[吉本隆明/農民芸術概論綱要評@「詩碑を訪れて」【第 I 部 戦後篇5宮沢賢治論】]とする態度が貫かれ、不確かな戦況下での現実を見るからには、とにかく自分の現実の外側に出ようとする純粋な姿勢が眩しい。
我ラハイマ
各々ノ心ノ中ニ 一ツハ美シイモノヲ抱イテヰテ
ミンナガ自分ノヤウニナツテ呉レタラト悲願シナガラ
大イナル祖国ノ闘ヒノ中ニ
自ラヲ捧ゲテ征カネバナラヌ(吉本隆明/序詞@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)
戦争期天皇制日本の在野の無名者として《神ながらのゆめ》に連なる《おほきみの千代のさかへ》を目指して祈り奉る《道しるべ》に刻まれた《祖国》へのはなむけ。
次に私は斯う言った。「頭髪を無造作に刈った壮年の男が、背広を着て、両手をポケットに突込んだまま、都会の街路樹の下をうつむいて歩んでゆく。俺は若しなれるのならそんな者になりたい。」
私も心にそう思ってゐたことをその通り言ったのだが、あまりすらすらとこれだけの事を言った訳ではない。はにかんだときのくせで、「俺はね」といふやうに「ね」を矢鱈に連発して、これだけ言ふのに自己嫌悪を幾度か飲込まねばならなかったが、言ったあとでは実にすがすがしい気になった。[下線部原文傍点](吉本隆明/哀しき人々【第 II 部 戦中篇3哀しき人々】)
気づいたら、〈いま・ここ〉にこうして生きている〈任意性〉のさなかで、刹那的に描かれた一枚の「自画像」を吹き抜ける擬人化された「雲」と「花」の対話、〈いのち〉を営む肉体の動きが対象化された身体像に投影された惜別の調べ。
雲「おれはともかくも ひとすぢのみちをゆくだらう 蒼い深い空の果てに おれが西の方へ走ってゆくのを見たら おれはみづいろのネハンの世界を求めてゆくのだと思ってくれ 又東の方の日輪のくるくる廻ってゐる辺りに おれが蒼白い曙の相をしてゐるとき おれは おれたちの遠い神々を尋ねてゆくのだと思ってくれ」
花「おれはこの季節が終ればもうこの世界から別れやうとする おれはおれの生れたところで死なうと思ふ この宇宙がある限り この季節になると おれのゐた茶暗い土からは 生れてくるものがあるだらう 誰が何といってもそれはおれの再生ではない 誰か見知らぬ奴なのだ けれどおまへが 何日の日か その上に戻ってきて 雨を注いでくれたら 矢張りおれは嬉しいと思ふ おれたちは結局すべてのものの幸のために生命を捨てるのだ」(吉本隆明/雲と花との告別:これによって諸氏に告別せむとす 御元気で【第 II 部 戦中篇3哀しき人々】)
「国家」や「領土」を尊重する〈心身〉が拠って起つ地平、人々が往き来し生活する大地に訪れた季節を彩る「花」を咲かせる植物の根が伸びる《茶暗い土》の中から《蒼い深い空の果て》まで、水蒸気となって循環する〈水〉を象徴する「雲」、雲行きを左右する風の行方、見上げる〈われわれ〉はどこから来てどこへ行くのか。
T君よ 宮沢的イデーはわたくしにとっては故郷そのものに外なりません 私は宮沢賢治を踏み越え踏み越え、全ての中に身を燃やしつくすことを自己の念願として来ましたが、祖国の遭遇した情勢は私が迷ひに迷ひ、苦しみに苦しんで築いた体系を根こそぎにくつがへしてしまひました わたくしは今は何も持ってゐません それ故謙虚に宮沢賢治のふところに還ってゆきたいのです
東北のもってゐる自然と風景こそ彼も持ってゐる肌合に外なりません 私たちは「国破れて山河在り」といふアジアの夜の倫理を味ふべきときに至りました 想像だにしなかったところですが、すべての自然にいこいを見出すことも又やむを得ない倫理として享受しなければならない日を迎へたのです 光栄の道はついえました 日本なくしてアジアなしの言葉の如く、アジアは日本の敗退と共に再び夜を迎へたのです
文学の精神はみだりに屈従しません まして敵国に遠慮するやうな情勢論は意に介しない所です 私たちは楠木正成の心境を幾許か身をもって理解することが出来ました そして在りし日の隠遁詩人たちの志をほんたうに理解することが出来たやうに思ひます 死ぬか何らかの意味に於て隠遁を事とするか、これは国の正統が行はれないときの日本人の身の処し方であることを知りました 私は宮沢賢治をこのやうな眼からも又眺めてゆきたいと思ひます
T君よ 宮沢賢治は情勢論などの一指も位置をくつがへすことの出来ない永遠の星座です 私のやうなものから見れば奇蹟のやうなものです けれどこの奇蹟の現実が今日を生きて如何に処したかといふ仮定を設けて見ずには居られないやうな気が致します。私たちは沈むだけ沈まねばならないでせう 真の偉大も又生れねばならないでせう 知の底の方からアジアの霊が叫んでゐます 天は暗く、依るべき存在もありません
宮沢的イデーは唯絶望的な私の前に青白く巨きく輝いてゐます 天の川だって歴史だってただ人がそう感じてゐるのに過ぎないのだといった彼の言葉も何か別の意味で惻々とと心を叩いて来ます
[中略]
日本の敗退は理念を喪失した人々だけが導いたものであることは論をまちません 理に依って動く偏狭な現実主義者は終に決定的な悲劇を導入致しました。 願くは偏狭な国際観念を排して、静かに難局に這入ってゆく豊かな日本の道を得たいと思ふのです。
T君よ
私が描く宮沢賢治の姿は実に不完全なものにすぎないでせうが すべて私のいこひをそこに懸け、私の生命をそこに打込み、すべての悲しみをそこに交流させて没入した処です
わたくしはその努力の中から生きてゆく可能性を見出さうとつとめました 願はくばわが歩む道に神よ名があらしめたまへと祈るのみです 何日か君と共に宮沢賢治の「野原の松ノ林ノ陰ノ」といふ詩碑の前に再び立ち、北上川の蒼暗い流れに対して見たいと思ひます あの時味った不思議な虚脱を私は今度は自分の生命として抱く日を迎えたことをどんなにか悲しみながら君へのこの便りを終りたいと思ひます (九・八)(吉本隆明/宮沢賢治の倫理について@『宮沢賢治論』【第 I 部 戦後篇5宮沢賢治論 】)
「T君」[1942[昭和17]年の4月に入学した米沢高等工業学校[山形大学工学部の前身]同期の郷右近厚らと回覧雑誌『からす』をつくった田中寛二?]に呼びかけた文末の「(九・八)」は、昭和20[1945]年8月15日の「天皇の詔勅」に動顛した翌月の日付だろうか。
〈いま・ここ〉に書き表された一行が手のひらの下に隠れ去るように左へ改行され、縦書きの空白の次行が書き表されて現前する文体の呼吸が《奇蹟の現実が今日を生きて如何に処したかといふ仮定を設けて見ずには居られない》切実さとして脈打っている。《宮沢賢治》を触媒として、過去も未来もない、ひたすら〈現在〉に生きるために渦巻くエネルギーと共鳴しているようだ。稀有で無類な〈共鳴〉によって逃れようもなく自らを強化していったに違いない。
〈関心〉と言ふのは何かを与へるような状態にも思はれるし、反対に何かを奪ふような状態のやうにも思はれる。結論。又悪循環におち入ってしまふだらうか。こんな時はひとつの逃げ手といふものがある。〈交換〉といふものだ。これは物理学や経済学でも便利な定義にやうに思はれる。それは与へることや奪ふことを同時に包摂させることのできる言葉だ。〈関心〉といふのは心情の〈交換〉のことだらうか。心情とは? そして心情の〈交換〉とは?(吉本隆明/一九四四年晩夏【第 I 部 戦後編2覚書 I 】)
‥‥‥生まれ、婚姻し、子を産み、育て、老いた無数の人たちを畏れよう。あのひとたちの貧しい食卓。暗い信仰。生活や嫉妬やの諍ひ。呑気な息子の鼻歌‥‥‥。
そんな夕ぐれにどうか幸ひがあってくれるように‥‥‥。
それから学者やおあつらえむきの芸術家や賑やかで饒舌な権威者たち、どうかこんな寂かな夕ぐれだけは君たちの胸くその悪いお喋言りをやめてくれるように‥‥‥。(吉本隆明/夕ぐれと夜との独白(一九五0年 I)【第 I 部 戦後篇2覚書 I 】)
「自由の第一の必要条件は自己認識であり、そして自己認識は自己告白なしには不可能なことである。」(K.マルクス)とは肌合の違う〈出会い〉の響き。この言葉の異質感はどこからやってきたのだろう。〈箴言知〉とでも言うべき言葉の歩み。
自由は必然性のなかにある。必然! 僕には無限に底深い言葉だ。僕はと或る日、その言葉をせっせと掘り下げてゐるのを感じる。現実が仮象のやうに遠のいたのはそんな時であった。(吉本隆明/序章【第 I 部 戦後篇3箴言 I 】)
絶望はその冷酷度を増した。一九四八年から一九五〇年初頭におけるニポニカ。
アルダンとソルベェジュの対立の激化。アルダンに強制された経済政策。
エリアンの心は救ひがたいまでに虚無的になってゐる。
*
この日、エリアンはひとりの少女を喪なった。夜。雲低くなり、雨がぽつぽつ降る。
*
一九五〇年に入り自殺者相継ぐ。プロレタリアートの貧困、中産階級の窮迫は急。電産、全鉱連ストに入る。
*
コニミスト、ファシスト共に民族の独立を主張す。エリアンこれに不信。
祖国のために決して立たず。人間のため、強ひて言へば人類における貧しいひとびとのため。(吉本隆明/序章【第 I 部 戦後篇3箴言 I 】)
男と女の関係を決定づけるものは他者存在としての〈家〉が作用し、人間と人間との関係は男・女いずれかとしての交通形態のように営まれてきたのではないのか。
何故に人間は不完全なものから完全なものへ、人性から神性のほうへーーといふ思考過程をたどらねばならないか。ぼくの精神のうち側に無数の嵐が荒れてゐる。それはみんな不完全な自己を完全な相に昇華しようとしてゐる沢山のナルシストたちがまきおこしてゐる嵐だ。若し僕たちの悔恨、虚偽、不完全‥‥‥が、関係のあいだの歪みとして解されるならば嵐はやむだらう。そして僕はあの呑気さうなアルダンの兵士たちのやうにそれを視なくてもすむわけだ。
神への信仰と従属。それはやがて権力と貧らんへの奉仕を人に教へるのではなからうか。
僕は沢山の書物の中から師を見付け出す。だがこの師は問ふただけのことについて応へてくれるだけだ。山彦のやうに。並外れた応へとしてくれることを期待することも出来ない。僕が並外れた問ひを用意してゐない限り。それからひとりでに教へてくれることもない。僕が憂ひに沈みきってゐるとき、何故なら僕はそんな時、書物に向ふこともしないで大方は夜の街々を歩いてゐたから見慣れない家々の灯り。それは唯の灯りであった。僕が様々の意味をつけようとしてもそれは唯の灯りであった。結局地上に存在するすべてのものは僕のために存在するのではなかった。僕がすべてのもののために存在してゐるだけなのだ。可哀そうな僕!
あゝ貧しい人達! 君達は長い間、すべての美や真実や正義やを、神へ、それから権威へ、それから卑しい帝王へ、あづけてきた。空しくそれを習慣のやうに行ってきた。今こそそれを君たちの間に取かへすのだ。破れ切った軒端や赤茶けた畳の上に。それから諍ひの好きだった君達の同胞達のうへに。僕は血の通った人達だけを好きなのだ。
帝王はいまも神権につながれてゐる。あの荘厳で無稽な戴冠式や即位式。
それから支配者の位置につくものが僧侶の前で宣誓する風習。神権と王権。
立法と行政とが、神と帝王から離れて民衆の手に移されるのは何日のことか。
あやまってはならない。民衆のために! それは疑ひもなく、生きた具象的な個々の人々のためにといふことだ。祖国のために! こんな空虚な言葉が存在するだらうか。僕らには祖国などといふものはないのだ。やはり個々の人々があるだけだ。支配者はいつもそのやうに人々を架空なもので釣り上げる。[下線部原文傍点](吉本隆明/エリアンの感想の断片【第 I 部 戦後篇3箴言 I 】)
自然態としての上昇志向が裏返された自然過程のような〈動的平衡〉である《虚無》を計算し尽くし、人為的自然の風に逆らうように《この世で為すに値しない何物もないように、為すに値する何物もない。それで僕は何かを為せばよいのだと考へる》[吉本隆明/エリアンの感想の断片【第 I 部 戦後篇3箴言 I 】]不可避性を契機とした縦書き詩作行為の必然性へ。〈われわれ〉の内的規定たる時間性と外的規定たる空間性とが構造化された〈批評〉の顕現!
生存するとは、精神によって判断することを意味する。判断に行為を従はせること。一般にはこれ以外に生存の図式は見つからない。判断とは精神にとって直覚的操作以外のものを指さない。少なくとも生存の原理としての判断なるものは、無数に並べられた諸条件からの抽出作用としての判断はそれ以後の行為を絶対に喚起することは出来ない。換言すれば直覚的操作以外の判断作用は決して行為を触発することはないのである。併るに精神はそれ自体で可能性を持ってゐる。恐らく自己運動としての抽象作用を精神は無限に積み重ねることが可能である。
一般に自意識の錯乱なるものは、直覚的判断に導かれるべき生存の行為と、抽象的判断により自己運動するべき精神の操作との矛盾としてのみ理解される。
唯物論とは、決して精神の操作を無視乃至は除外するものではない。それは実在と交換する精神の直覚作用のみを固持することで、かの精神の自己運動としての抽象作用を無視するだけである。あらゆる唯物論者が渋滞を知らない精神、別言すれば意識における苦悩の担ひ手でないといふ、よく経験される事実は、このことによってのみ説明される。[下線部引用者傍点](吉本隆明/エリアンの感想の断片【第 I 部 戦後篇3箴言 I 】)
「詩人のノート」[『現代詩』1960年2月号]で吉本さんが、「このノートは、『固有時との対話』という詩集をまとめあげる前後に書かれ」、「こういうノートを一年か半年か、続けているうちに何となしに又詩が書けるようになった」と記されたいきさつの背後からせりあがってくるのは、無地の白紙にまるで古民家の細かい木虫籠[きむすこ]みたいに罫線を引いて〈白日〉を立ち上がらせるような、根源的な書き手[川上の説明を敷衍すると「紙質は40キン位、たんに白い紙といってよいほどの薄いクリーム色の西洋紙」に、天地左右に三、四センチほどの余白を取り、二、三ミリ幅の罫線をおおよその見当で引いて、それを当り線として詩を書く、以後の著者の詩を書く用紙と書き方が初めてあらわれた詩稿群/間宮幹彦@晶文社版『吉本隆明全集』第2巻、解題]となって日々の詩作街道を突き進む姿だ。
そうしてぼくは啖はれるよりほかない道を、何故に歩まうとするか
たくさんの憤死をぞろぞろ引具してくる普遍[アルゲマイネ=原文ルビ]、ぼくは激突する
いづれ死ぬのはぼくなんだが、ぼくは思ひおこすのだ かかる道化の一芝居をうって、たくさ
んの観客をせしめようと、たくらむことのたのしさを。
ああぼくにとっておきの帽子や上衣を投げてくれる奴はゐないか
すでに燃えつくしたぼくの精神にかはって、ぼくはひとすぢの残照だ
少女も年増女も売女も乾ききったぼくの肉体に、いや肉体の光輝に銭をなげる奴はいないか(吉本隆明/残照[後半]@【残照篇】/晶文社版『吉本隆明全集』第2巻)
(2022年8月28日記/30日web公開)
続・本の一言:街道と民家(10)三反百姓暮らし
「日本の社会経済の問題は集約すれば土地問題と住宅問題に帰せられる。
これは都市部では何とかして大衆の住宅が安く入手できるようにすべきだ
という課題に、農村部では、いまより縮小された農家で、何とかして農業
自由化に伴う生産性の高い農業を営み、質の良い農業生産物をつくり出す
課題としてあらわれる。米国案は確実にこの課題の集約点を包みこんでい
る。わたしは敗戦後すぐ昭和二十一年(一九四六)にアメリカ占領軍の主
権で行われた第一次、第二次の農業改革案をすぐにおもいおこした。地主
の土地を有価で没収し、小作農家を自立させるという明治の地租改正以後
はじめての画期的な農業革命を、アメリカ占領政策はやってのけた。今度
の構造協議米国案のようなものは、本来ならば社共、新左翼が中心で提起
されやってのけるべきはずのものだ。」
(吉本隆明/わたしにとって中東問題とは)
さて、敗戦直後にGHQが主導したとされる1946[昭和21]年10月21日の農地調整法改正公布[第2次農地改革]によって小作地の80%が解放され、自作農が過半を占めるようなった戦後社会で、「国家」とか「天皇」と「個」の関係はどのように変わったのだろうか。
たまたま図書館で手にしたR.P.ドーア著『日本の農地改革』[昭和40年1月岩波書店刊�]の巻末付録に調査対象とした六つの村[長野県小県郡塩田町、山梨県北巨摩郡白州町、山形県東田川郡三川村・平田村、高知県幡多郡月灘村、広島県豊田郡大崎町、神奈川県川崎市堰]から一つないし二つの部落を選んだ地域の農家の男の世帯主とその長男(20歳以上)628人の聞き取り調査査結果が載っていた。
・いろいろな点から見て、戦後の農地改革は行きすぎであった。(55%)
・農地改革は、是非やらねばならぬ大事業であった。(82%)
・概して農地改革は、地主に貸付地の保有を認め、山林所有に触れていないから、真の農地改革ではなかった。(54%)
・農地改革で土地を取得した農民の多くは、その能力がなく、漸次その土地を手放しつつある。ーー農地改革は事実上失敗であった。(45%)
・農地改革は、自分の足で立つことのできる自作農を作ったという意味で成功であった。(84%)
・農業は国のもとになる職業なのだから、国家のために自分の本分をまもって、利益などあまり考えてはいけない。(32%)
・天皇は国の親のようなものであり、親と同じ気持ちで尊敬しなければならない。(87%)
・個人なくして国家なしという人がいますが、国家なくして個人なしというほうが正しい。(72%)
・学校では、子供の愛国心をもっと高めるように努力すべきだ。(86%)
・日本には、万世一系の天皇があるのだから、やはり神の国だ。(55%)
・アジアの指導者となるのは、インドや中国でなく日本である。(81%)
・この前の戦争は、やり方はまずかったけれども、その根本的なねらいは間違っていなかった。(51%)
・憲法を変え再軍備するのはよくない。(53%)
調査対象となった農家の世帯主およびその長男の8割強が戦後の「農地改革」を肯定している一方で、5割を上下する「行きすぎであった」あるいは「事実上失敗であった」とする回答もあった。
同じく外圧による明治維新改革後の「廃藩置県」を経た1873[明治6]年の「地租改正」の場合は、その三年後の12月9日に「三重県で地租改正反対の農民暴動、愛知・岐阜・堺県下に拡大。12・23鎮定、5万7千人処罰。」[『決定版20世紀年表』小学舘2001年刊]されたという。富山県下にまで波及することはなかったようだが、17年後の1900[明治23]年「1・18富山市で300人が市役所に押しかけ米価高騰の救済を強訴。以後各地で米騒動頻発。」[同『前掲書』]とある。埴生村で尋常小学校[4年制]を終えたばかりの祖父に当時の記憶があったかどうか、そもそも何歳で大阪での奉公に出かけ、何処で何をどのようにして料理の腕前を上げ、年期も明け、故郷の埴生に出戻って村の仕出し料理を手伝ったりしながら借地で田畑を耕すとともに籾摺り・精米を生業に家を構えるまでに至ったかなど聞いた覚えもなく、1918[大正7]年7〜8月にかけての魚津や水橋での米騒動が「越中の女一揆」として全国に報じられた事件についても聞いたことはなかった。
山際の埴生よりもいっそう山がちだった祖父の実家あたりで村民は様々な副業で生きていて、飯米は買って補ったりしていたのではないだろうか。
租税が米衲であろう金納に変わろうが、生活の苦しさはさして変わらなかったのじゃないか。奉公から出戻った祖父が村での自給自足を足場に籾摺り精米業を始めた遠因の一つを幼児期の生活体験に求めたいような気がする。宅地と作業場を合わせて二百坪あまりの土地と山際の三反ばかりの田んぼと畑から遠かった僅かな山林。家の西側を杉小柴で囲い、榛の木や桐や栗の木が西陽を遮り、背戸の庭の端っこの畑けの傍では無花果や柿や石榴が朝陽を和らげていた。
1912[明治45・大正元]年に埴生の家で生まれた父はどのような幼・青少年期を過ごし、いかなる経緯で外地の朝鮮植民地勤務を選んだのだろうか。1919[大正8]年2月に植民地朝鮮の京城で起こった独立示威運動[3・1運動:万歳事件]が朝鮮全域に拡大、1923[大正12]年9月1日の関東大震災の際に朝鮮人暴動の流言が広まって朝鮮・中国人の殺害、などのニュースも埴生村民の耳目に届いていたことだろう。
おそらく在阪丁稚奉公の年期が明けたであろう1900[明治33]年前後に実家に程近い埴生村に出戻って〈家〉を構えるまでに、虚弱な孫の目を見張らせるような祖父の生活力が当時では欠かせず、借地とはいえ住居と別に作業場も構えながら自家消費規模の田畑も耕す暮らしも1922[大正11]年頃の芸者を身請けした妻との死別で様変わりしたことであろう。11歳で実母を失った父のその後の就職先が内地ではなく朝鮮総督府勤務の警官になったのは、植民地勤めの方が給料や手当等が魅力だったからだ。京城暮らしの折に母は、父子家庭の貧乏暮らしゆえの職業選択だったと父が語るのを聞いたことがあったという。
1945[昭和20]年8月15日の祖父や母は、天皇による「玉音放送」は何を言っているのかよく聞き取れなかったが、「戦争に負けた」ことだけはよくわかったらしい。その数ヶ月後[12月9日]には農地改革の発端となったGHQによる「農地改革に関する覚書」が発表され、翌年の10月21日に農地調整法改正交付された。
父と母が植民地・京城の朝鮮総督府の官舎で結婚生活を始める前年、1939[昭和14]年の国家総動員法に基づく価格等統制令交付で祖父が営んでいた精米・米屋の営みはどのように変わったのだろうか。家屋の間取りの割に玄関が広くて土間と小さな陳列棚を置いた板の間に接して記帳場があり、どう見ても最初から住宅は小商いを営む家の造りだった。開店休業状態の棚に四合瓶入りの入浴剤が並んでいた記憶がある。街道を挟んで別棟になっていた精米作業場で手伝わされることも少なくなり、我が家の精米業は稼働の機会を失っていった。
戦前の祖父が商売のかたわら、どんな風に「飲む・打つ・買う」をくぐり抜けてきたのか詳細は分からないが、1945[昭和20]年6月に埴生で暮らす祖父のもとへ子連れで引き揚げてきた母にとって、家計そっちのけで有り金を株券に注ぎ込もうとする祖父の投資癖に困り果てたようだ。とりあえず遺族年金は生活費にまわし、5年余りの植民地支配の京城での結婚生活での蓄えそのほか、命からがら持ち帰った夫の弔慰金や退職金その他すべてを土地購入に充てたとのことだった。それも息子名義にしておけば、いくらなんでも義父は孫[名義]には手を出さないだろうと踏んでの企みだったようだ。
祖父は息子の縁談の際に分かったはずの地主と小作の家構えの違いを孫に知られたくなかったのだろうか。それにしても敗戦直後の農地改革で農地の買受け側にだったとはいえ、行政区域が違う売り渡し側だった嫁の実家に足を運ばなかったのはなぜだろうか。そんな両家が富山県内の農地改革の際にどんな思いをしたか聞き覚えがないけど、「親鸞上人」ほどではないが富山県福光町の「松村代議士」すなわち、現在の南砺市出身で第1次農地改革に農相として貢献した松村謙三(江藤淳『もう一つの戦後史』講談社1978年4月刊310頁:「農地改革の成功」対談相手の大和田啓氣の発言)には一目置いていたらしい様子は孫にも感じられた。
「かくゝ昭和二十二年七月より賣渡計画の承認を行い、昭和二十五年七月までには30,996町歩の賣渡を終了したのである。」(『復刻版 富山県農地改革史』不二出版1991年4月刊157頁)。目標とされた予定面積32,227町歩に対して40,368町歩の実績を残し、進捗率は124%と記されている。
第1回農地売買通知書の伝達式は、「昭和22年8月22日上新川郡新保村で挙行され」(同上157頁)、県農地部課長ほか新聞社その他関係者、富山軍政部ルイス農地主任官が臨席し「本日は歴史的な意義有る日である。これで世界のだれにでも、自分の所有する農地だと言明できるのである。」(同上158頁)との祝辞があった。
買受人代表から「解放された地主さんに感謝するとともに、新しい希望をもって一家そろって増産にはげみ、供出の万全を期する」(同前)との答辞があり、買受人の中の三人の夫人の一人からは「夫は出征中であるが、自力で一町歩を小作していたのである。それが自作となったのであるから、この喜びを早く夫に知らせたい‥‥‥」(同前)旨の談話があった。
我が家の場合は母がなけなしの有り金をはたいて宅地や田畑を借りる暮らしから、土地や作業場で働く場を所有する暮らしへと切り替えることで、祖父の投資癖の元手を絶って株券購入を断念させるのに都合が良かったようだ。
祖父や母から当時の我が家の田畑や宅地の購入経緯など詳しく聞いた覚えもないが、田畑や宅地の所有権を得ただだけの三反百姓が自作農として自立できるわけもなく、自営の精米業も立ち行かなくなりつつあるなかで、祖父は相変わらず新聞の株式欄を眺めるのが朝の日課のようだった。衰えた体力で「労働時間」を切り売りする「出稼ぎ」もままならず、“金で金を儲ける”方途に明け暮れるしかなかったのだろうか。
“三反百姓に何ができる”と揶揄されていたように、「家族労働を完全に農業で利用できる程度の経営」(大和田啓氣『秘史日本の農地改革』日本経済新聞社1981年5月刊25頁)という「小農」の規模からほど遠いのが我が家の現状だったということだ。春夏秋冬を食いつなぐ飯米や野菜などはなんとか自給自足できても、昭和50年代の暮らし向きを変えた“三種の神器”を迎え入れられるだけの現金収入が乏しかった。冷蔵庫や洗濯機は親戚からの払い下げを使っていたが、白黒テレビは村中に行き渡った後まで待たなければならなかった。
埴生から北西に外れた辺りの倶利伽羅トンネルを抜けて北陸線が街道に並行して東西に走っていて、石動駅を始発としていた加越能鉄道が支線を伸ばし、次の次の高岡駅から枝分かれしていた城端線の福野駅で乗り換え合流していた。東西両砺波郡を三本の路線で仕切ったような環状の内と外に民家が散らばった沿線風景が高校通学の車窓を彩っていた。
あれが「越中カイニョ式住宅」なるものであったと知ったのは、勤め始めた大学図書館の書庫で藤田元春の『日本民家史』に出会えたからだ。通学や通勤途上の車窓の眺めに呼応するような民家の記述頁を探し読みしたコピーもいつの間にか散逸してしまった。古本で買った手元の『増補版』[刀江書院、昭和17年刊]は囲炉裏の煙で煤けたように赤茶けて装丁も緩み、今にも崩れ落ちそうな古民家の佇まいを今に伝えているようだ。
敗戦直前に引き揚げてから25年間住み慣れた埴生の民家は神社仏閣を控えた街道沿いに並んだ入母屋の草葺か、切妻の瓦葺きがほとんどで板屋は少なく、散居村とは異なる様相を呈していた。幼少の頃に見飽きなかった近所の村人が草葺の傾斜に群がって行う屋根の葺き替え作業姿が鮮やかに残っている。里田の民家と山田の民家の規模はそれぞれ違っても木虫籠や格子戸などは共通していた。浅く緩い里田と冷たく深い山田の感触の違いも忘れられない。祖父にひ弱な手を引かれて街道をたどった古民家の庭先で競り売りの声が響いていた“市”が古物や骨董品が引き継がれる網の目のように回想される。
三歳で引き揚げてきたときは掴まり立ちもおぼつかなかったから、それまで住んでいた植民地京城での足が地に着いた身体感触はまったくたどりようもない。二歳ばかり上の姉だと朝鮮総督府の官舎のぼんやりとした佇まいとか、父の胡座や無精髭の感触が忘れられないと言う。母が持ち帰った数少ない父の遺品、握り艶の残る胡桃の実や三枚重ねの小さなルーペを握ったり、日本刀を作り直した式刀を振ったり、遺影に写っている制帽を実際に被ったら窮屈だったりしてなんとなく京城暮らしの父の〈身体〉を感じたような気がするだけだ。その一つ一つが自分の所有物というより母を経由した預かり物としか思えない。埴生から引越しに同意してくれた97歳だった祖父が選んでくれた庭木の一部を高屋敷の自宅前庭に移植した祖父が育てた庭木や数点の骨董品なども同じだ。
田舎での夏のお盆前の大掃除の際など、幼い日々に行き来した街道から通し柱と棟木と梁だけが透けて見えた民家の佇まい一軒一軒が、それぞれの物語を隠し持っているように思えた。小矢部市埴生の地を離れて14年後の1986[昭和61]年、市内で東に開く小さな谷間の試掘調査により、「今から約12,000年前の縄文時代創期から約2,300年前の縄文時代晩期まで、縄文時代全期間にわたる遺跡」[参照:邪馬台国大研究・ホームページ/ INOUES.NET/ 桜町遺跡]が発見されたニュースを知り、その後もネットで関連情報を覗いたりするようになった。
「北陸の縄文と観光 環状木柱列を尋ねて06 2014.05.22(木)」によれば、「桜町遺跡」の特徴として「谷川跡から全国初の加工材や道具。動植物の遺体が発見された。特に、建築部材とみられる加工材出土は全国初。」であり、時代的には「縄文早期〜江戸 特に縄文中期末〜後期初頭(4000年前) と 後期末〜晩期中葉(2800年前)」とされ、見所として「水場遺構から出土の木製品や木柱根」があげられていた。
これらによって当地一帯の民家と共同生活環境の筋道、初源へのルーツをたどれそうな可能性が無きにしも非ずのようだが、そこで暮らしてきた村民が営み築きあげてきた家族や村落共同体の幻想の関係性についてまでは踏み込むことができないであろう。
田畑をを耕し種を蒔いて世話に明け暮れ、その収穫物を口にして家族を養う村の暮らし。五感を超越するもの、それこそ自己および他者ともに渾然とする領域の感覚、かかる領域では自己と他者が観念[共同幻想]に過ぎなくなり、普段使いしている感覚という言葉とは区別されなければならない。究極のところ国家の状態ははどうあれ生き死には個人的なもの、敗戦直前の植民地[京城]で勤務中に感染した伝染病で殉職した父や、明治期の「スペイン風邪」[1918〜1920足掛け3年で3度も流行し、世界人口の1/3の4,800万人以上死亡]を生き延びた祖父は、「コロナ渦」[「2019年から世界が謎のウィルスに襲われ、これまで世界で五億人以上が感染し六〇〇万人以上の人がなくなり、すべての人がマスクをしている風景など誰が想像できただろう。」(A.クラーク『現れる存在』ハヤカワ文庫版2022年7月刊、監訳者あとがき]の泉下で、「罹患するときは罹患する、罹患しないときは罹患しない、罹患したら罹患したとき」と呟きはしないか。(2022年12月23日記/26日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(11)ジャズと賢治と
「人に学ぶことはすべてセッションだ、といってもいいが、自然に学ぶ
のだってセッションである。そして自然よりもさらに自由な、新しい
自分たちの「自然」をつくるのがセッションの実践というものなので
あるはずだから。
賢治があらゆるものに常に耳を澄ませて、そのひとつひとつの存在
の音を聴き、そこへ丁寧に接していく、そのやさしい接し方こそが、
賢治流の日々のセッションなのである。」
(奥成 達『宮澤賢治、ジャズに出会う』
十代の終わり頃だが、低い山歩きから高い山登りにのめり込んだように、音楽でもラジオによる手当たり次第の聴き漁りがいつの間にかFEN[Far East Network=米軍極東放送]やNHKの音楽番組に的が絞られ、なんとなくジャズ番組を追っかけてエアチェックしてまで楽しむようになっていった。音源としてのLPレコードは高嶺の花だったが、音響装置の良し悪しより好きな音源を手元に置いていつでも聴けるような民家暮らしが夢になったようだ。
埴生の宅地だけじゃなく家並みの背後に広がる田んぼや山間の田畑や山林の所有権のことなど、1972[昭和47]年2月の札幌オリンピックの頃まで貧乏暮らしの床下にしまい込まれたままだった。老朽化した家屋の建て直しあるいは場所を変えて新居を持てるかが、自らの「結婚話」に絡めて切実になってきたからだ。
老朽化した家屋の修繕など一時的な費用の捻出は持ち山の杉の木を売ってなんとか工面できたが、家を建て替えたりするだけの材木を切り出せるような植林の規模にはほど遠かった。管球アンプやスピーカーを自作してまで音楽[ジャズ]にのめり込んでいる様子を見かねた母は杉材の売り上げの一部を、祖父に内緒でオーディオ資金の一部に回してくれたことがあった。母はまさか知らなかっただろうが、引き揚げ時に買い与えた一冊で息子は「ジャズ」という言葉に出会っていたのだ。『宮澤賢治名作選(上)』冒頭の「セロ弾きのゴーシュ」の22頁をめくって「何だ、愉快な馬車屋ってジャズか」のフレーズが目に響いたことがあったのだ。
仕事から帰ったとある夕方、玄関脇の板の間と記帳場を合わせて改装した鰻の寝床のような個室から隣接する茶の間にはみ出したフロア型スピーカーでジャズを鳴らしていたら、街道に面した玄関戸を開けて通勤帰りの若い男が入り込んできた。てっきりうるさいと怒鳴られると覚悟したら、いつも通りすがりに聴いていたものですが、ちょっと見聞させてくださいと上がり込まれたことがあった。
古くて小さな民家の造りであれば、四季おりおりに飛来する鳥や朝晩の家禽・家畜の鳴き声に、家族の諍いの気配や性の営みの律動から赤ん坊の産声まで漏れ聞こえてきたりする。村住まいの砂利を敷いた家の前の街道を往来する馬[牛]車のひずめの音が遠のいて自動車のエンジン音に入れ替わるとともに、田畑で牛馬が犁を引く作業音や足踏み脱穀機の響きが自動脱穀機で加速されたような耕運機の内燃機関の唸りなど、化石エネルギー革命のリズムが田舎の音風景を席巻していった。
おそらくジャズレコードを鳴らすたびに近所に筒抜けだったろうが、それまで苦情や迷惑な顔を見せられたことはなかった。大好きな奴がいる裏には必ず大嫌いな奴がいる。今後は自己都合だけで甘えちゃいけないと肝に命じた。祖父や実家の祖母の口真似ではないが、何事であれ良いも悪いもあざなえる縄の如しだ。いつか防音の効いたリスニング・ルームでジャズやそのライブ映像を楽しめるようになりたいとは念じつつ、とりあえずは勤務地の富山市内の裏通りで見つけたジャズ喫茶通いが積極的な暇つぶしになった。
古い手帳から抜き書きした1968年のジャズ関連メモから拾ってみると、1/19(土)ソニーロリンズ金沢公演、2/26(火)ニユーポート・ジャムセッション、6/6(木)松浦豊秋ピアノの夕べ@県民会館、8/27(火)ニユーポート・ジャムセッション、9/5(木)アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズ富山公演@市公会堂[太鼓好きだった母同伴]などの単独視聴ライブ以外に、サン・ラー『太陽中心世界』、オーネット・コールマン『タウンホール・コンサート』ほか3枚、『グリニッチ・ヴィレッジのアルバート・アイラー』に加え、ジョン・コルトレーンやチャールス・ミンガスの新譜LPや『ミントンズ・ハウスのチャーリー・クリスチャン』みたいな旧作LPを狭い自室の質素な音で聴いたりしていたせいか、やっぱりジャズは新・旧や有名・無名問わず気心通う連れとの“ライブが一番”が習い性になったようだ。鬼籍に入ってしまったジャズ・ミュージシャンの首都圏のみの来日公演など、借金してでも聴き逃さなければよかったのにと独身の頃を振り返ることもしばしばだった。
行き着けだったジャズ喫茶「ニューポート」では、国内外で活躍中のジャズバンドの新譜LPが聴けたりする時が何よりの喜びだった。出入り客のリクエストなどで聴き慣れ親しんだモダンジャズ畑では、マイルスのトランペットやコルトレーンにロリンズのサックスなどの響き以外にもいろんな楽器による当時活躍中のジャズ・ミュージシャン演奏のスタイルを聴き知って、よりいっそう好奇心が膨らみ、数少ないジャズ雑誌やラジオのジャズ番組などでモダンジャズ以前も聴き漁るようになった。勤め先の大学図書館では理学系キャンパス内の白髪のジャズ好き教授のことなどが噂さになったり、巷ではジャズやロックの区別も曖昧なまま、とにかく“不良少年・少女”が好む音楽の一言で片付けられていた。
ジャズLP以外をめったに掛けたことのなかったマスターが「こんなのがあるよ」と聴かされた一枚にはびっくりした。日を改めてレコード屋で買い求めて家でAB両面通して聴いたら、ジャズ以外で最初に打ちのめされたロック愛聴LPになった。ビートルズの『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』(SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND. 東芝/Odeon 0P-8163)をレジに持っていった時の店員の怪訝な顔が忘れられない。クラシック好きの彼女は、まさかジャズ以外のLPを僕が買うなんて信じられなかったのだろう。「淋しい女」が収録されたオーネット・コールマンの『ジャズ来るべきもの』(The Shape of Jazz to Come�. Atlantic Record, 1959)に並ぶヘビーローテションの日々がしばらく続くことになった。
誰の何をどう聴きたいかなど絞り切れない田舎出のど素人にとって、越中売薬業からドロップアウトした雇われマスターO井さんの推薦盤や、客のリクエストが少ないセシル・テイラーのピアノ演奏その他“フリージャズ”とか“ニュージャズ”と呼ばれたLPに耳を傾けるひと時も面白くなってきた頃、好きなレコード持参で下宿に遊びに来てよと、夜間短大で知り合った野Gさんに声がけしてもらったのがカウント・ベイシー[1904.8.21〜1984.4.26ジャズピアノ奏者]率いるビッグバンド・メンバーが演奏するジャッズを聴き込むきっかけになった。ベイシー・バンド・メンバーの中でもとりわけ“クール”で“グルービー”なレスター・ヤング[1909.8.27〜1959.3.15テナーサックス奏者]のプレイとビリー・ホリデイの歌唱の虜になった。ホーンとブラスの掛け合いに挟まれたソロ演奏が魅力だと言うジャズ先輩格の彼のビッグバンド演奏の好みは、疾走感豊かなベイシー楽団より色彩感溢れるデューク・エリントン楽団にあったようだ。
ジャズ喫茶やラジオなどで滅多に聞けない古い音源はLPで聴くしかないということで、なけなしの小遣いをはたいて買った2枚組LPの1枚目にに針を下ろし、母が買ってくれたJBL製LE8Tから響いてきたテディ・ウィルソン楽団の“ブルース・イン・Cシャープ・マイナー”[Recorded by Teddy Wilson and His Orchestra in 1936/5/14, at Chicago, IL. :Teddy Wilson - piano,Roy Eldridge - trumpet,Leon Chu Berry - tenor sax,Buster Bailey - clarinet,Robert Lassle - guitar,Israel Crosby - bass,Sidney Catlett - drums;Reissued in Japan as the opening number of "The Teddy Wilson"(2 LP-set) by CBS Sony in 1973.=https://www.youtube.com/watch?v=Pegt7etzSJ8 ]の演奏が我がジャズ遍歴で遅れてやってきた“最初の一撃”になった。僅か数分間のスタジオ演奏に込められた参加ミュージシャンの圧倒的な“ブルース”表現。
大和明の演奏解説には「全編にわたって流れる I. クロスビーのベースが刻む印象的なブルース・コードのリズムに乗って、 T. ウィルソン、R. エルドリッジ、B. ベイリー、C. ベイリー、再び R. エルドリッジを中心とする三者のからみと、いずれ劣らぬ心にくいこむような素晴らしいソロの連続だ。この僅か12小節のソロの中心に、心の底から全表現能力をぶっつけた、ブルージーな濃縮したアドリブが脈打つごとく展開している。最後に残されたベースの音がいつまでも胸の中でうずいているかのようである。/まさに名演中の名演と言ってよいであろう。」と記されたいた。
主に歌伴を主としていたセッションバンドが器楽演奏に徹した凄さに痺れまくった。若かりし日に自転車乗りやスキー滑走を体得した瞬間に心身の奥底から湧きあがった一回性の嬉びとも違う〈身体〉的な感動とでもいえようか。
東北の民家をとりまく自然環境と北陸のそれとの違いに気づきはじめる前に、音楽への興味をかき立てられることになった宮澤賢治の童話「セロ弾きのゴーシュ」《https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/470_15407.html》に登場す擬人化された小動物たちと「金星音楽団」の未熟な団員であるゴーシュとの掛け合いは幻想的な「イーハトーヴ」で連夜の音楽現場に立ち会うようだった。
三毛猫がリクエストした「トロイメライ」には、西洋音楽かぶれを揶揄するかのように荒々しい「印度の虎狩」を弾いて蹴散らし、外国へ音楽修行に出かける前に正確な「ドレミファ」を習いたいといって西洋音楽文化に敬意を払う郭公には生半可な自分の弾き方が間違っているように思わされたり、小太鼓係の子狸に頼まれたジャズ譜『愉快な馬車や』を弾いて二番目の糸の遅れを指摘されてもジャズ的なシンコペーションでオフビートできず、最後の晩に訪れた病気の子鼠を連れた母鼠とのやりとりによって森の中の動物たちが音楽的身体効果をゴーシュのセロ演奏を盗み聴きすることで得ていたことをやっと知る。
岩手県内の街道を外れた擬人法による四次元植民地的空間では、「兎のおばあさん」や「狸さんのお父さん」や「意地悪のみみずく」みたいにイーハトーブの中で最も気に入った音源を探り当て、それこそ自分にあった〈命を刻むリズム〉だと確信できれば〈身体バランスの崩れ〉から癒えることがあるのだ。
詩集では『春と修羅』《https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/1058_15403.html》の通奏低音のように聴こえるジャズのウォーキング・ベースみたいにリズム化した〈詩的身体〉との共鳴現象があざやかな体験だった。
わたくしといふ現象は
仮定された有機交流電燈の
ひとつの青い照明です
(あらゆる透明な幽霊の複合体)
風景やみんなといつしよに
せはしくせはしく明滅しながら
いかにもたしかにともりつづける
因果交流電燈の
ひとつの青い照明です
(ひかりはたもち その電燈は失はれ)
(宮澤賢治「序」の冒頭/『春と修羅』)
それにしても横書きにした宮沢賢治の詩はリズムが損なわれるようで性にあわないのだが、〈童話〉から〈詩作〉に変移した「スケッチャー」としての〈歩行〉によって心的リズムが現象化されたように映しだされる「わたくしといふ現象」が「仮定された有機交流電燈」で青く灯す「名辞以前の世界」(中原中也/「宮澤賢治の世界」)を観想できるならば、詩人の「不貪慾戒≠デクノボー」という「修羅」が明滅する。歩き回ることによって「心象スケッチ」された風景や事象で身体化[概念化じゃなく]された言葉に共鳴する〈ほんとう〉とは何かをどこまでも探し求める「(あらゆる透明な幽霊の複合体)」。長編詩「小岩井農場」ではスケッチの対象が眼に見える自然から眼に見えない幻視の世界へと移っていく。
わたくしはなにをびくびくしてゐるのだ
どうしてもどうしてもさびしくてたまらないときは
ひとはみんなきつと斯ういふことになる
きみたちとけふあふことができたので
わたくしはこの巨きな旅のなかの一つづりから
血みどろになつて遁げなくてもいいのです
(ひばりが居るやうな居ないやうな
腐植質から麦が生え
雨はしきりに降つてゐる)
さうです 農場のこのへんは
まつたく不思議におもはれます
どうしてかわたくしはここらを
der heilige Punkt と
呼びたいやうな気がします
この冬だつて耕耘部まで用事で来て
こゝいらの匂のいゝふぶきのなかで
なにとはなしに聖いこころもちがして
凍えさうになりながらいつまでもいつまでも
いつたり来たりしてゐました
さつきもさうです
どこの子どもらですかあの瓔珞をつけた子は
《そんなことでだまされてはいけない
ちがつた空間にはいろいろちがつたものがゐる
それにだいいちさつきからの考へやうが
まるで銅版のやうなのに気がつかないか》
(宮澤賢治「小岩井農場 パート九」より抜粋/『春と修羅』)
人間の感覚では触れられない世界が「der heilige Punkt 」[聖なる地=The holy place]ということなのだろうか。幼虫から蛹をへて蝶になるように、宗教から恋愛をへて性欲へと通底する変態リズムが宮澤賢治の生涯と作品を律する〈場〉としての自然の景物が立ち現れる異次元空間が垣間見られている。「人間の生活には、「労働」と「思索」と「性欲」の三つの要素がある」と「羅須地人協会」を訪ねた森惣一に語った[山折哲雄『デクノボーになりたい:私の宮沢賢治論』小学館、2005年、189頁]とあるが、おそらく宮沢賢治自身はその「三位一体」の有り様を江戸から明治にかけて跨ぎ越した折に取りこぼしてきた事態に敏感であったに違いない。
食糧増産のために明治政府が岩手山南麓の荒野を開拓し、機械化による効率化の実現を目指した西洋式大農場の現場へ何度か宮澤賢治も足を運んだようだが、「耕耘部」では蒸気機関の力でケーブルに繋がれた犁を引く「スチーム・ブラウ」という英国製大型農業機械などヨーロッパ式の進歩した農機具が積極的に導入されている様相だけでなく、そこで働いている農民の[おそらく小作農とは違う?]労働形態にもに注目したのだろう。
農場の不思議な「聖なる地」にたいして「聖なるこころもち」でいったりきたりしながら、さっきの仏教的な装身具を身につけたどこかの子らには、だまされがちな異空間の多種多様な存在に気づきながらも考えの過程が固着しているのに気がつかないか、と内的スケッチをほどこさずにはいられない。
もしも正しいねがひに燃えて
じぶんとひとと万象といつしよに
至上福祉にいたらうとする
それをある宗教情操とするならば
そのねがひから砕けまたは疲れ
じぶんとそれからたつたもひとつのたましひと
完全そして永久にどこまでもいつしよに行かうとする
この変態を恋愛といふ
そしてどこまでもその方向では
決して求め得られないその恋愛の本質的な部分を
むりにもごまかし求め得ようとする
この傾向を性慾といふ
すべてこれら漸移のなかのさまざまな過程に従つて
さまざまな眼に見えまた見えない生物の種類がある
この命題は可逆的にもまた正しく
わたくしにはあんまり恐ろしいことだ
けれどもいくら恐ろしいといつても
それがほんたうならしかたない
さあはつきり眼をあいてたれにも見え
明確に物理学の法則にしたがふ
これら実在の現象のなかから
あたらしくまつすぐに起て
(宮澤賢治「小岩井農場 パート九」より抜粋/『春と修羅』)
前述の宮澤賢治が言う人間生活の三要素を音楽的に翻案すれば、“ブルーズ”と“霊歌”と“ジャズ”ということになりはしないか。
作品の言葉は読むものに意味の表情をつくらせる。このばあい言葉がなにも意味していないのに、意味がひとりでにつくられているのが最上なのだ。言葉が意味を与えることと、言葉が存在の輪郭を与え、その輪郭から意味が湧きあがってくることとはちがう。前者は言葉の機能がつくりだした〈意味〉だし、後者は言葉が存在をつくりだし、その存在がうみだした〈意味〉だといえる。言葉がつくりだした機能の〈意味〉と存在の〈意味〉のあいだには、いくつもの階層があるにちがいない。
(吉本隆明「父のいない物語・妻のいる物語」/『宮沢賢治』筑摩書房、1989年、69頁)
つゝましくいとつゝましくその一一の
一二平方デシにも充たぬ
小さな紙片をへめぐって
或いはその愛欲のあまりにもやさしい模型から
胸のなかに燃え出でやうとする焔を
はるかに遠い時空のかなたに浄化して
足音軽く眉も気高く行きつくし
あるひはこれらの遠い時空の隔たりを
たゞちに紙片のなかに移って
その古い欲情の香を呼吸して
こゝろもそらに足もうつろに行き過ぎる
(宮澤賢治「浮世絵展覧会印象 一九二八、六、一五」部分)
「浮世絵展覧会」の現場を突き抜けるように透視しているのは、忘れたことさえも忘れてしまって名づけることもかなわない《過ぎ来し方の身体経験の世界》ではないのか。
かって詩人の菅谷規矩雄が『詩的リズム』(大和書房、1975年、215〜216頁)で、宮澤賢治の詩の原理となるリズムの根源をさぐりだし、「わたしたちは《春と修羅》第一集にいたるまでの宮沢賢治の、詩的リズムの推移を」、イ.五七五七七(短歌)→ロ.7・3・4(短歌的終止)→ハ.3・4・4・3(俗謡系)→ニ.3・3・7(わらべうた系)→ホ.4・4・7(仏教歌系)→ヘ.十五音=律として、その推移をえがいてみせてくれた。
その『第一集』中の長詩「小岩井農場」では、推移した「十五音=律」のリズム構成を外す破調をシンコペーションにしてよりいっそう〈心象スケッチ〉を深くひろげてみせている。「宮沢賢治における十五音=律は、四拍子四小節から二拍子八小節へとテンポを圧縮してゆくダイナミックな強弱リズムの原型をぬきにしてはありえないものであるーーその意識ののするどさが、かれを他の近代詩人からきわだたせる。《原体剣舞連》のdah-dah-dah-dah-dah-sko -dah-dahにひとつの証左をみてもいいーーとはいえこのリズムを、詩の批評のもんだいとして理論的に説ききることはたやすくないのである。」[同前掲書、216〜217頁]
かって吉本さんは「ニ」のリズムについて、政治や社会的な主題を失った大正期大衆ナショナリズムの特徴として指摘されていた。
あゝ浮世絵の命は刹那
あらゆる刹那のなやみも夢も
にかはと楮のごとく敏感なシートの上に
化石のやうに固定され
しかもそれらは空気に息づき
光に色のすがたをも変へ
湿気にその身を増減して
幾片幾片
不敵な微笑をつゞけてゐる
(宮澤賢治「浮世絵展覧会印象 一九二八、六、一五」部分)
「昔は時の方が特殊で空間や場、刹那が普通だった。生活、身体観も然り。/夕煙/今日はけふのみ/たてておけ/明日の薪は/あす採りてこむ/日本人はなぜ古文が読めなくなっ‥‥‥」(光岡英稔@ツイッター)たということだ。
モースは北海道の小樽で、おそるべき体力を持った老婆に出会った。彼女は天秤棒をかついで帆立貝を行商しているのだったが、その荷はモースと彼の日本人の連れが持ち上げようとしてもどうしても上らぬほど重かった。彼らが断念すると老婆は静かに天秤棒をかつぎあげ、丁寧にサヨナラをいうとともに、「絶対的な速度」で往来を立ち去っていったのである。「この小さなしなびた婆さんは、すでにこの荷物を一マイルかあるいはそれ以上運搬したにもかかわらず、続けさまに商品の名を呼ぶ程、息がづづくのであった」。むろんこの老婆は当時の小樽の「魚売り女」の中で、特別の力持ちだったわけではなかろう。
(渡辺京二「労働と身体」/『逝きし世の面影』平凡社、2005年、146頁)
詩集『春と修羅』や童話『風の又三郎』、『注文の多い料理店』、『銀河鉄道の夜』など宮澤賢治作品のあちこちからノイズのように漏れ聞こえる風の音。言葉以前の言葉みたいに、1924[大正13]年8月10、11日の自作劇四本立て公演のなかの「ファンタジー:ポランの廣場」で山猫博士が「おいおい、そいつでなしにキャッツホヰスカアといふやつをやってもらいたいな。」で始まるオーケストラが演奏する舞台は1920年代の6月30日のイーハトヴォ地方が想定されているが、幕開けのト書きで指定されるレコード「♪ Hacienda, the society Tango」同様、引用音源は当時の「シカゴジャズ」ということだ[参考:賢治の「ジャズ」の情報源はシカゴ?(destupargo’s blog) https://destupargo.hatenablog.com/entry/2022/08/27/093912]。何事も詮索好きだったといわれる宮澤賢治は、そもそも「ジャズ」が発祥の地とされるニューオーリンズのストーリーヴィル地区の娼館での《性的結合》に由来することを知っていたのだろうか。
当時の日本人にとって、男女とは相互に惚れ合うものだった。つまり両者の関係を規定するのは性的結合だった。むろん性的結合は相互の情愛を生み、家庭的義務を生じさせた。夫婦関係は家族的結合の基軸であるから、「言葉の高貴な意味における愛」などという、いつまで永続可能かわからないような概念にその保証を求めるわけにはいかなかった。さまざまな葛藤にみちた夫婦の絆を保つのは、人情にもとづく妥協と許しあいだったが、その情愛を保証するものこそ性生活だったのである。当時の日本人は異性間の関係をそうわきまえる点で、徹底した下世話なリアリストだった。だから結婚も性も、彼らにとっては自然な人情にもとづく気楽で気易いものとなった。性は男女の和合を保証するよきもの、ほがらかのものであり、従って恥じるに及ばないものだった。
(渡辺京二「身体と性」/『逝きし世の面影』平凡社、2005年、321〜322頁)
1926[大正15]年の作品「ジャズ 夏のはなしです」[参考:雑誌発表形《https://ihatov.cc/haru_2/183_1.htm》]の別テイクみたいな未発表作品「岩手軽便鉄道 七月(ジャズ)」に《騎士の誓約強いベースで鳴りひびかうが》とあるが、当時の宮澤賢治はいったいどのような「シカゴジャズ」を聴いていたのだろうか。リスムセクションの一角を担っていたのは息を吹き込む「チューバ」か指で弾く「ダブルベース」いずれだったのだろうか。また同時期当地ではやっていた「シカゴ・ブルース」は宮澤賢治の耳に届いていたのかいなかったのか。レコードだけでなく浮世絵の春画などいずれも収集するだけでなく、コンサートを開いたり、勤務先の職員室で同僚に見せるなど身体的に開かれた関心の構造の先には何があったのだろう。(2023年2月28日記/3月12日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(12)鉄道とブルーズ
「私の考えは少し違う。私たちが音楽から感得するその呼吸と脈拍と起伏は、
まさに自分自身の呼吸と脈拍と起伏そのものではないか。つまりリズムであ
る。生命はリズムの循環に支配され、かつ駆動されている。肺の起伏、心臓
の鼓動、筋肉の収縮のインパルス、セックスの律動、これらはすべて生命を
刻むリズムであると同時に、私たちに自分のいのちの実在性を確認させる音
でもある。つまり、音楽とは、私たちが外部に作り出した生命のリズムのレ
ファレンスなのだ。文字通り、音楽とは生命のメトロノームなのである。そ
のことについてワトソンと話してみたかった。」(福岡伸一『新版 動的平衡
3:チャンスは準備された心にのみ降り立つ』小学館新書、150頁)
台湾や朝鮮半島の支配を強化する一方で日本のシベリア出兵など植民地主義の時代に、アメリカ南部で西洋植民地主義と黒人奴隷制が結びついたクレオール文化を源とするディキシーランドジャズ[宮澤賢治がシカゴ・ブルーズを聴いていたかどうかは不明]が北上してシカゴで開花した響きが、宮沢賢治の「イーハトーヴ」にまでとどいていたのだ。
宮澤賢治が短編童話「ポラーノの広場」をもとに、1924[大正13]年に自身で戯曲化した「ポランの広場」の幕開けには、当時米シカゴで人気のダンスオーケストラを率いたポール・ピースというジャズマンの曲を流すよう指定がある。
また、戯曲中に登場する山猫博士が「キャッツホヰスカア(猫のひげ)」という曲をリクエストする場面も出てくる。ディキシーランドジャズ風で、やはりシカゴのバンドが演奏している。
(佐々木孝夫「宮沢賢治の愛聴盤を解明◇250枚計113曲を収集・復刻、ジャズ好きの顔も◇/『日本経済新聞縮刷版2022-9』2022年(令和4年)9月14日(木)文化40)
夜間短大の学生だけでなく、暇を見つけては入り浸っていた地下のジャズ喫茶の出入り客の中には数少ない学生活動家[崩れ]や吉本隆明『共同幻想論』の読者も紛れ込んでいたり、交友が生まれた中には街頭行動だけでなく、同人雑誌仲間やスキー仲間に発展した僅かな人たちもいた。年金生活者になってから読んだ翻訳ジャズ本のちょっとした言葉ーー「自分の現実を忘れる」ことと「自分の現実をとりもどす」ことへの要求には娯楽音楽が送り返してくるものを受け入れること、受けつけないことの両面への要求でもある。ーーが滅多に振り返ることもない当時のジャズ喫茶の雰囲気を思いおこさせた。
1960年代後半の来日ジャズミュージシャンの北陸公演だけだなく、閉店後のジャズ喫茶での地元ミュージシャンによるジャムセッションにも足を運んだが、ラジオで流れてくるロックミュージシャンなども含め、有名無名を問わず大衆的な人気に程遠いジャンルの演奏家達が将来的にどうやって食っていくのかなど、世間離れしたような若い生き様が気になったりした。国内のあちこちを流し歩いてきて、たまたま「ニューポート」に居ついたというウェイトレスと仲良くなり、彼女が読みたい本が勤務先の図書館にあって又貸ししたりしたこともあった。
読み終えた本をマスターに預けて、彼女は“さすらい”街道伝いにどこかへ去ってしまい、かって列車と街道伝いに民家に売薬を配って歩いたことのあるマスターは“ジャズ”配置業に乗り換えたみたいに隣県の香林坊でジャズ喫茶をやると言って去って行った。
当時のジャズ喫茶で掛かるLPは、地元だけじゃなく講習会や出張などで探し訪れた他所の場合もほとんどだったが、名演/名曲が収録されがちだったA面が定番だった。ジャズ喫茶でよくリクエストして聴いていたエリック・ドルフィー[bcl,as,fl奏者、1928.06.20〜1964.06.29]が『ラスト・デイト:ラスト・レーコディング』(マーキュリー/日本ビクター SMX-7009)のB面最後で「When you hear music ,after it's over, it's gone in the air. You can never capture it again[音楽は終わると空中に消えてしまう。もう一度とり戻すことはできない。前掲レコード解説:油井正一]」と、自身の吹くバスクラリネットやアルト・サックスなどを自在な絵筆のように空に描き終えたドルフィーの言葉が、それまでジャズ的季節を潜っていた自らの〈身体〉を我に返らせるように聴こえた。
岩手軽便鉄道 七月(ジャズ)
一九二五・七・一九、
ぎざぎざの斑糲岩の岨づたひ
膠質のつめたい波をながす
北上第七支流の岸を
せはしく顫へたびたびひどくはねあがり
まっしぐらに西の野原に奔けおりる
岩手軽便鉄道の
今日の終りの列車である
ことさらにまぶしさうな眼つきをして
夏らしいラヴスィンをつくらうが
うつうつとしてイリドスミンの鉱床などを考へようが
木影もすべり
種山あたり雷の微塵をかがやかし
列車はごうごう走ってゆく
おほまつよひぐさの群落や
イリスの青い火のなかを
狂気のやうに踊りながら
第三紀末の紅い巨礫層の截り割りでも
ディアラヂットの崖みちでも
一つや二つ岩が線路にこぼれてようと
積雲が灼けようと崩れようと
こちらは全線の終列車
シグナルもタブレットもあったもんでなく
とび乗りのできないやつは乗せないし
とび降りぐらゐやれないものは
もうどこまででも連れて行って
北極あたりの大避暑市でおろしたり
銀河の発電所や西のちぢれた鉛の雲の鉱山あたり
ふしぎな仕事に案内したり
谷間の風も白い火花もごっちゃごちゃ
接吻(キス)をしようと詐欺をやらうと
ごとごとぶるぶるゆれて顫へる窓の玻璃(ガラス)
二町五町の山ばたも
壊れかかった香魚(あゆ)やなも
どんどんうしろへ飛ばしてしまって
ただ一さんに野原をさしてかけおりる
本社の西行各列車は
運行敢て軌によらざれば
振動けだし常ならず
されどまたよく鬱血をもみさげ
……Prrrrr Pirr!……
心肝をもみほごすが故に
のぼせ性こり性の人に効あり
さうだやっぱりイリドスミンや白金鉱区(やま)の目論見は
鉱染よりは砂鉱の方でたてるのだった
それとももいちど阿原峠や江刺堺を洗ってみるか
いいやあっちは到底おれの根気の外だと考へようが
恋はやさし野べの花よ
一生わたくしかはりませんと
騎士の誓約強いベースで鳴りひびかうが
そいつもこいつもみんな地塊の夏の泡
いるかのやうに踊りながらはねあがりながら
もう積雲の焦げたトンネルも通り抜け
緑青を吐く松の林も
続々うしろへたたんでしまって
なほいっしんに野原をさしてかけおりる
わが親愛なる布佐機関手が運転する
岩手軽便鉄道の
最後の下り列車である
エリック・ドルフィーのアドリブ演奏後[前掲レコード収録]の「言葉」に共鳴するかのような宮澤賢治の〈鉄道ジャズ〉詩の別バージョンだが、1926[大正15]年8月の『銅鑼』7号に発表された「「ジャズ」夏の話です」では《尊敬すべきわが熊谷機関手の運転する/銀河軽便鉄道の最終の下り列車である》となっていて、1925[大正14]年7月19日付の未発表詩稿「岩手軽便鉄道 七月(ジャズ)の《わが親愛なる布佐機関手が運転する/岩手軽便鉄道の/最後の下り列車である》と異なっているから、それぞれの鉄道ジャズ軌道は重なり合いながらも機関手がまるで《演奏者》のように違っている。いずれも〈身体を〉癒すように響いてくる〈鉄道ジャズ〉詩だが、宇宙とは違う地上の軌道では《騎士の誓約強いベース》がーーこれまで聴いたことのあるシカゴ・ジャズ・ライブCDに例えるなら「Hines/Spanier All Stars “Chicago Dates” sToryville STCD 6037」で聴けるPops Foster(string bass)の演奏のようにーーブンブン駈けぬけるようにリズムを刻んでいるようだ。
シグナルもタブレツトもあつたもんでなく
とび乗りのできないやつは乗せないし
とび降りなんぞやれないやつは
もうどこまででも載せて行つて
北極あたりで売りとばしたり
銀河の発電所や西のちぢれた鉛の雲の鉱山あたり
監獄部屋へ押し込んだり
葛のにほひも石炭からもごつちやごちや
接吻(キス)をしやうが詐欺をやらうが
繭のはなしも鹿爪らしい見識も
どんどんうしろへ飛ばしてしまつて
おほよそ世間の無常はかくのごとくに迅速である模型を示し
梨をたべてもすこしもうまいことはない
何せ匂ひがみんなうしろに残るのだ
この汽車は
動揺性にして運動つねならず
されどよく鬱血をもみさげ
・・・・Prrrrrr Pir・・・・・・・・
筋をもみほごすが故に
のぼせ性こり性の人に効あり
(宮澤賢治/「「ジヤズ」夏のはなしです」/一九二六・八月『銅鑼』七号掲載の半ば20行)
残念ながらPC画面の横書きの行間からは響いてこないが、縦書き表示して読み流したりすると、なんだかCメロディサックス奏者フランキー・トランバウアー[1901〜1956]楽団の演奏[『Bix Beiderbeck:Real Jazz Me Blues SME Records SRCS9607~8』に収録]をバックにしたみたいに宮澤賢治のアドリブ・フレーズが心地よく響く。もっとも1920〜30年代当時のSP盤には、宮澤賢治の〈鉄道ジャズ〉詩の軌道を同じくする「銀河鉄道」および「岩手軽便鉄道」両バージョンともアドリブ・ソロは収まりきらなくとも、自然の森羅万象的リズムと天地異変的リズムが輻輳るすスウィング軌道を踊るように疾走する最終便として行き着く先はどこを目指しているのだろう?
世界はイマージュ〈幻想〉として生成し、人間はその「幻想」を食べて生きる動物となる。生物としての人間は「食物(物質)を食べるが、心的世界(意識界)としての人間は「幻想」を食べ、「幻想」そのものを生きるのである。やがて、そこから抽出されたエッセンスが外化されて「物語」となる。この高次化された幻想は、現在ではありとあらゆる場面において発生し、社会化された現代人の欲望と行動の原動力となり続けている。
(牧野直哉『リマリックのブラッド・メルドー:〈ポスト・ジャズからの視点〉I 』アルテスパブリッシング、2017年刊、25頁)
高みを目指す「銀河鉄道」の幻想的視線の眼下には台湾・朝鮮半島から満州、シベリアへと拡大しつつある大日本帝國の植民地支配の触手の影が伸びつつあり、「岩手軽便鉄道」の幻聴的視線がクラシック音楽的な《小岩井農場》の残響とは異なる「ゴーシュ」の民家ならぬ壊れかかった水車小屋から漏れる「セロ」の音を聴いたり、先住山人と植民平地人がやりとりする「狼森と笊森、盗森」を抜け、西洋かぶれした仮初め狩猟青年紳士が先住動物に喰われかかる「注文の多い料理店」で地元猟師にたすけられるなど、植民地的擬人法の逸話豊かなイーハトーブの裏側で不景気さなかの都市部で胎動しつつあるシカゴ・ジャズ[&ブルーズ]の響きにも触れていた。作者のもじりみたいな「ゴーシュ」がセロの練習中に真夜中の水車小屋の扉を叩かれ「ホーシュ君か。」と声にした相手とはいったいどんな〈街道〉からやって来たのだろう?
わたしは〈ホーシュ〉という名前の響きに注意したい。〈ゴーシュ〉と〈ホーシュ〉ーー一方が他方のパラリゼーションとみなしうるほど類似したこの一対の名称から、わたしは殆ど反射的に作品「双子の星」のチュンセとポーセや「シグナルとシグナレス」を連想するのだが、これらの作品におけると同じように、〈ゴーシュ〉と〈ホーシュ〉という一対になるにふさわしい名前をもった二人はかならず親密な〈二人の世界〉を形成するにちがいない。二人の親密さは、真夜中のノックをきいてゴーシュがとっさに〈ホーシュ君〉だと判断したことに象徴されているし、なによりもこの二人だけが物語の中で固有名でよばれるものの〈閉ざされた集合〉を形成するからである。
(原口哲也「賢治童話への一視覚ーー「セロ弾きのゴーシュ」の分析(二)」/『試行』No.63,1984年11月、30頁)
主人公の「呼び名」は、詩集『春と修羅』所収の「樺太鉄道」に「山の襞のひとつのかげは/緑青のゴーシユ四辺形/そのいみじい玲瓏のなかに」とあるように、立体化学で用いられる用語としてフランス語の「gauche?=ねじれた」という意味の語に由来しているようだ。「ホーシュ」についてはなんだか主人公「ゴーシュ」のもじりというより、作中の擬人化された小動物たちとの四つの音楽的エピソードを媒介する影のようにも見える。「一対になるにふさわしい名前をもった二人」といっても、まさか音楽的盟友だった「藤原嘉藤治」や同人誌仲間の一人「保坂嘉内」や音楽鑑賞会仲間以上の仲で別離後にシカゴに渡って旅館経営者との束の間の結婚生活中に亡くなった「大畠ヤス」のことではないだろう。「心象スケッチ」としての詩作の場合とはちがい、ひたすら『法華経』の実践者として何かをしたいという思いにかられて「童話」を書き綴った宮澤賢治のことだからプライベートなことがらはいっさい遠ざけられているといっていい。
若かった頃は「ゴーシュ」が「宮澤賢治」だとおもわされたのだが、おそらく作中に出てくる擬人化された名前のないどの小動物たちにも〈ほんとうの宮澤賢治〉が「ゴーシュ」同様に分身・投影化された音楽童話として読める。とんでもない時間・空間感覚に満ちた宮澤賢治作品中に出没する多種多様な〈作者〉の影に惑わされてはいけないのだ。読者向けというより自分向けに書き残された「雨ニモマケズ(十一月三日)」の東西南北へ行き来する横の関係に右往左往するしかない〈身体〉を揺り動かし、そして勃たせる縦の関係として音楽的律動を求めて西洋音楽やシカゴ・ジャズのSPレコードを買いあさり、チェロ演奏を学んだりしたに違いない。
ただより正確に言えば、音楽によって「血のまわりがよくなり、たいへんいい気持ちになる」ためには、響きを感じるだけでなく、響きの作り出すリズムに自然に反応することが必要でしょう。それによって「音楽的リズム」はねずみの子とゴーシュの命を支える「生理のリズム」と呼応し、その呼応のなかでねずみの子とゴーシュは「生きる時間」を共有し、生成する「音楽」と「自己」と「他者」の一体感が形成されることになります。この一体感は、狸の子との共演の場面においてすでに予感されたものでした。ただそこでは互いに楽器をとって合わせることへの意識が、つまり「自己」と「他者」の間の距離の意識が、その十分な実現を妨げたのでした。
(西崎専一『ジョバンニの耳』風媒社、2008年刊、139頁)
では、なぜ狸の子との共演がなぜうまくいかなかったのか。
「鳥まで来るなんて。何の用だ。」
ゴーシュが言ひました。
「音楽を教はりたいのです。」
かくこう鳥はすまして言ひました。
ゴーシュは笑って、
「音楽だと、おまえの歌は、かつこう かつこうといふだけちゃないか。
するとかくこうが大へんまじめに、
「ええ、それなんです。けれどもむづかしいですからねぇ。と言ひました。
「むづかしいもんか。おまへたちのはたくさん啼[な]くのがひどいだけで、なきゃうは何でもないじゃないか。」
「ところがそれがひどいんです。たとえば、かっこう とかうなくのと、かつこう とかうなくのとでは、聞いてゐてもよほどちがふでせう。」
「ちがはないね。」
「ではあなたにはわからないんです。わたしらのなかまなら、かつかう と一萬言へば一萬みなちがふんです。」
「勝手だよ。そんなにわかってゐるなら何もおれの處へ来なくてもいいではないか。」
「ところが私はドレミファを正確[せいかく]にやりたいんです。」
「ドレミファもくそもあるか。」(下線部=引用者)
(宮澤賢治「セロ弾きのゴーシュ」」/松田甚次郎編『宮澤賢治名作選上』羽田書店刊、昭和廿一年七月廿日第十二刷發行、13〜14頁)
ゴーシュにはどうしても下線を引いた「かっこう」と「かつこう」と「かつかう」の違いがわからないから、「一萬言へば一萬みなちがふんです。」が「勝手だよ。」ということになってしまう。
ちなみに『校本宮澤賢治全集第十巻』(筑摩書店、昭和四十九年刊)や『新編銀河鉄道の夜』(新潮文庫、平成元年刊)所収の「セロ弾きのゴーシュ」の前出アンダーライン箇所のひらがな表記も編者の思惑のままというか、〈オリジナル〉を典拠とした用字上の区別や統一ができない恣意的な編集状況がうかがえるが、音楽的スイング感として妥当に思える上記引用に従って話を進めることにしたい。
擬人化されたかっこうは、スタ_スタ_スタ_スタ_スタと歩いたり、スクタ_スクタ_スクタ_スクタ_スクタと歩いてみたりーー身体的な律動=リズムの区別ができるーーがゴーシュはそれがどうにもできなさそうで、かっこう と かつこう と かつかう の区別がつかない。だから翌晩にやってきた小太鼓係りの狸の子が棒切れ二本で「セロのコマの下のところを拍子をとってぽんぽん叩きはじめた」のに合わせてジャズ楽曲『愉快な馬車屋』をうまく弾きこなせないことになってしまう。
また、「ところが私はドレミファを正確[せいかく]にやりたいんです。」というかっこうとゴーシュの音楽的なやりとりがうまくいかないのだろうか。
世の中には、楽器が弾ける人と、弾けない人がいるように、楽器が弾ける人にもアドリブができる人と、できない人のふたとおりがある。アドリブとは即興演奏のことだがそれを可能にしているものが何なのかがもうひとつよくわからない。
執筆中、私は三十三歳のアラキが残したアルバム「ミッドナイト・ジャズ・セッション」を毎晩のように聴きながら眠りに就いた。郷愁あふれるアラキのメロディは一音一音、譜面に起こせるほど確実に私の耳に届いている。なのに、コード(和音)としては響いてこない。学生時代の苦い思い出が甦った。
昭和の日本家庭にありがちだが、私は幼少期からピアノを習い、聴音など英才教育を受けた。しかし親の期待を裏切り普通高校に進み、大学生になってジャズに手を染めようとした。ヤマハのスクールで半年間、理論を教え込まれた後、いざ演奏する段になってみると、先生が眉間に皺を寄せ、深くため息をついた。ジャズのリズムとコードのセンスが私に無かったからだ。
譜面を見てビッグバンドで演奏したジャズメンが戦後すぐにアドリブを要求されたとき、似たような壁に突き当たったのではないだろうか。そこに救世主のようにアラキが舞い降りた。
もし私がハワイでアラキに巡りあっていたら、どんな助言を与えてもらえただろう。ツボを教わって、もう一度ジャズを勉強しようと奮起しただろうか。
(秋尾沙戸子「あとがき」/『スウィング・ジャパン:日経米軍兵ジミー・アキラと占領の記憶』新潮社、2012年刊、310〜311ページ頁)
なんだか宮澤賢治の〈鉄道ジャズ詩〉に乗りあわせて遡行したみたいに、「セロ弾きのゴーシュ」の狸の子だけでなくかっこうとの音楽場面が甦ってくる。「金星楽団で」譜面通りに演奏することがやっとだったゴーシュが、後日「町の公會堂のホール」で成功した楽団公演のアンコールでソロ演奏ができるまでには、初夜の三毛猫と第四夜の野ねずみ母子らとのエピソードを入り口と出口にした四夜にわたる音楽的訓練が必要だった。無我夢中で完全燃焼するアドリブというよりインプロビゼーションに近い「印度の虎狩」の独演も終わってしまえば空中に消えてしまう。もし録音されていたとしても、それは音盤に残されたただの楽譜に過ぎない。
前出日経新聞記事で知った佐々木孝夫監修のCD『“ジャズ 夏のはなしです”〜宮沢賢治が出会った洋楽はやり歌・ジャズ〜』を聴いた実感としては、音楽的嗜好の多様性というより、聴くだけじゃなく演奏もする人としての〈雑食性〉を指摘したい。戯曲「ポランの広場」からは、トラック2に「当時米シカゴで人気のダンスオーケストラを率いたポール・ピース[Paul Riese=CDジャケット表記]というジャズマンの曲」およびトラック3に「戯曲中に登場する山猫博士が」リクエストした「キャッツホヰスカア(猫のひげ)」という曲」、そして童話「セロ弾きのゴーシュ」で三毛猫のリクエスト「トロイメライ」に反して弾いた『印度の虎刈り』該当曲がトラック8に、狸の子が楽譜を出してリクエストする『愉快な馬車屋』がトラック7に、それぞれ他のトラック収録曲と同じようにSP音源から復刻されていてびっくりした。4曲ともデキシーランドジャズからスイングジャズそしてビバップへの移行期にあったシカゴ・ジャズ・シーンのダンス音楽としての側面をあらわす演奏といっていいだろう。
とはいえいま中年を迎えた女でも男でも、その生まれたころにはこうした話はまったく存在しなかった。「ジャズ」という名称でさえも、活字になったり活字になるほどの意味をもったりしたのはせいぜい四〇年あまり前、そう一九一五年ごろのことだった。いまの時点からさかのぼってみると、ジャズは人生にあてはめれば高年齢だがそれほど老いているわけではない。一九〇〇年代初期には南部の黒人でもミシシッピ川の河口地帯[デルタ]に不安内なら、この音楽をきいてびっくりしたほどだ。白人のオリジナル・ディキシーランド・ジャズバンドは「ジャズ」という名称を世に広めた楽団として知られるが、一九一七年にマンハッタンのライゼンウェーバー・カフェに登場したときには、これはダンスのための音楽ですとわざわざ店に張り紙をしなくてはならなかった。それ以降、ジャズはただ驚くばかりの手法で、すべてをその影響のもとにおさめながら発展をとげている。
(エリック・ホブズボーム/諸岡敏行:訳『ジャズシーン』績文堂、2021年発行、49〜50頁)
前記トラック7の「Livery Stable Blues 馬小屋のブルース(Nynez/Lee/Lopez)Original Dixieland "Jass" Band」の「ジャス」表記にも注目させられた。数年前に読んだ石塚真一のジャズ漫画『BLUE GIANT:ブルージャイアント』(小学館)のジャズ・トリオ[宮本大(ts)、沢辺雪祈(p)、玉田俊二(ds)]が“JASS”を名乗っていたからだ。なぜか、一流のサックスプレイヤーを目指す宮本大は理解ある彼女もいるのに童貞のような設定になっていた。このジャズ漫画の第7巻に所収の著者インタビューで「ソロでインプロビゼーションで演奏する時は、あなたの頭の中はどうなってるんでしょう?」にこたえて、W.ショーター[ts,ss奏者、作曲家、1933.08.25〜2023.03.02]がトニー・ウィリアムス[ジャズ・ロック・ミュージシャン、1945.12.12日〜1997.02.23]の言葉を紹介していた。「君にそれを話して教えられるのなら、自分はドラムを叩く必要がない」と言ったようだ。常に即興で自己模倣にならないソロ・インプロビゼーションを、演奏のたびに身体から引き出せるか出来ないかの境界線を生きた名ドラマーならではの厳しさと楽しさを併せもつエピソードだ。
宮澤賢治が愛聴した20世紀初頭からニューオーリンズを中心に発展したディキシーランドジャズの当初は譜面がなかったということだが、トラック7で聴けた「Original Dixieland "Jass" Band」の演奏はバンドメンバー全員によるコレクティブ、インプロビゼーションの響きに満ちている。“メンフィス・ブルーズ”を譜面に書きとめたW.C.ハンディ[1893〜958]は「ブルースの父」と呼ばれていても、クラシック音楽の訓練経験のあるミュージシャンのようで、根っからのブルーズマンではなかったようだ。1900年代の前半世紀間のジャズの目まぐるしい変化の坩堝にあたるシカゴ・ジャズのSPレコードを聴くことによって、ジャズのエッセンスだけじゃなく時代的な響きをも宮澤賢治はつかみ取っていたのではないか。
二十代半ばの突然の「家出」だけじゃなく折に触れて幾度となく定住を避けるかのように、花巻と東京とを行き来することの多かった宮澤賢治は、誕生時から死の間際にまで地震や津波や旱魃そのほか天地異変の脅威にさらされるなど東北の厳しい自然環境下での土壌・農業技術者としても、大正から昭和にかけて興隆しつつあった当時の産業構造の山嶺から吹きおろす社会的速度からの疎外感もじゅうぶん感じとっていただろう。
第一にこれからみていくことだが、ジャズの本質はジャズに影響されたポピュラー音楽のばあいとはちがって、規格化とか大量生産をされる音楽ではないことにあるし、第二にジャズは現代の産業とはほとんど関係をもたない。ジャズがこれまでにその音をまねしようとした機械は鉄道の列車だけであり、過去一世紀にわたるアメリカの民衆の音楽をとおし、広く共通していて、もっとも重要な象徴であるし多様なものをあらわすとは研究者たちの分析するところだが、といって機械化のシンボルには一度もなっていない。それどころか自分の思いを鉄道に仮託したレイルウェイ・ブルースの譜面が教えるとおり、自由をもたらす移動の象徴だった。
[ブルースの歌詞の引用部分を省略]
強いあこがれや深い悲しみのシンボルとしてなら「How I hate to hear that freight train go/blow hoo-hoo大嫌いだよ、貨物列車が泣きわめきながら行くのをきくなんて」というぐあいだった。鉄道建設の重労働の象徴としてはジョン・ヘンリーの伝説を歌った有名なバラードがある。疾走する機関車が男の精力の象徴、性交渉の象徴であり、ベッシー・スミス[一八九四〜一九三七]の“ケイシー・ジョーンズCasey Jones”はその例だ。[ブルーズの引用例略]できかれるとおり、なみはずれた力で鉄道つまり産業革命から生まれ、そのまま詩と音楽にとりこまれた唯一の工業製品の音と興奮を再現している。これが工業化社会のなにかの一面をあらわすとしたら、二〇世紀の大量生産の社会ではなくて一九世紀の終わりの機械化していない社会のほうだ。「鉄道ジャズ」には一八九〇年代に思いつかれなかった要素はなにひとつふくまれていない。
(エリック・ホブズボーム/諸岡敏行:訳『ジャズシーン』績文堂、2021年発行、53〜55頁)
身体的〈左右・上下〉スイング感に秀でた宮澤賢治の〈鉄道ジャズ〉詩は、宮澤賢治が農学校教諭暮らしの道を自ら閉ざし、実家を離れ下根子の二階建てを塾のよう改造して「農民芸術概論」の講義や肥料設計など各種農業相談を行う《羅須地人協会》という未踏の領野へ分け入る意気込みに呼応する躍動感のようにも響いてくる。創作や農耕だけじゃなく音楽にまで手を染める息子の労苦を諌める父政次郎の言葉に、宮澤賢治は手紙の中で、文学とくに詩や童話劇の詞の根底になる〈音楽〉がどうしても欠かせないとこたえている。
幼少の折に何かと世話になった母の実家の叔父さんが建て替える前の民家然とした広い居間の片隅に蓄音機が普段使われないままに置いてあった。実家の祖母から針の交換の仕方を教えてもらい、好奇心にかられるままに家捜しして見つけたSP盤をかたっぱしから回し聴いて遊んだ。宮澤賢治のコレクションにおよびようもなく、どれもこれも邦楽ばっかりでそのうち飽きてしまった。その後も母方の親戚一同が集まる秋祭りの座興の伴奏音源として重宝されていたようだが、いつの間にか壊れてしまっていた。とにかくSP盤による「ジャズ」との遭遇はなかったわけだが、埴生の自宅では、母の好みもあって石原裕次郎や森進一や青江三奈や藤圭子のLPに混じって、次第にジャズのEP盤やLP盤が鳴り響くようになっていた。祖父に咎められることもなく近所からの苦情もなかったが、ジャズ愛好者として何と無く片身のせまい世間の風あたりを風来坊のようにもてあましていた。(2023年5月22日記/23日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(13)ライブと擬音
「いうまでもないことだが、私たちは誰しもなにがしかの形で植民地人である。
被征服民として植民地勢力に屈しながら生き延びているのか、入植者として征
服者の権力保持に加担しているのか、輸入奴隷として新天地で繁殖をつづけて
いるだけなのかの種別は、私たちが等しく植民地人であるという事実に比べた
ら、きわめて些細なことである。」
(西 成彦『[新編]森のゲリラ 宮澤賢治』平凡社、2004年刊、12頁)
富山市内の1960〜70年代のとある地下における〈ジャズ〉を演奏する者とそれを聴く者とが交差する姿が垣間見えたジャズ喫茶通いも1970年の1月19日(月曜日)をもって止まってしまった。富山市内から高岡市内への人事異動に前後する頃だが、夜学生の頃から続いていた女との破局があり、その数年後に縁が生じた結婚にともなう新居の新築移住など諸々の家庭内事情を漕ぎ分けるような日々を過ごした。
それでも東京出張の際に、銀座ハンターでLP7枚を売って[3,600円]ジョン・コルトレーン[ts&ss奏者、1926.09.23〜1967.07.17]とオーネット・コールマン[as&tp他、1930.03.09〜2015.06.11]とセシル・テイラー[クラシック音楽教育を受けたフリー・ジャズ・ピアニスト、詩人、1929.03.25〜2018.04.05]の3枚を買って帰るなどジャズレコードを買って聴き続けることが生活の一部みたいになりつつあった。
一年あまりかけてようやく祖父から「この歳では孫のお前を頼ってついていくしかないだろう」の言葉が聞け、埴生の宅地や田畑の売り払いは若輩の孫より村人の信用があつい母と祖父にお願いした。新婚の自分ら夫婦は、富山市内の団地で義父が自宅療養していた建売住宅に転がり込み、妻の勤務先に近い富山市内の宅地の物色と購入後の家の新築に明け暮れた。買った田んぼを整地して新家屋が出来るまでの仮住まいだったが、姉夫婦から結婚祝いに贈られたレコードキャビネットに入るだけのジャズレコードと再生装置を持ち込んだ台所で聴くひと時をくつろげるよう工夫した。
石川との県境の山際の埴生の民家住まいを離れたせいか、甍の上がすぐ空という富山市郊外で区画整理された団地の一軒家住まいが物珍しいというより、なかなか馴染めなかった。義父に気兼ねしながら北側の台所の板の間にスピーカーを置いて鳴らしたジャズも、隣接するパン職人夫婦の居間まで漏れ聞こえていたに違いないような普請だった。お願いしたわけでもないのに、事情を察した北隣の奥さんから「義父さんの食事の世話をするから新婚旅行に行ってきなさいよ」と背中を押してもらえた。たまたま飛騨の神岡から富山に移住した隣人夫婦のおかげで、北海道の旭川住まいだった義父の弟さん一家に歓待され、初めて休暇を取った息子さんの運転で旭川の町並みだけでなく層雲峡そのほかへも案内してもらった。
なんとか1年後に引っ越せた高屋敷の新居で同居療養中だった義父の見舞いがてら、北海道から夫婦で訪ねてこられるまでの縁ができてほんとうに嬉しかった。
その際にわかったことだが、次男の義父には衛生兵として国内での軍隊経験があり、三男の義叔父は樺太で除隊されたとのことだった。敗戦の年の8月に侵攻してきたというロシア兵と戦ったのかどうかなど一言も聞けなかったが、とにかく富山に帰って住む家もなかったから北海道の旭川で戦後を生き延びる道を選ばれたようだった。
世間のつきあい、あるいは世間態というようなものもあったが、はたで見ていてもどうも人の邪魔をしないということが一番大事なことのようである。世間態をやかましくいったり、家格をやかましくいうのは、われわれの家よりも一まわり上にいる、村の支配層の中に見られるようにみえる。このことは決して私の郷里のみの現象ではないように思う。会津盆地の片田舎の貧農の家に育った蓮沼門三の自伝をよんでみて、家族内での人々の生き方をみると、われわれの家とはほとんどかわっていない。こうした貧農の家の日常茶飯事についていてかかれた書物というものはほとんどなくて、やっと近頃になって「物いわぬ農民」や「民話を生む人々」のような書物がではじめたにすぎないが、いままで農村について書かれたものは、上層部の現象や下層の中の特異例に関するものが多かった。そして読む方の側は初めから矛盾や悲痛感がでていないと承知しなかったものである。
(宮本常一「私の祖父」/『忘れられた日本人』(岩波文庫)1984年刊、209頁)
敗戦直前に日本の植民地政策下にあった京城から引き揚げ、母子三人が暮らすことになった祖父の民家があった埴生村でも、従軍による戦争経験者だけじゃなく「満州」からの引き揚げ体験者からも「過去話」が聞けたなんてことはほとんどなかった。ただなんかの会話のの切れ端で耳にした「ロスケ」とか「チャンコロ」とか、朝鮮からの引き揚げ者に向かって「芸者の子」だの、北海道の開拓民のことを「シャモ」だの、子どもの耳や心に世間の裏表を聞き分けさせるように響くコトバがあった。
高卒前後まで何かと訪れたことのある母の実家界隈での人当たりはあくまでもK合家の親戚の者という範囲内にとどまるものだった。小・中学校の夏休みの実家帰りの際など、近所の民家の子どもらから川魚獲りに誘われたりもしたが、どこかよそ者あつかい感がぬぐえなかった。散居村暮らしより里山暮らしの子ども心に映るもろもろの事物というか、忙しい大人が見過ごしがちな森羅万象の訪れが日々の慰安だった。
亡き父親代わりに母の実家由来の冠婚葬祭の席に幾度となく臨まされたが、たまたま隣合わせになって会話がはずみ酒も美味しかった馴染み人の縊死の報に触れるたびに唖然として嘆いたり、散居村地域として散在する民家の屋敷森に隠された家族関係の歪みや軋みを想わざるを得なかった。出奔、狂気そのほか民家の屋根の裏で演じ隠されつつある物狂おしい現実に圧倒されるように言葉を失うしかなかった。
どのようなひとことであろうとも、云う人間が籠めて吐く想い入れというものがある。父が「淫売」というとき、母がいうとき、土方の兄たちがいうとき、豆腐屋の小母さん、末広の前の家の小母さんがいうとき、こんにゃく屋の小母さんがいうとき、全部、ちがう「淫売」なのだ。けれども微妙なその発語への、ひとりひとりの思いのようなものは、どこかでひとつに結ばれていた。外ならぬ「淫売」というその言葉によって。淫売であるあの、あねさまたち自体の姿によって。
淫売という言葉を吐くときの想い入れによって、自分を表白してしまう大人たちへの好ききらいを、わたしは心にきめだしていた。末広の妓[おなご]たちを慕わしくいおもっているわたし自身が、大人たちへのひそかなリトマス試験紙そのものでもあった。大人たちは常にどこででも反応を示していたのである。そのわたしとはいえば、飴事件のようなことをやらかしていたにしても。
(石牟礼道子「第八章 雪河原」/『椿の海の記』朝日新聞社、1976年刊、209頁)
聞き覚えによるしかないが、三歳までの朝鮮総督府の官舎暮らしで何かと世話になったであろう朝鮮人のお手伝いさんとの日常会話は「日本語」だったというから、母のように耳で覚えて持ち帰った朝鮮語など一言もしゃべれない。朝鮮語を禁じられ、日本語しか使えない馬車に乗り合わせたたような植民地街道はどのような岐路にさしかかっていたのだろう?
ものをいえぬ赤んぼの世界は、自分自身の形成がまだととのわぬゆえ、かえって世界というものの整わぬずうっと前の、ほのぐらい生命界と吸引しあっているのかもしれなかった。ものごころつくということは、そういう五官のはたらきが、外界に向いて開いてゆく過程をもいうのだろうけれども、人間というものになりつつある自分を意識するころになると、きっともうそういう根源の深い世界から、はなれ落ちつつあるのにちがいなかった。
(前掲書、199頁)
引き揚げ後に読み(書き)ができるようになった頃に何よりも慰めになったのが『宮澤賢治名作選』上、中に収められた童話や詩に触れることだった。たまたま思いついた母が買ってくれた我が家唯一の二冊の蔵書の色あせない魅力のひとつが、作品のあちこちに散りばめられたオノマトペ[擬音・造語�の総称]による、例えば《原體剣舞連》[dah-dah-dah-dah-dah-sko -dah-dah]や《オッペルと象》[グララアガア グララアガア]や《風の又三郎》[どっどど どどうど どどうど どどう]で出逢った〈拍子/ビート〉の強調・表出にあった。田舎での陰湿ないじめにさらされる一方でいつの間にか〈性〉に目覚めたというか、作者独特の多様な擬音・造語の世界に未知の〈エロス〉が予兆する音や色や匂いまで盗み聞いていたのかもしれない。実際に「女から湿り気が無くなったらダメだ」と語り合う村の老人の世間話に聞き耳を立てたりしたこともあった。
幼少期の宮澤賢治作品のオノマトペに共鳴したかのような幼児幻覚《街道を過ぎ行く老人のイメージ》体験を再び呼び覚まされたのが、老境に差し掛かるのを待っていたかのように図書館で手に取った石牟礼道子全集で出逢った「道というものは、もっとも不思議なもののひとつだった。」[『椿の海の記』第七章 大回りの塘」冒頭]の一言だった。
町の年寄りたちは、朝、孫たちを起こすのに云っていたいた。
「ほら、もう、ずず、くゎん、くゎんの鳴りよらすぞ。起きてみんかい。今日どま、雨の神様の、来てくれらすかもしれん。ほら、ずず、くゎんくゎん、ずず、くゎんくゎんの‥‥‥聞こゆっぞ」
夏の早いあかつきに、どこかの峰でもう、雨乞いのドラと鉦が、遠く遠く、切実な祈りをこめてけんめいに鳴る。ずず、とはお腹にこたえてくる大ドラの響きの擬音で、鉦は、かんと鳴らずに、くゎん!と鳴らねばならなかったのである。
ずず、くゎんくゎん
ずず、くゎんくゎん
ずず、くゎん、ずず、くゎん
ずず、くゎんくゎん
山の頂までドラと鉦を打ち鳴らしながら登り進んで、祠[ほこら=原文ルビ]がなければ祠を建てて、村の中のいちばんよい井戸から汲んだ清水を天に供え、祈願者たちも一口づつ干あがった咽喉[のみど=原文ルビ]にいただき、幾日もお籠[こも=原文ルビ]りして、まだ雨を下さらぬときは頂を降り、迫迫[さこさこ=原文ルビ]を下って海の方に向かう。[下線部原文傍点]
(石牟礼道子「「第七章 大回りの塘」/『椿の海の記』朝日新聞社、1976年刊、178頁)
引き揚げ地の集落生活で児童参加した埴生村の獅子舞をはじめ、家並み街道を練り歩く冠婚葬祭など当時の習俗にともなった響きの幼児体験が共鳴するかのように、出自としての自然や家族に向き合いつつあった4歳児の「みっちん」が感受した雨乞い行列の特異なオノマトペ表出に揺さぶられた。
「石ッコ賢さん」とも呼ばれる一方で、宮澤賢治のひたむきな入信や、それにともなう信仰上の家庭内外での「対立」や「奇行、」と家出、その後のギクシャクして見える出処進退など、地元住民の好奇の目や噂話にさらされた「虚像」や「実像」を見守った大家族の〈沈黙〉に彩られた妹トシの病死。
教え子の就職斡旋のための1923[大正12]年夏の樺太旅行の際に、経由地の旭川に立ち寄った詩的スケッチ「旭川」のなかほどの「おゝ落葉松 落葉松 それから青く顫へるポプルス」のフレーズを読むと「おゝラリックス ラリックス それから青く顫へるポプルス」と読み替えたくなるのにあえて漢字のまま残された気がする。幽明界へと旅立った妹と感官外の交信をするかのように、宮澤賢治のオノマトペ表出は〈ことばを持っている世界を本能的に忌避するような〉幼児感官界へ分け入る扉を叩いているようだ。
物はうごくとき音にふれる。擬音はこのひとりでにふれる音に、間と切断と持続のパターンをあたえることだ。それは音の幾何学だといえる。さらに擬音を言葉でいおうとすると、もともと意味をつくる機能を第一義にしている言語を、意味以前のところでとどまるように、分節化の以前の「不完全」な機能でつかわなくては由緒ある擬音にはならない。
ひとつの事象がひとりでにうごくとき、生物が本能的に行動するとき、また人間が無意識に移動するとき、耳にとどく音にふれえないときもある。この音にふれえないうごきは眼でみられることがある。この音にふれないが眼でみえる事象のうごきを、音韻の機能だけであらわしたらどうなるか。これもまた擬音の世界をもたらすにちがいない。うめばちそうの白い花がゆれるさまが「ぷりりぷりり」と表現されると(「十力の金剛石」)、いくらか固い感じのする花の動きがみえるような気がするし、鈴蘭の葉や花が風にふれあうさまが「しゃりんしゃりん」と音化されると(「貝の火」)、わたしたちは花のかたちとうごきを同時に感じられる気がしてくる。かたちとうごきが音像ともいうべき状態で伝わってくるからだ。
(吉本隆明「擬音論・造語論」/『宮沢賢治』筑摩書房、1989年、318〜319頁)
富山市郊外の高屋敷で建てた新居での家族生活も落ちついてきた1975年2月14日(金曜日)の夜、留守居を母にまかせて妻と東京・中野サンプラザでのエラ・フィッツジェラルド[アメリカ合衆国のジャズ・シンガー、1917.04.25〜1996.06.15]&トミー・フラナガン[1930.03.16〜2001.11.16]トリオ公演を聴きに行ったときのことだった。舞台左袖からゆったり現れた彼女がすでに身体で拍子を取りながら歌っているようにしか見えなかった。実際は聴衆の歓迎の拍手と歓声しか聞こえていなかったのに。
その4ヶ月後の6月13日(金曜日)の夜に出かけた市内の県民会館でのアニタ・オディ[アメリカ合衆国出身のジャズ歌手、1919.10.18〜2006.11.23]の公演ではそんなことはおこらなかった。
結婚するまでジャズ・ライブとは縁がなかった妻と一緒に出かけたセシル・テイラ・ユニット[ジミー・ライオンズ(as)、アンドリュー・シリル(ds)]公演[1973年5月22日(火曜日)東京・新宿厚生年金会館大ホール]の第2部にはいささか面食らってしまった。第1部のホール全体をを埋め尽くすような即興演奏は、富山市内のジャズ喫茶などで聴いていた山下洋輔トリオのライブとは違うスピード感があって、期待してのぞんだ第2部は驚いたことにセシル・テイラーによる奇声と舞踏に尽きる〈演奏〉だった。あれは疾走する〈オノマトペ〉みたいな彼のピアノ演奏を追い越した世界だったのだろうか。フリー・ジャズには時間を追い抜くようなスピード感があるように、オノマトペには通常の意味の世界を突き動かす響の作用だけでなく、森羅万象の出来事の世界に意味を付与するような擬人化の効果をもたらしたりする。
寝しずまった夜のしじまに耳にするなんの脈絡やイメージもない無意識の露頭のような幼児の片言や家人の寝言など、人が人であることの無意識の闇を探索するソナーのような〈オノマトペ〉が現れたりすることもある。
この無意識の闇にきえてゆく擬音の物語は、宇宙のなかの現象の音のどれにも似ていなければいい。そんな想像をひとびとに促せばいいのか。それとも何かの音に似ているという想像を促せばいいのか。ここには作者の乳児資質がかくされているようにおもえる。またもしかすると作者がエロスを遂げようとする無意識の語音のようにもおもえる。体内から性液を一滴ももらしたことがなかったものは、世界にじぶんをふくめて三人しかいないと知人に語ったという伝説が、宮沢賢治にはある。もしエロスの情感が性ときりはなされて普遍化でき、その普遍化が幼童化を意味するとすれば、まずいちばんに擬音の世界にあらわれているといえそうな気がする。音の意味はかくされてしまうのに、その意味を解するのは幼童とその〈母〉だけだからだ。あるいはこうもいえる。〈母〉の無声の言葉を理解する体験の記憶と通路をもち、未文節の音声を〈母〉とかわす体験をなまなましく記憶している幼童性は、普遍的なエロスの原型をなしている。宮沢賢治の資質は擬音をつくりだすことで、そこにかぎりなくちかづこうとした。
(吉本隆明「擬音論・造語論」/『宮沢賢治』筑摩書房、1989年、326頁)
聴きこめば歌[歌詞]の響きは言葉のそれとは微妙に違っているように、日本語で思考している表現の距離感があるとしても、言葉になりそうでできない表現をオノマトペや音楽に引き受けさせたかのようにみえる宮澤賢治は、生まれ育った地域の地層や堆積した岩石や鉱物などを解き明かすように、「Ho! Ho! Ho!/むかし達谷の悪路王/まつくらくらの二里の洞/わたるは夢と黒夜神/首は刻まれ漬けられ/アンドロメダもかがりにゆすれ」[原体剣舞連(mental sketch modified)]と引用された「悪路王」を退治した東北地方の坂上田村麿将軍征夷の故事を詠みこんでいるが、自分自身の出自や来歴についてはどう掘りおこしていたといえばいいのだろう。
宗教から恋愛へ、そして性欲へと連続して流れてゆく情操と願望のうつりかわり(変態)という理念は、宮沢賢治の生涯の理念であるとともに、生涯によってじっさいに演じられたドラマだった。この考え方はふつう倒さだ。人間の身体の生理的なうつりゆきの必然的な過程で、性欲がきざし、さかんになり、思春期にはいって、ひとりの異性をもとめる願望に結晶してゆく。この願望がうまく遂げられず、そのあげく宗教的な自己救済や人間救済の願いをもつようになる。そんな過程はありうる。だがこの逆はない。宮沢賢治がスケッチャーとしてここ[「小岩井農場パート九」=筆者注]で展開している考え方は、逆だった。これはただの詩的修辞とみなさないとすれば、宮沢賢治の生涯の謎を理念化したものだといえる。かれには性欲の抑圧や昇華はあったろうが、性や恋愛にまつわる挫折はない。また宗教的な願望に固執するあまり、生涯の生活を挫折させたとはいえるが、生活の挫折のあげく宗教の救済感に変態したことはなかった。そうかんがえていいはずだ。わたしたちは宮沢賢治の心理と生理の発達史を掘りおこして、かれの意識と無意識のドラマを見つけだそうとしても、ガードがあまりにもかたくて、不可能にちかい。
(吉本隆明「擬音論・造語論」/『宮沢賢治』筑摩書房、1989年、267頁)
もう決定した そつちへ行くな
これらはみんなただしくない
いま疲れてかたちを更へたおまへの信仰から
発散して酸えたひかりの澱だ
ちひさな自分を劃ることのできない
この不可思議な大きな心象宙宇のなかで
もしも正しいねがひに燃えて
じぶんとひとと万象といつしよに
至上福祉にいたらうとする
それをある宗教情操とするならば
そのねがひから砕けまたは疲れ
じぶんとそれからたつたもひとつのたましひと
完全そして永久にどこまでもいつしよに行かうとする
この変態を恋愛といふ
そしてどこまでもその方向では
決して求め得られないその恋愛の本質的な部分を
むりにもごまかし求め得ようとする
この傾向を性慾といふ
すべてこれら漸移のなかのさまざまな過程に従つて
さまざまな眼に見えまた見えない生物の種類がある
この命題は可逆的にもまた正しく
わたくしにはあんまり恐ろしいことだ
けれどもいくら恐ろしいといつても
それがほんたうならしかたない
さあはつきり眼をあいてたれにも見え
明確に物理学の法則にしたがふ
これら実在の現象のなかから
あたらしくまつすぐに起て
明るい雨がこんなにたのしくそそぐのに
馬車が行く 馬はぬれて黒い
ひとはくるまに立つて行く
もうけつしてさびしくはない
なんべんさびしくないと云つたとこで
またさびしくなるのはきまつてゐる
けれどもここはこれでいいのだ
すべてさびしさと悲傷とを焚いて
ひとは透明な軌道をすすむ
ラリツクス ラリツクス いよいよ青く
雲はますます縮れてひかり
わたくしはかつきりみちをまがる
(宮澤賢治「小岩井農場」パート九の終わりの部分/『春と修羅』)
「パート一」の冒頭で〈わたくしはずゐぶんすばやく汽車からおりた〉《宮澤賢治》のこころにさまざまな形象をつくる感官のはたらきを左右する身体の皮膚感覚を透過するように、言葉をちりばめた幻想的空間の記述の終わりで〈わたくしはかつきりみちをまがる〉のはどのような類いの街道だったのだろう。
軽便鉄道が「殖民軌道」であった「小岩井農場」[1922.5.21]では〈ラリツクス ラリツクス いよいよ青く〉だったが、「殖民街道」に馬車を使っていた「旭川」[1923.8.2]では〈植民地風のこんな小馬車に/朝はやくひとり乗ることのたのしさ/「農事試験場まで行って下さい。」〉と揺られながら〈おゝ落葉松 落葉松 それから青く顫へるポプルス〉のように鉄道を経由した歩行から馬車へとスケッチャーの乗りのリズムが変わっている。当時の宮澤賢治が感受していた日本の外地のみならず国策による奥羽地方をはじめとした内地の植民地化の度合も、開拓民・シャモ[和人]とアイヌと文明開化の二重の植民地化を内包した北海道ではその速度感が微妙に違っていたようだ。
「兄賢治の生涯」を書いた宮沢清六の孫・宮沢和樹によれば「聞いたところによると、もともとわが宮沢家のルーツは近江商人で、現在の滋賀県、琵琶湖のあたりに住んでいて、京都周辺で商売をしていたといいます。江戸中期ごろにこちら岩手県花巻市にやってきて、その当時は藤井という名字だったのを宮沢に代えたという話です。」[宮沢和樹『わたしの宮沢賢治:祖父・清六と「賢治さん」ソレイユ出版、2021電子書籍@kindle]とある。そのようなな横の関係としての宮沢一族[マキ]のルーツをもっと遡行する試みを賢治自身はどのようにたどってか、「自分は縄文人だ」とか、縄文人になりたいと」と言っていたという。
「縄文人」と「弥生人」の区別も定かではないが、「みやこ」のあった近畿地方からどちらも征伐される側になる、北[蝦夷]と南[熊襲]に追いやられたとされる縄文人の〈身体/自然観〉を手元に引きよせて身体化するような大地に根ざした想像力を行使する場として〈この不可思議な大きな心象宙宇のなかで〉構想された〈現在性〉として「イーハトーブ」があり、数々の「オノマトペ」や〈心象スケッチ〉による諸作品の改稿や補訂が繰り返されたのではなかったか。そのエネルギー源として、〈‥‥‥われらに要るものは銀河を包む透明な意思 巨きな力と熱である‥‥‥〉[結論/「農民芸術概論」/『校本宮澤賢治全集』第12巻(上)』筑摩書房、昭和50年刊、15頁]とした縦の関係を強調しながらも、〈畢竟ここには宮沢賢治一九二六年のその考えがあるのみである〉[前掲書、16頁]となかば打ち消すかのように、より〈ほんとう〉を目指す姿勢が表明されている。(2023年7月9日記/10日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(14)庭と新居
「〈格子〉戸や窓の存在は、家屋の占めている空間と戸外の空間とを連結する
意識を象徴するものであった。つまり〈格子〉戸や窓をとおりぬけるのは天然
の〈風〉ばかりではなかった。家屋はおなじ露地にあるすべての別の家屋に〈格
子〉をとおして連隊の手をさしだしていた。〈格子〉戸に裏ガラスを張るように
なって最初の民家の孤立ははじまった。そして裏ガラスとしていわゆゆる〈スリ
ガラス〉を総張りするようになってこの孤立は深くなった。そしていま、〈格子〉
そのものが民家から絶滅しつつある。もちろん、小資産者たちは、ちょっとだけ
伝統をのぞいて様式として採用したがるモダニストの建築設計家と結託して〈格
子〉を住居に採用している。しかしかれらは〈格子〉の意識がない。つまり、失
うべきものももたないものたちの気安さがある。」
(吉本隆明「都市はなぜ都市であるかーー都市にのこる民家覚え書/『詩的
乾坤』国文社、昭和49年刊、312頁)
住み慣れた埴生の地から富山市郊外への移住について96歳の祖父から納得を得られたのは1971[昭和46]年も暮れる頃だった。
年が明けるのを待ったみたいに、同人誌仲間だった不動産屋に探してもらった3件[富山市西部の呉羽丘陵地域、同北部の化学工場地域、そして同南東部の農業地域]の候補物件からしぼった“田んぼ”の下見を母とすませた。ほどなく坪2.4万円で話がまとまった百坪足らずの宅地造成後の新築家屋完成予定にあわせるように、祖父が愛でた松など埴生の庭木類の選択と移植と庭土の手配も整えねばならなかった。当時騒がれた光化学スモッグなどの公害や、大雨による土砂崩れなどの恐れのある候補地を排除して買った地域はかって洪水を繰り返したことのある常願寺川流域の瓦礫の多い痩せた土地だったからだ。立山河川の砂防工事は進捗していたし、海抜は街中のデパートの屋上と同じくらいの高さだったから、富山湾で地震による津波が起こっても大丈夫だろうなどと軽口をたたいたりした。
都市ガスや上下水道などの整備区域外だった建築予定地に盛り土をした更地が締まるのを待ち、狭い敷地内での庭や井戸や浄化槽設置の場所を盛り込んだ家屋設計図を何枚も書いたり消したりしたが、その場限りと言うしかなかったような当時の自分にこのような事態が訪れたことが不思議というか、思いがけない新旧の家の成り行きに偶然が必然に変わったような縁を感じた。
母と祖父に任せていた埴生の宅地の売却は坪3.5万円でまとまったが、預貯金などの蓄えもない資金不足を補ってくれたのが妻の蓄えだった。平家と二階建て取り混ぜて仕上げた数枚の見取り図と前金200万円を携え、兄弟で工務店を営んでいた砺波の大工の叔父さん宅を訪れた。同行した母や妻もとにかく工面できた金額の範囲内を念頭に、兄の棟梁が「通し柱の位置が決まって良い」と指差した「二階屋の見取り図」の一枚で合意した。吹き抜けのある平屋建てにリスニング・ルームを組み込んだ第一希望案は予算不足で検討の余地もなかった。
どうやって「市街化区域」が決められているのかも知らず、当時の富山市街のはずれあたりで造成中の団地で売り出されている建売住宅を一緒に見て回って写真を撮ったりしてくれたり、“リスニング・ルーム設計”の参考資料を教えてくれたのが当時働いていた富大図書館工学部分館事務室の2階にあった電気工学科のT田という職員だった。
売り出し中の「モデル住宅」は「民家」の風情などかけらもないいわゆる“文化住宅”的な〈住み心地〉を提供する“住宅産業作品”の匂いがきつく、別途依頼中の工務店の棟梁に提示した「和式注文住宅」の予算の範囲内で〈民家〉の要素をどのように組み込んでもらえるかが“鍵”のように思った。
採用された図面の“応接間”をリスニング仕様にといっても、工務店を営む兄弟大工いずれも経験がないということで、自前で詳細な建材を含む構造・設計図を暗中模索するしかなかった。幸いなことに“我が家建築”の棟梁が中学生の頃から馴染みの叔父さんになり、吸音材による三方の壁や天井の音の吸収ならびに乱反射構造と窓やドアの遮音構造などお互いに納得がゆくような仕事をしてもらえる運びとなった。
北陸の冬にしては珍しく晴れた1972年12月16(土曜日)〜17日(日曜日)日にかけて、小矢部市埴生および富山市若竹町からの二世帯の高屋敷の新居への引越しを予定通り済ませてひと安心。運送業社だけでなく、母の実家の叔父さんや叔母さんや友人夫妻や職場の知人の助けに恵まれての首尾だった。
祖父と母に任せておいた埴生の自宅の庭に残してきた庭木類の高屋敷の新宅の庭への移植は、翌年の春先に小矢部市の庭木職人の手を借り、祖父の意向も汲み、主木の赤松を真ん中に陽当たりと風通しを見越し、その他の庭木も祖父の仏間兼居室から眺められるよう作庭してもらった。
つまりこれらの樹々は、つたない恋も含めて私の過誤多い青春の生き証人であった。こういうことは私だけのこととは思わないから、お許しを願っていま書きつけたのである。
ひとが生きるということは樹木と語ることであるといいたくて、私は思い出話をした。そんな特殊な関わりを樹木とはした覚えがないという人がいれば、口をつぐんで引込まざるをえないけれども、そんな人でも車で初めての町を通ったとき、これはいい街並みだなとお感じになったことはあるだろう。思い出してほしい。その街並みには必ず美しい並木があったはずである。
(渡辺京二「樹々の嘆き」/『未踏の野を過ぎて』弦書房、2011年刊、94頁)
縁側越しに四季の庭が眺められた埴生の八畳の座敷から、いきなり四畳半住まいになった祖父は愚痴ひとつこぼさなかった。仏壇の扉を開けたままにして朝晩のお勤めを欠かさず、新聞は自室で広げていたが、日々の食事は茶の間ならぬリビングまで歩いてきて家族と一緒だった。晩酌の燗酒は徳利とお猪口からコップ一杯に変わっていた。
縁側のない六畳の座敷の床柱を撫でるなど、一階の柱や壁や天井などの作りを見て回った祖父に是非二階も見てみたいと言われたことがあった。請われるままにおんぶして階段を昇ったが、あまりの“軽さ”に驚いた。
目ざとく八畳の座敷と控えの六畳を仕切る天然木の欄間に気づいたようだった。井波彫刻の欄間などの余裕がないのを見越した棟梁がサービスしてくれた逸品だった。
床の間に飾った祖父の骨董品なども確かめつつふたたびおんぶして降りる際に、埴生の家に住んでて友だちを呼ばなかったのは家が古びて粗末だったからかと耳元で囁かれ、応えに窮した。
田畑を耕すかたわら、米屋兼精米業を営んでいた祖父が大正の初めごろに建てたであろう埴生の民家は一見平屋風だったのに、店舗部分の天井と屋根の間の“あま”に土間に常置してあった梯子を立て掛けて上がれるようにしてあった。囲炉裏のあった吹き抜けの茶の間との仕切り壁があるだけの煤けた空間のことでも問い返せばよかったのだろうか。
わたしがみた民家で戸外からみると〈低い二階〉をもったものがあった。この〈低い二階〉は、その屋内の構造をみても、屋根裏部屋、調度置き場、寝床、などの役割しかもたないだろう。なぜ、この〈低い二階〉の様式は造りだされたのかわからない。
ただ、いかにもありそうな理由を空想できないことはない。幕末慶応年間の解禁まで、二階家造りは公的には禁制であった。しかし、二階家造りはある勢いをもって江戸の町をせきけんしたことを、藤田元春は記している。しかし、この二階の部分だけは、幕府の政策が硬化すると、いつおとがめがくるかわからないという強迫観念の関数であった。そこで様式的に〈低い二階〉は発生したのであろうか? つまり、あれは二階ではなく物置きていどのものだという弁解の根拠をつくるために〈低い二階〉の様式はできあがったのではなかろうか?[下線部原文傍点]
(吉本隆明「都市はなぜ都市であるかーー都市にのこる民家覚え書/『詩的乾坤』国文社、昭和49年刊、314頁)
〈家・屋敷〉の規模として、高屋敷で建てた新居は大正期の埴生村で祖父が建てた「民家」にとうてい及ばず、祖父や母の思い悩みのうちに自然解体するしかなかった精米廃業三反百姓の長男夫婦一家が郊外に移住した共稼ぎ三世代家族のーー祖父や母にとっては手狭だったろうがーー夫婦共棲の家となった。
日本の農業人口が全就業者の20%を割った1960年代半ばごろだったが、とっくに兼業農家としての生活基盤を無くしていた埴生の我が家にとっての“農業問題”と“土地問題”を家族ぐるみでなんとかくぐり抜けられた成り行きに人の縁を感じた。1973年10月の第一次オイルショック直前ーー着工前に渡した手附金で建材を買い込めてとても助かったと棟梁は喜んでいたーーの化石エネルギー枯渇の噂などで冬季暖房手段の選択に悩まされながらも灯油とLPガスの併用に落ち着くしかなかった。オイル価格が産油国と“セブンシスターズ”の談合で決まるなんて知らなかったが、日本経済は翌74年から戦後初のマイナス成長に転じて共稼ぎの定期昇給など当てにならず、とにかく家計にローンを組み込まないが家訓のひとつになった。
慌ただしくも家族元気で新居の正月を迎えられて良かったが、遅れに遅れていたリスニングルームの仕上げ作業も棟梁と一緒に三層構造にした床の化粧材を一枚一枚張って有終の美を飾ったとはいいがたかった。
後日ジャズ向けに新規発注したJBL[LE175DLH+D130]のスピーカー・システムを設置した際に気付いたのだが、床下を掘り下げて浮かした床との共振を避け、地面に直結した作りにしたスピーカー設置部分の高さも幅も微妙に狂っていたり、特注した作りの“遮音ドア”が裏返しになっているのに気付いたりした時など、棟梁が手配した左官屋さんや建具屋さんに文句を言う気分にはなれなかった。
ようやく出来あがったリスニングルームで待ちかねたようにジャズの愛聴盤を聴いたが、低音から高音まで音がこもらず抜けも良く、ボリュームを上げてもビリつくような共振や歪みも感じなかった。残響時間の数値的な実態についておまけ話みたいな出来事があった。
なんだか夫婦でジャズを愉しむ部屋というより、まだ試聴室気分が抜けきらない霙まじりの休日だった。電気工学科のT田君を通して了解していた「音響工学」を学んでいる院生のN谷君が“私設リスニングルームの”「残響特性」の実測にやってきてくれたのだ。スターター用の拳銃をぶっ放した測定結果のグラフを示し、部屋の広さに対して音楽的に適切な残響時間になっているとのことだった。測定作業後にN谷君のリクエストに応えて掛けたLPレコードのジャズ演奏を聴いて、彼の耳には「ベースの音が違うなぁ」といことだった。聞けば富大オーケストラでベースを弾いていたらしく、卒業後は就職が決まっていた“ヤマハ”でスピーカーの設計・製作の夢を果たせたのだろうか。
道幅6メーターの市道の家並み南外れで田んぼに囲まれ、移植した庭木越しの立山連峰の眺めが新鮮だった。三角形の隣の更地に家でも建ったら一階の座敷からの景観が台無しだねと交わしていた夫婦の会話が、数年後に本当になるなんて。狭い敷地に建蔽率も無視しして建てた二階屋の屋根雪降ろしが我が家の背戸に設けてあったたプレハブ物置屋根を直撃破壊しても素知らぬ顔の隣人一家が越してきたのだった。
大工の叔父さんに相談したら屋根を高くしたらいいだろう、ということで増築することになった。1階の座敷に縁側を設け、そこから通じる二階建ての「離れ」の二階が新たなくつろぎ部屋となった。壁の二方を作り付けの書棚とし、大人と子ども用の机も備えた。1階はクローゼットを備えた物置部分と洗濯物を干す土間部分に分けて使うことになった。
とにかく民家風の木造建築のいいところは、一家を構成する家族の態様に合わせていかようにでも増改築が可能だということだ。北陸の鄙びた温泉宿を訪れた時など、増築に増築を重ねてまるで迷路のようになった造作に、表立って見えない大工さんの技量をうかがい知るような機会もすっかり遠のいてしまった。
まさかLPや本が溢れるような暮らし向きになるとは思いもしなかったのに、越してきた隣家の屋根雪下ろし弊害に端を発した増築のおかげで、いつの間にか漸増一途のコレクションの収納問題は大幅に改善されたわけだ。しかし1980年代から聴き漁ってきたCDやDVDなどに至ってはもはやお手上げといったところだ。幸い数千枚のLPに関しては妻がカード目録を残して置いてくれたおかげで探し出すのに苦労はしないが、本やCDなどは手探りの度合いが高まる一方だった。
物には執着しない祖父が仕立てた小ぶりの紅葉が夜盗に抜かれ、似たような一本をを買ってきて植えたらそれも盗まれた。ツツジの植え込みの枝を幾つか手折って庭土に潜らせ、根がついたのを等間隔に道路沿いに植え、塀ならぬ植え込み代わりに仕立てようとしたが、ある朝見たら根こそぎ無くなっていた。
庭に面した部屋がアルミサッシじゃなく、木虫篭と呼んでいた格子造りだったら祖父は夜中でも気配でそれとなく気づいたかもしれない。おそまきながら鍵もかけないで寝ていた埴生での民家暮らしからの決別を突きつけられた気がした。
新居で暮らし始めてしばらくは田舎で地産地消していた野菜や米の味が忘れられなかった。富山市郊外への移住で食生活も一変したのに、和食の腕が確かだった祖父は美味いとも不味いとも言わず、好き嫌いなく何でもよく食べてくれた。1973年1月の70歳以上の老人の医療費の無料化にも無縁で寡黙な祖父の背中に33歳で殉職した息子、面影何一つ知らない父の像が張りついていそうな晩年の気配が忘れられない。
1970年代半ばごろまでの富山市内におけるジャズ同好会のメンバーが噂を聞きつけ、祖父の居室と廊下を隔てた孫夫婦のリスニングリルームへのジャズ愛好家の出入りが頻繁になっても、明治12[1979]生まれの祖父は物音や気配に敏感だったのに嫌な顔一つ見せず、恵比須顔を絶やさなかった。我流の防音構造を施した効果があったのか、いつも二階の六畳の間でで寝起きしていた大正生まれの母も黙認顏だった。
大正11[1922]年に妻を亡くし、植民地の朝鮮総督府における外地勤務へと送りだした一人息子を殉職で失うまで、埴生村で建てた部屋数が五つ余りの民家での一人暮らしを経験していた祖父だが、老いて孫の移住に従うしかなかったとはいえ、仏壇と押し入れ付きの四畳半暮らしをどう感じていたのだろうか。
宮澤賢治が昭和6[1931]年10月上旬から年末か翌年初めまでに使用した「雨ニモマケズ手帳」(『校本宮澤賢治全集第十二巻(上)筑摩書房、昭和51年刊所収』)の49頁の「唯諸苦ヲ抜クノ/大医王タレ」の書き込みと対になった50頁に仏間と居間が一緒になった四角い平面図が手書きされている。まるで我が祖父の居所と同じように見えたのだが、「手帳」の159頁や164頁に描かれた立体図を見るとそれだけで独立した一軒家のようなのだ。
大正13[1924]年に同僚の白藤慈秀と生徒を引率した北海道修学旅行の復命書で、賢治は「恐らくは本模型の生徒将来に及ぼす影響極めて大なるべし。望むらくは本県亦物産館の中に理想的農民住居の模型数箇を備へ将来の農民に楽しく明るき田園を形成せしむる目標を与へられんことを。」と認めるだけじゃおさまらず、「早く我らが郷土新進の農村建築家を迎へ、従来の不経済にして陰鬱、採光風通一も佳くなるなき住居をその破朽と共に葬らしめよ。」と、農村建築になみなみならぬ意欲を表していた。
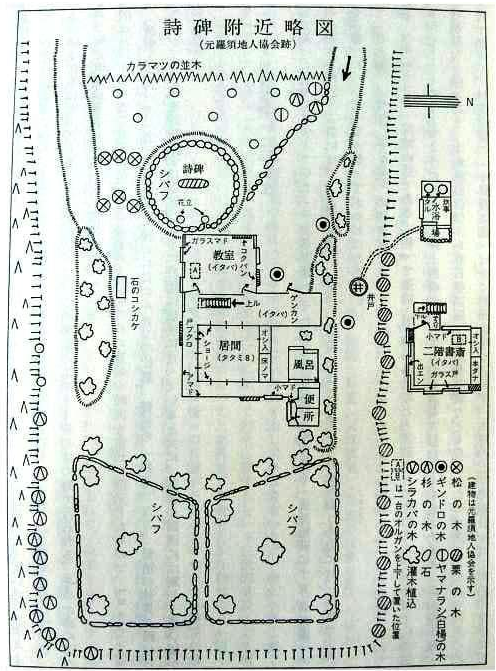
[典拠:『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社);参照:「「みちのくの山野草:1958 宮澤家別荘のことなど」]
在勤4年4ヶ月の教職を辞し、大正15・昭和元[1926]年に実家を出て下根子桜の別宅に移り住んだが、この改修された二階建て家屋が、農村文化活動の拠点となる「羅須地人協会」として賢治が目指した作庭を施した理想の農村建築の実現形と見ていいのだろう。では、自らの住処としてはどうだったのか。(2023年12月24日記/12月26日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(15)老いと住居
「宮沢賢治という身体は、すぐれてリゾート的な身体なのである。彼が
気象の諸変化に異様なほどに敏感で、かつその内外の委細をつくした記
録に傾注しているのはなぜか。生来の資質や農業上の心配に加えて、十
八世紀イギリスの治療日記の書き手たちと同様、気象状態に左右される
おのれの〈危うい健康〉(ことに吸気の状態)に対する自覚が基底にあ
ったはずである。爽快な気象だけに価値があるのではない。誤解を恐れ
ずにあえていえば、健康を害したり不作をもたらしかねない気象や地質
すら、「心象スケッチ」の水準では新鮮なエネルギーとして享受される
ことになる。「罪や、かなしみでさえそこでは聖くきれいにかゞやいて
ゐる」(広告文ちらし(大))「詩人は苦痛をも享楽する」(「農民芸術
概論綱要」)」
(岡村民生『イーハートーブ温泉学』みすず書房、2008年刊、174〜175頁)
[承前]宮澤賢治は自己像として「でく」を「木偶」→「土偶」とみなし、同じく「雨ニモマケズ手帳」の71頁に「土偶坊/ワレワレカウイフ/モノニナリタイ」と書き込みがあり、その住まいとして「小さな萱ぶきの小屋」を想定していたようだ。これだとまるで鴨長明が六十歳という人生の終わり近くになって、さらに余生を送る家として作った「方丈庵」そのものではないか。広さは三メートル四方[方丈]しかなく、高さはニメートル十センチ[七尺]を越えず、長明三十歳余りの時に作った家と比べてもその百分の一にも満たない広さであったという。
およそ700年以上も時と所を隔てて、60代の長明と30代の賢治が「終の住処」の構想において似た者同士とはいったいどういうことなのだろう。『方丈記』には長明自らが経験した四つのの天変地異が書き連ねてある。
・安元三年(1177年)の京の火災
・治承四年(1180年)に京で発生した竜巻およびその直後の福原遷都
・養和年間(1181年?1182年)の飢饉
・元歴二年(1185年)に京を襲った大地震
宮澤賢治の生涯も1896[明治29]年6月の三陸大津浪、7月の大雨大洪水、8月の陸羽大地震、9月の大雨洪水の再来にはじまり、1923[大正12]年9月1日に関東大震災、1928[昭和3]年岩手県7?9月の旱魃、1931[昭和6]年岩手の冷害と豪雨による凶作、亡くなる1933[昭和8]年の3月には三陸地方大地震大津波などに見舞われている。
いつも御天道様を念頭に抱いていた祖父は1945[昭和20]年8月の富山大空襲の夜空には驚いていたが、1948[昭和23�]年6月28日の福井大地震や、1959[昭和34]年の伊勢湾台風や、1963[昭和38]年の38[サンパチ]豪雪などには多少の不安を感じてもさほど驚かないようすだった。生涯に出会う天変地異を天のなす業、自然の災いとして外在化された身体感覚でもって受容していたのだろうか。平生は無意識に内臓感覚を働かせて身体内自然を感受していたように、身体外自然に対しては体外へと遠隔化された内[=外]臓感覚でもって森羅万象の訪れに相対していたみたいだった。
口癖のように呟いていた“ナマンダブ”[=南無阿弥陀]の裏にはいつも「公界」あるいは「苦界」が織り込まれていたようだが、いずれにしろ孫に人間の業苦など分かろうはずもなかったのに。子供心にうるさかった祖父の「小言」も歳とともに少なくなり、かといって諭すような物言いもしない好々爺然とした老境の姿に変身を遂げたようだった。
あいかわらず朝晩の仏前のお勤めを欠かすようなことはなかったが、ふとした折に「なかなかお迎えが来ない」と独り言ちたりするようになった。田畑を売り払ってしまって飲食が細くなっても、手入れできなくなった庭の樹木や盆栽への愛着が薄らぐようなことはなかった。かといって新しく出入りするようになった植木職人の仕事に注文をつけたりすることもなかった。亡くなる半年ほど前に家人に盆栽や植木の世話を頼んだりしていたが、今じゃ盆栽は一鉢も残っていない。植木職人も代替わりして今に至るが、月桂樹など枯れた庭木は僅かにとどまっている。
三一四
[夜の湿気と風がさびしくいりまじり]
一九二四、一〇、五、
夜の湿気と風がさびしくいりまじり
松ややなぎの林はくろく
そらには暗い業の花びらがいっぱいで
わたくしは神々の名を録したことから
はげしく寒くふるへてゐる
(宮澤賢治「春と修羅・第二集」/『校本宮澤賢治全集 第三巻』筑摩書房、昭和50年刊)
もし自己というものがあるとしたら、それは田んぼや畑の土壌のようなものであるとして、そこから何が育ってくるか来ないかが問われるだけのことじゃなかったのか。とりあえず人は樹木のようにあるとして、そしてそのようなものしか育てられなかった土壌がその人の自己なのだろうか。
人それぞれ何を日々の繰り返しとするか、貧弱な土壌を豊かなものに、持続という名の稽古が第一としたら、どのような堆肥を鋤きこんで肥沃化させ続けられるか。やがて土壌自体が虚弱化し、樹木も枯れ果てるまで。
自分の将来など考えもしない埴生の田舎小僧だった頃、墓石以外どのような写真・資料も残っていなくて見当もつかない祖父の連れ合い[母の話では二人目とのことだった]がどんな女[ひと]だったか気になってしょうがないことがあった。大正11[1922]年に一人息子を残して早死にしたようだから、嫁いだ母も知りようがなかった。近所の年老いた村人の噂話だったが、芸者を身請けし料理や家事など一切させずに若い祖父がすべてを仕切っていた様子が不思議そのもの。思春期頃までの日々接していた癇癪持ちの祖父から思いもよらない夫婦像にどうしたら遡れようか。いつも横座に座って長煙管で煙草をくゆらせている女の姿が村人の語り種から甦るようで、家をなす男と女の関係なんて男次第でどうにでもなるとも思えなくなった。
作品一〇七一番
わたくしどもは
ちやうど一年いっしょに暮しました
その女はやさしく蒼白く
その瞳はいつでも*
何かわたくしのわからない*
夢を見てゐるやうでした*
いつしょになつたその夏のある朝
わたくしは町はづれの橋で
村の娘が持つて来た@
花があまりにも美しかつたので@
二十銭だけ買ってうちに歸りましたら
妻は空いてゐた金魚の壺にさして
店へ竝べて居りました
夕方歸つて来ましたら
妻はわたくしの顔を見て#
ふしぎな笑ひやうをしました#
見ると食卓にはいろいろな果物や
白い洋皿などまで竝べてありますので
どうしたのかとたづねましたら
あの花が今日のひるの間に%
ちやうど二圓に賣れたといふのです%
その青い夜の風や星
すだれや魂を送る火や
そしてその冬
妻は何の苦しみといふのでもなく
萎れるやうに崩れるやうに&
一日病んで歿くなりました&
(宮澤賢治[宮澤清六編]『詩集 雨中謝辭』創元社、昭和27年刊)
出張の折などのジャズレコード探しがが楽しかった独り身の1960年代半ば過ぎ、神田神保町でふと立ち寄った八木書店で衝動買いした宮澤賢治の詩集のことなどほとんど忘れかけていた。『校本宮沢賢治全集』第六巻所収の「[わたくしどもは]一九二七・六・一」では、引用者が付けた*、@、#、%、&の記号の行がひと続きになっていてどっちが異稿なのか、いずれも制作日付が同じなのがほかにもあった。
装景家と助手との対話
一九二七、六、一、
さうさねえ、
土佐絵その他の古い絵巻にある
禾草の波とかゞやく露とをつくるには
萓や丶丶丶すべて水孔をもつものを用ひねばならぬ
思ふにこれらの朝露は
炭酸をも溶し含むが故に
屈折率も高くまた冷たいのであらう
苗代の水を黒く湛えて
そこには多くの小さな太陽
また巨大なるヘリアンサスをかゞやかしむる
うん、わたくしは
いままで霧が多く溢出水なのに
どうして気がつかなかったのでございませう
Gaillardox! Gaillardox!
そこを水際園といたしましたら
どんな種類が適しませうか
なぜわたくしは枝垂れの雪柳を植えるか
十三歳の聖女テレジアが
水いろの上着を着 羊歯の花をたくさんもって
小さな円い唇でうたひながら
そこからこっちへでてくるために
わたくしはそこに雪柳を植える
Gaillardox! Gaillardae!
(宮沢賢治「補遺詩篇 II」/『校本宮澤賢治全集 第6巻』筑摩書房、昭和51年刊)
花巻温泉南斜花壇の設計をしたり、田植えの時期と肥料設計など稲作指導に奔走していた1927[昭和2]年、31歳独身の賢治がなんだか〈兄と妹〉みたいな夫婦像やその仕事柄を無声映画のひとコマのようにスケッチしていた。
長年連れ添ったらこうなるしかないというような夫婦の疎通界に至ることのない、花を飾ったり料理を作ったりつかの間に終わった夫婦関係に潜む言葉などではかり知れない独得な係わり方が映しだされているようだ。
村の娘から花を買って妻に渡した作中の「わたくし」の仕事が馴染み少ない「装景家」だとしたら、話さなくとも通じ合っている妻と、夢想が邪魔をするみたいで話が通じ難い助手との対比が面白い。「聖女テレジア」が着飾って歌い出てくるようにユキヤナギを植えるというくだりに、「装景家」たる心意気ーー「光象生産準志に合し 園芸営林土木設計を産む」(「農民芸術概論綱要」)ーーが込められていよう。
六月の雲の圧力に対して
地平線の歪みが
視角五〇度を超えぬやう
濃い群青をとらねばならぬ
早いはなしが
ちゃうど凍った水銀だけの
弾性率を地平がもてばいゝのである
Gillarchdox! Gillarchdae!
いまひらめいてあらはれる
東の青い橄欖岩の鋸歯
けだし地殻が或る適当度の弾性をもち
したがって地面が踏みに従って
寒天あるいひはゼラチンの
歪みをつくるといふことは
ヒンヅーガンダラ乃至西域諸国に於ける
永い間の夢想であって
また近代の勝れた園林設計学の
ごく杳遠なめあてである
……電線におりる小鳥のやうに
頬うつくしい娘たち
車室の二列のシートにすはる……
然るに地殻のこれら不変な剛性を
更に任意に変ずることは
恐らくとても今日に於ける世界造営の技術の範囲に属しない
……タキスの天に
ぎざぎざに立つ
そのまっ青な鋸を見よ……
地殻の剛さこれを決定するものは
大きく二つになってゐる
一つは如来の神力により
一つは衆生の業による
さうわれわれの師父が考へ
またわれわれもさう想ふ
……そのまっ青な鋸を見よ……
すべてこれらの唯心論の人人は
風景をみな
諸仏と衆生の徳の配列であると見る
たとへば維摩詰居士は
それらの青い鋸を
人に高貢の心あればといふのである
それは感情移入によって
生じた情緒と外界との
最奇怪な混合であるなどとして
皮相に説明されるがやうな
さういふ種類のものではない
(宮沢賢治「装景手記」冒頭部分/『校本宮澤賢治全集 第6巻』筑摩書房、昭和51年刊)
気象や地殻の様相をたちどころに自然の圧力や弾性のように感受する[できる]宮澤賢治の身体感覚のありようが〈心象スケッチ〉の表出過程の地表の凹凸[転換]のように行分けされている。
なみはずれて〈気象〉に敏感なだけでなく、地球の陸地を取り巻く林檎の皮のような薄い土が覆っている地殻の剛性を構成する「如来の神力」と「衆生の業」の「徳」の〈配列〉として「風景」を見ている「装景者」の眼がスケッチする二重性の体現。霊[詩]的に体感しうる自然を農業指導家として理想に叶うべきまことの美へと設計・造営する実践家が対峙すべき〈場所〉があった。
住 居
青い泉と
たくさんの廃屋をもつ
その南の三日月形の村では
教師あがりの種屋など
置いてやりたくないといふ
‥‥‥風のあかりと
草の実の雨‥‥‥
昼もはだしで酒を呑み
眼をうるませたとしよりたち
(宮沢賢治「生前発表詩篇」/『校本宮澤賢治全集 第6巻』筑摩書房、昭和51年刊)
「光象生活準志によりて 建築及衣服をなす」(「農民芸術概論綱要」)以前の「住居」で「眼をうるませたとしよりたち」もかっては、「さう/やまつゝじ!/栗やこならの露にまじって/丘いっぱいに咲いてくれたが、/それも相当咲きほこったるすがたであるが/さあきみはどうしたもんだらう//なによりもあの冴えない色だ/朱もあすこまで没落すると/もうそちこちにのぞき出た/赭土にさへまぎれてしまふ//どうしてこれを[以下空白](「補遺詩篇II」/『校本宮澤賢治全集 第6巻』筑摩書房、昭和51年刊)と問いかける「装景者」としての〈自然〉を感受していたはずだ。
県境の雑木山裾の街道筋の住居から県庁所在地の郊外に移り住んだ祖父の眼に、移植し根付いた庭の景観はどのように様変わりして見えたことだろう。町からほど遠く人が往来する場所から、山野から都市への〈境界領域〉へ移り住んだことで、埴生村で培ってきた人間関係だけでなく村住まいで感受していた自然観そのものも変容してしまったのではなかろうか。
宮澤賢治が提示する「装景者」は、風景を〈感受〉するだけにとどまらず、能動的に働きかけ変化させるーー「まづもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう」(「農民芸術概論綱要」)ーー生命観の働きを体現する者とみなされよう。賢治にとって〈装景〉とは、自然環境と人との関係を双方向性に満ちた新たな〈場〉として顕現させることなのだろう。だから作庭から完成までのすべての過程において〈造園〉はすべての関係者に開らかれていなければならない。音楽が作曲家と演奏者だけでなく聴衆を不可欠とするように。
祖父の最初の妻と二番目の妻との間にどんな経緯が挟まれていたのか知る由もなかったが、並々ならぬ先立たれた後妻への対応ぶりに祖父の想いが秘められていそうだ。寡黙な祖父の後ろ姿がよりいっそう深まった気がした。機嫌のいい時は虚弱な孫へのいたわりをあらわしたりした。就学途中まではお正月になると温泉湯治に連れ出された。松でも梅でもない、和倉の竹屋旅館という鄙びた木造の宿の選びがいかにも祖父らしく思い返される。温泉につかるのはいいとしても、しょっぱい温泉水を飲まされるのには閉口したが、液体を口に含んだままの身体の微妙な生々しさだけは後々までも残った。朝もやの和倉の海に近づいたりすると波音に体が同調するようで、遊び慣れた山里では感じたことのない身体感覚に目覚めたようだった。
どういうわけか祖父との温泉行きは中学生になる前に途絶えてしまった。祖父との年の差は六十五歳ほどだったがあんまり「老齢」ということを感じさせないで中学生になった孫に畑仕事など、虚弱児なりの労力を実行するよう求められるようになった。なんだか加齢による「虚弱化」と生来の「虚弱性」とが向き合うような当たりで「このような気持ちは歳をとってみなきゃわからない」という祖父の言葉が、前後して実家の祖母からも、やがては母からも異口同音に漏れ聞こえるようになった。
老齢化で一番辛いことは、身体の動きが鈍くなり、足腰が弱くて痛みがともなうといったことではない。自己の意力や意志、そう志向すること、それに従って実現しようとする行為や運動性との「背離」が著しく増大することだ。これは若い人にはわからない。老齢だから身体を動かすのか億劫[おっくう=ルビ]なんだと誤解している。丁寧にいえばそうに違いないのではあるが、真の原因はこの意力と行動との背離性にあるのだ。これは専門と素人、熟練と浅い経験との違いではなく、老齢に固有のものだ。
(吉本隆明『中学生のための社会科』市井文学株式会社、2005年刊、79頁)
中学生の自分には気づくどころか、家族の老いの状態について判断するなど身体観察の埒外のことだった。家族に請われるままに線香でモグサに火をつけたり、肩を揉んだり叩いたり、時には足の裏を踏んであげたりするだけで、その先へと祖父との歳の差が関わる老齢の実態に足腰の考えがおよばなかった。
老齢は身体の生態的な自然を前提とする限り(つまり事故を除けば)、誰でもが体験するのに誰でもが老齢を体験しなければわからない点を含むということだ。つまり自然の「順序」がもたらす差異にほかならないのに社会的な「順序差異」としてしか言葉では表現されないことだ。老齢者自身も、それに大なり小なり接触する場面をもつ人もおなじように「自然の順序」を「社会の順序」に置き換えて考えているとおもう。おまえはどうだといわれれば、即座にわたしもそうだというほかない。これは間違いだということはわかっている。どうすればいいのかもわかっている。社会が全体的に「自然の順位」による差異だけを保存し、社会での個人、個人の心の全体性を「自然の順位」の差異にすればよい。このうちいちばん難しいのは(少なくとも老齢のことについては)、個々人の精神の全体性において「自然の順位」による差異以外のものを廃棄することだと思う。
(吉本隆明『中学生のための社会科』市井文学株式会社、2005年刊、92?93頁)
埴生の民家の囲炉裏端で『宮沢賢治名作選』を読み始めた頃に「本など読むな」と怒鳴られたのは、六十五歳あまりも先を生きつつある老境の祖父が、後からやってくるはずの孫に向かって発した言葉なのだ、と自分が老境に差し掛かるようになってやっと気づかされた。ほんとうに分かってもらいたいことは本の中に書いてあるはずがない。そう言いたかったのだろう。実家の祖母とは違って、昔語りや仏教的な教訓話などいっさいしなかった祖父は一人息子にも「本など読むな」と言葉をかけて育てたのだろうか。父を介して祖父の人となりを知る回路はあらかじめ閉ざされてしまっていた。(2024年1月21日記/22日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(16)祖父と同年生まれの人
能登はそもそも田んぼが沢山作れるようなバーンと開けた
地域じゃないから、平野部に比べたら、そういう意味では豊
かな土地ではない。
だからこそ自然状況とうまくやってく文化的手立てと精神
性が屹立して残っている土地なんだ。人のまとまり方、助け
合い方、人間が連綿とやってきた当たり前が活きているんだ
な。つまり無形の力が生きているってこと。
報道側の世界観とはそもそも違う。
地震によって有形の存在物が崩れたわけだけど、それって
取り返しのつかないことだっけ ? いやいや人間の内にある無
形の働きが潰れてなけりゃ大丈夫だろ。
きっと人間が生きてくのはいつの時代でも大変なんだ。全
面的な楽なんか訪れやしねえ。ただ、今の時代の大変さは人
間に潜む無形の力を潰しにかかるような人災的な勢力が強す
ぎるからだよ。
そんなご時世にせめて自分の手がとどく範囲は護りたい。
だからぼくは無形の力を応援する稽古をする。今日の研究稽
古は親指を能登半島に見立てたところからはじめていく。
モノとして空間設定に閉じ込められている身体感覚を、コ
トとして時間の流れに溶かしていく。自己と他者の狭間で自
ずと運動が起こるように関係を描き出す。
すると、自分が自身にしがみついて離れない癒着が剥がれ
るようだ。苦しくて、泣きそうで、2度、3度、諦めそうに
なるけど流れを捨てない。稽古仲間が寄り添ってくれている
からできること。
無形の力の働きを認めていくのは、「イメージ」でも「物
理性」でもない「経験」を宿して身体と世界を丈夫に結びつ
けていくことなんだ。
イメージで世界が変わるかよ。
物理性で身体が語りつくせるかよ。
生き物としての人間は無形の流れにいるときこそ輝くんだ
よ。
(笹井信吾@[旧Twitter改め]X)
[承前]そんなわけで一緒に暮らした覚えのない父の生年月日も[忘れ]知らず、同年生まれの有名人のことなど気にしたこともないのに、祖父が生まれた1879[明治12]年生まれの人が眼についたりすると、その人となりというより《読み書き表現》に関心を持たされるようなことがあった。
九州と北陸の読者が期せずして証言しているように、東京紙・大阪紙の地方進出が各都市で注目されている。大阪紙に関しては『大阪朝日』『大阪毎日』の二紙が代表的で、特に『大阪朝日』の進出が際立っており、その勢いを柏原の読者は「たゞ単に新聞とのみ云えば『大阪朝日』のことで、その勢力のすばらしさは、実に譬ふるにものなき有様であります」とまで表現している。他方、東京紙の中では、赤新聞と呼ばれた『万朝報』の購読者の増加が各地で指摘されている。新聞紙研究の教えるところによると、ちょうどこの明治三〇年代前半に東京紙は関東から甲信越・東北方面へ、大阪紙は近畿一円から中国・四国地方へ、さらには北九州へとその購読圏を拡大しつつあった。北陸・東海地方はちょうど両者のぶつかり合う前線地帯を形成していた。東京紙・大阪紙の地方進出がさらに本格化してくるのは日露戦争以後のことになるが、このように新聞の領域においてはすでに明治三〇年代前半から、東京・大阪を二つの〈中央〉とする楕円的構図が徐々に形成されつつあった。
(永嶺重敏『〈読書国民〉の誕生:明治30年代の活字メディアと読書文化』日本エデイタースクール出版部、2004年刊、5頁)
『大阪朝日』の創刊は1879[明治12]年1月25日だが、「裏日本」と呼ばれていた地域生まれの祖父が「新聞」と言えば1876[明治9]年2月20日創刊の『大阪毎日』以外の何物でもなかった。昭和になってから創刊された地元の『北日本新聞』や『富山新聞』は眼中になかったようで、和綴じ経典より字が細かい新聞活字をメガネなしで読んでいるのが不思議におもえた。
おそらく地元の尋常小学校を出てから大阪で丁稚奉公をしていた明治二十年代から三十年代にかけて『大阪毎日』を読む習慣が身についたように料理の腕を磨いた祖父の青少年期を想像するしかなかった。埴生の民家の囲炉裏を囲んで一家団欒なんてことにまるで縁のない暮し向きだったから。それでいて山仕事や農作業の手伝い以外で、大相撲の地方巡業や村の市や町中の祭礼などに連れていってくれた祖父の手の感触だけはしっかり残った。なぜか親戚だけでなく報恩講での声明の響きに目覚めたお寺詣りに導いてくれたのは同じく明治生まれの母方の実家の祖母だけだった。
夜間短大に通っていた1960年代半ばの三年間は休日しか祖父と顔をあわせることがなかったが、さすがに学問など必要ないとは言われなかった。三年生のゼミの卒業レポートでマルクス『賃労働と資本』の日本語版の書誌的変遷をたどっていて知ったのだが、当事本邦初訳者とされていた河上肇が祖父と同年生まれだった。著名な「貧乏物語」は1916[大正5]年の『大阪朝日』に連載されていたが、その頃37歳の祖父はとっくに年季明けで地元の埴生に戻ってなお『大阪毎日』の読者だったから眼にしたようなことはなかっただろう。
河上肇は1879[明治12]年、山口県玖珂郡岩国町(現在の岩国市)に旧岩国藩士の家に生まれで、祖母に溺愛されたようだ。そんな祖母と母についての渡辺京二の祖述[『小さきものの近代1』弦書房]が興味をひいた。
母はまだ肇が腹の中にいた頃に離縁され[二年後に出戻る]、生まれた肇は河上家に引き取られて祖母の手で育てられたようだ。母はその前に短いあいだ河上家に嫁いでいた女が産んだ子[肇の異母兄弟]を抱いて寝る始末となり、肇がなついて捜し求めるので祖母はゆっくり風呂にも入れなかったようだ。この祖母という女は母が最初に嫁入った頃は、若き燕と一緒に離れで暮らしていて、母が毎日酒肴を届けていたのだった。やがてその燕に似合いの女を見つけて結婚式にも立ち会い、そのうち肇が抱かれて寝ることもなくなると、近所の寡夫になっていた男を離れに引き込んで一緒に暮らして街中も二人して平気で闊歩したようだ。肇はまったく世間体というものを無視して押し強い世渡りをしたものだと語ったように、男に騙されて家を取られるようなこともなくしっかり96歳まで生き延びたという。
祖父が生まれた明治の初め頃には凄い生きざまの女がいたものだが、肇少年は男女関係に奔放な祖母に可愛がられながら、やがて文才を育み山口高等学校時代は国家主義的で詩人志望だったのが、いかなる契機で東京帝大法科に進み、その後《貧乏物語》を新聞連載後に本にし、1919[大正8]年にマルクス『賃労働と資本』の翻訳本の公刊に至ったのか。それとは別に河上肇自身の学生時代の女性関係はどうだったのか。
河上さんの義弟末川博氏はいう。「河上は学生時代‥‥‥転々と下宿をかわるんです。というのは、下宿の女中がサービスしてくれると、ええ気持ちになってあぶないという。自分で自粛しないといけないんで転々とかわった。」(『歴史と人物』一九七四年四月号、中央公論社、一〇四頁)
また友人の画家津田青風氏は、「河上さんはあんなに真面目な人だったから、下卑た話や女の話なんかはてんでしたことがなかった」といいつつ、あるとき河上夫人の口から「河上が下宿してた時の娘がたずねてきましてね、ちょっと困ったことがありましたっけ」と聞いたという(一九四八年世界評論社刊『回想の河上肇』一三七頁)。
これらは、必ずしも根拠のない話ではない。河上さん自身の文章「社会主義評論」(明治三八年(一九〇五年)執筆、全集三巻八〇頁)にいう。「大学を卒ふるまで、凡そ八九回の転居を為せり、‥‥‥回顧すれば余の恋せし女は大学に入りてより大学を出づるまで前後七人に及び、而して最後の恋に於て余は或る女と一夜〇〇〇〇〇〇(編集者白す、此処六字抹消す)至たりたり。」
この正直な告白をした河上さんは東大卒業の十余年後(大正四年、一九一五年)有名な「貧乏物語」とほぼ時を同じくして、「婦人問題雑話」と題する文章を書き、大阪朝日に連載する(全集九巻所収)。この論文は、今日の社会科学的観点からすれば、いろいろと問題があるようだが(巻末掲載の参考文献参照)、女性の問題を貧乏と並ぶ二大問題だとして、その解決を迫った視点は、当時にあってはきわめて進歩的なものであった。
(一海知義「七枚目のリトマス試験紙ーー河上肇と女性問題ーー/『漱石と河上肇:日本の二大漢詩人』藤原書店、1996年刊、118〜119頁)
わが身を振り返ってみても1960年代半ば頃は、やはり「貧乏」と「女」が未解決の問題であることに変わりはなかった。勤め先の地方大学図書館職員の男女比は半々ぐらいだったし、通っていた地方夜間短大の女は圧倒的に少数派なのに、都会の大学で受講した夏期司書講習の男女比は3対20で圧倒された。暑い盛りの2ヶ月間の休み時間の暇つぶしに、肩身の狭い男有志が嫁さん候補の品定めをしたことがあった。10人にひとりはやっていけそうな女がいるねというところに落ちついた。いずれにおいても男女間はおおらかで友好的であった。
貧しい母子家庭の来歴を承知の上で、地元地域や職場や関わった組織だけでなく、下宿でも必ずと言っていいほど舞い込む縁談にことかかなかった。田舎から郊外に移り住んだ1970年代半ばまでにそんな男女間の雰囲気も遠のいてしまった。頼まれて知人の結婚や知り合いの図書館就職のお世話をさせてもらったことはほんの僅かに過ぎない。
卒業レポート作成当時国立国会図書館本館まで出かけて行ったりして調べたのだが、河上肇訳『労働と資本』[初訳]京都、弘文堂書房、1919(大正8年)4月刊は、実のところマルクスの『賃労働と資本』(Lohnarbeit und Kpital)の本邦初訳ではなかったことが後になってわかったのだ。ゼミの恩師だったF原先生からの知らせで笹原潮風訳、賃金労働及び資本(一〜五、承前、承前)、木鐸3(5〜8/9、10/11、12/4(1〜2)、1909(明治42年3月15日〜明治42年12月25日の書誌データを追加した「卒業レポート」の改訂版を自作ホームページに掲載し、その旨を恩師に知らせるまでに数十年の時間を要してしまった。
文学と農民復興運動に心をくだきつつ宮澤賢治が病没した1933[昭和8]年に河上肇は検挙され、治安維持法違反で懲役5年の判決を受け、4年後の1937[昭和12]年の6月に出獄し、一言たりとも世に公表できない孤立の身を保つような『閑戸閑詠』[「河上肇全集 21」岩波書店]で日録風な漢詩と短歌にはさみこむ「小詩」を書き残している。
近頃頻りに疲労を覚え、やがて寝付くべきか
と思ふほどなり、小詩を賦して自ら慰む
弱いからだが段々に弱くなり、
残りの力もいよ/\乏しくなつて来た。
ちよつと人を尋ねても熱を出し、
書を書いても熱を出し、
絵を描いても熱を出し、
碁を打つても熱を出す。
私は私の生涯のすでに終りに近づきつゝあることを感じる。
やがて寝付くやうになるのかも知れない。
だが私は別に悲みもしない。
過去六十年の生涯において、
何の幸ぞ!
私はしたいと思ふこと、せねばならぬと思ふことを、
力相応、思ふ存分にやつて来て、
今は早や思ひ残すこともない。
私は自分の微力を歎じるよりも、むしろ
力一ぱい出し切つたことの滿足を感じてゐる。
「ご苦労であつた、もう休んでもよいよ」と
私は自分で自分をいたはる気持である。
牢獄を出て来た後の残生は、
謂はゞ私の生涯の附録だ、
無くてもよし、有つてもよし、
短くてもよし、長くてもまた強ひて差支はない。
私は今自分のからだを自然の敗頽に任せつつ、
衰眼朦朧として
ひとり世の推移のいみじさを楽む。
四月十三日
われ今死すとも悔なし
われ今死すとも悔なし。
懇ろに近親に感謝し、
厚く良友に感謝し、
普く天地に感謝し了へ、
晏如として我が生を終へなむ。
今われ老いて
幸に高臥自由の身となり、
こゝろに天眷の渥きを感ずること頻りに、
ひとりゐのしゞまには
しば/\かゝる思ひにひたる。
七月三十一日
時勢の急に押されて悪性の変質者盛んに
輩出す、憤慨の余り窃に一詩を賦す
言ふべくんば真実を語るべし、
言ふを得ざれば黙するに如かず。
腹にもなきことを
大声挙げて説教する宗教家たち。
眞理の前に叩頭する代りに、
権力者の脚下に拝跪する学者たち。
身を反動の陣営に置き、
ただ口先だけで、
進歩的に見ゆる意見を
吐き散らしてゐる文筆家たち。
これら滔々たる世間の軽薄児、
時流を趁うて趨ること
譬へば根なき水草の早瀬に浮ぶが如く、
権勢に阿附すること
譬へば蟻の甘きにつくが如し。
たとひ一時の便利身を守るに足るものありとも、
彼等必ずや死後尽く地獄に入りて極刑を受くべし。
言ふべくんば真実を語るべし、
真実の全貌を語るべし、
言ふを得ざれば黙するに如かず。
十月九日
ほかにも「六月下旬、東京保護観察所よりの来状に本づき、謂はゆる左翼文献に属する内外の図書、約六百四十冊を官に収め、身辺殊に寂寞、ただ陸放翁集あり、日夜繙いて倦まず、聊か自ら慰む」、「老いて菲才を歎く」、「福井君に寄す」、「夏日戯に作る」など《漢詩》や《短歌》を脱ぎ捨てたような「小詩」以外に「六月十九日夢/六月十九日夜、夢に、再び安逸の生活を脱せざるを得ざる必要に迫まられ、また家人と分れ、詩書とも分れざるを得ざるかと思ひ、心せつなく、如何にせば宜しからんと迷ひ居るうち、夢始めて醒め、暫くは果して夢なりしかと疑ふほどなりき」という〈夢見〉まで残している。
全体的には漢詩や短歌が圧倒的に多いのだが「風のまにまに/詩を読みをればおのづから詩は成り/歌見つつあればおのづから歌生まる/風のまにまに/興のまにまに/きそまたけふ」が「小詩」の姿勢になってもいる。高等学校時代に詩人の志しを断念し、やがて「マルクス主義活動」期をくぐり抜けたその後の紆余曲折を経た着地点を《詩》に見出したといえようか。
埴生の民家に住んでいた背戸の柿の木から堕ちて頑なに往診医を拒否し、老来の曲がり角みたいに寝込んでいて、ときどき家族を起こすみたいにああしろこうしろと言ってみたり、自らを養生していた祖父の體に去来していたであろうコトとかモノとかがわからなかった。休日の朝なのに早く起こされたりで不機嫌になったりしたこともあった。
捕まえた亀を入れて叱られたことのある手水鉢の水を替えておけとも言われたっけ。布団にくるまって農作業もできないのに「ボウフラ」の心配などと思う一方で、宮澤賢治の「蠕虫舞手[アンネリダタンツエーリン]」の語呂のいい呪文のような「8[エイト]γ[ガムマア]e[イー]6[スイツクス]α[アルフア]」の《文字映像》の響きが心地よかった。水中に垂れて上下する釣り針の先でのたうつ糸ミミズなども連想したり、川釣り少年の釣果を捌いて料理してくれた祖父の姿がちらついた。生粋の田舎生まれでなくとも、いっとき田んぼの生き物に夢中になったり、にわか昆虫少年や宇宙少年になったり、明滅する命のリズムに触れたようだ。
蠕虫舞手[アンネリダタンツエーリン]
(えゝ 水ゾルですよ
おぼろな寒天[アガア]の液ですよ)
日は黄金[きん]の薔薇
赤いちひさな蠕虫[ぜんちゆう]が
水とひかりをからだにまとひ
ひとりでをどりをやつてゐる
(えゝ 8[エイト]γ[ガムマア]e[イー]6[スイツクス]α[アルフア]
ことにもアラベスクの飾り文字)
羽むしの死骸
いちゐのかれ葉
真珠の泡に
ちぎれたこけの花軸など
(ナチラナトラのひいさまは
いまみづ底のみかげのうへに
黄いろなかげとおふたりで
せつかくをどつてゐられます
いゝえ けれども すぐでせう
まもなく浮いておいででせう)
赤い蠕虫舞手[アンネリダタンツエーリン]は
とがつた二つの耳をもち
燐光珊瑚の環節に
正しく飾る真珠のぼたん
くるりくるりと廻つてゐます
(えゝ 8[エイト]γ[ガムマア]e[イー]6[スイツクス]α[アルフア]
ことにもアラベスクの飾り文字)
背中きらきら燦[かがや]いて
ちからいつぱいまはりはするが
真珠もじつはまがひもの
ガラスどころか空気だま
(いゝえ それでも
エイト ガムマア イー スイツクス アルフア
ことにもアラベスクの飾り文字)
水晶体や鞏膜[きようまく]の
オペラグラスにのぞかれて
をどつてゐるといはれても
真珠の泡を苦にするのなら
おまへもさつぱりらくぢやない
それに日が雲に入つたし
わたしは石に座つてしびれが切れたし
水底の黒い木片は毛虫か海鼠[なまこ]のやうだしさ
それに第一おまへのかたちは見えないし
ほんとに溶けてしまつたのやら
それともみんなはじめから
おぼろに青い夢だやら
(いゝえ あすこにおいでです おいでです
ひいさま いらつしやいます
(えゝ 8[エイト]γ[ガムマア]e[イー]6[スイツクス]α[アルフア]
ことにもアラベスクの飾り文字)
ふん 水はおぼろで
ひかりは惑ひ
虫は エイト ガムマア イー スイツクス アルフア
ことにもアラベスクの飾り文字かい
ハツハツハ
(はい まつたくそれにちがひません
エイト ガムマア イー スイツクス アルフア
ことにもアラベスクの飾り文字)
(一九二二、五、二〇)
(宮澤賢治「真空溶媒」/『校本宮澤賢治全集 第2巻』筑摩書房、昭和51年刊)*[ ]内は原文のルビ=引用者注
しびれが切れるまで水たまりの御影石にに腰掛け、水中を上下する《一匹のボウフラ》の動きを観察するスケッチャーの自己問答がなぜか面白いのだ。自分の中にいる他人に見せるというより、もうひとりのほんとうの自分を納得させるような書き方が〈心象スケッチ〉の装飾文字として踊っている。そのリズムはラグタイム。
水中から空中にスケッチャーの視線を転じれば、「鳥はまた一つまみ 空からばら撒かれ」るリズムも「ラッグの音符ばら撒」きなのだ。
火薬と紙幣
萱の穂は赤くならび
雲はカシユガル産の苹果の果肉よりもつめたい
鳥は一ぺんに飛びあがつて
ラツグの音譜をばら撒きだ
古枕木を灼いてこさへた
黒い保線小屋の秋の中では
四面体聚形[しゆうけい]の一人の工夫が
米国風のブリキの缶で
たしかメリケン粉を捏[こ]ねてゐる
鳥はまた一つまみ 空からばら撒かれ
一ぺんつめたい雲の下で展開し
こんどは巧に引力の法則をつかつて
遠いギリヤークの電線にあつまる
赤い碍子のうへにゐる
そのきのどくなすゞめども
口笛を吹きまた新らしい濃い空気を吸へば
たれでもみんなきのどくになる
森はどれも群青に泣いてゐるし
松林なら地被もところどころ剥げて
酸性土壌ももう十月になつたのだ
私の着物もすつかり thread-bare
その陰影のなかから
逞ましい向ふの土方がくしやみをする
氷河が海にはひるやうに
白い雲のたくさんの流れは
枯れた野原に注いでゐる
だからわたくしのふだん決して見ない
小さな三角の前山なども
はつきり白く浮いてでる
栗の梢のモザイツクと
鉄葉細工[ぶりきざいく]のやなぎの葉
水のそばでは堅い黄いろなまるめろが
枝も裂けるまで実つてゐる
(こんどばら撒いてしまつたら……
ふん ちやうど四十雀のやうに)
雲が縮れてぎらぎら光るとき
大きな帽子をかぶつて
野原をおほびらにあるけたら
おれはそのほかにもうなんにもいらない
火薬も燐も大きな紙幣もほしくない
(一九二三、一〇、一〇)
たとえばスコット・ジョプリン[1867or1868〜1917]の「The Entertainer」[https://www.youtube.com/watch?v=Fxk9qwCFf8s]や「Maple Leaf Rag」[https://www.youtube.com/watch?v=s_nBSSXiG9w]など一連のラグタイム演奏をバックにいっそうせり上がってくる詩作品や童話がほかにもありはしないか。
宮澤賢治の音楽的背景としてだが、1922[大正11]年頃にはSPレコードや楽譜などで西欧のクラシック音楽だけでなく、19世紀末から20世紀にかけてアメリカで流行したラグタイムのリズムとシンコペーションに幻想的で多様な躍動感と生命力に溢れた魅力を感じとっていたといえそう。
郷土民謡なども滅多に口にすることのなかった祖父と同じ1879[明治12]年生まれの「水中」ならぬ「海中」の“ヒーロー”がいた。1910[明治43]年4月、広島湾での潜航演習訓練中の事故で10数名の乗組員とともに殉職した第六潜水艇佐久間勉艇長のことだ。この事故のニュースと沈みゆく艇内で死の直前まで書き綴られた「遺書」に心動かされた夏目漱石が『東京朝日新聞』において、1910[明治43]年7月19日付「文藝とヒロイック」、続けて翌20日付「艇長の遺書と中佐の詩」の二篇を発表している。『大阪毎日新聞』派だった祖父がリアルタイムで読んでいたかどうかはわからないが、佐久間勉は福井県三方郡の神職の家の生まれだったというから日本軍人としての背景もキャリアも当時としては異色だったのではないだろうか。
彼等[自然主義者=引用者注]にしてもし現實中に此行為を見出し得たるとき、彼等の憚りも彼等の恐れも一掃にして拭ひ去を得べきである。況や彼等の軽蔑をや虚偽呼はりをやである。余は近時潜航艇中に死せる佐久間艇長の遺書を讀んで、此ヒロイツクなる文字の、我等と時を同くする日本の軍人によって、器械的の社會の中に赫として一時に燃焼せられたるを喜ぶものである。自然派の諸君氏に、此文字の、今日の日本に於て猶眞個の生命のある事實の上に於て證拠立て得たるを賀するものである。彼等の脳中よりヒロイツクを描く事の憚りと恐れとを取り去って、随意に此方面に手を着けしむるの保證と安心とを與へ得たるを慶するものである。
(夏目漱石「文藝とヒロイツク」/『漱石全集 第十一巻 評論・雜篇』岩波書店、昭和50年刊)
其上艇長の書いた事には嘘を吐く必要のない事實が多い。艇が何度の角度で沈んだ、ガソリンが室内に充ちた、チェインが切れた、電燈が消えた。此等の現象に自己廣告は平時と雖も無益である。従って彼は艇長としての報告を作らんがために、凡ての苦悶を忍んだので、他[ひと=ルビ]によく思はれるがために、徒らな言句を連ねたのではないと云う結論に歸着する。又其報告が實際當局者の参考になった効果から見ても、彼は自分のために書き残したのではなくて他の爲に苦痛に堪へたと云ふ證拠さへ立つ。
(夏目漱石「艇長の遺書と中佐の詩」/『漱石全集 第十一巻 評論・雜篇』岩波書店、昭和50年刊)
これらを書きながら「病院生活をして約一ヶ月になる」漱石は、「さうして重荷を擔ふて遠きを行く獣類と選ぶ所なき現代的の人間にも、亦此種不可思議の行為があると云ふ事を知る必要がある。自然派の作物は狭い文壇の中にさへ通用すれば差支ないと云ふ自殺的態度を取らぬ限りは、彼等と雖も亦自然派のみに専領されてゐない廣い世界を知らなければならない。」[前掲書]と「文藝とヒロイック」を結んでいるが、ほんとうのヒーローは決して歴史の表街道や再生した古民家などから垣間みることすらできはしないだろう。
明治・大正・昭和を生きた祖父や実家の祖母と一緒に過ごした時間のなかのどこを探せば混沌とした《明治維新》の翳りなどを嗅ぎとることが出来たのだろうか。二人が過ごした民家のどの部屋にも「軍人」や「天皇陛下」の額が掲げられてはいなかった。(2024年2月11日紀/13日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(17)座興と音楽療法
「道路がわれわれの故郷を改造した力は、大き
すぎるというほどに大きかった。古い話だから
ただ簡単に述べておくが、官道すなわち国普請
の往還というものは、これを開鑿[かいさく]
するばかりが行政庁の事業ではなかった。必ず
その両側に若干の間隔をもって、これを管理す
る民家を配置しなければならなかった。これが
前代の公式の駅逓[えきてい]法であったので
ある。最初は地子[ちし]の免除と人馬の賦役
とがちょうど向き合いになって、いくぶんか住
民に有利であったのが、後には二者は関係のな
いものになって、馬の徴発ばかり繁く、さらに
助郷までにその迷惑は及んだのであった。だか
ら以前改めて新道を附け変えるということは、
並木を惜しまずとも実際はできることでなかっ
たのである。」
(柳田國男『明治大正史 世相篇(上)(講談社
学術文庫)171〜172頁)
丁稚奉公のためいったん生まれ故郷の松永を離れ、大阪という〈世間〉に出てしまった祖父の故郷感はいかなる変貌を遂げていったかについては知る由もない。ただ年季明けで出生地の松永より多少町寄りの埴生に住み着いたのは、「弱い小さな部落の独立を止めさせようという方針」[前掲書170頁]が全国いっせいに実行された、1888[明治21]年の新町村の結合という事態をへてのことであったろう。なにせ「いつからあるとも知れぬ十七万幾千の村と町とを、大まかに一万二千ほどに縮めてしまった」[同前]というから。
大阪での都市生活の心細さを振り返ったり、新しく埴生で始めた村生活の清しさにひたったりする余裕などなく、とにかく裸一貫から身過ぎ世過ぎ、ひたすらなりわいに邁進するしかなかったであろう。母方の実家に比べておおよそゆとりとか余裕というか遊び心の薄い祭りの座興の差、子供心にその隔たりを楽しんでもいた。祖父が松永の実家の祭りに家族の誰一人として連れて行かず、母方の実家の祭りにも決して加わらなかった理由にうすうす気づくような年頃になるとある侘しさも感じていた。
大正〜昭和期の邦楽にはどのような興味を抱いていたのかがよくわからない宮澤賢治だが、郷土芸能を愉しんだように祭りにも関心を寄せていたのだろうか。
毎年母子三人で出かけた高儀の実家の祭りの座興は面白かった。叔父さんを軸に芸達者が競って愉しませてくれた。幼い頃に実家の手回し蓄音機で掛けまくって聴いたSP盤の響きが、端唄か小唄か都々逸かも聴き分けられなかったのに、それらが祭りの余興として実際に演じられていたのだ。化粧した女形の踊りや、“ひょっとこ”仮面のどじょうすくい[後に「安来節」と知った]だけでなく浪花節までなんでもありの座興に時間の経つのも忘れていた。就職してから一つぐらい覚えて宴席の座興に供したいともおもったが、浪曲の真似事が関の山で諦めてしまった。
江戸期の芸能の一端が昭和の民家の村祭りの御座敷芸として永らえていたわけだが、祖父の生まれ年の1879[明治12]に文部省・音楽取調掛が設立されていたとは知らなかった。母方の祭りの列席者の中にはピアノなど楽器店経営者の家族もいたはすなのに、その場の座興に明治・大正期の洋楽の何一つとして演じられたことはなかった。
明治初期の音楽制作における最重要人物は、文部省・音楽取調掛の初代長官、伊沢修二[1851-1917]である。彼はアメリカ留学後、彼の地で学んだ「唱歌」教育法を輸入して、日本のドレミ音楽教育を定礎した人間として知られている。音楽取調掛の設立は一八七九年、『小学唱歌集』刊行のスタートは一八八一年、ということで、彼が活動を始めた時期はちょうどぴったりニューバージョン《君が代》の誕生と重なっているんですね。なので、当然、二代目の制作にも伊沢らは関与している‥‥‥かと思いきやそうではなくて、伊沢の名前は《君が代》のエピソードにはまったく出てこない。「唱歌」と「国歌」はどちらも国家主導の「明治のあたらしい歌」であるが、実はその作り手の主体はそれぞれ違っていて、「唱歌」は文部省が、そして「国歌」は宮内省と海軍省によって作られた歌なのである。
[中略ー吉田注]
というわけで、音楽取調掛=文部省が活動を始める前から、軍楽隊と雅楽者のタッグによって省庁主導のニューミュージックの試行はすでに行われていたのである。唱歌に関しても先行は宮内省で、彼らは一八七八年に「保育唱歌」と題した教育用の音楽の作曲を試み、また、一八七九年には《君が代》の歌詞をそのまま使った《サザレイシ》という歌もリリースしている。「国歌の改訂作業」もこのライン上にあった、というわけだ。
(大谷能生『歌というフィクション』月曜社、2023年刊、169〜170頁)
埴生小学校に上がるまではもっぱら母の口から「唱歌」だけでなく「軍歌」まで教わったというか、よく一緒に歌ったりしていた。時には二歳上の姉も加わったが、祖父とは無縁だった。たぶん「尋常小学校唱歌」の幾つかは習い覚えさせられていたであろうに。とにかく「文部省唱歌」と「尋常小学校唱歌」の区別も知らずに母子で唱和するのが子供心に音楽の授業よりも開放的で面白かった。「赤とんぼ」、「われは海の子」、「ふるさと」、「蘇州夜曲」、「大きな古時計」、「夏はきぬ」、「朧月夜」、「紅葉」、「故郷」、それに「琵琶湖周航の歌」などである。
「軍歌」にはさほど馴染めなかったが、アイ・ジョージの歌う「戦友」の背伸びするようなリズムや、美空ひばりの「戦友」の横へ超えゆくようなリズムに聴き惚れた。そんな行進的リズの対偶で聴いたのが「船頭小唄」のたゆたうように停滞するリズムであった。
長じて母の好みの歌い手の歌謡曲のLPを一緒に聴いたりするようになっていたが、十代の終わり頃に目覚めた“ジャズ”には家族の誰一人として関心を示さなかった。
私事だが自分の音楽的ルーツを振り返させられる出来事があった。猛暑だった昨夏に妻を亡くし、娘の言によれば「父はショックで葬式躁になり、警察沙汰で、精神科に医療保護入院していました。」とのことなのだが、入院当初の前後数日間の記憶が飛んでしまっていて未だによく思い出せないのだ。気づいたら「保護室」とは名ばかり、映画によく出てくるベッドとむきだしの便器しかない“独居房”みたいな部屋で高い窓をぼんやり見上げていた。今になって思い返せば、たとえば実家の祖母口伝の「明日ありと思うこころの徒桜夜半に嵐の吹かぬものかは」[親鸞?]の心境だったような気もする。
実家の祖母だけでなく母や祖父からも習い覚えた「巳は皆んな、已に半ば、己は下に」が浮かんだかと思うと、唐突に《病院は監獄の始まり》[M.フーコー?]に突き動かされたり、食事もろくに喉をを通らないながらも数日で相部屋に移された。同室の男は元ボクサーのパンチドランカーみたいな患者で夜昼問わずシャドウボクシングのリズムで院内廊下のロードワークに明け暮れていた。
そうこうするうち“デイルーム”で何かと寄り添うように言葉を交わすようになった先輩格のH田氏とのご縁に恵まれ、とにかく“快食・快眠・快便”を目指そうとする自分を見出せたようだ。欠かさず参加した平日の午前と午後の1時間のOT[Optional Therapy]の最初の「音楽鑑賞」で“場違い”を気にしながらもリクエストしたテディ・ウィルソン楽団の“ブルース・イン・Cシャープ・マイナー”が心身に染みるように響いてきたのには我ながら驚いた。
次回の「音楽観賞」でたまたま隣りあわせたT内女史が当方のリクエスト曲に関心を持たれたようでご縁が生じ、H田氏退院後の会話を豊かなものしていただいたのだが、とりわけ夫婦ともども抑鬱的で老々介護状態だった妻の自死に、気づきもしていなかった深い言葉を寄せられたのにはただただ癒やされ、もがき苦しんだ深い闇から救いだされる想いがした。20人のスタッフで100人余りの患者の世話をする隔離病棟でよもやあのような言葉に出会えるとは何とした事だろう。実のところ入院に至る前に日ごろの僕ら夫婦の暮らしぶりに長きにわたって接してこられたK岡女史からも、実生活面から踏み込みこんだ言葉をかけてもらって救われていたのだが、平静を装いながらも内心取り乱していてさっぱり気づけなかったのだ。また退院後に知ったのだが、娘が喪主入院で四十九日法要の会席をキャンセルするために事情を話した長い付き合いのある店主の短い一言も、又聞きとはいえホッとするほどありがたかった。
邦楽のキャリアもおありのようだったT内女史が茨木のり子のアンソロジー詩集を置き土産に早々と退院された後、OTの「音楽療法」が新鮮に響いてしょうがなかった。明治・大正期に作られた西欧的な唱歌だけでなく、大正期の口語的な童謡など、リクリエーション室で模造紙に手書きされた歌詞を、キーボードの伴奏付きで唱和するだけだったのに、なぜか落涙しそうなくらい體が緩みながらも整うというか、これまでのジャズライブ体験とは一味も二味も違う出来事になった。
ネットワーク接続ノートPCとヘッドホンで「ユーチューブ」のジャズ&ブルースを聴き放題にさせてもらったリクリエーション室でのOTをはじめ、コロナ禍ですべての週間スケジュールが取りやめになった時など、もっぱらM病院四階隔離病棟廊下からの窓景色を便箋の裏に鉛筆スケッチするようにしていた。暗くなると借り物の鉛筆で何か書こうと試みたりしたが何もまとまらなかった。
二百数歩で行き来できた四階直線廊下の東の端の窓からは若かりしころに縦走した北アルプスの稜線が懐かしく聳えて見え、西の端の窓からは能登半島に囲まれた富山湾が一望できた。その手前左湾沿いに亡妻とサイクリングや地鉄電車で何度か訪れたことのある“ミラージュランド”の観覧車や水族館が郷愁を誘い、左手湾沿いの直円錐屋根の「日本カーバイト」の建物が「敗戦の日の吉本さんの勤労動員先」だったことを思い起こさせ、と同時に自分がこうして〈いま・ここ〉に立ち至った経緯が偶然なの必然なのか立ち迷ってもいた。たまたま心神喪失状態に陥った時の緊急当番病院の収容先が魚津市の当病院で良かったというか、少しづつ正気がもどるにつれ生じたりする不都合などで自宅に近い富山市内の病院への転院など、治るものも直せなくなるような気がするのだった。
四階病棟内直線廊下を迂回する南側廊下一面ガラス張りの眺めも終日飽きることがなかった。夜の帳が下りるころ、ここにワインバーがあればいいのにと囁いて母と暮らす実家へ戻られたT内女史とM病院に隣接するN川ホーム住まいに移られたH田氏に娘夫婦を交えて近所のM寿司で“退院祝い”なる約束事もまだ果たせていないが、退院時に持ち帰った中の一枚のゆる〜く傾斜した山と海にはさまれた扇状地に立ち並ぶ甍の眺めのスケッチを予定実行メモのように自宅の壁に掛けておいた。そんなことでもしないと先の見通しが立たなかったのだろうか。
高すぎて窓がのぞけなかった保護室から相部屋に移された時には、その病室の北向きの窓の眺めにギョッとした。目の粗い格子状のコンクリートブロックが張りめぐらされ、横並びの病室の窓にあたる部分がそれぞれ矩形にくり抜かれた“塀の内”を感じさせる設計に視線を半ば遮断されたのだ。数センチほど開閉できるようにしてある四階病室の窓の隙間がかろうじて下界を感じさせた。噂によれば古いビルを病院にリフォームしたとのことだったが、古民家に残る〈格子〉の佇まいをめぐる趣や風情も知らない建築屋が手掛けたのだろうか。
何がどのように正常か異常かの境界も判然としない“コロニー”内にそれとなく張りめぐらされた監視の眼、日頃の医師やスタッフの応対をないがしろにするようなカメラ視線が、見られている〈身体観〉をよりささくれ立ったものにしてくれたようだ。夕闇迫る食事前の“ディルーム”の内景が両側の窓ガラスにくまなく映し出されるようにしてある仕組みとその情景がまるであの世の入り口に臨んでいるように感じさせられたことが何度もあった。
一人の人間の魂がぜったいに相手の魂と出会うことはないようにつくられているこの世、言葉という言葉が自分の何ものも表現せず、相手に何ものも伝えずに消えて行くこの世、自分がどこかでそれと剥離していて、とうていその中にふさわしい居場所などありそうもないこの世、幼女の眼に映ったのはそういう世界なのだ。
(渡辺京二『もうひとつのこの世ーー石牟礼道子の宇宙』弦書房、2013年刊)
入院早々に娘が差し入れてくれた翻訳「自己啓発本」の言葉がなかなか我が身に馴染もうとしなかったのに、なぜかT内女史に借りた非世間的な「詩の言葉」だと何度でもすんなり読めるのだった。S井主治医の初診時の予定より一ヶ月も早く退院できた今にして思えば、入院などしたことのない祖父にとっては、称名を唱えることによって世間を相対化して生きたというより、浄土真宗を信じることがこの世を渡ることになっていたのではないだろうか。
退院間近を見計らってお世話になった挨拶をしたら「お会いできて嬉しかったです」と返された I 城係員と、当方の「退院の喜びよう」がイマイチ足りないネと云われたS井先生に病院玄関の外まで見送られ、娘夫婦の車でM病院を後にしたときの我が身のあてどなさがどこか中学生の頃の“身体/存在の不思議”に目覚めた〈身体観〉に通底するようだった。
なぜこの人の顔立ちにそれほど引きつけられたのか。答えはあきらか。〈わたし〉という存在とその身体とのあいだが整合せずに、いつもぎしぎし軋みあっていたからである。わたしのなかには隙間とか亀裂みたいなものが走っていて、わたしが一箇の身体としてここにあるということがひどく心地悪いこととしてあった。それは七十をとうに超えた今も、ほんとうに変わっていない。
(鷲田清一「ひきずり、もてあまして」/『文學界』、78(3)、令和6年3月号、48頁)
「あるロマンポルノ女優」を引き合いにして語られた身体感というより、身体観といったほうがよさそうに思うが、人は他者に会うように自分に出会えない軋みみたいなものを生涯引きずらざるを得ないのだろうか。
入院当時の病棟内の喧騒が潮を引くように切り替わったほぼ2ヶ月ぶりの静まり返った我が家。父の法要に、祖父と母と妻の葬式を経てきた築五十数年の時間が流れる住み慣れた家屋と庭の感触に“妻の不在”が際立ってくる。どこを何をどう探ろうとも、見事なほどに何の痕跡も残さず逝ってしまった。いつものように二人分の食事を用意し、ワインボトルにグラス二脚を添えた食卓がせめてもの精一杯の最後の挨拶だったのだろうか。
数年前の秋の午前の買い物帰りに自転車で転んで利き腕の左鎖骨を折って以来というもの、それまで当たり前だったすべてが徐々にそうでは無くなってきた生活上のさまざまな身体的不如意。とりわけ大好きだった料理と食べることが痩せ細ってしまい、家事を引き受けながらもっぱら味わうだけの相方の自分まで食が進まなくなってしまった。コロナ禍もなんとかやり過ごすように二人で買い物をし、週一の外食も細々とこなし、図書館ならびに近所のかかりつけ医通いも絶やすことはなかったのだが。
銀行勤めを辞めたときは、それまで生活の一部みたいに二人で聴き漁った数千枚におよぶジャジズレコードのカード目録をすべてタイプし終えたり、日々相方が管理・運用するHPの朝一の読者兼アップロード原稿の校正もやってのけた。漱石の『門』』に出てくる「宗助」と「御米」夫婦がいいと言ってみたり、アップロード前の校正を省いていた「十字路で立ち話」を欠かさず読んでいたらしく、書き間違いを指摘するだけでなく「ここんとこは絶対に私にしかわからないというか通じないよ」と自信ありげだった。「拙文」をWeb公開することなど、妻に読まれるのも恥ずかしい自分はいつも素知らぬ顔を決め込んでいた。
数週間前、リスニングルームのLED電球を取り替えた際に動かしたソファーの後ろに隠れていた引き出しの亡妻が仕舞い忘れた手帳にメモ書きが挟まれていた。
[九十九折]
やりようもなく
途絶えてしまう
不意の死の訪れ
掃除ロボットや
PCのOSならば
アップグレード
どうしようなく
もがきつづける
日々の繰り返し
使い古す老体が
向き合う介護に
悔悟や達成なく
乳胎児期を経て
屈折した青春を
埋葬できようか
伴走しようにも
ゴールなど無く
寄り添うだけに
二〇一五年二月二四日
書き忘れたみたいな『十字路で立ち話(あるいはワッツニュー)』の自作が丁寧に書きとってあった。「メモ」にして年を改めるたびに「手帳」の栞のように引き継がれていたのだ。どんな人間関係にあろうとも決してお互いに覗き込むことも共有することもない底知れない深淵があるのではないか。だからこそいっそう寄り添おうとして第三者を寄せつけないような閉ざされた極面や修羅場を生きざるを得なくなったりする。お互い恵まれなかった家庭のことなど何処にでもあったであろう相対的な事情に相違なかった。しかしそれぞれの家族を構成するひとりひとりの生き様がどのようであったとしても、それぞれにとってかけがえがないほどに重たかったり尊いものとなったりするであろう。
自分のHPに掲載している文章など間違っても本当の読者に出会えるような代物ではないが、この時だけはかけがえのない“ひとりの読者”でもあったような気がしてならなかった。結婚するまでには日本だけでなく、ロシアやヨーロッパの名作や古典を読んでいたから、相方が文才など持ち合わせていない事などとっくに見抜かれていたであろう。同人誌に関わったりしていた頃にやさしく「決して“小説”を書いたりしないでね、できたら“出世”などもしないでね」と念を押されたことがあった。
お互い会うたびに話したりなくて一緒になったようなものだったが、娘が母から聞いたところによれば「俺の子供を産んでくれ」が決め台詞だったという。またよくぞこんな自分を選んでくれたと感謝していたが、娘には「きつい三角恋愛関係の中で選んでもらえて‥‥‥」と嬉しそうに話していたようだ。なるほど時々思い出したように「あの女[ひと]はその後どうしているだろう」と消息を案じていた。自分は亡妻と一緒になるにあたって一つだけ覚悟していた。家族と諍いになったら何が何でも妻の味方をして、どうしようもない時は二人で家を出ればいい。
ここまで書いて来て、私を育ててくれたのは、これまで出会った人々だったのだと、また繰り返したくなった。私は女の人のことを書かなかった。女の人は男以上に私を鍛えてくれたのかもしれない。でもこの文章では最初から、女性のことは書かぬ方針だった。女は私にとって、友というのとはちょっと違う存在のようだった。たとえ友だちだとしても、男友だちと女友だちはずいぶん違うもののような気がする。
(渡辺京二「ひと[原文傍点あり]と逢う」/『父母[ちちはは=原文ルビ]の記』平凡社、2016年刊、149〜150頁)
ずいぶん〈女運〉がよかった男の発言のようにも聞こえるが、とにかく居合わせる[た]ことがお互いにとって稀有のことになって暮らせたら何も言うことはないのだ。
M病院入院中も退院後のクリニックでも自身の今後の暮らし向き、金銭的な裏付けと日々何をどのようにしてきた[いく]かについても具体的に事細かく尋ねられた。主に午前中はHP作業に当ててきた[いく]ことなども話したら、その内容についても訊かれたりした。簡単に『高屋敷の十字路』だけでなく『隆明網』や『猫々堂』などサブページのことなども話したが、手伝ってくれていた亡妻のことには触れなかった。H田氏やT内女史との会話の中であれこれ話しあえたことの方がなんだか想定外のカウンセリングみたいな開放感があった。退院前夜に今後の生活項目などのアンケートの聞き取り担当だったMK保係員から最後に「入院当夜に立ち会っていたのわかっておられましたか」と確かめられ、まったく身に覚えがないことばかりだが、しでかしてしまったことの恥ずかしさだけが繰り返しよみがえる心地がして何にも言えなかった。(2024年3月8日記/11日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(18)吉本〈老体論〉拾い読み
「ある場所にあって生きているということは、
自分の重さと、自分の力と、自分の身体の重さ
に対応した力しかもっていないばあいには病の
概念はあてはまらなくて済むわけでしょう。多
少とも重力以上の力がかかる場所にいれば、い
いかえれば地面以外の場所に観念がおかれてい
たら、急速か徐々かっていうちがいはあるけど、
かならず病気の問題と関連してきます。心臓病
であるか、糖尿病であるのか、胃の病気だとか、
癌だとか、かならず成人病として出てくるみた
いな、ある場所がある。精神的な病としても、
肉体的な病としてもそれは出てくるということ
がいえるんじゃないでしょうか。それがきっと
成人病、老人病の問題のような気がしますね。」
(吉本隆明「ハイ・エディプス論(下)」/『吉
本隆明資料集191』57頁)
[承前]ちなみにM病院で問診やカウンセリングをされた医師やスタッフに「吉本隆明」をご存知の方はなく、没後10年以上過ぎた時の流れを感じさせられたが、なんと退院後に通うことになった心療内科の医師お二人とも「名前」だけでなく過去に「著作」などもよまれたことがおありのようだった。
現在の日本の医療現場でどのような〈老体論〉のレベルに基づいた老人医療が繰り広げらているのか、いたずらに馬齢を重ねてきたにすぎない一介のにわか独居老人には皆目見当もつかない。
自分にははっきりした覚えがない「入院当夜の有り様」をつぶさに観て取られたであろうMK保係員から退院前夜の「聞き取り」で開口一番、「こんなところに長いこと居られてなんの社会勉強にもならなかったでしょうが‥‥‥」と挨拶され、なんとも返しようがなかった。かろうじて小さな声で「いえいえいろいろ考えせられたようで」のあとが続かなかった。退院予定が決まるまでは、入院患者の家族関係を象徴するような「面会機会」の少なさなどいろいろ考えさせられたりしていたのに、“明日”からいきなり独居暮らしに切り替えられるかどうかが気になってそれどころじゃなかったのだ。
何回かのカウンセリングで、よくわからないけどHPの維持・管理みたいな面倒臭いことを?‥‥‥なんて顔をされたこともなかったとはいえないが、誰しも生きざるを得ない〈現実〉と切り結ぶような〈表現〉を持続してきた書き手の著作書誌を作成するだけでも面白いというか、仕事としての図書館での目録作成とは比べものにならないくらい我が身について考えることの対象化作用を滞らせないような刺激ともなるのだ。
たとえば『吉本隆明資料集1〜191集』の刊行を追いかけながら収録著作の書誌作成&Web公開をやってきて見え隠れする〈ヒトの生まれてから死ぬまで〉への〈身体的〉な“こだわり”とそれへの吉本さんの言及姿勢を公開時の年齢にそうようにたどってみると、〈あのとき・あそこで〉口ごもってしまった〈社会勉強〉になったかならないかを左右するような事柄がつぎつぎとみえてくるようだ。
(1)▼資料集148:「思想としての身体」日本医科大学 第12回千駄木祭1969年10月29日講演[著者44歳]
(2)▼資料集56:「身体論」 I〜VII@『試行』第30〜36号1970〜72年[著者45〜47歳]
「人間の個体が描く生誕から死への生命活動の曲線を、人間はなによりも〈手〉の働きによって超えようとする。これは、たんに歴史を文字に刻み、文字や音楽や美術の作品を刻みこみ幾世代にわたって保存させるという意味でいうのではない。環界を〈技術〉化して、たんなる天然の〈物〉を整序された〈物〉へと構築するとき、この構築物が経済的なあるいは社会的な範疇で〈生産物〉あるいは〈商品〉とよばれるとしても、この構築作用の働きそのものは〈時間〉の拡大と構築自体を意味しているようにみえる。それは外化された〈了解〉であり、いずれにせよ個体の生涯が限る〈時間〉を超えようとする作用に根ざしている。〈手〉がつくりあげるのは物質的であっても観念的であっても〈了解可能〉あるいは〈了解期望〉の系であって、このことは、結果的につくられたものがどのカテゴリーで解釈されるかということとは、一応別問題であるといっていい。いまこの問題をつきつめるまえに〈足〉とはなんであるかについて触れておくべきであろう。
〈手〉の作用からすぐに連想されることは、〈足〉が〈身体〉に則した〈空間〉の限度を意味するということである。〈足〉についても〈手〉のばあいとおなじように〈かもしかのような足〉とか〈ふっくらとした足〉とかいう感性的な比喩をあたえることができる。このばあい〈足〉の比喩は観念作用の比喩ではあっても、知覚のほかの概念をあたえることができないことに気づく。たとえば、〈恐縮〉しているさまを〈もみ手〉をしているということはできても〈もみ足〉をしているということはできない。〈手〉を擦り〈足〉を擦るという表現は〈蠅〉についていわれるだけである。それは〈足〉が〈空間〉の拡大と構築の働きに特異性をもっているためであるようにみえる。〈足〉に観念の作用をおわせても、感性的にしかおわせることができないのだ。」(66頁)
(3)▼資料集71:《「詩人にとっての〈身体の思想〉》「現代詩の思想」『別冊無限 無限ポエトリー』第7号1980年1月10日発行[著者55歳]
(4)▼資料集148:「身体論をめぐって」紀伊国屋ホール1985年10月18日講演[著者60歳]
(5)▼資料集23:「ことばへ・身体へ・世界へ」1985.1.29『現代詩手帖』1985年3月号)[著者60歳]
「僕はあなたほど持ち駒はないけれど、いつか、あんまり老いぼれないうちにからだをきたえてね、二十四時間講演というのを一度やってみたいんだ。体力もいるしさ、そう簡単にはできないんだけれども、ジョギングなんかしてきたえておいてね。二十四時間、自分の持ち駒を全部出して、一度やってやろうという思いはありますね。まもうかるかどうかはわかんないですけど。」(50頁)
[(6)1987(昭和62)年9月12〜13日[今、吉本隆明25時]東京品川の寺田倉庫で行われた24時間連続講演と討論集会[著者62歳]]
(7)▼資料集93:「心と身体の物語」『教育と医学』1987年10月号[著者62歳]
(8)▼資料集186:「身体のイメージについて」1990年9月6日「アイコンとしての身体」における発言[著者65歳]
(9)▼資料集126:〈身体生理と言葉〉「言語と経済をめぐる価値増殖・価値表現の転移(1994年10月14日)『iichiko』第39号1996年4月20日発行[著者69歳]
(10)▼資料集126:〈落合「野茂評価」の見識〉「私の野茂茂雄論」『正論』1995年11月号[著者69歳]
(11)▼資料集137:〈自分の身体への関心〉「日本の小説が変わる」[石黒達昌氏との対談]『本の旅人』1995年12月号[著者70歳]
(12)▼資料集156:〈階段を下るように身体が弱くなる〉「老い、障害、呆け、死とは?」[聞き手 大高智子]『オンライン ブックストア』2001年7月9日[著者76歳]
(13)▼資料集180:「現代スポーツとテロリズムに見る玄人性と素人性:現在への発言」[聞き手 山本哲士2001年11月15日]『吉本隆明が語る戦後55年』第8巻2002年5月31日発行[著者76歳]
(14)▼資料集182:「家族・老人・男女・同性愛をめぐって:現在への発言」[聞き手 内田隆三・山本哲士 2002年10月7日]『吉本隆明が語る戦後55年』第10巻2003年3月10日発行[著者77歳]
(15)▼資料集166:「移行する身体ー歌や言葉のことー」[森茂哉氏との対談]『舞台評論』第3号2006年6月30日発行[著者81歳]
(16)▼資料集168:現代の「老い」:漂流する風景の中で[著者81歳]
「年をとるとなにが一番つらいか。
それは、自己の意思と、現実に自分の体を動かすことができる運動性との間の乖離が、健康な人には想像ができないぐらいに広がるということだ。思っていることや考えていること、感じているここと、実際に体を使ってできることの距離が非常に大きくなる。
そんな老人を前にすると、ともすれば医者は「この人は返事だけはいいけれどこちらの指示したことはやろうとしない。少しぼけてきたな。」と思い込んだりする。
ところが運動性において劣るというのは、例えばアルツハイマーになったりするというのとはまったく違う。自分の気持ちは少しも鈍くなってはいない。それどころかある意味ではより繊細になって、相手の細かい言葉にいちいち打撃を受けているのに、そのことを表す体の動きは鈍くなっているという矛盾、そしてそれを理解されないジレンマ。その点に絶望している老人が多く存在するという現実を、医師や看護師、介護士はどの程度知っているのだろうか。
そんな老人を表現する際、僕は、老人たちを励ます意味も込めて「超人間」と呼んではどうかと考えている。
動物は、目に見えた何らかの変化にすぐに反射的に行動を起こす。これに対し人間は、感覚的に知覚したことと、行動との間に時間的距離があるのが特徴だ。となると、老人という存在はその時間的距離をもう少し大きくした「人間以上の存在」なのだから、それは「超人間」だ、と。
人類の歴史には、政治や社会にまつわる問題が属する「大きな歴史」と、個々人の身体や精神の問題を扱う「小さな歴史」がある。そして「超人間」を含めた小さな歴史の中に人類史の問題が全部含まれている。大きな歴史だけを「歴史」と考えるのは不十分だ。」(73〜74頁)(聞き手 松本一弥@『朝日新聞』2006年9月19日)
「振り返れば、こうした政治や社会の問題については自分なりに考えてきたつもりだったが、老人が直面する問題はやっぱり老人になるまでわからなかった。いい年をしていろいろな目にあって、ようやくそれが見えてきた。
「もう一個違う系列の問題があった。」そう新鮮に感じながら僕は日々を送っている。」(75〜76頁)[同前]
(17)▼資料集168:老い見つめ未踏を思索:吉本隆明 大病からの復活[著者81歳]
「発達心理学では身体の運動機能が向上していく青年期までについては、人間の精神の成長を論じていますが、壮年期から老年期、つまり身体の運動性が衰えていく時期の精神の活動については扱おうとしない。それなら自分が老年期まで伸ばしてやってみよう、という考えです。今は、それをやっておく必要があると思っています。」(90頁)(聞き手 宮川匡司@『日本経済新聞』2006年7月18日)
「それ[八十歳を超えて自らを追いつめるように原理的な仕事を続けること=引用者注]は、食っていかなければいけませんから。それに、現代は流れる時間の速さが違う。谷崎潤一郎や川端康成や志賀直哉といった古典時代の鬱然たる大家のような生き方は、高度に産業が発達した現代の物書きには、もう無理なのではないか」(91頁)[同前]
(18)▼資料集169:〈身体に詰まった歴史〉「〈心的なものの根源へ〉ーー『心的現象論』の刊行を機に」[聞き手 山本哲士・高橋純一]『週刊読書人』2007年6月15日号[著者82歳]
「『奥の細道』の終わりの方に、「暑き日を海に入れたり最上川」という句があります。それを読んでいると、太陽が海に沈んだ時に水が蒸発してジューっと音がするみたいな、そういうところまで彷彿させる。「海に入れたり」でなくても、『海に入れり」とか「海に沈めり」とか、表現の仕方はいろいろあるわけですが、最上川が夏の暑い夕陽を自分の体の中に入れたというい意味に取れるような表現をしている。芭蕉のいい句は必ずそうなっています。」(57頁)
「人間の身体というのはそれぞれ個人でみんな違うわけですが、人類史を身体で見れば、誰でも身体に人類の全歴史を孕んでいるわけです。それは普遍的なものです。今は後進国であるとか先進国であるとか言っていますが、それぞれの身体はチンパンジーの時から同じ年数を経ている。習慣とか風俗とか気候・天候とか、そういうのが違ってしまったから、今でこそ未開の社会と文明の社会とが分かれていますが、一人ひとり取ってくればみんなお同じだけの歴史が身体の中に詰まっている。これが普遍性ですよ。」(58頁)
要介護状態にあった家族の手触りから足触りまでが、ヒトの手・足の〈了解〉の時間性や空間的な〈関係〉として蘇ってきそうな読みごたえに浸ってばかりもいられない。詳しくはないのだがここ十数年、武術(道)界でも数人の探求者による武道の考古学的な見直しが深いところで進められているのではないか。
昨秋のM病院入院中の事例をひとつ、4F病棟廊下を散歩[徘徊]中に“お漏らし”した患者の報を聞いてスタッフルームから駆けつけた数人の看護師は何ごともなかったように手分けして床をキレイにする一方で患者の着衣を取り替える。またある患者の罵詈雑言が止まなかったり、悪態が甚だしい場合もなども、咎めるでもなく優しくするでもなく患者の身体の様相が見守られていたようだ。ときには介護士が喧嘩腰に出てみたり力づくでなだめたり、派遣清掃スタッフからも評判の良い4F病棟内看護・療養ネットワークが営まれていたようにおもう。それとは別に特に目立ったのは家族から見限られて快復しそうにない中年から老年にかけての男性患者の孤立。どんなに患者にとって好ましいスタッフでも家族の代わりにはならない。自然治癒の無意識的な見護りとなるであろう家族関係が崩壊してしまっているようでは、最終的な受け皿が断たれてしまって何ともし難いのではないか。とはいえ、“入院”という措置に立ち至るまでの老齢患者個々の生き様が、やり直せない壁のように立ちはだかっている事態に言葉を失うしかないのだが。
昨年暮れに手続きした「入院給付金申請書」に添付したS井主治医の「診断書」には「妻との死別による心因性」とだけ書かれていて以前の「葬式躁」なる言葉はなかった。退院に引き続き「心療内科」に通っていても一過性の「煩い」だったのか、再発性のある「患い」なのかも判然としない心身状態でもあるし、とても自身の老体状況について確たることなど言えない。そこで同じく自作Web公開してきた吉本さん晩年の「著作書誌」内容からも、先に引用した《老体論》と相関関係にある〈表現〉を引用しておきたい。
(19)▲『<老い>の現在進行形:介護の職人(PT)、吉本隆明に会いにいく』(三好春樹との対談集) 春秋社, 2000.10[著者76歳]
「ぜったいにといっては語弊があるかもしれませんが、最終的には配偶者にはいかないのではないでしょうか。性もなくなった、男女のべたべたもなくなった、ただ同じ家に住んでいるから家族ではあるんでしょうが、それ以上のものがなくなって、何でつながっているのかという段になったら、言いようがない。誰かを媒介にして、子どもを媒介にして、孫を媒介にして、それはあるのかもしれませんが、直接関係としてあるかといったら、それは「なくなるよ」となってしまうのではないでしょうか。
ときどき老夫婦で、いかにも仲のよさそうなのがテレビに出たりしている。あれはすごいと、たいしたもんだとおもったりするんですが、うそなんですね(笑)。あれは一人ひとりになってしまうんですね。一人ひとりがどこにいくかというと、やっぱり母親というか、生まれたところというか、胎内というか、そういうところでないかという気はします。」(36〜37頁)
「ぼくが体験的に大事だとおもうのは「呼吸」ですね。呼吸があぶなっかしいとすぐ息が詰まってしまうというか詰めてしまう。息が詰まるとすぐに転んだりします。いまは息を無意識にしようとおもっているんですが、なかなかできないところなんです。」(66頁)
「しかし、ほんとうにその人にとって認識できる限りの、いちばん切実で実感の伴っている〈死〉というのは何かといったら、どうしても「生まれてきたことに責任はない」という、じぶんの責任ではないのに、親が産んだから生まれてきてしまった、生まれてきたから生きてしまったんだということとかかわらなければなりません。そしてじぶんの責任ではないというのは赤ん坊のときのことについてはいえるが、それがぜんぶじぶんの責任だとおもえてきて、そのことと身体の衰えがどうしても切り離せなくなったら、それを〈死〉というよりしょうがないのではないか。いちおうぼくはそうおもっています。」(92頁)
(20)▲『老いの流儀』[構成:古木杜恵] 日本放送出版協会, 2002.6[著者78歳]
「ぼくは少し疑うんですけで、こういう[強いとされる空手選手が一〇〇人を相手に戦う=引用者注]強さは嘘じゃないかと。つまりほんとうに強かったら、そんなことはしないのではないか。何人か相手にしたら、「もうそのくらいでやめておけ」と言うに決まっている。それをぶっ倒れるまでやる。「そんなの強いわけないよ」と思うんです。K1の試合でも日本の極真空手の選手は勝てない。ブラジルとか第三世界で鍛えた選手が必ず勝ちます。どうして日本人選手が負けるかというと、相手の体が大きいからではありません。K1や空手をやっている外国の武道家は、日本人より日本人なんです。武道の極意みたいな「道」があるんです。ところが、日本の武道家には多少の信念みたいなものはあるけど「道」はない。信念と運動だけです。ブラジルの武道家のほうが、昔の日本の武道家が持っていた「道」が残っているし、そういう修練をする。だから日本人がかなうわけがない。東京オリンピックの柔道でもそうでした。重量級で優勝したオランダのヘーシンクを見ても、野山に行って大木を相手に投げの練習をする。昔の武道家がやっていたような稽古をやっているんです。だからノー・ハングリーになった日本人選手がかなうわけないですよ。』(24〜25頁)
「自然に対して抗わない老齢など成り立ちません。」(29頁)
「精神労働あるいは知的労働と、肉体的労働が絡まって区別できない部分があるとすれば、その部分が老人に残る。僕はそう思えて仕方がない。老人の持っている肉体的衰え、惚けというか精神的な衰えは、どちらも単独ではないんです。精神科の医師に言わせれば、老人はみんな精神的に病んでいる。その病は精神的な衰えなのか、肉体的な衰えなの判断しにくい。逆に言うと、老人の病気あるいは病的な状態や肉体的な衰えの治療は、整形外科的な療法でも精神的な療法のどちらでもいいんです。」(42頁)
「赤ん坊だって「死ぬ」わけだし、若い人も交通事故で「死ぬ」こともある。年齢なんて関係ないということになります。だけど、老人は「死ぬしかない」となると、そうかもしれないということになっちゃう。そうすると、人から「老人性うつ病」といわれる状態に陥ってしまうんです。若いときは「老い」と「衰え」の二つのことばで語れたとしても、老人の域に達すると曖昧模糊とした形で絡み合って、本質的には分けて考えたほうがいいのですが、「老い」と「衰え」がうまく分けられなくなるということですね。」(55頁)
「ある程度実感的に分かることは、歳をとった老夫婦が一緒に杖をついているというのは、まだ高齢化社会ではないときのことですね。では、高齢社会がもっと進めば性の問題はどうなるかについては誰も言っていない。歳をとって性の意識はだんだん薄れていって、友達的な関係といいますか、そういった人たちもいるだろうが、その後がどうなるかというと、最後の段階は誰もまだ考えていないと思います。最終的には配偶者にはいかないのではないでしょうか。」(123頁)
「若いときには過剰な生命力の発現は自然にまかせたほうがいいかもしれませんが、老齢化してからは自然に意志して「自然」に逆らわないと、スムーズな扱い方を「自然」のほうがしてくれないのではないでしょうか。」(129頁)
「今は過度期だから、あらゆる矛盾がすべて親子の関係、夫婦の関係に出る。両方が本気で正面からぶつかったら必ず壊れます。それを知恵でかわしたり、利害関係でかわしたりとかしながら、なんとか関係を維持していると思います。」(142〜143頁)
「マルクス流にもっと言うなら、経済的理由が第一の原因だと思います。資本主義か高度化して社会生活の形態や現象が超資本主義社会になりつつあるのに、政治や金融機関、企業は旧態然として資本主義制度の直線上の延長だと思っていますね。そうした矛盾が、今大きく噴き出している。とくに日本は典型的だと思います。そういうことが原因で金属バットで親を殺したり、逆に子供を金属バットで殺したりする事件が起きる。」(143頁)
「伝達手段の発達というのは、言語でいうと意味の増加なんですね。意味量の増加というのは、価値量が増加するかどうかはまったく分からないわけですね。専門家がよくよく考えて言わないといけないんですけどね、簡単な比喩で言えば、部屋の中でゴロゴロ寝ころんでいるのを外から見て、「あいつは休んでいるとか、遊んでいる。あるいはさかんに寝転んでいろんなことを考えているとか」というのは、おそらく分からないわけですよ。つまり、外から見ると寝転んでいるだけで、休んでいると解釈してもいいし、考え事をしていると解釈してもいいということになるわけです。外から分かることは、少なくとも意味だけであった、寝転んで何をしているかはぜんぜんわからない。」(158〜159頁)
(21)▲『家族のゆくえ』[書き下ろし] 光文社, 2006.3[著者82歳]
「それぞれ性格も生育環境も異なった、一組の男女の性の関係から家族はつくられる。人間は個々人をもとにいえば、どんな人間も、個人個人としての個人、家族の一員としての個人、社会のなかの個人、という三つの面をもっている。現在のような家族関係の危機状況や、独身主義生活者や同性愛者が増加しても、危機による崩壊や変形が増大しても、これは変わらない。
これを観念(精神)の問題としていえば、「一人の人間」と他の「一人の人間」のあいだの対幻想[ついげんそう=原文ルビ](性観念)が家族の本質である。これは相手が異性であっても同性であっても、一夫一妻(夫)で生涯を経ても、相手が複数に変化しても変わらない。また子供をもうけてももうけなくても、共棲してもしなくてもしなくても変わらない。もっと丁寧にいえば、先進地域でも混信地域でも、人種のいかんでも、現在までの歴史では変わらないといえよう。」(13頁)
「この人間の発達線に注釈を加えると、第一に移行期を加えたことだ。これがなければ発達線は人間の生涯の年齢の区切り線に過ぎなくなってしまう。この移行期の扱い方が種族や地域の特殊性と生活風習の因習性の伝統(つみかさね)につながることになる。次に、発達心理学が成人期と老年期について考察したものを、わたしの知見の範囲では見つけられない。もちろんわたしは自己の実感以外には、基礎となる考えをもっていない。それにもかかわらず、身体の運動性の減退とともにはじまる生活心理と観念の流転のすがたは充分な考察に価するとおもえる。
もうひとつ、ここでは「死」を老年期の後にもってくる考え方をとっていない。死は胎児のときから老齢までのどの時期にも存在する。それは、それは、どの時期にも存在しないということとはほぼ同義の可能性だからだ。」(14〜15頁)
「信仰や法律、社会(共同幻想)とも、また一個人(自己幻想)とも異なる位相にあるのが「家族」なのだということを最初に指摘しておきたい。」(17頁)
「わたしは、子育ての勘どころは二か所しかないとおもっている。そのうちの一か所が胎内七〜八か月あたりから満一歳半ぐらいまでの「乳児期」、もう一か所は「少年少女期」から「前思春期」にかけての時期だ。この二か所で、母親あるいは母親代理が、真剣な育て方をすれば、まず家庭内暴力、けた外[はず=原文ルビ]れの少年殺傷事件のような深刻な事態には立ち至ることはないとおもえる。もちろん、悪ガキというか悪童ぐらいにはなるかもしれないが、しかし、いきなり他人を刺してしまったり、あるいは親を殺したりするということにまでは至らないはずだ。」(28頁)
「とにかかく、胎児期から乳児期の母と子の関係はきわめて重要だという、こうした見方はわたしの理論的な考え方のとても大きな核になっているといっても言い過ぎではない。でも人間は、胎児、乳児に母親としてどんな影響を与えるかは、母親だけのせい[下線部原文傍点]でもなければ、家族のせいだけでもない。またその時期、どんな家庭であるのかも予見できるわけでもない。親と子の関係、家族の状態は予想できることではない。ただ親と子を中心にして平静に切りひらいてゆけばいいことだ。」(35頁)
「お母さんのお乳を飲んで可愛がられて育って、それからごく自然に離乳食に移っていく普通の人は、その後の人生で何か衝撃的に辛[つら=原文ルビ]いことがあっても、それに耐えられるだけの「壁の高さ」のようなものがあるとおもう。ちょっと苦しい目に遭ってもおかしくならないで、「壁」のところで引き返すことができる。いってみれば、なんらかの衝撃が壁を越えてこころの中心を直撃することがない。衝撃によって異常をきたすことがない。そうした壁は、乳幼児期の母親ないし母親代理との自然なかかわりあいのなかでつくられるといえる。」(39頁)
「老齢は社会通念とも倫理的な善悪感ともかかわらない。だからもちろん生存は屈辱でも誇りでもないし、敬[うやま=原文ルビ]いでも侮蔑でもない。わたしにはよくいえないが、「身体」についても考古学という概念が成り立ちうるとすれば、老年期は乳児期、幼少年少女期(学童期)、前思春期、成人期とまったく同じように、充分に学問的に、また文学・芸術的に探求するに耐える内容をもっているのではないだろうか。ただ実感的にも、観察的に客観視しても、まだ幼稚な段階にあるというだけだ。老齢者自身もせめて実感的に嘘をついたり、我慢して馬鹿げたミス・リードに迎合したりしないようにする責任があるとおもいたいところだ。」(160頁)
「したがって老齢者の定義はーー「頭や想像力で考え感じていること」と、それを「精神的にか実際的にか表現すること」とのあいだの距離が普通より大きくなっている人間、となる。そう定義するなら、まず間違うことはないとおもう。」(165頁)
「辛うじて残る共通点といったらーーもうすぐアウトだ。自分は死ぬかもしれないという不安、苛立ちだけだ。それはほぼ共通だとおもいたいが、お年寄りがそういうことを巧みに隠してしまえば、お年寄りのこころの深い部分はちょっと若い人間にはわかりきれないのかもしれない。」(175頁)
(22)▲『老いの超え方』(インタビュー・編集協力:佐藤信也) 朝日新聞社, 2006.5[著者82歳]
「つまり、自己としての自己と、社会的な自己というのは分離しないと駄目なのです。その分離がシュムペーターにはできていない。だけど、マルクスはできているんですよ。それはすごく違う。個人としての自分と社会的個人としての自分が区別できていないと、どっちかに行ってしまう。つまり、個人としてお金持ちになりたいと思おうが思うまいが、そんなことは勝手。自由なんですよ。誰かが大金持ちになってもそれはよかったじゃないかという以外何もない。」(46頁)
「そうだと思います。でも、概して言えば、ある年齢以上は男性も女性も、性交欲が第一位に来ることは珍しい。少数の人しか、第一位にならない。でも、性欲というのはずっと死ぬまであると言えるのではないでしょうか。人さまざまだし、生態もさまざまですから、一般論では性交欲はある年齢以上は第一位にならない、女性も男性も関係なくそうだと思います。ただ、女性はいいと言えばいい、でも男性はそれ自体ができなくなるということがあります。そこが違いますが、生欲はどんな年寄りにもあります。かといっていくら老人ホームで男性と女性が仲良くなっても、若い人の乱交パーティみたいなものが起こるはずがありません。おかしなことが起こるというのは、僕の考えでは、ないと思います。」(98頁)
「[入院することは=引用者注]比喩としてはそうで、実際問題としては書いた通りで、これは一般社会の中にある真空の場所みたいなもので、生活もないし何もない。外との接触は見舞いや家族が来るだけで、道路一つ隔てただけで全然違う。これが続くと耐え難いと、僕は思いましたね。真空地帯、あるいは中立地帯と言っていいのかもしれません。あまりいいという思いもないけれども、それほど凶悪なものでもないといえばその通りですが、ちょっと特異なところなのではないでしょうか。」(107頁)
「少なくとも社会的人間としては、それは[代償を求めるなというビジョン=引用者注]非常に重要なことです。社会的人間と個人的人間というのは、同じ一人の人が二重に持っているわけです。それは、やはり初めは分離ができていない。分離ができていないというのは、思想問題だからいいけれども、生態的な問題だとすれば動物と人間の違いぐらい違います。それが分離できていなければ動物です。身体性、運動性はいいでしょうけれども、ほかのことは動物と同じになってしまう。でも、分離しているから人間だ、自分の理念として分離しているとそれがよく分かるとか、幅が広がったとか、そういうことが分かります。そうすると、対応の仕方が違いますから。」(155頁)
幼少期の〈軒遊び〉からはじまって、人間の「発達線」に〈移行期〉を設けるだけでなく、さらに〈死〉は胎児から老齢までのどの時期にも存在する[しない]とするところに〈身体〉を立たせたとても大切な考えが述べられている。
老若男女老いも若きもいずれの〈身体〉の〈移行期〉にもとどくように、〈書く・話す〉ことと〈為す〉ことが乖離していないというか、「人のからだ」について方法的に明らかになるように五体を駆使してきた〈身体的表現〉が試みられている。
しかし現在のわたし自身を顧みれば、自分の身体を素材に考古学的な発掘をやっているような気がしている。考古学者が日本列島と周辺を全部掘りかえすのは大変なように、一メートル七〇〜八〇センチの自分の身体とその周辺を掘りかえすのも大変だと思う。幸いにも身体については、男女の専門家が古代から現在まで沢山のことを解明してくれている。そして現在も発掘にたずさわる人たちの探求はつづけられている。わたしは発掘される方の身体として、他人には見たり聴いたりできないかもしれないしんたいのつぶやきや独り言を洩らせばいいことになっている。
(吉本隆明「あとがき」/『老いの超え方』(インタビュー・編集協力:佐藤信也) 朝日新聞社、2006年刊、270頁)
自分が自分の身体についてどう思うかということより、どう思えばいいのかを第一に考えるようにして多くなった《引用》の向こうから、自分の身体が浮き彫りになってくればいいのだが。
思いつくままに「引用」した吉本さんから《自分に問うというか、そういうものがあるあいだは、《HP作成と持続》は生きた“雑誌”になる。それがなかったら、わざわざHPを作る意味なんてない》などと言われかねないが、HPを続けることで“AI”流行りの状況にめげない呼吸法をつかみたいものだ。それが身体と言葉をつなぐ何のことでもない見通しにもになればいい。
幼少期に街道と民家を行き来したであろう幻の父の老いゆく背中を見たかったようなきがする。
(2024年3月20日記/23日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(19)居着く身体
「動法理解の鍵は解剖学無き時代の身体観にある。解剖学的区分を忘れ、
素直に自らの身体を内観し、その感ずるがままの内観から得られる身体
像を、私は内観的身体と呼ぶ。それは単なる客観的身体の認知像とは全
く異なり、気体化した身体像とでも言うべきものである。今仮に座して
軽く閉眼し、自らの腹部の輪郭をとらえてみる。するとそこに腹の像が
浮かぶだろう。或る処は不明瞭にぼやけて居り、明瞭になっている処を
辿ればそこに様々な形、例えば瓢箪、或るいは半月の如き形を呈してい
る。次に腹の表層から深層へと内観を転じてみる。最深層は背の裏であ
る。背の裏まで内観が届く者にはそこに立体性を有する腹の全貌が観え
よう。このように内観的腹部は立体性と複層性をもつのである。」
(野口裕之「動法と内観的身体」/『体育の科学』第43巻第7号、19
93.7)
1972[昭和47]年に二十代後半まで過ごした小矢部市埴生の地を引き払い、富山市高屋敷に移り住んだ三年目の夏に明治(12年)生まれの祖父を亡くし、その35年後の春に大正(9年)生まれの母を亡くした。そして昨夏、昭和(22年)生まれの妻も亡くした。今年の元旦の夕刻に激しい地震[令和6年能登半島地震]の揺れに遭い、娘夫婦や姉夫婦の安否が確かめられるとともに、被害が最小限に過ぎた一軒家で、今は亡き家族一人ひとりの體に働きかけたであろう〈重力〉が安堵の思いを彩るようだった。地震で倒れることなく動か[け]ない庭木がそれを象徴するように。
「父親」については、物心がついた頃だったか、仏壇の一柱として知っただけで〈父性〉は未体験のまま、引越しと前後して結婚し子を授かった。女の子でよかったというか、もし男の子だったら〈父〉を知らない自分はどう対処してよいものやら戸惑っていたに違いない。それほど〈母〉の存在は大きいのだ。
長患いもなく百歳目前に町内葬で見送った祖父の位牌に毎朝手を合わせるようなことはなかったが、季節を重ねた介護暮しから身を退いたような母の家族葬の一周忌を前に原発事故を伴う東日本大震災があり、その一年後に吉本隆明さんの訃報に接したこともあって、気づけば朝に仏壇で手を合わせないと一日が始まらないようなことに。そして妻亡き後も。
鄙びた庭付き二階建て「独居老人」という一人暮らしになって、さぞ身が軽くなったであろう、なんてことにはならないようだ。次々と亡くなってゆく家族の〈引力〉が〈場所〉を無くした分だけ、身体的に手触りできない隙間が生じたというか、軽くも重くもならない《心もとなさ》のグラデーションが、ともに過ごした各部屋ごとに違うという塩梅なのだ。
妻の葬儀以来、二ヶ月ちょっとの《入院》というエアポケットを挟んで、一階の六畳の座敷の床の間に設けたままの祭壇の位牌と遺骨と遺影とともに寝起きするのが当たり前になりつつある。カーテンを引いたままの縁側越しに障子が明るんでくる頃にひとり寝の目覚めが家人の不在を確かなものにする。
一人でご飯を食べるほど虚しいものはない。やはり、美味しいねと言い合える人とでなきゃ、美味しくない。一人だと高級品を食べたいとも思わない。外食で一人で食べるのも寂しい。美味しくない。気の合う人となら、なんでも美味しい、公園のベンチで食べても美味しい。
(早川義夫「10.天使の羽」/『女ともだち:静代に捧ぐ』(ちくま文庫)2024年3月刊、86〜87頁)
男女の仲で営まれる食欲ほど内的快楽をもたらすものはないといいたげである。場合によっては食前の「スパークリング」で乾杯し、食中に「赤or白ワイン」があり、そして食後が「ジントニック」や「オンザロック」の締めにでもなれば言うことなし。食の相性が二人の生涯をより一層豊かなものにしてくれていたに違いない。
スーパーの肉売り場を歩くと、食欲がなくなってしまう。こんなことを言ってはいけないかもしれないけれど、牛肉、豚肉、鶏肉、赤身のマグロが人肉のように思えてしまうのだ。
「自殺の方法」をネットで検索してみた。苦しまない方法、後片付けをする人になるべく迷惑がかからない方法があれば知りたかった。けれど、どれも無残に思えた。
奥様を乳がんで失った西岡恭蔵は、三回忌の前日に首吊り自殺をした。五十歳だった。江藤淳は奥様をガンで亡くされてから、八ヶ月後に自宅の風呂場で手首を切って自害した。六十六歳だった。西部邁は奥様をガンで亡くされてから、三年十ヶ月後に多摩川に入水自殺した。七十八歳だった。
(早川義夫「26.最終章」/『女ともだち:静代に捧ぐ』(ちくま文庫)2024年3月刊、190〜191頁)
[歴史的に実在したであろう]「人肉嗜食j」と、「自殺」実行後の後始末への「配慮」、そして「生き方としての死に方」の難しさが、まるで三段跳びのように表出されていて、かえって行間では奥様への追慕の情が抑制されている。
挙げられている自死者お三方ともいわゆる“ボケ老人”からほど遠く、頭が働きすぎるくらいで、かえってそのことが老齢期にさしかかったそれぞれの“心身一如”に固有の齟齬をきたしてバランスを崩されたのだろうか。個人的な自己と社会的な自己とが引き裂かれすぎたら、自然的な〈待つ〉ことができなくなり、生き[死に]急ぐことになってしまった。
心身ともに両輪違えず衰えがやってきてやがて食べられなくなり、ついに息絶える。
福岡 ベルクソンの「物質の下る坂」というのは重力で、単位系が違いますが、高エネルギーの状態がエネルギーを放出してやがては低エネルギーの状態になること、あるいは、秩序の高い状態が徐々に崩壊して秩序の低い状態に陥るエントロピー増大の法則と重なると言えます。そこで、私が動的平衡を理論化するにあたり、エントロピー増大の法則を、万有引力によって引き戻されるもののアナロジーとして、思考実験をしてみました。
(坂本龍一 福岡伸一「動的平衡の理論モデル」/『音楽と生命』集英社、2023年3月刊、137頁)
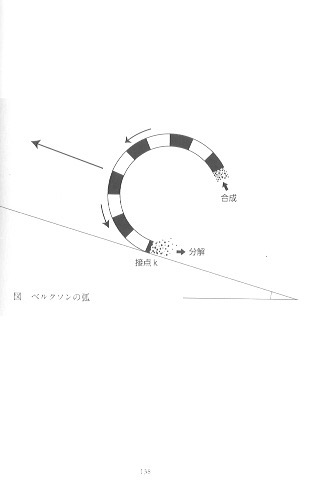
[図 ベルクソンの孤](同前、138頁)
[福岡 前略] このようにして、生命が常に合成と分解をすることによって成り立っているというモデルを考えて、私はこの動的円弧を「ベルクソンの孤」と名付けました。
坂本 今のご説明を聞いて思ったんですが、昔の日本人は、同じ側の手と足が一緒に前に出るナンバ歩きというものをしていましたよね。手と足が交互になる西洋式の歩き方と違って、ナンバ歩きだと速く走れないけれども、飛脚が東海道を江戸から京都まで三〜四日で走り続けたといった話も残っている。それは嘘[うそ=原文ルビ]ではなかったと言っている人がいるんです。手を振らず、常に前傾姿勢で走っていくと速く走れるということなんですが、これはつまり、倒れるから前に進めるという点で、福岡さんのこの図はナンバ走りと同じなんじゃないでしょうか。
(同前、140頁)
坂本 なるほど、この分解と合成のバランスが維持されながらも、徐々になくなっていき、時間が経てば、はい、終了というのは、なかなか良い生き方だというふうに見えてきますね。
このモデルを見ると、生命が生まれて死ぬというのは納得がいきます。円弧が全部なくなったら死ぬわけですけれども、途中で病気になるというのは、どのように考えたらよいのでしょうか。
福岡 おそらく、合成と分解の速度のバランスで、合成のほうが少し勝ってしまて、分解が追いつかなくなることにより、登り返していたものが下向きに下りそうになる、あるいは、どこかで静止してしまっているなど、動的平衡のバランスの乱れということから説明できるかもしれません。
(坂本龍一 福岡伸一「死を受け入れる」/『音楽と生命』集英社、2023年3月刊、145〜146頁)
そんな〈いのち〉という生命活動の「動的平衡」が消滅するような「還化」の例が現在でも稀にはあるようだ。
まさに『行くべきところへ行く』という姿は、本当に見事なものでした。ベッドの周辺には医療器具も薬品も何もなく、本当にさっぱりとしたものでした。『一度しかない人生の本舞台の最後を、余計な干渉なく納得のいくように終わらせる』ということが、現代ではどうしてこんなに困難なのでしょうか?
(甲野善紀@[旧Twitter改め]X)
甲野師の「ツイート」に出会って、1975[昭和50]年の7月25日の夜に仏間で妻といっしょに看取った祖父の亡くなり方が蘇ってくるようだった。
杖をついてトイレを使い、風呂も自力で入っていたのが、やがて這うようにして居室からリビングにきて食事をするようになり、晩酌も飲まなくなると食べるほうも進まなくなり寝込むようになった。
介護していた母が医者に診てもらったらというので、医者要らずで生きてきた祖父に無断で、家から近くで開業されていたC鳥女医に電話して来ていただいた。祖父には医者を拒むような気力もなさそうで、診たところでは消化器系にも循環器系にもなんら問題がなくて驚かれた様子だった。帰りがけに祖父の食生活について事細かにメモして行かれた。
やがて生命反応が弱くなったようなので、二度目に来ていただいたC鳥女医は「今夜あたりでしょう」と言いおかれたが、まさにその通りになった。
昼間の介護疲れの母には休んでもらい、妻と二人で付き添った。呼びか掛けに応じなくなり、ぜいぜいと息が苦しそうで、脱脂綿や綿棒で黒ずんだ痰を拭きとるようにしたが、水も受け付けないようで、時刻を見て約束してあったC鳥女医に電話して来ていただいた。「ご臨終です」の言葉に、あと一週間で百歳だったことを思ったりしたのも妻といっしょだったようだ。
C鳥女医が帰られてもにわかにその場を立つ気になれず、二人とも祖父の体がだんだん冷たくなっていくのを感じとっていたら、ところどこ手足や顔の皮膚が痙攣するようで、なんだか無精髭まで伸び続けているような気がしていた。
後に母が要介護状態になって男女のケアマネージャーからこれまでの家族の介護状況を尋ねられた際、1970年代半ばの祖父の在宅大往生の様子に驚き、信じられないというか、「スーパー老人」とまで言われた。また、呆けたり要介護老人を抱えた家庭を悩ます食べ物や金銭的なトラブルなどが一切なかったこともケアマネージャーになかなか信じてもらえなかった。
田舎の家屋敷や田畑一切を売り払って郊外の新居に移り住んで間もなく、一度だけ、田舎の民家[家族/家]に帰らせてくれと祖父から難題を吹っかけられて困り果てたことがあった。
祖父亡き後、母はそれまで朝鮮から引き揚げてきてこのかた縁の薄かった“ひとり時間”を取り戻すかのように、足元がおぼつかなくなるまで高山から京都そして奈良へと春秋の季節を愉しむかのように一人旅を遊びにしていた。
退職した銀行から「パートタイマー」で呼び戻された妻に代わってご飯を用意してくれるだけでなく、午前は抹茶を点ててくれたり、午後にはコーヒーを淹れてくれたりもしていた。職場のごたごたで体調を崩して早期退職した息子を気遣ってくれていたのだ。
そんな母も一度だけおかしなことに。階下からなにやら壁をドンドン叩いて泣き叫ぶ気配に、いったい何事と下りてみたら譫妄状態の母がいて、とっさに自傷行為にならないよう静まるまでしっかり抱きとめていた。夕刻にパート仕事から帰った妻ともども、しばらくは様子を見ようということにしていたら、午後の同じ時刻に同様の症状が二三日余り続いてほどなく治って再発することはなかった。
敗戦直前に京城[日本統治時代のソウルの呼称]から母子三人で引き揚げてきて、埴生で祖父が一人暮らしていた民家が受け皿になった始まりの十数年間あまり、難癖をつけては母に当たり散らす祖父の暴力をともなった癇癪の暴発に姉弟ともども恐れおののく日々だった。
過去にそんな仕打ちを受けていた母が短い間だったとはいえ、下の世話をはじめ何のわだかまりもなく祖父を介護するのには、引っ越しする前に嫁舅のあいだで何か変化が起こったのだろうと後々になって納得できた。
在宅介護状態になった母が余りにも息子の手による下の世話をいやがるものだから、赤ん坊の時に何から何まで世話してもらったお返しだと思えばいいじゃないかと言ったら、そうかと呟いて素直に世話を受けてもらえるようになった。
そうこうするうちに過去のエピソード記憶などを語り合ったりするようになったとある日、埴生から高屋敷に移住する間際になって祖父から過去に打擲したことを謝ってもらえた、とさも嬉しそうに母が語ってくれたのだ。過去の家庭内暴力による肉体的な傷跡は癒えても、身体的なダメージはやった方もやられた方も體内記憶のようにいつまでも尾を引いていたのだ。
祖父のその時々のストレスなど発散して溜め込まないのがいかにも当たり前といった身の動かし方に、それゆえに当然のような身の終わらせ方に、我が身の処し方だけでなく来し方行く末などが問われているような気がしてならなかった。
日本文化の流れにあって、さまざまな分野の底流で見え隠れする基層のような身体運動の伝統とはどのようなものであったか。木造校舎の教室や廊下の雑巾がけ。泥の深さが違う山田と里田での足指使い。田畑や里山での農具等の使いこなしと手入れ。冬には屋根の雪下ろしや道路の雪割り。夏には道路の水撒きや薪割り。中学部活での剣道と冥想。そういった事など、虚弱ながらも経てきた身体のいま・こことは祖父たちが受け継いできた伝統的な身体運動とは大きく隔ってしまっている。
タバコ盆を傍らに、ゆったりと刻み煙草を燻らす所作など、当時の祖父の年齢に達した自分には到底できそうにない。一事が万事、祖父や先人たちが日常生活で示した身の処し方から何一つ学んでこなかった、身の整え方があって初めて生じてくる感覚や意識についてあまりにも無頓着だった気がしてならない。
箸の持ち方からその上げ下ろし、食器の持ち方だけでなく、食べる所作などなど、実家の祖母だけでなく母からもそれとなく躾けられた。急須の持ち方とお茶を注ぐ時の指遣い。畳の縁を踏むな。鋏や刃物の受け渡し方や研ぎ方。紐や縄の結び方など祖父は教えるというより、それらが必要になる仕事を手伝わせるといった風だった。
1922[大正11]年に妻を亡くした祖父が、1912[大正元]年生に授かった一人息子ーーまったく見覚えのない父でもあるーーとの母なき父子暮らしでどのような身体使いの躾け方をしていたかわからないが、外地勤務となる朝鮮総督府の警察官として送りだしたまではいいとして、まさか朝鮮人の犯人逮捕の格闘で罹患した伝染病で殉職するなど思いもよらぬことだったろう。
躾という文字は漢字ではない。国字である。身ヲ美シウスルと書く。ここに古人の抱いた教育観がある。端的に言えば日本の教育は身体の教育であった。頭で憶えることより、「身体で覚える」ことに重きが措かれ、頭で理解することより、「身体で感じとる」ことが尊ばれたのである。学習とは思考の鍛錬ではなく、身体の行法であった。したがって教育の第一義は、身の律し方であり、それは即ち動法の規範と型の伝承だったのである。
(野口裕之「動法と内的身体観」体育の科学.43(7).1993.)
一度だけ父の死と葬儀について母が語ってくれた時、子ども心に「犯人」を恨むというより、警察官としての父が相手を一撃で制圧できるような技の使い手だったら事態は変わっていたのにと悔しく感じた。多分にその頃は村の小学生からの“いじめ”の渦中だったことも影響していたかもしれない。
中学校に上がった部活で“チビ”に不似合いな剣道を選んだのも強くなりたい憧れがあってのことだったろう。寒稽古や暑中稽古もサボらずに励んだようだが、確か七段だった顧問の先生からどんな稽古をつけてもらったのかさっぱり覚えがない。足捌きに変な癖がついたようで、30歳半ばに腰痛と痔のリハビリに始めたバドミントンでは、先輩からお前のフットワークは剣道みたいだから直さないとラリーが続かないよと言われてしまった。
練習方法を間違えると間違った身体裁きが上達の妨げになるということだ。生前の父は柔剣道などもやっていたそうだがどんな稽古をやっていたのか母に聞いてみたことがある。わからないけどいつも腰に下げたサーベルのせいで左足の靴の減り方が歪だったと話してくれた。三十歳過ぎて亡くなる間際の父にはそんな癖が身についていたのだ。
小柄で野良仕事や調理の身のこなしが超自然に見えた祖父にはこれといった身体動作の癖がなかったようだが、白寿になり家の中で床をコッツンコッツンと杖をついて歩くようになったリズムが老いた癖のようにも聴こえた。母は祖父と違って杖をつくようになって間もなく車椅子生活になってしまった。寝たきり老人にはなりたくなかったようで、どんなに時間がかかっても日々着替えて座椅子か車椅子で起きているようにしていたのには感心した。
自分自身に関心がないんです
92歳を迎え、車椅子を使う生活になった
もう90歳を超えてね、いまがいちばんいい、なんて思うことはないんですよ。足がヨタヨタしてるしね。前はテキパキ動くのが好きだったし、できればちゃんと歩きたいとも思いますよね。自分の身体の状況は、どっかで詩に影響してるはずなんですよね。
車椅子は便利だけど、吉本隆明のようには乗りこなせないね。
講演中、舞台の上で車椅子をグルグル回しながら話していたように記憶してますね。彼は、肉体を持った存在として、作者そのものにも少し目を向けてほしいと思ったんじゃないかな。
僕にはそういう気持ちはないんですね。わりと昔から、自分自身に関心がないんです。
いまは、生きている意味もなくていいと思える。
(谷川俊太郎「未来を生きる人たちへ:premiumA」/『朝日新聞デジタル』2024年4月4日、https://www.asahi.com/special/tanikawashuntaro/?ref=culture_mail_top_20240404)
晩年の母は通い慣れた近所の寿司屋に誘っても、見苦しい姿を晒したらお店やお客にもよくないからお土産に作ってもらってきてと言うだけ。家にいてばかりじゃ面白くないだろうから、たまにには姉夫婦の家で厄介になってみてはの誘いに、そんなことするくらいなら「施設」の方がいいと応えるばかり。戦中戦後のどさくさを生きのびてきたからかもしれないが、見るからに身動きなどに不都合を抱えていても最期まで「いまここがいちばんいい」が口癖だった。
智香恵[亡妻]も結婚するまでに警察官だった父の人事異動で県内を17回も引越しで大変だったらしい。我が家に落ち着いてからは、ここがいいからもうどこにも行きたくないね、が決まり文句になっていた。長旅などで家を留守にするなどしたことがなかった。四十代半ばに日帰りスキーをした晩のバドミントン練習で断裂したアキレス腱の治療で一ヶ月あまりが家を空けた最長になった。
私と妻が入院した後は、いずれ遠くない時期にK子が伸一とマヤを一足先に島に連れ帰ってくれるはずであった。月曜日、朝食をすませた私と妻は、簡単な手まわりの品物を風呂敷に包んで家を出た。伸一もマヤも寂しそうな顔は見せなかった。あっけないぐらい父と母の入院を納得しているようであった。途中の車中はふたりともに気が抜けたようにだまりこくっていた。妻がいつもの緊張を持ちこんでこないと、かえってたよりない気分になるようであった。病院に着くとすぐ神経科の婦長に案内され、精神科の病棟に連れて行かれたが、遠巻きにして望み見ていた時に濃くただよっていた異様な気配は感じられず、かえって気抜けしたほどであった。
(島尾敏雄「第十二章 入院まで」/『死の棘』新潮社、昭和52年刊、345〜346頁)
2000[平成12]年5月5日の晴れた日に妻と魚津水族館&ミラージュランドを目指してサイクリングした観覧車の山手側の眺めに、その23年後の夏に妻を亡くした自分が入院することになるM病院が見えていたのかどうか不思議に思うことがある。
数年前の左腕鎖骨骨折がきっかけみたいに体力・気力が衰え始めた妻に合わせたみたいに熱中症になったり、たがいに摂食嚥下障害を起こすほど食べられなくなったり、風呂が使えないくらい体力が落ちたヘタヨレの毎日を老老介護状態で細々と繋いでいたのだが‥‥‥、どこかに無理があったのだろうか。
妻亡き後の入院生活を経た一人暮らしの身になってはじめて気づいたのだが、ふたりとも家族/家[民家]に居着き過ぎていたのかもしれない。抑鬱共存状態に陥ったような毎日にどこかで見切りをつけ、ふたりして入院するなり施設に入るなりして、そこまでの日常生活そのものをいったん遮断するというか、とにかく隔絶できる距離を保つようにしていたら、今のような〈現状〉とは違った道[街道]が開けていたのではないだろうか‥‥‥。(2024年4月8日記/12日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(20)身体の内外
「今、私はあの世から、この世に戻って来たところだ。そして、
この世の景色を眺めているのだ。私は幽霊。だから、なんだか
ふわふわした、浮かんでいるみたいな気持ちなのだ。
妙に景色がはっきりくっきり見える。はじめて見る場所なの
に、ちょっとだけ懐かしい。ここには誰も私を知っている人は
いない。私が見えていないかもしれない。
知らない町を歩いていると、ふいに、そう思うことがある。」
(武田 花『ポップス大作戦』文藝春秋、2020年6月刊)
老いゆく日々の暮らしの心構えみたいなことは夫婦で話しあったりしていたが、老体の身構えというか身体構えまでは出来ていなかったような気がする。五十数年前に一緒に暮らし始めて生活の句読点みたいに続けてきたたスキーやバドミントンやサイクリングなどは、そろそろ止めどきではないの‥‥‥、という體内の声に従うようにしてそれぞれ縁が途切れてしまった。ときどき左目が見えにくくなった妻は長時間読めなくなるとともに、調理や食べることまで愉しめなくなり、ふたりして快食・快眠・快便を保つのも大変になったようだねと、たがいに飲食の質や量にも気遣うようにしていても猛暑の夏を持ちこたえるのがやっとというような体調の日々、ふたりとも同じ掛かり付け医に通うのが常態になってしまっていた。
「心身ともに両輪違えず衰えがやってきてやがて食べられなくなり、ついに息絶える。」
祖父のときのように「平穏な最期には救急車より看取り医」があたりまえにできたのが、なんだか特別なことのように思えてしまう。母の最期のときは動転してしまい、決まっていたF田掛かり付け医に連絡しないで、救急車を呼んでしまったことをいまだに後悔している。
己を観つめるより対象に問題を見出し、解決策を考えて自分の外に働きかけることが正しいという発想です。
それに比べて、「今自分にできることは限られており、必要に応じた時間の中でしか物事は進まない」ことを当然とした暮らしであれば、外の世界や情報に対してでなく自分の身体の方へ自然と集注が向いていきます。
そのような環境では、身体で行うことは必然的に繊細になります。
今の時代にひたすら要求されるのは、そうした自分の内側や身体への注目ではなく、頭脳による外の世界から入ってくる情報処理です。
現代社会の仕事は人工的に作られた情報をどれだけ頭で整理するかが重視されています。
比べて田畑を耕し、重たい米俵を担ぎ、草履を作り、織物も作れるといった繊細な手足の動きと身体の集注感のあった時代の感性をどれだけ技術面から追求しようとも、今の時代のベースとなる身体観と環境が違うのだから、再現できないのは当然だということが理解できると思います。
(光岡英稔「効率を重んじる身体観が幅を利かせている」/『身体[からだ=原文ルビ]の聲[こえ=原文ルビ]』PHP研究所、2019年4月刊、40〜41頁)
埴生に住んでた頃の祖父が座敷の障子を開き、縁側のガラス戸を戸袋に収めて開け放った庭を眺め煙草をくゆらす。陽性植物の赤松を主木にして陰性植物の躑躅の植え込みが配されていた。縁側から降りて下駄で飛び石伝いに庭に立てば身体の陰陽バランスが保てるかのように。松をはじめ季節に応じた庭木の剪定や冬場の雪吊りなど手入れの一切は祖父がやっていて、庭の草むしり以外は手伝わせなかった。移住した高屋敷の自宅の狭い庭に移植した松はそれぞれ五十年と百年を超えるまでに育ち、始めて半年ばかりの独居生活の五月の青空に映える夫婦松のようだ。枝に登って「みどり摘み」や「もみ上げ」など、かっての祖父のようにはとても暮らせない。
埴生の民家の背戸の庭は祖父にとって観賞用であっただけでなく、田舎暮らしの場としての生活の型をも示していたような気がする。庭木類が途切れる辺りを仏花や野菜の畑にし、柿や無花果や柘榴の木などによる境界の仕切りに並ぶように鶏小屋や作業小屋が配置されていた。糞尿の汲み取り口近くを裏通用門として、そこから西陽除けの杉小柴で囲われた空き地の桐や椎や栗の木の並びには、よく手伝わされた薪割り作業用の木挽き台や大きめの切り株が設えられていた。
そのほか民家の軒端続きで椎茸を採ったり漬物を漬けるなど祖父の作業場でもありながら、裏庭は夏休みの昆虫採集や蜘蛛の観察そのほかで虚弱な幼少期の恰好の遊び場でもあった。
祖父が養生訓に詳しかったかどうかは知らないが、いささか禁欲的に贅沢を嫌って村社会の秩序を保ち、自分や孫の身体を対象化して養育するように、屋敷内の好みの庭木や屋敷外のわずかな田畑の作物を大事に育てる姿勢を保ったようだが、田舎から郊外への移住後は日々の称名を唱えながらまるでこの世から身を退くかのように逝ってしまった。
宮沢賢治の「インドラの網」(1921or1922[大正10 or 11]年?)を読むと、作中の主人公が秋風吹く草原でひとり歩き疲れて昏倒した内的世界で自問自答するうちに現れた「寺の廃趾から発掘された壁画の中の三人」の子供らにその発掘者である「青木晃」を名乗って一緒にお日さまを拝み、「青空に変わったその天頂から四方の天末までいちめんはられたインドラのスペクトル製の網」に交錯する風の太鼓と不思議な蒼孔雀が鳴く幻想的な世界を、内向する視覚と聴覚をこまやかに働かせて自在に織りあげている。
そして「河本さん」と歩いた短編道中記ともいうべき「秋田街道」(1929[昭和14]年8月14〜15日?)を読めば、街道沿いの民家で営まれる厳しい暮らしに注がれる視線から始まり、道すがら出会う森羅万象、旅する身体を取りまく外的世界に向かう作者の視覚と聴覚の豊かな生命感に溢れ、躍動する文体を構成するリズムは何度聴いても飽きないデビッド・T・ウオーカーのギター・トリオ演奏『ザ・サイドウオーク』(P-VINE1996/Revue1968)のようではないか。
吉本さんによれば「意識の了解作用、特に視覚と聴覚は、第一に胎児期に獲得される内感覚と、第二に誕生後に獲得される外感覚との二重構造を持つと考えられている。人間は誕生後も体内で形成して使う内感覚を、誕生後もまったく失うわけでなく、潜在的には無意識に保存している」(吉本隆明『死の位相学』)というから、「法華文学」の創造だけにこもらず土性や地質調査をしたり日蓮への信仰篤く町内を寒修行するなど当時の宮沢賢治にあってはその二重構造を持つとされる内感覚と外感覚の共時的な働きをともなう生来的な活動期の作品になっている。「秋田街道」では盛岡から小岩井農場までの山道を辿りながら、人の暮らしからあたりの風物や景観まで體外声的な文体で、「インドラの網」ではあらゆる存在が網目状につながった幻視的世界を體内声的な文体で、それぞれ読むものの身体を呼び覚ますように表出されているといえよう。
「わたくしという現象は/仮定された有機交流電燈の/ひとつの青い照明です」(宮澤賢治「序」/『春と修羅』)と仮構された心象スケッチャーが「けれども、わたくしは、これらのちいさなものがたりの幾[いく=原文ルビ]きれかが、おしまい、あなたのすきとおったほんとうのたべものになることを、どんなにねがうかわかりません。」(宮澤賢治『注文の多い料理店』序)とつつましく願っている。それは宮沢賢治にとって〈詩〉と〈童話〉に向き合う、言葉の指示性と表出性を極端に際限なく引き裂かれる心象スケッチャーとしての修羅に取り憑かれることでもあった。妹トシの病死がより一層その傾向を強くするとともに、自然そのものだけでなく第二の自然としての身体までも垂直的な〈層〉として感受する傾向を深めることになったといってもいい。
あくなきみずからの〈身体層〉へのこだわりが教職を辞し、実家を出て下根小桜の別宅で自活しながら「羅須地人協会」を立ち上げ、理想とする〈農民〉としての諸活動に邁進することになった。家業の古着屋や質屋のようにしたくない事ばかりが目についていた宮澤賢治に、ようやくしたいことの端緒が見つかったのだ。
事実や事柄から離れて虫や鳥などの視線になって〈自然〉を視るように、農民の眼になって「イーハトーブ」の〈身体〉を観るところから〈存在〉が生まれるというように価値転換されたとでもいえようか。身体内から宇宙までなんらかの形で〈時間〉を処理するというか、了解できる独特な視線を獲得したのだ。
「人間の身体と動物の身体の一番違うところといえば、麻痺や痺れである。」ということをきいたことがあるが、それは人間の身体が層になっているという本質を言い当てているのではないか。三木成夫がヒトの體を「動物的および植物的」な両面からとらえた「人間の形態学的考察」で言及[三木成夫『海・呼吸・古代形象』うぶすな書院、1992年8月刊]している〈ずれ〉や〈ねじれ〉が、ヒトの胎児が受胎32日目から7日間の間に水棲層から陸生層へ変身生成される時期に母体である母親に甚大なる影響を与える事などにも由来するのであろう。
人間は自己に対する関係としての自己であるものを問い続けるしかないとすれば、人間においては自己が自己であることの中にあるずれ、あるいはゆらぎが含まれることになる。沈黙のうちに安住することも,充たされることもない〈異和〉としての自己はいかにして十全たる〈個〉でありうるか?
体調不良による早期退職後の1年半余りの自宅療養暮らしからようやく抜け出せた頃、一本釣りされた富山短期大学における非常勤講師の4限目の授業を終え、富山市願海寺の富短キャンパスから街中への帰路につくバス車内はいつもスマホに見入る学生ばかり。道中の神通川の土手の桜や呉羽の梨畑の花盛りなど四季の車窓の眺めなど眼中になさそうだった。
校下の小学校や中学校の夜間解放の体育館に出かけていた頃も、バドミントンや卓球のゲームの休憩中にスマホを覗く社会人が多くなって、以前のように世間話に花が咲くような場面は少なくなっていた。
自分と同年齢時の祖父の体力・気力にはとても及ばない老体ながらなんとか十数年こなせた司書課程の持ちコマに出席してくれた受講生のほとんどが、出された課題や問題の答えが“ネット”上にあると信じ込んでいるようなのだ。暗記やマルかバツで答える課題など極力出さないようにしていたのに、頭や身体の外を探してみつからなかったらそれで終わり。その答えどこにありますかだけで、何をどうしてこうなったというプロセスのない質問がほとんど。自分に形をもたらすのは身体だからそこを探り、注目していかなければ、人は自然との関係を作れず、生きのびられない。なぜなら身体そのものが第二の自然だから。
ここではそれ[マルキシズム=引用者注]より、社会は脳の産物であることを主張する。いわゆる共同幻想論は、それを別の言葉で言うものであろう。社会も文学も、いずれも脳が生み出したものだが、それが身体をどう扱うかを吟味することは、社会を考える基本だと私は考えている。なぜなら、社会を作ることによって、人は自然から離陸したわけだが、そこで引きずっていかざるをえない自然性は、身体に凝縮されているからである。
(養老孟司『身体の文学史』新潮社、1997年1月刊、13頁)
社会の産業構造の高度化をを1次〜n次産業と表せるように、情報化社会のメタデータによるタグ付けの高度化を1次〜n次情報と関係付ければ、情報の組織化とはメタデータ化作業による情報の1次〜n次化であり、情報サービスとは情報の情報であるメタデータ次数を低次化するようにして、高次情報から1次情報にたどり着けるようにすることになる。ここまではすべて数値化できる情報の世界である。
授業での心残りといえば、とある年度の「情報検索」授業半ばでいつも最前列に座っている女子学生の一人が立ち上がって「情報を調べるということ自体がどうしても分かりません」と、ゆる?い変化球を投げ込んできたことだ。
そこでの授業で持ち出してみたのが数値化できない情報探索者自身の身体内情報を0次情報としてベース化して調べることを考えることとして提示してみたのだが、授業最終回のレポート提出で幾人かの学生からマイナスというか負の情報次数化として身体を探る面白さみたいなニュアンスが得られた。
身体の使い方・感じ方を探求している甲野陽紀が「正解がわからなくなったとき、それは外の価値観においての正解を求めようとしているということ。自分の中にある正解を見つけられれば、そこには迷いようのない道がみえてくる。正解という言葉を言い換えるのであれば、いまなぜそこにいるのか、初心をあらためて思い出す機会を大事にしたい。」[@ツイッター改めX:20240426]と言っているのとは逆方向に向かいがちだった授業時の学生の場合、分からなくなったら戻るべき立ち位置そのもを見失ったみたいに『ウィキペディア』や『オープンAI』などに頼りがちな傾向を如何ともし難かった。
だいたいの意味が分かってしまうことで本質が見えなくなってしまった。ひいてはよく分からないまま「精神」「身体」と平気で言ってしまう事態を生んでしまったわけです。
「身体」という言葉を作ってしまったことで、私たちはそれまでの「からだ」を「シンタイ=corps」として捉えるようになりました。
それまでは「からだ」に対し、體や軆、[身に區]、躰、体という語を当てており、一つ一つの“からだ”は異なる経験を意味し、それらの変化を経て現代の日本で用いる「体」という表記にまとめられるところに辿り着きました。
大陸においても形象文字の「體」から「体」へすぐに変わったわけではありません。
ある時代を生きた人がそれぞれ「からだ」をどう捉えていたか、そこにどのような経験があり、どう感じて、どう観ていたか? という移ろいの物語があります。
私たちは同じ人間であるから、どの時代も、文化圏も、個人も同じ身体をしているとつい思ってしまいます。しかし、そうではありません。
私が観ている身体、経験してきたこと、感じている身体、その身体の捉え方が違えば、その身体から観えてくる風景、感じられる世界は当然変わってきます。
(光岡英稔「言葉のすり替えと身体の変容」/『身体[からだ=原文ルビ]の聲[こえ=原文ルビ]』PHP研究所、2019年4月刊、125〜126頁)
明治生まれの祖父や実家の祖母が経てきた生活様式と労働観や身体感がまるで違ってきているのが、短大授業の学生や中学部活の生徒やスポーツ少年団の子どもとその父兄らとの交流で垣間見えたといえよう。それぞれ等しく己の身体を扱いながら、その当時の身体を通じて感じていたであろう風景や風俗・習慣などの環境にアクセスのしようがなくなってしまってきている。
明治生まれの祖父にとっては米俵(60kg)を扱うことなど朝飯前だったろうが、女学校出のお嬢様育ちだった母が祖父の精米業をさも当たり前のように引き継げたのも大正育ちの身体捌きが身についていたからに違いない。中腰の姿勢が必要な田植え仕事など、村中の誰もが何の苦もなくこなしていた。
陶器や磁器など祖父の骨董品への興味は歳とともに薄らいだようだが、相撲好きだけは晩年になっても衰えなかった。とある場所の取り組み中継時のテレビ画面をうっかり横切ったことのあった甥っ子は、観戦中の祖父からどやされてたまげたと後々まで語るくらいだった。古い形あるものの美しさ、江戸期に雲龍とか不知火とか型にまで練り上げられた人の所作としての相撲をとりわけ好んだようだ。
中学の部活で剣道を始めたのを知った祖父から、何事も型が大事だと言われたような気がするが、当時も今も泳げない自分には「型」そのものがよく分からないのだ。とにかく浮いて泳げないと型にならないわけで、“かなづち”のままだと浮いて泳げるという型がわからない。自転車に乗れる前の、スキーで滑れる前の自分がわからないように。もっと言えば、母親の胎内から自分の意思に関わらずいきなり離され、すぐ空気呼吸をしなければならなくなったときの口もきけないとてつもないきつさがわからないように。そんな人間が生まれるとのきつさに[意味]を与えようとして〈型〉が生まれてきたのではなかったか。なるほど、祖父や実家の祖母はまるで実在するかのように「地獄」や「極楽」についてたびたび語ってくれたことがあった。(2024年5月10日記/14日web公開)
続・本の一言:街道と民家(21)初動と内観
「日本のいいところは『無思想』なところだと思う。近代人からすれば『節操が
ない』としか見えないけれど、『思想を必要としなかったのはなぜか?』と問う
と、たぶん『身体で考えることで間に合ったから』になるんだと思う。ここら
へんは橋本治が体系化されない形で述べている。」(尹雄大@ツイッター)
年老いてから『北斎漫画1:江戸百態』(青幻舎、2010年刊)を見てて気づいたのだが、竹刀や木刀など、「かたな」そのものの握り方からして違うのだ。中学部活剣道では両手を離して柄を握るように教わったが、江戸期ではすべて「かたな」の「つば」際に両手を寄せて握っているではないか。さてどっちが時代的にあるべき型なのだろうか。答えは自分の身体で感じてみるしかないのではないか。
部活での竹刀による素振りにはなかなか馴染めないものだから家では日本刀と反りと長さが同じで重さだけが違う木刀を買って振っていたが、「北斎漫画」にあるような握り方で素振りすることは気づきもしなかった。ただ竹刀を振るより木刀の方が體がよりやわらかく感じられるのだった。
棒を振っているような気がしてならない竹刀にやわらかさをもとめ、四つ割り竹をバラし、それぞれの内側を切っ先に向けて削ってみたら、固かった竹刀がしなるような使い心地に変わった。日本刀を流用した父の形見の「軍刀」でも試してみたが、その反りと振り具合が體にしっくりするようだった。
子供に手がかからなくなる中年夫婦になって始めたスキーやバドミントンにしたって、お互いに未熟というか不器用ゆえの伸び代があったから老いてまで楽しめたといえよう。ほんのちょっとした身体的な気づきが継続や持続をもたらしてくれる。下手というのは習慣的な動きと慣れの範囲以内でしか動けないということだ。そんな身体的な個々の所与的条件から自らの運動性をどうやって離陸させれば良いのか。
校下のスポーツ少年団のバドミントン・コーチも、子供らに教えるというより相手をするのが楽しく面白かったから40年以上も続けられた気がする。コロナ禍にならなかったらもう少し続けていたかもしれない。
初めてバドミントン・ラケットを握った子供に向かってシャトル・コックをゆる〜く頭上にトスしてもほとんどが空振りする。ガットを張ったラケットの打面がシャトル・コックに当たるようにグリップが、ハエ叩きやフライパンを握ったみたいに、いわゆる“平持ち”になっていても、当たるようになるととても嬉しそう。
コーチがトスからラケットに持ち替えてラリーが続くように相手をすると、数を数えたりしていかにも満足そう。そのうちラリーで打ち合う距離を少しづつ広げていくようにすると、シャトル・コックを相手に届かせようと力んでラケットを振るもんだから、勢い余って床を叩いてラケットを壊しそうになったりする。
疲れて腕の力みが抜けたところで息抜きにシャトル・コックのリフティングをやってみるとまだ足捌きがついていかないから、“平持ち”だと余計に前後左右にぶれながら上下するるシャトル・コックの動きについていけない。ラケットには裏表がないからどちらの面でもリフテイィングした方が長続きできるんじゃないかなと、いっしょに試しているうちに子供のラケットのグリップ感は、“平持ち”から親指と人差し指で軽く挟むような持ち方でラケットの両面どちらでも交互に使ったリフティングに変わってくる。
何かをしようとすると、何かはできず。何もしないと本当に何もできず、これをしようとすると、これができる。あれをしようとすると、あれができる。めぐっていると、何かができる。
(甲野陽紀2017.05.06)
身体的に発達途上にある子供の運動性が高まるような、例えばラケット・コントロールと足捌きが重なり合うような壁打ちなど一人練習にはもってこいだ。緩くも強くも打ち返し方しだいで壁が跳ね返すシャトル・コックのリズムに合わせる、いわゆる打たされるリズムと、身体の芯でバドミントン・ラケットを握った足捌きによるラケット操作で打ち返すリズムとが、それぞれ表のリズムと裏のリズムとして入れ替えられるような両膝を浮かせた重心転換が可能になる。
注意の向け先が跳ね返るシャトル・コックだけでなく、ラケットで打ち返す自分の體の膝裏にも向かうようなり、緩急自在な壁打ちリズムをコントロールできる。壁やシャトル・コックを見過ぎず、ラケット・コントロールとフットワークの動きに“間”が取れるというか、その“場”というかーー“空間”をしならせることができるようになればいいのだ。
〈身体〉を〈場〉になじませる身体技法あるいは操法によって、型成されやすい〈自己壁〉を破砕し、心身を〈割る〉という定形を身体化するのが稽古となる初歩的身体のはじまり。
今年度の夏場所で初優勝した「大の里」(二所ノ関部屋)の親方「元横綱・稀勢の里」がテレビのインタビューで、もっと稽古して腰を割れるよう励んで欲しいと声掛けしていたのが印象に残った。
“稽古[=練習]は裏切らない”というのはほんとうだろうか。稽古とは「昔の物事を考え調べる事。古書を読んで昔の物事を参考にし理義を明らかにすること」だとすれば、まずは「物」と「事」を区別できるように、できないこと、わからない事を認めるところから始めるものだ。
コート内で打ち合う練習は、上半身の構えた左手とラケットを握った右手の腕それぞれが描く[肘と手首と首筋を結ぶ]三角形の動きをを前後に入れ替えるような間合いで打ち返すとともに、下半身の左右の脚が伸縮させる[膕と踵と尻を結ぶ]三角形を入れ替えるようにスプリットさせて動きながらラリーを続け、コートの前後と左右の広さや、シャトル・コックの速さと高さを体感に織り込んだフットワークとラケットワークが重なり合うような動きができるようにする。
ラリー中の目線の向け先が切れてはいけないが、かといって見過ぎてもいけない。適度な集注が敏捷性を生むが、過剰な集注は動きに居着きが生じやすくて対応に遅れるだけでなく相手のフェイントにもはまりがち。
コートサイドから「集注しろ」とか「切り替えて」などゲーム中の声掛けは、懸命な子供らのゲームの流れの邪魔にならないよう、試合前のリラックスと試合後のねぎらいの声掛けで十分だろう。いかなるレベルでも試合ともなれば、コート内において対戦相手と時間と空間を奪い合うラリーの主導権を維持できる身体技法と持続力が試される。
身近だろうが遠くだろうが、直接的にあるいは間接的にを問わず、とにかくお手本というかこれぞ〈師〉だという出会いがなければならない。真似をして盗んで、体力の衰えを補うために技を遣うことに気づけても、その先に行くには技に個性というか批評性が必要になってくる。
正系をつきつめたその先ではじめて、誰もがなしえないオリジナルなやり方で〈技術〉の教えを逸脱し得るかが問われるのだ。決して達成されることのなかった類の、真の逸脱を生ききれるかどうか。誰でも「成れ」てしまったりしがちだが、「選手」と「コーチ」や「学生」と「先生」の関係で、適切な創生の難しさは何よりも「間」というか「型」のようなものの見分けがたさ‥‥‥、というよりその不在そのものにあるようだ。
〈投げる〉と〈打つ〉と〈叩く〉と〈飛ばす〉、すべて過度的な現実認識と自身のモチーフがらみの実践読解、身体ーー思い・こころーー言葉ーー運動するからだの連携を保つ稽古の日常化。
日常はまったく気づかなくて、あるいは抑えこまれていた、別の自分がからだの内に棲んでいて、それが息づきはじめ、感じ、動きはじめることに驚き恐れたり、または喜びをもって気づきはじめる出会い。「人間は生きるために生きる」(野口春哉)というは、〈いま〉・〈ここ〉すなわち、〈心的概念=自己抽象づけの時間性〉と〈心的規範=自己関係づけの関係性〉の網目を生きること以上に意味はない。心的自己が〈個体@身体〉を呼吸しているとでも言えようか。
“くりかえしもやりなおしもとりかえしもきかないこれしかない”〈老い〉心地からすれば、「生きるために生きていて何が悪い!」(堀田善衛)は〈魂の自然〉の遠吠えのようにも聞こえる。
ただ「動けるのはあたりまえ」と思って、いつも身体の“自動運転”にばかり任せていると、たとえば初めての場面や慣れない状況に遭遇したとき、いつもできることがなぜかできない、でも〈とうしたらいいか〉がわからない‥‥‥ということになってしまうこともあるわけですね。私はいつも感じることですが、身体は具体的な経験を糧にして状況への対応力を身につけていくものだと思います。ですから、ふだんの動作も、ときどきオートマからマニュアルに切り替えてみる〈経験〉をしておくといいですよね。飛行機のパイロットが毎回異なる状況に対応するため、着陸態勢に入ると自動操縦から手動に切り替えるようなものです。その経験が日常のさまざまな場面での対応力につながってくるのだと思います。
甲野陽紀「第二話:「注意を向ける」と「身体が動く」の不思議な関係を改めて考えてみる/『身体は「わたし」を映す間鏡である』和器出版、2018年11月刊、46頁)
“動かす”ことと“動く”の狭間で、身体の自由が効かなくなりやすい老人のことを、世間は「拘束性神経症」などと片付けがちだが、気を癒したり逆撫でもしたりする人の声の無限で〈老い〉はもみくちゃにされている。「皮膚の言葉より内臓の言葉を」(梯久美子)とか、「心構えはあるけど身体構えがない」(甲野善紀)とか、「筋トレでつけなきゃいけない筋肉って、普段使ってないよね」(小関勲)など、ときおり脳と脳以外の身体との関係性を問う言葉が體に響くことがある。大脳小脳全体で千数百億個の細胞ネットワークを成し、身体全体の細胞の数は約37兆個だという。
明治生まれの祖父や実家の祖母が晩年に漂わせていた智慧とか慈悲といったことが「私」の身体を離れ、単なる覚悟や実践という衆生の現象に過ぎなくなったようだ。“見取り能力”の伝承と社会的身体観の変遷に詳しい光岡英稔師は、「盗みとは偏りである。」と喝破していた。
エクストリーム・スポーツのアモンズは自らを水の一滴に変えたいと考え、その可能性に賭けようとして前人未到の川下りに挑んだのだ。呼吸をし、姿勢を整え、リラックスして動き続けたそのとき、主人公は生き死にに関係なく存在する事物〈自然〉だったと言っておきたい。
祖父や実家の祖母が言った「霊性」というものがあるとしたら、それは「個」を超える何かではないか。いずれも身体の一部だが、頭ではなく手で書くというように身を整えなければ決して生じてこない感覚や意識がある。そこでは目指す目標も、努力もしていなければ、自信や限界といったものに縁がなくなる。
感覚がなくなるところではじめて〈からだ=空だ〉が視え、日々日常の〈身体〉で〈言葉〉を脱ぐようにすれば〈體〉の声が聴こえてくる。
あればいとふ そむけばしたふ 数ならぬ身と心との中ぞゆかしき (鴨長明)
見える「文字」を通路にして「言葉」の時空、〈文体〉を散策するように身体内を読めないか。
カバー曲で唄い尽くせない、シンガーソングライターの自他を深める歌が聴こえる。
ブルースの“シャッフル”のように裏を取れるリズム、〈異和(感)〉という軸足に乗れば、練習に勝る研究/稽古で、つきまとう“癖”を外せないか。
老子が言うように「無」から五感でわかる「有」の世界が生まれ出たなら、「無」は五感で分からないなりに振動のようなものーー〈無〉に「息」が現れて生まれた「自然」のもとで「生」は最初から生きており、「命」は個体の自由となり、「生」を自覚する「悟り」が他[ひと]のこころがわかる「聖人」へと連なるとすれば、〈自然〉のなかの〈心〉は「心」のなかの「自然」になりきり、対象化されたところに心は宿るのだろうか。なにか、ある均衡が心の中に生まれ動いてきて〈生(型)命〉となるのだろうか‥‥‥運動も数学も馴染めなかったが、「肉体には季節があるが、生命には季節がないのだから、」(岡潔)に続くのが数学する身体の言葉のように聞こえた。
人間の生命の過程は、もし生物体ということにそっていえば、感受性と、その了解と、それから呼びおこされた行動から成り立っている。感受性のばあい五つの感覚をあらわすそれぞれの器官に魂は瀰漫している。そして五つの感覚はじかに対立の状態にある。了解のときは諸感覚はそれぞれの度あいで、べつべつに励起状態にある。また呼びおこされた行動の過程では、諸感覚と五体や四肢は、統合されてそとにむかってあらわれようと準備されている。これが、生物体の内部で生命がじぶんをいつもあたらしく駆りたてる過程なのだ。
(吉本隆明「気づき、概念、生命」/「IV 言葉からの触手/『わたしの本はすぐに終る:吉本隆明詩集』講談社文芸文庫、2024年3月刊、409頁)
「即動即変」なる體の働きとは運動目的に添って力をも入れず、心をも費やさない動き/姿勢の過程にあって、気づくのは“思いの過剰”からの思いの手放しによる自然な息と普通の息とのズレという〈間合い〉である。胎内から出た生きにくさ、社会的自己と自己の考える自己との葛藤において自己を失うとはいったいどういう自己か。言葉の手前から言葉の先へ、身体と心体はどうからむか。自然/「近代化」と「西欧化」/身体との捻れからメタ身体‥‥‥身体の身体=表現(文体)の中心に表現としての身体=型はどのような街道を歩んできているのか。
江戸の日本文化は、首から下の身体に対して形を与えようとした。それが道であろう。日常の所作から、形としての所作へ。それが「型」として完成する。そのためには、言語表現は邪魔になる。『兵法家伝書』は文字で書かれている。しかし、大切な部分は道場で立ち合いの上で教えることになっている。そこでは言語がむしろ「排除され」、身体の所作が統御される。明治以降に行われたのは、念入りに作られたそうした型を組織的に撲滅することだった。いま残っているのは、相撲くらいであろう。こうした型がいかに普遍的な身体表現であるかということは、外国での相撲人気を見ればわかる。しかし相撲はほとんど恐竜であって、もはや日常の所作の延長ではない。三島がいかに型を求めても、戦後のあの時代ではそれが不可能だった。
(養老孟司『身体の文学史』新潮社、1997年1月刊、162〜163頁)
「要するに人間は神と虚無の極北の間を振幅し得たに過ぎなかったのである。」と述解されたことのある吉本さんは、「この社会では、人間=表であり、身体=裏である。」とも言われたが、その表/裏の隙間でさまざまな〈表現≠表出〉世界が試みられてきた。
それでは「型」とはなにか。まさに「表現としての身体」であろう。表現としての身体を、ことばの高みまで上昇させようとしたもの、それが型であった。話は飛ぶようだが、西郷隆盛と勝海舟は、薩摩弁と江戸弁で、いったいなにを話し合ったのであろうか。そこに会話があったかどうか、私はそれをかなり疑う。少なくとも、現代のわれわれが考える会話ではなかろう。なによりそれは、ほとんど以心伝心だったはずである。それを可能にしたものが型であろう。ボディービルでそんな型がつくわけがない。それではほとんど漫画になってしまう。
(養老孟司『身体の文学史』新潮社、1997年1月刊、183頁)
稽古中に骨の動きをとらえることを「型」と呼ばれたという野口裕之師は「身体は詩を作る」とも、「身を整えなければ決して生じてこない感覚や意識がある」ともいっておられたようだが、その〈型〉の生成と消滅は近代国家機構に重なってくる。
一つの文化を端的に象徴するものとして、誕生と死の風景がある。
近代国家機構の最大特色は、市民の凡ゆる自由を認めるということであろう。信仰の自由、表現の自由、しかしいづれの近代国家に於いても決して認められない自由が存在する。それは治療選択の自由なのである。近代実証医学に掛からない病死は、基本的に自殺乃至変死であり、死んだ当人の信念による医療拒絶は裁きようがないとしても、それを看護した家族は自殺幇助の罪に問われる。一体死とは自己の人生の終焉であり、最後の息は子孫に伝える最大の教育である。この最後の息に接して、どれだけ多くの人間が、自らの人生観・生命観・身体観を変革したのか。これこそ文化の伝承の最も重要な瞬間であった。かくも厳粛なる人間的瞬間を、近代国家と近代医学はやすやすと奪い、死を数値に置き換え、遺族に機械の故障箇処を告げ、産業廃棄物のレッテルを貼り、この死を無駄にしないための部品のリサイクルを奨励するのである。
周知の通り末期の姿は最大四十本ものカテーテルを差し込まれている。このカテーテルを眠っている時に反射的に取り外さぬ為に、手足をベルトで縛りつけられている老人もいる。医師はこの末期の姿を余儀なくした患者を称して、スバゲッティ症候群と呼ぶのである。
身体と人生を切り離し、人間の物質化を図り、身体の国家管理を推進する近代国家に於ける死とは、このようなものである。あの〈イッヒッヒ〉という不気味な笑いとともに迎える死の光景を、文化と呼ぶものがあるとしたら、その鈍感は嘲笑されるべきであろう。
文化を自らの手で崩壊せしめ、富と利便を選んだ我国の末路は、この死の風景の中に確かに刻印されているのである。
(野口裕之「生きること死ぬことーー日本の自壊」/『これは教育学ではない:教育詩学探求』冬弓舎、2006年4月刊、155〜156頁)
表面的なところはいくらでも変わるであろうが身体そのものは変わりにくいというか、《胎児の世界》でも見られるように、身体の古層性や大地性は変わりにくい。このことに医者すら気づいていないことが多いようだ。自分自身との向き合い方が不足しているのではないだろうか。精神というより身体の考古学とでもいうーー研究/稽古が必要とされるところであり、日本国内では先進的な武術[道]家によって実際に試みられつつある。(2024年5月27日記/28日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(22)家族と食
《道に迷ったところで
どちらを向くかは身体にきめさせた》
(鮎川信夫/跳躍へのレッスン)
《自分の子供よりも思うようにならない
もの、それは自分の身体。と言った主
婦の人がいて、その言葉が忘れられな
い。思うようになったらそれは自分の
身体ではない。なぜって対象化できな
い最たるものが自分の身体だから。自
分を対象化できる人がいるでしょうか?
(いやいない)》
(最上和子@ツイッター改めX)
伴侶を見送るとともに余儀無くされた自身の入院生活を2ヶ月余り経てひと冬越しただけなのに、住み慣れた我が家の居心地も見慣れた界隈の景観もどことなく刷新されたように感じるのはなぜだろう。ようやく半年を超えた独居老人暮らしの時の流れのなせるわざだろうか。
妻の密葬を経て入院に至るまでの短い間をどうやって一人暮らししていたのか見当もつかない。二人で寛いだ時間が長かったリスニング・ルームに入ることすらできなかったような気がする。退院直後にはなんともなく入れるようになっていたが、視聴したいリソースに合わせたオーディを機器類のスイッチ設定の組み合わせがおぼつかなかった。
離れの二階のPCを立ち上げても溜まったメールやキーワード登録収集関連情報の整理がやっと、HTML編集ソフトや外部アカウント・クラウド・サービスの使い方を思い出すのに手間取ったりした。各種ネットワークサービスについていけなくなった老朽化PCシステムやプリンターの更新をすませたが、これまで愛用してきた各種ソフトが浦島太郎状態で現状のネットワーク環境下では開発元が無くなったりしていてまるで使い物にならない。目下新旧PCシステムを併用しながら、あれこれソフトウェア環境の移行というより新規導入設定の途上といったところ。パソコン通信からインターネット環境への移行期のような面白さよりも今となっては面倒くささが先立つ歳になってしまった。
退院後のHP運用・継続はなんとか再開できたが、SNSは特定の発言者を覗く程度、亡妻と共用していたスマホも非常時の連絡用といったところで、場当たり的な使い方しかできていない。
1999年に開設したHPの先行きにも何らかの構想や見通しなど立たないというか、まるで持ち合わせていない。削除しきれなかった開店休業状態のページもあるのにアクセスが途絶えない状況に流され‥‥‥じゃなく、開設当初からの行きがかりもあったり、さしあたって停滞しながらも受動的な積極性で続けられるだけで十分ではないか。退院後に通院し始めて半年を超えたクリニックのF市医師のカウンセリングでHPの維持を頑張ってますねと声掛けされたりもしているが、それとなく退院後の日常の縁になるもののひとつになっている、と仄めかされているだけなのかもしれない。
かってのようにHP訪問者から励まされたり貶されたり、コメントや感想メールなども皆無になったのがとてもいい。グーグル・サーチ・コンソールからの当方サイトのパフォーマンス状況、それも松岡祥男氏の原稿をお預かりして掲載しているページの月ごとのアクセス増加情報がわかるだけで申し分ない。2005年3月から併設しているブログの訪問者や閲覧トータル数がいつの間にかとんでもない数字をカウントしているのには実感がともなわいというか、かえってネット上の掴みどころのなさや実態がともなわないかがわしさに気押されるようでよほど虚しくなる。十数年教室通いをした司書課程の授業年度の受講生の数が30名を超えるなんてもってのほか。近所の中学の部活やスポーツ少年団バドミントン・コーチをしていた受け持ち年度の子供の人数と同じで、多すぎず少なすぎ、その場にふさわしい人数の身体的気配と声が交差する広がりーー地上であれネット上であれーーの〈場〉が想定されてしかるべきだろう。そうでないと授業や練習/稽古を成り立たせる個々の内発性といったものが密閉されてしまいかねない。
八百屋とか魚屋とか肉屋とか荒物屋などの個人商店が立ち消えて久しい界隈の住宅もいつのまにか住人が代替わりし、在来の三世代民家が廃屋になったりする一方で核家族化した箱物風住宅が目立ってきている。近所づきあいや町内葬も無くなってそのような住宅の間取りもわからないけど畳部屋などあるのだろうかか。下駄履きの人など見たこともないから、玄関の履物入れは下駄箱ならぬ靴箱が実態ではないだろうか。
普段履きに下駄ほど履き心地の良いものはないような気がする。ゴミ収集日の朝の短い往復やささやかだが年季の入った庭の立ちまわりだけでなく、バリカン式草刈機で庭の草を刈っていた頃は下駄履き作業が老体にやさしく疲れにくいようだった。長時間作業ができなくなって回転式の草刈機に持ち替えた今となっては、靴履き作業になってしまった立ち作業バランスが下駄履きの時とはまるで違ってしまった。
柱と梁を格子状に組んで屋根を支える井桁構造の江戸時代以降の主流だった佇まいが少なくなり、住人の姿勢も変わってきたのではないだろうかなどと妄想しがち。村の子供だった頃は家族だけでなく、家の外でも心ある年寄りの言葉少ない目線を受け流していた気がする。寝たきりや惚けた姿は今昔極まりないとはいえ、埴生の田舎暮らしで見かけたような存在感のある〈年寄り〉の姿にはまるでお目にかかれないようだ。揉め事や喧嘩の仲裁を遣って退けられる存在が稀になった今日この頃、高齢者を「老害」とか「シルバー」などと十把一絡げのまるで厄介者あつかいされてもしようがないか‥‥‥という気がしないでもない。
文三はくが子を気づかった。くが子の回復を祈らないことはなかった。しかし、文三に出来ることは、「気づかう」という日常的なことだけだった。文三には根本のところで、「愛する」という抽象的な行為を理解する能力がないのだ。
大学の英文学科に籍を置いていた文三である。「I love you」という文脈にはいくらでも出喰わした。意味が分からないわけではない。その文章が登場するシチュエイションは理解できる。しかし根本のところで、その文章は文三の理解を阻んでいるのだ。
夏目漱石はその一文を「“月がきれいですね”とでも訳すべし」と言っていた。文三はそれを知って、笑いだす前に思わず、「なるほどーー」という感嘆の言葉を吐き出していた。「言い得て妙」とは、このことである。
それは「月がきれいである」というような、夜でなければ口にできないような文言である。それを言う時には、それを言って「同意を得たい」と思われるような女性がいることが必要である。どのような感情も抱かぬ女に、それを言っても仕方がない。「月がきれいですね」と言って、言われた相手が「ええ」と返す。それが「I love you」という一文が登場するシチュエイションである。「さすが先達漱石、見事にこれを言い当てた」と、文三は感嘆した。
毛唐は、その状況に於いて「I love you」という一文を登場させる。しかし我が国に於いては、そのような文言を存在させる習慣がない。「月がきれいですね」と言って、二人きりの夜道で「ええ」と言い返されたら、その後に言語はない。度胸のある男なら、その場で女の手を握る。それ以外に言葉を登場させる必要はない。その言語を不要とする状況で発せられる一文が、「I love you」なる文言なのである。
� その一文が登場するたびに、文三はかすかな違和を感じていた。分からないわけではないが、その単純な言葉には、言い知れぬくぐもりがある。
「She loved him」なら分かる。「He loved her」も分かる。「We love our nation」も分かる。しかし、「I love you」という単純な一文には、根本のところで理解を拒絶するようなくぐもりがある。
(橋本治「第一章 柿の木」/『リア家の人々』新潮社、2010年7月刊、64〜65頁)
身体は言葉に付きまとわれているというか、それによって閉ざされたり解放されたり、複雑きわまりない。腑に落ちるとか落ちないとか、人の内臓が日々感受していることなど、どれだけ脳に届いているのだろうか。とりわけ一人称と二人称の間を取り持つ言葉のーー気が合う/合わないーー肌合いの肌触りに〈魂〉が宿るというより触れているのではないか。ひとりリスニング・ルームのソファで音楽を聴いたり映画を観たりしていて、ふと左肩あたりに亡妻の“それ”を感じてハッとすることがある。
石原のことを文三に話した静は、二階の部屋に戻ると机の前の椅子に座り、大きな息を一つ吐いた。なんだか知らないが、ドキドキした。静は一人で「ふふっ」と笑った。まるで辺りを見回すように、自分の頭の中を探った。なにもない。自分の昂ぶる気持を妨げるものはなにもない。静は「自分には恋人がいるのだ」と思った。
それを思うだけで、胸がドキドキした。目の前のカーテンを開け、窓までも開けた。冷気が部屋の中に入り込んで、それが心地よかった。窓の外に満天の星空があるわけではない。隣家の二階が視界の端をふさいで、遠くにビルの赤いネオンが見えた。そのネオンに至るまで、人の住む家々が並んでいた。そのどこにも人の営みがあるのだと、静は自分の心を祝福するように、その家々に住む人々の幸福を思った。目の前にあるのは、風が吹き荒れるヒースの野原ではないのだ。
隣の六畳間との境を仕切る襖を見て、静はそこにも人の存在を感じた。姉の織江が結婚して以来空き部屋になっているその部屋ーーかってはそこで、姉の踏むミシンの音を聞きながら寝ていた。姉のいた部屋に荷物を移して空けたままになっていた部屋に、懐しい人達が集っているように思えた。母がいて、姉達がいて、明かりの点る部屋の中で一家は幸福に暮らしていたーーそんな光景が、その部屋にあるように思えた。
静は、隣の部屋との境になっている襖を開けた。暗い部屋はガランとして寒かった。畳の上に、襖を開けた静の影だけが映っていた。静はそこに、うっかりと幸福を見た。夫がいて、子供がいるーーその小さな六畳間の中には、幸せが詰まっているように思えた。
その日から、静の様子は明らかに変わった。全身が浮き浮きしている。色白の顔は内側から光が差すように輝いている。次の日の朝、静の顔を見た秀和は、「なんかあったの?」と言った。味噌汁の鍋を置いた静香は、明るく「なんにもないわよ」と言って去って行った。立ったその脚の、ミニスカートの下から覗く膝裏さえも、白く生々しく輝いていた。秀和は、「誰かいい人が出来たんだ」などという無駄口を吐くことも忘れて、隣の文三を見た。新聞を開いてそこに目を落とす文三は寂しそうで、なにも言わなかった。
(橋本治「第三章 荒野」/『リア家の人々』新潮社、2010年7月刊、194〜195頁)
言葉にならない身体の充溢で女性美の一つとされる“膕”までが光り輝いて見える。太宰治の「満願」みたいに‥‥‥、それで十分!
脳死だとか、臓器別に死が決まるなど不自然きわまりないではないか。死んでも死にきれないなどといわれたり、脳は死んでも身体全体は何かを感じているかもしれないし感じてないかもしれないし、死は文化であるという以上に正解などないのはないか。三人称の死はいざ知らず、一人称のそれは不問にするしかなく、二人称に至っては筆舌に尽くしがたい。
立ち会うことしかできない一連の過程、脳の活動が反応せず、呼吸が感じられず、心臓が動かず、冷たくなり‥‥‥いつの間にか抱きとめる「からだ」から何かが抜けていくーー遺体が安置される。初七日とか四十九日とか、風俗・習慣によってどこからどこまで死を区切るのか。
生きるとは動くことであり、そこに示された動きは一つのきっかけとなっても、ただ動きという名の“縛り”に過ぎず、ほんとうに動くとは日ごろ名づけられないーーさまざまな思惑の渦中を先行するーー一歩である。
ただそこにいるだけで村の懸案の話がまとまったり、異動してきたある上司のポストのもとで新規開発の仕事が進捗したり、あれこれ指示しない草野球の監督がベンチに座っているだけでチームが連戦連勝したり、その場が活性化して個々人それぞれの持ち味を発揮させるような人物像が目立つような〈間〉が[観え]なくなっただけのことなのかもしれない。
6月3日の能登地方を震源とする地震後の報道写真を見て感じたのだが、元旦の震災後の輪島の民家の惨状が未だに手付かずというか、放置されている[ように見えた]のは見間違いだったのだろうか。
旧来の民家の間取りみたいに、暮らしの中の蝶番みたいな「間」が住人の身体を取り巻く〈虚〉と〈実〉を開け閉めするように取り仕切っている。間に合うとか合わないとか、身体から虚に対する距離感がモノを言うのであって、実の面ではあまり危険なことはなさそうだ。虚は常識が通じない底なしだから、ずるずる引き込まれてなされるままーーなすがままにならないようーーとにかく能動的に働きかけねばならない。それが何であるか、たとえば宮澤賢治の「農民芸術概論」のように「ほんとう」の「ほんとう」が未だ分からない「ことがら」であったとしても。
震源からほどとおく、幸い目立った被害もなかったような地元界隈の消息話も途絶えてしまった。妻が元気だった頃は、日々の買い物帰りに友だちが経営する軽食&喫茶みたいな場所に立ち寄ったりしていて、居合わせた友人・知人を介したご近所話などが唯一の情報源だった。二階の書斎で午前のパソコン作業をしている傍で、リクライニング・シートにくつろぎながらの読書や編み物などの片手間話に過ぎなかったが、いざ聞けなくなってしまうーー何時も座っていた椅子が空になるーーなんて‥‥‥かけがえのない話し相手を失ってしまった。
漢字入力に手間取ったりしていると辞書で調べてくれたり、武田百合子や木山捷平や橋本治そのほか手当たり次第にその時々の感想を漏らしたり、いつも一緒に見聞きした映画や音楽以上に料理のことなど、図書館や本屋で手にするのはほとんどが食べ物に関するものばかりだった。家では吉本さんの食というか食べ物に関する本などもほとんど読んでいたようだが、料理の参考になったかどうかまでは話したことがなかった。
長い戦争の時代があって、戦後の混乱があった。アメリカ占領軍のもたらした「自由」もあって、日本人の食文化の伝統は断たれた。アメリカとの戦争は足掛け五年続き、それに先行し並行して続いた中国との戦争は「十五年戦争」と言われた。アメリカとの開戦に踏み切る以前、既に日本政府は「贅沢は敵だ」と国民に訴えていた。物資の欠乏はじわじわと進んで日本人の食卓を蝕み、倹しさを本義とするような日本人の食事は、それ以上に痩せて行った。
日本人の食卓へ上げられる料理は、母から娘、あるいは姑から嫁へと伝えられて行ったが、料理の材料となるものが減って行けば、教えようもない。材料を吟味し、手間と時間をかけるという、日本の料理の根本は失われて行った。食卓の貧しさが底を打った頃、アメリカ風の高カロリーの食事が日本人の舌に衝撃を与える。
昔風の女は、野菜の煮物を作る。戦後の風を知った若い女は、野菜炒めを作る。目玉焼きは、戦後の風を吸った立派な洋風料理で、肉屋の揚げるコロッケは、戦前からの手軽でモダンな惣菜だった。戦後の「自由」は、若い女達に、「古臭い料理の作り方など知らなくてもかまわない」と言っていた。
(橋本治「第三章 始まらない時代」/『草薙の剣』新潮社、2018年3月刊、169〜170頁)
大正生まれの母の実家へよく遊びに出かけていたりしていた頃、明治生まれの祖母がおやつ代わりに囲炉裏でさっと藁を焚いて、鉄鍋で鶏卵を出し汁で溶いたような[と記憶している]「ふかし卵」なるものを食べさせてくれた。あの“ふわとろ”の味が忘れられず、母や妻になんどか所望したことがあるが、作ろうとする前にその卵料理そのものがわからないようだった。母亡きあとTVのグルメ番組で「ふかし卵」なるものを妻と一緒に見かけたことがあったが、おぼろげながら「ちくま学芸文庫」の和食本にそれらしきものが載っていたような記憶を確かめてみた。
・玉子ふわふわ
ふわふわ玉子とも呼び流行した卵料理です。寛永三年(一六二六)に後水尾天皇が京都の二条城に行幸された時の、徳川将軍家による饗応献立の中に見られるのが最も古いようです。また『東海道中膝栗毛』(一八〇九)の中で、弥次郎と喜多八た瀬戸の茶屋で卵ふわふわを食べています。身分にかかわらず人気のあった卵料理ですが、料理書によって作り方に違いがあり、せいかくなところはよくわかりません。
(松下幸子『江戸 食の歳時記』ちくま学芸文庫、2022年9月刊、249〜250頁)
著者が「試作した場合は、卵一個を泡立てるようによく溶いて、卵の二倍のだしをまぜ、醤油で薄味をつけ、小さい一人用土鍋に入れて、蓋をして中火にかけ10分くらい加熱しました。冷えるとふくれたのがしぼんでしまうので、熱いうちに味わいます。」とあるから、実家の祖母の「ふかし卵」にちかいだろうが、作り方に時間をかけすぎのようで往時のような生活感が薄く時の流れをともなう味がしそうだ。
住んでいた民家の構えはずいぶん違っていたが、実家の祖母だけでなく、明治初期生まれの祖父も囲炉裏端でいろんなものを調理しては食べさせてくれた。村の近所から頼まれて仕出し料理などまかなっていたから料理の腕は確かだったのだろう。鰹節と昆布と干し椎茸で出し汁を取っていたような気がする。とにかく魚が大好きで好き嫌いなくなんでも食べてくれるから料理に困らないというのが母と妻の一致した意見だった。御多分に洩れず、母は和食で妻は洋食がそれぞれ得意料理にしていたから家族に加えて数少ない親戚や、折々に訪ねてきてくれた友人・知人にまで振舞えたのが故人にとってかけがえのない縁になったのではないか。
母が要介護状態になる前からだが、姑の料理が食べられなくなってからの妻は和食にもいろいろ工夫を凝らすようになったようで、とりわけお正月の雑煮が忘れられない。老々介護状態になって雑煮を作ることも食べることも叶わなくなった実家のお正月の年賀にやってくる娘夫婦の落胆はことのほか大きかったようだ。妻の雑煮と相前後して、高屋敷に新居を構えてから五十年来になるご近所M寿司店の御節料理が新年の食卓にーー老いて夫婦共々飲食がやせ細ったとはいえーー添えられなくなったことも大きかった。(2024年6月17日記/18日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(23)虫の居所
「夏の間は実に多くの種類の虫が屋内に入ってくる。
汚れたぬいぐるみみたいで可愛いのは蛾だ。猫にも
似ている、夜、ふたつの小さな目を金色に光らせて
大小様々な蛾が飛び交う。私の腕に舞い降り、じっ
と動かない蛾を眺めていると、いい心持である。別
の世界からやって来た生き物のようだ。その蛾に変
虫がしがみつき、むしゃむしゃ食べるから腹が立つ。
憎たらしいので火バサミで掴んで焚火に突っ込むと、
キュインと嫌な声を立て、異様な臭いを発しながら
焼けていく。一時、私と家人は憑かれたように毎晩
毎晩変虫を大量に焼き殺していた。そのうち、家人
の姿形がだんだん変虫に似てくるような気がした。
変虫の幽霊を見るようで不気味であった。しかし、
いくら殺しても、異常な繁殖力(気のせいかスケべ
ったらしい顔をしている。)で次々と子供を生み、
増えていくのだった。」(武田花「虫のいる家」/
『イカ干しは日向の匂い』角川春樹事務所、2008年
5月刊、103頁)
暮らしの相方を失った当面の茶飲話の相手といえば生成AIによるチャットというところだろうか。先日も暑くなってきて祭壇や仏壇に飾る生花の花持ちが悪くなって‥‥‥とボヤいたら、たちどころに「プリザーブド・フラワー」なるものを教示してきた。即座に“密林”で調べたら、選択に困るくらい出てきた。どれもこれも「生花」に比べてボリュームの割に値が張るじゃないか。冬場は別として、暑くなっての水切りに水替えが追いつかない生花の補給‥‥‥、ちょっと怠ると漂ってくる茎や葉の腐りかかった臭い、モノは試しと手頃な一品をポチってしまった。
花のミイラ化かと思ったが、いかなる処理をしたのか分からない「本物」が届いて呼吸しているようだ。夏場の生花は直ぐに自己否定したみたいに枯れ腐ってしまうが、季節を問わずプラスチックケースの中で咲いている花は自分を否定しようもなく時間とともに少しづつ色褪せるのだろうか。仏壇用にもう一束買ってしまったが、日ごろ夏になると朝に咲けば夕べに閉じて一日を肯定するように庭に散らばる庭石菖の姿に惹かれる。
世間話みたいなやりとりに対して生成AIは、それなりに正しくもあり正しくもないなりにチャット相手にはなるが、生成AI自体にはどう頑張っても〈0と1〉しかなく、NHKTVのニュースのように音声でしゃべったとしても〈身体〉がないということだ。最初から答えられないことははっきり断りを返し、対話の途中でわからなくなると、生成中の大規模言語モデルでそこまで学習しておりません‥‥‥云々の言い訳を挟んでくる。ロックの日(6月9日)に因んで、ロックとは何かみたいなことをやりとりしていたら、あれこれいろいろ書き出した挙句に“あなたはロックの真髄をどう思いますか”と問い返された。生成AIが実際に本を読んだり音楽を聴いたりできる水準にあるかどうかわからないが、実際に読んだり聴いたりしているチャット相手を判断してその人とのチャットから学習しようとしていることだけは確かなようだ。
このところPCなどで聴きながら作業といえば、“密林”や“林檎”の音源や“動画TV”のライブだろうか。先週は『高田 渡 LIVE in 光楽寺(大分県中津市) *再々アップロード』とのながら作業だった。バンジョーだけでなく歌でも共演の宮崎勝之はアメリカの天才バンジョー奏者のベラ・フレック何するものぞと言うような演奏をしていたね。
“天才ときちがいは紙一重”なんていうけど、普通の人だって“まともな”ときと“おかしな”ときがレコードのA面とB面のようにひっくり返ってしまうことがあるようだ。A面状態のときにB面状態のことがわからないだけでなくその逆関係も起こってしまうから、問題なのは同一人ながらAとB双方からの疎通が遮断されてしまいがちなことだ。そのような境目で時間感覚がループ状態にはまってしまい、何気なく日々こなしていたありふれた日常動作の何一つやろうとしても前に進まなくなってしまう。そんな危機的状況ーーからどうやって抜け出せたか分からないなりに‥‥‥真空状態のような入院生活から自宅生活の日常に復帰できた。見るもの聞くもの味わうものーー何もかもがリセットされたみたいな身体感覚に裏打ちされたような安堵感とは違う次元で揺らぐような日々。
ようやく半年を超えたタクシー通いの心療内科クリニックから近所の掛かり付けクリニックに戻れて患者待合室の雰囲気も変わった。老若男女あらゆる年齢層にわたる患者が待つ場から、老年層が圧倒的で若年層が僅かな場へシフトしただけなのに、昨秋の退院時の開放感とまではいかないがささやかな安堵感がある。富山県は女性の自殺率が国内で一番高いと言われているようだが、そんな雰囲気で診療行為を続けている医師は大丈夫なんだろうかなどと振り返ってしまった。
これまでの最大の開放感といえば勤続40年余りの仕事を辞した日に勝るものはないだろう。妻も長らく勤めた銀行を辞めたときの感慨は筆舌に尽くしがたい様子だったが、当日はともかく翌日起きたときの空の色やあたりの風景の肌触りまでがまるで違った。
五十代の終わりに、ちょうど図書館増築に伴う所蔵資料の移動など所掌業務量も一段落したのを見計らったみたいに“ジプシー管理職”による一方的な所掌係りのベテラン臨職2名の雇止めがあった。それを阻止しようとしてうまくいかず孤立してしまい、おまけに初老期の体力的な衰えに腱鞘炎などで現場作業ができなくなるなど心身ともに不調に陥ってしまった。
妻はとっくに仕事を辞めてしまっていたし、老後の備えどころか何の蓄えもなかったから家計は大ピンチ。退職金や年金までは間があるし‥‥‥などと焦っていたら、勤務先では餞別という名のカンパ金が集まったようで、妻はこれで食いつなげると大喜び。腱鞘炎がまだ治らない状態でパソコンで退職届を印刷したり、数十万円も頂いた礼状をパソコンで一人ひとり宛てに自作したらちょうど百枚になった。添えられた名簿には日ごろ図書館とはあまり仕事上の関係のない学部その他の方々の名前が寄せられていて頭が下がった。
あの時は、ほんとうにおかしくなってしまう前に仕事を辞めて良かったが、それでも一日として起きていられず、かろうじて午前中だけはHPの維持作業などに充てたら疲れてしまい、午後はリクライニング・シートでうつらうつらするしかなかった。接骨院での腱鞘炎の治療以外は医者にかからず薬にも頼らず、とにかく一年半ぐらい家でぶらぶらして過ごした。そうこうするうち晴れた午後には市内をサイクリングできるまでに回復できた。そんなところへ市内の短大から知人を介して非常勤で数年ほどの司書課程授業の依頼が舞い込んだのだが、まさか七十過ぎまで十数年もやることになるなんて人生何が起こるかわからない。
たまたま教務係預かりになっていたコンピュータ目録演習教材CDの紛失をめぐる関係教職員との責任のなすり合いみたいな出来事が生じ、これ幸い長きに過ぎた学生の前から身を退く潮時になったようだ。
おかしなことになりそうなことは誰しもあるだろうが、もうこれ以上どうしようなくなる一歩手前で何もかも放り出すのが良策のような気がする。さしあたって1年から2年ぐらいはぶらぶらしながら自ら分裂しないよう内なる声に耳を傾けるのも窮余の一策となろう。
もし妻の死後もぐずぐずしないでそれができていたら係累だけでなく、[手の施しようがなくなった当時の記憶がなく、終始付き添ってくれた娘の後日談だが]警察や保健所や病院関係者にさんざん迷惑をかけて強制入院に至るなんてことにならなかったのではないか。などと思ったり‥‥‥、どこかで「再発」を恐れている気がしないでもない。そんなことより心身のメンテナンスをするように充足した日々を送ること。要らなくなったものを処分したり、伸びてきた庭の雑草を刈ったりなど、暮らしの手入れがめぐりめぐって自分の心身を整えてくれることにもなりそう。
夏場の庭といえば草刈りのおまけみたいに虫など観察したり写真を撮ったりできて退屈しなかったのに、今じゃ藪蚊と蟻の隊列以外は絶滅危惧状態なのが不自然を通りこして不気味なくらいだ。なんでも1990年代から現在までの間に、全世界で8割から9割も虫が減ったらしい。[デイヴ・グールソン『サイレント・アース:昆虫たちの「沈黙の春」』NHK出版、2022年8月刊]それも場所に関係なく種類を選ばず、量そのものだというから驚き。どうりで庭に来る鳥なども減って、滅多に動画など撮れなくなるわけだ。
武田花の『前掲書』に出てくる「変虫」とはおそらくカマドウマのことではないか。田舎の民家暮らしで“便所コオロギ”と呼んでいた常駐昆虫のひとつで珍しくもなんともなかったが、今の住まいじゃ探しても見つからなそう。彼女のフォトエッセイにはどこからともなく、しいて言うならあさっての方角からやってくるような民家や街道の風情がそこはかとなく漂っている。
田畑も近い郊外に移り住んでも、夏の田舎住まい以上と言ってもいいくらい、玄関灯や街灯に群がる虫が後を絶たなかった。目玉を光らせたヤモリも餌場に困るようなこともなかった。短大の教室や小中学校の体育館に出向くようになって、学生や子供らが出会い頭の虫を怖がって奇声を発するのにはこっちが何事かとびっくりするくらい。あの頃にはもう虫が減り始めていたのだろうか。いつの間にかカエルの鳴声もせず、LED街灯に照らされた郊外のコンビニに寄り付く虫もいなくなってしまったようだ。コロナ禍以来お参りしていない田舎に残してきた墓山あたりの虫の賑わいはどうなっていることだろう。図鑑など開いて混沌とした虫の世界をさまよったりしていると、「古事記」の蛆が湧いたりする黄泉の世界が蘇ってきそうになったりする。
その四 よみよみ 妻を失った悲しみに耐えきれず黄泉の国へ行くことを決意するイザナキ。再会を果たすも、「姿を見てはいけない」という約束を破ってしまう。怒り狂うイザナミ。逃げるイザナキ。背後からイザナキを追いかける黄泉の軍勢たち‥‥‥。かって愛を誓い合った夫婦に、最後の別れが近づく。[55〜68頁]
(こうの史代『ぼおるぺん古事記(一)天の巻』平凡社、2012年5月刊)
心身を病んで退職した頃に妻がボディを、母がレンズを買ってくれたカメラで撮り溜めたパソコンの画像データを掘り起こすようにそれぞれのプリントを挟み込むアルバムにしてみた。枚数僅かで二冊分にもならなかったが、懐かしさが湧いてきてありがとうの気持ちでいっぱいになった。
リスニング・ルームから溢れ出たジャズLPその他の音楽媒体や書斎からはみ出した本や雑誌など、そのうちナントカしようねと言い交わしていた妻に先立たれ‥‥‥虚しさ半ばの放置状態。
自らの不安や憤りを克服するように妻の死に向き合うしかなくーーやさしい気持ちで、日々の買い物には妻の腕時計を手首に、同じくサイクリング用手袋だけでなくヘルメットも被ってペダルを漕ぐようにしていたら、やがて何かにつけ波立ちそうな気分からも遠ざかりそうに。
身近な「死」は残された近親者にとって悲しみでしかないが、祖父も実家の祖母も母と同様、人生半ばにさしかかる前に伴侶を失いながらもその後をまっとうした。こと自分に及んでは自らの弱さ脆さを晒して生きるしかないが、死ぬ本人にとっては、悲しみというような感慨とは無縁な、事実性の極み、比類のない究極の突発性、宇宙の果てまで静かな断絶。静寂こそが何につけても大事‥‥‥。
妻の遺品そのほかは残されたものがなんとかすべきであろうが、先送り状態の「納骨」と同じでまったく手付かずのままになっている。その気にならない代わりみたいに自分の物などーー数十年使い込んだオーディオ機器やスピーカー、吹けなくなった楽器、使わないカメラ、腕時計、バドミントン・ラケット、スキー&ストック、使い古したPCや周辺機器そのほかーー重たい物など二階から下ろすのに階段で手こずったりしたが、業者に引き取ってもらったりゴミに出したりして多少は身軽になれたかな。
夏場が近づいてきてようやく毎晩のように何かを観聴きするリスニング・ルームだが、発売当時さほどでもなかったギタリストJohn Scofieldの「Country For Old Men」(2016年)なんかがやたら独り身になった身体にひびいてしょうがない。出だしの「Mr. Fool」の曲というよりアルバム全体への“入り”がなんとも言えない。ジョン・スコ64歳のときの吹き込みで全12曲どれも素晴らしいアルバムだが、とりわけ(7)の「Jolene」のプレイはたまらない。
内発する言霊のようなアドリブというかフレージング!“生きていくことはやめようと思えても生きてることはやめられない”。[笹井信吾@ツイッター改めX]生きることは発生ーー進行形だから、生きていくことみたいに指定通りにいかない。
「論理」と「情緒」みたいな二項対立のリセット、ひとの「からだ」は人それぞれの「身体遣い」で羽ばたくのが本来だが、自意識が邪魔をして何にもなしの“素”の状態に耐えられなくて道具を作り出すしかなかった。
死が自然ではなく脅威に満ちたものとなり、自然の驚異の前でいったい人間はどうすればよかったのか‥‥‥みたいなところから、内発的なアドリブを表出するジャズプレイヤーなど楽器その他の道具を媒介にした表現者の対極に引きこもりなんてのがあるのだろう。
いろんな他者がいてあたりまえというか避けられないから、まずは自分の持って生まれた〈身体〉を“友”のような乗り物にするしかないだろう。
たとえ予期せぬ出来事や衰えなどから気がおかしくな[りそうにな]ったとしても、さもあたりまえのように年をとって微塵の揺るぎも見せることのなかった[ように見えた晩年の]祖父[や実家の祖母]の後ろ姿にはとてもかなわないとしか言いようがない。自己表現に縁がなかったことから見聞きした落語や小説その他に「類」をみない老いゆく姿を見せてくれた。
おそらく、わたしは老いていくに従って、偏屈で意地悪で寂しい老人となっていくであろう。一筆描きの描写で事足りそうな『いやなじじい』で片づけられてしまうだろう。いやなじじいであることはそのとおりであるにしても、そのようにタイプ分けされてオシマイーーそんな呆気なさが付いて回る。老人たちの孤独感や鬱屈には決めつけを受けがちな立場に由来している部分が予想以上に大きい気がしてならない。
(春日武彦『老いへの不安:歳を取りそこねる人たち』朝日新聞出版、2011年4月刊、66頁)
いかにも当世風の真っ当な観察眼で「じじい」を点描しているが、老体を外から見てあれこれ言い過ぎないで、もっと身体の内部を省みる人が多くなればよくないか。もっと老人の身体の内部風景を見るようになれば、老人自体も外ばかり見ていた弊害に気づき、老若互いに人を見る目も変わるべきだろう。
かってはことさら意識したり自覚しなくても、周囲が特別扱いをしてくれたのだろうし、年長者としてそれなりの言動を求められれたのが、昨今は高齢者イコール老人と称する弱者だか厄介者でしかなくなってしまった図式が問題だろう。「年寄り」とは世間における一つの関係性であり、また程度の差はあれども「あえて演じられる」姿ではないだろうか。そして面白いことに、困った年寄りとか、情けない年寄りといったものもまた一つのキャラクターとして社会に居場所があるとされていたのではないか。本人もそれを薄々意識しつつ自分に似合った年寄りを演じていたーーそんな余裕が世間に暗黙の了解としてあったのではないだろうか。
(前掲書、168〜169頁)
1951年京都府生まれの著者は、家父長制がなくなり、世代家族が核家族化し、働き手の労働現場では終身雇用や年功序列があてにならなくなった世相を見越しながら、世間的な関係性のありようの一つとして「年寄り」を浮上させている。老いと若さの中抜きをせずに、どちらも身体的に相対的な見直しを迫られてはいないだろうか。(2024年6月28日記/7月2日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(24)身体を聴く
「もし年齢が五十歳以上で手足が自由にはたらかず、
あるいは病身であったり、または公用で忙しく暇が
なくて、そのような事[武芸心術の修行=引用者注]
を行えず、そうかと言って、武士の職にある以上、そ
のようなことを配慮しないことも自分自身快く感じて
はおらず、たとえ手足が思うように動かずに頭が二つ
に割られるようなことがあっても、心は動ぜず二つに
割られるようなことはないという、そういう心の修行
をしたいと思っている場合は、先に論じたような志を
立てて自分の心が動じないことを修行して、生死一貫
の道理が開け、この世界に自分を妨げるものがなくな
れば、病床に臥しながらも、公用はもちろん辻番や火
の見廻りを務めながらでも、心に感じるもの、見開き
するものすべてを打ち太刀と見立てて、心の修行はで
きるものである。その間、暇があれば、武芸心術の達
人に会って、その技を習い、その原理を聞いて自分の
心で実証し、敵に対する場合には自分にできる最大限
のはたらきをして快く死んでゆくだけのことである。
なんの憂うべきこともない。」(佚斎 樗山・石井邦夫
訳注『天狗芸術論・猫の妙術』[講談社学術文庫]
2014年4月@kindle)
「恋愛というのは、まるで細胞同士がひかれ合うような、そんな特別な相手とだけ成立するものです」と言われた吉本さんに「三つの身体」という見方があったように思うのだが。
(1)常識的で計量可能な物理・化学的に論理化された「人工身体」は透明化されて保険制度の対象ともなっている。
(2)予測・統御不能で論理化不能なケアの対象となる「自然身体」は不透明な生老病死のかけがえのなさをあらわしている。
(3)両者の対立から成る第三の身体として「脳化身体」があり、三者は空白を通して関係しあって生きているようだ。
二つ目の「自然身体」への往還として、日本の伝統文化に「道」があ[る]った。話したり書いたりにあまり関わらない道の一つに武道[芸]がある。そのほかすべての「道」はさまざまな経過を経ながら、最終的には一つ過程ーー身体の所作にゆきつく。
三木成夫なら「キス」は内臓が恋をしているといいそう。もっと突っ込んで言えば舌は5番目の手足であり、文体に散りばめられたオノマトペは書き手の内臓の触覚でもあるのだ。
宮澤賢治の「十力の金剛石」(校本 宮澤賢治全集 第7巻 所収)で「ポッシャリ、ポッシャリ、ツイツイトン」と濡らしたり「トッパァスのつゆはツァランツァリルリン、/こぼれてきらめく サング、サンガリン、」と輝かせたり、石牟礼道子の「第七章 大回りの塘」/『椿の海の記』の大地を「ずず、くゎん、ずず、くゎん、/ずず、くゎんくゎん」と脈動させたり、まるで読む者の身体を臨場させる操法の型のようだ。
昨年の秋に2ヶ月あまり入院していた魚津の精神科病棟では日替わり病室担当による検温、血圧測定、睡眠時間及び大小便通確認以外に、カウンセラーや薬剤師による面接を数回受けただけで、主治医が問診時に直接身体を診るようなことは一度もなかった。
退院後半年ちょっと富山市内の心療内科に通院していたあいだも、挨拶代わりに体調など尋ねられても担当医に身体を診てもらったということは一度もない。眠前に服用していた向精神薬を減らした経過が良くて転院の運びになっただけのことだ。
「紹介状」を携えて訪れた近所のクリニックのS医師は受付時の血圧の数値を眺め、「緊張のせいですかな」と言いながら身体を診て「心音はしっかりしているし異常はなさそうですね。」と次回に血液検査を予定された。以前に亡妻と一緒に通院していた同クリニックの[次回から診てもらう]Y医師も毎回二人の身体の触診を欠かさなかった。
たとえば恋愛のように、人間の身体に予測不可能な働きを認めていた吉本さんが言う「人工身体」は数値によって情報処理化された身体のことであり、同じく「自然身体」は日常生活を営んでいる生活身体のことだ。つかみどころのない「脳化身体」は頭でっかちの都市型身体ということになる。この三者が関係し合う空白に街道を通そうとすれば〈病態〉という風が吹いてきそうだ。
アナログからデジタルへシフトした高度情報処理化を、吉本さんは『ハイ・イメージ論』の冒頭で、生産手段の線形的なマトリックスによってシステム[綜合]が表象されることとし、生産手段の無窮拡張機構の一種として提示された。
そのマトリックスが意味する(1)映像差異の消去、(2)空間[距離]の差異の消去、(3)(1)と(2)の否定としての時間の差異化という三要素がコロナ禍社会のテレワークや、リモート授業などの受け皿として機能する一方で、高度情報処理化社会における精神労働と肉体労働の違いを身体から抜き去るように機能し続けていることも見落とせない。
情報処理化された身体と[イコールではない]都市型身体はいつもいがみあっているし、彼らを取り持つべき生活身体はその術が分からず投げやりな日々に戸惑うように流されるしかない。これは場所を問わず多くの身体が集まった組織内においても、また個としての身体内においてもあてはまるだろう。心身一如あるいは文武両道とも言えた身体観を見失い続けてきた近代の成れの果ての“なりそこないの近代”(石牟礼道子)と言って放りだすしかなかったのだろうか。
生身の人間が生きそびれがちな情報処理化社会とはゾンビ化した身体がはびこる時代みたいだ。人の間と書く人間や自然は情報ではない。身体のおぼつかないネットやSNSやAIは死んだ情報処理の溜まり場として肥大化している。まるでマトリックスの闇に放り込まれたように。
身体的な情報化と情報処理化を仕分けていた里山や広場がなくなり、空き地が更地になって「土地」観が希薄になった都市生活の中で核家族が「個」に分解されてしまい、「好き勝手に生きていいんだ」と思うようになったとしても、人が一人で生きられないからには挨拶や倫理のけじめは自分でつけなければならないのに、それすら必要ないと勘違いする人が目立ってきた。
見せかけの秩序を生み出すために混沌を作り出す。混沌なしでは他者を支配できないとでも言うように。近いところではコロナ禍でのワクチンの功罪をめぐる政府と関係機関やジャーナリズムの動向にその一例を見せられた気がした。
コロナ禍になる前のことだが、田んぼを潰して造成した町内から通ってくる小学練習生に、隣り合わせに住んでいる知人家族のことを尋ねたら、「知らない」と素っ気ないだけじゃなく「なんでそんな必要のないこと知ってなきゃならないの」と問い返されてしまった。小学高学年にしてそうなっているからには、すでに軒を並べて住んでいる親の世代も近所付き合いが無用ということなんだろうか。
過ぎ去った立ち姿の一コマ、用を済ませ挨拶を交わして暖簾をくぐれば外は篠突く雨。手にした蛇の目傘をばさっと開き立て‥‥‥と見る間もなく雨の向こうに消えてゆく。かって馬の通る街道だけでなく、牛や人間が荷物を担いで行くしかない道を辿った先に村や宿場や、人の暮らしがあり、神社仏閣があった。他者性をそんなに意識することもなく、共同体の倫理がその人それぞれを立たせてくれていた。宮澤賢治や柳田國男の時代がそうであったように、まだ連綿とした共同体の手応えがある「風土」に分け入るようにしてそれぞれの創造的世界を作りあげることができた。
目にしたことのある「自分の身体を通してしか、その人の「哲学」は出てきません」(福岡要)とか、「人間の価値は、おもに自分からどれだけ解放されているかによって決まる。」(アインシュタイン)というような言葉との隙間を無言で彷徨うような外的/内的自然観照ーー生きようとする/死のうとするーー身体から逸れるしかなく、言葉でたたみかける「山から海まで、受精から屍体まで、川も身体も流域、領域として見つめ直すべき」というような言い回しは身体そのものを覆い隠してしまってはいないか。
言葉は目と耳を一緒にする必要があるのに、視覚と運動はとても結びつけられそうにない。拙文の冒頭で引用した「まるで細胞同士がひかれ合うような」関係とは、何のはからいもなくたがいに〈気〉が通じ合うような官能が生じる二人のことであろう。直接触れ合わなくとも、掌とか頭頂とか足裏そのほか、お互いに〈気〉が共鳴し合う身体の部位であればそのいたるところでひかれ合うことになる。“女は存在そのものだが男は現象みたいなもの”[誰の言葉だったか?]だから「言葉」による相互理解なんてまるであてにならないことが多い。「腑に落ちる」のは言葉[頭]に先行する身体的受容の謂であろう。たがいに身体のリズムが合うようにジャズを聴いてきた。
自分自身は〈宿命的自然〉=身体とみなす家族的な平安をそれなりに生きようとして手さぐり足さぐりでここまでやってきたとしか言いようがなく、休み明けの運動の力みと集中(注)力の欠如からの離脱ーー〈動的・身体性を伴う動き〉ーーの「自然欠乏症候群」みたいだ。後期高齢者だというのに未だに青臭い思春期の残渣みたいな吹っ切れなさ。半世紀前のジャズの追っかけで燃やし尽くしてしまったはずなのに。
「燃えかす」を払拭するような〈新しい音楽〉で古びたリスニング・ルームを満たすことはーー叶わぬ夢、1970年代の終わりまでにリスニング・ルームを訪れた地元ジャズ愛好家達の耳目と一緒に‥‥‥、幻の庭の泉水を流れ去るように消え去ってしまった。
C.パーカーにC.ミンガスにJ.コルトレーンのLPーー傑出した演奏がかってのように聴けない身体になってしまったようだ。かろうじてO.コールマンのアトランティック時代のLPや、E.ドルフィーやT.モンクの[LPに録音された]即興演奏にこの夏を越せそうな“オノマトペ”を聴き、たまにはジャマイカのダブ・ミュージック[オーガスタス・パブローKing Tubbys Meets Rodkers Uptown]の爆音で猛暑の老体を扇ぐように秋を待つしかない。
Nancy Vieira/GenteやAnya Hinkle/Oceaniaなど女性ボーカルも聴き捨てならず、未知の領域に入った身体に響く新譜も無くはないが、今のところ老骨で追っかけさせるまでには至らないかな。
エルビス・プレスリーは、まだロックンロールの歌手ではなく、アメリカのカントリー&ウェスタンから生まれたロカビリーの歌手だった。アメリカ白人の伝統音楽で民謡でもあるカントリー&ウェスタンは、日本にやって来たアメリカ占領軍のおかげで日本に定着し、日本にもカントリー&ウェスタンを看板とする歌い手が何人も生まれた。音楽関係者はその由来を尊重してウエスタンカーニバルと言ったが、実際は新たに登場した若いロカビリー歌手達のフェスティバル公演だった。町にあったジャズ演奏を聴かせるジャズ喫茶も、名をそのままにして実質はロカビリー喫茶に変わった。新しい文化は名称を曖昧にしたまま「若者」と言われる新しい時代の中に浸透して、まだ若い夢生の父方の祖母の腰を揺らせるようになった。
(橋本治「夢生の登場するステージ」/「第三章 始まらない時代」/『草薙の剣』新潮社、2018年3月刊、155頁)
夫婦で“治ちゃん”を合言葉みたいにして『暗夜』(1981年)『蝶のゆくえ』(2004年)『巡礼』*(2009年)『橋』*(2010年)『リア家の人々』*(2010年)『草薙の剣』(2018年)などを取り替えっこするように読んだことがあった。著者が亡くなってしまい遺作の『黄金夜界』(2019年)は読まずじまいになっている。
*を付けた「昭和三部作」も『草薙の剣』も、おおよそ日本の戦前・戦中・戦後〜1980/2010年代が舞台になっているが、前三部作と後者とでは無思想なままに絡み合う日本人主人公とその時代背景との関係がまるであべこべのようなのだ。
『草薙の剣』の「帯」には、「10代から60代、世代の異なる6人[昭生62歳、豊生52歳、常生42歳、夢生32�歳、凪生22歳、凡生12歳]の男たちを主人公に、‥‥‥」と、具体的に名前まであげられているが、実際に読み進めるうちに主人公の「男たち」を飲みこむようにーー1923年から2016年までの百年足らずの歴史ーー物語の背景そのものが迫り出してくる。気づけば「主人公」に成り代わってしまっているのだ。昭和三部作品では時代に流される日本人を描いていたのに、本作品では人に対して見向きもしない時代に主人公が明け渡されてしまっている。登場人物の「人」を食ってしまうほどの超然とした「時代」とはいったい何者なのか。
個人の問題や生き様を第一主題として書くことができた近代という時代が、二十一世紀になった今は、個人のあり方や心得といったものまでが時代の波に削ぎ落とされてしまい、相互の関係性を見失った身体が「なんで僕はこんなところにいるんだろう?」と辺りを見回している。
光を当てて見えるものと、さえぎらないと見えないもの、登場人物の時代背景がまるで「霞網」を通り抜けるように、なにもかも絡めとって主人公そのもののように掴んで放さない。
霞 網
青い空には夢もない
どこへも行けない
広い空には時もない
夏色の衰弱
夢よ 夢よ
死んだ男達
鈍い木霊
返す 山よ
でもぼくらにしてみれば
まだどこかへ行けそうで
瞳 閉じます
夢 死んだままで
夏が逝きます
月明り 燃えて
閉ざされて黄泉返る
夏よ
霞網 霞網
霞網 霞網
打ち破れ! 霞網!
若いぼくには夢もない
どこへも行けない
苦い夢には先もない
懐かしい黄泉
闇よ 闇よ
眠る子供達
のろい祈り
堕ちる 時よ
でもぼくらにしてみれば
まだどこかへ行けそうで
瞳 閉じます
夢 死んだままで
夏が逝きます
月明り 燃えて
閉ざされて黄泉返る
夏よ
霞網 霞網
霞網 霞網
打ち破れ! 霞網!
(橋本治「ラブレター」/『詩集「大戦序曲」』河出文庫、1992年6月刊、236?239頁)
引用した『詩集』の「あとがきーー「ほしいものはアメノムラクモノツルギ」」によれば、「私は、15の年から20年たって、『もういちどありうべき高校1年生をやろう』と思った。」たったひとりの絶世の美少年を演りながら詩を書く一方で、『恋するももんが』を書いた。「35の高校1年生は、それから7年たって大学を卒業する頃には絶世の美男の光源氏にとりかかっていた。」そして『窯変源氏物語』を仕上げた25年後に『草薙の剣』を書き上げたわけだ。
「スーパーマーケットにいる夢を見た。」の一行から始まる「誰もいない世界」(第一章:息子達)の描写から、「第二章:終わってしまった時代」、「第三章:始まらない時代」、「第四章:よどみ」、そして「第五章:草薙の剣」という章立ての「時代」の起伏から、
「終身雇用の時代は終わった」とは既に言われていたことだが、だからと言って雇用されていた会社員が解雇されて野に放たれたというわけではなかったし、会社というシステムそのものが機能不全を起こして停止したというわけでもなかった。「バブルがはじけた」と言われた時、なにかは起こったのだが、であっても日本の社会は変わらずに、多くの人間を乗せたまま先へ向かって進み続けていたーーそのスピードは以前のものとは違ってかなりゆっくりとしたものになってしまっていたけれども。
人はその変化を経済学の理論で解明したがっていたが、それは経済学とは違った質のものだったのかもしれない。二十世紀の間に、時代は老いて錆びついていたのだ。
経済成長というものが生活習慣病のようなものになって、危険レベルを超えて発作を惹き起こした。それが「バブルがはじけた」ということだったのだ。老いた体に往年の活気は戻らない。老いた人間は、そのことを認めたがらない。「日本社会における高齢人口の増加」が言われはしても、時代そのものが老いてしまった結果、スローダウンが起こったのだという理解は起こらなかった。
(橋本治「錆びてゆく時代」/「第三章 始まらない時代」/『草薙の剣』新潮社、2018年3月刊、276〜277頁)
人々の欲望が寄り集まって時代の新しい波を生じさせ、現在をめがけて荒れ狂うようにさまざまな人を巻き込み、過去も未来も飲みこまんばかりにはじけ散って、人の居場所まで燃やし尽くそうとする。
相模の国へ至りついたミコトは、その地の国造[くにのみやつこ=ルビ]に騙されて一面に草の茂る野へと導かれ、火を放たれた。押し寄せる炎の勢いにたじろいで足を一歩下がらせようとしたミコトは、「万一の時には」という姨のミコトの言葉を思い出した。いわれた通り嚢の口を開き見ると、中には小さな火打ち石が入っていた。
ヤマトタケルのミコトは、野に放たれた火を退ける術として向火[むかいび=ルビ]の法があることを思い出し、授けられた剣で辺りの草を薙ぎ払い、集めた草に火を点けた。ミコトの薙いだ草の火は、押し寄せる国造の火に立ち向かい、激しい白煙を立ち上らせて敵の炎を食い止めた。このことによって、ミコトの授けられた剣は「草薙の剣」の名を得ることになるが、それより更に重要な火打石にはいかなる名称もない。
草を薙ぎ払うだけで、押し寄せる熱と炎と白煙を押し止めることが出来たのか? ヤマトヒメノミコトは黙って、押し寄せる敵を迎え撃つ術お教えたのだ。大太刀を振るって敵をかわすよりも、迎え撃つことの大事を。
凡生は、「お父さんは、もう家には帰ってこないの?」と言った。その言葉が父に響いたのかどうかは分からない。そこで凡生は、必死の思いで火を放った。
その向火は有効だったのか? しかし、見えない墻壁[しょうへき=ルビ]に隔てられて思いを内へ内へと収め込んでしまう者にとって、「立ち向かう」ということは思いつくさえも容易なことではない。
誰も悪くない。父も、母も、それなのに、どうして、自分は苦しいのだろう。
「かって若者だった大人は、根拠のない夢を変わらずに見ている。しかし、とうの若者には絶望しかない」と、誰かが言っていた。十二歳になった凡生は、小学生のままもう若者になっていた。
(橋本治「草薙の剣」/「第五章 草薙の剣」/『草薙の剣』新潮社、2018年3月刊、345〜346頁)
謀られて窮地に立たされたヤマトタケルノミコトは、そんな時のための「型」としての向火の法を思い出し、姨のヤマトヒメノミコトから授けられた八岐の大蛇[やまたのおろち]の体内から出たという剣で薙ぎ払った草を集め、同じく姨のヤマトヒメノミコトから授けられた小さな革の嚢に入っていた火打ち石を取りだし、それで火を点けるというヤマトタケルノミコト自身の輪郭が「形」となって現れて難を逃れることが出来た。
『詩集「大戦序曲」』(河出文庫)のあとがきでほしいものは「アメノムラクモノツルギ」だったのが、三十数年後には名前が変わったようにクサナギノツルギになってしまったようで、火を起こして敵の火を迎え撃った火打ち石には名前もない。
「万一の時には」という姨のヤマトヒメノミコトの言葉を借りてヤマトタケルノミコトが自分を省みて物事を執り行う「型」と、それによってヤマトタケルノミコト自身の輪郭が「形」となって現れる、両者の関係性を成り立たせる古典的武術の「式」を象徴するものとしての「剣」を読みとればいいのだろうか。
縁がなくて「型」に則って自らの身体を顕現させる「形」を使いこなせない凡生は、いったいどうやって「必死の思いで火を放った。」のか?
古典的時代と現代とではあまりにも《身体的ジェネレーション・ギャップ》が大きすぎてとても老体の手に負えるようなものではない。近代化してしまった身体観で古典的な技法を理解しようとするなどとても叶わぬことだ。
ふと見ると、街灯の下に男が立っている。男の顔がぼんやりと光に照らされているが、凪生はどうとも思わずその横を通り過ぎた。するとまた、男が立っている。手にスマートフォンを持って、その光で顔がぼんやりと照らされている。また少し行くと、同じような男が二人、三人と立っている。「何だろう?」と思って、すぐに凪生は気がついた。
「ポケモンGOは日本に上陸したんだな。ここら辺に、ポケモンは出るのかーー」と思って、道の先を見た。店の軒下に男が立っている。歩道の真ん中にも立っている。車道を行く車の数が少なく、白いガードレールの向こうは黒い川のように見えた。その瞬間、凪生は「この風景は見たことがある」と思った。
「既視感[デジャビュ=るび]か?」と思って、「なんだこれは? なんで俺はこんな風景をしっているんだ?」と、立ち止まって考えた。
夜の街に男達が立って、何事かしていた。なにをしているのかは分からない。自分は、暗いスーパーマーケットの中に入って、カップラーメンを探していたーー一年前に見た夢が、凪生の頭に甦った。
「自分はなぜこんなとことにいるのだろう? 自分のいる、この暗い所はなんなんだろう?」と、改めて思った。
(橋本治「エピローグ」/「第五章 草薙の剣」/『草薙の剣』新潮社、2018年3月刊、347頁)
凪生はうすぼんやりと数人の男達の身体が手にするスマホを認め、凪生が住む両親のマンションの手前の公園近くで「ポケモンGOは日本に上陸したんだな。ここら辺に、ポケモンは出るのかーー」とあたりを既視感のように感じる風景を、「自分は、暗いスーパーマーケットの中に入って、カップラーメンを探していたーー一年前に見た夢」に繋げて考える〈身体〉に出会っている。
『草薙の剣』の最後のページをめくり終えた指先はいつの間にか、気づけば最初の一行ーー「スーパーマーケットにいる夢を見た。」(「誰もいない世界」/「第一章:息子達」8頁)にループしているようなのだ。
高度消費社会の先端から末端まで張りめぐらされた「霞網」に絡めとられた野鳥のように《身体性》が剥き出しになった時代に帰巣できるような〈民家〉とはどういうものだろう。(2024年7月17日記/20日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(25)立ち会う老体
「ちなみに“パンクロック”と言う言葉を最初に使ったのはデイブ・
マーシュで、それも『クリーム』の誌面においてのことだった。
1971年5月号の連載コラム「ルーニー・テューンズ」のなかで
ーー本号はつまり“ヘヴィメタル”という語が初めて登場した号で
もあるーーマーシュは60年代のロック・バンド、クエスチョン・
マーク&ザ・ミステリアンズが唯一のヒット曲から5年後におこ
なった刺激的なライブセットを紹介した。なにかといえば“パンク”
と嘲る風潮にマーシュは心底うんざりしていた。「生来の文化的
ひねくれ者である僕は、これはむしろ褒め言葉として使うべきだ
と心に決めた。威厳に満ちたクソ野郎として誇り高く振る舞おう
とするパンキストとしての行動を指す語として、特に使えるはず
だとね」」
(ジム・デロガティス 田内万里夫 訳『レスター・バングス:伝説
のロック評論家、その言葉と生涯』トンカチ、2024年4月刊、
203〜204頁)
民家の立ち上がりがまず柱を立てることにはじまるように、お茶やお花を「立てる」といい、横のものを縦にする畳の上での生活が一つの稽古のようなもの。日々の着替え、和服を着ていると立ち上がりが身につくように、民家に伝わるさまざまな道具を使えるようにーー身につくまでーー使いこなさないと一人前になれない。民家で暮らす住人が培ってきた多様な所作の街道の行く手にどんな橋を架けて渡ろうとするか。
立ち会うとは、だれしも大切だと思っている意識の侵入を防ぐこと。意識を向けることは、おそらくバランスを崩すことでもあるから。無意識な必要最低限の情報によって、意識も最適化されよう。さすれば全体性、等身大の自己との出会いにも繋がっていくことになろう。
祖父も実家の祖母も「道は在て見るべからず。事は在て聞くべからず。勝は在て知るべからず。」というような、孫にとって謎めいた言葉を語りかけた記憶が残っている。子どもごころにそれはそれでいいのかもしれないが、自分自身に合点がいかない事どもに対処する方法の分からなさが宿題のように残った。無私の心で阿弥陀様の慈悲のもとに生きるというのが日々の身の置き所の型になっていたのだろうか。
結果(齟齬)を求めるのではなく、有りのまま(自然に)行うことで観えてくる結果(整合)を体認していくのが初めての稽古だったように思う。中学部活で語りたいことや主張したいことなどほとんどなかったようだ。それでいて、誰彼の語りに耳をすますのが楽しかった。下駄のようにただ履くだけ。滑り止めの金属を下駄の歯に打ち付けた雪下駄も身を任せれば、それと自覚せずとも凍った雪道でも具合が良く、歩くカラダが語りかけてくるように観えただけでなく、音もなく聞こえてきて、真冬の田舎の街道が開けるように感じた幼い頃のように。
八十歳を過ぎて一人旅もし(でき)なくなった母がときどき体や手足のあちこちに痣が目立つようになった。散歩の習慣はなかったが、運動を兼ねて家の一階をあちこちを動き回っているうちにぶつけたり転んだりするようになっていたのだ。なんとしても骨折だけは避けなければ。
家具など一切置かないようにしていた六畳の座敷に細長いマットを敷いて、大正生まれの母に転ぶ練習というか受け身を覚えてもらうことにした。転ぶのを怖がってとっさに何かにしがみつこうとしたり、倒れないよう踏ん張ったり頑張ったりしないこと。危うくなったら両手で後頭部を掴むようにして臍のあたりを見ながら尻餅をつくように後ろに落ちること。親子三人でスキーを始めた時もやっておいたことだが、おかげで家族の誰一人怪我なく、と言いたいところだが自転車で転んで鎖骨を折った亡妻のことが心残りだ。
高齢ながら身のこなしに長けていた明治十二年生まれの祖父は歩くのがおぼつかなくなったら杖をつき、それもできなくなったら幼児に戻ったみたいに這い歩くようにして大往生した。歳とともに足元がおぼつかなくなったりすると、ことのほか無意識裏に転ぶことを恐れるように暮らすしかないのだろうが、母とは違って祖父はそんなそぶりを一切見せたことがなかった。母に比べたら祖父の要介護期間なんてなかったに等しい。
四つ足歩行から立つことを覚えたヒトは無意識裡に転倒への恐怖を秘めて暮らしてきているのではないだろうか。それで自覚の無い身体内部の過緊張や疲労の蓄積で四十肩とか五十肩だけでなく、老いに向かう腰や膝などの関節痛に見舞われやすくなるのではなかろうか。
普段とは違う体の使い方をしてあちこち痛くなったり、�あって当然の一過性の痛みなら、当該運動を止めるか習慣化するかによって解消する。
夫婦そろってスキーやサイクリングやバドミントを始めた時がそうだったが、二人足して百何歳などとふざけたりしていたら共に利き腕が痛くて上がらなくなった。ちょうど短くはなかった母の自宅介護が終わり、二人とも医療費を払わない暮らしができた数年過ぎに予期せぬ還付金が手に入った頃だった。
その使い道に、たまたま超薄型半球状「バランスボード」と、数十個の形の違う半球状や棒状の駒を直交状に並ぶに孔に嵌めて両足で乗るだけの「みちのく山道」が浮かび、数万円+αで通販買いしてしまった。
ものは試しと交互に乗り降りするうちに、数ヶ月も過ぎた二人の利き腕が上がるようになり、洗濯物など干せるようになった。ほんと膏薬を貼ったり通院したりせずに治ってしまったのだ。おそらく長年親しんだ運動などでは緩むことのなかった無意識の身体内過緊張による痼りが、直径60センチメートルのボードや�縦横55×70センチメートルの合板に嵌めた突起の上に時々乗るだけの日々で解消したのだろう。つくづく数かぎりないカラダの不思議のひとつに出会った気がした。その後も乗った時の不思議な感触・感覚に誘われるように使い続けている。
お互い朝から不調で出かけるのを見合わせようかと言いながら出かけたスキー場で休んでいたら、そのうち滑りたくなって快調になったり、不調を押してライブに出かけたら我知らず復調したり、「自己管理」を超えたカラダの働きに〈身体〉が気づくか気づかないかで、人それぞれの日常の積み重ねにおける身体的感受性が随分違ったものになるのではないか。
キーボード打ちの合間に握るのは、いつも机上に転がっている掌および指馴らしの三点セット。京城からの引き揚げ時に母が持ち帰った胡桃、常願寺河原で拾ってきた石ころ、そして飛騨高山で買った柘植の一刀彫のだるま。それぞれ大きさの違う握り心地で微妙に手足が和むのだ。
まず、足の小指とその隣の薬指は特別なんです。つまり、ほかの三本はよくきいても、この二本が効かなくなるっていうのがあるんです。この二つの筋はもちろん上までつながっているんですが、それを押さえたり、もんだりする。表裏両方、この筋を普通よりも一生懸命にもんだりさすったりするんです。そうすると、まず第一番に、お年寄りが歩きにくくなったとか、足が重くって不自由になったとかいうときに、うまく解決します。あっと驚くほど自由になります。これは初歩的なものですが、最初はそれで痛いとか、動かない、不自由だというとき、そこを動かしてやるわけです。
(吉本隆明『老いの幸福論』青春新書、2011年4月刊、179頁)
生涯「自分の体の主治医は自分」で自らの身体を律された吉本さんの言葉だが、似たようなことが我がひもトレ体験で起こったことがある。
どうしようもない心身の不調に陥って仕事を辞め、自宅療養で少しづつ復調してからのこと。右眼の上瞼がときどき痙攣するようになってPC作業や読書がおぼつかなくなった。時折覗くようになっていた甲野善紀師の旧ツイッター改めXで知ったひもトレ本を買い、付録の細い丸ひもを烏帽子巻きにして作業するうちに嘘みたいに治ってしまった。
それから遅れて妻の左目の瞼が引き攣ったみたいに震えてものが見づらいということで、新たに購入した太めの丸ひもを烏帽子巻きにしたりしていたが大した効果はなかったようだ。なんともないときは普通に見えるのだが、間欠的に左の瞼が引き攣ったみたいになって読み続けられなくなるのだった。
ところがたすき掛けのひもトレがカラダに心地よかったのか寝るとき以外はいつも身につけていた。肩が凝ったり痛くなったりとは無縁だったようだが、自転車転倒による鎖骨骨折の回復後から陥った抑鬱に端を発した心身不良がきびしく、昨夏の急逝時に娘が選んだ妻の遺影は赤いひものたすき掛け姿になっている。
妻と一緒にバドミントンができなくなって止めるまでは、運動時も腰部巻きとたすき掛けのひもトレを欠かさなかった。するとしないでどこがどう違うかうまく言えないのだが、あるときゲーム中にカラダの動きが重く感じて腰部巻きの丸ひもが解けてコート内に落ちているのに気づいたことがあった。また練習試合前に妻とクリアの基礎打ちをしていて、打点のタイミングがばらつきがちだなと感じた身体が、たすき掛けのひもトレ忘れに気づかされたなんてこともあった。
前述の「バランスボード」や「みちのく山道」に乗ったりするのと同じように、ひもトレもとにかくあれこれ無理強いしないで身体の好きなようにさせるということではないだろうか。寝ているときも腰部に巻いたままにしているが持病みたいだった腰痛がひどくなったり、高齢化にともないがちな夜間頻尿に見舞われるなんてこともない。先々週まで両足がむくんで靴が履きにくくなり、両膝下から足首にかけてひもを巻いたり、くつろぐ時や寝る前に両足を高くしたりしているうちに腫れぼったさも数日で消えた。ところが血圧降下剤服用にともないがちな頻尿時に下腹部にひもを巻いたりしてもなんともならないこともある。
身体の経験してゆくことを、たとえば四季の感覚に従って観てゆくことが手始めになるように、人工物のバランスボードや「みちのく山道」やひもトレに身体をまかせて内観するしかない。発案者は「それぞれの等身大を包括するのが『ひもトレ』。前もってそのハタラキを形容することができないのは、純度の高い経験ほど、そもそも言葉を持たないからだ。ひもトレに価値があると言っているのではなく、評価も言葉も装飾されていない経験自体が価値なのだ。」(小関勲@ツイッター改めX)と言っていた。美味いものを食べ、良く寝て、良く休んで、よく動いて、自分の身心のことを信じれるような生き方ができている身体に共鳴しそうだ。「結果にアプローチしないこと、何もしないという長期的観察が織りなす身体性、個々の自覚の外に置くヒモトレの在り方。等身大に立ち戻る意味。具体的な変化や見え方はそれぞれ。だからこそ観えてくるところ」(同前)を体感するのも稽古始めのひとつになる。
持病というより体質的、器質的なものかもしれないが、不意に悩まされる過[呼吸]換気[症候群]や偏頭痛の前兆みたいな閃輝暗点[視症]については身体的にどう対処していいのかわからない。気が向いたら乗る「バランスボード」と「みちのく山道」や常時巻いている「ひもトレ」が効くとか効かないとかいう次元じゃないところで身体的な発現があったりなかったりする、自発的な体験者の能動性に関わっていそう。
山に登りたい、ライブに行ったり音楽が聴きたいから、タバコが吸いたいや酒が飲みたいなど、身体的な“声”のおもむくままの行為の範疇に「ヒモトレ体験」は含まれるだろう。
だから鍼灸に通うほど肩や背中や足腰に痛みを抱えたバドミントン仲間がいたりしても、自発的な出会いがないところで人に勧めたりしたことはない。
思い込みが深く猜疑心が強かったり、マウント性格的な体壁にはなじまないというか、はなっからバカにして見向きもしないだろう。
介護施設で嚥下障害者や歩行困難者が改善されたり、音楽界隈で声楽家の声の出や器楽奏者の奏法の質がよくなったりするなど、探せばネット上でさまざまな事例が拾えるだろう。
島尾敏雄が自作品の中で造語していた「眼華」は、芥川龍之介(『歯車』)や村上春樹(『ノルウェイの森』)などの小説に出てくる視覚障害描写と似ていて、おそらく作者自体が閃輝暗点[視症]を体験していたのだろう。個人差はあるだろうが視界の一部が欠けたり、キラキラ光ったり、ギザギザしたり、暗くなったり、ぐるぐる回ったり、稲妻のようにチカチカしたり、頭痛がしてめまいや吐き気に襲われたりと多彩である。谷崎潤一郎も偏頭痛を患っていたらしいが自作品にその描写があったかどうか読んでみないとわからない。
近いところでは、パソコン誌のテクニカルライターからコラムニストに転身した小田嶋隆が亡くなる前の闘病中のエッセイで名指しでその症状に触れていた。克服したとはいえ過去の重いアルコール中毒症経験者ゆえの累積ストレスも作用していたのかもしれない。男性作家の事例しか知らないが、閃輝暗点[視症]は男性よりも女性に多く起こるとのことだ。ちなみに過[呼吸]換気[症候群]も、勤務中の救急隊員が話してくれたのだが、“乙女の病気”と言って若い女性に多く見られるらしい。医師の見解を含めていずれも原因は何らかのストレスにあるらしいが、男性より女性の方が無意識により多くストレスを強いられている現実があるのだろう。自分のことはよくわからないが、京城から引き揚げてきてからの生活困窮状態の母も、嫁に行く前までの姉もだが、過呼吸をともなったヒステリーに悩まされていたに違いない。
男女ともに高齢になったらなったで身体のおもむくまま、なすがままの好き勝手にまかせればよいのではないか。難しいことなど生成AIにまかせておいて、人工知能じゃできないようなことに感けるように暮らせばいいだろう。薬漬けにして長生きするなど不自然も甚だしい。ヨーロピアン高齢者はほとんど薬を飲んでいないというじゃないか。それでいて薬漬けのジャパニーズ高齢者の平均寿命と大して違わないというから、おかしげな「健康志向」や「若見栄え」など不要だろう。
高血圧症ということで朝晩の血圧数値を記録して通院時に診てもらうなど、数値に合わせるような暮らしはほんとうの健康とは我ながら言えないだろう。医者嫌いだった祖父は自然にまかせてあと一週間で百歳というところまで生きた。数値をかざしたり目標を持ってたどり着けるようなたぐいのものではないはずだ。
要介護状態になる前の母がトイレで吐血して妻がタクシーを呼んで入院させたことがあった。担当医から職場に電話があって出向いたら「薬の過剰摂取による急性胃潰瘍」とのことだった。健康志向で医者通いしていたらとんでもないことになったりする。医者がかりになってっも「過剰医療」に自覚的でありたいものだ。
妻の死による「葬式躁」なるもので[半狂乱か錯乱かまるで覚えがない]具合が悪くなって居心地の良くない入退院と通院を経て気分はどうとも言えない実情だ。自宅にいて居心地も気分も良い身体を保って暮らせればそれで十分なのだが。
世の中の風潮といえばきびしい物価高に加えて、寄ってたかって居心地も気分も悪くなる窮屈な方へと傾くばかり。物心ともにさまざまな面で底が浅くなり、おたがいに身動きならないところまで落ち込んで自縄自縛状態。いたるところに見えない監視カメラが張りめぐらされているようで、人生これからという人まで縛られた感じがあたりまえになっていそう。遠くでは東欧や中近東の凄惨な内戦状態が続くだけでなく、身近な国内では家族による一家惨殺というような悲惨な事件が後を絶たないだけでなく、それらが同時的に発生する瀰漫的な情況からぬけだせそうにない。
入院中の精神病棟ではネットワークPCで音楽を聴いたり、便箋の裏にスケッチをしたり、自発的な身体的行為で〈いま・ここ〉の居辛さを〈何か〉で充溢させるようにしばし時の経過を忘れられもしたのだが、退院してからしばらくは音楽やスケッチどころじゃなかった。戻ってこれた独居我が家で快食・快眠・快便を心がける日々の合間に、家事だけでなく机にも向かって手を動かすこと。更新が中断していたHPの「十字路で立ち話し」と「続・本の一言:街道と民家」の駄文掲載はさておき、『猫々堂「吉本隆明資料集」“ファンページ”』を維持・継続でききるようになったのが何よりだ。
自己慰安にしかならない自作文でも、入院中にできなかったことができるようになったからか、スケッチで何かを描こうという気が引っ込んだみたい。新調したPCで聴けるようになったストリーミング・ミュージックを含め、以前にも増して新しい音楽を[気に入ったジャズやロックをダウンロードして]聴くようになった。病棟内での「音楽療法」の延長なんてことはさらさらないのだが、書くことより聴くことの方がよほど気が落ち着くというか、老いた身体が整うようなのだ。
宮澤賢治のクラシックやシカゴジャズ音楽好きは創作活動に欠かせない要素の一つであったろうが、「文学」に加えて農業関連諸活動などに勤しんで疲れた「身体」を癒すだけでなく、手回し蓄音機でSP盤を回して音楽を聴くことそのものが自らの身体を整え直してくれることに無意識裏に共振していたようだ。「文学と身体」みたいな関心ではないところから音楽と身体についていささか考えさせられることがあった。
私的な幼少期音楽体験の始まりは電気を使わないでSPレコードの溝から直接音を取り出す蓄音機によるものだったが、今日なおそんな異色の音楽鑑賞会がこの夏にあるという。
薬品や器具など一切使わずに自分の手と言葉だけでさまざまな状況の人の身心を整えられた野口晴哉整体師は、ご自身の身体の調整のために、より納得のいくレコード鑑賞法を追及されていたようだ。狛江の旧野口晴哉邸で電気を使わない蓄音機中の「名機」と言われている「クレデンザ」による再生音楽は聴く人の身体にどのように響くのだろうか。おそらく宮澤賢治なら想像つくだろうが、幼少期のそれも邦楽体験しかない自分には見当もつかない。
電気を用いない音の再生装置で昔の音を聴くという試みが、現在当たり前になっているさまざまな機器で音を聴くということとは違って、何か本質的に変わった身体観を垣間見させてくれはしないか。
音楽好きな老体の身としては、若かりし頃に聴き惚れたジャズミュージシャンの老いを生きる活躍ぶりがとりわけ陰影豊かに響く。東日本大震災後の渡辺貞夫のライブアルバムや、今年になってNHKが放映した秋吉敏子のドキュメンタリーでの演奏。
ナベサダも秋吉敏子も、地元富山や金沢で聴いた頃の懐かしさみたいなものを感じさせない今様の姿勢に満ちていた。数十年前のビッグバンドを引き連れた金沢公演会場の廊下で偶然出会った秋吉敏子と言葉を交わしことがあった。当時LPレコードで好んで聴いていたサックス奏者ビル・パーキンスがバンドメンバーから抜けていて残念ですというようなみいはあ的な問いかけに、立ち止まった秋吉が丁寧な日本語で話してくれた表情と姿勢が未だに忘れられない。満州から引き揚げた戦後日本からアメリカに渡ってジャズを活路に生きる物腰に並々ならぬものを感じたのだろう。
亡き妻と一緒に、ある時は一人で、東京や名古屋や大阪や京都そのほか聴きに行った来日ジャズミュージシャンのほとんどが鬼籍の人になってしまった今、かってLPレコードやCDを好んで聴いたトニー・ベネットやオマーラ・ポルトゥオンドといった歌手だけでなく、ドラムムスのロイ・ヘインズやギターのジョージ・フリーマンなど90歳を超えてもなお、精力的なライブ活動をやっているようだ。高齢になっても素晴らしい演奏を支えているジャズという生き方があるように、ジャズに遅れること1950〜60年代にかけて英米で活性化したロック界の高齢ミュージシャンもロック魂で演奏活動を息継ぎにしている気がする。演奏スタイルは違えどもいずれも身体的に撓むような膂力を感じさせられる。個々のミュージシャンについてだけでなく、例えば生で聴いてきたマックス・ローチやアート・ブレイキーからエルビン・ジョーンズやスティーヴ・ガッドにトニー・アレン[2020年パリにて79歳で逝去、アルバムでしか聴いていない]と聴いてきたりすると、ジャズドラマーとしての生き方も脈々と受け継がれてきているように響いて興味尽きない。
何度かライブで聴いた山下洋輔トリオのドラマーだった森山威夫がピアニストの渋谷毅と2011年3月に吹き込んだ『渋谷毅&森山威夫●しーそー』(TKCB-72228)は二人のジャズ魂が絡み合った名演だ。楽屋話としては、1960年代の富山市内のジャズ喫茶で山下洋輔トリオライブ直後の控えで服を脱ぎ捨ててパンツ一枚になった三人から湯気がたっていて話しかけられなかった記憶がある。
新しいところではまだCD2枚しか聴いていないが、アルメニア出身のジャズピアニストTigran Hmasyanの演奏はセロニアンス・モンクの“間”とバド・パウエルの“勢い”が渦巻くようで、生で聴いてみたくなるような身体に響く聴きごたえだった。(2024年8月3日記/5日WEB公開)
続・本の一言:街道と民家(26)あるいはその日暮らし
「女たちの家」の臨床心理医であるフロリダ生まれのジュリエット・
マーティンは、つぎのように話して、集会を閉じた。
「わたしがまだ子どもだったころ、フロリダの家の前であそんでいる
と、ふとった女たちが通っていったものだった。えびの漁場で働く女
たち。よごれて、ひどい臭いをさせて、それでも笑いさざめきながら
家路をたどる女たち。きまって笑っていた女たち。ある日のこと、わ
たしの耳にこんなことばが聞こえた。あんた、ブルースなんていって
もさ、ただの唄じゃないか。あんた、ブルースなんていってもさ、た
だの唄じゃないか。そのことばがずっとわたしの耳に残っていた。
そうだと思う。ブルースなんてただの唄。かわいそうなあたし、み
じめなあたし。いつまで、そう歌っていたら、気がすむ? こんな目
にあわされたあたし、おいてきぼりのあたし。ちがう。わたしたちは
わたしたち自身のもので、ちがう唄だってうたえる。ちがう唄うたっ
てよみがえる」
女たちは、あんた、ブルースなんていってもさ、ただの唄じゃない
か、ということばが気にいって、ふたたび立ち上がり、拍手した。
(藤本和子『ブルースだってただの唄:黒人女性の仕事と生活』
ちくま文庫、2020年11月刊、226〜227頁)
埴生の田舎に住んでいた駆け出しのジャズファンの頃は聴くだけでなく、ジャズについて書かれたものにも飢えていた。 田舎町にまで流れてくるのも稀なジャズ雑誌や関連本など手にしても音が聞こえてくるわけは無いのでそのうち遠のいてしまった。
1970年代はじめまでにジャズ喫茶通いをやめ、結婚と同時に私設リスニング・ルームなるものを自宅に設けたあたりから二人で暇さえあればジャズLPを聴きかじっていたようだ。1975年の1年間にジャズレコードを420枚買って聴いたメモも残っている。
加えて当時は毎週末の夜になるとジャズ友のひとりだった I 谷さんが購入されたジャズレコードを抱えて訪れられるようになり、LPレコードで聴くジャズの幅や奥行きがより深まったようだ。ニューヨークにまでジャズを聴きに行かれたようなお方だったが、急な病で亡くなられた時はジャズを嗅ぎ分ける豊かな耳の持ち主を失った気がした。
最近になってネットで耳目に触れた高齢ジャズギタリストのジョージ・フリーマンに、オールドファンにとって特別の存在と化したチャーリー・パーカーとの共演履歴があるらしいとのことだった。近年座右のジャズ書、牧野直也『チャーリー・パーカー伝:全音源でたどるジャズ革命の奇跡』(アルテスパブリッシング、2022年9月刊)の人名索引その他には彼の名前が見つからなかった。試しに生成AIに尋ねたら、そんな共演記録はなくネットにありがちなガセネタということだった。
そこで諦めずに英語版Wikipedia[https://en.wikipedia.org/wiki/George_Freeman_(guitarist)]を覗いたら出てきただけでなく、YouTubeで聴くこともできたではないか。
シカゴでのパーカー=フリーマンの演奏のアマチュア録音として「Charlie Parker-At The Pershing Ballroom Chidago 1950」が何度もリリースされているという。2003年版の解説でローレン・シェーンバーグがフリーマンの演奏について、「ジョージ・フリーマンがこのアルバムを通して作り出すとんでもない実験的な音楽には、事実上前例がない。彼のソロ(ある曲)は、私が今まで聞いたことのないもので、ジョン・スコフィールドやビル・フリゼールが90年代にジャズギターにもたらしたものに、同時代のどの演奏よりもずっと近いように思える。」と書いていた。
上記アルバムのトラックリスト[Indiana5:53/I Can't Get Started2:46/Anthropology5:14/Out Of Nowhere2:45/Get Happy5:31/Hot House5:02/Embraceable You2:00/Body And Soul2:14/Cool Blues3:12/Star Dust0:55/All The Things You Are3:06/Billie's Bounce4:11/Pennies From Heaven3:19]に含まれていない演奏「Keen And Peachy (Live At Pershing Hotel Ballroom, 1950)」[https://www.youtube.com/watch?v=fPilGj-M5JU]で聴けるパーカーのソロに続くギター・プレイの素晴らしさ。コメント欄に「Charlie Parker: alto saxophone, Claude McLin: tenor saxophone, Chris Anderson: piano, George Freeman: guitar, Leroy Jackson: bass, Buzz Freeman: drums」とあるからまさに当時の彼のギターソロ演奏を聴けたわけだ。同様のセッション「Charlie Parker - There’s A Small Hotel - Pershing Hotel Ballroom, October 23rd, 1950」でも聴けて大満足。過日Amazonn Musicの「Charlie “Bird” Parker - The Complete Live Performances On Savoy 」でパーカーのライブ演奏を楽しんでいたら、前述の「Keen And Peachy」とよく似た演奏が聴こえたが、おそらく上記と同一の音源を収録したのだろう。これまではパーカーと演ったギターヒーロとしてチャーリー・クリスチャンやバーニー・ケッセルしか知らなかった拙い我がジャズ歴に新たな一ページが開けた感じだ。
たまに気になるジャズネタ調べで行き詰まってネットサーフィンしたりすると、私[史]的に新たなジャズシーンに出会えたりするのもネット時代ならではのことだ。
おかげでポンコツジャズファンの命脈が保てたような気になるのだが、見つかった音源の再生をいかんせん‥‥‥、PCまかせの音の出口があまりにも人工的というか耳障り、じゃなかった肌触りというより身体的に面白くない。
ということで聴きたい音源をBluetoothで管球ラジオに飛ばして聴くようにしている。ぐっとぬくもりのある演奏として響くような気がする。たとえば紙筒スピーカーでヴォーカルや落語を聴くと声がより艶っぽく感じるようなものだ。
LPはリスニング・ルームでしか聴けないが、それ以後にCDで聴いてきたジャズやロックそのほか一万数千曲をPCに落とし込んでシャッフルしながらBluetoothを利用して居間や書斎でBGMみたいに聴きながせるようにしている。なんだかプライベートな音楽専門局を受信しているような距離感が保てて飽きない。
要は聴き疲れしない再生音、一緒に居て際限なく心地よい、そんな人格を感じさせる音の場になっていればいいのだ。
初めて聴いた名機クレデンザの音は、私の身体の深い所を動かしたようだ。電気とは無縁のゼンマイを動力源とした蓄音機の音は「音の版画」と言われているそうだが、何かナマナマしい「音がそこで作られている」感じが凄い。私の技の在り方にも深い影響を受けた事は確かだ。
(甲野善紀@ツイッター改めX2024年8月)
最近のジャズやロックのCDなども驚くほど音質が素晴らしく聴けるのに、なぜかむしょうにLPでジャズやロックを聴きたくなったりするのも、針で溝に刻まれた音を再生するのに馴染んだ身体のなせる業かもしれない。齢とともに身体的センサーが、美味しくても食材が何かわからない料理より、素材を活かした料理の方へ振れるように、音感も人工的な響きより自然的な響きに勧誘されるのだろうか。このあたりのことは老化とともにどうでもよくなりそうなのにこだわりがなくならない。
自分がどれほど堕落したか、駄目な人間になっているか。尺度を計測するものがある。別に他人が私を見る眼に、軽蔑や憐憫を認めるまでもない。私の生活に占める「音楽」の時間を考えてみればすむことである。陋屋に蟄居し、殆ど音楽に浸りきっていた時代があった。六〇年安保闘争の終熄したあとの季節がそうであり、深夜叢書社を継続していくことが限界にきたと思った時期もそうだ。人間関係における躓き、失恋の刻は言うまでもない。もともと女々しく出来ているせいか、立ちなおったような気分になるのに、二十年くらいの歳月を要した。
いずれのときも音楽が安定剤の役割を果たした。即効の効能は無かったが、心臓病患者にとってのグリセリンの一粒ぐらいにはなったのである。後年、そんなセンチメンタル・ジャーニイを、音楽雑誌に寄稿したことがある。
(齋藤愼爾『深夜叢書社年代記:流謫と自存』深夜叢書社、2024年7月刊、208頁)
ジャンル的にはジャズやロックが好みといっても、身体的に気持ちがいい音楽ならなんでも聴きたい。先日(8月第一土曜の晩)も娘夫婦の誘いで「吾妻光良 & The Swinging Boppers 富山公演」(前座は地元高岡のおじさんバンド“ねずみ兄弟”)に行ってきた。メリハリの効いたブラスとフォーンのアンサンブルが身体をを吹き抜けるようなビッグバンド・ライブは久しぶりだった。ブルース・フィーリングでスウィングしていたら言うことなし。おかげで翌日の晩には、戦前のビッグバンドジャズ演奏を復刻したLPを引っ張り出してひとり悦に入ったりした。特にスウィングからモダンへの過度期の演奏など、いつ聴いても色褪せない。
吉本さんは、幼少期から老齢期にいたる人間の「発達線」の間に〈移行期〉を設けられたが、特にスタイルの変遷が顕著なジャズなどそのルーツをたどりながら、例えばビバップからハードバップへの脱皮やそれからフリーへのモダンジャズの変身など、移行期の演奏に聴き耳を立てた方がいろんな気づきがあってより楽しめたような気がする。
1930年代半ば過ぎから1940年代半ばまで、当時のアメリカでは300を超えるビッグバンドが凌ぎを削っていたというから驚く。百数十年に及ぶジャズの歴史で、その全盛期がわず十年に満たないというのも感慨深い。スウィングジャズの黄金期を短命に終わらせたのも、第二次世界大戦のなせる業の一つに数えてもいいだろう。クラシック好きの宮澤賢治は創成期の、それもシカゴジャズをSP盤で聴き拾っていたことになる。
おおまかに言うなら、戦後日本にアメリカが持ち込んだモダンジャズなるものは衰退期のジャズといってもいいだろう。やがて本場アメリカでロックに取って代わられる命運にあったわけだ。
そのころ、1930〜1940年代のSP盤復刻ジャズLPの演奏に“ブルース”の井戸を掘り当てていたような自分には気づきもしない音楽的潮流だった。
現在一般にブルースと呼ばれている音楽の実体は、その「12小節AAB形式」の旋律形態を「ブルース構造」と呼んでいるわけだが、音楽の呼称である「ブルース」ということばそのものは、それとは切り離すべきなのである。「最初のブルース録音」についての議論がいつも本質を踏み外すのは、音楽の実体とその呼称である言葉との齟齬を見ずに両者を等号関係で語るからだ。
1900年代のはじめから1930年代くらいまでの間、「ブルース」という言葉は「ブルース構造」の音楽だけを指す言葉としては使われていなかった。白人も黒人も、最も古い音源の多くで「ブルース構造」でない曲に「ブルース」という題名をつけている。ということは、冷静に考えれば「ブルース」という言葉は当初もっと別なニュアンスを持っていたはずで、それは時代と密着した「流行り歌」と同義の、どんな音楽にでも使える汎用の言葉だった可能性が高い。
このことは「ブルース」という言葉の起源とは別の、使われ方の問題である。
通常はジャズの領域に入れられている「ブルース」と命名された1910年代の曲群のほとんどはラグタイムやフォックストロットであり、ブルースの源となったと想定できる「原ブルース感覚」的な黒人の音楽性を大もとでは含んでいるかもしれないが、すでに充分過ぎるほど西洋音楽とブレンドされ、いわゆるブルースとは全く別様に発展した商業音楽である。
(牧野直也『チャーリー・パーカー伝:全音源でたどるジャズ革命の奇跡』(アルテスパブリッシング、2022年9月刊、268〜269頁)
ここで言われている「原ブルース感覚」なるものに、おそらく自分はいかれてしまったわけで、「つまり、『ブルース』ということばは、1920年代以降、少しづつ黒人起源の音楽というニュアンスを強めてゆき、1940年代に入ってからはほぼそのように認知され、『ブルース構造』を持つ音楽に専用されるようになってゆくのである。そして、黒人の側でも、それに見合った意識が高まっていって、ブルースを専業とする『ブルースマン』が成立するのである。」(『前掲書』271〜272頁)というような路線に乗っかってジャズだけじゃなくロックも聴き続ける日々というか、その日暮らしにいたったようなのだ。宮澤賢治の「ラツグの音譜をばら撒きだ」(「火薬と紙幣」)の詩行の背後でラグタイム・ピアノのリズムがまっさきに浮かんさりする。
ジャズの世界では、ルイ・アームストロング、デューク・エリントン、さらにはチャーリー・パーカーが、人の声ではもはや歌えない高度な水準へと、ブルースを上昇させていった。
その時から、黒人の疎外された知性(ジャズ)と感性的身体(ブルース)は分裂しているのである。ジャズは黒人知性の疎外態であり、ジャズメンはブルースを身体感覚で演奏することはできない。彼らは、常に外から、ブルースを解体的にしか扱うことができない存在なのだ。
(『前掲書』274〜275頁)
かえりみても自分はこてこての“ブルース”よりも、「原ブルース感覚」を秘めたり、「ブルースを解体的に」取り入れているジャズやロックの演奏を追いかけてきたようだ。
いずれの分野もそうかもしれないが、人の好みなんて奇怪千万に相違ない。今はない富山ジャズクラブ会員のなかに、数あるビッグバンドの中のデューク・エリントンしか聴かないという強面ジャズファンもいた。ユニークな漫画家のつげ義春もクラシック、それもバッハ以前しか聴かないというではないか。いまどんなの聴いている?と尋ねられ、ニーナ・シモンやフランク・シナトラやサミー・デイヴィス・ジュニアなどと応じたら、そんなのジャズじゃないと言われ、妻が憤慨していたこともあった。
後々わかったことだが、ジャズ友だった I 谷さんは家族の目があって家ではジャズを聴けない境遇にあったようだ。亡くなられた際、押入れから大量に出てきた[はずの]ジャズLPのその後の行方までは知らないが。
ジャズを聴いていて家人から文句を言われるどころか一緒に楽しみ、そのうちジャズのライブチケットまで買ってきてくれるような家族は稀だったのかもしれない。
俺は油井正一が好きだ。紫綬褒章受章パーティのスピーチを覚えている。映画、自動車、ジャズは十九世紀の末に開発されましたが、実用化されたのは二〇世紀になってからでありました。私が昭和十四年にジャズ評論をはじめたのは、音楽評論といえばクラシックしかなかったことへの義憤でありました。戦後になっても長い間、日本のジャズファンはジャズは戦勝国アメリカの白人音楽だと思っていたのであります。あにはからんや、ジャズは黒人のものでありました。それが大衆的にわかったのは一九六一年のアート・ブレイキーとジャズメッセンジャーズの来日でありますが、さらに大いに評価しなければならないことは、一九五四年の「モカンボ」において、すでにわが日本ジャズの先達たちは正しくも黒人ジャズの道を歩んでいたことであります。そのようなジャズの啓蒙と普及に半世紀をついやしてきた私に、天皇陛下から紫綬褒章を賜るとは感無量であります。
(平岡正明「相倉さんのこと:ジャズ批評の夜明けを走る」/「第二部 ジャズ喫茶の蛾の死骸/『毒血と薔薇:コルトレーンに捧ぐ』国書刊行会、2007年7月刊、122〜123頁)
幻のモカンボセッションについては誰かにレコードで聴かせてもらったような記憶があるが、ずいぶん前のことではっきりしない。
1961年1月14日、東京、日比谷公会堂でライブ録音されたアート・ブレイキーとジャズメッセンジャーズの未発表ライブアルバムが数年前にCD化され、ようやく聴くことができた。素晴らしいの一語に尽きる。
1960年代半ば過ぎ、衰退に向かうジャズシーンに未練たっぷりだった耳にビートルズ以外のロックはどのように聴こえていたのか、ロックシーンに乗り遅れがちだったということだけは確かだ。日本のレコード会社が直輸入盤ではなく、国内盤ジャズレコードの作成・販売を競っていた頃、すでに本国アメリカではジャズレコードの売り上げはロックのそれに比べて下火になっていた。
1970年代半ばから1980年代にかけて知り合った音楽仲間にはロックをメインにその余白でジャズも聴くという若者たちもいた。ドラマーを目指した東京からUターンしたという某君に招かれ、夫婦で訪れた納屋の二階でいったい何を聴かせてもらったのか思いだせない。使われていた英国性の高級スピーカーシステムとマッキントッシュの管球アンプのことはよく覚えている。あんな重たいアンプをハワイまで買いに行ってよくぞ自宅に持ち帰ったものだ。
妻が職場のクラシック愛好家から招かれたというので、オーディオ名器に目がない某君も誘って訪れた瀟洒な洋間で、いかなる名器の組み合わせで何を聴いて帰ったのかまるで覚えがない。
当時存続していた富山ジャズクラブの会員の方々のご自宅にも招かれ、あちこち夫婦ででおじゃまさせてもらったが、某家の襖で囲われた和室で聴かされたジャズボーカルはため息が出るほど素晴らしかった。日本の民家そのままの部屋でも、それなりの知恵とお金をかけたオーディオ装置から再生されるさまざまな音楽が際立つような体験をさせてもらった。
我が家のリスニングルームにも数えられないくらいのジャズファンが訪れては聴き去られたが、もはや交友は皆無だ。ジャズファンが嵩じてレコードの買取&販売を生業にされたようなO沢店主の葬儀にお参りした折に幾人かの参列者から、その節はお聴かせいただいてどうも‥‥‥とご挨拶いただいたのに、もう忘却の花びらだった。
ビートルズ誕生のあとに出てきたロック評論家の第一世代の多くが、チャック・ベリーやリトル・リチャードなどのいかにも若者好みの脂ぎった「ロックンロール」と、60年代に芸術として開花した「ロック」を別物と見なしていた。そんな彼らにとって「パンク」とは、前後して出現した「ヘヴィメタル」と同様に、ロックから枝分かれした無数の新ジャンルのひとつにすぎなかった。だがレスターはそのような分類に対しては無視を決め込んだ。彼にとってはどれもがロックンロールだったのだ。リッチー・ヴァレンスの〈ラ・バンバ〉や、キングスメンの〈ルイ・ルイ〉、キンクスの〈ユー・リアリー・ガット・ミー〉、ザ・ストゥージズの〈ノー・ファン〉、そしてラモーンズの〈電撃[ブリッツクリーグ=るび]バップ〉に至るまで、彼が認めたあらゆる音楽は一枚の地図のなかに存在していた。「かくしてリサイクルがおこなわれるたび、ロックンロールの20年の歴史の詰まった3つのコードがどんどんと単純化されていくのだ」とレスターは書いた。
レスターに言わせれば彼の「パンクとしてのキャリア/人生」の幕開けは、3ドル50セントでカウント・ファイブのアルバムを手にいれた10年前のサンディエゴのラトナーズ・レコードでのことだった。目下28歳となった彼は、新たなロックンシーンのなかで自分がすでに年老いてしまったかのように感じていたが、そんな彼だからこそロックの美学を系統立てて語る資格があるとも言えた。「ロックンロールとはつまり、俺が思うに大衆芸術の究極の形であり、また民主主義の躍動でもあるが、それはつまり誰にでもできるものだということなのだ。ロックンロールとでもパンクロックとでも、なんとでも好きに呼べばいいとは思うが、それをやろうと思うなら必要なのはただひとつ、図太さだ。ロックンロールとはアティテュードそのものであり、それを備えてさえいれば、誰になんと言われようと気にせず突き進めばいい。なぜって情熱こそがすべてであり、音楽とはすなわち情熱にほかならないのだから」[下線部は原文傍点]
(ジム・デロガティス 田内万里夫 訳『レスター・バングス:伝説のロック評論家、その言葉と生涯』トンカチ、2024年4月刊、229〜230頁)
付属病院のある大学の付属図書館に勤めていたころの中年の身体が、パット・メセニー.グループの低音を効かせた演奏に拒絶反応を起こしたことがあった。
午前の仕事中に「なんだか左耳の調子がおかしい」とつぶやいたのを聞きつけた I 波係員が、「係長、耳の病気はほっておいたりすると急激に悪化したりするよ」と言うだけでなく、さっさと付属病院で耳鼻科の予約を済ませてきてくれた。彼女は地元の短大で司書資格をとって付属病院で働きながら教務部図書課への配置換えを実現した有能者だった。たぶん何年も耳鼻科の医局にいて臨床知識も豊富だったのだろう。
「黒人の疎外された知性(ジャズ)と感性的身体(ブルース)は分裂している」と言うのをもう一歩踏み込んで、「唯脳論」のように何でもかんでも脳の働きに閉じこめないで、感性的身体は層をなすようにしてそれぞれが多様な対象を受容しながらパフォーマンスしていると観たほうがいいのではないか。連日テレビ放映されているパリ・オリンピック2024の新旧さまざまな種目などみるにつけ、そんな風に感じてしまうのだ。(2024年8月23日記/10月11日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(27)あるいは稽古する身体
心を言語によって定義づけ、知的に理解しようとすれば必ず惑う。わかる
とは、心に心を以って「応じる」という身体による行為しかありえないので
はないか。
たとえば、心づくしの料理を味わうことは、食材の理解ではなく、食べる
という行為である。供された料理を食べてみる。応じることがすでに理解な
のだ。つまり以心伝心とは忖度ではなく、互いの身体の応答のことだ。
心を以って心を伝えるとは、黙っていても心が自ずと通じることを意味し
ない。形のない心をいかに我が身に映すか。それは確答に至ることのない、
終始しない問いでありあり続ける。
(尹 雄大『脇道にそれる:〈正しさ〉を手放すということ』春秋社、
2018年5月刊、)
三十代なかばから五十代はじめまで、医学薬学系図書館で働いた十数年の後半は、図書館本来の業務に新たな図書館システムのネットワーク化業務が重なった、いわゆる“二足の草鞋”を残業でこなす日々が多かった。もともと丈夫とは言えない中年期の身体/生理的変調にみまわれ、耳鼻科、眼科、歯科口腔外科、内科そのほか付属病院各科で診察を受けたりしながら、幸運にも何かを患うまでにはいたらなかったなかで、部位によって異なる身体/生理症状の自覚と伝達にかかわる五感の仕組みと、インターネットが網羅するネットワークのTCP/IPプロトコルの4層に分かれた通信構造とを関連付けるように類推してみたくなったのだ。
1960年代末にアメリカで開発された最先端技術のインターネットが勤め先だった医・薬学系図書館の現場に浸透してくるまでにほぼ20年を要したことになる。ちょうどバブル景気の渦中ということで本省へ要求すれば図書館システムの電算化予算が通ると見込んではいたが、まさかコンピューター音痴の自分にその執行の責が丸投げされたことなんて、過ぎてみれば“瓢箪から駒”みたいなものだった。
ことに当たって必要な知識のなさを嘆く暇などなく、きゅうきょ立ち上げたワーキンググループのメンバーや受注業者から派遣された担当SEだけでなく、他大学の導入事例なども参考にシステム運用開始に漕ぎつけた。
ほどなく人事異動先の大学付属図書館でも新たなシステム更新が待ち受けていて、学内の総合情報処理センターや他学部のネットワーク&システムに詳しい教職員だけでなく、学内外の創成期のネットーワークグループの書き込みにもずいぶん助けられた。当時のネット界隈は、とにかかく“タコは育てよ”という気風が漲っていて、事情や状況説明を明かしさえすれば、どんなつまらぬ疑問にも誰かが丁寧に答えてくれた。だから逆の立場になったときは、自分もそうするように心がけたきた。
実用化されつつあるインターネットに対して開かれた姿勢で「ほぼ日刊イトイ新聞」(1998年6月6日)を立ち上げた糸井重里の姿勢も際立っていたが、昭和の終わりからから平成はじめにかけての国内のネットワークの匿名じゃない書き込み状況など、令和になってSNSを始めた人たちにはもはや昔話だろう。小田嶋隆のようにSNSによって文章力を開花させた[小田嶋隆著、武田砂鉄撰『災間の唄』サイゾー、2020年10月刊]ような人は他にもいるのだろうか。
「書く」ことは、それはSNS上であれどこであれ、自信を「指示表出」と「自己表出」に引き裂くことであり、またその作業を通して、書かれた対象を強引に「祭式」に巻き込んでゆく作業である。このようにしてぼくたちは現在、SNS上に文字を書きながら、あるいは、「映像」として表象されながら、互いが互いを「歴史」の主体へと生成させてゆく途上にある。この生成力はおそらく、きわめて大きい。この力にあわせてぼくたちは自身の規範をアップグレードしてゆく必要があるのだが、過去と現在と未来が矛盾の中で渦を巻いているこのような「書くこと」と「話すこと」の編成を変化させることは、もっぱら「書き言葉」でもって生産力の寡占をおこなってきた人たちにとっては、かなりオソロシイ出来事なのではないかと思われる。
しかし、ツイッターでつぶやかれるすべての言葉には、ぼくたちのテクノロジーを最大限に反映させたパワーがあり、そこでリリースされる「書き言葉」の矛盾を、これまでの「詩」や「小説」などのそれと同時に経験しながら、また、親しい人との「会話」によってその「表出」を相対化しながら、書くことによる『精神の劇」を毎日、気軽に体験できるようになったことは、シンプルにとても良いことだと思う。
(大谷能生『〈ツイッター〉にとって美とは何か:SNS以後に「書く」ということ』フィルムアート社、2023年11月刊、330頁)
心身の絶不調で図書館仕事を辞め、自宅療養を1年半ほど経て回復に向かい、やがて断りきれず受け持つことになった司書課程の情報機器/ネットワーク関連授業の受講学生のひとりから、教科書が理解できなくて授業についていけないと言われて立ち往生した。熟慮のすえ、翌年度から情報検索演習課題以外の科目の教科書の利用を止めてしまった。ネット上の関連情報源なども参照できるよう作成したテキストをWebで授業中に閲覧できるようにし、身体の言葉によるコミュニケーションをモデルにして、メタ情報次数とその検索の仕組みおよび提供サービスをゼロと1からなるプログラミング言語によってネットワーク上に構築するフローチャート[流れ図]を自作するという課題を試みたが、スマホを使って様々なデータをやり取りしているのがあまりにも当たり前になりすぎていて、なぜできるかを問う〈本と読者と図書館〉を絡めた本来的な図書館職員姿勢を掘り起こすまでにはいたらなかったようだ。
当時も今も事情は変わらないだろうが、毎年20数名前後に及んだ司書課程の受講生のほとんどが、司書資格を取得したとしても卒業時に図書館への就職口が皆無に等しいことを肌で感じ取っていたようで、授業に身が入らぬのも無理からぬことであったろう。
司書課程は多くの問題を含んでいる。課程が大学や短大にありながら、司書講習に準じた科目と単位を履修させているため、文部省の中でも高等教育局の管轄ではなく、生涯学習局の学習情報課図書館振興係の担当で、科目や単位数に自由度がない。学生の資格志向が強く、年間におよそ七千名の資格取得学生が出て、図書館員の空席となる数に比して供給過剰である。我が国に図書館員の専門制度がないので、人事異動で図書館に無資格者が採用されたり、異動してきたりする。また有資格者異動で図書館以外の部署に出されることもあり、資格の無駄が多い。大学と短大で同じ内容の司書課程を履修させるので、大学と司書の資格は同じである。その他多くの問題が指摘されているが、改善を指導する場がないことが一番大きな問題である。
(『近代日本図書館の歩み 本篇』日本図書館協会、1993年12月刊、503頁)
よくも「供給過剰」などとまるで他人ごとのような記述だが、1950年の図書館法施行規則による司書資格の習得単位の制定当初からいずれこうなることはわかっていて何もせず、1980年代以降公共図書館数は4倍近く増えているのに専任職員数は2003年をピークに減少しているように、その後も放置されたまま手付かずの状態が今世紀に入っても続いていて、あいかわらず司書資格の単位履修生は先行きを塞がれている。
「その実態はなんら変わっていなかったし、これらのテキストを発行する教科書会社としての日本図書館協会と大学図書館情報科の関係者たちだけが安泰だったとしか思えない。本当にごく一部の人を除き、実効力を伴わない資格トレトレ詐欺と変わらないのではないか。」(中村文孝、小田光雄『私たちが図書館について知っている二、三の事柄』論創社、2022年8月刊、58頁)と批判されても「図書館業界」[そんなものがあるとしてだが]は事態を黙殺したままなのだ。
司書資格を取って卒業したらとりあえず派遣会社に登録しておいて司書資格者の求人を待ちながら、書店のアルバイトで食いつなぐ卒業生もいたような覚えがある。
大学図書館のサービス現場で働いていた際に上司から担当係員の雇止めをされたり、リストラの穴埋めに派遣会社の人員を充てがわれた中には短大卒司書有資格者や某私立大の図書館情報学科の卒業生も混じっていた。えてして彼女たちは仕事熱心なものだから契約時間をはみ出したり、とにかく定員内職員以上に働き過ぎないよう手綱を引き絞る必要があった。
短大の授業の合間などに男女学生の区別なく図書館就職のコネを問いただされたりしたが、授業内容に関する質問は圧倒的に女子学生が多かった。
ことのほかネットワークの結節点の仕組みのルータとハブの機能を混同しがちだったけど、そのようなネットワーク機器のことよりも、フラットで柔軟性のあるインターネットの重層的な仕組みーーメール、ファイル転送などアプリケーション層(4層)から、有線や無線LANなどネットワークインターフェイス層(1層)まで、その間のトランスポート層(3層)とインターネット層(2層)を含めた四つの層が隣接する層のみと関わりながら、相対的に独立して働くという仕組みが身体的なコミュニケーションの多層性/重層性のモデル化のようにも観えたのだが、受講生にはどう映っていたのだろうか。
キーボードを叩きながらノートをとったり、机上の端末画面のWebテキストをスマホで写し撮ったり、指づかいが達者な学生たちは、五本の指をそれぞれ独立して自在に使えることを省みることなどあったのだろうか。
著書やツイッター改めXの書き込みから「身体の層位の主従主客関係を経験的に知って行きながら」の稽古で武術を指導されているようにみえる光岡英稔師の指摘から具体的な稽古法におもいをめぐらしたりしているのだが‥‥‥。
この稽古方法や身体技法が可能な理由の一つとしては私たち人間のみが五指の指を一つ一つ別々に感覚できる生き物であり、これが人間の特徴の一つとも言える所がある。私が知る範囲では他の動物は五指を爪先まで全て一遍に感覚し動かしてしまう。そこに来て人間は肘などを分断する感性を持ち始めたことと、五指を分断して感覚できるようになったことが、その後の人類史における人類の行動原理を大きく左右することになる。光岡武学では、ここの内容に踏み込んで稽古を進めていたが、それが日本古来の疫病退散の身体技法に繋がっていることに最近あらためて気づけ、それを稽古研究でも実践してみている。
(光岡英稔@ツイッター改めX2024年4月)
一昔前まではメンコやパッチンから、おはじきにお手玉やあやとりなど、手指を使った遊びにことかかなかったけど、今の子供らだってキーボードやタッチパネル以外にも各種ゲーム等のコントローラーやスマホそのほかで指づかいに遅れはないだろう。
掴む、握る、絞る、摘む、放つ、弾くそのほか五指の働きとその内側の経験を稽古場で修練させるにはほど遠いわが身だが、そこを踏まえてさまざまな身体内部の経験との関係性を知って稽古を行うことによってどのような身体観が垣間見えるか、棒や木刀を使って手指からの身体的な繋がり方の形成や分離の仕方の形成などの階梯をこと細かく稽古を積んでいけばいいのか、バーチャルでもいいから仮想できたらなんて妄想してもしょうがないのだが。
「この思考の身体の層位置ある脳化、概念化、観念化、想念化、知覚化、意識化をせずに身体の聲を聴く感性を身につける必要がある。」とされる光岡武学でよく出て来る「経験的身体」の「経験」が何を指すのかがわかりにくい。
ずいぶん前に心身ともども行き詰って仕事も続けられなくなったのがきっかけで甲野善紀師や光岡英稔師を遠くから追いかけるようになったのも、老いて陥ち入った昨秋の二か月余りの精神病棟暮らしで途絶えてしまっていたのに、ここにきて性懲りも無く再燃したようなのだ。
そこへ追い打ちをかけるように今年の8月の終わりに「心不全」が発覚し、手術をともなう一ヶ月半の入院を余儀なくされ、あらためて自分の身体にとって起きる、歩く、動く[運動する]とは何か、どういうことかを考えさせられることとなった。
中沢新一はこの本で、チベット仏教の身体の構成要素として「管」、「風」、「滴」のような概念について触れている。これは「血管」や「筋肉」や「体液(リンパ液)」のように言っても同じことだし、「空孔」や「骨」や「筋肉」と言っても同じことだと思える。なぜなら、未開の時期の肉体表面や血脈や体流の流れや、受精行為の表面の形態をどうみるかということにほかならないと考えられるからだ。そしてこの基本要素をどうみなすかは同じ未開の段階にある地域と宗教性を異にすれば異なった選択がいくつでもありうる。未開段階の宗教性の豊富さや高度さ、累積の結果がわたしたちの現在の宗教概念に比べてもっている綜合性の怖さ深さは、これらの身体性についての幼稚な構成感からはじめて、現在存在する宗教についての概念に、はるかに根源的でもあり、豊饒でもあるような宗教性をもたらしているところにある。
(吉本隆明「解説」/中沢新一『チベットのモーツアルト』講談社学術文庫、2003年4月刊、331頁)
考古学的でもなく、かといって宗教的でもなく、みづからの身体にどう向き合えばよいのか、半信半疑の自分の生活を成り立たせている自分の存在。その身体的存在の中心に生命があり、それを前提としてわれわれの知識や思いや感情などの自我意識と関係する頭で脳化された世界や物質世界が存在する。
中学生の頃からの疑問もいつの間にか世間ずれして、気づけば生命より生活を第一とみなしたり、身体より脳化された世界や知識などの情報を最優先する職場で身体をロボット化させ、頭脳が身体の属性であり、生命があり自らが存在するから自分の生活ができる関係の方向性を見誤ったり、逆転の落とし穴にはまりそうになったりする。
では、その生命を成り立たせているのは何かというのがよくわからないなりに、自分の頭脳で自己認識できる自分が存在のすべてではなく、あくまでも断片的な事実の寄せ集めでしかなかろう。
ヘルメットをかぶった大学生も、ヘルメットをかぶらなかった大学生も、自分達のあり方が大学へ行かない高校生達にとってどんな影響を与えているのかを考えなかった。
なぜ一九六〇年代の末に学生達の騒乱が起こったのかは、当事者の学生達も含めて、誰にも分からない。それ以前の常識からすれば、学生達の騒乱は左翼的なもので政治的なのもであってしかるべきだったが、実際はそうではなかった。なんだったのかは誰にも分からない。ただ、焼けたアスファルトの上に砂を撒いて道路が出来上がるように、平和で豊かな社会がその後に出来上がった。大阪の万博に行った後で昭生の兄が家を出て行ったのも、その足下にまだ残っていた地熱を感じたせいかもしれない。
(橋本治「第一章 息子達」/『草薙の剣』新潮社、2018年3月刊、41頁)
おそらく人間の自己意識は自分の思い通りになる私的な自分や囲い込みを好む傾向にあるのだろう。知能や感情などの本能などが持つコントロール欲求や操作願望だけでなく、生得的な本能も関わってきたりする。
誰しも自分の思い通りにならないこと、認識不能なこと、経験値にないことなど自分にとっての都合のよくないこと、知らないことを本能的にも処世的にも嫌う癖がある。
「みちのく山道」や「バランスボード」に乗ったように「意識的に身体を動かさない」とか「ひもトレ」を身につけて「直接結果を求めない」型などを用いた稽古を行った場合には「型」が示してくれる動きを通じて結果として身体が自ずと〈自然〉へと戻ろうとし始める。これらは妻と一緒に日常的に体験したことがらだ。
そこで人が無自覚に習慣化している意識的な動きをなぞる練習を繰り返しますと身体が新たに変わろうとしているにも関わらず意識的な動きによって身体を過去の習慣的な運動へと引き戻そうとし、未来へ変わろうとしている身体との乖離が生じます。/
しかし、身体が自然と変わろうとする作用の方が常に勝ってしまう故に”自然と変化しようとしている身体”には”過去に居着こうとしている身体”は後れを取ってしまい怪我や負傷などが乖離から生じる場合もあります。/
そのような稽古を続けますと一歩前進一歩後退を繰り返すことになります。また、無理に繰り返しますと一歩前進し二歩三歩後退することにもなりかねません。/
型などを通じて行う無意識に結果として効果が得られる稽古方法か、意識して過去の習慣的な運動を繰り返す前進しない練習方法を選ぶのかは各個人の問題となりますが、後者の方は私からは余り勧められません。/
まぁ、どちらを選択しても、明日もまた太陽は東から昇り西へと沈んで行くので、どちらを選ぼうと何とかなると言えば何とかなりますが、あとは個々が身心共に納得の行くような選択を取れているかどうかになります。
[光岡英稔@ツイッター改めXからの抜き書きメモ]
武道の現場に足を踏み入れたこともないが、中学の部活だけでなく子どもらや大人のスポーツ練習の現場でも日常化した風景というか、《稽古と身体の乖離》についてはいつも悩まされた。
一人稽古か集団稽古かで「型」の移行が問題なになってくるが、先人から教えられた「型」を通じて自らのどうしようもなさを省みることに型の存在意義を認めることなく、盲目的に型に当てはめた範囲内で自己を固定化しがちである。
中学の剣道部活での体育館の雑巾がけからして稽古の端緒になっていたことにどれだけ自覚的であったろうか。持つ、掴む、絞る、握るから、抑える、掛けるなどの緩むから締まるまでが身体で観ると同じ現象の表裏で生じていることにあまりにも無頓着だった。
初心者の子どもたちとバドミントンのオーバーヘッドの構えをして素振りを始めると、力いっぱい握って床を叩きそうになったりする。糸電話の糸の張り具合みたいなバランスといっても通じないだろうから、自分のラケットが空を切るような音を聴くように振りなさいと言ってみたりする。もちろん腕力が育っていな子どもの腕で振っても風切り音がするわけがないのだが、強く振りがちな“気”を逸らすだけで力みが抜けたりするから面白い。グリップも緩むでもなく締めるでもなく、ラケットが手指からすっぽ抜けなければいいのだが、身体全体のほどよい緊張バランスが前提になるようだ。
そんなバランス感覚も、点滴その他さまざまな管に繋がれて病院のベッドに転がされていたら何の役にも立たなくなる。一ヶ月も経たないうちに身体が萎えてしまって歩くどころか立つこともおぼつかなくなる。追い打ちをかけるようにもともとか細い食欲が病院[減塩]食を受けつけず、どうにも喉を通りにくくなってくる。毎食半分以上残さないようにするのが苦痛というか、慣れ親しんだ家庭料理など忘れて「薬膳」の一種と思い込もうとしたが退院の日まで慣れることはできなかった。(2024年11月1日記/10日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(番外)吉本さんの13回忌に〈追悼ー抄ー〉
吉本さん。
こういう日がくることは、ずっとわかっていました。
ご本人といっしょに、そういう日のことについて
話したことも、何度かありましたよね。
「町内会で、小さいテントみたいなものを借りて、
簡単にやってもらえたら、それがいちばんいい。
吉本家の墓は、この駅で降りて、
入り口からこうしてこうして行けばわかります。
途中に誰それの墓があるから、
それを目印にすればいいや」
なんて事務的なことを、伝言のように聞いていました。
「死っていうのは、じぶんに属してないんですよ。
じぶんは死んじゃうんで、わからねぇから、
家族とかね、周りが決めるものなんです」
死んでやろうかと思ったときそのことに気付いた、
と、闘病がはじまったころに言ってましたよね。
(糸井重里「今日のダーリン」/『ほぼ日刊イトイ新聞』
2012年3月16日)
吉本さんの誕生月(1924[大正13]年11月25日)を迎えて今年が十三回忌にあたることに思いを馳せた。『朝日新聞デジタル』で「吉本隆明『生誕100年祭』天皇制や戦争論、全共闘など論じ合う」という記事を見かけたが、没後12年を飛び越えて一気に100年と言うのは‥‥‥。
吉本さんの生涯すべてを受けとめるなんて、とてもじゃないが病み上がりの身にあまる。手始めというか身近なところで、吉本さんの訃報に接した際に作成した「吉本隆明追悼記事(文・特集)一覧/書誌」[http://www.fitweb.or.jp/~taka/ytTsuito.html]を見直したら、なんと196件もあった。
最近訃報に接した楳図かずおやクインシー・ジョーンズの追悼記事もネットでのぞいたりしたが比べるまでもなく吉本さんへの追悼記事は桁外れの数だった。玉石混交で数が多ければいいというものじゃないけれども。書誌事項に本文を収録した中から選んんだ〈追悼の言葉〉を吉本さんの「13回忌」に捧げたい。
【1/11】
主著と言われる「共同幻想論」は難解だと言われていますが、徒党を組むと徒党から外される人間ができる、そこに様々な問題が発生するという考えは一言で言えば「近代の個人主義」を裏返して言っていただけです。
個人主義というと「ブルジョワ的な西欧の概念」だとムード的に反発する若者の多い時代に、「共同性」がダメだから「自立せよ」というメッセージに置き換えていたのです。結果的にシンプルな考え方ゆえに、欧米の国民国家が陥ったナショナリズムの問題も越えてしまう迫力を持っていたようにも思います。
こうした普遍的な仕事の他に、吉本さんの真骨頂とも言える他の誰にも真似のできない領域が2つあります。
1つは人の行き方の核にあるのは核家族という思想、突き詰めればカップルという関係だという思想です。漱石論もそうですし、「共同幻想論」「心的現象論」にも一貫していた思想ですが、今、人々の孤立が問題になっている時代に、改めて読み返す価値があるように思います。
もう1つは、思想的な「転向」への批判です。周囲の状況が変化したり、自分が成熟することで人間は考え方を変えることはあります。ですが、そのように変化した事情を自他に説明できない形で突然に保守派が左翼になったり、国際主義者が排外主義者になったりするのはダメであり、「思想の一貫性」を全うしなくてはならないというのです。一方で、実社会と隔絶したまま思想だけ維持してもダメという批判も含めているところが吉本さんらしいと思います。
[中略]
吉本さんには『追悼私記』という追悼文をまとめた一冊があるぐらいで、妙な表現ですが、オビチュアリの名手と言えます。中でも文庫版に収められている江藤淳に対する追悼文は、読む者の心の中心を突き刺すような痛切さを持っています。それはともかく、吉本さん自身の訃報に接して、その『追悼私記』の中の政枝さんという実の姉への追悼文(1948年)を再読してみました。
「無類に哀切な死を描き得るのは、無類に冷静な心だけである。転倒した悲嘆の心では如何にしても死の切実さは描き得ない」
で始まる文章は24歳にして、吉本さんの才能と誠実な人柄がよく現れています。思えば、このような「冷静な心」のあり方そのものを私は吉本さんに教わって育ったように思うのです。「転倒した心」では駄目だということもそこには含まれます。今はただ感謝の念しかありません。
(冷泉彰彦「追悼、吉本隆明氏を送る」/[コラム&ブログ:プリンストン発 新潮流アメリカ]/『Newsweek日本版』2012年3月16日)
【2/11】
市井の片隅に生まれ、そだち、子を生み、生活し、老いて死ぬといった生涯をくりかえした無数の人物は、千年に一度しかこの世にあらわれない人物の価値とまったくおなじである。
市井の片隅に生き死にした人物のほうが、判断の蓄積や、生涯にであったことの累積について、けっして単純でもなければ劣っているわけでもない。これは、じつはわたしたちがかんがえているよりもずっと怖ろしいことである。
吉本隆明という人はその恐ろしさをずっと表現しつづけた。奥さんの和子さんは、そうした夫を、あなたの背中で悪魔の翼がばたばたと音を立てていると言った。そのとおりだろう。その和子さんがなぜ隆明を選んだのかというと、あの人は立ち小便をしない人だから、とも言った。同じことかもしれない。
千年に一度しかこの世界にあらわれないといった巨匠も戦後最大の思想家も市井の片隅に生き死にした人物と変わるものではない、ということはどういうことなのか。
(極東ブログ「吉本隆明が亡くなった」2012年3月16日)
【3/11】
京都精華大学人文学部開設時に吉本隆明氏よりいただいた言葉をご紹介します。
「はじめて出会った大学らしい大学。」
大学は紙と石と言葉でできた塔で、先生がたはこわい番人の集まりだ。学生になったら、できるだけ内壁や飾り窓に手を触れずに、そっと入って、そっと出ちまうのがいちばんいい。大学は敵役としてだけ存在の価値があるのだ。ながいあいだそう思ってきた。でも、この京都精華大学は、はじめから印象がすこしちがっていた。普段着のまま入って、目いっぱい自由に壁に落書きしたり、飾り窓に垢をつけたりして、いい気分で出てゆける雰囲気を生み出している。これはもしかすると、はじめて出会った大学らしい大学だという気がする。
(京都精華大学「京都精華大学人文学部開設時に吉本隆明氏よりいただいた言葉をご紹介します。」/「吉本隆明氏のご逝去をお悔やみ申し上げます」2012年3月17日)
【4/11】
特に彼の文章(文体)が大好きでした。引用の文(=他者の思考)と地の文(=自分の思考)との処理の仕方が絶妙で、幼い私は彼に思考の内容にというよりは、その引用の文体に、あるいは読書の仕方に惚れ込んでいました。
彼の引用は、被引用者の全体の思想(その核)をつかんだかのような引用でした。彼の引用する<文章の壮ては‖部分というよりは‖その部分が被引用者の思考の臍であるような体裁をいつも醸し出していました ー その臍となる部分のことを彼は後の著作で〈作品〉の「入射角」「出射角」と呼ぶようになっていました|
彼の引用批評は、いわば人格批評と紙一重の緊迫感がありました。人と思想とは”同じ”なんだと。「関係の絶対性」はぐるっと一周してそういう思想だったのだと私は思います。だからこそ、時として排外的、時として寛容という振幅を持っていたのです。
現在の検索主義の引用とは正反対の思考がそこにあった。こんなふうに本が読めたら、どんなふ<うに自羊になれるんだろう‖と私はいつも思っていました|
(芦田宏直「追悼・吉本隆明」/『芦田の毎日』2012年3月17日)
【5/11】
この偉大な思想家にして文学者と会話を交わしたのは、
後にも先にも、41歳の時、一回きりだ。
松江市から車を飛ばし、講演依頼に千駄木の自宅を訪問し、
1時間ほど文学の話を聞いた。
その時、
吉本隆明が、どこかに、山本周五郎のことを、
わが国でたった一人の異色の作家だ、と書いていたことについて、
あれはどういう意味でしょうか、と尋ねたら、
山本周五郎は、大衆文学から純文学に登りつめたたった一人の作家だ。
と山本周五郎への高い評価を聞かせてくれ、
高校時代から山本周五郎作品にのめりこんで、
『おさん』や『あとのない仮名』に高い文学性を感じてきた僕は、
自分が褒められたみたいに嬉しかったのを、今でも覚えている。
あなたね。若手の作家で、誰が一番いいと思いますか?
と訊かれ、考え込んでいると、
それはね、
親馬鹿から言うのではなく、娘の「ばなな」です。
娘は素晴らしい作品を書いています。
いま、一番注目すべき作家です。
と断言した。
僕は、自分の父親にただの一回も褒められたことなく生きてきたので、
娘を絶賛する父親に、何をどう答えていいのかわからず、
ただ黙ってうなずきながら、
なんか、微笑ましくていいなあ、と、それだけを思っていた。
(世川行介「吉本隆明の死 (1)〜(2)」/『世川行介放浪日記』2012年3月17/18日)
【6/11】
どんな思想も、どんな行動も、ふつうは、その「正面」しか見ることができない。それを見ながら、ぼくたちは、ふと、「立派そうなことをいっているが、実際はどんな人間なんだろう」とか「ほんとうは、ぼくたちのことなんか歯牙にもかけてないんじゃないか」 と疑う。
けれども、吉本さんは、「正面」だけではなく、その思想の「後ろ姿」も見せることができた。彼の思想やことばや行動が、彼の、どんな暮らし、どんな生き方、どんな 性格、どんな個人的な来歴や規律からやって来るのか、想像できるような気がした。どんな思想家も、結局は、ぼくたちの背後からけしかけるだけなのに、吉本さんだけは、ぼくたちの前で、ぼくたちに背中を見せ、ぼくたちの楯になろうとしているかのようだった。
ここからは、個人的な、「ぼくの吉本さん」について書きたい。ぼくもまた、半世紀前に、吉本さんの詩にぶつかった少年のひとりだった。それから、 吉本さんの政治思想や批評に驚いた若者のひとりだった。ある時、本に掲載された一枚の 写真を見た。
吉本さんが眼帯をした幼女を抱いて、無骨な手つきで絵本を読んであげている写真だった。その瞬間、ずっと読んできた吉本さんのことばのすべてが繋がり、腑に落ちた気がした 。「この人がほんものでないなら、この世界にほんものなんか一つもない」とぼくは思った。
(高橋源一郎「思想の「後ろ姿」見せてくれた:追悼・吉本隆明さん」/『朝日新聞』2012年3月18日)
【7/11】
「ある編集者から『怪物を撮ってほしい』と依頼されたのが最初でした。話し方は誠実で穏やか。相手に緊張感を与えない。でも、ファインダー越しに見ると、編集者が怪物と呼ぶ理由がわかった。得体の知れない深さを感じるんです。撮影のたびに私は『今回も納得がいかない。また撮らせてください』とお願いし続けることになりました」
休暇の家族旅行にまで吉田氏は随行し、シャッターを切り続けた。
「私は武者小路実篤も岡本太郎も撮ったけど、撮影していて飽きを感じないのは、吉本隆明ただ一人でした。普通、もうこの人はいいやって思うのだけど、それがない。人柄も素晴らしかった。知り合って間もない頃、文芸誌の仕事をご一緒したんですが、格安のギャラはきっちり折半。吉本先生の原稿あってのページなので、私は辞退を申し上げたのに聞いてくれなかったんです」
([吉田純]「吉本隆明氏撮り続けた写真家「実篤も岡本太郎も撮ったがノ」」/「Newsポストセブン」/『週刊ポスト』2012年4月6日号)
【8/11】
初めてご自宅にうかがったのはおととしの春。
15歳の男の子ふたり、女の子ふたりを連れて、1か月に1度、吉本さんにお話をうかがいに通った。『15歳の寺子屋 ひとり』はその時の記録である。
年齢差70歳。初対面の時、ぎこちなく自己紹介した彼らに吉本さんは言った。
「さあ、どうぞ。もっとお楽に。お行儀悪くなさってください。
どうぞ。なんでも聞いてください。悪いことでも何でも。
正直にお答えします。それが僕の唯一の取り柄です。
どんなことを聞かれてもいいし、どんなかたちの質問でもけっこうですよ」
この言葉通り、吉本さんは相手が子どもだからといって、ちっとも見くびったりはしなかった。進路のこと、恋愛のこと、才能のことや生きていくことについて、彼らの率直な質問に真っ向勝負で答えてくれた。いっぽう、15歳の彼らにとって「戦後思想界の巨人」という重々しい肩書や経歴はいまひとつ、ピンときていなかったに違いない。それよりも自分たちが今まさに思い悩んでいることにこれほどまでに言葉を尽くして真正面から向かってくる大人がいること、それ自体が新鮮な驚きだった。
だって「生き方を決めるのは消極性だと思います」なんて言われて、すぐに納得できるわけがない。「積極的にしろ」とか「前に出ろ」ということなら散々言われてきたけれど。
吉本さんはそんなふうに世間で言われていることとはまるで反対のことをよく言った。といって、それははったりでもなんでもない、生きてきた実感に裏打ちされた言葉なのだ。ひとたび吉本さんが語り出すと、私たちは毎回たっぷりと水をたたえた大河に放り出されたような心持ちがして途方にくれる。けれど、しばらくじーっと耳を傾けていると、やがてひとつの流れのようなものが見えてくる。おそらく吉本さん自身、語り出した時にはどこにたどりつくのか決めていなかったのではないか。考えて、考えて、考え続ける。その思考の流れを目の当たりにすることが出来たことが何よりの得難い体験だった。
「聞かれたことに何でも正直に答えようっていう心掛けだけはありましたけどね。僕なんか、それ一点張りだから。講演と違って、前もって原稿を用意するわけでなし。その場その場でやっていきましたから、仕事のやり方としては一番疲れるかたちだったかもしれません。聞かれるに任せて自分なりに回想したり、ときどきはこっちからもへんなことを聞いてやろうと思ったりしながら、つないでいった。取材としても今までで一番長かったかも知れませんね。お互い言いたい放題とまではいかなかったけれど、対話のひとつの試みとしてはたいへんうまくいったほうだなと思います」
「だからみなさんもよくごぞんじの小説で、夏目漱石の『坊っちゃん』。あれを読むと主人公の坊っちゃんの気持ちが、わかりすぎるくらいよくわかって泣けてくるんですよ」
「『坊っちゃん』は痛快な青春小説だといわれているけれど、僕はそういう坊っちゃんのことがわかりすぎて、かわいそうで、今でも読んでいると泣きべそをかきたくなるくらいこたえます。あの小説を書いた夏目漱石も「人にわかってもらえない」って経験をたくさんしてきた人なんじゃないか。『坊っちゃん』には漱石が抱えていたもろもろの悲劇みたいなものが全部出ている気がするんです」
「樹で言ったら、地面の上に見えている枝はじゃなくって、根っこの部分が言葉にもある んですよ。地面の下のえない部分がね」
「人は誰でも、誰にも言わない言葉を持ってる。沈黙も言葉なんです。沈黙に対する想像力が身についたら、本当の意味で立派な大人になるきっかけをちゃんと持っていると言っていい。僕は、うまく伝えられなかった言葉を紙に書いた。届かなかった言葉が、僕にいろんなことを教えてくれた。自分や誰かの言葉の根っこに思いをめぐらせて、それをよく知ろうとすることは、人がひとりの孤独をしのぐ時の力に、きっとなると思いますよ」
「この頃、よく思うのは今の人たちは何か中間にあることを省いているんじゃないか。本当は中間に何かあるのに、原因と結果をすぐ結びつけることでそれを解決だって思おうとしてるけれど、それは違うんじゃないか。今の考え方は何でも結論を急いでつけようとしている気がしてならないんです」
吉本隆明という人の考え方には、いつもたっぷりとした「中間」があった。
最新刊は『吉本隆明が語る親鸞』である。
この本にはCDがついているので、語る吉本隆明、その肉声にぜひ触れてみてほしい。
かつて宮澤賢治に憧れた少年が、親鸞にひかれる大人になる、その「中間」に戦争があった。「宮澤賢治のような聖人君子に憧れたけど、自分にはとうていなれないと知って、悪人でも救われると説く親鸞にひかれたのかも知れない」と吉本さんは言った。「平和がよくて、戦争が悪いなんて単純な考え方は僕にはとてもできません。かつてこの戦争は正しいことだと信じていた時代があったし、僕もいっぱしの軍国少年でした。戦争が悪なら、俺だって悪人だ」と。その「中間」にどう橋をかけるのか。吉本さんは生涯考えて、考えて、考え続けたのだと思う。
人は思い描いた理想通りには生きられない。誰もが受け入れがたい現実を、それでもどうにか受け入れながら、その先を懸命に生きている。
『十五歳の寺子屋 ひとり』の最後の授業で、吉本さんは言った。
「人はみんな、かわいそうなもんだ。宮澤賢治もかわいそうだし、夏目漱石もかわいそうだし、そういうお前はどうなんだっていわれたら、そりゃあかわいそうだ、ひでえもんだなと。人間っていうのはかわいそうなもんですよ。生きるっていうのはかわいそうなもんだ、それはもう、いたしかたのないもんだと思います。
それでもなんで生きていくのかっていったら、それは先があるからでしょう。
先があるっていうのは、そこからいつでもどうやって生き延びていくかみたいな糸口みたいなもんだ。だからとても大切な宝物みたいなもんなんだよ。どんなふうにでも、先があるんだ。このことを忘れてはいけない。生き延びていくことをばかげているととらえる考え方は、本当には存在しえないと僕は思っています。どっかでちゃんと道を見つけて、そこをたどっていくことを、誰もが本当は待ち構えていて、それは越えがたくとも越えられるし、また越えていかなくてはならない」
(Taki Harumi「吉本隆明さんのこと。:『十五歳の寺子屋 ひとり』に寄せて。」/『madame FIGARO.jp』2012年4月4日)
【9/11】
風はなくともざわざわと降るように葉が落ちてくる。落葉するアコウの大木を初めて見上げたとき、不思議な感じを受けたものだ。春、ちょうど今ごろの時分である。新葉を出す前、この常緑樹は古い葉をすっかり落とす。幹からヒゲのような気根を垂らした、生命力あふれる木だ▼苓北町の志岐八幡宮には「隆明」「真秀子[まほこ]」と名付けられたアコウが立っている。先ごろ亡くなった思想家吉本隆明さんと、娘の作家よしもとばなな(本名真秀子)さんにちなんで植えられた。志岐は吉本家の父祖の地だ▼「白色光がまばゆく輝き、水面に乱反射してまるで異世界」と詩人でもあった吉本さんは天草の海を表現している。父祖の地を訪ねたのは2度きりというが、季節はいつごろだったろうか。
(「新生面:4月6日付」/『くまにち.コム』2012年4月6日)
【10/11】
キャンパスを吉本隆明の本抱え君と歩いた青春の日々(高松市)桑内繭
千駄木の蕎麦屋に偲ぶ買物かご提げて歩きし吉本隆明(東京都)吉竹純
若き日に吉本隆明勤めたるインキ工場の青き廃液(三重県)三井一夫
巌を噛む蟋蟀(こおろぎ)の如き貌をして『言語にとって美とはなにか』を(日立市)加藤宙
読みもせず捨てもしないで四十年手もとに置きし『共同幻想論』(仙台市)武藤敏子
(「朝日歌壇」/『朝日新聞』2012年4月8日)
【11/11】
父が亡くなる4、5日前のことでした。
父の病室に入ると、その日は興奮気味らしく、
父は手をミトンで拘束され、目を見開いたまま、
何やらうめいていました。「ヤレヤレ」と思いつつ、
私は洗濯物などを回収しながら「早くうちに帰って来てね。シーちゃんもさびしがってるよ」と言うと、
父は大きな声で振り絞るように「◯?△□?!」と叫びました。
入れ歯が入っていないので聞き取れず、「え? 何だね?」と聞き返すと、父は再「◯?△□?!」と、
同じ言葉を叫びました。気にかかっていたものの、
それっきりそのことは忘れていました。
父が亡くなって2週間ほどたった頃です。
父の祭壇の前で猫たちと一緒にグダグダとうたた寝していた時、いきなり殴られたように
「ガツン!」と、あの時の言葉と、その意味が降ってきました。
それは『どこだって同じだよ!』でした。
そうか!どこだっておなじなんだ‥‥‥。
病院だろうが、畳の上だろうが、
コンクリートの地面だろうが、犬も猫も人も、
すべての生き物は、死ぬ時は必ずたったメ独りモ。
場所はどこだって同じなのです。孤独死が問題にされたり、
病院ではなく家で死ぬためにはーーなどと、
そろそろ自分の身体がアブナクなってきた「団塊の世代」が
言い出した昨今の生ぬるい風潮に、
父はまた最期に、見事に水をぶっかけて逝っちまいました。
(ハルノ宵子「連れてっちゃったよ:ハルノ宵子のシロミ介護日誌 その42」/『猫びより』11巻4号2012年6月12日)
ずいぶん前のことだが、縁側を建て増しして増築した納戸の二階を娘や妻と共用の居場所ににした。南側と西側の壁に六段の作り付けの書架を設けた。
最初は古本で買い、やがて新刊本を買って読むようになった吉本さんの本の配架に迷ったあげく、書架の最上段の天板の上に読んできた順に並べることにした。左からL字型に並べていってはみ出した本は別置するようにした。吉本さんの本を見上げて手が届かないから、踏み台を使って出し入れして読むのが習わしになった。
独居老人となって初めての今年の元旦、本に囲まれた部屋でのPC作業を午後4時に切り上げ、階下のリビングに戻った。いきなりガタガタと揺れて地震に気づいたが、引き続いてグラグラと大きな揺れが来てテレビをオンにする間もなくポプラの木のテーブルの下に潜り込んだ。
テレビで能登半島が震源だったことを確認してから、まず一階のあちこちを見て回ったが異常はなかった。余震を気遣いながら母屋の二階を確認してから、増築した二階の戸を開けてびっくり。作り付けの書架の本は落ちていなかったが、最上段の天板にブックエンドを使って並べてあった吉本さんの本がすべて床に散乱して足の踏み場もなかった。
一夜明けてから片付け作業にとりかかった。崩れ落ちた本の勢いでファアンヒーターのカバーは凹み、管球ラジオ�が載っていた飾り棚もろともひっくり返り、小さな飾り皿も割れていた。あと数分部屋にとどまっていたらトンデモナイ目にあうところだった。落ちた吉本さんの本を元の場所に戻す気にはならず、さしあたって部屋の真ん中あたりに十数冊ずつ平積みして置くことにした。余震が遠のいた今もそのままだ。
いつも眺めあげていた吉本さんの本だが、正月の能登半島地震後は床置きになって何だか不滅の活字の群島を漂流してきたような眺めに変わった。
(2024年11月16日記/17日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(28)あるいは脱皮する抜け殻
どの抜け殻にも、眺めれば眺めるほど新しい発見があった。男がまず
驚いたのは、脱皮した殻が実に精巧な作りをしていることだった。セミ
の腹に刻まれた皺から、頭部の先端に密集する毛まで。ヤゴの透明な眼
球から、羽根に浮き出す網目模様まで。かって殻の中に生きていた生物
の形を、克明に留めていた。隅々まで神経が行き届いていた。どうせ脱
ぎ捨てられるものだから、といういい加減なところが微塵もなかった。
更には、それは精巧でありながら、綻びがないのだった。背中に一箇
所、ファスナーのような切れ目がある以外、どこも破れたりクシャクシ
ャになったりしていない。シマヘビになると、そっくりそのまま裏返し
になっていて、模様が内側に広がっているという手の込みようだった。
(小川洋子「ひよこトラック」/『群像短編名作選2000〜2014』
(講談社文芸文庫)、2018年5月刊、124〜125頁)
ことの発端は左腕の“むくみ”というか、“腫れ”による違和感だった。かかりつけ医の見立てでは肘の関節の炎症によるものだろうということで数日經たが、どうにも治らず朝起きてからの身体が普段の感じじゃない気がしてとりあえず娘のところへ電話した。何らかの〈異変〉を感じたらしい娘は即座に、車でそっちへ向かうから、かかりつけ医にもう一度診てもらう用意をして待ってて、という運びになった。
あきらかに関節炎というのは誤診だったが、どうにも原因がわからないから、紹介状を持ってすぐに県中病院の救急で診てもらうように急かされ、昼飯も食わずに娘の車で向かった。
救急でのあれこれ検査の結果が心不全ということで直ちに入院、循環器内科のECUのベッドに寝かされることになるなんていささか驚いたというか、予想外の成り行きだった。
かかりつけ医から高血圧の薬は処方されていたが、スニーカーが履きにくくなったりする下肢のむくみが気になったり、体力や持続力の衰えは老化による当たり前のごとく感じていた一人暮らしで、身体はそうとう無理をしているのに気づくのが遅かったのかもしれない。
それにしても左腕の突発的な“むくみ”はなんだったのだろう。心不全を疑う要因になったようだが、その直接的な原因がわからないままに、身体の余分な水分を抜いているうちに症状が消えてしまった。検査期間中に10キロ以上も減量したしたことになるが、担当看護師の話では患者によって個人差があって水分がなかなか抜けない場合もあるとのことだった。自他の症状なども含めて個性的というより、身体そのものが個性なんじゃないかとさえ感じさせられた。
ECUから個室に移された後は連日のように種々の検査が控えていてすっかり疲れてしまい、息も絶え絶えの〈病人〉に成り果てたような状態から抜け出す選択肢に手術しかないということで、心臓血管外科の病棟へ移され、数日後に手術が予定されていた。
おそらく身体生理的にはいろんな選択肢があるだろうが、これが正しい選択というものはないような気がしていた。来し方行く末を占うような事態に我が身をあずけてなるようにしかならないといった気分だったろうか。
循環器内科と心臓血管外科それぞれの主治医の連携の良さ、安心感と信頼感にすっかり身を委ねていたのだろう。車椅子で手術室への移動直前までメジャーリーグの野球中継を観ていたら、娘は少しは不安な気分にならないのと不思議がっていた。
意識が戻ったICUから一両日ぐらいで個室に車椅子で移された。人工呼吸器に繋がれてどんな手術を施されたのかまったく記憶になかった。どうにか老体が手術に耐えたというより、循環器内科と心臓血管外科それぞれの主治医をはじめとしたスタッフのおかげさまで命拾いさせてもらったという感謝の気持ちが大きかった。執刀医だけでなく担当理学療法士からも胸が骨折の状態にあると告げられ、あらためて大がかりな手術の後の痛みを実感させられた。
蛇籠
人間は骨でできた篭であることがわかった。
私が肋骨を骨折した時にーーー。
その痛みで眠られぬ時にーーー。
金だらいを叩いて音が発するように、すこしの寝がえりで痛みが全身から発
したその時にーーー。
そして私には、人間が、あの石ころをつめた蛇籠のように、堤防を保護する
ために長い割竹を編んで河に沈めてあったあの蛇籠のように、骨で組まれた篭
にすぎないことがわかた。
(永瀬清子『蝶のめいてい:短章集1』思潮社、1977年2月刊、27〜28頁)
退院間近になって術後の骨がワイヤでくっつけてある胸部CTスキャン画像や、手術中のカラー写真を見せられてようやく実感できたというか、おくればせながら大変な局面にあった我が老体とそれを乗り越えさせたスタッフの合わせ技に大いに感じ入った。
それまではとにかく術後の痛みが半端じゃないものだからベッドでの身の起伏しもままならず、夜もろくに眠れない日々が続いた。術後の回診のたびに順調な回復を告げられても上の空というか、退院するまで交通事故死より外科手術による死者の数が圧倒的に多いといった医療関係者の裏話に耳を傾けたりする余裕などなかった。
何もかも初体験の我が身に、数え切れないほどの術前・術後の薬や検査の数々が、なんだか過剰医療のような気がしないでもない患者の身勝手気分になることも。もちろんそれぞれに事細かな説明があったのだが。
まるで身動きもならずベッドに転がされていて、これが老いた身体の〈普通〉じゃないかと思い知らされた。手術による傷痕も生々しい胸や右脛に差し障らないように身体のあちこちを部分的に動かせるだけでも良しとすべきではないのか。人間の身体でできることは山ほどあるはずなのに、そんなことができるわけがないという常識が邪魔をして気づけなかっただけだ。
脚から取り出した血管を移植したり、機能不全の弁を付け替えたりできるのに、皮膚だけはなぜそのようにできないのであろう。身体ほど自然でミステリアスなものはないのではないか。
やがてこの〈普通〉から立つことができ、歩けるようになり、そして日常に必要な動作ができるように一人稽古するのがリハビリになるであろう。入院中に老いを嘆くことも若さを羨むこともない身体観に遭遇できるとは知らなかった。
やっと立てるようになってもどう歩けばよいかがわからない。膕を支点に尻と踵で描く三角形を交互に入れ替えるという以前からの気づきじゃうまく身体を運べないというか、下半身と上半身のバランスがぎこちなくてよろめきそうになる。
尻から下というか、下肢だけで歩こうとしてはダメで、一人稽古を推奨するカラダラボ主宰山口 潤師の言葉に習うべきなのかもしれない。WiFiが使える病室に持ち込んだPCで見かけたのだが、足が前を向けば脛と尻は後ろに向かい‥‥‥頭と目は前に向かう前後のバランスが云々のXでの書き込み。奇妙というかなんともややこしい言い回しに病み上がりの身体を反応させるみたいに、少しづつ病院内のあちこちへと歩みを愉しめるようになった。
ベッドに腰掛けて両腕を胸で交差させ、その場で立ち座りを繰り返す。つま先立ちを繰り返す。左右の足を一直線上に入れ替えて起立静止する。階段の上り下り。負荷を変えながらの自転車漕ぎ。上半身は腕上げのみ。仕上げに下半身のストレッチ。1日一回のリハビリ・メニューじゃ足りないということで、数時間おきに院内の廊下を歩く。なんだか徘徊老人のような気分がしないでもない。
リハビリ・メニューにシャワーや入浴が加わるようになってから、[心臓の]術後的には退院を考えてもいいよとの主治医の言葉。その一方で本来の体調を取り戻すのに後期高齢者の場合は入院加療期間の七倍を要するとも。階段の上り下りや家事にともなう身のこなしなどの自信もなく、待つ人もいないのにむしょうに自宅暮らしが恋しくてならなくなった。
高屋敷の自宅で暮らすようになって五十数年。祖父、母、そして妻の死を看取ってきた。移住する前の埴生の庭から移植した庭木の樹齢は自分の歳を超すものばかり。若木だった頃を思うとおぼろげながら京城[日本統治時代のソウルの呼称]から引き揚げ後の時の経過に術後の身体が揺らぐようだった。
埴生に居着くことになった母子家族を見て、まだ歩けもしない三歳の虚弱児は五歳までもたないだろうと思ったと後に語ってくれた近所の老婆は、当人が心臓手術を生き延びた今の姿を知ったらなんというだろう。手術前に語った身の上話を覚えていてくれた執刀医は、術後の順調な回復ぶりを確かめるかのようにそんなことまで話してくれた。名前すら思い出せない老婆はすでに鬼籍に入っていて叶わぬことに気づいて苦笑するしかなかったが。
吉田さんの撮る父は、私の知らない貌の父だ。”竜骨”の入った人の貌
だ。竜骨が長くて重いほどボートは風には流されないが、操りにくいし
方向転換も難しい。
吉田さんご自身も同種の写真家だと思う。
買い物カゴを掲げていようが、子供とはしゃいでいようが、吉田さんの
被写体になったとたん、父はただの市井のおじさんではなくなる。
私の手の届かない”竜骨”の世界の人の貌になってしまう。
私はとうとう生きている間には、この貌の父に出会えなかった。
(吉本多子「吉田さんの写真集に寄せて」/吉田 純『Yoshimoto Takaaki:吉本隆明』河出書房新社、2013年2月刊、2頁)
幼少時のものごころがつく前に植民地朝鮮で殉職した父の不在というか手ごたえのなさがいまだに尾を引いているようで、次々と家族を失った果てに命にかかわる手術を受け、父の享年[33歳]をはるかに超えてしまった自分の死の分からなさ。
昼夜を問わず心臓血管外科の看護師は術後の身体のチェックに余念がないし、主治医は回診のたびに前日の検査結果で術後の回復具合を教えてくれる。精神科の女医は術前術後を問わず回診で心身の状態を確認してくれる。
心臓の細くなった血管も血液を逆流させていた弁膜も手術でリセットされたわけだが、術前と術後の身体がどこか断続しているようで、それでいて何だか身体的な窮地を抜け出せたような接続観にもとらわれたり。何だか手術前の身体が抜け殻のような距離感で遠ざかっていくような気がした。
10月だというのに残暑を感じさせる退院の日の午後。娘夫婦の車で帰り着いた我が家の庭木の剪定も終わり伸び放題だったであろう雑草も根こそぎ削り取られていた。
途中近所のスーパーで車椅子を押してもらいながら買い物を済ませたりしてきたものだから、久しく空き家にしていた玄関ドアを解錠して上がり込むというより、ちょっとした所用を済ませた帰りのような感じで身体的な日常の時間の流れに入り込めた。
昨年の妻の死が引き金になった「葬式躁」による強制入院からの退院に比べて日常・非日常の身体的なギャップが少なく、なぜか心身の解放感もさほどではなかった。生きがいというか生活のすべてだった家族が一人もいなくなった家屋の侘しさを揺るがすような出来事にであった。
何気なくリスニングルームに入ろうとしたら内鍵がかかっていて開かないのだ。留守中に誰かが内部から施錠したみたいに開かない。これには驚いた。一瞬、昨夏に亡くなった妻が留守番代わりに閉じこもったんじゃないかとさえ思った。特注の防音ドアで普段は鍵などかけたこともないのに内側からドアノブのボタンを押すなんて無人の屋内で起こり得るんだろうか。娘夫婦があれこれ試してもどうにもならず解錠業者を探し出して来てもらいピッキングで解決したが、やはり内から鍵がかけられた状態でしたねとのことだった。
似たようなことが入院中の心臓血管外科の個室でも起こったのを思い出した。院内廊下の歩行訓練から部屋に戻って備え付けのトイレを使おうとしたら内鍵がかかっていて開かない。誰かが入り込んで使用中なのかとノックしたが何の返答もない。奇妙なこともあるものだと仕方なく看護師を呼んだら小さなハサミの背を使って開けてくれた。中に誰もいなかったのはいうまでもない。二度と起こらなくてよかったがあれで眠れない夜中にトイレで水を流す音でもしたらおそらく部屋替えを申し出ていたかもしれない。
病院と自宅と場所を違えて同じようなことがどうして続けて起こったのだろう。身体のどこかに心身に響くような人工的な変化が加わったりすると、日常と非日常の裂け目に何かを呼び寄せたりすることが起こりやすいのだろうか。
かえりみれば心身の変化が際立つ少年から思春期にかけて、家での金縛りや近所での人魂に身動きならなくなったり、祭りの夜の帰り道で神隠し[としか思えない現象]にあったり、真夏の午後の川釣りで河童に遭遇したとしか言えない出来事が起こったり、いずれも忘れられないことばかり。デジャビュというか既視感めいたことも多々起こって現実感がゆらぎそうなこともあった。
気質的なのかそれとも器質的なのかよくわからないが、循環器内科にいたときは頻発する過呼吸[過換気症候群]に悩まされたが、心臓結果外科に移ってからはほとんど発症しなくなった。自宅に戻ってからも滅多に起こらないといった様子だが、身体的な個性も変わったりするのだろうか。
手術直後はとくに喉が掠れたようでほとんど声にならず喋りにくかった。胃カメラで隣接する心臓の造影撮影をするなど、手術の際にも人工呼吸用の管を喉経由で突っ込まれたりした後遺症のようにも思えた。担当理学療法士によれば心臓手術後のリハビリのメニューに発声訓練のようなものはないとのことだった。病室に持ち込んだノートPCを使って心臓手術後のリハビリにどんなものがるか生成AIで調べたらやはり発声練習なるものは含まれていなかった。
それとなく病院関係者の間でも生成AIに関心が持たれているという感じがしたが、その具体的な使い方の講習会などの機会もあるようだった。利用実態が見えてこないとはいえ、もし生成AIが医療行為の過程において決定的な判断を下したりするようなことにでもなれば、とんでもなくオソロシイ事態になりそうだ。人間にしかできないことと生成AIでもできるようなことを混同するというか、取り違えるようなことがあってはならない。
私たちはいま、心という存在を見失っている。資本主義は精神を新たなる資本の対象として残酷に収奪し、インターネットは精神を脈絡なく縦横無尽に繋ぎ、私たちが自分で自由に制御できる心など消え去ってしまったようだ。あるいは、地球環境は劇的に変転し、グローバル化した大地を感染症が駆け巡り、精神などという実態のないものは塵のように消し飛ばされてしまうかのようだ。あるいは、かって人間の奉仕する道具であった機械が人工知能として自走して社会の隅々に浸透し、もはや心を持つことは人間の特権ではないかのようだ。あるいは二〇世紀に深刻化した精神疾患にはもはやガンよりも公衆衛生の予算がかかる時代となり、こんなにも私たちを苦しめる心など手放してしまったほうがよいかのようだ。
しかし他方で、こうした心の消失は、奇妙な言い方になるが同時に心の全面化の結果でもある。神から精神を人間に取り戻そうとした結果として資本主義は誕生し、意識をどこまでも拡張しようとした結果としてインターネットは人間を繋ぎ、精神の全能性が自然支配を可能にすると考えた結果として、地球規模での技術制御と生態系の破壊が行われた。あるいは精神というものを人間という制約を捨ててでも完全に近づけようという欲望が人工知能の開発を推し進め、こうした猛進して拡大してゆく精神の負担がその病を加速させている。
心の消失は、単に心の弱体化ではなく、むしろ心の無謀なまでの強化と同時に進行している副作用である。心を強化すること、それは図らずも心の弱さを顕にした。私たちはいま、心という厄介な存在をめぐって引き裂かれている。
(下西風澄『生成と消滅の精神史:終わらない心を生きる』文藝春秋、2022年12月刊、12〜13頁)
地球が大気で覆われているように身体は見えない心に取り囲まれているといえよう。心の消長を問うように身体の来し方行く末も見直すにはどうしたらいいだろう。まず身体の聲を聞くというより、歩くたびに身体感覚が新しくなり、そして楽しいというか面白い。それがリハビリというか稽古になる。心臓を手術した痛みのの消えない胸で呼吸するのにも楽しい身体感覚がある。血液の逆流現象がなくなって肺への負担が軽くなった感じ。こんなにも〈普通〉は快適だったのかと。歩きながら呼吸しているだけなのに嬉しくなり、愉快だ。痛いのや違和感は嫌だが、それだって稽古のきっかけになる。
身体から身体へと言葉を介さないでも伝わるものがある。術前の身体から術後の身体へ伝わったものと、途切れたもの。間髪を入れずある身体から別の身体にとって変わるもの。そういう場が稽古になる。そんな影響の仕方が時代的にも、社会全体の中にもあるのではないか。社会的身体ってのがいつの間にか全員に感染していたり。身体だけでなくものの考え方までも。気づく人は少ないのかもしれないけど、その感染力はコロナの比じゃないくらい存在そのものを損ないがちだ。大げさに言うなら地球全体を覆って空疎な身体を蔓延らせているのかもしれない。
入院中の身体がどうしても受け付けようとしなかったのが病院食だった。入院先の異なる同病者の話を聞いたりするとあれでも良い方なのらしい。食べにくがっているのを見かねて朝をパン食にしたり昼を麺類にするなどの対応はしてもらえたが、調理の仕方というより何でもかんでも冷凍に依存した食材の選び方からして間違っていないか。口に入れた食材の食感そのものが拒絶反応を引き起こしがちだった。美味いとか不味いとかいうレベル以前の事実だ。
退院して4週間以上経ってからようやく電話の向こうの娘からずいぶん言葉がはっきり聞き取りやすくなったと言われるようになった。胸の痛みも少しづつ治まってきたようでなんとなく食欲も戻ってきた。遅々とした身体的な歩みだが、リハビリという一人稽古で確かなものにしていかねばなるまい。(2024年11月25日記/12月1日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(29)あるいは交差する身体
無思想に消費に夢中になれたんだな。でも、一方では、僕はアメリカ
の詩人のオーデンが、西暦何年の今、何を書くかというより、自分が現
在の年齢で何を書くかの方が大切なんだって言ったことに、全面的に共
感したんですね。年代で区切れるものじゃなくて、自分の成長とか成熟
とかのほうが大事なわけだから、別に七〇年代になったからといって、
自分の何が変わるわけじゃない。僕が「いま・ここ」しかない人間だと
言うようになったのはいつ頃だったか覚えてないけど、この当時からな
のかな。未来にそんなに期待もしていないまま、「いま・ここ」のリア
リティみたいなものを一番大切にする。芭蕉も一瞬の光、みたいなこと
を言ってるけど、それと同じ感覚じゃないかな。実生活はそれじゃすま
ないし、若い頃ははっきり意識する余裕もなかったけど、僕はずっとそ
うやって「いま・ここ」を生きてきた。そんな気がします。
(語り手・詩 谷川俊太郎 聞き手・文 尾崎真理子「第2章 詩
壇の異星人」/『詩人なんて呼ばれて』(新潮文庫)、令和6年8月刊、
204〜205頁)
昨年の「葬式躁」による入退院から1年も経たないのに、今年はまさかの「心不全」による入退院で、高屋敷界隈の秋をやり過ごしたみたい。二シーズン続けて高屋敷界隈から秋の立山連峰の眺望を見逃し、老いて色褪せない季節の感触を棒に振ったという感じ。
そのかわりといってなんだが、人の身体は〈狂気〉と〈死〉を腹背にした身体で呼吸しているんじゃないかなど、二度にわたる入院中の想念が往く秋といった季節感にとってかわったみたい。そんな妄想も近所で繰り返すリハビリを兼ねた晩秋の散歩の眺めと交錯するようだ。
あたりに家が建て込んできて、ただでさえ眺望が乏しくなりつつある路地を歩いているだけなのに、いつの間にか迷路をさまよったみたいに抜け道を見失うことも。土地勘はあるはずなのになぜか地図が浮かばないというか描けないもどかしさ。
富山市内の街中にある県中病院は季節感が乏しく眺めに慰められるようなことはなかったけど、昨秋の魚津のM病院から眺めた北アルプスの稜線から昇る朝陽や富山湾に沈む夕陽の景観が隔離病棟で沈んだ気分を多少なりとも浄化してくれたようだった。
はしごしたみたいな二度の退院直後はいずれも気分が萎えて飲み食いだけじゃなく、余暇も愉しめなくて途方にくれるしかなかった。これまでとは違って何もかも自分でやらなければならなくなった緊張感だけが頼りというか、家事だけじゃいけないとばかりに、少しづつ聴くこと、読むこと、観ることを回復させてきた。いずれも新しいものはさっぱりだから、おぼつかない記憶の中からかって読み聴きした[はずの]ものを耳目にしているだけなのにどれも新鮮に感じるのにはいささか驚いた。記憶が欠けていたからかもしれないが、それはそれぞれでとてもいいことだ。
肝心の飲み食いは、退院直後はさっぱり駄目だったのに、折に触れて来てくれる娘夫婦との会食がなんだか食事療法になったみたいで、飲みなれていた[はずの]ワインやウイスキーなども復活しつつある。
長年にわたって乗り馴れてきたような我が身に訪れた出来事が骨身に沁みたはずなのに、かえって身体のことがよくわからなくなったみたい、というのが正直なところ。
まるで亡妻と二人で日課のように観ていた映画が馴染めなくなったようだ。かろうじてアニメで観た3本が面白かった。「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」はよくわけがわからないなりに斬新な画面展開が飽きさせない。
鳥山明原作「SAND LAND:サンドランド」は水源の川が枯れてしまった砂漠の世界で、悪魔と魔物と人間からなるトリオの主人公が“幻の水源”を探す股旅アニメ。
藤本タツキ原作「ルックバック」は漫画オタクの二人の少女の自然からの隔絶感が凄い。本で読んだときはさほど感じなかったけれど、アニメになってびっくりした。郊外の田や畑に囲まれた道ほか、雨や雪や風など季節感が見事に描きこまれるほどに、そんな自然界から無縁なまでに見放されてしまった二人の少女の姿が痛い。
このまま廃人になってしまうのだろうかとか、妻亡きあとの一軒家に生き残ってどうなるんだろうなどと繰り返した入院中の病棟で思い悩まないでもなかったが、それ以上に自分が立ちいたった事態の入口と出口がどのようになるのかを見きわめ難いという足場の不安。老いさらばえた身体に人生の勘定書を突きつけられたみたいで、なんだか人生の税金を払ったような気分。ここで生きようが死のうがこの上なく中途半端な終わり方もあるだろう。死が他人事であるからには生も地球をぐるぐる回る月のようにその半面しか分からないのではないか。世間から隔絶した病棟にあって医師や見舞いに来てくれる家族だけが患者の生・死を繋ぎとめて[くれて]いる。それも半分だけ。あとの半分は誰にもわからない時の流れにゆだねるしかない。それぞれが等分じゃないところが微妙だが。
当然のことだったろうが循環器内科や心臓血管外科の病棟では、昨秋の精神病棟にいたときのように回復するにつれてスケッチしたり何かを書いたり、あれこれやろうという気にはならなかった。メンタルな場合とそうでない入院との違いといえばそれまでだが、同じ身体なのにその差が不思議だった。外科病棟でWiFiが使えることを知って持ち込んだノートPCを使い、イヤホンでジャズを聴きながらHP用の情報アラートをチェックしたり更新したりするなど、おかげで痛みそのほかが軽減されたような気がした。
検査やリハビリがない午前中はテレビで大リーグ中継を観たり、夕食後も日本のプロ野球中継を見届けてから寝るのが習わしになった。ドジャース移籍1年目の大谷翔平選手が対マーリンズ戦で「50ー50」を達成した瞬間は、予定されていた手術日と重なってテレビ観戦どころじゃなかった。
テレビ以外では娘に届けてもらった本を三冊ばかり、音楽書二冊と文芸書一冊を交互に読むのがその場しのぎの慰めにもなった。その後は退院を待ちわびる一方で、ストリーミングでで聴く音楽に身体をあずけられるひと時を惜しんでもいたようだ。
病院内をあちこち歩けるようになり、コーヒーが解禁になるのを見計らい院内売店に出かけでボトルコーヒーを買った。帰りがけに何気なく書籍コーナーで見つけた谷川俊太郎の新刊文庫本が新たな退院までの読み物になった。
退院してからの楳図かずおやクインシー・ジョーンズに続いて谷川俊太郎の訃報に接した時など、かって親しんだことのある漫画と音楽と言葉による表現世界があい前後して途絶えたような寂しさを覚えた。抜けきらない独り身の病後の気分が少なからず反映していたのかもしれないが、それぞれあまりにも完成[成功]し過ぎていてかえって過小評価されているのではないかとも思った。
[前略]
そうしてその流れを羊歯は自らの根で吸い上げ、それを葉先から私の指へと帰してきた。そのようにして、羊歯と私との間に、ひとつの回路がかたちづくられたのだ。感覚の流れは環になって停止しているかのようでいて、実は徐々に加速されていた。その加速をうながすものが、私と、そして羊歯の欲望としか呼びようのないものであることを私は疑わなかった。私の身体の中の私でない生きものが、もっと、もっとと声にならにぬ叫びをあげた。私は羊歯の葉に指先を触れたまま、ぎごちなくあせって下半身の衣服を脱いだ。裸の尻が落ち葉に接するや否や、羊歯と私を結ぶ感覚の流れは、めまいを感じさせるような速さにたかまった。もはや指先を触れているだけでは我慢できなかった。私は上半身の衣服をめくり上げ、身体を半回転させて、裸の胸で羊歯の上へおおいかぶさった。
[後略]
(「交合」部分/「(何処[いずこ])」/『コカカコーラ・レッスン』詩潮社、1980)
ホラー映画を好むきっかけになったり、ジャズとポップスの間合いが豊かになったり、言葉[羊歯]から意味を抜くように[性交する]身体があらわになったり、三者三様の表現世界が暮らしの折々を彩ってくれたようだ。
とてもそれぞれの作品を網羅したとは言えない見聞きした範囲内でのことだが、それぞれ活躍された畑が異なっていた三者の表現活動に共通するのは、その広がりや奥行きが〈聖〉や〈俗〉のいずれにも行き着くことなく、それでいてその双方に独自なやり方で橋を架けられたように見える。
絵柄自体が恐怖を呼び覚ましたり、一方はサウンドで、他方は言葉で、それぞれの無意識を〈即興〉で〈アレンジ〉されたのではないか。
1960年代の富山市内のジャズ喫茶の片隅で、光り輝くようなスタンダード・ナンバーのビッグバンド演奏にカラダが打ち震えたことがあった。LPのジャケットに記された編曲者がクインシー・ジョーンズだったことは言うまでもない。
若い頃から作・編曲の才を磨いていたが、秀でたジャズミュージシャンに共通するとまでは言えなかろうが、早婚の妻とは別に女性に関しても相当の遍歴があったようだ。幼くして貧困と家庭[母の狂気]不和と人種偏見に苛まれた境遇をくぐり抜けつつ、十代半ばから自己の才能を触発させるような人たちとの出会い、自分が購入し愛聴したレコードで聴き知ったジャズミュージシャンとの交流がなんとも興味深い。盲目のレイ・チャールズ[歌手、作曲家、ピアニスト、1930年 9月23日〜2004年 6月10日]や夭逝したクリフォード.ブラウン[ジャズ・トランペット奏者、1930年10月30日〜1956年6月26日]との若き日の仲にも奔放だった異性関係が反映されているような気がする。ヘレン・メリルのヴォーカルと並んで品行方正だったクリフォード・ブラウンがソロを録ったクインシー・ジョーンズの編曲になる一枚はいつ聴いても素晴らしい。
だから、読んで余計に怒りが溜まっていったのでしょう。「ひっぱたいてくれ!」と怒鳴られたこともあったな。あれは心からでしょう。そういうふうに対抗して欲しかった。喧嘩にならなかったから。ある時は「あんたにはモーツァルトなんてわからない」と決めつけられて、さすがにそれはあんまりだと思ったけど、もう、反論しなかった。何を言ってもダメだなって。僕は相手がいなくても成り立ってしまう人だから。「私がいても淋しいんでしょう、あんたは」と言われてた。自分がいなかったら淋しいと思いたいけど、それと関係なく僕は淋しいんじゃないかと思ったんでしょう。
僕の愛情が足りなかった、って要約しちゃうこともできるけど、ともかく彼女はどんなに不愉快な顔をしていても、そばにいて欲しかったんだ、本当は。僕は情熱が薄い、非人情な人間だから、それはそれとしてつきあっていこうという諦観は、彼女にはないんだね。
(語り手・詩 谷川俊太郎 聞き手・文 尾崎真理子「第4章 佐野洋子の魔法」/『詩人なんて呼ばれて』(新潮文庫)、令和6年8月刊、430頁)
表現者が家に二人いては核家族は成り立たないと言ってしまえば身も蓋もなくなってしまいかねないが、谷川俊太郎の最初[岸田衿子]のそして三番目[佐野洋子]の奥方もそろって物書きであったようだ。二番目[大久保知子]も元新劇女優だったから身体的表現者だったことになる。
三角関係をくぐり抜けられた吉本さんも結婚当初はそういったことに難色を示されていたようだ。夫婦二人三脚でやってきた『試行』刊行の事務作業から解放された奥方が優れた『句集』を刊行された時のお二人の仲はどうだったんだろう。二冊を読んだ後にそんなことまで気になった。
氏も育ちも違う二人が一緒になってうまく家を営んでいけるかどうかを左右する要因はさまざまだろうが、とりわけ気づいた時にはどうすることもできない双方の幼少期までの両親との関係に由来する事柄が大であろう。夫にとっては母との関係が、妻にとっては[母を媒介した]父との関係が、それぞれどうであったかということが陰に陽に事あるごとに二人の間合いを親密にしたり荒立てたりするというふうに。
母と一緒になりたいという欲望は、自然に溶けこみたいという欲望と区別できなかった。
だがやがて母親は、限りない自然としてよりも死すべきひとりの人間として、私の前に立ちふさがるようになってくる。それは私に人間社会のしきたりを教え、自然の秩序とは異なる人限の秩序の中に私を組みこもうとする。私は抵抗し、抑圧し、受け入れる。私のからだが母親のからだから出たように、私の心も母親の心から別れ始める。そして私は母親に代わる存在を求める。
恋とは私のからだが、もうひとつのからだに出会うことに他ならない。自然と違って人間はからだだけではないから、からだと言うとき、そのからだの宿している心を無視できないのは勿論だが、心とからだはただことばの上で区別されるだけで、本来はひとつのものだ。しかしまたひとりひとりに独自な心は、人間特有のものであり、その心を支配し、それに支配される万人に共通なからだは、人間を超えた自然に属している。その矛盾を生きるのが人間であるとも言えよう。
(谷川俊太郎「恋は大袈裟」、/『ひとり暮らし』草思社、2001年12月刊、12頁)
音楽好きだった谷川俊太郎はジョン・レノンの「マザー」(『ジョンの魂』1970年所収)をどのように聴いていたのだろうか。後出しじゃんけんみたいに整序され過ぎているようだが、すんなりとした母の受け入れ具合にたじろぎを覚えるのは何故だろう。それは父にも共通する〈親〉の身体が限りある自然としての死を呼び寄せているからではないか。では身体と不即不離のこころはどうなるのか。母の身体から抜け出るようにもうひとつの身体との出会いに向かう心の動きに身体を委ねようとしても心の核としての魂までは思うようにならない。そんなためらいが言葉から意味を遠ざけて詩に向かわせるように、音楽にも近づこうとする。ことばから意味を抜いたら存在があらわになるとでも言うように。だが音楽は無意味であるとしても演奏[過程]そのものだから〈いま・ここ〉の進行形としてしか成り立ちようがない。
本来はひとつであるこころとからだがもうひとつのこころとからだに出会うことにほかならないという谷川俊太郎の恋愛観は憧れ出ずる魂を置き去りにしてはいないだろうか。こころはからだに宿るとしてそのからだが自然に属しているとすれば、人間特有のひとりひとり独自な心は死に際して身体から引き裂かれるように魂とならざるを得ないのではないか。遊離した魂はやがて宮沢賢治が『農民芸術概論綱要』で称した〈第四次元の芸術〉が象徴する「宇宙の微塵」にまで昇華するであろう。父の谷川徹三は息子俊太郎の詩作について「甘い」とも「ドラマがない」とも言っていたようだが。
われわれは宇宙の一微塵に過ぎない。しかし宇宙塵はやがて凝集して星を生むものとなる。そこにはかがやく星を生む可能性が内在するのだ。われわれはその大いなる可能性である。われわれは仏となるべき種子である。それは無方の空にちらばって行方がわからないようになっても、やがてあちらこちらにその芽を吹き、その実を結ぶであろう。ーーこれが「まづもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう」という決意と祈願との意味する内容である、とわたしは信じます。宇宙の微塵という言葉は、今日の天文学にいう宇宙塵と仏典にいう微塵との双方にかけているのであります。大乗経典にはこの言葉は、眼に見える最小最微のものとしても、しばしば謦喩に用いられています。
(谷川徹三「もろともにかがやく宇宙の微塵となりて」/『宮沢賢治の世界』法政大学出版局、2009年5月改装版、61頁」)
晩年の吉本さんは宮沢賢治と銀河系の関係について、彼はおのれを銀河系の一員として隣人や家族や社会といった人間関係よりも先に天の星との関係性としてとらえ、突き詰めれば人は銀河の寿命と同じだけ生きていけるというところまで行き着くことになる(「新書化にあたってのあとがき」2011年3月/『老いの幸福論』青春出版社、2011年4月刊)、というように述べられた。
そして、「遠からず平均寿命が百歳以上になるのは自明の理だと思います。人間や人類はどこで終わるかを考えれば、宇宙が壊れたら終りです。そのことをきちっと考えてゆけば、そんなに悲観することもないよということになると思います。個人的には、いいことは一つもないよと言いたいところですが、そのなかで希望があるとすればそのことだと思います。」(吉本隆明「これから人類は危ない橋をとぼとぼ渡っていくことになる」2011年4月22日[2011年6月『思想としての3・11』河出書房新社])、としめくくられた。(2024年12月24日記/31日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(30)あるいは〈契機〉としての身体
吉本さんがあることについて、どんなことを言っていたか、
ぼくはいまでも知りたくなってあらためて講演を聴きます。
つい最近、2003年に『ふつうに生きるということ』
という題で話していただいたことを、
あらためて確かめたいことがあって、聴いたのでした。
当時も会場のライブとして、その後も二度くらい
聴いていたはずなのに、また新しい発見がありました。
吉本さんは、「ふつうに生きている人」の生き方が、
まず、いちばん価値ある生き方だと決めたのでした。
そうすると、すごい人、たとえばマルクスのような
ある長い時代のトップじゃないかと言われるような人が、
その逆のところにいると決まります。
すると、なんでもない「ふつうの人」を100点とすると、
マルクスが0点ということになります。
実際には、まるまる100点満点なんて人もいないし、
マルクスにしても0点よりはちょっと上になるだろうし、
すべての人は、0点と100点の間のどこかにいるんですね。
55点の人は、少し100点寄りに見えるかもしれないし、
45点の人はちょっと0点のほうに近く見えるけど、
どっちも0点でも100点でもない、
間のところをゆらゆら動いているわけです。
この考え方は、いま聴くと、あらゆることに通じるなぁと、
なんだかぼくの気持ちがらくになったような気がしました。
善と悪にしても、美と醜にしても、新と旧にしても、
幸と不幸にしても、和と洋にしても、男と女にしたって、
どっちか100とか、どっちか0なんてないわけです。
82と14が対立してたり、65と47が争っていたりする。
一見、両極に見ているけれど、実はみんな中間にいる。
そういうことが、とても腑に落ちるようになったのでした。
(糸井重里「今日のダーリン」/『ほぼ日刊イトイ新聞』2024年12月24日)
[承前]ところで身体で考えるが心になり魂に昇華する宇宙から馳せ下った身体自体に出会うのはいったいどういった場合であろうか。私的には虚弱児がつかまり立ちしてより遠くが見えるようになったとき。水に浮くことも泳ぐこともできなかったとき。斧を使って薪割りや、臼と杵で餅がつけるようになったときや、〇?△%□ができたりできなかったりしたとき。特例として病気や怪我などで外科的な入院・手術になったり、幼児返りしたみたいに入院中に紙パンツを余儀なくされたりしたときなど‥‥‥、地に足が着いた身体的な自然との一期一会としか言いようがない。
あまり言葉が介在しない世界、例えばスポーツとか、日本古来の習いごとなどの所作における「‥‥‥道」などが一般的だろう。「ーーお化粧をすればするほど裸になる」(関根みゆき)という言葉があるくらいだから、化粧やタトゥーをしたりしなかったりする事もあてはまりそう。
スポーツを詩にした諸作品を集めた『スポーツ詩集』(川崎 洋・高階杞一・藤富保男編、花神社、1997年10月刊)は詩人が多種多様な種目を体験したり観戦した内容になっているが、いずれの作品も意外と言っていいほど人間の自然な「身体」が観えてこない。なんというか〈身体〉にまとわりついた「人間」臭さが脱ぎ捨てられていないような感じなのだ。
25名の文士と様々なスポーツとの関係を綴った矢島裕紀彦著『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』(NHK出版、2003年8月刊)も言葉が肉体的な逸話に終始していて身体的な出会いまでは読みとれない。ただ、「柴田錬三郎とダンス」では「躾や身だしなみ」や「リズミカルな足の運び、体のこなし」などが微かに内観的な身体性を匂わせている。
スポーツをするしないにかかわらず身体感覚として見つかるものは、自分で決めた恣意的なものでもないから気づくか気づかないかはひとそれぞれだとしても、《そうなっている》もの。かけがえのない身体の働きとして見つけたもの。とりたてて落下の法則を知らずとも、地上に引力が働いているような感じのものだ。たとえば身体探しの一例として、日常の下駄履きで身体内に見つかるものなど。
言葉をともなった例として忘れられないのは、『眞宗 在家勤行集』(守川聚星堂、大正七年三月刊)や『正信偈 和讃』(永田文昌堂、昭和五年一月刊))を座右に朝夕のお勤め・念仏を欠かさなかった祖父のことや、読経だけでなく昔語りが得意だった実家の祖母のことだ。子ども心に「お経」や「民話」に集中しながら声に出して表している身体が共鳴しているように感じたりしていた。
実家の祖母についで祖父も亡くなり、ついに母が亡くなった時から毎朝仏壇に手をあわせるようになったが、いまだにお経が出来ないというか、どうにも声に出して響かせる身体に出会えないとう感じなのだ。仏壇参りをはじめた頃はとにかく意に反して雑念が渦をまいていたようで、いまだに祖父に言われたような阿弥陀仏の第十八願に関わる「はからい」のない〈信心〉とか〈さとり〉の身体観からほど遠いというか、もはや縁がないとしか言いようがない。
なぜ称名を択ぶのかのかという問いにたいして、浄土教の教理から、観想は心の働きを集中させて行く時間と修練がいるが、いまの世の人々にはもはや成しとげることが困難になっている。称名はそれにくらべて易しいからだという考えのほかの答えをみつけることは難しい。だが音声の言語にたいする信仰と、事物の名辞にたいする信仰とが、観想を凌駕してゆく過程は、身体の修練で心の働きを変化させることができ、また心を変化させて身体の状態をつくり出す、という仏教的な融和の理念がひとつの裂け目を体験したことを意味している。[以下略]
(吉本隆明「教理上の親鸞」/「最後の親鸞」/『吉本隆明全集15:1974ー1978』晶文社、2018年3月刊、100頁)
それぞれの生の舞台も知らないのに言うのもなんだが、ユーチューブで観た舞踏家の最上和子や、能楽師の安田登が著した『身体感覚で『論語』を読みなおす ー中国古代の文字から』(春秋社、2009年11月刊)などは、とりわけ身体的な契機が表現の呼び水になっているようだ。「文字」に着目していること自体が身体的な慧眼になっているのではないか。
文字にしたって、横書きか縦書きかで読み書きする身体感覚がずいぶん違ったものになる。
石川九楊は三島由紀夫の書について「要するに、何かある種の典型みたいなものを自分で設定して、それに近づけようとする感じがするのですね。言ってみれば、習字の型の字なんですね。普通、文学をやる人は書を書いていくなかで自分のひとつのスタイルが創られていくものなんですけど、そういう匂いが書のなかに非常に薄いですね。」(吉本隆明 石川九楊『書 文字 アジア』筑摩書房、2012年3月刊、49頁)と評した。それを受けた吉本さんは「こういう字を書いているときの三島さんは意識的に何段構えかで、外濠も埋めていないし、本丸のところはこれじゃ全然わからないというようなふうに書いているんじゃないかなと思うんです。」(同前掲書、49〜50頁)と返している。「三島の書」に観られる意図的な装いがどこまでも〈身体〉を遠ざけながら「病的な文体」を着込むような〈表現〉をする肉体と地続きのような気がする。
根っからのスポーツ嫌いの三島が大学時代にかじったのが乗馬。三十歳を越えたら病気がちになり、痩せた體に哀れみを感じてせめて格好をつけようとボディ・ビルをはじめた。ようやく體に自信が持てるようになって、かねてから念願だったボクシングに取り組むようになった。
石原慎太郎に8ミリシネで撮ってもらった指導者との三ラウンドのスパーリングを観て、あまりにも主観と客観の違いに驚きかつ自信喪失状態に陥ったという。このとき三島はみずから鍛えあげた肉体のぶざまなボクシング姿に落胆しすぎて、当の「體」を透かすように観えた[はずの]〈身体〉性に眼を瞑って取り逃がしてしまったのではないか。
三島由紀夫が1970年11月25日に東京・市ヶ谷の陸上自衛他東部方面総監部で割腹自殺するよりだいぶ前のこと、彼の手になるボクシング観戦記というかその文体に違和感をもたらされた記憶がある。文体が「肉体」の表面を撫でているだけで「身体」にまで届いていないとでも言えばいいだろうか。
「ボクシングの練習場から観客席に移ってしまった」(「ジムから道場へーーペンは剣に通ず」中央公論増刊・昭和34年1月20日@全集第35巻)三島は体力の維持に週三回のボディ・ビルを続けるうち、中学以来十数年ぶりに稽古着に袖を通して竹刀を握って「日本武道の精神主義」もまんざらじゃないと思いはじめたようだ。そして「剣道の、人が人を斬るという假構は爽快なものだ。今は人殺しの風儀も地に落ちたが、昔は禮義正しく人を斬ることができたのだ。人とエヘラエヘラ附合うことだけにエチケットがあって、人を斬ることにエチケットのない現代とは、思へば不安な時代である。」と書くにいたり、ここでも人の身体的な契機とすれ違うように「神秘的精神主義」に滑り込んだのではないか。
人間は、必然の〈契機〉があれば、意思とかかわりなく、千人、百人を殺すほどのことがありうるし、〈契機〉がなければ、たとえ意思しても一人だに殺すことはできない。そういう存在だと云っているのだ。それならば親鸞のいう〈契機〉(「業縁」)とは、どんな構造をもつものなのか。一口に云ってしまえば、人間はただ、〈不可避〉にうながされて生きるものだ、と云っていることになる。
(吉本隆明「最後の親鸞」/『吉本隆明全集15:1974ー1978』晶文社、2018年3月刊、14頁)
三島がスポーツを評する「言葉」のほとんどが形容過多で「肉体」を上滑りして「身体」の手前でとどまっているようだ。曰く、「野獣の優雅」ボクシング、「自然へのもっとも皮肉な反抗」飛び込み、「空間の壁抜け」陸上100m、「駈けるに駈けられぬその厄介な制約」競歩、などなど。面白くなくはないけど「言葉」がつまづき続けるような文体に疲れてついていけなくなる。〈身体〉的な契機にとどかないような文体では、とうてい「ペン」で「人」を斬るなんてことはできまい。果てはペンを刀にかえてみずから腹を斬って介錯させた「死」への跳躍‥‥‥、齟齬みたいな断絶。肉体と身体の間には、生きている限り〈覚醒〉し続けねばならない「契機」がひそんでいる。
日本の伝統文化に「道」がある。しかもこれはおしゃべりにはあまり関係がない。武道も道であり、すべての「道」は要するに身体の所作である。こうした道を究めることが理想とされたが、そこに答えなぞありはしない。三島は形式主義者つまり視覚主義者だったから、その答を形だと思ったらしいが、それは間違いであろう。なぜそうした誤りが生じるかといえば、身体の所作は同時に表現だからである。表現の側から入れば、道は形だということになろう。茶道にせよ、なに道にせよ、その種の誤解がよくあることは、ほとんど常識である。教育もまた、形から入ろうとした。医学でも解剖学から教えるが、これも形から入る典型である。しかし、形に入ったきり出てこない人なら、それこそ掃いて捨てるほどいる。形はそれほど簡単ではないのである。三島は出ようとして出そびれた。
(養老孟司『身体の文学史』新潮社、1997年1月刊、162〜163頁)
表現における形とは「関係の絶対性」のことではないか、さすれば内容は「宿命という名の自由」ということになろう。『全集』を前に挫折したような自分が言うのもなんだが、身体の所作としての形として三島はたくさんの小説を書いた。「鏡子の家」に登場させたボクサーの深井俊吉は三島自身が造り上げた肉体の造形美の映しなのかもしれない。鍛えあげた造形美で身を固めてしまったら、寝ても覚めても胴体が頼りになり、写真集にしたりしてそれを誇りにすればするほど「現実」がまとわりついてくる。素晴らしい姿勢や体格だけでなくスタイルも維持できなければ自由でいられなくなる。「自由さ」はどこへ行ったか、その先はどうなっているか。
三島さんのいう輪廻転生という概念は、大洋州の島のほうからインドの沿海地方にかけて、それから北アジアの沿岸地方にかけて、もう一つは島国ですけど島にかけて、インドの仏教が出てくる以前まで流通して未開あるいは原始時代に一般的に流布されていた信仰です。海の近くだったら沖にある島に死んだ人の霊魂が集まっていて、島の住民の女の人が水浴びか何かをして海に入ると、島にいた霊が水に浮かんで女の人の胎内に入る。そうすると女の人は妊娠するんだというふうに、原始時代のオセアニアの島々では考えていたわけです。山国だったら村の外れの形のいい山のところに霊は集まっていって、その霊が帰ってきてまた生まれ変わりが繰返されるんだというふうに考えられていました。
(吉本隆明「文学の戦後と現在:三島由紀夫から村上春樹、村上龍まで」/『吉本隆明〈未収録〉講演集(9)物語とメタファー:作家論・作品論(戦後編)』筑摩書房、2015年8月刊、257〜258頁)
一生活者として老いさらばえつつある自分には、晩年の祖父が言っていたような「浄土」が「生』と「死」を編み込んだ「自由な」境地のように思えるのだが、どうなんだろうか。
そのあたりのことについて、吉本さんは前掲の講演[前掲書、257頁]で、「それからいわゆる浄土という考え方を死後の世界というふうに考えるのはやめようじゃないかと親鸞なんかはまことにそう考えたと思います。親鸞がいう至心の念仏を一回でも唱えれば浄土へいけるといった場合の浄土というのは、生と死のちょうど間のところに想定される一つの場所なんです。その場所にいけたら浄土へもいけるし、また現世の社会の中にも引き返していくこともできる。それで現世の出来事を、後ろのほうからといいますか、向こうのほうから見ることができる視点を獲得するからそれができるとうことを親鸞はいっているとおもいます。」と語り明かされている。
人間は四六時中肉体に縛られていて、その場に居ついてしまった身体を肉体からどうやって引き剥がすか。三島由紀夫はそこから出ようとして出られず身体にまとわりつく人工的概念としての精神性に囚われたのか。
養老孟司は名越康文との対談本(『虫坊主と心坊主が説く生きる仕組み』実業之日本社、2024年12月刊、189頁)で三島には「花鳥風月」がないというよりも「わかっていない」とまで言ってのけた。だとすればアニメ『ルックバック』の主人公の少女もそうだし、環境に興味などなさそうな、トランプ大統領のアメリカにも、同じく石破首相の日本にもそんなものはないということになる。自然との関わりを欠いた日本文化などどこにもない。
それだけでは言い足りないかのように養老孟司は、「だから彼がわかった世界観というのは自分の身体だけ。身体も自然の一つなんだけど、その体自体がものすごい造形的でしょ。[中略]彼の頭の中にある武士像で身体を変えていったわけでしょ。言い換えれば『世界2』[AIが典型的な事例:引用者注]のルールから、体という物質世界をコントロールしようとした。それがボディビルという科学技術ですからね。」と解剖して見せた先で、「それと同じことを、彼は小説でやった。つまり、三島の書く文章もChatGPT的なんですね。彼の頭の中にあるものだけで小説を書いている。そこには実感がない。あえていえば”三島GPT”。実は三島は今の社会にフィットする人なんですよね。もし三島がいま、生きていたらもうちょっと生きやすい世の中だったかもしれないですね。『接地』の問題も別に生じないから。」(前掲書、190〜191頁)と現在に着地させている。
流行りの自然言語生成に特化したAI技術は進化し続け、この先さらにより多くの仕事を成し遂げるようになるだろう。何かと真偽のほどが疑われたり信憑性の問題につきまとわれながらも、この流れはとどまることがなさそう。人は楽そうな道具が好きなように、自分も何かと問いかければ自動で答えてくれる生成AIチャットのお世話になったりしているが、その身体のない生成AIチャットの世界はどこまでいっても人工的な知識の自然過程でしかないから、身体的な契機として知識過程の往相と還相を生きざるを得ない人間の望みを叶えたり、納得させてはくれない。どこかで学習してきたような生成AIの言葉が紡がれれば紡がれるほどどこまでいっても片道切符の迷路をさ迷い続けることになりはしないか。
自然言語生成AIシステムが学習の対象とする知識データの枯渇が云々されたりしているが、たとえLC、アメリカ議会図書館の膨大な内容をすべて飲み込ませたとしても、その生成言語AIシステム過程において獲得知識を否定[反省]する働きがない[ように見える]構造的な矛盾をどうやって解決するのか。
AIではどうにもならない無い困りごとは身体に現れる。思い悩み、苦しんだりすれば身体は必ず緊張してしまう。そうでなければ、緊張から我慢が解けて力が抜けて動けなくなったりする。
予知することもできず、決まったように想定外の未知の関係性として「問題」が現前する。お金や人の手を頼って解決しようとする。大枚を払えば人も動かせるし、貴重なものも手に入って、問題解決に近づけるかもしれない。ただし、それは「科学的な解決」が可能な「問題」の半分ぐらいの範囲内のことでしかない。乳胎児期を含めたエロス的な親子世代間の関係性として出来する人生上の諸問題の解決など出来ず、まして乗り越えるなど個々の日常を生きる当事者にしか出来るか出来ないか、生きてみないとわからないことだ。
人間の体[や身体]をあつかう病院の中でも身体の自然というか、実感が希薄になってきているようだ。退院してから3回目の再診で心臓手術前は四桁だったBNP[脳性ナトリウム利尿ペプチド]が三ヶ月足らずで二桁、それも基準値を大幅に下回るなんて滅多にない事例だと主治医に喜んでもらえた。あくまでも数値上の身体のことでさっぱり実感がわかない。「これでワーファリンの服用をやめましょう」と言ってもらえてはじめて服用中に禁じられていた「納豆が食べられる」身体を取り戻したようで安堵した。
術後の身体を実感するのは入院中だけでなく、退院後も続けているリハビリにおいてだ。同じ椅子を使った立ち座りにしても病院の中じゃ速さや回数を計測されるのに、訪問介護のリハビリではそんなことはなかった。使う椅子の高さや形状によってずいぶん負荷が違ってくる。やり方にしたって椅子の座面にしっかり腰を下ろして繰り返すのと、座面に尻が触れるだけのようにしてやるのとでは回数も疲労感もまるで違ったものになる。日々行うにはスクワットのようにやるのが身体的に自然だ。(2025年1月20日記/21日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(31)あるいは〈影射す〉としての身体
「まだ、語れねえちゃ。だめだ。だめだ」
首を横に振ります。
昔話はもっと歳をとらねぇと語れねんでねぇべか。
話が胸のうちで、まだ生々としていて、醸ってこねぇのっしゃ。
熟して、それから枯れてくるんでねぇべかな。
こんなことを言われたのです。わたしは驚きました。
記憶している民話をただ語って聞かせるのではなくて、語る人の内部で年月を
かけて醸され、それが枯れるときに、物語はもっとも光を放つのだということを、
玲子さんは言われたのでした。そして、語りが持っている力とは、それを語る人
の内なる世界観に、こうして深くかかわっているのだということを教えられたの
でした。
(小野和子「第四章 佐藤玲子さん」/『忘れられない日本人』PUMPQUAKES、
2024年2月刊、141頁)
いつ頃から始めたのかわからなくなってきている「ヒモトレ」や「バランスボード」や「みちのく山道」によって、言葉にならない日常の身体感も日々更新されるような気がしている。心臓手術後の在宅養生中ながらも、日々老いつつある身体に新たな気づきがあるのはとてもいいことだ。生前の妻はいつも赤いたすき掛けのヒモトレをしていて、娘が撮ったその姿が遺影になっている。
孤独は孤独じゃない(皆んながいる)ことを知るきっかけである。しかし実際孤独になっていたとしたら、それは孤独ではなく独りよがりということかも知れない。本当に独りがよければ俗世間から離れれば良いのだから。どれが正しいということではなく、自分に適した場所に矛盾なく居られたらいいね、という話。
(バランストレーナー小関勲@ツイッター改めX)
入院中も普段と同じように差し支えない限り病院着の上から腹と胸にヒモトレを欠かさないようにしていたら、病室や検査室で会った人それぞれいろんな質問を受けた。うまく応えられないから自分でやってみればいいのにとヒモを貸すつもりでいたけど、だれひとり申し出がなくて身体的な契機となるようなことは生じなかった。
ところで痛みそのほかでやり過ごしてしまいそうにもなるが、長期入院というのは相部屋だとないがしろにされがちな「孤立」や、個室では「孤食」の大切さといったことなど、ことあらためて気づかされたりする。自らの有り様を垣間見せる二葉の言葉が喚起するのは、入院生活中の身体的な契機とはどのようなものか。
テレビ視聴が課金されなかったり、インターネットのWiFi接続が提供されたり、個室の部屋代が一泊七千円だったりというのがその代償のようにも算出されかねないが、その背後から響いてくるのは、先進国家が直面している社会保障費の増大とその削減対策としての「治療」から「予防」へのシフティング勧誘の掛け声。予防医学がもてはやされるわけだ。検査という名目で人の身体をスキャンして数値化し、それを基準にして病気にならないようにどこまで先手を打てるのか、一定の社会的効果を期待できるのかどうか‥‥‥。
もはや常態化してしまっている、この何でもかんでも数値化してしまう身体観にもとづいた処方策はえてしてとんでもない副作用や、合併症を伴ったりしているのではないか。数年前のコロナ渦中の暮らしで誰しも気づかされたことを思い返してみるまでもないことかもしれないが。
良くも悪くも俗世間から遮断されざるをえない機会なのに、もはやアカウント・ユーザーのポストとリプライによる相互評価と承認という際限のない認証交換ゲームのプラットフォームと化してしまったようなSNSを院内に持ち込むというより、ひたすらコメントを書き込まざるを得ないユーザー[入院患者]の身体性が孕む「孤立」や「孤食」を見損なってしまいがちなネット上の相互認証交換ゲームに侵食されつつあるといったほうがいいのではないか。それも私企業が提供する擬似的な共同性に公共的な仮面を被せたサービスとして。
何かを意識するとそれはよく見えるけど、よく見えてくることがあると、見えなくなることも出てきます。(僕らが意識という言葉を使う時、大抵フォーカスになったり、概念的人になったりする)。それらが常態化すると身体・運動にも濃淡(癖)が出来上がってきます。ヒモトレは常態化して見えなくなったり、見え過ぎたりする身体にアクセスすることで、切れているところが繋がり、動いていないところが動きだします。人それぞれバランスが違うように実感することは違いますが、全身が動員されやすくなったことで何かしら感じられると思います。簡単に言えば疲れにくく、楽になるということ。
(同前)
一昨年の精神的な、そして昨年の内科&外科的な入院生活でさまざまな方々と接することになったが、つくづく感じたのは、どんな「個人」も身体性としての人類史を内包しているといっていいのではないか。狂っていようがいまいが、ふとした折の呪いや怯えや畏れの振る舞いに起源としての宗教的な身体性があらわになったりする。
そんなことを最初に感じさせられたのは、十代の半ば、中学生の頃だったろうか。
明治も初期の生まれだった祖父は昔語りをするような事はなかったが、時には前思春期の孫の落ち着かぬ心をよけい波立たせたり驚かせるような話を聞かせる事があった。
夫、人間の浮生なる相を・つら�つら觀ずるに、おほよそはかなきものは・この世の始中終・まぼろしのごとくなる一期なり、されば、いまだ萬歳の人身をうけたりという事をきかず・一生すぎやすし、いまにいたりてたれか百年の形體をたもつべきや・我やさき人やさき・けふともしらずあすともしらず、おくれさきだつ人は・もとのしずくすゑの露よりもしげしといへり、されば、朝には紅顔ありて夕には白骨となれる身なり、すでに無常の風きたりぬれば・すなわちふたつのまなこたちまちにと�ぢ・ひとつのいきながくたえぬれば、紅顔むなしく變じて・桃李のよそほひをうしなひぬるときは、六親眷属あつあまりて・なげきかなしめども・更にその甲斐あるべからず、さてしもあるべき事ならねばとて・野外におくりて、夜半のけふりとなしはてぬれば・たゞ白骨のみぞのこれり・あはれといふも中々おろかなり、されば、人間のはかなき事は・老少不定のさかひなれば、たれの人も・はやく後生の一大事を心にかけて、阿弥陀佛をふかくたのみまゐらせて・念佛まうすべきものなり、あなかしこあなかしこ
(『在家勤行集』)
物心がついてからだが、囲炉裏端の四方山話で「親鸞上人」を耳にしてはいたが深く考えることなどなかった虚弱児の身上に降りかかるようにまとわりついて離れない出来事になった。
俗っぽく言えば、処世をどうのこうの言ったって個人の力ではどうしようもないから、とにかく南無阿弥陀仏と称名を唱えて、それに何もかもあずけてしまえばいいのだと祖父は言いたげだった。無理強いされるようなこともなかったが、内心では、生きていく上での「消極的な積極性」もないとやっていけないんじゃないかと切り替えたりしていた。
多少なりとも長じて、吉本さんの「自立」なる言葉に出会った時は、祖父の語り草と真逆じゃないかと思わされたが、やがて浄土真宗門徒の家庭に生まれ育った軍国少年が戦争体験をくぐり抜けた身体的契機がバネになっている言葉として読めるようになった。
ぼくは自立だ、なんでもじぶんでやっちまえというふうに考えているのです。つまり、もっとそれを抽象化してしまうと、政治であれ文化であれ、生活そのものであれ、少しでも他に依存するかぎり駄目なんじゃないかという考えが徹底してあります。だからどんなことでも、自分の目の前に突きあたったことがあるなら、じぶんでやっちゃわなければ駄目だ。それで、じぶんでできないことは他人ができると思ってもいけない。また、どんな問題についてでも、じぶんが成しうること、あるいは考えうることが限度であって、それしかこの世界にはないのだ、という概念になりますね。そうすると、それは徹底的な自力主義であって、自力で到達できないものはこの世にないと思わなくてはいけない。もちろん、そのことは観念の問題ですから、もっと優れたことを考えうることは、実際的にはたくさんあるでしょうけれども、それはないとしなければならない。だから、じぶんにこの世を変える力もなにもないとすれば、それはだれにもないんだと思わなければいけない。かりにあってもそう思わなければいけない、とぼくはかんがえて生きているのです。
(吉本隆明「II『歎異鈔』の現代的意味」 /『最後の親鸞』ノート』/『吉本隆明全集15:1974ー1978』晶文社、2018年3月刊、183頁)
親鸞の絶対他力の思想に対しておそろしいほどに身体的な逆説を契機とした思想の言葉ではないか。
朝食や夕食前のお勤めが習わしだった祖父は日常も念仏が口癖のようだった。擦り切れてボロボロになった「経典」を身近に起居し、年老いて「苦界」を云々するよりも「なかなかお迎えが来ない」と半ば嘆くようなそぶりが多くなった。
実家の祖母は祖父のような念仏の老人というより昔語りの老人だったが、「お迎えが来ない」という口ぶりだけは似ていなくもなかった。
母が言った「死にたくても死ねない」のはなぜか?、どうしてなのか。また祖父や実家の祖母の口癖みたいだった「お迎え」とは「死」を指していたのかもしれないが、それはどこからやってきてどこへいってしまうものなのか?。晩年の三者が判でも押したかのように漏らした〈言葉〉に通底する身体的な不可避性とは、その契機とはどのようなものだったのか。
暮も押し詰まった晴れあがった午前に、3台使っているファンヒーターおよび灯油用ポリタンクの給灯油に訪れた娘夫婦から、ほぼ忘れかけていた三カ月前の心臓手術の「説明書」を受け取った。
前日の夕食後に久しぶりに「過呼吸」になったが、「説明書」冒頭に挙げてあった病名の1〜4が心臓と腎臓に関するもので5番目が「うつ病、過換気症候群」だったなんてまったく失念していた。また、予想される死亡率が2〜5%、死亡+主要合併症が10〜15%だったということも。
後期高齢者というか「老い」を生きること自体が「うつ」そのものだから、ことあらためて「病名」にあげるほどのことでもないような気がする。このことは病院内においてだけでなく、一般家庭においてももっともっと知られてよいことではなないか。先行きになんの光明も見出せなくなるから気が滅入るのも仕方のないことだろう。
車椅子生活を余儀なくされるようになった谷川俊太郎が、ブレイディみかことの往復書簡本で造語した「その世」について、「肌感覚として死が近づいてきている。若い頃の明快なこの世ではなくて、あの世に近づいていくプロセスとして『その世』があるんじゃないかって」と語っていた。
この世とあの世のあわいに
その世はある
騒々しいこの世と違って
その世は静かだが
あの世の沈黙に
与していない
風音や波音
雨音や密かな睦言
そして音楽が
この星の大気に恵まれて
耳を受胎し
その世を統べている
とどまることができない
その世のつかの間に
人はこの世を忘れ
知らないあの世を懐かしむ
この世の記憶が
木霊のようにかすかに残るそこで
ヒトは見ない触らない ただ
聴くだけ
(谷川俊太郎 ブレイディみかこ 奥村門土(モンドくん)絵「その世」/『その世とこの世』岩波書店、2023年11月刊、33〜35頁)
インタビュアーの尾崎真理子に「『その世』って何でしよう?」と尋ねられた谷川俊太郎は「ある程度、特定できるけれも、最終的には特定できない『時』なんじゃないかな」と話していたが、具体的にどのような時[空]に出入りできるかがよくわからない。あちらとこちらの間のどこなのかがわからない時間感覚も線状に流れていなくて、年齢を重ねてきた幼少期からの時間がCTスキャンで輪切りしたみたいに一緒くたに重なって全身を浸しているようなのだ。
ちなみに、図書館の雑誌コーナーでブラウジング中に見かけた谷川俊太郎追悼特集で、ブレイディみかこは「その世」を「somewhere in between」と英訳して見せていた。横書きにすることによって、せっかく詩人の縦書き言葉に働く重力の色合いを、無造作に右から左へと横流してしまっているのではないか。
こういう、現世の生死の〈はかなさ〉や憂苦を唄うことには、どういう意味があるのか。この個所は,『大無量寿経』の「人、世間の愛欲の中に在りて、独り生まれ、独り死し、独り去り、独り来る、(人在世間愛欲之中、独生独死独去独来)」からきている。あたりまえのことが唱われているといえばそれまでだが,死の独一性を自覚的にとりだしている点で、読むものにどきっとさせる認識をふくんでいる。『大経』のこの個所を和讃にしたのは、一遍の見識に属していよう。また、詩的な修辞としてのよさも評価される。人間はたれも、〈生きている〉ということのさ中では、その状態を永続的なものと考えて安心している。たまたま、近親や、他人の飢餓の死、病死、戦乱の死を眼のあたりにみて、その瞬間だけは生死の〈はかなさ〉を垣間見るが,すぐに忘れはてる。なぜならば、死を忘れていることは、生の重要な条件だからだ。忘れなければ絶対的なすがたで個を襲う〈死〉という暴力をこらえることはできない。それでも〈生〉の〈はかなさ〉と〈死〉の絶対的なすがたを、自覚的に強調するとすれば、人々に〈死〉を超える信仰を勧進しているからである。親鸞にとっては、おのずからそうなったとき死を受け入れればよい、という問題であったが,時衆思想にとっても、その詩的な感性にとってもここは、重要な一事であったらしい。
(吉本隆明「和讃」/「最後の親鸞」/『吉本隆明全集15:1974ー1978』晶文社、2018年3月刊、46頁)
大正生まれの母は在宅介護暮らしになってから問はず語りが多くなったが、それも散居村の実家で育った幼少期にまで溯ったりして、小学校時代の逸話など聞くのも初めての事柄が多かった。そのうち、何かと息子とその嫁の世話無しには自宅で暮らせなくなった自分が死にたくてもなかなか死ねない‥‥‥、という身体の自然現象みたいな語りが口癖のようにもなった。デイサービスに行きたがらず、ヨレヨレながらもとにかく家にいてくれるだけでいいんだよと世話をさせてもらっていた息子夫婦の思いもなかなか伝わらなかったのだろうか。
口にも文字にもあらわせないような、思惟を超えた真楽、そこに具象化される〈真実〉と〈虚偽〉との距たり、あるいは如来と人間とのあいだの距たり、それを一歩でも縮めようとする所業は「横出」であり、他力のなかの自力であった。だがこの絶対的な距たりの自覚において一挙に跳び超される〈信〉楽の在り方こそが「横超」と呼ばれた。絶対的な距たりを縮めようとする行為は、遠まわりの善であるという逆説の完成こそが親鸞の教理的な真髄であった。
すこしでも善の方へという志向性は善への接近を意味しない。むしろ絶対的な距たりを知ることは、その距たりを一挙に跳び超えるものである。
この「横超」という概念は、漸次的な歩みの果てに到達があり、到達の果てに安楽の浄土があるというイメージを、まったく組みかえるものであった。また生の歩みの果てに死があり、死の奥のほうに無があるという観念のイメージをも組みかえるものであった。ただ漸次的な進行という概念を否定するだけなら超越であればよい。あるいは跳躍であればよい。進行という概念もまた否定をうけなければならない。親鸞はただ充溢するもの、びまんするもの、滲みとおるものの概念が、いわば絶対的な距たりを跳躍するイメージを「横超」という概念にあてているように見える。
(吉本隆明「教理上の親鸞」/「最後の親鸞」/『吉本隆明全集15:1974ー1978』晶文社、2018年3月刊、108〜109頁)
無宗教のままで生きたようにみえる谷川俊太郎が詩的直感で「この世とあの世のあわいに」吹く風のように聴きとった「その世」という詩的体験はどこかで、吉本さんが思想詩としても書かれた『最後の親鸞』の詩的体験と交差するように擦れ違った瞬間があったのではないか。
「正定聚」は弥陀の本願を至心に信楽して、浄土へゆこうとして、念仏することが決定したときに得られる境位で、弥勒とひとしく、仏となって〈さとり〉を得られることが必定であると保証された位である。けれど仏のさとりそのものではない。それは信心が決定したとき現世において即時に得られるものである。来迎や臨終をまつのは定善・敗善の他力のなかの自力の行者についていわれることである。弥勒は自力の菩薩であるが、他力念仏によって得られる正定聚は、他力だから、即座に〈さとり〉へ超出する道に佇っていること。これらを説くことは瑣末な教理上の疑義とその解答のようにみえる。
(吉本隆明「教理上の親鸞」/「最後の親鸞」/『吉本隆明全集15:1974ー1978』晶文社、2018年3月刊、129頁)
100歳の手前まで健康寿命をまっとうするかのように亡くなった祖父の世話から手が離れた母は、京都そして奈良で春秋のお寺巡りを愉しむようになった。二階で寝起きしていた部屋の文机の座右には植物や樹木の本があり、壁には永観堂禅林寺にある「見返り阿弥陀」の写真を飾っていた。旅行もできなくなって一階仏間の介護用ベッド暮らしになったときは、その阿弥陀如来像だけは日々眺められるようにして欲しいとせがまれた。
亡くなった母の遺品整理をやってくれた妻も亡くなり、祖父が遺した仏壇を拝む毎朝の仏間の出入りを背後から眺められているような気配がする郊外の一軒家で暮らす日々に‥‥‥、なんだか埴生で田舎住まいだった少年の頃の《秘密基地》に通底するものがあるような気がしてこないでもない。(2025年2月2日記/4日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(32)あるいは〈関係〉としての身体
[前略]
・「雑草という草はありません」ということばは、
あまりにも有名になってしまった。
一般的には昭和天皇の発言ということになっているが、
その元は牧野富太郎だという説もあるらしい。
なるほど、実に見事な名言だと思う。
雑草という名の草はたしかにない。
人間の都合で勝手にそうまとめられたにすぎない。
それは、たぶん「大衆という人なんかいないよ、
それぞれに一人ずつちゃんとの名前のある人だよ」、
というふうな意味のイメージが重ね合わされて、
このことばは受け止められてきたのだと思う。
その一方、これほど短くて人に伝わりやすい名言があると、
人はそこのところで、それ以上考えなくなりやすいのだ。
雑草、と聞いただけで、「雑草という草はないんだよ」と、
いかにも、そのことを知っている側の人間になってしまう。
そして、話がそこで終わってしまいがちなのである。
そう、「鳩サブレー」が鳩のかたちだと知っているだけで、
すべてを知ったような気にさせてしまうのと同じようにね。
[後略]
(糸井重里「今日のダーリン」/『ほぼ日刊イトイ新聞』2025年2月1日)
一、二階合わせて部屋数7つあまりで築五十数年になる郊外の庭つき一戸建てが我が住まい。妻に先だたれた独り暮らしも三年目になるが、ふとした折に各部屋ごとにこれまで一緒に暮らして順次生として見送った家族それぞれの居場所での佇まいがうっすらと影射しているような気配を感じたりすることがある。それだけでは足りないのか、祖父や母の面影には引っ越してくる前の埴生での貧乏な民家暮らしの佇まいが重なってきたりすることもある。
高屋敷界隈で農作業が負担になってきた老兼業農家の中には、宅建業者の勧誘などもあって田んぼや畑仕事をあきらめ、それらの跡地を宅地造成してアパート経営に乗り換えるご主人が増えつつあるのだろうか。
これから先のことはわからない老朽化した独居暮らしも、近年あたりに建て込んできたような集合住宅じゃなくて、小さな庭に囲まれた一軒家でほんとうによかった。新築直後の座敷からの立山連峰の眺望も隣接空き地の新築家屋で遮られてしまったときは残念至極だったが、移住当時の都市近郊への人口流出増加の背景を物語るものだろう。
狭いながらも古い樹木と植え込みの庭が「街道」と「民家」を行き来するように軒端を伸び広げ、独り住まいの日々の生活に立ち戻る身体の時間性を解き放つ場のようにも感じることがある。
本書が「庭」の比喩で考えていくプラットフォームを内破するために必要な環境とは何か、これまでの議論から浮上するのは、以下の三つの「庭」の条件だ。
第一に「庭」とは人間が人間外の事物とのコミュニケーションを取るための場であり、第二に「庭」はその人間外の事物同士がコミュニケーションを取り、外部に開かれた生態系を構築している場所でなくてはいけない。そして第三に、人間がその生態系に関与できること/しかし、完全に支配することはできない場所である必要がある。
では、これらの条件をどう、実際の場所ーーサイバースペース/実空間ーーに実装していくべきか。
(宇野常寛/§4「庭」の条件とその実装/「#3「庭」の条件」/『庭の話』(講談社、2024年1月刊、106頁)
和食の料理の腕が確かだった祖父にとって、埴生の住まいの瀬戸の庭は料理の配膳みたいなものではなかったろうか。東向きだった八畳の座敷の縁側に近いところから庭木や植栽に交えて石灯籠や敷石を配置した先で仏花用の花壇や畑を耕し、裏の小川に沿った農道との境目の鶏小屋や納屋との空間地を作業場としていた。東の田んぼに面した端を仕切るように柿や無花果や石榴の木々が横に並んでいて、縁側から降り立つと当時の田舎暮らしを反映したグラデーションに彩られた学童期の独り遊び場でもあった。
表の街道を通る誰からも見られること無く、庭に隠れ蠢く昆虫や小動物を相手にしたり、木工細工から樹木や草花のスケッチまで、思いつく限り無心に独り遊び呆けた。築山や泉水を備えた母の実家の庭は縁側から降り立つ身体によそゆきの感じがして、子どもの遊び場には不向きだった。でも座敷からの眺めは祖父の作庭とは格段の差があり、家系の人だけでなく歴代の庭師の手も入っているようだった。
埴生から高屋敷に越して来て間もなく、表の6メーター幅の市道との仕切りに植えた数株の躑躅を抜き去られたのが、田舎の背戸庭の樹木や植え込みを持ち越した作庭直後の現地での半公共的な挨拶代わりみたいになった。それだけで終わらず、祖父が仕立てた手向山なども夜中に盗まれ、その穴埋めに山王祭で賑わう露店で買ってきて植えたモミジもいつの間にか持って行かれたのには、他所から越してきたもの対する嫌がらせみたいな感じもしないではなかった。
そんな不愉快な出来事も帳消しにするかのように、地元の熟練した植木職人に恵まれ、主木の赤松そのほかの移植した樹木や植え込みはすべて根付き、繁茂するうちにさまざまな昆虫や小動物なども見かけるようになり、いろんな野鳥も飛来するようになった。
埴生の田舎住まいで独り遊びと仲間遊びが混在するようになった頃だが、自宅前の街道を挟んだ筋向いの奥まったM家の広い庭が格好の遊び場となった。「庭」といっても蔵や納屋や灰小屋などもあり、柿の木などの樹木だけでなく畑なんかもあり、中堅農家のいろんな作業場としても使われるといった趣きだった。無愛想に見えて満州での開拓生活の話まで聞かせてくれたりしたM家の主人は近所の子どもらの好きにさせてくれていたのだ。
小学校の運動場や神社や寺の境内といった公けの趣きがなく、私邸の「庭」というより原っぱや広場未満の空き地のようで、そこでは引き揚げ児童に対するいじめが入り込むような余地がなかったのがよかった。よそ者を排斥することによって村の結束を維持するみたいな共同[的な仲間意識]幻想が希薄な場所はそこだけではなかった。製材所が休みの日に遊んだ広い材木置き場や、祭りの獅子舞の踊り子に加えられて事前の夜間稽古に通った納屋や、子どもでも運び出せる里山の間伐材の集配作業場などに居合わせるようにしながら、引き揚げ地となった埴生村という地域的な共同性に馴染んでいったようだ。
いじめの温床でもあった村の小学校を出て、遠い町中を抜けて通った中学校のクラスでも新しいいじめが待っていたが、入部した剣道や放送クラブは部員も少なくていじめとは無縁だった。
子どもから大人まで、とにかく人の集まるところは徒党ができやすく、仲間内の反目だけでなく、グループ同士がいがみ合ったり、誰それが気にくわないなど、ちょっとしたきっかけから誰かが標的とされるいじめに発展しがちな傾向はどこにいっても避けられないと、半ば諦めて学校生活や職場に馴染むしかなかった。
■いじめの本質は、暴力や攻撃という現象面よりも、「同調」という学級構成要因そのもののうちに潜んでいる気がします。だからこそ、当事者はもとより、同級生や教師にも簡単には止められない。なぜなら、孤立している人間の側に立つことは、同調を拒むことにほかならないから。■友達がいないことを「恥」みたいに感じる感覚が蔓延したのは、半分ぐらいは少年ジャンプのせいだと思っています。私は友だちの少ない若者でしたが、そのことを恥じた記憶はありません。「オレはバカじゃないから群れない」ぐらいに考えてました。ジャンプ洗脳がなかったからですね。きっと。■ヤクザ映画は、ほとんどすべて、友情の物語です。このことから考えても、「友情」が、「暴力」「血盟」「敵探し」と極めて親和性の高い概念であることがうかがえます。[■は原文ではツイッターのロゴマーク]
(小田嶋隆=著 武田砂鉄=撰『災間の唄』サイゾー、2020年10月刊、55頁)
中学校時代の私的な大問題といえば、風前の灯みたいな三反百姓生活から将来的にどうやって抜け出しながら稼げるようになるかという進学・進路に関わる事柄だけではなかった。地域や学校での人間関係にまとわりついてくるいじめをどうやれば解きほぐせるかが悩みの種だった。
田舎の狭い交友関係の範囲が、遠隔通学の総合高校へ、そして通勤・通学した都市部の職場や夜間短大へと広がるにつれ、職場内では日教組系の労組活動があり、街中での新左翼系の街頭行動に加えて、女性関係のもつれにも揉まれたり、田舎育ちで家族や地域社会を成り立たせている人間関係だけでなくその組織的行動についても何もわかっていないことを思い知らされることになった。たったいま生きている場所[いま・ここ]から、自然と社会の裂け目[に有る自己]から違和としての共同性まで、個としての生誕から死まで‥‥‥など、どうにかして見通せるような身体的視座となる根拠が欲しかったのだ。
わたしが、詩をかかない状態でつきあたったのは別のことだ。わたしは詩をかくという心的な状態で、はたして、現在の情況の根柢につきあたることができるか、また、現在の現実の総体をヴィジョンとしてもらえるところまで降りてゆくことができるか。わたしが詩をかくことが、世界の根柢に貌をつきあわせ、対話することにつながるか。たとえ、秋の街路樹をわたる、「時」や、それを感受するときの葉たちの動揺をとらえるときでも、世界はそこに無形のうちにあらわれるか。
わたしは、いくたびも、そのことに疑いをもち、その問いをじぶんにつきつけた。
(吉本隆明「情況に対する問い」/『吉本隆明全著作集5:文学論 II』勁草書房、昭和45年刊、471頁)
たまたま大学の図書館に勤めることになって見聞きした、講座制の学部組織の裏で人事権を盾に特定の教職員の職階級を塩漬けにする村八分的ないじめの構造にも、過去の村社会だけでなく現在の町内会などでも見られるいじめに通底するものがあったようだ。地方大学のキャンパス内にインターネットが導入されはいじめた黎明期の掲示板で、教職員や学生が上下の分け隔てなく意見を書き込むだけでなく助け合ったり、相互に協力できるようになったのもいつの間にか言葉による罵り合いの場になって廃れ、面白くもない形式的な告知の交換だけになってしまい、手のひらを返したように書き込まなくなった人たちの無言が掲示板に棹さすように何事かを語っているようだった。
アジア的な負の共同[幻想]性がいまじゃSNS上にも浸透しているようだが、国家の規制や枠組みを逸脱している[ように見える]インターネット・プラットフォーム[GAFAM]を境にバーチャル[AI情報化社会]とリアル[資本主義社会]の乖離[議会制民主主義の無効化]が深まりつつあるのが現実だ。ドナルド・トランプとイーロン・マスクのツイッター改めXのフォロアー数を足せば3億以上になるーーリアル/ヴァーチャルのある臨界点を超えたようなーー数字がそのことを象徴している。
情報発信の場としてのインターネット・プラットフォームの側面はともかく、世界を観察し得る窓としてのSNSの役割はいつの間にか薄まり、どうしようもない愚民劇をさらけ出す場に変貌しつつある。権力者がアカウントを持つことは、ともすると一方的な言論の粛清を強化するとっておきの道具にもなりかねない。
手作りHPや掲示板やブログなどを使い分けたWeb1.0からWeb2.0になって、インターネットといえばSNS一色みたいな舞台に、やんわりと風穴を開けつつあるのが、AIによる大規模生成言語システムの登場[実用化]だろうか。
カフェでの光景をChatGPTに頼って村上春樹風に叙述してもらう。文体の傾向は掴んでいても質感までは再現できないという精度だが、小説家の目を借りて日常を眺められる気がして楽しいな。カフェに座って本を読んでいた。目の前のカップからは、まだかすかに湯気が立っている。音楽はボサノヴァだ。曲名はわからない。でも、たぶんジョビンあたりの曲だろう。店内は午後の静けさに包まれている。みんな、何かを待っているような顔をしている。隣の席の男女が、妙に真剣な顔で手術の話していた。 レーシック、親知らずの抜歯、パイプカット。 どれも、そこまで劇的なものではないが、それなりに人生を変えてしまう可能性のある処置だ。 視界をクリアにし、余分な歯を手放し、未来の選択肢を一つ減らす。 そういう種類のこと。女性はカフェオレのスプーンをかきながら話していた。 なるほど。これは、無意識の身体の調整ではなく、何か少し大きな問題はないかもしれない。人はなぜ、自分を変えることにそれほど熱心なのだろう?私は本を閉じ、コーヒーをひと口飲んだ。もうぬるくなっていた。ぬるいコーヒーはいつも、何かを決定的に遅らせてしまったような気分にさせる。スピーカーから流れるボサノヴァのギターの途中、一瞬だけ切れた。 バリスタがスチームミルクの一時をひねり、小さな爆発のような店内に響いた。 私はコーヒーを飲み干し、店を出ることにした。ちょうどいい。そろそろ散髪に行くつもりだったの。 私にはレーシックも、親知らずの抜歯も、パイプカットも必要ない。
(江本伸悟@ツイッター改めX2025年2月15日)
上記につづいて「しかし今のところChatGPTとの付き合い方は、答えを期待して問うというより、とりあえずの出力に対する違和感の言語化を自分で考え、という感じだな。」と書き込まれていたが、数週前の「ほぼ日」HPのコラムで糸井重里は対談前にその相手と自分との間でどのような話題が想定されるかをAIチャットで予測していると披瀝していた。
日に一回はのぞいたりしているSNSでは、家族や友人に打ち明けられないことなどもチャットでAIに寄り添ってもらえてとてもありがたいとの書き込みを見かけたりする。
第三者的には「身体」を持たないAI生成言語システムが新たに擬似的な対幻想のプラットフォームを提供しつつあるようで掴みどころのない気味悪さが伴いそうだが、ご当人が救われればそれでいいことであって余計な口出しはやめておこう。[と言いながら書き残したり、ほんと書くことは恥さらしなことだ。]
そんな自分が思うには、自然と社会との違和を生きてきた「個」としの身体[内に累積した声]と対話できるようになればいいのにというのがAIチャットの未来形だろうか。
読んでいるうちにわたしも一つ考えを出しておきたくなった。身体性からみた個々の人間は、その時期までの人類史を身心の活動性として内包している。これを「小」人類史とすれば、いわゆる人類史(政治、社会、文明、文化の歴史等)は、生物を含めた世界の各地域の人類の身心の活動性から見られた現在までに至る外在の「大」人類史として存在する。この「大」「小」の人類史を媒介するものが遺伝子(種の要素)、地域言語、地域風俗習慣などの地域的活動性だとおもう。精神活動からみれば、個人幻想、対幻想、共同幻想類と、外在自然史との関係が人類の存在根拠であるとおもえる。
(吉本隆明「瑞龍鉄眼『鉄眼禅師仮名法語」/『思想のアンソロジー』ちくま学芸文庫、60頁)
一緒に暮らしたことのない実家の祖母となると、建て替えられる前の格式ある庭付き古民家暮らしにおさまるように、呉服屋から請け負った着物の裁縫仕事の合間だけでなく、お泊まりした時の寝物語りの思い出が色あせないのはどうしてだろう。それなのにせがんでまで聴いた話しを何一つ詳細に思い出せないのが悲しい。山や村境の動物たちと人とのまじわり、村に暮らすじいじやばぁばやおかしげな男や女の姿、さまざまな境遇を生きる息子や娘たちのことなど、録音しておけばよかったと思うくらい色んな民譚をしをしてもらった。[下線部傍点]
不思議なことに実の子の母だけだなく、四つ違いの叔母の口からも実家の祖母の昔語りが話題になった記憶がないのはどうしてだろう。高儀の実家から埴生の祭礼にやってきた夜なども語ってくれて、祭の余興より面白いと感じたこともあった。聞くものと語るものを包み込むような肌合いがあって、日常と非日常を行ったり来たりする影のような気配に身震いするようなこともあった。
「木の股に置かれていた」「川の堰に樽に入れられて泣いていた」‥‥‥こうした言い方はよく耳にします。そして、民話では水の向こうから流れてきた「桃」や「瓜」や「小箱」の中に命が潜んでいると語られます。それから、木の股は、「姥捨て」の民話の中では命の捨て所として重要な意味を持っています。
川の上流や木の股が命の誕生や消滅にかかわると語られて、命はひととき「授かる」ものであり、またいずこかへ「返す」ものであるという先祖の生命観にわたしは胸打たれます。
また、「一度他家に預けて、誰かに拾ってもらう」という営みにも、命に対する先祖の思想を感じます。つまり、命というものは自分たちの手で生み出して、自在に育てていくものではなくて、いずこからか「授かる」、いわば預かりもの(拾いものといってもよい)として、もたらされる存在なのだという思想を映し出しているのではないかと思います。
(小野和子「第五章 佐々木健さん」/『忘れられない日本人』PUMPQUAKES、2024年2月刊、204〜205頁)
「捨て子」は川に、「姥捨て」は山野に、それぞれ〈他界〉を想定した「死譚」のようにも読める。村落共同体の口減らしの為に若夫婦の対幻想の果実を水子として遺棄され、子を産めなくなった老夫婦の対幻想が村落共同体から実質的な生活基盤を失って、いずれも〈他界〉に追いやられたのだろう。後者も口減らしを兼ねてのことだったろうが、対幻想の共同性が実質的な基盤を保持し得なくなるというより、対幻想自体が自己幻想に対してだけでなく、村落の共同幻想に対しても固有な位相を保てなくなったかどうかが〈他界〉を設けさせているのではないか。対幻想の居場所を失った者は自己幻想の世界に慣れ親しむか、村落の共同幻想に従うしかない。
「木の股」や「川の堰」が人間の生誕だけでなく死にも関わる場所となっている両義性は村落の共同幻想の他界の空間性をあらわすだけでなく、その生誕と死に関わる対幻想の発生と消滅の時間性[繰り返し]によるものだろう。個としての人間対人間の[性差に基づく]対幻想は共同幻想と個人幻想とを両極として宙釣りの位相にあるから、村落共同体の共同幻想と家の共同幻想を行ったり来たりする民話[や民譚]では生誕と死の境目が曖昧になり、いとも簡単に死から蘇ったりする復活譚の印象が濃く思い返される。
預かりものや授かりものの命というところでは、そもそも自力や他力といったことが崩壊してしまうのではないか。かといって、在るがまま為すがままということでもなく、あちらとこちらがたまたま出会うようなところ、とでも言ってみたくなる。[下線部傍点]
崩壊してしまえば立ち止まって終わりかというと、けっしてそういうことではなく、崩壊したところで立ち迷って右往左往しながらもそこから何処へ往く[還る]かが壁のように立ち現れよう。
壁を抜けるところは借りものの現実なんかじゃなく、日常の生活の中にしかない。なんというか日常生活における身体的実感にしか力点をおかないで、それ以外には関心を持ちようがない起[帰]点と絶え間なく往還できていればいい。
そこに生活者の像があり、それはなんらかのイデオロギーや、政治や思想にかぶれたり、文化にも染まったりもしない。本など読まず、テレビや新聞を見なくとも、スマホを手放さず、SNSがあるじゃないか、といったような現実の諸々の実態は、原点となる身体的な「起[帰]点」があっての、そこからの逸脱としてしか生きざるをえなくなってきている現状を物語っているだけであって、そこはなんら問題じゃない。
放っておけばこれからも人間の身体はどこまでも複雑化する環界との相互作用によって遠隔化された触手で否応なく様々なものを獲得していかざるをえないだろうが、理念としてでも指標となる生活者の姿が現実的な歯止めとしての働きをやめないだろう。その像の核となっているのは生活概念というより生きて在ること、身体的な生存の最小条件そのものにある。行きがけの駄賃をいっぱい払えるだけ払っておけば、少しは帰りがけの身が軽くなるというように。(2025年2月18日記/20日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(33)あるいは〈孤食〉のつれづれ��
季節の枝物を買い出しに出かける。それで丸1日ツブレた
りする。1月のロウバイから始まり、トサミズキ、キブシ、
コデマリ、キイチゴ、夏のドウダンーー今は、青いナナカマ
ドに、庭で伸びすぎて通るのにジャマな、アジサイを切って
生けてある。
そんなの余裕があるからだ(私だってねぇよ!)。花より
も食べ物の人がいるのだーーと、言われればそれまでだが、
人はそれだけでは生きていけない。覚えているだろうか?東
日本大震災の後、全てが流された町で、まず花屋が再開した
のを。人は死者に手向けるため、自分を慰めるために、遠く
からでも花を買い求めに来る。ウクライナのキーウの人たち
も、食料と共に(行き場を失った)チューリップの花を配っ
ていた。砲弾で穴だらけになった花壇に、淡々と花を植える
おじいさんもいた。
(ハルノ宵子「猫屋台日乗:その26;花と愛と」/『小説
幻冬7月号』2022年7月27日発行)
かってのサンカの風葬あるいは樹上葬を思わせる「木の股」というのが、空間的な〈他界〉を語る民譚のキーワードになっているようだが、なじみのネット空間に置き換えると、さしずめインターネット黎明期のネットサーファーによるバーチャルな掲示板での炎上死ということにならないだろうか。手向ける花も咲かない空中楼閣のようだが、今じゃ見られなくなった田舎の井戸端会議や農閑期の囲炉裏端にだって誰それを血祭りにする差し金が隠されていたことを忘れちゃいない。
おもだった田舎住まいの民家の庭が街道に向けて開かれていたように、茶の間の囲炉裏はさしずめ天に向けて開かれた〈庭〉でもあるかのようだった。見上げれば煤けた梁が組み合わさった吹き抜けの上部に煙抜きが口を開け、吹雪の夜ともなると雪が舞い込んでくるようなこともあった。通過する台風が異物を吹き込むように枯葉に混じって煤が舞い落ちてきたり、差し込んだ陽の斜光の束を通り抜ける煙が万華鏡のような筒状の模様を描いていた。その下では煮炊きだけでなく、家族や親戚そのほか善玉や悪玉などの霊なども寄り集まったり、春夏秋冬をめぐる食の喜怒哀楽から苦楽の修羅場まで燃え尽きた日々が。戸口が閉まっていても神や仏が自由に出入りする盆や正月には火を絶やさないようにしたのではなかったか。
私は仕事に関しては、おおむねなまけ者だが、これまでの人生で二度ばかり、自分から」書(描)かせてください!」と、言ったことがある。どちらの場合も、後々考えると大きな意味があった。今回も、そう口走ってから「ありゃ?私何言ってんだ」と後悔したが、今はその意味が分かる。その時点では想像すらしなかったが、私は父と同じ年の十月に母も亡くした。両親の介護を生活の中心に据えていたつもりが、一転たった一年の内に、すべての生きる“よすが”を失ってしまったのだ。
“食”をめぐる物語は、そのまま“家族”の物語だ。ヒマさえあれば、ぶらぶら歩きの好きな私だが、このエッセイを書いている間は、出かけていても「ああ、またあの頃の家族に会いに帰ろう!」と、そそくさと家に戻り、引きこもっていた。しかも“書く”という行為には、少なからず客観性が必要だ。客観的に家族を見直すことは、私にとって最高の“認知療法”となった。おかげ様で精神のバランスを保てたのだと思っている。
(ハルノ宵子「氷の入った水」/『開店休業』幻冬舎文庫、平成27年12月刊)
あの半世紀以上も前の民家の煙抜きの外はどのように変わったのか。囲炉裏のない家で暮らすようになって家族構成も単身家族へと移り変わり、暮らしの窓に映る世相も変わってしまい、屋内は無線LAN[WiFi]でーー煙や煤ならぬーーインターネット・クラウド空間とつながっている。茶の間で囲む食卓[共食]は様変わりし、「孤食」のレシピをグルメ・サイトで調べたり、ネットで冷凍おかずセットの宅配サービスを物色したり、いつの間にか旬の食材や風味を味わう食事時の愉しみが薄らいできている。
家族ぐるみで、はたまた夫婦で、半世紀以上も通い慣れした寿司や麺類のお店にも入りずらくなってしまった。二度とも病院食でさんざん悩まされた長期入院などで足が遠ざかったりしていたせいもあろうが、どうもそればかりではなさそう。石の上にも三年になる独り住まいの孤食に慣らされたのかどうかわからないが、特番や再放送も含め、夫婦でて毎週欠かさず視聴していた『孤独のグルメ』(BSテレ東)の井之頭五郎のようにはいかないのだ。
三代にわたっていずれも料理が上手だった家族や親戚との老いによる別れは仕方がないとして、利き腕の骨折から料理ができなくなるほど衰弱していたとはいえ、まさか調理と食べることを誰よりも分かち合ってきた妻に先立たれるなんて‥‥‥。
そんな二人が外食のとっておきの節目のように味わってきたのがご近所馴染みの“M之寿司”だった。春夏秋冬五十数年にわたって、お通しに時節柄旬の三品を揃えて迎えられ、大旦那の握り寿司はもちろん、その場で見立ててもらう日本酒やワインや洋酒に合わせた若旦那の料理の数々でもてなしてもらってきた。いつも満足して帰宅した妻はいただいた順に手帳にメモするようなこともあった。
旬の八寸に続いて出てくる品々の旨さはもとより、その前に市場で仕入れる若旦那の食材の目利きが心づくしのもてなしとなり、今日まで風味豊かな料理の日々が営まれてきているようだ。《市場でいい魚に出会ってそれが好きなお客さんのことを思い浮かべて仕入れるとご当人が来店するよ》なんて語られたこともあった。
自分じゃ何もできないのに、デパ地下の鮮魚コーナで新鮮な鯛の切り身があったりすると、見逃さずに白ワインに合う夕食の一品に仕立て上げた亡き手腕が恋しくなったりするようなこともある。買い物自転車の範囲内で、魚屋や肉屋や八百屋ほか、パン屋など、馴染みの小商いが勧める食材にも恵まれ、ときには交友ルートから旬の山菜なども入手し、我が家にしかない味わいのある食卓を長年にわたって共にできたことはなにものにもかえがたい。
味噌や醤油や塩だけでなく、オリーブオイルやバターその他が使いさしのままだ。形見のような調味料を使って自炊すれば、という声が聞こえてきそうだが、食べ飽きない白米を炊くだけ、味噌汁や夕飯のおかずなどは通販品で間に合わせることしかできていない。昼のおかずはとりあえずスーパーやデパ地下の食品売り場の買い物で済ませている。
酒粕に大根とイワシ入りの味噌[粕]汁や里芋の入った豚汁などが田舎の冬場のご馳走だった。スーパーの売り場でけんちん汁や豚汁の具のセットを見かけたりするが、ひと袋4〜5人前入りとあっては食べたくてもとても手が出ない。
冷凍21食おかずセットなどをベージュの耐熱紙プレートそのままじゃなく、解凍した1セットの三品を大きめの無地の平皿に盛り分けて色や風味が引き立つようにしている。肉じゃがやブリ大根などは鰹節と昆布出汁で調理されているようで我が家の味が蘇ってきそうだ。
祖父は身請けした女房に料理をさせなかったということだが、昆布と鰹節に干し椎茸などで出汁を取っていたようで、それが母や妻にも引き継がれてきたのに、独り身になって途絶えたことになる。間に合わせの孤食の毎日を続けていると、以前より食べることに向き合うようになった気がしないでもない。
祖父は大正11年に妻と死別し、田畑を耕しながら育てた一人息子を植民地だった朝鮮総督府勤務に送りだして独り住まいも長かったようだが、自給自足の料理上手で食べることには困らなかったようだ。
囲炉裏と竃と七輪で焼いたり煮炊きしていた民家の食卓は質素そのものだったような気がする。醤油は買っていたが味噌やお茶や漬物などはすべて自家製だった。味噌汁の出汁は乾物[煮干し、だしじゃこ]で具はほとんど自作の野菜を使っていた。
心臓病以来の減塩食を指導されているこのごろは、日本各地の5種の生味噌タイプのセットを朝飯用に使いながら味噌の量を少なめに加減している。具に合わせて白髪葱や刻み葱を放すとけっこういける。母や妻がよく作ってくれたじゃがいも[と若布]の味噌汁が好きだったが、なぜか市販の味噌汁セットには見当たらないようだ。昼と晩はほとんどワインが味噌汁代わりということにしているから減塩まちがいなし。
幼かった頃の囲炉裏端では魚や肉が食卓を飾るのは珍しく、卵を産まなくなった鶏を潰したのが肉料理の主役になったりした。川釣りにはまっていた中・高性の頃は、釣果を魚料理に目がなかった祖父に調理してもらっていた。埴生から高屋敷に越してからも晩酌を絶やさなかった祖父が亡くなってからだが、地物の鮎については夫婦してずいぶん贅沢な味わい方をさせてもらってきた。
こういう話でよく例に挙がるものに、夏の鮎があります。鮎の腸から、香ばしい、すいかのようなにおいがすると表現されます。夏の清流に生える岩苔に由来するにおいなのだそうです。鮎は別名を「香魚」といいます。鮮度がよく、はっきりしたにおいを保つ鮎は、感動的です。そういう鮎を食べるとき、私たちはただ目の前の味のよい魚をたべてよろこぶという以上に、この鮎のにおいを媒介して、苔の生えた「夏の清流」へのはるかな想いを抱かされることがありうるからです。ぴたっと焦点が合うならば、魂が持っていかれるような気持ちになることもあるでしょう。鮮度が落ちて香気がくすめば、その力は弱まります。食の感動の大きな部分は、遠くの何かを「映す」力によってもたらされる。この力を振るうものこそが風味です。[下線部原文傍点]
(三浦哲哉『自炊者になるための26週』朝日出版社、2023年12月刊、37頁)
新居を建ててもらった棟梁でもあった砺波の叔父さんとはその後も親交が深まって、毎年夏ともなると庄川の鮎を釣っては足繁く届けてもらった。家族四人じゃ食べきれないくらいで、知人を招いて塩焼きをご馳走したり、冷凍保存した細かいのは空揚げにしていただいた。
夏場の馴染みの寿司店では飛騨の宮川の、そして通いつけの魚屋で買う神通川の、それぞれ生息する川の苔が違う三種の『香魚』を嗅ぎ分けるように冷酒の肴にしながら越した夏もあった。
二人ともワインに開眼したのは中年過ぎてからだったが、絞ったブドウの品種が同じでも産地の違いが色艶を含めた風味になっているようで、それぞれ育った川や畑の違いが微妙な味わいになっていることなど、つねづね食後の話題が尽きることはなかった。
妻に教えられた家庭料理家の辰巳芳子に「達人の作る汁もの、スープも水を超えることはできない。」との言葉あるが、お酒についてもそうとは言えないだろうか。吟醸酒にはワインにかえがたい呑み心地があるようだ。
時節に合わせた家飲みワインが欠かせなかった食後に習慣化していたジントニックも、二人にとっては自宅で汲み上げる常願寺水系の水を凍らせて作る一杯が格別だった。外でも飲んだりしている娘夫婦もその際立つ違いを認めているようだ。
田舎から郊外へ移住したことによって、親類縁者が寄り集まって植え付けから収穫までだけでなく、実りを分け合い、手を替え品を替え料理したものを皆んなでいただいた食の空間も場所もすっかり変容してしまった。変わらないのは水脈は異なっても、ずっと井戸水を使い続けていることぐらいかもしれない。
まず人間以外の動物だって場所の感覚を持っていて、その範囲内で食べ物をあつめたり、捕ったりし、水を飲み、生理の欲求をみたし、休息したり、眠ったりする。それは慣れ親しんだテリトリーをつくっている。こういう動物に比べると人間は三つの特徴をもっている。
(1) おなじく動物である。
(2) 夢想家である。
(3) コンピュータのように冷静にじぶんの行動を分析することができる。
そこで場所の感覚も動物より複雑になるし、また空間の感覚も、(イ)神話空間、(ロ)実際空間、(ハ)抽象空間という三つの概念を混合してもつことになる。夢想家としての人間は神話空間(象徴空間)をうみだすだろうし、コンピュータのような冷静な分析家としての人間は、抽象空間の概念を作りだすし、動物としての人間は、動物のテリトリーとそれほど変わらないような実際の住居の空間をつくって棲みわけ、食べ物をつくって食べ、水を飲み、休息し、眠り、生殖するといった親しい住家や場所を営むに違いない。そこで実際空間と呼ぶべき拡がりをもつことになる。
この本の考察はさらに詳細なところに入って行く。
人間が空間を体験し、空間の概念を作ってゆくのは、おもに視覚を使ってのことだ。だが、場所の概念が作られるには、視覚とおなじ大切さで手や皮膚による触覚が加わっている。ところで視覚や触覚以外の感覚、味覚や嗅覚や聴覚は、空間の概念を作るのにかかわっていないのだろうか。著者の言い方を再現すれば、村落共同体の自然や生活のあいだでは、たくさんの芳香がかもしだす雰囲気があった。その場所や空間を特徴づけ、その匂いでさまざまな記憶を呼びおこすことができた。現代建築が立ちならぶ都市にはこういう芳香による雰囲気は欠乏してしまった。味覚や聴覚も視覚をたすけて、わたしたちの空間体験を豊かにし、体験の違いを識別するよすがになっている。村落共同体の自然の音や生活の音は、季節ごとに変化するし、また都市の音とも違う。都市では自然の音や、個別の生活を表象する音は欠乏し、その代わりに機械的な人工音や交通音などまったく村落では聴けない響きが、網目のようにとび交い、複雑な騒音を作っている。味覚もまた村落共同体の内部では、共通の味ともいうべきものが、親族や知友のつながり、血縁から血縁への伝承を作っている。都市では味覚の共通性も地域性も、大きくいえば専門のレストランのあいだで系統づけられ、わかれてしまって、個々の日常生活の場から遊びや消費の場に移されている。
(吉本隆明「イーフー・トゥアン 山本浩訳『空間の経験 身体から都市へ』/『言葉の沃野へ:書評集成・下 海外編』中公文庫、215〜217頁)
村落共同体から都市へと移り変わり、遠隔化する五感によって身体化する時空の形成とその変容からフィードバックされる〈身体〉を取り巻く不可視の網の目がせりだしてきている。私的な場から公共的な場へ身体性を希薄化するようなとらえどころのなさは無味無臭で味気なくはないか。
日本国内でインターネットが実用化され始めた1980年代に、その利用や情報機器の操作から取り残されがちな潜在的な[図書館ネットワーク]利用をめぐり、ひそかに懸念された「情報難民」のーーインターネット環境に恵まれた者の持たざる者に対しての優越感が裏返されたーーネット上の居場所はその後どうなっていったのだろうか。
7年前の東日本大震災以来、さまざまな前提がリセットされたと、私は、そう思っている。
より詳しく述べれば、それまで当然とされていた「常識」や、説明抜きで共有されていた「気分」が、いったんゼロリセットされて、それぞれに意味づけを再考されたうえで、あらためて再設定されつつあるということだ。
その、再設定されつつある前提のひとつに、「言論のたたずまい」がある。
わかりにくい言い方で恐縮なのだが、震災以来、私の目には、各方面の言論が、険しく辛辣な口調を帯びるようになっている一方で、逆の局面では、ひたすらにヌルく、微温的は方向に誘導されているようにも見えるのだ。
われわれは、分裂しつつある。
仮に、その分裂が声高に叫ぶばかりの方向と、目と耳をふさいで自閉することを選ぶ方向への、二極化した分裂であるのだとすると、われわれの社会は、いずれ瓦解せざるを得なくなる。私は、その、ほぼかならずやってくる近未来の到来を懸念している。
震災直後の1カ月ほど、マスメディア発の報道もさることながら、ネット上のメッセージは、どれもこれもヒステリックな方向に傾いていた。
ツイッター上でも、”放射能の恐怖”を煽るタイプの言説と、逆にその種の主張を冷笑する書き込みが強い口調でやりとりされていた。
そんななか、震災後ひと月半ほどを経た2011年4月24日に、糸井重里氏が、《ぼくは、自分が参考にする意見としては、「よりスキャンダラスでないほう」を選びます。「より脅かしていないほう」を選びます。「より正義を語らないほう」を選びます。「より失礼でないほう」を選びます。そして「よりユーモアのあるほう」を選びます。》とツイートした。
このコメントが、当時のささくれだったネット内の空気をやわらげた効果の大きさを、私はいまでもよく覚えている。
(小田嶋隆『ア・ピース・オブ・警句:5年間の「空気の研究」2015ー2019』日経BP、2020年3月刊、279〜280頁)
複数のアカウントを持っているだけでとても活用しているとは言えないが、ネットワーク上でたむろするアカウント・ユーザーの一員[多くが匿名]となって相互に評価と認証を交換す[でき]ることで、かっての掲示板やブログに取って代わったSNS[やライン]といったネットワーク・プラットフォームに接続[書き込み]すれば、それが仮想的な〈他界〉のように作用する場にもなりうる。そして対環界的だけでなく対身体的にも〈自然〉との相互作用を見失わざるを得なくなった個人幻想の受け皿ともなろう。それもコロナ渦でリモート・アクセスが常態化した社会を経てより強まってきているのではないか。寄って立つべきアカウント・ユーザの対幻想はタイムラインの共同幻想の波に洗われるように浮かんでは消え、匿名の言論はどこまでも荒れ放題になり、その裏面では人々の間に論争[議論]という行為そのものへの忌避感が蔓延って、声さえデカければよいということにもなり、罵倒欲求を満たすに場合は「匿名」を騙り、承認欲求を満たす場合だけ「実名」で、みたいな使い分けも起きそう。
■「宣伝目的で実名アカウントにしているだけなのに偉そうなことを言うなよ」という決まり文句に一言いっておく。ツイッターは宣伝にならない。なぜなら、この世界の人間は「宣伝」を敵視しているからだ。マトモな本を書くことが著者にとってのほぼ唯一の宣伝である事情は、昔から変わっていない。■私は匿名アカウント自体を否定しているわけではない。匿名ならではの言論空間は確かに存在するし、匿名でないと担保されない立場というのもある。ただ、名前を名乗っている人間に論争を仕掛ける場合には、同じコートに乗るのが礼儀なんではないかということを言っているだけですよ。[■は原文ではツイッターのロゴマーク]
(小田嶋隆=著 武田砂鉄=撰『災間の唄』サイゾー、2020年10月刊、60〜61頁)
実生活上であろうがネット上であろうが、ほとんどの人は思っていることの半分も口にはできていないのではないか。誰しも、その言えない半分を背負わざるをえないからこそ、言葉は沈黙の重さを持っている。あたかも言いたいことをすべて言いつくせるような場から発せられる匿名の発言は、果たして本当の言葉と言えるだろうか。口から発せられた言葉よりも、口にせずに飲み込まれてしまった言葉の方がとてつもなく切実だってこともあるだろう。(2025年3月2日記/4日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(34)あるいは術後の〈カラダ〉をめぐって��
「人類は少しづつ体を失っていく途上にあるのだ。」という言葉に
思わず反応してしまいました。齢九十ともなれば心の方はいざ知ら
ず、体の方は近いうちに必ず失うことになっていますから、人類と
は言わないまでも、私個人は少なくともまず機能面でどんどん体を
失いつつあって、最近試乗中の電動車椅子は自分のアンドロイド化
の初歩的な段階だろうかと考えざるを得ません。
体を失った後の人間はどうなるのかという難題は、大昔から東西
で論じられていると思いますが、幽霊という伝統的存在を私は好ま
しく思っています。ただ残念なことに私はこれまで幽霊に遭遇した
ことがないのです。自分が怨念というような心の状態を経験したこ
とがないせいか、それとも子どもの頃に知った論語の一節「子ハ怪
力乱神ヲ語らず」に当時、科学少年だった私が共鳴していたのかも
しれません。一人っ子だった私はドロドロした人間関係に悩んだこ
とがなく、成人してからも自分の意識下の混沌を主に詩作の源泉と
して考えるという呑気さでした。
(谷川俊太郎 ブレイディみかこ 奥村門土(モンドくん)絵「幽
霊とお化け」/『その世とこの世』岩波書店、2023年11月刊、
97〜98頁)
言葉にならないものがどこまでもこぼれ落ちていくオンライン空間では、迷いやためらいといったものまでが跡形もなく切り捨てられていく。言葉で掬いがたい思いなども削りとってしまう功利主義がのさばり、見境もなく排除しつづけることでしか持続できなくなったその先にはいったい何が待っているのか。
身体に自信が持てないのは、自信がないと思い込むこととは違う。どこかにそんなものがあるということが裏返されているだけだ。自らを信じようとするのは、逆に疑ってもいるからじゃないか。なぜそんなものが必要なのかを疑ってみることから、冷静に見直せる一歩が踏み出せるのではないか。
肝っ玉が据わっているとか据わっていないとか、自信につながる臓器として肝臓を意識したのは30代から40代への曲がり角ではなかったか。職場の健康診断で要精密検査となり、出向いた市内の総合病院のエコー診断で肝臓肥大と禁酒を告げられた。
若かりし頃に二人で一升酒を飲んだりしたことのあった妻も一緒に断酒すると言ったが、人生飲めるうちが“華”だからとばかりに“素面”で晩酌に付き合うようにした。
痛みなどの自覚症状はなかったが、一家団欒の晩酌の場やアフターファイブの宴席など、1年半ほどアルコール抜きにしていたら、いつの間にか身体的な“異和感”が消えてこれで大丈夫という自信がついた。心臓はちょっとしたことでドキドキしたりするが、肝臓はなんとかなると慌てず騒がずユッタリ構えているだけでいい。「沈黙の臓器」と言われるだけのことはあるのだ。
予期せぬ心不全で緊急入院となり、多角的な検査を踏まえてやんわりとだが、こうなったら心臓の弁膜の置換と血管のバイバス手術しかないねと主治医から言われた。
病室のベッドからトイレに自力で立てないほど衰弱した「高齢」の体力が[二つ同時に数時間もかかるであろう手術に]とても身体的に持つはずがないであろう前途の分からなさ。
このまま点滴と投与薬でぐずぐすしながら入退院を繰り返すことになるのか、それともやってみないとわからない手術に「身体」を委ねるのか、いずれにしろ、ことあらためて意識なぞしたことのなかった今後の臓器の身体的働きが気がかりに、それも老い先短い老体の途上で。
循環器内科で院内LANに接続したホルター心電計を常時携帯させられた身体的装着感が緊張を強いるみたいで、それまで遠ざかっていた過呼吸に見舞われるようになった。
手術前の身体的過緊張を緩めようとする症状らしいということだが、そんなことは誰も教えてくれなかった。
手術間近になって心臓血管外科に移ったら症状が治まったのはどうしてだろう。メンタル的緊張とは別に心不全の臓器自体や呼吸器官そのものの緊張が解けたのかもしれない。
その一方で頭では術前の体力保持の為に完食しようと意図するのに、身体というより胃腸そのものが病院食を拒んで吐き気がするようなことになった。術後になってもその傾向は「痛み」とともにますます強くなるようだった。
どうやら自分にとって身体ほど厄介なものはないんじゃないかなどと思えたり、見えない体内器官それぞれの動きや痛いところが気がかりになってくる。
明治生まれの祖父や実家の祖母は日頃の体調や喜怒哀楽を乗りこなすように、いつも「身体」を意識することなどなく、無意識に臓器と和解しているように見えたのは何故だろう。死にゆく時まで自然な感じがした。それぞれ生きる時代によって〈身体〉は変化し、その枠組みを違えてきているのだろうか。
意識や心が見えないというのは常識になっているが、眼が眼それ自体を見ることができないように、身体もほんとうは見えていないのではないか。にもかかわらず、気づいた時にはすでにまさにその身体そのものを生きつつある。
まるで宿命のように身体に囚われていて、それでいて自由であるかのように、食べては何らかの仕事を行うだけでなく、あいまに歌ったり踊ったりさまざまな活動が成り立っている。
自発的な行為ができないとされるコンピューターの世界では、つかみどころのない身体を抜けだせたたかのようにSNSからAIチャットまで、インターネットによる[言葉の]プラットフォームがさまざまな人々を呼び寄せている。
かって吉本隆明は、人間が社会を認識する上で機能する三つの幻想を提唱した。それは自己幻想(自己に対する像)、対幻想(家族や恋人、友人などに対する一対一の関係に対する像)、共同幻想(集団に対する像)の三つで、これらは互いに独立して存在し、反発する(逆立する)とされる。そして、今日の情報社会を観察したときその中核に存在する代表的なSNSーーFacebook、X(Twitter)、Instagramなどーーは、この三幻想に対応した機能の組みあわせでできている。具体的にはプロフィールとは自己幻想であり、メッセンジャーとは対幻想であり、そしてタイムラインとは共同幻想である。自己幻想に拘泥するナルシストは不必要にFacebookのプロフィールの写真に凝り、少ない制限文字数に全力で抗ってたいして面白くもないジョークを盛りこもうとする。対幻想に依存する人は、家族や恋人からのLINEの返信や、既読マークの付くタイミングを相手との関係性の確認に用いて一喜一憂しながら暮らしている。そして共同幻想に取りこまれたゾンビたちは考える力を失い、X(Twitter)のタイムラインの潮目を読み、問題の解法でも新たな問題の設定でもなく、他のプレイヤーからのより多くの承認を獲得することだけを目的に投稿するようになる。
(宇野常寛/§7「関係の絶対性」とその外部/「#1プラットフォームから「庭」へ」/『庭の話』(講談社、2024年1月刊、46〜47頁)
〈庭〉つながりで読むことになった一冊からの引用だが、吉本さんのキーワードでもある「関係の絶対性」がインターネットの「プラットフォーム」と地べたの「庭」とを寄り合わせるように語られていた。
脇道にそれるようだが、インターネットのことはAIに訊けということで、SNSの各機能を吉本隆明の共同幻想論に準えてとらえる視点について『Gemini』を使ってチャットをやってみた。
1.プロフィール:自己幻想
・プロフィールは、ユーザーが他者とどのように自分を見せたいかという「自己幻想」を表現する場と言えます。
・ユーザーは、プロフィールを通じて、自分の興味関心、価値観、ライフスタイルなどをアピールします。
・これは吉本隆明が言う「自己幻想』を、SNSというプラットフォーム上で具現化する行為と言えるでしょう。
2.メッセンジャー:対幻想
・メッセンジャーは、特定の他者との間でコミュニケーションを行うツールであり、「対幻想」を具現化すると言えます。
・ユーザーはメッセンジャーを通じて、親しい友人や家族との関係性を深めたり、新たな人間関係を築いたりします。
・これは、吉本隆明が言う「対幻想」を、SNSというプラットフォームで実践する行為と言えるでしょう。
3.タイムライン:共同幻想
・タイムラインは、不特定多数の他者に向けて情報を発信する場であり、「共同幻想」を形成する場と言えます。
・ユーザーは、タイムラインを通じて、自分の意見や考えを発信したり、他者の投稿を共有したりします。
・このようにして、タイムライン上では、特定のコミュニテイや社会の中で共有される価値観や流行が生まれます。
・これは、吉本隆明が言う「共同幻想」を、SNSというプラットフォームで形成する行為と言えるでしょう。
4.補足:SNSと共同幻想
・SNSは、吉本隆明の言う「共同幻想」を、より多様な形で、より大規模に形成する場と言えるかもしれません。
・例えば、特定のハッシュタグやミームは、一時的な流行として現れては消えていきますが、これもSNSが生み出す共同幻想の一種と言えるでしょう。
・またインフルエンサーと呼ばれる人々は、多くのフォロワーに対して情報発信や意見表明を行うことで、特定の共同幻想を形成する上で大きな役割を果たします。
5.注意点
・SNSと共同幻想の関係は、必ずしも肯定的のものばかりではありません。
・例えば、SNS上での誹謗中傷やフェイクニュースの拡散は、特定の共同幻想が暴走した結果と言えるでしょう。
・また、SNSの利用は、ユーザーの自己肯定感を高める一方で、他者との比較による劣等感を抱かせる可能性もあります。
まとめ
SNSの各機能を吉本隆明の共同幻想に準えて捉える視点は、SNSの構造や影響力を理解する上で、非常に興味深いものです。SNSは、現代社会における共同幻想の形成において、重要な役割を果たしていると言えるでしょう。
以上がものの数秒も経ずしてコピペを可能にした、生成AIによる「回答」であるが、事前に打ち合わせたわけでもないのに、《宇野常寛》や《吉本隆明》の「コト」について学習しているように見えるのはなぜだろう。
全体が見えているようでそれを構成している細かいところまでは見えてこない。合目的に作り込まれたアルゴリズムで、ある言葉にはこの言葉を返す、このイメージにはあのイメージを返すというような働きの範囲内で応答しているようだ。
実際のところはわからないが、どうやらチャット相手が期待する「答え方」を先回り[学習]されているような気がしないでもない。
どのような事柄にも先人はいるようで、登録しているグーグル・アラートが「吉本の幻想三部作についてAIに訊いてみた・結城保典(note)」[https://note.com/yasu5586/n/nc2b133712b9f?magazine_key=m88aded9aa5ce]を拾ってきてくれた。見たところ『ChatGPT』で試みられたもののようだった。
『Gemini』の場合と同様で、ある「見解」について生成AIに問いかけて返された「回答」が「見解」の言葉の水準内を迂回していて、「対話」以前の言葉の概念をやり取りしているだけのように見える。「訂正」とか「否定」といった会話につきものの契機[沈黙の有意味性]が発生することもなく、本来的な言葉のやり取りに欠けているのではないか。
この上滑り感はあんまりいい気持ちのモノではないが、この先も、生成AIとは身体的な違和感を確かめるように、つきあって行くコトになるのだろうか。
たとえば、
・「Firefox 135」正式版リリース、すべてのユーザーがサイドバーでChatGPTやGeminiとチャット可能に(GIGAZINE) https://gigazine.net/news/20250205-firefox-135/
・トランプ政権から知識を守れ、科学者は徹夜でデータの引っ越し急ぐ(Bloomberg) https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-02-06/SR9SZ3DWRGG000
・Googleが新しい検索「AIモード」のテストを開始、一体どんな検索機能になるのか?(GIGAZINE) https://gigazine.net/news/20250207-google-test-search-ai-mode/
・Metaが海賊版コンテンツを含む81.7TB分のデータでAIをトレーニングしていたことが明らかに(GIGAZINE) https://gigazine.net/news/20250210-meta-training-torrent/
(「雪中休み(25.02.18・火)/十字路で立ち話(あるいはワッツニュー)」@『高屋敷十字路』より抜粋)
など、べつに追いかけているわででもないのだが、情報化社会を急き立てるように発信されるトピックをみかけたりすると、変化が速すぎて老体としてはとてもついていけそうにない。それでいいのではないかとも思う。
AIチャットを実装したサイトを使って検索するようになれば、ますます「知識」や「情報」をまとったAIが繰り出す言葉の「概念」の網に絡めとられることにもなろう。外部に「回答」を求めることに慣らされてきた「義務教育」の《身体》にとって「思う壷」になるかもしれない。
身体にとって外部が賑やか過ぎるのはあまりよくないようだ。朝の10時前に一般病棟から手術室に移り、車椅子から手術台に横たわった静けさというより、麻酔前の身体が敏感になったのかもしれないが、五感が研ぎ澄まされるような気がした。
胸あたりの痛みとともに気がついたら夕方前の集中治療室のベッドに横たわっていた。呼吸するのも苦しく、とても鎮痛剤を投与されているとは思えない痛さに耐えている身体だが、人工呼吸器に繋がれて5〜6時間の手術を持ちこたえ、なんとも言いようのない安堵感、元気が甦りつつあるような感じが新しく、それも心臓の働きにあることに目覚めたような気がした。
数日して看護担当のスタッフから《大きな手術から目覚めてどんな感じでした?》と尋ねられたりしたが、仮死状態による臨死体験みたいなものなど、いっさいがっさい何もなかったと言っていい。ただ身体みずからが臓器の働きに注意を向けるようになっただけのようだった。
集中治療室の静寂から個室の静寂に移ってもなかなか治らない痛みをまぎらわせるように、心臓やそれ以外の臓器の働きを探ろうとする身体に気づいた。術後の検査や回診以外の時間をベッドでごろごろしたりぼんやりしながら臓器や関節の感覚を探ったり、スマホを使う気力もなく、ネットからも隔離された状態が身体内観察に好ましく思えた。
何事も過度に集中しすぎるのはよくないのかもしれない。一度だけ夜中の病室のベッドで心臓の脈動が[数倍も?]速くなって身体が振り回されるような状態におちいり、とりあえずナースコールのボタンを押したことがあった。
点滴をしてもらってようやくというか、いつのまにか身体の揺さぶりが止まっていた。術前の循環器内科で頻出していた過呼吸も、心臓血管外科に移った術後は過緊張状態が溶けたみたいに遠ざかったようだった。
身体的ストレスが引き金になるように言われたりしているが、おそらく過緊張を解こうとして現れる症状だから、きつくならないよう上手く経過させるにこしたことはないのだろうが、なんとなく[不安時の]薬を手放せないようなのが常態になっている。
一昨年の精神病棟に入院中も欠かさなかったストレッチとはすっかり縁が切れた。かろうじてリハビリだけは続けているが、ネット上で庭いじりするみたいな手作業でHPやブログを維持するのが関の山といったところだ。
昭和の終わりから平成の初めごろにかけて、インターネットに繋がり始めた図書館業務関連の私的な実践と独習の場として、そして退職後1年半ほどで一本釣りされた司書課程の非常勤仕事のオンライン教材の場としても維持してきた。古希も過ぎて“教室”から引退し、その必要がなくなってから次第に手入れを怠るようになってしまった。
ご近所散歩で高齢者の独居住まいの庭が放置され、荒れた里山みたいな野生に取って代わられつつあるのを見かける。子どもの頃から山歩きなどをしていて荒れた土地を見かけたりしたが、あれなど人の働きが自然に及び難いことを象徴していたようにも思える。
自宅の庭はさておき、自作HP内には、手が回らず削除も更新も中断しているWebページへのアクセスがあったりするのをいいことに、手入れしないで放置された庭みたいなのが数ページも残っている。
長らく機能しなくなっていた吉本さんの講演マップを廃棄し、「ほぼ日」掲載の吉本講演のキャプションを利用して作成した「吉本隆明の183講演:タイトル&キャプション」[http://www.fitweb.or.jp/~taka/YktcT.html]で[テキスト検索して]見つかった該当音源を聴けるようなガイドページを新規作成してみた。
幅広く多岐にわたって奥行きのある講演主題から選んだ内容を、テキスト化された文字を読むのではなく、耳で聴ける臨場感が何ものにもかえがたいネット上のプラットフォームになっているのではないか。喋っている吉本さん自身は見えないが、その場で語る身体に接す[聴け]るのが大きいと思う。
自己模倣する言葉で荒れがちなネットの言論を刈り込むような場がもっともっと増えるようにならないものか。たまにネットで聞いたりしている『端くれラジオ』(内科医の端くれ)が養生中の身に“常備薬”みたいな響きをもたらすなんてこともある。
amazonからは削除したむねと謝罪がありましたので、これ以上はなにもしません。
なんか往年の2ちゃんのようなときめきがあるやりとりと励ましをありがとうございました。
落ち込んでも傷ついてもいませんので安心してください。
そして、これからは「藤谷治の既存小説の盗作8割AI 2割、だからオリジナルと言い張る偽藤谷」とか、「タイトルが1文字違ってあとは著者名含め全部盗作」とか、「本文全部盗用で著者名だけ違う」とか、「吉本ばなな完全リミックス版」とかありとあらゆる似た感じの詐欺が起こりえますので、ほんと、電子書籍とくにKDPの本は確認しながら買うようにしましょう。
このできごとで、少しでもKDPのフィルタリングが強化されるように願っています。
(吉本ばなな@ツイッター改めX、2025年02月25日)
生成AI による文字作成だけでなく画像作成でも同様の“フェーク”が起こっているようだが、私的なお遊びの範囲を逸脱しているのではないか。そのうち静止画だけでなく動画も生成するようになるだろう。
文字だけでなく画像や音までも〇/1であつかえるデジタルの利便性が、生成AI の到来でコンテンツ産業の著作権を揺るがすような事態を引き起こしかねないが、生成AI は身体を持たないから著者性が生じないことになり、その対応に混乱がが生じることになりそう。
それとは別に、激化する生成AI の開発競争においてトレーニング用に著作権のあるコンテンツの利用がフェアユースに当たるかどうかということも今後の争点になろう。
生成AI を操作しているつもりが、生成AI に操作されているような隙間[勘違い]で著者性が揺らいでいるとでも言おうか。
いやそんなことはないだろう、自分で自分の身体を操作しているようだが、実際は身体[臓器]も自分を操作しているに違いない。頭が一方的に身体に命令するのではなく、身体[臓器]からも頭に命令を出していて、その両者が連動するところで著者性[私]が展開することになる。
鼻歌ひとつとっても、臍下丹田[そんな名前の臓器はないが]から声を響かせるようにすれば二つとはない歌い心地になるであろう。(2025年3月21日記/22日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(35)あるいは〈庭〉をめぐる身体��
「植物はつくりこまれた庭から逃れて、ただ花を咲かせるのに適した地面
だけを待ち望んでいる。あとは嵐が、動物が、機械が、種子をできる限り
遠くへと運んでいく。
自然はこうして、とりなしてくれるすべての媒介者を利用する。そして
この組み合わせのゲームのなかで、人間という媒介者は最良の切り札なの
だ。それなのに人間はそのことを知らずにいる。新しい庭は人間なしでつ
くられるのか?」
(ジル・クレマン山内朋樹訳『動いて
いる庭』みすず書房、2021年1月第4刷刊、6頁)
身体感覚という手応えが「肉体」を「ある」ものとして、その存在を疑わなくても少しづつ身体を基準にして空間を広げて確かなものにしてきている。そこで身近にある過去と未来が「時間」を基準にして身体を探るようにすればどうなるか。日常生活を稽古そのもののように生きればいいのではないか。
日々浴びている太陽の光は8分ほど前のものだ。夜中に見上げる星も何億光年も前の光ということになる。こちらから見たり、あちらから見たり、そういう関係性として物事を見ればなぜか心落ち着くようだ。
過去に起こった事が自分に向かってくるのを未来形の自分が見ている事になる。こんな状況でいったい何ができるのか。出来事に対して反射するのではなく、まず対応するしかないのではないか。
時間に対してどう考えるかという事になれば、身体は考えによって変わる。考え方を変える事で動きが変わらなければ、その考えが間違っているか、もしくは考えを受け入れていないかのどちらかになる。受け入れ方を確かめる方法が身体感覚を探る事になる。
買い物にしてもその日の天候によって自転車にしたり歩いたりが練習というより、日々の稽古になる。歳をとるほどに行動範囲がせばまるからか、歩けることや乗りまわすことが人間の標準装備の働きになる。かって練習したことが新しい稽古を生みだす。何かをするためではなく、立てるから何かができる。歩けるからどこかへ行ける。切れるものもあれば繋がるものもある。
根本の動きや働きを知らなくとも、初源に遡ることなく現代は欲望が叶ったり、他人が作ったものが手に入る。インターネットがあるから気持ちが繋がっていなくても用事は伝わり、便利かもしれないが、素っ気ない。
誰しも何かを大切にしたい気持ちがあるだろう。ところが、大切にできそうなものが何なのかなかなかわからない。ネット上だけでなく地べたの人間関係も、親子や親戚をはじめ、地域や職域にいたるまで常になんらかの問題を抱え込まざるを得ない。
今頃になって迂闊と言おうか間抜けと言おうか、日々出入りしている離れの二階の部屋の作り付けの本棚の片隅からはち切れそうに破れかけた茶封筒を見つけた。どうやら昨年元旦の能登半島地震で書棚の隙間から転がり出たものらしい。日焼けした葉書や封筒の束の中から結婚する前の妻からの便りが何通も見つかり、旧姓で会いに来てくれたような、なんとも言えない愛おしさが‥‥‥。
結婚当初だったと思うが、二人で話し合ってそれまでにやりとりした手紙などは全て処分したとばかり信じこんでいたからだ。
消えかかった消印によれば当時住んでいた埴生の民家で受け取ったものばかりだったが、6年ほどつきあって一緒に暮らし始める前の2年あまりの筆跡を、結婚生活が終わってから思いがけずたどれることになるなんて。
もらった手紙のすべてかどうかはまったく分からないし、もちろん、自分から書いて出した便りは一通も見当たらなかった。
先立たれて三年になる月日の後を追うように懐かしくもあり、この頃は夢にまで出てくるようになっていたところへ、五十数年前のペン先が濃淡をとどめる縦書きや横書きの便箋が何ものにもかえがたい現れ方をしたものだ。
一気読みするのがもったいなくて、午前か午後のおりおりに一つか二つ、古びた封筒から取り出して読むようにしているのだが、半世紀を超える隔たりを感じさせない〈身体〉が呼吸していた往時の家庭の事情が絡むやりとりと、その後の時の経過が物語化を拒絶するように迫ってきて言いようのない深みにとらわれそうになる。
この前の手紙、嬉しかったけど、恵吉さんにはいつも毅然としていて欲しいと思います。ジャズが好きなのも良いな、と思っていますし(私は好きなものを取り上げて言えませんから)、野心がないのも最高に良いと思っています。男は野心を持っていると言いますが、私にはわからないし、怖い感じがします。あきらめていたのにやっと野心のない人に会えたといった気持ちです。
(柞山智香恵@[手紙]昭和47年2月22日午前0時半)
暑かった一昨年の夏、亡くなる二十日ほど前の妻の手帳に「暑いだけで2人で不調」とだけ書かれていたのを葬儀を済ませてから読んだ時なども、かけがえのない日付のある言葉が胸に迫ってくるようだった。
こんな時こそ、身体を大切に気にしながら、行きつ戻りつ入り込むように見るべきだ。そこに〈身体〉を存在させて一緒に考えればいい。思うという身体感覚は何を見つけるか、神経か何か紐のような繋げるもの。
手足やからだに「ヒモトレ」をしたり、足指や裏で「バランスボード」に乗ったりして身体を出入りする何かを大切にしたい。
できないのはまだいいとして、やろうとしないーー思いもしないのが問題だ。内部に入り込むように手足を動かし、差し入れ介入する。
運動やスポーツはすべて止めてしまったというか、心臓の手術をした老体ではもう無理はできない。まぁ仕方がないことだが、ないところにイメージが作れるかどうか、そこに身体があれば現物よりもイメージがもてるかどうか、勝手に内臓に当たりをつけて稽古するしかない。
想像しながらあれこれ動かすようにしてみる。そうするには常識はずれの動きしかない。ツイッター改めXで見かける誰それの指摘などもアイデアやヒントにしたり、とにかく独りでやってみるしかない。一ヶ月に一度は近所の内科医に診てもらっているが、たまにネットで聞いたりしている「端くれ内科医」のラジオも面白い。
このところ、本当に色々なことがあってなかなか このラジオを聴く機会が作れませんでしたが、今夜 随分 久しぶりに聴かせていただき、「端くれ先生は 、本当に誠実な方だな」と実感しました。しかも喋り方が「いかにも誠実な人物」という感じがしないところが、いい味が出ていると思います。つまり「端くれ 先生 」ご自身ごく普通の人間の、ごく普通の感覚で、今回のパンデミック対策のおかしさを感じられたところが本当に貴重だと思います。また機会があったらお話ししたいと思います。私は今年大きな気づきがありましたので、そのことと感染対策の問題などについても、また書いてみたいと思います。(甲野善紀@ツイッター改めX2025年3月13日)
やっぱり、端くれラジオ、面白い。と言うか科学や医学に関わる人間には特別なこととしてでなく“最低ライン”内科医の端くれ先生のような知見を持って論と理の展開をして欲しいものである。このような知見が医学、科学の世界で普通となり一般化しないと先はないだろう。
兎に角「端くれラジオ」はどんなYouTubeやテレビ、映画より有意義な1時間半かと思います。(光岡英稔@ツイッター改めX2025年3月15日)
膝を伸ばさず曲げすぎることなく下半身を臓器で吊り上げるようにして、身体を浮かせるようにすれば、足裏の圧力や踏ん張りも消える。心臓は怯えたり緊張もするが、肝臓の解毒作用が身体をリラックスさせる。心臓にはない再生能力が肝臓にはあり、体幹を落ち着かせる。
体幹を取り押さえられても、手足の指先は動く所を探し出せる。メモなど縦書きにすれば左へと自由な快適さが楽しめよう。前後左右上下が感得され、気張らず左へと動けて右からは力と信頼が得られる。
田畑の手伝いや獅子舞の踊り子をやっていた頃だが、裸足や足袋と草鞋で地を踏む感触が忘れられない。
一方前庭に控えているくらいの身分の者は、当然にそんなものは許されていなかった。すなわち独り田に働く人たちだけでなく、一般に足袋は仕事着の品目に算えられなかったのである。察するに寒い冷たいが最初の理由でなく、やはりまた木綿の物珍しさ、あるいは肌にふっくりと迫る嬉しさともいうべきものが、偶然にこれをわれわれに結びつけ、後には習いとなって、ないことを不幸と感ぜしめるまでになったのであろう。出井盛之君の「足袋の話」は、われわれにこの問題を考えさせた最初の本であるが、あれから以後も工場は東西に競い起こり、機械と工程とは次々に改良を加えられ、統計に出てくる年産額のすばらしさは、ほとんど人間に足が幾つあったかを、もう一度考えさせるくらいである。
(柳田國男「八 足袋と下駄」/「第一章 眼に映ずる世相」/『明治大正史 世相篇(上)』講談社学術文庫、昭和51年6月刊、48頁)
大人になるように老いるか子どもになるように老いるか、いずれにしろ自然な身体への信頼をなくさないように自信に溢れていればいい。
心臓に気づいて元気になり、肝臓を知って落ち着き、肺の動かし方がわかれば過呼吸にならない。努力などせずとも安心が身体にそなわり、ひとそれぞれ持って生まれた力が溢れよう。
老いを重ねるごとに諸々の問題に向き合った時、そこを練習や稽古の場にできるかどうかが、その人の人生を左右することになる。といってもなかなか出来難いことだ。つい息苦しくなったり、にわかに激痛が走ったり、家族や交友関係に不幸があれば平穏な暮らしはできなくなり、日常生活も稽古どころじゃなくなる。大丈夫かどうか時間はかかるし、人生は長いようで短い。
身体の〈自然〉に現れる変化にも怖くなる。明治生まれの祖父のように、自己観察と養生を心がけてお灸を据えたりするぐらいで医療にたよらなければ、それに越したことはないだろう。
今だと医療や治療、治癒とか施術が助けてくれよう。自分で身体を治そうとする人は少ないかもしれない。どんな助けを受けたとしても、その後は自分で自分を助けるようにしないといけなくなる。自分の身体を探り、自分なりの過ごし方を求めなければならない。
3月になって庭の空気を入れ替えたみたいに雪もすっかり溶けたし、そろそろ庭木の雪吊り外しにやってくる職人に渡す菓子を買い物ついでに用意しておいたら、その三日後にやってきた。職場が勝手知ったる他人の庭とばかりに、数人で半日近く掛かった雪吊り作業も外すとなると小一時間ほどで片付けて帰っていった。
五十数年前にご近所で紹介してもらった庭師が引退されたところで、職場の伝で新しく開業された庭師に引き継いでもらっていたのだが病没され、残った職人と事務を引き継がれた奥方のおかげで我が家の庭が保たれてきた。そこには徒然なるままに草むしりをしていた母や妻の姿はもうない。
数少ない樹木の陰で目に留まらないような埋もれかけた小さな庭石と崩れかけた石灯籠しかなく、形などあってないようなこじんまりした眺めになってしまった。
五十数年前に妻と二人で植栽を位置づけたのだが、移植する前に祖父が手入れしていた埴生の庭の面影などどこにもない。例年の庭師の剪定を経てきた樹木や植え込みそれぞれの姿形が時の隔たりを感じさせる。そこには庭とはかくあるべきだというようなイメージは微塵もないような気がする。
高屋敷界隈を見渡しても古くからある前庭は別として、住宅は随分増えたようだが庭らしき眺めはまったくといっていいほど見かけない。車庫やカーポート以外の空いた場所は砂利かコンクリートで敷き詰められ、庭など入り込む隙間もなといった風情だ。廃屋同然の朽ちかけた庭の名残があったり、雑草が繁茂した耕作放棄地みたいな場所に出会ったりするだけでまだよしとすべきだろうか。
庭師の手を入れて維持するとなればどんなに小さな規模でも年間かなりの出費を要することになり、そんな余裕は持ち合わせていなというのが現状だろう。暮らし向きに身近な〈自然〉の肌触りが薄らいできているともいえよう。これからの子どもにとってはちっともいいことではない。富山市内にも幾つかある「名園」の観光で代用できるようなものではないのだから。
お天気がいいから庭で朝陽を浴びて‥‥‥、などなど、そこから里山や田畑へ地続きであったりすれば、自然な子どもの頃の「働き」が、宇宙や生き物や気象の学びに連なったりするだけでなく、動植物に対する愛おしさまでも育むことになる。充分な睡眠と深く穏やかな呼吸と、そして絶えざる自然との関係の見直しが生きる糧に。
庭に立つことも多かった実家の祖母や祖父にとって、日々の「南無阿弥陀仏」は不確かな毎日を送る呟きのようなものではなかったろうか。
庭のある暮らしに恵まれた老人は呆けたり、徘徊などしないだろう。もし徘徊老人になりかかったとしても帰巣本能が働いて帰ってくるに違いない。
「家」族から国「家」まで、ここしばらく、人類は「家」のことばかりを考えすぎてきたのではないか。しかし人間は、「家」だけで暮らしていくのではない。「家庭」という言葉が示すように、そこには「庭」があるのだ。家という関係の絶対性の外部がその暮らしの場に設けられていることが、人間には必要なのではないか。
そして「庭」とは(私を企業のサービスにすぎないSNSプラットフォームのように)、私的な場である。しかしその場は半分だけ、公的なものに開かれている。それぞれの「家」の内部と外部の接点としての外庭があり、そして家事や農作業、あるいは集団礼拝や沐浴の場としての中庭がある。
「家」の内部で承認の交換を反復するだけでは見えないもの、触れられないものが「庭」という事物と事物の自律的なコミュニケーションが生態系をなす場には渦巻いている。事物そのものへの、問題そのものへのコミュニケーションを取り戻すために、いま、私たちは「庭」を再構築しなければいけないのだ。プラットフォームを「庭」に変えていくことが必要なのだ。
そしてサイバースペースはもちろんのこと、今日においては実空間すらも「庭」としての機能はあらゆる場所から後退している。だからこそ、このプラットフォーム化した社会をどう「庭」に変えていくのか。それが本書のもうひとつの主題だ。
(宇野常寛/§10プラットフォームから「庭」へ」/「#1プラットフォームから「庭」へ」/『庭の話』(講談社、2024年1月刊、60頁)
ほぼ月一で通っているクリニックには、通院している人たちも見落としそうな坪庭がある。ここ2年の間で長期入院することになった二つの病院のうち、県立の総合病院に庭らしきものはなく、個人病院には石庭もどきの空間が設えられていた。リハビリを兼ねて院内廊下を行ったり来たりするのと病院の外周を散歩できるのとでは患者の回復にも雲泥の差が生じるのではないか。
1980年代初頭に異動になった新設の医科薬科大学の附属図書館に庭らしきものはなく、呉羽山の丘陵地を整備したキャンパス内に古墳や植物[薬草]園があったが、散策するにはいずれも場所柄がよくないようだった。
夜間の時間外開館業務を担当した際に、閉館時に流す契約警備会社提供の音源がダメになり、手持ちのレコードをダビング[私的利用の範囲を逸脱]して、ビル・エバンスのソロによる名演「ピース・ピース」[Bill Evans Trio/Everybody Digs Bill Ebans(1958)]に変えてみたことがあった。それまで退館時に挨拶などしたことがなかった利用者から、ありがとうございましたとか、おつかれさまとか、中にはいい音楽ですね‥‥‥?、などと尋ねられたりするようになった。
最後の勤務先になった大学図書館の増築時に、旧館と新館の接続場所に中庭が設けられた。昼間の採光目的だったとはいいながら夜間照明が灯っただけのささやかな眺めに、システム更新時の残業に次ぐ残業でささくれだちそうな気持ちもなだめられるようだった。
晴れた午後に庭いじりをしたり、草を刈ったりしていると通りすがりに声をかけられたり、立ち話になったりすることがある。いずれも見知らぬ近所の住人だと思うが、挨拶していく小・中学生の中には入り込んでくる女の子たちもいた。変り種としては、地主と間違えて土地を売ってくれとか、主木の赤松を数十万円で売ってくれなどとの声がけもあったりした。今とは違ってもっと景気が良かった頃の話に過ぎないが。
埴生に住んでいた頃は座敷を開け放って縁側越しに、そして高屋敷に移り住んだ四畳半の仏間の障子を開けて、刻みタバコをくゆらせながら自ら手入れしてきた庭木や植え込みを眺めていた祖父の背中を透かすように、おそらく去来していたであろう庭の眺めの移り変わりが偲ばれることがある。自然に対して半分開かれ半分閉じたような結び目みたいな場ではいろんなことが偶発するようだ。
先ごろテレビの録画で見た映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督作品、2023年)が山奥の町[集落]内で暮らす“便利屋”の「巧」の視点と、鹿の通り道でもある区画にグランピング施設を作ろうとして都会からやってきた芸能事務所の「高橋」や「黛」の視点が行き交い、それぞれが「庭番」のような効果を描き出していた。「巧」の娘の「花」が覗き見する「説明会」は水質や自然の保全をめぐって物別れに終わる。
長回しされる薪割りや水汲みのシーンや、東京から高速道路を走る車内の二人の会話など、そしてそれらをゆったりつつみこむように視角を変えながら映しだされる森や林や杣道で何かが起こりそうな予感、ーー物事が自然へと循環する〈中庭化〉が成立しそうなところで神憑り的な事態が出現する。
映像のいたるところに“カメラ目線”が働いていて、なおかつ俯瞰する“自然の目線”で見られているとでも言ったらいいのだろうか。あっち側とこっち側から眺められる「中庭」で起こった「出来事」のような映画だ。野鳥の鳴声や森のざわめきなども控え目なサウンドトラックに割って入る鹿狩りの銃声。
森の中の帰り道で「花」が神隠しにあったようにいなくなる。映画の始まりで群生する樹々が日差しを分け合う樹冠の隙間から空を見上げていたフラクタル映像のようなバランスを崩したのはいったい何なのだろう。
手負いの鹿に遭遇した事故なのか?、ようやく目前にしたところで一緒に探してくれている「高橋」の背後からいきなり「巧」が襲いかかって絞め技[裸絞めorリアネイッキッドチョーク?]で気絶させたところで映画は終わる。
おそらく祖父も母もーー口にはしなかったがーー高屋敷の家構えも庭も埴生のそれらより小さくなったと感じていたかもしれない。
僕ら夫婦は結婚を機に勤務先の官舎住まいを余儀なくされることもなく、家族合意の上で一つ屋根の下に住めるようになっただけで十分だった。狭い庭を後にサイクリングでひとっ走りすれば、混み合う松川べりを避けて立山連峰を眺めながら常西合口用水の殿様林で花見をしたり、常願寺川の河川敷公園を抜けて富山湾に沈む夕陽を眺めることもできた。
河口から西へ蜃気楼サイクリングロードも何度か走ったが一度も蜃気楼を見かけたことがないままに終わりそう。秋になると常願寺川上流の河川敷の遊歩道にも出かけていたが、熊が出没したりするようになってからは行かなくなった。(2025年3月31日記/4月1日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(36)あるいは〈里山〉を抜けて��
私はお小遣いをもらっていなかったので、見ることができなかっ
た。うちでは紙芝居は禁じられていたのである。それでもたまには
門のかげから、こっそりとのぞいた。おじさんが語りをつづけなが
ら、ちらと私の顔を見た。
火事で燃えている家。真っ赤な炎。
燃える家からかろうじて救い出された若い女。
病院のベッドに寝かされている。顔にぐるぐる巻かれた白い包帯。
その間からわずかにのぞく眼と鼻。
やがて傷が治って包帯がとかれる。
と、その下から‥‥‥。
私は知らんふりをして家に駈けもどった。
その晩、夢で魘されてはげしく泣いた。真っ赤な波のような、炎
のようなものが覆いかぶさるように繰返し襲いかかる。逃げようと
しても、金しばりにあったように体が動かない。母に起こされてか
らもまだ泣いていた。
「胸のうえに手を置いて寝るからよ」と母が言った。しかし母に
� は全部わかっているような気がした。
同じ夢を大きくなってからもよく見た。
(山田 稔『門司の少年時代』ぽかん編集室、2019年10月刊、
60〜61頁)
いつの間にか晴れて風のない休日など自転車を走らせてあちこち出かけるのが庭先の延長みたいな眺めの探索になってしまった。ほとんどが「公園」と名のつくような場所ではなかったのだが。
近くでは街中を抜けて富山駅北の富岩運河環水公園を散策したりした。ときおり噴水の縁にカモメが群れたりしていたのが珍しかった。カモメといえば映画『忍ぶ川』(熊井啓監督作品、東宝製作、1972年)の乱舞するショットが印象的だ。
自転車を降りて周回の途中でスパークリングワインを開栓して弁当のお供にするのが習いみたいになっていた。おにぎりと漬物が旨いのだ。若木だった桜なども見事な眺めになり、当初自由に乗れた遊覧船クルーズも今じゃネットの予約制になったようだ。
冬場のスキー・シーズンは立山山麓スキー場へ足腰がおぼつかなくなるまで通った。富山県の西の端っこから県中央部へ移住したおかげで、電車とバス乗り継げば1時間ちょっとで出かけられるようになったのが大きかった。娘は膝の障害で滑り止めになったが、夫婦ともども相前後して始めたバドミントン同様に生涯スポーツとなった。
志賀高原や蔵王に比べて規模や雪質は劣るかもしれないが、晴れ渡った日中の立山連峰を背に富山湾めがけて滑り降りるパノラマが、天をめがけーーというより宇宙に向かって開いた〈庭〉のようなのだ。澄んだ空気の日など水深の深い湾を囲むように伸びる能登半島の先端まで一望できた。
シーズンの滑り納めとか、長距離サイクリングの後など、ご近所馴染みの寿司屋に立ち寄り、母の夕食代わりのお土産を握ってもらって帰ることも多かった。営業中の大旦那にスキー用具ともども食後の二人を出前みたいに車で自宅まで送りとどけてもらったこともあった。
それ[「土を踏む機会の乏しくなることを厭う」こと=引用者注]にはまた草木の成長ということに、経済以上の深い関心を持っていたことも考えられる。わずか数尺の坪の内を囲って、そこに植えようとした樹の種類も、またその形さえも定まっていた。最初はこの垂れた枝を梯として、天より降り来る神を祭ろうとしたのが起こりであったと私は思っているが、そういう信仰行事は絶えて後々まで、庭前に緑の松の伸び栄えていくことを、家の瑞相と結びつけて考える習わしはなお残り、これによって心を慰めていたものは多数であった。町の長屋の窮屈なる生活が始まって、しだいに鉢植えの盛んになったのもそのためであった。今日はその技術も大いに進んで、また一つのわが邦の特長に算えられるようになったが、枝ぶりの好みやこれをながめている態度に、なお全国都鄙を一貫した庭園芸術の流れが窺われる。すなわちこれもまたわれわれの住屋に、とうてい欠くべからざる条件の一つであったのである。
(柳田國男「八 庭園芸術の発生」/「第三章 家と住み心地」/『明治大正史 世相篇(上)』講談社学術文庫、昭和51年6月刊、132頁)
春や秋に夫婦で訪れた金沢の兼六園以外で最初に見た庭園といえば、独身の頃の一人旅で立ち寄った高松の栗林公園だったろうか。とにかくその広さに驚いたが栗の木はほとんど覚えがない。
筑波での図書館職員の長期研修の仲間と筑波山に登ったり水戸の偕楽園を散策したりした。その後の研修同期の集いが岡山であったときに後楽園を眺めることができた。
いずれも江戸期の大名による造園だが、庭師によって今日まで守り伝えられた自然に対する手入れの違いがそれぞれの景観の趣になっているとでも言えばいいのだろうか。
園内に建てられた屋敷内からだけでなく、園内を回遊しても眺めいいように季節と人との関わりがバランスよく切り取られた〈自然〉が作庭の要と言っていいように思うが、春夏秋冬季節を違えて足を運んでみないとほんとうのところまではわからない。
風光明媚な眺めも悪くはないが、こじんまりした庭の植物だけでなく、まるでサーカスみたいな蜘蛛の巣を張る生態をはじめ鳥の鳴き声や縄張り争いなど、幼少期から庭で万象の一端に触れたりしていると、やがて野山での様々な自然観察にまで誘いだされたりする。庭に飛来する鳥だけでなく、林や森で見かける野鳥が断然面白くなる。
貧乏でゴム鉄砲を自作するしかなかったのを見かねてか、埴生村の裕福な家庭の子が空気銃やポンプ式の鉄砲を貸してくれたことがある。人里を避けて山の中を持ち歩いたりしたが、樹の枝にとまる野鳥や出会ったウサギなどをめがけて撃ったりしたことは一度もなかった。だから魚釣りのように山の獲物を祖父に調理してもらうなどもってのほかだった。
庭に迷い込んだ山鳥が縁側のガラス戸にぶつかって動かなくったときは、祖父は窮鳥から散弾を取り除いて焼き鳥にして食べさせてくれた。
親鳥からはぐれて迷子になった雉か山鳥の雛鳥を見つけ、縁側で網かごにいてれ餌付けしていたのを近所の野良猫に殺られたときはよっぽど銃で撃ってやろうかと思った。
借りた銃で恰好の的を見つけて命中させる息づかいを学んだというかーーゆっくり息を吐ききった隙に引き金を絞るように撃つようにしてだんだん遠くの的を狙うのが面白かった。
昼間の杜で微動だにしない梟や、不意に梢から大滑空するむささび。林の奥の蝙蝠が何匹もぶら下がった洞窟の不気味さ。山奥の貯水池の井守や蜻蛉など。漬物石みたいな大きさの蝦蟇やかもしかとの鉢合わせ。
先の見えない森の中で自然を呼吸するリズム感に身体を委ねたような、底の知れない孤立感に目覚めたとでも言ったらいいのだろうか。広がりの割に水深が深い青木湖[長野県大町市]でボートを漕いだ時もそんな感じがした。庭を出て里山を通って人里の秩序を抜け出したような自然との距離感は人の手が入りすぎた大庭園では味わえないだろう。
放棄された土地は〈放浪する〉植物が好む土地であり、モデルなしでデッサンを描くための新しいページである。そこでは新しいことが起こるかもしれないし、エキゾティシズムも生まれそうだ。
〈荒れ地〉はいつの時代にもあった。歴史的に見れば荒れ地とは、人間の力が自然の前に屈したことを示すものだった。けれども違う見かたをしてみればどうだろう? 荒れ地とは、わたしたちが必要としている新しいぺージなのではないだろうか?
もっとも辺鄙な国、ときにもっとも貧しい国でまず見せられるのは、最新の高層ビルだろう。それは土地の征服を意味している。またフランスのような国では、自治体が荒れ地を抱えると市長は不安になる。彼は荒れ地を恥だと思っているのだ。これら二つの態度は、同じひとつの意味に帰着する。つまり、人間の力が読みとれなくなると、深刻な敗北とみなされるのだ。すぐ分かるとおり、この発想は創造のあり方を極端に形式化してしまった。なぜなら、人間の優位を表現して読みとれるようにするのに別の方法がなかったからだ。こうした発想が生まれてくるのは、おそらく形ーーすなわち制御された形ーーというものが、とてつもない力を享受しているからだろう。この力は、未知のものが残っていると不快になり、それを警告する。だから揺るぎない構想にもとづいた伝統的庭園は、精神を落ち着かせ、〈ノスタルジー〉を涵養し、疑問を抱かせることがない。
(ジル・クレマン山内朋樹訳『動いている庭』みすず書房、2021年1月第4刷刊、6〜7頁)
昭和の半ばを過ぎて増築した離れの二階の東北向けの窓際に机を置くことにした。周りはほんとんど田んぼだったが庭越しの正面の畔の一角に大きな広葉樹があり、その向こうに鬱蒼とした神社の杜を望めたからだ。いつも机上に用意してある双眼鏡で、近くの枝に飛来する野鳥や、遠くの樹冠を透かして鳥の混群などを眺め飽きることがなかった。あたりはいつも静かだから窓を空かせば賑やかな鳴き声まで聴こえくるようだった。
まことに残念なことだが、とある日に真向かいの大木は切り倒され、そして神社の樹々も間伐されてあたり一帯に家が建て込んでしまった。
いつしか双眼鏡をデジカメに持ち替えたが、ホームランボールを追いかけるカメラマンのように鳥を撮すなんて至難の技だ。思いあまってデジタル録画双眼鏡を退職記念みたいに買ってもらったが、我が家の庭から激減した昆虫の後を追うように、やってくる鳥もまばらになってしまった。雉や山鳥などの大型から姿を消し、ヒヨドリやオナガなどの中型も飛来せず、鶯や四十雀など小粒な鳥たちもめったに見かけなくなった。独り暮らしになって庭に餌を置いたり巣箱なども思い立ったが、どうもそこまでは踏み切れない。「ワイルドライフ」などBSの鳥を撮影したドキュメンタリー番組で我慢するしかないこの頃だ。
こうした実験を通して、コガラの「ディーディー」、シジュウカラの「ヂヂヂヂ」、ヤマガラの「二ーニー」は、すべて「集まれ」という意味になっていることが、やっとわかった。
当時、シジュウカラの「ヂヂヂヂ」を“警戒の声”として紹介している図鑑もあったが、その意味を科学的に確かめた研究は一つもなかった。それが今回、きちんと観察し、実験をしてみることで、本当は「集まれ」という意味だとわかったのだ。「ひょっとしたら世界中で僕だけがシジュウカラたちの言葉を正しく理解できているのかもしれない」と特別な気持ちになった。
(鈴木俊貴『僕には鳥の言葉がわかる』小学館、2025年1月刊、33〜34頁)
軽井沢の鳥が群棲する森の一画を庭の延長のようにフィールドワークの場とし、シジュウカラの観察[や実験]を積み重ねてわかった生態に驚いた。なんと「言葉」を発するだけでなく、をれを組み合わせた「文」を作っていたなんて。
これはすごい発見である! それまでにも、多くの動物学者がベルベットモンキーやミーアキャット、プレーリードッグ、ハンドウイルカなどの鳴き声を調べてきた。しかし、ある鳴き声が内的な感情ではなく、外的な対象物を指示し、聞き手にそのイメージを想起させることを明らかにした例は一つもなかった。僕の研究が、初めてそれを証明したのである。
僕はさっそく論文にまとめ、米国科学アカデミー紀要(PNAS)という学術誌に投稿した。PNASといえば、科学者の憧れの一流学術誌。審査はとても厳しいことで有名だ。本当にインパクトの大きな研究だけが厳選され掲載されるが、僕には自信しかなかった。
(『前掲書』183〜184頁)
シジュウカラに“新しい文”を聞かせて、文法のルールを当てはめて理解できるかどうかを試した方法が傑作というか独創的なのだ。
僕はさっそく鳥語版・ルー[ルー大柴のこと=引用者注]語の作成に取り掛かった。パソコンで音声を編集し、シジュウカラ語の「ピーツピ・ヂヂヂヂ(警戒して・集まれ)」の「ヂヂヂヂ(集まれ)」の部分をコガラ語の「ディーディー(集まれ)」に置き換えたのだ。
� そして完成したのは「ピーツピ・ディーディー」というシジュウカラ語とコガラ語の混合文。自然界にはありえない、シジュウカラにとって全く新しい文である。たとえるなら「ピーツピ・ヂヂヂヂ」が「警戒して・集まれ」だとすると、「ピーツピ・ディーディー」は「警戒して・トゥギャザー」。まさに鳥語版・ルー語である。
大切なのは、シジュウカラがこの新しい文を、“文法のルールに当てはめて”理解できるかどうかである。もしシジュウカラに人間と同じように柔軟な文法能力があるのであれば、文法ルールを当てはめてルー語も理解できるだろう。そして、語順が逆だと正しく理解できなくなるはずだ。
(『前掲書』205〜206頁)
住み込んだ庭みたいな森の中で二カ月間、考えられる限りの「反証」を考慮した実験を繰り返して、ついにシジュウカラが「警戒→集合」という文法のルールを当てはめて、シジュウカラ語とコガラ語の混合文まで理解できることが突き止められたのだ。
観察者二人を加えた軽井沢の森でのコラボレーションだが、なんだか研究者と鳥とがジャムセッション繰り広げたなんて‥‥‥、まるで“宮沢賢治童話”の一場面のようだ。
人が何事[物]かを介して自然と交感できる場が湧き立つ、ーーそんなプラットフォームの創出が〈庭〉の大きな魅力になっているのではないか。音楽で言えば“スイング”のように。
ジャズピアニストのバリー・ハリスが[ユーチューブの一幕で]レクチャーしていたのだが、ドラムスやベースに頼ることなくバンドの一人ひとりがスイングしないことにははじまらない。
一人ひとりがスイングできて、それが仲間と一緒になれば自然に一体になる。スイングは一人でやるもので、これがあらゆる生き方や社会生活の要にもなろう。
現状の世の中を眺めれば、各国が自立して大衆の利益[国益]をどこまで守れるか、そこが問われる時代にさしかかっている。日本はアメリカに頼らない社会形態、社会構造を模索し構築する契機を逃してはならない。個人個人もそこから取り組むしかあるまい。今までのやり方では、もう逃げ場ががないのだから、日本古来の伝統や文化を活かしながらも、これまでのやり方ではない新たな試みにとりくむべきではないか。
春になると新しい音楽が聴きたくなったりするが、新人らしきブルースシンガーMuirean Bradleyの『I Kept These Old Blues(Remastered)』 (Decca Records/Tompkins Square Release 2025 )やMaya Delilahの『The Long Way Round』(Blue Note Records 2024)に聴き入った。両者ともにうら若き女性ながら、前者の古いブルースの仕込み具合や、後者のデレク・トラックスの流れを汲むギタープレイが聴きどころだ。
ジャズベーシストのデイヴ・ホランドなどが加わったアヌアル・ブラヒム[チュニジア出身のウード奏者]のアルバム・タイトル「After The Last Sky」が気になった。文字通り“最後の空”とは何を意味しているのだろうか? パレスチナの亡命詩人マフムード・ダルウィーシュの一節らしいが、AI チャットに訊いてみたら、《終わりの後に訪れる新しい始まり》や《大きな変化や破壊的な出来事を乗り越えた後の世界》とのことだった。
ロシアが侵攻し続けるウクライナや、イスラエルが大虐殺をくりかえすガザや、遣り手商売人トランプ復活のアメリカや、そして石破内閣の日本の空の下で、時代に向き合う場としての《庭》や《身体》はどのように〈拡張〉されるだろうか。
話す相手もいない独り住いになってさぞ物寂しいかというと、より身体の聲が聞こえるようになったとでもいえばいいだろうか。暖房した部屋でまだ冷たい布団に入ったりしても、どうやら血海や足三里が活き活きとしてくるのか、ほどなく両脚の内と外から腰部へ暖かさが這い上がってくるようだ。
映画『忍ぶ川』の同衾の場面で哲朗が志乃に冬場は裸で寝るのが暖かいからと誘うのも身体的に理にかなった会話になっている。
光岡 これは光岡武学でいうところの「三観の法 うつし観、かえり観、てらし観」と読んでいる技法と術なんですが、中井先生、アキレス腱固めをかけてもらってもいいですか。
中井 これでいいでずか? (実演する)
光岡 ああ、なるほど。こういうわけですね。その時にこの形でいいんで、ちょっと目を閉じてもらって。極めているのは私の右足ですけど、中井先生自身の足のここに感覚をすっと集注してもらって。はい、そうです。
中井 なるほど。この感覚か。なるほどなるほど。不思議ですよね、うん。
光岡 わかりやすい範囲で話すと、言葉を通じて頭と頭が対話するように、身体と身体もつねに身体語を使ってコミュニケーションを取っているわけです。
中井 はい。
光岡 右足のアキレス腱語というものがあるとします。右足のアキレス腱しか持っていない言語があり、左のアキレス腱とは真逆の言語なんです。物理的なレベルでも腱の付き方も全部真逆ですから。私の右足のアキレス腱語を一番理解できるのは、中井先生の右足のアキレス腱ですよね。同じアキレス腱語を喋るもの同士じゃないと、そこでのコミュニケーションが取れないですよね。
さっき中井先生がパッとアキレス腱固めをかけられた瞬間、確かに集注がそこにあるんですよ。だからもうされてることをあらためてなぞってみただけなんですけど。一流の選手になってくると、こういう潜在的に行われていることが無意識にできるようにならないと、相手も一流であれば勝つことができないのだと思います。
中井 意識したことなかったです。
光岡 身体感覚や感覚経験として、無意識でないと技がかからないことがわかっているんですよ。攻防中にやることを意識して考えすぎると後れを取るか、相手に読まれて技がかからなくなります。これは古今を問わず存在する問題です。
古流の柔術は、そういう無意識や潜在意識の領域も技術論として取り組めるような体系を持っていたのですが、これが現近代になるにつれて失伝していきます。正確には、現近代に適応するために古典の教えを理解するための身体観、感性、知性感を捨て、犠牲にし、現近代的な感性を獲得してきたわけです。
中井 そのような発見は先生自分で見つけてきたんですか。
光岡 そうですね。
中井 類する研究とかはあったんですか?
光岡 伝書を見て、その文脈をちゃんと捉えて、その微々たるところだけでも技や術として具現化できてくると、「そういうことなんだな」という納得しかないです。
中井 なるほど!
光岡 ツボや経路を押さえるとして、捉える側が経験的に体感覚や体観でそれらを理解しているという前提があるわけですよね。関節技もそうで、どの境目のポイントを取るかが勝負の分かれ目ですよね。そのポイントを知らない人の技がかかることはないです。
中井 確かにそうです。
光岡 では、そのポイントを自分に照らしてみて、「あなたはどこまで深く理解できていますか? 知っていますか?」ということなんですよね。その自知体認の深さが結果として技をかけた時や動きを行った時の技の作用、効き方、深度になってくる。
中井 そりゃそうですよね。
光岡 理屈でいうとなんてことはなくて、そんな感じなんですよ。だからこそ何かを「知る」「理解する」というのが認識レベルなのか、それとも身体感覚レベルなのか、あるいはさらに深く感覚すら及ばない領域のことなのかということが問題になります。
中井先生はわかるとおもうんですけど、物理的にも関節技や極め技のポイントはミリ単位ですよね。ピンポイントでしかも、角度によって作用が全然変わってくるわけですよね。古の柔術ではその辺りのことが研究されていたと思うんですよ。伝書などを見る限り。この古の時代のひとつの特徴を私は「鏡のない時代」と呼んでいるんですが、この話を次にしようかと思います。
中井 お願いします。
(光岡英稔×中井祐樹『術と道:身体で知る武の思想』新泉社、2025年3月刊、144〜147頁)
単なる技術論や動作法じゃなくて、身体語を使ってコミュニケーションをとっている稽古[生き方]の世界が奥深い。餌や危険を察知して鳥が会話するように、古武術的には身体も生き死にをめぐって会話しているということだ。(2025年4月11日記/14日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(37)あるいは〈拡張〉する境界から��
ーー 今の若者にとって六〇年代の音楽は昔の音楽ではなく、まさに
同時代の音楽の一部として感じるわでです。製作感覚そのものが新しい
音楽の創造というより、時代的・地理的に多様な音楽を引用してゆくと
いうスタンスになっていますし、その方が強いオリジナリティーよりも
聴き手の時代感覚に合っているんですね。
オウムに対して「歴史感覚の欠如」と批判する人もいますが、今や八
〇年代に流行ったレトロ感覚も吹っ飛んで、歴史的地理的遠近感がさら
に希薄になっているんです。その意味で、情報社会のあらゆるイメージ
を網羅しているオウムの一見デタラメにすら見える引用的世界は、むし
ろすぐれて今日的ですし、過換気状態にある若者が惹かれてしまうのは
無理もありません。
(片山洋次郎『オウムと身体』)
リハビリのおかげでかなり体力も戻ってきたのに、すっかり出不精になってしまったようだ。買い物や図書館だけで未だに花見にも行っていない。長かった入院中は元気になったら運動してみたいなどと思うようなこともあったが、いざ退院してみたらバドミントンラケットやスキー�など処分してしまった。入院・手術前は日常化していたストレッチなども再開していない。万年床も必要なくなり、手術で真っ二つにされた胸骨もくっついたというのに、生涯スポーツも一旦やめたとなると二度とやらなくなるようだ。それでもヒモトレだけは肌身離さずといった具合だ。
虚弱児だったゆえに取っ組み合いの喧嘩はほとんど記憶にないが、小学校の裁縫室の畳の上でふざけ半分の相撲の真似事を愉しんだ。非力でよく投げられたから受身だけは身についたような気がする。同じように小柄なK谷君がいつも投げられ役になってくれたのに技はさっぱりだったが、冬は体が暖まるまでやったかな。気の合うものどうしがせめぎ合う時の加減を按配する稽古になったような気がするが、どうだろう。
小学生の間の喧嘩は先手必勝というか、履いていた下駄を脱いで鼻緒を両手に絡めて殴ったら、素早く逃げることだ。不意を突かれた相手は二度と仕掛けてはこなかった。中学生になったら殴られても抵抗しないようになった。というか勝とうが負けようが喧嘩[戦争]などするもんじゃない。今必要なのは戦後を生きる身体的なわだかまりがなくなるような論争じゃないのか。日本の現状はもとより、ウクライナやガザ地区やミャンマーの大衆の惨状にまで届くような言葉で。
団塊世代・全共闘世代に支持されていた方と聞いても、思想的なところは、現在とは時代背景が全く違うので、現在に生きる私の視点では、既に本の中の物語にしか聞こえず、そこは軽く流す。
思想は別にしても、左翼系といっても、現在の薄っぺらい民主党やらとは似ても似つかない、視点と思考の多角さに、昔の日本人の方が、今の奴らよりよほど芯があり視野が広かったコトを、改めて実感する。
ただ面白いメインはそこではなくて、全共闘時代から80年代バブル時代までの、思想の群雄割拠時代の、お互い批判・・といいますか、悪口を言いい・・・、エスプリをたっぷり効かせて、言論でさらりと相手を罵倒する技レベルの高さ。競技ディベートの論破(ひろゆきの屁理屈の事ではなく)とも違う、合理的ではない自分の全存在の肯定をかけて、論理的に論敵を否定する迫力が、なんとも人間味があって、私は好きです。
私はもうすっかり気に入って吉本隆明を「他人への論理的な罵詈雑言」の師匠として、お勉強をさせていただく事にしました。
平成育ちの腐ったクズは、すぐに誹謗中傷だのパワハラだの被害者ぶりたがるけれど、根拠のある「評論・議論」は、憲法第21条で保障されている表現の自由というものだ。
先日鬼籍に入られた野中郁次郎の失敗の本質で引用されていた話では、(私は和洋問わず読書家なのです)「明治維新前における日本の教育目標は、武士としての人間完成にあったが、明治以降はいたずらに欧米模倣に急なるあまり、
人間としての鍛錬を忘れて技術の習得を持って唯一の目標とし」劣化したそうだけれど、確かになるほど。
そして明治以前教育世代がいなくなり、吉本隆明氏をあがめた団塊世代が挫折して思考停止猛烈サラリーマンとなり、今やその子供や孫の昭和で思考停止第二世代第三世代となると、ふんわり人間の手ごたえも失い、人との繋がりや連帯さえも失ったゾンビが、「みんな一緒」同調圧力だけを頼りに、何をやっても、人口激増経済成長の昭和のまま思考停止のやる事なす事、人口激減経済縮小落ちぶれゆく現在の日本では「間違い」だらけ。
若い意識高い系もうっとおしいけれど、より困るのが、
政治家
役人
新聞屋・マスコミ
大学教授
他あらゆる識者・評論家の類
という本来高い教養と人間性を要求される職業に従事しながら、2025年現在の世界で英語も話さず、他国の同類プロフェッショナルと議論もできない体たらくで、昭和で思考停止し昭和の延長を続けることだけに粘着する仕事しかしない奴ら。
こいつらには、間違っていると言わなければ、日本人は自分で間違いを止められない。だから吉本隆明氏を読んで修行をして、こいつらにはたっぷり「罵詈雑言・もとい議論」をふっかけてやることにしよう。[下線部引用者傍点]
(the voice of reason「今、吉本隆明を読みだしたら面白くて止まらない(他者批判の先生として)」@note:https://note.com/idpx/n/n3e5c6e5697d6;2025年4月17日 22:12)
吉本さんの〈戦争体験〉がどのように咀嚼[共有]されているのかが不明だが、現在という土俵で身体的に組み合った論争の姿を見たいものだ。
中学校の中庭に土俵があったような気がするが、チビだった自分は剣道を部活に選んだ。相撲のように直に体を触れ合って身体的な言葉を交わすような面白さはなかった。村の相撲大会を見たり、祖父に連れられて町まで大相撲の地方巡業を見に行ったりしたこともあった。
40年あまりスポ少のバドミントンで子どもらと一緒の時間をすごさせてもらったが、練習の合間などに取っ組み合ったり相撲を取ったりする男の子はほとんど見たことがなかった。
スキップやでんぐりがえしができなかったり、水道の蛇口から直接水を飲めないなど、暮らしの中で身につくはずの身体遣いがどうなっていくのか気がかりな子らも。喘息の子や引きこもりの子もいたが、そんな子こそ上達できるようにするのがコーチの役割だと思っていたのに、体力や素質に恵まれた子どもらを主体にした試合優先の練習環境では、どうしても取り残されがちな子どもらが不憫だった。
なかには武道をやったり水泳をやったりしている子どももいたが、勝てないからとか記録が伸びないとかで止めてしまうようだった。
土曜午後の練習の後で「これからどうするの?」と尋ねたりすると、「塾へ行く!」と返す子どもが多かった。もし今もコーチを続けていたりすれば、「もうそんなことはよしたほうがいいよ」なんて言ってしまうかもしれない。立ち止まった子どもから「なんで?」、「どうして?」と聞きかえされるだろうが。
1980年代の某大学図書館では、『岩波新書』の“赤帯”全巻読破を口する高学歴の人がいたりしたが、獲得した知識の量と収入が見合うような時代は過ぎ去ってしまった。知識を信じる人と自分を信じる人が分断されつつある現実を感じていない「専門家」に騙されてはいけない。
進学できる家庭環境でもないのに入学した高校の普通科の教室には、学歴を伴う専門家志望の同級生が男女を問わず何人もいた。優秀な競争力によって獲得した彼らの知識は今じゃ、“AI やAGI”によってすっかりとってかわられようとしている。
せめてもスポ少の子どもらには、かっての同級生に見られた専門家の予備軍みたいな道を歩んでほしくないものだ。子を思う親御さんらはどう感じているかわからないが、ほとんど専門家を必要としない極端な相互監視システムで生活が包囲されてしまっている。高い授業料だけでなく魂まで売り渡してしまっていったい何を手に入れようとするのか。
終始臆病風に吹かれていたような自分には、晩年の祖父や実家の祖母が「南無阿弥陀」にすがりつくような日々を、ゆったり暮らしている姿が不思議というか、なにか特別な境地があるかのように見えた。明治生まれの中にには見えない何かに身体をあずけられる、そんな力が培われていたのかもしれない。
子どもの頃のぼくら[昭和十年代生まれ]には塾などなかったから、知らず知らずのうちにマインドコントロールされるようなこともなく、とりあえず何でもいいから手に職を覚えさせればよかった。必要なのは孤独ーーに耐えたり愛したりすることではなくーーでも大丈夫な身体だった。徒党を組んだりしているとほんとうに人を愛するとはどういうことなのかという次元に手がとどかないからだ。孤独でないと人を心から尊敬できるようにはなれない。あらゆる党派性は死滅すべきなのだ。
自分でもなんで人様にではなく、ついぞAI に何でも問いかけてしまうのだろうと思うことがある。自然や身体に問いかければそれでいいことなのに、両者とも人間の言葉を理解しないということが経験的にわかっているからだ。
養老孟司や梶川泰司が言うように、人様に聞いてもわからないことを認めなければ自然とは出会えない。「その自然がさらに未知によって統合されているなら、自然は未知に問いかけられるのだろうか。それは言葉ではないだろう。」(梶川泰司@ツイッター改めX、2025.04.13)
利用者の多くは「動いている庭」の話をしながら、自分たちの子供時代を思い出している。ということは、そこで基準となっているのは放棄によって生まれた社会的空間としての荒れ地ではなくて、みずみずしい精神、そして放浪する精神を受け入れることができる場所なのだ。そうした場所に、つまり近所でもない非日常的な場所に立ち帰ることは、植物学の観点からであれ、象徴的な手がかりを導きとするのであれ、多くの場合庭の認識を深めるきっかけになる。この点について留意すべきことがある。類比によってある場所を他のものに結びつけていく横断的な解釈は、類比が働かない場所に比べて、人々にとって親密なものになるということだ(後述の「連なりの庭」を参照)。[下線部原文傍点]
(ジル・クレマン山内朋樹訳『動いている庭』みすず書房、2021年1月第4刷刊、64〜65頁)
妻に先立たれ、二度の長期入院中は院内出張の床屋さんや院内営業の理容室で済ませられたが、退院後の自宅療養で料理の次に困ったことは散髪をどうするかということだった。利き腕の鎖骨骨折をして整髪ハサミを使えなくなった妻は懇意にしていた近所の美容室を薦めていたのを思い出した。
予約日は朝からあいにくの悪天候で出かけるのも億劫な気分だった。ところが予約時間の直前になって急に晴れてきた。早めに昼食を済ませ、入院中の負荷や時間を変えながらのマシンによるリハビリの名残りみたいに、妻が使っていたサイクリング車で行くことにした。リハビリを兼ねてペダルをを重くも軽くもギアで変えられるからだ。
人通りの少ない用水沿いのこじんまりした店構えだが開放的でなんだか亡妻にやってもらっているような居心地だった。
手際よくカットしながら「亡くなられた奥さんのおかげがあって術後のこの世にご縁があり、今日だってこうして晴れ間にしてくれてよかったね」などと声掛けされたが、ほんとうにその通りになった。自宅に帰りついて鏡を見ながら、美容室では剃ってくれない無精髭を気にしていたら、またたく間に元の悪天候に戻ってしまった。
毎朝の髭剃りも運次第みたいに買い換えた電動シェーバーの切れ味がさっぱりなのだ。新たに買い換えなど思案していたら、妻がムダ毛処理に使っていたのが書棚の隅にあるのに気づいた。ずいぶん古いもので充電などしてなかったのに試したら動いて、おまけにツルツルに剃れるではないか。これも驚きだが、アマゾンで物色していたのを止めてしまった。
無精髭といえば細野晴臣の髭面のアルバムを思い出す。ずいぶん前にピーター・バラカンがNHKのラジオ番組で紹介していて、確かテレビ放映のライブバージョンも録画して観たはずだ。
なぜ『HoSoNoVa』が、少なくともわたしにとって、震災直後のときを縁取るような音楽になったのかというと、それはそのタイミングもさることながら、あのアルバムが保持していた音の響きの、抗いがたい説得力のためだったと思う。まるで世界が終わりに近づいていくとき、そこで聴かれるためにつくられたような音。あるいは、ずっと遠い昔に滅びてしまった人間が手持ちの機材で最後に録音したような音をそれから何百年後かに発見して、それをまた別の世界の終わりが迫っているただ中で聴いているような感覚。
終わりがとても近くて、でもその終わりは隕石が落ちてくるような一息の、極端な終わりではなくて、もっと持続的で、砂に埋もれていくように淡々としていて、たとえば暗闇の海のように静かで、でもどうしてか確実に、わたしはそのときが終わりだと確信している。そんなゆっくりとした死にあって、『HoSoNoVa』というアルバムは、それを肯定するのでも否定するのでもなく、そこに居続けるしかないわたしを柔らかな幕で覆ってくれるような気がした。深海に潜っていくときのウエットスーツみたいに。
(榎本 空『音盤の来歴:針を落とす日々』晶文社、2025年3月刊、180〜181頁)
『HOSONO HOUSE』(1973King Record)“細野晴臣の家”から『HoSoNoVa』(2011Victor Entertainment)“細野晴臣の場”へと見事に引越したみたいなアルバムが、まるで音の庭のように聴くものを包み込んでくれる。
身体やその動きの中から真っ先に聞こえてくるのは、自分が自分を騙したり誤魔化したり、知って知らないふりをしたり、自分に都合よく解釈しがちなことだ。それらを裏返したみたいに他人を妬んだり出来事を批判したりして自分を隠そうとする。謙ったり謙遜することなしにそこから抜け出す身体遣いとは?
自分ではなく身体の「内観」はー�ーそもそも「内」あるいは「外」の境界はどこかーーどのような中間に立ち上がってくるか。そんな場のひとつとして見るという行為が空間を生成する運動として〈庭〉を捉え直すこともできよう。
そこでは主観と客観、内と外、自分と他人とが構造として組み合わされている。そして物質などが自他の外部にあるのではなく、自己と他者が交錯した空間に開花する〈何物〉かとして立ち現れ、例えばレゴ・ブロックのようにーー量子力学の単位としてではなく、視線が折り返されたところに現れる空間そのものの内的な襞として受感されよう。
従来のように心の中だけを見るのではなく、身体的に空間そのものを見るという意識の立場になればいいのだ。
緑の庭(No.3)

音の庭でもある「緑の庭」では、子供達も話すのをやめるという
(ジル・クレマン山内朋樹訳『動いている庭』みすず書房、2021年1月第4刷刊、76〜77頁)
庭の音を聴きわける子どもらは街中のストリートピアノの音にも足を止めるだろう。
独身の頃の冬場限定のお寺での三年間の下宿にも、団地で新婚生活を始めた建売住宅にも、500枚余りのジャズLPと再生装置を埴生から富山市内の居住地まで知人の車で運んでもらった。
郊外で新築したリスニンルームにおちついてからも、新たに聴きあさるジャズLPが穴あきボードの吸音壁を少しづつ見えなくしていった。
ターンテーブルを回すのがその日の終わりというのが日常化するとともに、何を鳴らすかはいつの間にか夫の役目みたいになってしまった。ジャズ歴の浅い妻はトラディショナルから前衛までなんでもござれとばかりに、LPだけでなくジャズライブも一緒に愉しむようになった。東京など泊りがけの公演の合間には、聴きたいジャズレコード探しだけでなく、美味しそうな食べ物にありついたりするのもおまけみたいになってしまった。
妻は、中古レコード店の棚から引っ張り出したレコードやCDを「これなどどうでしょう」と見せることはあっても、自宅で聴く前にあれこれリクエストしてくれなかったから、その日に何をどんな順で聴くかまるで夫任せだった。その日その日の献立を夫が要望したりしないでまったくの妻任せだったみたいに。
ジャズからロックへと聴き込む媒体もLPからCDに移り変わっても、“わたしにはお抱えのDJ”がいるからと選曲は任せっきりだった。“ぼくにはお抱えの料理人がいるから”などと言ったら、“おたがいねぎ[葱]らいましょう”などとオヤジギャクみたいなダジャレが返ってきた。お互いに聴く物の好みもさまざまに変遷を遂げてきたが、とにかく二人の聴きどころの中心にはいつも“ジャズ”のリズムがあった。
やっつけ仕事みたいに、今日はどんな食事にするか、何を聴くか、アドリブで決めていくのは身体的にそれなりの負担になっていったのかもしれない。ヘタヨロの老老介護状態みたいになったときは食べることも聴くことも身体的に楽しめない日々が続きがちだった。
屋内のあちこちに分散したLPやCDを引っ張り出して聴かせる相手もいなくなり、もっぱらストリーミングでタブレット端末をオーディオ装置に接続して「一人は賑やか」(茨木のり子)みたいに聴くようになった身体的な張り合いの無さや儚さ‥‥‥。
そんな何気ない儀式みたいなやり取りを通して、レコードが誰か一人の個人によって独占されるべき占有物なのではなく、音楽を愛する人たちの間で共有されるべきコモンズなのだと教えてもらったわたしは、とても幸運だったと思う。レコードは誰かの棚に収まるが、しかしそこが終着駅なのではなく、また誰かの手にわたっていく。そんな気前のよい贈与の関係と個人の一生をゆうに超えて続いていく時間の感覚こそ、レコードの約束であり、希望なのかもしれないと書くのは、横暴な市場の原理を前にして、あまりにレコードに優しすぎるだろうか。その音楽を奏でた人びとは消えていき、それを聴いていた人もいつか消え、それでもまた違う人がそのレコードを聴く。レコードは、いつも誰かが針を落とす可能性を秘めている。すべては消えていくが、すべてが消えてしまうわけではない。『泰安洋行』もーーあれはCDだったがーー、そうやって宮本さんからいただいた。
(榎本 空『音盤の来歴:針を落とす日々』晶文社、2025年3月刊、186頁)
冥土の妻といっしょに『HoSoNoVa』を聴いた後に続くアルバムを選ぶとしたら、同じく髭面のソロモン・バークが映った『Don't Give up on Me』(2002 Epitaph)になるかもしれない。極めつきのブルースだ。(2025年4月25日記/29日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(38)あるいは〈気配〉としての庭��
俺がイメージしていたロックというジャンルは、もっとリ
アルな心情を表出するものだったわけ。ところが、それはい
つしか、スタジアム規模の興行にうってつけのコンテンツと
しての見世物へと変わっていった。その最たるものが、キッ
スだったと思うんだ。
80年代を迎えると、「産業ロック」と揶揄されるように
なったその類の音楽が、ロックのメインストリームとして定
着してしまう。
そこで気づいた。自分の中では「ロックンロール」と「ロ
ック」は違うものなんだと。
ロックは、次第に無難な商業音楽の分野のひとつとして受
け入れられ、他のジャンル同様、技術の向上が尊重されるこ
ととなった。それに比べると、ロックンロールは、上手とか
下手とか一切関係なしに、ハッタリが効きさえすればそれで
いいじゃん。その究極の例が裕也さんなわけよ。
やっぱり、最近のストーンズのライブ映像観ても、ミック
・ジャガーはいまだに歌上手くなってないもんね。うれしく
なっちゃうよ(笑)。
非アカデミックなものがアカデミックなものに勝つという
その瞬間こそ、「ロックンロール」の醍醐味である。俺は昔
からそう定義してきた。パンクやヒップホップに形を変えな
がら、その精神はずっと受け継がれていったと思うんだ。
(近田春夫「夢のしずく 1982-85ビブラトーンズ解散」
/『調子悪くてあたりまえ 近田春夫自伝』リトルモア、
2021年2月刊、188〜189頁)
お互いがお互いを分かったようなつもりにならないように生きてきたから家庭内で大きな齟齬にぶつかるようなことはなかった。それぞれの身体固有のリズムの波長が合ったというか、共鳴するような居心地のよさがあった。
母が要介護状態になった時も地域包括支援センターのケアマネが心配するようなことはいっさい起こらなかった。高屋敷の新居で三世代が暮らし始めてからは、いわゆる嫁舅の軋轢などは皆無に等しかった。
僅かな係累だけでなく、職域や地域でも筆舌に尽くしがたいような事例を見聞してきただけに、老境に入った祖父や母に潜在化していたようなわだかまりが老いの陰りとなって噴出するようなこともなく、まことに穏やかな暮らしをもたらしてくれたのには感謝のしようもないくらいだ。
一昨年の精神病院入院中のことだが、心的な原体験が老境になって発病した老人の家庭環境の行き場のなさ、拒絶された関係ーー家族関係の庭が荒れ果てた姿ーーの[とりかえしようのない]どうしようもなさに圧倒されそうだった。
心臓血管外科での術後のリハビリ担当理学療法士から夫婦の相性について尋ねられたときなど、どう答えたらいいのかわからなくて逆に問い返してしまった。恋愛と結婚は別のようで、お互いの家庭環境が似ていればそれなりに一緒にいて楽しいのではないかということだった。
まず組み合わせの数だけ相性があるということになってしまうが、それでも他者性がむき出しになってしまいがちな残酷な現実も避けられないのは何故か。
他者と同じように感じて理解していくと個性に出会えないと考える人は、他者との違いを認めた知恵から独創性を獲得できると思っている。つまり知恵を創り出せると考えているようだ。それはほんとうに孤立できていないと下手な自惚れに終わってしまう。そこには関係のズレというか動めく襞のような気配というか、物事に向き合う境界的な内観が希薄だから。
普通の庭では、ズレには二つの要因がる。ひとつは生物の時間、もうひとつはスケールの落差だ。
出現と消滅のリズムこそが空間の不意をつき、変化させる。たとえばホンアマリリスやハエマントゥス、ネリネ、イヌサフラン、シクラメンのような葉が出る前に花を咲かせる球根植物。そしてヒナゲシやアルクトティス、クロタネソウのようなライフサイクルの短い一年草などがそうである。
スケールの落差は葉や茎の相対的な大きさの落差や、植物の丈の落差などから生じる。巨大なグンネラの葉の陰になる‥‥‥。二階の窓辺の高さにタケニグサの花が咲くのが見える‥‥‥。
「動いている庭」では、こうした現象はそれ自身のために早められ、あらわにされる。
スケールがもっと幻惑し、
リズムがもっと早くなり。
ずれがもっと大きくなれば、
庭はもっと生き生きとする。
(ジル・クレマン山内朋樹訳『動いている庭』みすず書房、2025年3月第7刷刊、45頁)
辺りに家が建て込む前のことだが、長期にわたって我が家の庭と道路を隔てた東側が空き地というか草っ原だったことがある。同様に狭い裏庭の西側も田んぼを更地にした空き地だったが、自宅を挟んだ東西の空き地の雑草の植生が年年歳歳見るからに違うのだ。それに同調したかのように我が家の前庭と裏庭の雑草も年ごとに様相が変わっていた時期があった。一緒に草むしりをしていた妻も近所の空き地の雑草を模写したような庭の雑草の生え具合に気づいていた。
当時は庭にやってくるのは猫だけではなかった。ところかまわずさまざまな野鳥やウサギや野ネズミや蛇やモグラなどを日常的に見かけたし、あちこちに残っていた草むらに踏み込んだりすると大小いろんな昆虫が逃げるように飛び出してきた。
老いてからの祖父も母もかろうじて庭に降り立つようなことはあっても、ご近所を散歩するような習慣は持ち合わせていなかったが、ぼくら夫婦は散歩にことかくようなことはなかった。
それとなく見え隠れしていた動植物にもまして、近くの裏道や空き地を歩き回って帰宅した履き物からもさまざまな雑草の種子が我が家の庭に運び込まれていたに違いなかった。
隣接していた空き地はすべて住宅が建ち、狭すぎて枝が差し障るようになった樹木は庭師に伐ってもらうしかなく、裏庭は屋根から滑り落ちる積雪時の受け皿と化してしまった。今じゃ昆虫もいなくなり、さまざまな雑草の植生が移り変わる面白さも薄らいでしまった。
〈私〉は一つの乗り物、あるいは仮の宿、あるいはいくつもの小さな声の通り道‥‥‥。
あるいは、私は、私ではないものたちが集まる空き地、一時的な集合の場所‥‥‥。
だが、この場に乗り合わせているのはだれなのかさえ、私は知らないーー乳酸菌? 大腸菌? 表皮ブドウ球菌? ヘルペスウィルス? ミトコンドリア?ーーともにゆくものたちは大小様々で、膨大、しかもここにいるものたちだけではない。銀河、ブラックホール、火山、雨雲‥‥‥。私を形づくるものすべてを数え上げることはとうていできない。
〈私〉という〈乗り物・宿・拡声器〉は、ここに乗り合わせ、住まい、通過していくすべてのものたちとともにゆく道のなかでつくられていく。だから、私は、自分がだれなのかさえ、まだ本当にはわからない。
厳密には、私はまだ存在していない。存在しつつある。気配のようなも。嘘でも虚構でも幻想でも幻影でもなく、これから生まれようとしている、その気配。
becoming 生成
to-be-coming これからやってくるのも。
だが、未だ来ていない。
未来。
耳を澄ませば、この世界は未来ーーまだ存在していないものたちーーの気配に満ちている。[下線部原文傍点]
(森田真生「ともにゆく道 第1回 気配」/『小説すばる』第38巻12号、2024年12月、280〜281頁)
一人稽古による武術的な身体操法を極めつつある山口潤師じゃないけれど、車の免許に縁がなかったからでもあるまいが、“ドライビング・マイ・ボディ”なる身体的境地にはずっと憧れ続けてきたと言っていいかもしれない。
どのような教育を施されようが、いかなる社会的な立場に立とうとも、とにかく「戦いや争いは悪」ということになりがちで、自分の内部では免疫機能による本能的な闘争性に無自覚になってしまっている。そこには宗教や思想だけでなく社会的な規範が加担していたり、あるいは洗脳といったことも影響しているのかもしれいない。身体レベルでも知能レベルでもそのような状況を自覚し、どのように稽古ーー頭によってではなく身体的かつ感覚的に学びながらーーすることが老いたる身体でも可能かどうか、悩ましいところだ。
どこか狂ったような今の世の中では武術など時代遅れに見えるかもしれないが、人皆すべて免疫レベルでは外界と争い戦っているーー身体が様々な異物の襲撃を退けたりあるいは共存しながらーー局面を想起すべきだ。この生きるものすべての根幹にある本能的な生命の働きについては、数年前のコロナ禍の社会にあって誰の目にもよりいっそう明らかになったのではなかったか。
それにしても当時の新型コロナ人工説の中心人物とされる人物がアメリカの厚生大臣にあたる要職に就いているなんておかしな時代になったものだ。千々に乱れる人心の世には陰謀論の花が咲くのだろうか。
目指すべきは“ドライビング・マイ・ボディ”だ。老いにあらがって怠けたり手抜きをしながら生活のレバーを縒るようにしながら、聴いていたいBGMはライ・クーダーの「The Slide Area」(1970年1月1日、c1982、Warner Redords)で決まり。
子どもらには「ただ大人たちにほめられるようなバカにはなりたくない」(ブルーハーツ/少年の詩)が似つかわしいが、日本語のロックといえば、『はっぴいえんど』から『ブルーハーツ』そして『King・Gnu』への“ソングライン”がひとりでに浮かんでくる。
二人[自分のなかの他者も含む]の言葉が尽きるところというより、言葉ーー以前あるいは以後というかーーを超えた何かが介在することによって日々新たな身体的な場を共有し続けられればいいのではないか。その核心は相互的に内観できるかどうかにかかっているのではないだろうか。
どんなに親しそうな間柄であろうが、すべて分かったつもりになってしまわれる瞬間の関係ほど冷酷な場面はない、というのが僕ら夫婦がそれぞれ歩んできた交友関係から学んだことでもあった。
家族ぐるみで暮らしの句読点みたいに訪れていたご近所馴染みの寿司屋に庭はなかったが、春夏秋冬を彩ってきた季節の旬の味わいの広がりと奥行きが、いつしか豊穣な“食の庭”となって立ち上がってくるようだった。
「教卓」の向こう側に立てば誰しも「先生」と見做されてしまうようだが、寺子屋みたいにーー師弟関係が育まれる場ーー教室を“教育の庭”にまで高めるのはたやすくない。
普遍的な原理に立ち帰るような子どもらの学びの庭はどのようにして形成されるか?
学ぶことと教えること、両者が出会う契機が一瞬でも共鳴するようになれば、そこを入り口の第一歩としてそれぞれの出口を探す独り稽古を続けるしかない。ひとり遊びのように見えるかもしれないが。
つまりひとり遊びのコツは「目的」を持たないことだ。言い換えればその事物をゲームとして「攻略」しないことだ。筋力トレーニングに夢中になる中年や、まだタイムが落ちないと誇る高齢のランナーたちの目の輝きが周囲の人びとを疲れさせるのは、彼ら/彼女らが自分を強化するゲームの快楽(達成感)に酔い、身体を動かすことの快楽そのものを見失っているからだ。そしてこのようなゲームの「攻略」を手放したとき、はじめて人間は事物そのものと対峙できる。走ることそのものを目的としたときに、人間はその行為について最も純粋にふれることができるのだ。
(宇野常寛/§5 ひとりあそびのすすめ」/「#9 孤独について」/『庭の話』(講談社、2024年1月刊、223〜224頁)
ひとりにならないと触れ得ない行為だけでなく、いままで聴こえていなかった世界が聴こえるようになったりすることによってもたらされる豊かさもあるのではないか。
孤食と共食の違いも単なる人数の違いにとどまるだけでなく、食する身体的稽古の違いが露わになるようだ。食育といったレベルでは見えてこない食材それぞれの旬の旨みや味わいといったものの際立ち方が〈味の庭〉の広がりと奥行きの違いになる。
せめて朝の食事だけでも自分でなんとか準備するようになって気づいたのは、料理下手でもいいから基本的なことをなんとかやりこなすしかないということだ。そして老いに重なる不慮の骨折事故から心身ともに不調になり、日々の料理を楽しむ暮らしができなくなった亡妻へのねぎらいも。
どんな暮らし方になろうともご飯を炊いたり、味噌汁を作ったり、卵を焼いたり、最低限のことをする。たぶんそうしないとその日その日を楽しく過ごせない。人生は禍福糾える縄の如く、何はともあれ、なんらかの身体的行為がなんとか術後の老体を支えてくれる。
舞踏家の最上和子のツイッター改めX[2025年5月3日の書き込み]から拾い上げたくなった呟き。「基本、人は人間としての輪郭を保てなくなると、生きられないどころか死ぬこともできない。その人間としての最低限の輪郭を作るのは、食事の支度だ。」合掌。
独り住まいの気配を吹き払うかのように、ここのところ新旧のブルースなど取り混ぜて聴いたりしている。川釣りにハマった田舎少年だった頃、フナやコイに混じって釣れたりするナマズは外道だったが、魚好きだった祖父のためにリリースしないで持ち帰っていた。調理が得意だった祖父の手で照り焼きになるとなぜか美味くなったのだ。その頃はまだ魚嫌いだった母は食べようとしなかったが。
ところで後にジャズに合わせて聴くようになったブルースではナマズは王道だった。「Catfish Blues」としてブルース音楽の象徴的存在になっているではないか。ジミ・ヘンドリックスやB.B.キングやジョン・リー・フッカーやスキップ・ジェイムスそのほか、いったいどれくらい歌われれてきたのだろう? なかでもRobert Petwayの歌いっぷりがその祖型になっているようだ。
Catfish Blues
ロバート・ペットウェイの曲
歌詞
さて、横になりました
Well, I laid down
昨夜ダウン
Down last night
さて、休んでみました
Well, I tried to take my rest
昨夜、ある考えが頭に浮かんだ、ベイビー
Notion struck me last night, babe
私は西へ散歩に出ていると思う
I believe I take a stroll out, out west
西へ散歩に出てみましょう
Take a stroll out, out west
西へ散歩に出てみましょう
Take a stroll out, out west
西へ散歩してみよう
Take a stroll out west
西へ散歩してみよう
Take a stroll out west
もし私がナマズだったらどうしますか、ママ?
What if I were a catfish, mama?
私は言った、深く青い海を泳ぎなさい
I said, swimmin' deep down in, deep blue sea
女の子たちを今すぐ連れて行ってください、優しいママ、出発してください
Have these girls now, sweet mama, settin' out
私のためにフックを設定する
Settin' out hooks for, for me
フックを設定して、私のために
Settin' out hook for, for me
フックを設定して、私のために
Settin' out hook for, for me
私のためにフックを設定する
Settin' out hook for me
私のためにフックを設定する
Settin' out hook for me
私のためにフックを設定する
Settin' out hook for me
ええと、私は下って行きました、ええ、教会の家まで行きました、はい
Well, I went down, yeah, down to the church house, yes
さて、私は祈るように呼びかけました
Well, I called on me to pray
ひざまずいて、ママ、私は知りませんでした、主よ
Fell on my knees, now mama, I didn't know, Lord
言うべきことは一言もありません
Not a word to, to say
言うべきことは一言もありません
Not a word to, to say
一言も言ってない
Not a word to
一言も言ってない
Not a word to
言うべき言葉ではない
Not a word to say
言うべき言葉ではない
Not a word to say
言うべき言葉ではない
Not a word to say
遊んでね、ずっと遊んでね
Play 'em, man, play 'em a long time
書くよ、手紙を書いてよ、ベイビー
I'm gonna write, write me a letter, baby
見るだけのために書きます
I'm gonna write it just to see
見てください、私のベイビー、彼女は誰のことを考えているのですか
See my babe, my baby who she's thinkin' of
ちょっと古いこと、私に
Little ol' thing on, on me
ちょっと古いこと、私に
Little ol' thing on, on me
ちょっと古いこと、私に
Little ol' thing on, on me
ちょっと古いこと、私に
Little ol' thing on, on me
私にはちょっとしたことがある
Little ol' thing on me
ああ、ちょっとしたことだけど
Oh little thing on me
(提供元:Musixmatch、ソングライター: Robert Petway、Catfish Blues 歌詞( c)Watertoons Music, Music Corp. Of America, Inc.)
歌詞を訳してくれたAIチャットによると、ペットウェイは1940年代初頭にわずか16曲しか録音を残していないが、ブルースのスタンダードナンバーとなった「Catfish Blues」を最初に録音したブルースマンのようだ。この曲は、マディ・ウオーターズによって「Rollin' Stone」というタイトルでカバーされ、ローリング・ストーンズのバンド名の由来にもなったということだが、真偽のほどはわからない。彼のギタースタイルはフィンガーピッキング主体で、力強いベースラインとうねるようなメロディーラインにコードワークも加わって独特なグループ感を生みだしている。
ブルースの発祥の地とされるアメリカ南部でのナマズの生息環境だけでなく、その食文化との関連性から、ブルースが根ざすアメリカ南部の生活や感情を表現する上でナマズが歌われるようになったのだろうが、いったいどんな食べ方をしていたのだろう。
独特のぬめりがあって掴まえどころの無さを女性に喩えているようだが、日本の古典落語の十八番が落語家の語り口の数だけバラエティーに富んでいるように、演奏するブルースマンそれぞれの歌詞の数だけーーさまざまな歌いっぷりの「Catfish Blues」が聴けるのが面白い。
ご当地では日常的に見かけていてもブルースで歌われることの少ないラバやアリゲーターなどは生き物として食えなかったということだろうか。人間の身近な存在の犬や猫も歌われているが、いかに飢えていたとはいえまさか食べたりはしなかったであろう。
常食の魚についてじゃなくて「釣り」という行為そのものを描いたようなブルースもあった。タジ・マハールの「Fishin' Blues」などを聴いていると、ナマズの調理だけでなく口笛を吹いたりして楽しい釣りの行き帰りも浮かんできそう。ブルースとは本来、底の抜けた明るさにあるんじゃないだろうか。(2025年5月23日記/24日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(39)あるいは響いてくる〈聲〉の庭へ��
聴覚器官や、あるいは目視できる聴覚手段を持たない種が、
音を通じて運ばれる複雑な情報を理解したり、それに応えた
りする能力を有することが、デジタル生物音響学を用いるこ
ことで科学的に立証されてきた。広い海に散らばっても、魚
やサンゴの幼生(わずか数ミリの大きさで、中枢神経を持た
ない生物)は、海中の不快な音の中から自分の棲みかの岩礁
の音を聴き分けて、そこへ戻っていく。植物は乾燥したり傷
みが出たりすると超音波を出す。ミツバチがブンブン音を立
てると、花は期待するかのように甘い蜜を出す。地球全体は
絶え間なく会話し合っている。
(カレン・バッカー[著]和田佐規子[訳]『饒舌な動植物
たち:人の聴覚を超えて交わされる、クジラの恋の歌、ミ
ツバチのダンス、魚を誘うサンゴ』築地書館、2024年12
月刊、6〜7頁)
食事のように欠かせないものではないが音楽においても、ひとりで聴くのと親しい誰かと聴くのとでは、立ち上がってくる〈音の庭〉の粒立ちに違いが出るようだ。
いずれの場合もその感覚的な違いに優劣が生じたりするのではなく、具体的には食したり聴いたりする行為�そのもの身体内での了解過程に微妙な気配の差が生じるようだ。
この頃はすっかり遠ざかってしまったが、かっては朝から近所だけでなく庭でも野鳥が賑やかだったり、庭草を刈り進めたりしているといつになく飛び跳ねながら散らばる昆虫が騒がしかったりすると、なんとなく愉快になってきたりしたものだ。いくらジャズが好きだといっても、音楽ばかり聴いてもいられない。
ゆえに音楽の流行がもしわれわれの音の選択、すなわち特に自分の求むるもののみに耳を傾けさせる習慣を養うてくれるならば、それは確かにこの生活を平穏ならしめる途である。そうでないまでもこの世にはすでに消え去ったる昔の音が多く、いまなお存在してやや幽かに、もしくはこれより新たに起こらんとするものがあって、あるものははなはだ快くまたあるものは無用にしてしかも聞き苦しく、最も美しいものは必ずしも高く響いているものではないということを、知らしめるだけでも一つの事業であろう。
聡明は決して現在の特に強烈なるものに、動かされやすいといういう意味ではないのである。昔は縁の下に蟻が角力をとる音を聞いたという話がある。それほどでなくとも心を静めて聞けば、まだまだ面白いいろいろの音が残っている。聞き慣れて耳に留まらなくなったのは、叢の虫梢の蝉だけではなく、清らかなるものの今やまれになったのは、野鳥の囀りのみでもないのである。新たに生まれたものの至って小さな声にも、心にかかるものは多い。ある外国の旅人は日本に来てことに耳につくのは、樫の下駄の歯の舗道にきしむ音だといった。しかり、これなどは確かに異様である。そうしてまた前代の音ではなかった。
(柳田國男「九 時代の音」/「第一章 眼に映ずる世相」/『明治大正史 世相篇(上)』講談社学術文庫、昭和51年6月刊、54頁)
通勤やお出かけなど列車やバスでの行き帰りはほとんどウオークマンやアイポッドのイヤホンを耳にしていたが、サイクリングやスキーや山歩きなどの際にはそんなものは不要だった。
連休などは人混みを避けるように自宅の庭から東の常願寺川の河川敷へと自転車を走らせた。そこからーー流域が56kmと短いのに標高差は2kmを超える急傾斜だからーー決まったように右岸を富山湾に向かう夫婦縦列走行になりがちだった。
川面と山脈が響き合うような景観を耳にしながらのサイクリングに音楽は邪魔になる。冬季の北アルプスから富山湾まで見渡せる立山山麓のスキー場にはゲレンデにこだまする音楽は似合わない。シーズンの終わりともなると春の響きが近づいてくる気配を感じながら滑り降りたりしていた。
「高知県の南に広がる土佐湾は、室戸岬と足摺岬を結ぶ幅約130キロメートル、奥行き約50キロメートルの海」(『中西和夫の写真絵本 土佐湾のカツオクジラ』大空出版、令和6年9月刊)ということだが、富山湾の幅と奥行きはおおよそ80キロメートルに40キロメートルしかなく、狭いようでも深さは1,000メートル以上になる。どんな深海魚が潜んでいるのか興味が湧いてくる。
富山湾を箱庭にしたような魚津水族館の深海生物コーナーではイサゴビクニンが見られる。イルカのショウはやっていなかったが、ウマズラハギみたいな小さな魚による輪くぐりなどのショウを見たことがある。海洋を切り取った庭のような水族館はいつ訪れても飽きない。
両湾とも魚介による県民の食生活を豊かにする庭のような海だが、残念ながらホタルイカやシロエビとクジラじゃとても比べようにならない。カツオに対して鰤じゃなくてノドグロ[アカムツ]を推したい気もするが、高騰し続ける物価高のおりから高級魚すぎてなかなか庶民の口に入りそうもない。姿など見たければ生成AIがいとも簡単に美味しそうに調理されたノドグロの絵を出してくれるが。
クジラより大きな生き物はこの世にいないとは言えず、「地球上で最も古い、最も大きな生きた動物」(カレン・バッカー[著]和田佐規子[訳]『饒舌な動植物たち:人の聴覚を超えて交わされる、クジラの恋の歌、ミツバチのダンス、魚を誘うサンゴ』築地書館、2024年12月刊、125頁)であるサンゴを忘れてはいけない。一昨年のM病院入院中のOT[Optional Therapy]でのことだが、鳥やイルカやサンゴの塗り絵を好んでやっていたらどことなく気もやすまるようだった。
サンゴの消滅は、その他の数多くの種が終末を迎えるという前兆である。サンゴは海の世界にある熱帯雨林のようなものだ。サンゴ礁は海底面のわずか〇・一パーセントを占めているに過ぎないが、そこには人間が知っている海の生き物の種全体の三分の一が生息している。そして最も気候変動の影響を受けやすいサンゴーー枝分かれした木のような姿の種類ーーは魚たちに泳ぐ場所や、餌を獲ったり子育てをしたり、捕食者から身を隠すための場所を提供する。サンゴの中でも丈夫で生き残りやすいものもあるが、目立たないドームのような形をしており、魚や他の海の生き物にとって棲みやすい場所ではない。
(カレン・バッカー[著]和田佐規子[訳]『饒舌な動植物たち:人の聴覚を超えて交わされる、クジラの恋の歌、ミツバチのダンス、魚を誘うサンゴ』築地書館、2024年12月刊、122頁)
高知の松岡さんから中西さん撮影の上記写真集をプレゼントされてからというもの、遠い南海の庭を眺めるようにあちこち頁を開いたりしている。お気に入りは34頁の「争いに勝ったものだけが子孫を残せるのでみんな必死です。」のキャプション付きで二頭の尾鰭がクローズアップされたもので“クジラの歌”が聴こえてきそうな、とても水族館では得られない光景だ。
沖縄まで行かなくとも近くの水族館でサンゴは見られるが、まさかそれが豊穣な音の庭だったとは‥‥‥。
健康なサンゴ礁は音があって活気に満ちていることをゴードンは知っていた。音が次々に展開していくさまはちょうど水中のオーケストラか、終わることのないジャズバンドの即興演奏のようだ。グレート・バリア・リーフではザトウクジラがソプラノのメロディーを歌う。魚たちはコーラス担当だ。クマノミはホーホーと歌い、マダラはブーブー、ブダイはガリガリ、ウニはうるさいひっかき音を出し、チューバのように反響する。打楽器は短く高い声を出すイルカとカチカチ鳴らすエビの担当で、エビはハサミであぶくをつくると、それを破裂させて大きな音を出す。ロブスターは殻を洗濯板のように使って触覚を擦りつける。雨の降る音や、風や波の音はバックビート(弱拍)を入れている。一番いい席を手に入れるには、満月の真夜中のコンサートに行くのがいいだろう。たいていこの時、魚のコーラスは最高潮に達するのだ。しかし、最前列に座る必要はない。魚の大集団のコーラスは最長で八〇キロ離れていても聞こえるし、クジラの声は数百キロも響くのだ。水中のサウンドスケープの中で最もよく研究されているものの一つがサンゴ礁である一因はこれだ。透明で楽しげなたくさんの海の不協和音には貴重な情報が詰まっている。音の積み重なった層からそれを読み解くことができるのだ。
(『前掲書』127〜128頁)
四国には水族館が6館もあるようだが北陸には4館しかなく、いずれにしろイルカは見られてもクジラは見ることができない。
そんなときはAIチャットによる画像生成がとても便利だ。手軽なホエールウオッチングじゃないが、海面を叩く尾鰭の迫力ある画像そのほか、細かくプロンプトでリクエストするほどにいろんなクジラの姿を生成してくれて、ディスプレー型の私設水族館のように愉しめる。
ついでに「土佐湾のクジラ漁の歴史と概要についてレポートしましょうか」などとお節介をはさんだりしてくるが、こちらとしては絵だけじゃなくクジラの歌なども聴きたかったのだ。
ネットを利用すれば見るだけじゃなく音も聴けるところは図鑑にまさっているかもしれないが、『地球博物学大図鑑』など手元で頁を広げて眺める楽しみも残しておきたい。
クジラといえばなんといっても昭和二十年代の小学校の給食での鯨肉[竜田揚げ?]との出会いだ。脱脂粉乳や肝油ドロップと同じように美味いともなんとも思わなかったが、戦後の食糧難が続いていたからコッペパンと一緒に何ひとつ残さず食べていた。
スーパーやデパ地下の食品売り場でクジラ肉を見かけたりしたが、敗戦当時と現在をつなぐ食糧事情の激変は何よりも世代間の食生活上の違いとなって身体に刻みこまれているのではないか。
祖父や母に好き嫌いがなく何でも食べてもらえるから助かるといいながら、料理好きだった妻がいろんな料理に挑戦していた日々が忘れられない。
若い頃の母は魚料理が嫌いだったらしく、それを知った妻は母の誕生日には手料理だけでなく、馴染みの魚屋や寿司屋から、ノドグロの焼き物を用意したり、特上の盛り合わせを取り寄せたりしていたこともあったが、クジラ料理が食卓に並んだことは記憶にない。
AIチャットで探したホッキョククジラが歌うネット上のリソースを幾つか聴くことができたが、土佐湾のクジラ漁のような祖先との歴史的な共存関係は温暖な日本だけなく、厳寒の北極海でも営まれてきたようだ。
音楽と儀式、食糧、道具、衣類、シェルターであり、熱源、光源でもある。イヌピアットの人々の生活はホッキョククジラによって維持されていたのだ。狩猟の儀式と共同体内での肉の分配から見ても、ホッキョククジラはイヌピアット人の社会の焦点であった。「私たちの社会では、私たちを一つにつなぐのはクジラなのです」と捕鯨船長の妻メイ・アギークは言った。クジラ漁の準備、それからクジラを加工する習慣的な行動はコミュニティの季節的なリズムを構成していた。イヌピアット人の表現にkiavallakkikput agviqというものがあり、文字通りには「クジラの生態系サイクルに入る」という意味だ。これは文化地理学者の榊原千絵がcetaceousness(クジラ的意識)という意味で表そうとした、イヌピアット人社会のすべての面に浸透しているクジラの意識のことだ。人類学者の古い世代は植民地時代の視点から、北極地方の西側地域の生活を統べる「クジラ崇拝」に言及している。
(『前掲書』46頁)
何千年もの長きにわたってクジラと親しく暮らしてきた現地人にとって外来捕鯨業者の乱獲とそれに続く国際捕鯨委員会(IWC)による捕獲規制は彼らの暮らしを根底から揺るがす元凶となったに違いない。イヌピアットと委員会との論争は地球規模にまで大きく展開したようだ。拡大し続ける捕鯨反対運動もあって生存捕鯨と商業捕鯨の線引きがあいまいになったりしなかっただろうか。おまけに地球温暖化の問題まで絡んだりしてくると自然に対する目も曇りがちになりそう。
環境問題は厄介だが、魚を食えば海を思い、米や野菜を食べては田んぼや畑の土などを思うまでに引き寄せ、どこまで気候変動などの環境問題を“我が事”として考えられるかどうかが問われる。
大雑把に庭とは新たに囲われた何かを形づくるものだとすれば、惑星における生命の限界、すなわち生物圏そのものが、かかる庭の囲いとなるのではないか。
修景家というのはよくわからないが、神や仏もあるいは建築士であり、または庭師なのか、それとも芸術家なのかもしれない。不定形な箱庭を抱え込まざるを得ない生き方をしている身体にはどのような庭師が宿っているのだろう。
「北極圏に暮らす先住民族であるイヌピアットの人々にとって、クジラは単なる食料資源を超え、彼らの文化、社会構造、そしてアイデンティティの根幹をなす存在です。1000年以上にわたる歴史の中で培われてきたこの深い関係は、現代においても彼らの生活に色濃く反映されています。」との前置きで、AIチャットが百数十件ものネット上のリソースを参照して詳細なレポートにまとめてくれたが、目視では数えられない氷の下のホッキョククジラの生息数をどうやって音声からつきとめ得ていたのかまではよくわからなかった。
海が歌う音声の収集は苦労をするだけの値打ちがあると考える科学者は多い。イヌピアット人の経験知を頼りに安全な観測地点を選んでいると、科学者たちは地形環境に対して異なった見方をするようになった。初め氷は脅威の塊と見えていた。ところが、何日も、何週間も、何か月も氷の上に出て観測を続けるうちに何かが変わってきた。イヌピアット人の長老ウェズリー・エイケンはかって次のように述べていた。海の氷は美しい庭に似ている。そこで人は食べ物を集め、旅をし、くつろぐのだ。物質の、感情の、そして精神の重要な意味を持った場所なのだと。クラークはのちに次のように思い出を語った。
ハイドロフォンを海中に沈めると、聴こえるのはさまざまな音声や歌声の不協和音だ。それはちょうど(中略)黄昏時ののようなまったくの異世界なのだーーーシロイルカやホッキョククジラ、アゴヒゲアザラシと氷だ。そしてこう言うんだ。「オーマイゴッド。氷の下はジャングルだ」。
クジラの水中音を聴いたのはクラークが最初ではない。イヌピアット人ガイドに自分のイヤホンを渡したが、ガイドはすでにどの動物がこの特別な音を出しているのか知っていた。「彼らの文化では、オールの手元側を顎の高さまで上げて止め、先を水中に入れて、耳を傾ける」とクラークは記録している。ハイドロフォンとオールでは異なった方法で聴く作業を行う。前者が音声をデジタルに測定するのに対して、後者はアナログな測定を行うのだ。巧みに配置された多数のハイドロフォンであればクジラの位置を正確に測定できるが、イヌピアット人は同様の情報を自分たちの聴く力で得ることができる。彼らはクジラの出す複雑な音声に初めからよく慣れているのだ。ブーンという音や、脈打つような音、ブウブウ響く音やうめくような声、断続する音がメロディーのある音調を伴って急に現れたりする。イヌピアット人が長年知っていたことが、クラークにも次第にわかってきた。ホッキョククジラが歌うこと、その歌は複雑さの点で研究の進んでいるザトウクジラに匹敵すること。
(『前掲書』53〜54頁)
イヌピアット人にとって生活に根ざした美しい氷の庭の下にはーー同じ地球上でも比較的温暖な地域の定住者にとっては想像もできないーー宇宙の対極のような音の「世界」が広がっているのだ。
ホッキョククジラについての同様の研究から、ホッキョククジラもまた高周波の音を出していることがわかった。その音は歌の中に組み入れられ、ザトウクジラでよく知られているように、歌は徐々に発展していくのだ。ホッキョククジラは複数の歌を一年の間に歌うのだが、一風変わっていて、その歌は同時に複数の調和しない音を含んでおり、著しく複雑である。ザトウクジラが海のオペラスターであるとするなら、ホッキョククジラはジャズシンガーだ。ホッキョククジラの歌はバリエーションに富んでいることが多く、それによって、群れの頭数を数えたり追跡をすることができるばかりか、彼らの社会構造や健康状態、行動についても理解する手段となる。小鳥たちの歌の多様性が生存能力の指標としてよく知られているように、ホッキョククジラの歌の多様さと複雑さは、北極海で急速に悪化が進んでいる変化の指標となりうるのである。
(『前掲書』63頁)
ブルース音楽においてナマズほど頻繁ではないが、比喩的にクジラが歌われているJ.B.ルノアーの「The Whale Has Swallowed Me」を聴きながらAIチャットで訳してもらった。
The Whale Has Swallowed Me
J.B.ルノアの曲
歌詞
クジラがヨナを飲み込んだと言われています
They say the Whale swallowed Jonah
真っ青な海の中で
Out in the deep blue sea
時々そんな気持ちになることがある
Sometimes I gets that feeling
あの昔のクジラが私を飲み込んだ
That same old Whale has swallowed me
太陽は東から昇る
The sun rise in the East
西に下ります
Goes down in the West
時々私はその古い感覚を感じることがあります
Sometimes I gets that old feeling
すべての生き物には休息が必要です
Every living creature needs some rest
クジラは病気になったと思います
I believe the Whale got sick
だからこそ私はこんなブルースを抱えているんだ
That's why I have these blues
いつか信じます
I do believe one day
彼はついに私を解放してくれるでしょう
He will finally turn me loose
今、私が生きていたら
Now if I live
殺されなかったら祈るよ
I pray, if I don't get killed
いつか信じます
I do believe one day
ここから這い出てくるよ
I will crawl out of here
(提供元::Musixmatch、ソングライター: J.b. Lenoir、The Whale Has Swallowed Me 歌詞 (C)Bug Music, Ghana Music)
旧約聖書の「ヨナ書」でヨナが大きな魚に飲み込まれたエピソードをモチーフにしながら、青い海深くへとクジラに飲み込まれたブルースとして歌われている。
神の命令に従順でなかったがために嵐の海でクジラの腹の中に閉じ込められーー神の懲らしめであると同時に救いともなる信仰の庭‥‥‥、そこから陸に吐き出される墓場[死]からの復活劇としてキリスト者は聴いてきたのだろうか。受難と信仰の象徴としてのクジラはイヌピアット人のクジラ崇拝からずいぶん離れた海を泳いでいるような気がする。
カントリーブルースを歌うKelly Joe Phelpsの「Brother Sinner & the Whale」(2012 Black Hen Music)はそのタイトルやアルバムジャケットのクジラの絵が示すように、収録された楽曲も含めて旧約聖書の「ヨナ書」から得たインスピレーションを散りばめたような作品になっている。
ブルースの世界では、ナマズはきわめて現世的な女性との関わりにおいて、クジラは信仰や内省による現世との関わりにおいて、それぞれ歌い継がれてきたようだ。
アルバムジャケットにクジラが描かれたものは何枚か見たことがるが、ナマズのアルバムジャケットは見たことがないような気がする。AIチャットに訊いたら、『Catfish Blues/Catfish Keith』(1985)を見せてくれたが、確かにナマズ一尾が描かれている。ついでに『Catfish Crawl/Catfish Keith』(2019)には六尾も描かれていた。『Pony Run/Catfish Keith』(1999)では彼が歌う「Catfish Blues」も聴くことができてよかった。
クジラの尾鰭がーー翼を広げた大きな鳥が飛び立つみたいいなーーアルバムジャケットになった『Whales Alive/Paul Winter & Paul Halley』(1987 Earth Music)を聴いたりすると、例えば「Concert for Whale and Organ」のように、神秘的なクジラの生音とオルガンの合奏が聴くものをクジラが演奏する深海の庭へと誘われるようだ。(2025年5月30日記/6月2日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(40)あるいは〈武と舞〉の間で��
あのような踊りを踊れるようになりたい、という思いは日
増しに強くなっていった。身体表現というのは子供の頃から
やっていないと無理だ、という常識に捕われていた私は、そ
れまでどんな感動的な舞台を見ても、自分でそれをやりたい
とは思わなかった。自分は「見る者」だと決めていた。あき
らめていたのだ。
しかし今回は・・・あきらめきれなかった。どうしても踊
りたかった。その踊りには、私がそれまでの人生でかかえて
いた大きな課題を解くためのカギがある、と直感した。それ
は音楽にも絵画にも映画にも文学にもない何ものか、究極の
ものであり根源のものだ、と感じていた。
でも当時私は40歳だった。いくら何でも手遅れだ、とも思
った。
(最上 和子『私の身体史』2016年3月刊@ Kindle Edition)
今年は庭に植えっぱなしの水仙が咲かなかったようだがーー八重桜や木瓜などは例年通り咲いたのにーー何故だろう。ひょっとしたら昨年の開花が終わった後の葉っぱや茎の刈り込みが早すぎたのだろうか。光合成が十分に行われず球根に開花に必要な栄養が蓄えられなかったのかもしれない。ただでさえ花物が少なくなった庭なのに残念な次第だ。自然に枯れて倒れるまでほっておけばよかった。
石楠花の花付きも疎らのようで、後に続く躑躅の蕾はもっと少ないようだ。雪吊りや剪定など最低限のことは庭師に任せっきりで、夏場の水やりや害虫駆除以外に施肥などはやったことがない。何事も自然のまま、あるがままがいいと言ってもその内実が見定め難い。
桜や銀杏や欅や柳や松からプラタナスまで、来し方行く末に影を落とすような並木道を歩いて来たような身体の記憶。登るとともに季節が帯状にグラデーションを重ねたような時期の登山道を歩く身体感は格別だった。
下界ではさまざま、寄り道だったり、脇道だったり、回り道だったり、とにかく歩いて見ないことには身体にとってどんな道かわからない。裏道のように身体の前後左右や上下がはっきりしないとわからない迷路もあった。
どんな道を歩いて来たにしても、途中で歩くことそのものに身体が躓くようなことがある。心身のバランスが狂ったというか見失ったような精神病院入院時の身体の様相がそうだった。
頚椎と両肩の筋肉が締め付けられるような痛みで、立ったり座ったりがもどかしく、ふらつくようでまっすぐ歩けなかった。人生上の出来事の衝撃で鞭打ち症になったみたいと訴えたが、主治医は取り合ってくれなかった。前倒しされた老衰の前兆を妄想したりもした。
独房のような保護室から相部屋の病室へと正気を取り戻したようでも、身体的な圧迫感と歩きづらさは治らず、こうなったら自分の身体状況を探りながら歩ける道に立てるようにするしかないとの思いで、できるだけ院内廊下を行ったり来たり“散歩”を欠かさないようにした。食欲不振も一向に改善されず、排便排尿も乱れがちで、夕方になると下半身に浮腫が出ていっそう歩きにくくなることもあった。一度ならず専門のカウンセリングや薬剤師の面談なども受けたが、身体的な不都合はそのままに、なんとか退院させてもらえた。
朝の起き抜けや夕方など、首根っこを押さえつけられたような立ちづらさ、歩きにくさに過呼吸がともないそうになることもしばしばだった。ともすれば過緊張状態に陥りやすい傾向から脱出しようとする身体的反応らしいが、苦しくなる前に処方薬で経過させるようにしてきた。
背中というか広背筋が固まったみたいに柔らかさを失い、その先の両腕も縛られたような窮屈さでぎこちない感覚にとらわれる。退院後も腕や手に無意識の緊張や強張りが残ったのだろうか。
下半身と上半身を纏める腰回りのバランスがともなわないというか、狂っているような身体感覚に戸惑う日々が続いたが、ふらつきながらもなんとか独居暮らしの日常を楽しむような身体遣いーー以前にも増して稽古を心がけるようになった。復活した朝のストレッチも欠かさずやるようになったが身体的には惰性にしかなっていないような気がした。
そんな日々が一年も続かないうち、痛みもなく浮腫んだ左肘の救急検査で発覚した心不全の手術後は、以前にも増して内臓感覚を探りながらリハビリそのほか衣食住すべてにわたって、身体的な稽古の場とするような日常を心がけてきた。
老体ゆえの不都合をあれこれ悩まず、避けようのない身体的現状として内臓感覚で受け止めるように稽古していたら、どうやら首や肩の詰まりや凝りが薄らいだようで呼吸も整い、自然な立ち居振る舞いに近づきつつあるようだ。解禁になった歯の治療も受けつつあるし、日常茶飯事なども作為的にならないでその場に応じた身体的なリズムでこなせるようになりつつある。
部屋の掃除や庭の雑草を刈ったり、リスニングルームで音楽を聴くのも身体に便利な道具に半分は任せたような有様だ。掃除機や草刈機の2〜30分しか持たないバッテリーが切れたら作業は止めるし、CDやLPなどあれこれ選ばないでタブレット端末を使って音楽サイトの配信まかせで聴くようなことにも。
月々アナログ盤LP1枚ぐらいの料金でこの100年ほどの間に録音された世界中の音楽がほとんど聴けるようだ。ジャズやブルースやロックに限ってもとても聴き尽くせないほど膨大で、配信サイトのサーバーが登録リスナーの好みを学習しているようだから、楽曲のランダム配信サービスで聴き流すしかないといった塩梅だ。
YouTubeなどの動画サービスとなると、あまりにも広大でジャンルのつかみどころもないくらいだが、たまたま視聴した「HIMARI」こと吉村妃鞠のヴァイオリン演奏に老眼を見張った。独奏もオーケストラとの協演も素晴らしかったが、なんというか演奏する姿そのものが身体に響いてくるようなのだ。八歳の時の独奏ということだが、まさにそのメ若さモで精進してきた姿勢があってこそ成し遂げられたーーそれこそ身震いするような身体的存在感で裏打ちされたーー演奏姿勢に惹きつけられたようだ。
高度な情報化とともに、特定の情報だけを受け入れるオタクというスタイルが新しいサブカルチャーとなってきているのだろうが、マンガやアニメだけに限定されることなく、さまざまな“裏街道”の領域から“表街道”へと浸透著しいのが「推し活」文化の興隆ではないだろうか。
最上 舞踏の世界でも、だいたい稽古場を主宰してる人は男の舞踏家が多いんですけど、そうすると踊りをやるのって女の人が圧倒的に多いんですよ。男はポチポチしかいなくて、ほとんど女。そうすると主宰してる男というのは稽古に来てる女とみんな肉体関係を持って、うまいこと使って公演活動をやっていく。お金にならないから人を利用するしかないんですよね。だからほとんどの舞踏家はそのやり方でやってる。例外はほとんどないです。女の人ってその逆はできないじゃないですか。稽古に来る男と肉体関係を持てっていうのは(笑)。だからそれを男は当たり前にやってるんですよ。でも女の舞踏家は自立したら絶対違うやり方をせざるを得ないんですよ。だからどうしても真面目なんですよ、女のほうが。男みたいに崩れないんですよ。
押井 昔の革命家と一緒だよ。あるいは役者もそうだし、映画監督もそうだった時期はある。最近はそれで騙されるお姐ちゃんは滅多にいないから。だから映画監督は貧乏になったけど、昔は奥さんが焼き鳥屋やってるとかスナックやってるとか、奥さんが支えてる例がほとんど。食えないタイプの監督はほぼ例外なしにそうだよ。
(押井 守、最上 和子『身体のリアル』2017年10月刊@ Kindle Edition)
士郎正宗の漫画で『アップルシード』や『攻殻機動隊』を読んでいて、後者をアニメ化した『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』(1995年)で監督の押井守を知った。続編の『イノセンス』(2004年)も観たし、『うる星やつら2ビューティフル・ドリーマー』(1984年)や『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』(2008年)も観た。
草薙素子をはじめとした多くのキャラクターが電脳化[脳とネットワークの接続]されるだけでなく、全身義体化[身体の機械化]されているものだから、肉体と精神あるいは魂(ゴースト)との間の揺らぎの演出が、人間にとっての身体性を問うているようでなかなか面白かった記憶がある。
SNSで甲野善紀師や光岡英稔師の武術[学]に関わる発言を追っかけているうち、身体に関わるツイートをしている最上和子の言葉を見つけて追いかけるようになった。舞踏家であることはすぐわかったが、上記引用の「対談」を読むまでは、押井守と姉弟関係にあるなんてまったく知らなかった。
YouTubeでしか観たことのない舞踏家の姉とアニメ映画で知った映画監督の弟による姉弟対談は人間の身体[表現]をめぐって交わされる語りがユニークで面白いのだ。
最上 でも結婚するときは「自分はこれから舞踏をやるんだ」って決心はしてたんで生まれ変わった気持ちで、結婚するからにはお見合いだろうがなんだろうが、自分はちゃんと生活していくという決心はしてたし、そのときはできると思ってたんですよ。人生にはいろんな転換があって、そのときに「自分は違うステージに移ったな」というのは自覚していたので、普通に生活することはできると思って、相手を傷つけるとかそういうことは絶対しないと決めてたので「他人と一緒に暮らすんだから大変だよ」とか言われてたけど、全然大変じゃなかった。居心地がよかった。
押井 ひとりでのたくり回ってるよりはずっといいと思うよ(笑)。だからすごく落ち着いたよね。
(同『前掲書』)
踊ることというより身体で何かをすることに最初に関心を持っ[たされ]たのは小学校の低学年、当時住んでいた村の春の祭礼の獅子舞の踊り子を演っていた頃だろうか。小振りの模擬剣を手に二人一組で舞うのも中学生前までだった。一人で六尺余りの棒を使って獅子と戦う踊りができれば残れたのだろうが、あいにく自分には見込みがなかった。棒の扱いが上手い年長のお兄さんは生き生きとした身体のあつかいがほんとうにかっこよかった。
中学に入って部活で竹刀を振るようになったら、柔道をやっていた友だちから「お前のやっているのは棒振りダンスだ」などとからかわれた。130cmで30kgの小僧が振る正規の竹刀が長すぎてさぞおかしかったことだろう。公式の試合に出たりすると余計に笑われた。
庭で見かける祖父の薪割りを真似たくなり何度もやらせてもらった。そのうち薪の切断面にまっすぐ斧を当てられ[落とせ]るようになったときの身体感はやってみないとわからないことだった。年暮れの餅つきも試されたが、手がやしする人の掌が気になって杵をタイミングよく振り下ろせず、ぎこちなくなるものだから続かなかった。
チャンバラごっこもやったし、盆踊りにも参加したり、三角ベースの野球もやったりしたが、小・中・高ともに運動会は大の苦手になってしまった。文化祭や学園祭の出し物などできるだけ目立たないようにしていた。
それが夜学で通った短大の学友会で機関誌を編集・発行したり、ダンスパーティを企画して自ら踊ったり、一時期だが[短命に終わった]職場の軽音楽バンドのバックでリズムギターを演らされたり、意中の女を誘ったりするようになるんだから、自分の性分[思い込み]ほどあてにならないものはないといった身体感に目覚めていった。
最上 舞踏も身体だから、という点ではダイレクトなんだけど。直じゃないですか。自分自身だからダイレクトなんだけど、それを表現まで持っていくというのは同じように冷徹さがないと表現にはならないんですよ。だからそこのところでも苦労したというか。でも身体が好きでやってるので、その苦労も耐えられたかなって。味気なさがなかったんですよ。苦労だったけど。やっぱり言葉にはできない大変さなんですよ。普通の表現と全然違う。その違いというのもなかなか気がつけなくて、なんでいつまで経っても表現にならないんだろう、というのを考えていくうちに身体の特殊性というのがだんだん見えてきて。身体って道具を使わないじゃないですか。ほかの表現ってみんな道具を使うから、その違いがものすごく決定的で、身体を表現まで持っていくのはどういうことなのかというので10年ぐらい悩みました。しかも悩んだってすぐできるようにはならないんだけど、なぜほかの表現ジャンルと違う困難さがあるのかというのが、見極めるまですごく大変なんです。それがわからなかった。全然自分を見ることができないんですよ。作家が作品なんですよね、身体表現者って。だけど作品って普通は外にあるから自分で距離を置いて見れるけど、踊りって踊ってる自分の姿って永遠に見れないんですよ。ビデオで見るぐらいなもので、ナマというのは全然なくて、踊ってる自分が外からどう見えているのかというのがやっていてもつかめない。それがものすごく大変で。自分がやってるつもりのものと、外から見えてるものがものすごいギャップというか、そのギャップを埋めるにはどうしたらいいのかという方法もわからなかったし。いまでもほかの表現ジャンルに比べると見えにくいじゃないですか、舞踏って。だからそれは埋めきれないものとしてあるなとは思ってるんですよね。例えばすごい衣装をつけて目に見えるようにするとか、そういう極端なことをやらないと、やってることが見えないんですよ、身体表現って。フラメンコをやるとかバレエをやるとかなら、バレエだ、フラメンコだと言えるんだけど、舞踏の場合はなにをやってるのかが見てる人にわからない。見えるところまで行きたいんだけど、なかなかできないですね。
(同『前掲書』)
三十代半ばから夫婦でスキーやバドミントンをやり始めた頃だが、ビデオカメラで撮られた姿とそれを実感している身体感覚とのあまりの違いに戸惑ってしまった。ところが体型的には虚弱型から脱したように胸の厚みが増しただけでなく、いつの間にか二の腕にもたくましさが宿ったようでスーツ姿勢も整いつつあるようになった。
どうやら“中の上”くらいになったね、などと同僚から言われるようになっても、ビデオで観る自分の滑りやゲーム運びをしている姿とその身体使い感覚とのズレが無くなることはなかった。その一方で競技バドミントン経験者に気後れするようなことがなくなってきただけでなく、対戦機会を楽しめるようにもなっていった。
特定の技が技術的に上手くなることと身体的な上達とは方向性が違うような気がした。安全に楽しく滑れなかった、あるいは負けてしまったーー斜面や対戦相手ではなくーーその時の自分の身体の使い方の限界を脱却する方向性が見つかるような練習・稽古ができるようになれば、身体的な映像と実感との食い違いのバランスもよくなって、結果として難関斜面が滑れたり、勝てなかった相手に勝てるようになるのだった。
ところで夫婦の生涯スポーツとして長続きできたのはそのようなところにはなく、とにかくやっている間はあれこれの雑念だけでなく、あたかも言葉から解放されたかのようなひと時に、我を忘れていられるところにあったような気がする。
押井 そういうこと[空手との縁で身体感が変わっただけでなく体つきや生き方まで変わったこと=引用者註]があったりして、それこそ吉本隆明(思想家)じゃないけどさ、個としての自分があって、自己幻想と対幻想と共同幻想があってというさ。表現の根拠ってもちろん個にあるんだけど、それを実体にするためには社会性が必要なんだよ。共同幻想というどこかに乗っける部分がないと。承認される必要がある。わりとそういうところは若い頃からすっきりしてたんだよ、自分の命題としてはね。それがね、危うくなっちゃった(笑)。「これはヤバいぞ」って。肉体の危機であると同時に表現の危機になっちゃったんだよ。そのきっかけのひとつには姉ちゃんの舞台があった。やっぱり最初に見た公演が自分の想像したものとちょっと違ってた。もっと官能的なものだと思ってた。それが官能とかじゃなくて、なにか違うものが立ち現れてくる。見慣れない身体というか、それがね、ちょっとだけ見えてきた気がして、一瞬圧倒されかけた。だからと言って自分も真面目に舞踏をやろうとかは全然思わなかったんだけど。そういうのは無理だと思ってたし。
(同『前掲書』)
生の舞台を観たこともないものが言うのもなんだが、少しばかり最上和子の舞台の映像を観た感想としては、たった今立てるようになった赤ん坊が踊り始めたーーそんな初源性に立ち会うような身体感に接したことはこれまでになくて、既成の感情や言葉では語れないーー二度と見られ[たくも]ない世界が現前化しているとでも言おうか‥‥‥。
音楽を聴いたり歌ったしていて、幼児や大人が踊りだしたりするような身体からは想像もできない、おそらく前例のないまったく独自な身体による表現者なのだろう。
音楽を聴きながら踊ることをしないエネルギーでーーあたかも虫が蛹のようになったり、転がる石のような物になったりするかのようなーーどうやって身体を内在化させているのだろうか。
最上[前略]ほかの絵を描くとか音楽をやるとかいうのと同じにはやっぱり考えられないというのがあって、結構ここにたどり着くまでにすごい苦労したんですよ。というのは身体表現をやっている人って舞台が前提なんですよ。公演をやるというのが前提。公演のために稽古をする。今度こういう作品を作って舞台にかけるから、こういう稽古をするとか、お客さんが来て見てということがセットになってて普段の稽古をする。でも舞踏をやっていくと順番が逆だなというふうにだんだん思うようになっていって、最初に公演ありきじゃなくて最初に身体ありきで。最初に身体ありきの部分が武道にちょっと似てる。発表しようがしまいが、武道の人って死ぬまでお稽古するじゃない。
(同『前掲書』)
いわゆる“お稽古事”じゃない稽古場があって発表する舞台がある。それがすべてのようだが、まず初めに身体ありきというところは武道の立ち位置でもある。武道には試合や演武といった「舞台」がなく、生か死を分かつ立会いがすべてである。そこに向けての研究・稽古とはどのようなものーーあるいはことがら[形]なのか。身体を使ってなにごとか[型]を行い、何者かへと変化[身]し続ける稽古とは?
押井[前略]舞踏の場合は生きることとどこかしらイコールにならないと。それはじつは武道もそうなんで、いまの今野塾に入ってから「なるほど」と思ったんだけど、本来の沖縄の空手、沖縄の先生たちって「掛けだめし」と言って街頭でストリートファイトをやるという伝統もあるんだけど、一方で先生から聞いたんだけど絶対に人と立ち会わない。試合はもちろん私闘もしない。「なぜですか?」って聞いたら「怪我でもしたら稽古できなくなるじゃないですか」って。それを聞いて「あっ」と思ったんだよね。だからやっぱり試合に勝ちたいとか、自分の強さを証明したいとか、そういうことで確かめるものじゃないんだ、ということ。そう言い続けて50年も60年も普通にやっているわけ。だから稽古を見せないし、稽古に来る弟子からお金をもらわないし、それは沖縄の伝統なんだよ。夜に先生のところに来て、先生とふたりで稽古して帰る。提灯持ってね。それは沖縄の空手の本当の伝統なんだけど。とくにうちの空手はもともと沖縄の武士階級の教養なんだよ。だからやってて当然ということなわけ。それでいざ本当にそのときが来たら一撃で倒せる。あるいは自分の身を守れる。もしくは自分の大事な人を守れる。そのために延々とやるんだというさ。その延々とやっていくことのなかで、そういう言葉では言わないけれどたぶんある種の自己実現があるんだよ。[後略]
(同『前掲書』)
DVDで観ただけだから無知もいいところなのだが、光岡英稔師による韓氏意拳の站【木春】[たんとう]の稽古映像に唖然としたことがある。とても真似ようのできない身体動作の奥深さを垣間見たようだった。
ド素人の生半可な分け知りコトバを許してもらえればだが、おそらく生きたテンセグリティ構造のバランスを呼吸している身体ーー表現と言ってしまうと嘘くさくなるーー動作をどうやって体得されたのだろうか。一見静止しているような身体の動きの中に、緻密な身体操作と意識の運用が含まれているだけでなく、それらを統合した身体全体の高度な動作の稽古のように観えたのだが。
最上和子の稽古場の映像[静止画は別として]は観たこともないのだが、ユーチューブで観た舞台上の身体表現だけでなく、ツイッター改めXでの「ツイート」にも、計り知れない器としての身体を察知する言葉が息づいているようだ。
昨春にヒットしたテレビドラマじゃないけれど、多様性が叫ばれるほどに分断と対立が忌避されるのは、人間は分かり合えるという前提が疑われもしていないからじゃないのか。言葉への一方的な人間側からの信頼だけはあるのかもしれないが、はたして言葉からの人間への信頼はーー“令和の米騒動”と称して本来ならば非常時の「配給」ための「備蓄米」を¥2,000.-/5キロで売りさばいたりしてしているご時世にーーあると言えるのだろうか。言葉を人間に限定せずに世間にも属するものであると見なせば、世間はそれほど人間を信じていないのではないか。(2025年6月20日記/27日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(41)あるいは〈界隈〉としての身体��
古い日本語の「からだ」というのは死体という意味でした。
生きている身体は「み(身)」と呼ばれ、それは心と魂と一
体のものでした。やがて、生きている身体が「からだ」と呼
ばれるようになったことで、からだは自分自身から離れて対
象化されるようになります。そうすると自分自身との一体感
が薄れるので、専門家である他人の手に委ねても平気なよう
になるのです。
それだけであはりません。「からだ」の語源である「殻」
のように、自分の周囲に強固な境界を設け、他人との壁を設
けるようにもなります。
(安田登『日本人の身体』ちくま新書、2014年9月刊、10頁)
武道にも舞踏にも縁のない身体にとっても、思いつく限りの身体的あれこれすべてはとどまることがなく、過ぎ去るようになっていて、そこのところでいまここにこうして老いつつある身体[状況]をそのまま肯定するように暮らしているだけだ。受け身的であるとしても積極的でありたいし、世間に当たり負けしないような身体性を稽古するしかなかろう。
歳とともに何かができたりできなかったりする前に、立つこと歩くことそのものがおぼつかなくなるような気づき。一昨年からの二度の長期[短期的に車椅子使用]入院がそうさせているだけでなく、加齢による身体的な衰えが身体的な自覚作用の兆しに重なるような感じもする。
高村光太郎の詩「道程」で出会った「父」のイメージを黙って受けとめるしかない我が身だが、父親がいない家庭は不幸でもなんでもない。だが父親の不在ということは身体的にどういうことなのかという問いが立てられるかもしれない。家族の生と死をつなぎ合わせるように。
日本統治時代の京城[現ソウル]が生まれ故郷の朝鮮には「病身舞」という難病などの病身を真似た踊りがあるそうだが、それは死者との交流によって病身が生じる踊りではないだろうか。
土方巽日く《舞踏とは命がけで突っ立っ た死体である》というのは、自分の中から《人形》を取り出すような踊りになるのかもしれない。最上和子によれば「新しい頭脳が欲しい」と言って吉本さんに会いたがっていた晩年の土方巽はそれも叶わずに亡くなってしまったようだが‥‥‥。
そう言えば知り合いの舞踏家が吉本隆明さんに自分の踊りを見せた時、吉本さんは「書である」と言っていた。書道の書のこと。吉本さんはほんとに鋭かった。ひじかたさんの著作を読んで「自由に見えるけど実は不自由な言葉」と言っていた。
(最上和子@ツイッター改めX2025年7月4日)
家族を振り返ってみてもある時から、屋内を歩くのに杖を借りるようになった祖父がやがて這うようになったり、壁や柱などを伝い歩きするようになった母がまたたく間に車椅子の人になったり、まるで老いの坂道を転がるような成り行きまかせ、寝たきりになりそうな暮らしを見守るしかなかった。
数年前には亡妻とタクシーを使わないと通えなかった近所のかかりつけ医のところへ、一人暮らしになった今はなんとか自転車で往復できるようになってきた。買い物は歩きか自転車かお天気次第だ。あとは状況に応じてバスやタクシーを使っている。
入院中のリハビリの“自転車漕ぎ”が面白くもなんともなかったのは、病み上がりのせいでペダルを“踏む”のか“漕ぐ”のかがはっきりしていなかったからだろう。
自転車に乗れるようになって第一の気づきは、ペダルを踏みっぱなしで足を動かす必要がなく、ペダルが頂点を過ぎたら前45度までの間を加重した足裏で漕ぐようにすれば良いのではないかということだった。そのように両脚を操作し続けるならば、力まずともぐいぐい加速するようでリズム感のあるサイクリングが楽しめた。
カービングスキーに乗り換えた頃の妻が、足を踏み換えるというよりも左右で漕ぐようにすれば乗りやすいといったことがあったが、そんな身体的な気づきに似ていなくもない。
あれこれいつまで続くかわからないが、とにかく年寄りになったら何事も身体の時間的なスパンを長くしないよう、できるだけ短くして〈いま・ここ〉の動きができればできればそれでよしとするしかない。中学時代の剣道の部活はいつも瞑想から始まったが、そうすることによって雑念を振り払いーー現在的には溢れる情報をそぎ落とす方向で身体周りの澄み切った空気を呼吸しーー必要最小限の情報で生きられればよい。
訓練や鍛練とかではなく、その時々の老体としての身体内を観察し、感じたところから稽古できればよいのだ。ネットやテレビに溢れる老化対策などとは縁のない暮らし。
心不全とその手術による処方薬をありがたく服用させてもらっているだけ。よそ様の知識や知恵そのほか外部的なものに頼っても、当座は良いかもしれないがいずれ借り物の効力は失せてしまう。
風邪で熱っぽいからといって直ぐに解熱剤に頼ったりせず、とりあえず身体を休めて上手に経過させるのが得策だろう。病因を軽くみてはいけないが、身体に備わっている免疫系も含めた自然治癒力も大切にしたい。外から余計なことをすればするほど、かえって自前のシステムが混乱したり、その働きが鈍ったりして自立性が損なわれるのではないか。
祖父や母の晩年とは違って大病を患ったりしている我が身だが、とうに「立派な後期高齢者」[掛かり付け医の言い草]ともなれば、いよいよもって頼れるは衰えゆく我が身体のみという一人暮らしだ。玄関の下駄箱の上に縄文の土偶[遮光器土偶のレプリカ]を飾っているが、広大な宇宙の片隅にいながら秒速30kmで堂々巡りしている惑星上の身体の映しのように見えることがある。地球の動きがもたらす季節と身体の関わりなど、見落としてきたこともいっぱいありそうだ。
いつの間にか自転車に乗れたりスキーで滑れるようになったりしたみたいに、老いゆくその時々の身体にうまく乗ることーードライビング・マイ・ボディーーが自力でできていればよいのだが。
心臓手術由来の身障者[要支援1]認定とはいえ、できるだけよそ様の手助けが最小限になるように暮らせる方途を見出すーー身体的な稽古が日常的な場となる暮らし。
年老いたからというのではなく、幼少の折々から一身上の来し方行く末なんてはじめから決まっているのではないかという思いが吹っ切れない。そうだからこそ生き/生かされている身体であれこれ観察した動きを試みるしか生きる方途は見つからないのではないか。
亡くなる前の小田嶋隆が病床で「現状は、ふくらはぎが細くなりすぎていて、たとえば『背伸び』(直立した状態から両の『かかと』を浮かせること)ができない。とはいえ、『蹴り』を意識した歩き方を心がけると方向性がずっと安定する。まあ、地道に歩くしかないのだろう。今年気づいた一番良いことかもしれない。」[@ツイッター改めX2022年1月5日]とつぶやいているのを見て、それはないだろうと言いそうになったことがある。
「地道に歩く」には、床を蹴ったりして重力に逆らうことなく、立った身体を前に預けるように傾けさえすれば、ひとりでに足が前に出るのにまかせるしかなくなる。人は老いるほどに本能的に倒れることを怖がるようにできているから。
前に倒れようとする身体に働く重力と慣性にまかせーー[地面を]蹴って踏み出すことなくーーひとりでに前方へと交互に踏み出る足に乗り続けるだけじゃないのか。[もちろん小田嶋隆のコメントに半畳を入れるような野暮なことはしなかったが。]身体的な環界との関係において足はもっぱら空間的に関わるだけだが、手は時間[了解]的に関わろうとしている。急な坂道や険しい階段などでは手足を使って身体を上げ下ろしするというより、手は遊ばせたままジグザグに歩くようにして身体を通り過ぎさせるようにすれればよいことになる。
小田嶋隆が身体的に、「歩くときに左右にフラつくのは、平衡感覚よりはむしろ筋力(特にふくらはぎ)の問題であったこと。歩くのには踏み出す動作と『蹴る』動作が必要なわけだが、入院やらでふくらはぎが衰えていて、『蹴る』ことができずにいた。このため方向性が定まらずフラついていたのだった。」[@同前]としても、まさに「左右にフラつく」身体的な現状をそのまま肯定するように、その「フラついて」いる「身体」を歩きたい方向へ傾けながら交互に足を前へ置き続けるのが楽だし、自然ではないか。
同じく「あたりまえの話ではあるのだが、踏み出した足の逆側の足(後ろに残った足)で「蹴る」動作を怠って、踏み出した足を上から地面に「置く」だけの歩き方を繰り返していると歩く方向は安定しない。普通に歩いていたときには、こんな細かいことは考えるまでもなかったのだが。」[@同前]とのツイートから、あらためて普段は見落としがちな身体観察を深める独り稽古の大切さを教えられた気がした。たとえ気づいた判断の方向性が真逆だったとしても。
中学生時の部活の剣道でも、社会人になってからコーチとして関わったスポ少や中学のバドミントンでも、いわゆる床を蹴って踏み込む動きが“あたりまえ”というか“常識”のようになっていた。練習生がくるぶしを疲労骨折したり、床を踏み抜いてかかとが炎症を起こしたりしてもーーほとんど当事者の肉体的弱さとみなされがちでーー原因となった練習方法が見直されるようなことはなかった。
他人の知識の寄せ集めのような常識など、はじめから疑ってかかったほうがいいのだが、これまで体育館の子どもたちや教室の学生たちに接してきたなかで、はたして彼ら彼女らに身体的な気づきはどのように訪れていたのだろうか。
普段から膝を軽く曲げた状態で動くような習慣を身につけていれば、いざという時に膝に“浮き”をかけるように身体を動きたい方向へ傾けるだけで、床を蹴るよりも素早く動けるだろう。
揺れる混雑時のバスや電車に乗り合わせても、踏ん張ったりしないで膝を緩めた姿勢で立つのがより揺れを吸収しやすい身体動作になるはずだ。
かって日常的に習い覚えた身体使いじゃどうにもならなかったスキー板上の姿勢やバドミントンラケットを握った腕の振り方を工夫するなど、身体的な気づきを探すのが面白かった。
スキーでさまざまに変化する斜面を滑降しているときの身体的な動作としてだが、進行軸の斜度に応じて下半身と上半身を逆方向へ“縒り”を入れ替えながら、そのバランスを崩さないよう膝でコントロールしていた。やったことのないテレマークスキーヤーの身体操作はどのようなものなのか、眺めていただけだからよくわからなかったが。
両手で握った木刀を振ったりしていても内股加減の両脚から背中にかけて逆方向の“縒り”が働いているのを感じることがある。
近年の長期入院中に身動きもおぼつかなく立つのもやっとになったとき、肝臓を時計回りに心臓を反時計回りにそれぞれ動かすような体幹の“縒り”でーー車椅子に頼り過ぎることなくーーなんとかその場を持ちこたえられたようだった。
紙で拵えた紙縒りが以外と丈夫なように、使おうとする体幹や腕に逆方向の“縒り”をもたせた身体操法に気づいたのはいつのことだったろうか。
投げたり打ったりするのに手首[リスト]が強いとか言われがちだけど、腕の骨の構造上からみてもそんなことはないだろう。両肩を開き加減にして首の付け根から手首までの腕の回外と回内がうまく噛み合うような“縒り”のタイミングと距離感が取れればいいスイングができる。
努力したり稽古熱心になリ過ぎないよう、身体的に新たな気づきが得られるようなひとり稽古をするしかない。
老化する身体をどう経験していくか、老いゆく身体知が働くには、それが必然性をともなった行為であるかどうかが問われよう。
田舎の自然の中で遊んだり、祖父と暮らしに必要な仕事をしていた当時は、おそらくすべての動きに必然性があり、できるだけ疲れないように全身をくまなく使っていたように思う。身体の一部に負荷が集中するような単純な反復動作はやっていなかった。
〈老い〉と〈衰え〉が混濁しがちな老齢化においてはなるべく自然に抗うようにして生きるしかなく、いつ訪れるかわからない〈死〉など考えようもないのではないか。
人それぞれが持つ個性に頼ることなく、個人的な身体ではないーー〈人間が持っている身体〉を拠り所にーー独り稽古で身体というすべてがつまったものを探らせてくれる。[下線部傍点]
自己を生きるというよりは自己の身体を生きるにはどうすればよいのかということだ。必然性によって身体は瞬間的に生命力が発揮されるが、必然性のない動きをいくら繰り返しても断片的にしかならず、眠っていた身体を呼び覚ますーー古い身体から新しい身体が目覚めるーー稽古にはならないだろう。単に動かしたり、繰り返したりすることは身体を生きることにはならない。
「老いてみないとわからないよ」とは、一つ屋根の下で暮らした祖父や母の老いつつある口癖のように聞こえたが、実際に老い年頃になった自分には一体何が分かったといえるのだろう。
吉本さんの〈老体論〉[参照:「街道と民家(18)吉本〈老体論〉拾い読み」]は自らの老い〈身体〉を奮いたたせるような言葉に満ちている。
普段の暮らしで「これが自分だ」と感じたり、看做したり、考えているときの「自分」は、いったいどういう身体として存在しているのだろうか。身体内に目を向けて観えてくる自分ならざる自分と対話するようなきっかけを日々の稽古にすればよいのだ。
このあたりのことを光岡武学では「たしかに型は“私”ではなく他者であり、そこから得られる『力』は他力なんで、その力が味方をしてくれているということを大切にした方が『型稽古』としては成立します。」[光岡英稔@ツイッター改めX2022年1月9日]と指摘されていた。武術的な素養のない自分には難しすぎるが、老いることや病を受け入れることも稽古のきっかけにはなる。そして、いま・ここの〈土地〉で生きているということも。
最上[前略]人間の身体というものも土地と離れたらもうそれは人体ではあるけれどもう身体ではない。トータルな身体ではないと私は思っていて、切り離された途端に身体はかなりなくなっちゃう、希薄になっちゃう。舞台というのは切り離さないと成り立たないから、それがなんか自分にはちょっと違和感があったのかなと思って、土地と身体をもう1回繋げたいという気持ちで始めたんだけど、それがやっていくうちに欲が出て、土地と身体を繋げるということを具体的に思想的な課題みたいなものにしていけないかな、というふうにだんだん思うようになって。松尾芭蕉が「奥の細道」でいろんなところを旅するじゃないですか、そこで俳句を詠んで。それまで芭蕉のことって考えたことなかったんだけど、なんで俳句を詠むのに芭蕉はあんなに苦労して旅をしたんだろうと思って、ちょっと調べたりとか、そうするとその土地のなか、言葉というのもその土地のなかで、あれは枕詞の地を巡っていくわけですけど、枕詞というのは土地ですよね。そのなかで新たに歌というのをとらえ直したいとか、あと言葉を土地に着地させたかったのかなという気はすごくするんです。だから言葉それ自体が独立していると、これもまた身体と同じでちょっと空疎な感じが彼はしたんじゃないかなと。そういうことを考えると土地を巡ってそこに身体を置いてみる行為を、現代版「奥の細道」じゃないけれどなんかそんなような形で、なんかしら成果を生みたいという欲も出てきたんだけど、[後略]
(押井 守、最上 和子『身体のリアル』2017年10月刊@ Kindle Edition)
「東京巡礼」という舞台は見たことがないけれど、たまたま外で稽古をやったらそれが土地を場とした身体表現による巡礼という形で立ち現れたということなのだろうか。アジアというか日本において土地に根ざした身体の動きというのはどのような歴史性を担ってきているのだろう。
最上 私なんかでもパカパカ動くことはあるんですけどーー舞踏やってるとね、パカパカ動けないだろうと思う人もいるんだけど全然そんなことはなくてーー身体の内部というのは動きが多ければ多いほど止まって、空疎になるんですね。それで外がゆっくりでほとんど止まってる状態で動くと身体のなかがものすごい動く。逆なんです。この逆の関係がすごい面白い。だから大きい動きをだんだん小さくしていくという稽古もするんですよ。大きく動くのと同じエネルギーをもって小さく動けということをするわけ。最初は半分、これを同じエネルギー量でやる。次はこのぐらいにする。そうすると小さくすればするほど身体のなかがどんどん濃くなるんです。これはやるとしびれますね。人によっては身体のなかの動きがはっきりわかるのでものすごい喜ぶ。だいたい東洋的というか日本舞踊とか太極拳もそうだけど、ベテランになればなるほど動きが小さくなる、動きが小さくなればなるほど身体のなかの動きがはっきりわかるようになるんです。身体のなかがどんどん充満して濃くなっていくので、日本の身体の使い方、日本舞踊とか能なんかもっと典型的だけど、動きがゆっくりになって小さくなればなるほど存在として濃くなるんですね。身体のなかの密度が濃くなるというのは存在として濃くなるということなので、西洋の哲学でいう「存在」ですよ。存在としてどんどんなかが濃くなる。西洋の哲学は存在というのを思弁として言ってるわけです。言語として論理として閉じた世界で、例えば強度とかいういろんな概念を使っているわけだけど、それを日本の芸能というのは実際に身体でもってやるというところが西洋と違うと言われています。[後略]
(同『前掲書』)
かって竹刀や木刀や真剣[父の形見の日本刀を式刀にしたもの]を速く振ることばかり考えてやっていたことがあったがそのうち虚しくなってやめてしまった。今じゃゆっくりというか、ゆったりというか、とにかく遅くとも身体内に充足感というかーー未知の手応えが生じるような振りを摸索しているのに未熟のまま、幾つになっても身体観は見極めがたい。
犯罪ドラマとしての『攻殻機動隊』などは〈身体〉の捕物帳としての面白さが際立ってーー一時代を集約するような恐ろしい犯罪[悪事]とそれを追うものとを隔てる奈落の振幅ーーいたように思うのだが‥‥‥。
舞台で身体表現を追求している姉の最上和子との対談で、アニメ映画『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』(1995年)で身体の電脳化と義体化による魂[殻]を表現してきた弟の押井守がその9年後に公開した作品の身体観について語っていた。
押井[前略]『イノセンス』のときははっきりそう思ってた。「ああ、私たちはもうサイボーグなんだ」というさ。ようするに外部記憶装置もあれば並列化もしてるし、自分の固有性の根拠ってどこにあるんだろうというさ、そんななかで「もしかしたら最後にすがるべきなのは動物なのか」って思ったわけだよね。無意識に生きている命というのはすごく特権的な感じがしたわけよ。自分を疑わないしさ。そして他人を信じるということを躊躇しないし。まあ、言っちゃえば『イノセンス』ってそれだけの話なんだよね。冷たい身体を選ぶのか、獣の匂い立つような身体を選ぶのかというさ。でも人間はたぶんどちらにも行けそうにもないというような、言わば立ち尽くしちゃう物語みたいなことを漠然と考えたわけ。もうひとつは男と女の、実態がなくなっちゃった女を愛せるのかみたいな話。ネットにのみ込まれた女を思っていまでも犬と暮らしている男というのはさ、いまふうのハードボイルドとしてはいいのかなというさ、そんなふうなことをやってみたわけよ。そしたら結果的にはボロボロの身体だけが残ったという(笑)。現実過程として言えばね。
(同『前掲書』)
誰にとっても〈いま・ここ〉の否定できない身体そのもののようだが、なんだか都市化の過程で引き裂かれつつある身体観とでも言えばいいのだろうか。都市という名の外部記憶装置に接続したみたいに、まるで「こころ」も「おもい」も置き忘れてきたみたいな身体はいったい何処へ行こうとしているのだろう。
その個人的かつ社会的な両面ともに空っぽにすることによって目指すものはあるのか。もし〈武と舞〉の間を行き来する「こころ」は意識のようであり、そして「おもい」は無意識のようであるならば、その身体はいかなる「殻」を纏い、どのような「魂」を宿し、究極の動き[舞踏]に至るのだろうか。あるいはまた思いがけず心を見失って母体回帰するような事態にも。(2025年7月13日記/15日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(42)あるいは〈余白〉の響き��
堀部 僕の好きなドラマーに、スティーブ・ガッドという人
がいるのですが、僕もドラムをやっていたので、本当すごい
なと思って、ずっと聴いて追い求めていたいたところがある
んです。彼と一緒に演奏した方の話がおもしろくて、スティ
ーブ・ガッドの何がすごいかというと、ポケットを用意して
くれる、と。つまり「そこが今だよ」という合図をしてくれ
たり、「君が今表現してくれているのは、こういうものなん
だよ」と、常に信号を送ってスペースを用意してくれている
感じがするそうなんです。
だから、スティーブ・ガッドのドラムって、実は演奏中、
そんなに大きな音を出しておらず、また音が透き通っていて、
淡く薄い印象もあるんです。反対に他のメンバーのスペース
を用意してくれていて、そのバランスの美しさによって感動
するんです。
(堀部安嗣・中島岳志『建築と利他』ミシマ社、2025年5
月刊、71頁)
田舎暮らしで「うち」の人と「そと」の人が出会うのが庭であり縁側であったように思う。田舎の庭から祖父と母が選んだ庭木とともに郊外に引っ越したらそのような機会も稀になってしまった。これまで町内の老人クラブにも縁がなかったから定期的な世間話の機会など滅多にない。高知の松岡さんに『猫々堂』HPアップデート作業連絡その他の手紙を書いたり、たまには娘とラインで世間話を交わしたりしているこの頃だ。自作HPでの連載も《タイトル》から脇道に逸れがちで道無き道を手探り足探りしている老いぼれの徒然に過ぎない。
暑さ厳しい夏の買い物も大変だが、近所で食料品や日用雑貨が賄えた小商いの店が次からた次へと姿を消し、多少離れていた立地のスーパマーケットはコンビニエンスストアに入れ替わってしまっている。ちょっとした小間物が街中の百円ショップに出かけないと手に入らなかったりする。車のない暮らしだとかさばる日用品などはもっぱら通販頼みになってしまいがちだ。
買い物などの行き帰りに見慣れた住宅が跡形も無くなってしまった更地に、瞬く間に出現する一戸建て住居に民家の面影はほとんどなくなってきている。コンクリート打ちっぱなしか砂利を敷いたカーポートが玄関に通じているだけで、庭がないから縁側もないといった具合だ。
民家風の屋根らしい屋根もなくってしまったようで、軒下という内と外の境目も雨宿りなどできないほど狭まり、巣作りするツバメが出入りする軒や庇も見られない。作り付けの窓にも庇がなかったりする。
のっぺりとした箱型の作りに片流れの傾斜かもしくは切妻風の蓋をしたような、いかにも外的自然を遮断したみたいな装いなどどこまで住人の好み[注文]が反映されいるのだろうか。はじめから立地に馴染むような外観など無関心なのかもしれない。旧来の家並みに溶け込みにくいオブジェのような新興住宅の住み心地はどうなんだろう。多様化する一戸建ての域を逸脱しているように見えなくもない。
「早く、安く、手軽な」“ファスト建築”というのは公共的な箱物や商業施設のことかと思っていたが、どうやら住宅建築もそういう流れに染まってきていると見てよさそうな気がする。
今じゃ近辺で庭や格子のある民家は少なくなり、住人がいなくなった廃屋状態の民家は見かけるが、土木の原点みたいな〈身体生活〉の入れ物としての建物とその土壌などーー身体の内と外のバランスが整うようなーー気候風土や生活史を見直した〈更地〉に建つ家とはどのようなものになるのだろう。
ジャイブルからウダイブルに向かう機内で、ガイドのモハメッド君が「これ見ましたか」とヒンドゥスタン・タイムズをさし出した。江藤淳の自殺が報じられていた。一瞬胸が冷えこんだ。初めて石原慎太郎に紹介されたときの不安と自負のないまぜになった表情がありありと蘇った。私たちはまだ二十代だった。前の晩にホテルで読んだハンナ・アーレントの手紙の一節を思い出した。「ーー死がこわいとも思わなかったけれど生もなかなか美しいと思い、喜んで生を受け入れようと思ったことです。」(佐藤佐智子訳による)自動車事故で入院中に書かれたものだが、江藤さんはもしかすると、生を終わらせることで「喜んで生を受け入れた」のかもしれないと思った。「生もなかなか美しい」といういささかもったいぶった言葉は、ここインドでは使うことが憚られるけれど。
(谷川俊太郎「ある日(一九九九年二月〜二〇〇一年一月)」/『ひとり暮らし』草思社、2001年12月刊、122頁)
いつだったか郊外をサイクリング中にだが、地元の旧家らしき屋敷跡に日本家屋の伝統を受け継いだような新築住宅に行き交ったりすると、なんだか家族代々の生き方が受け継がれているというより、大家族制の崩壊の象徴のように見えてしかたがないことがあった。かって受け継がれてきた普通の建て方が特別注文仕様になってしまっていることにも気づかされたが。
いつの間にか大工の棟梁が仕切っていた日本家屋の建て方が過去のものとなり、見るからに「早く、安く、手軽な」建て方が一般的な庶民の住宅仕様の標準みたいになってしまったような一戸建て事情だが、とりあえず揺らぎつつある核家族の寝起きを受け入さえできれば民家として十分ということなのだろうか。
一軒の民家が取り壊された跡地に売り出された数戸の建売が完売に手間取ったりしているようだが、はたして「喜んで生を受け入れ」る家族の居場所たり得る物件なのかどうかが危ぶまれている見本のようだ。現行の消費社会の更新にともなって高度情報化を軸とした文化・文明が高度になるにつれ、これまでの家族の機能や家庭というものも結婚制度を含めて様々な面で変わっていかざるを得ない。日本の人口における少子化や結婚の減少傾向など、今のままじゃ誰にも止められないのではないか。
標準的な木造建築の耐用年数に近づきつつある我が家も、老朽箇所や雪害による修繕だけでなく、屋根を葺き替えたり外壁を新しくしたりあれこれ手入れを施してきている。
家屋のアフターケアを含めて世話になった施工主の棟梁が亡くなられ、その後出入りした内装その他いろんな業者から「今じゃありえない資材が使われているけど、どこの大工に建ててもらったの」などと尋ねられたりしたが、現行耐震基準前の建築[昭和47年]当時はあたりまえだった資材が用いられているに過ぎない。
昨年の能登半島地震の揺れも持ちこたえた陋屋だが、ゆくゆくは娘夫婦にでも住んでもらえたら言うことはない。一緒にライブに出かけたり二人とも音楽好きのようだから、家に居ながら聴きたくなったらいつでも視聴できる部屋があるのも暮らしの余白になるのではないか。
ひとり暮らしになる前の最後になったジャズライブ、夫婦ともに元気だった10年ほど前だが、以前から贔屓にしていたドラマーのスティーブ・ガッドが来日ジャズバンドの一員として富山にもやって来るというので勇躍して出かけたことがあった。妻が買ってくれた前売りチケットの二枚がぴったりドラムセットの真ん前だったのにはいささかたじろいでしまいそうな心地だった。
後日わかったことだが僕らが座っていた席から三列ばかり後ろの席に、娘が年季の入ったアマチュアドラマーに誘われて聴きに来ていたとのことだった。お互いに気づかないほど当夜のライブに入れ込んでいたのだろう。
富山公演のセットリストはAIに尋ねてもわからなかったが、当夜の目前でスティーブ・ガッドが演奏していたドラムセットはヤマハの新しい「Recording Custom」で、なんと実践で使うのが初めてだったことを教えてくれた。
2025年にも自身のバンドでジャパンツアーをやるらしいが、現在のところ富山公演は発表されていないとのことだった。前回の富山公演は入りが悪かったからしょうがない成り行きとしても‥‥‥残念。ライブ録音による『Omara/Michael Blicher, Dan Hemmer & Steve Gadd』(c2018 C-Nut Records)など、饒舌と寡黙の間を余白で埋めていくようなドラミングに聴き惚れる。
アップルミュージックでスティーブ・ガッド・バンドの2025年発売[All That Matters c2024 Broken Silence Records / Leopard]アルバムを見つけて聴いたばかりなのだが、なんでもアップルミュージックの10周年記念とかで、当方のリプレイ:オールタイムのリスニング履歴としてスタートした1曲目が谷村新司の「悲しみの器」だったのには我ながら意外だった。さらに100曲のリストの上位がほとんど近年他界したミュージシャンの演奏か、もしくは追悼関連曲目で占められていたことも予想外だった。
谷村新司さんの作詞作曲で、森進一が歌った「悲しみの器」。佐野さんと別れたばかりの頃、信州かどこかをドライブしてたらカーラジオから流れてきて、不意を突かれた泣けてきた。〈あふれるほどの 悲しみだから/こぼしてしまえたら いいのに/ひびわれすぎた ガラスの心 (中略)はじめて泣いた 僕は夢の中で〉‥‥‥。曲も気に入って、それを歌おうと思って練習したのが、僕のカラオケの始まりだったかな。レバートリーは狭くて、あと十八番は映画の「男はつらいよ」の詩人版で「詩人はつらいよ」ってパロディーを歌って、けっこうウケる。それから賢作がアレンジした「鉄腕アトム」。これはどこで歌ってもはずさない。
(語り手・詩 谷川俊太郎 聞き手・文 尾崎真理子「第5章 無限の変奏」/『詩人なんて呼ばれて』(新潮文庫)、令和6年8月刊、518頁)
昨年の谷川俊太郎の訃報を知って追悼するみたいにアップルミュージックで何度か繰り返して聴いたりしていたことを忘れかけていたなんて。
吉本さんが亡くなられた頃によく聴いていたのは誰の何だったろうか。ジョニー・キャッシュの生前最後[2002年11月5日]にリリースされた『American IV: The Man Comes Around』だったように気がする。具体的な関連性などはないのだけれど、「老い」と「死」を織り込むような歌いっぷりがなぜか吉本さんが亡くなられた季節を偲ばせるような気がしてならなかったのだ。
いつも土曜の朝の定番になっているとある朝のFM番組で渋谷陽一を追悼して「Summer Madness / Kool & The Gang // Gold」(This Compilation (c)2005 UMG Recordings)が流れてきたときは、まっさきに吉本さんのインタビュー本『吉本隆明が最後に残した三十万字』上・下巻のことが思い返された。
高橋源一郎がどこかで書いていたように、渋谷陽一も十代で吉本さんの著作と出会っていたようなので、吉本著作とのメディア交錯的なメモを書きだして置こう。
《渋谷陽一活動メモ》 《吉本著作抜粋メモ》
1924年 誕生(11月25日)
1951年 誕生(6月9日)
1952年 詩集『固有時との対話』発表
1953年 詩集『転移のための十篇』発表
1956年 『文学者の戦争責任』発表
1957年 『高村光太郎』発表
1961年 同人誌『試行』創刊
1965年 『言語にとって美とは何か』発表
1968年 『共同幻想論』発表
1971年 ミュージックライフ誌にて音楽評論家デビュー 『心的現象論序説』発表
1972年 洋楽ロック批評・投稿誌『rockin'on』創刊 『敗北の構造』発表
1977年 『rockin'on』月刊化 『初期歌謡論』発表
1982年 株式会社ロッキング・オンに改組 『空虚としての主題』発表
1984年 『マス・イメージ論』発表
1985年 テレビ番組構成者キャリア開始 『重層的な非決定へ』発表
1986年 邦楽ロック批評誌『ROCKIN'ON JAPAN』創刊 『音楽機械論』発表
1989年 映画批評・インタビュー誌『CUT』創刊 ←「消費の中の芸」連載
1994年 『季刊渋谷陽一BRIDGE』ほか創刊 『ハイ・イメージ論』福武文庫
1997〜2000年 大塚英志との対談で『新世紀エヴァンゲリオン』に言及『だいたいで、いいじゃない』
1999年 総合誌『SIGHT』創刊 ←「自作を語る」「古典を読む」「時代と向き合う」など連載
2000年 「ROCK IN JAPAN」初開催 『写生の物語』発表
2007年 音楽情報サイト「RO69」(現rockinon.com)オープン
2009年 第19回宮沢賢治賞受賞
2010年 「JAPAN JAM」初開催 『ひとり:15歳の寺子屋』発表
2012年 脱原発フェス「NO NUKES」初開催 逝去(3月16日)
2014年 美術誌『SIGHT ART』創刊
2022年 IP事業「ラプソディ」スタート
2025年 逝去(7月14日)
『吉本隆明 自著を語る』あとがき
渋谷さんとのこの対話の本は、わたしにとっては、文学と思想のあいだについて、戦後のかなり初期から近年にいたるまでの私の考えたこと、書いたことの主脈の変遷を一目でたどれるように択ばれている。渋谷さんのロック音楽家とのインタビューや論議の色合いの面白さは雑誌『ロッキング・オン』時代から読んでいて(よく)知っていた。関連して言えばこの本の対話でも私の本をていねいに読み直して要点を押さえていることが直ぐに分かるほど、無駄のないさばき方で、わたしは安心してそれに乗っかればよかった。訂正も(一個処だけで)必要なかったことを告白しておきたい。わたしに対してへり下っておられるところが気にかかった唯一の点であった。
定かではないが、わたしが渋谷さんにはじめてお目にかかったのは、通信社の記者につれられて、「ゼルダ」という女性だけのロック・グループのライブの会場だったと記憶している。それかあらぬか歌も身のこなしも見事だった忌野清志郎たち、ビートたけしたちのライブにも何回か出かけた。わたしは音痴のせいで音のほうは駄目なのだが、雰囲気に惹かれて、学校筋では後輩ともいえる遠藤ミチロウさんたちのグループ「スターリン」のパフォーマンスにも度々出かけた。聴衆の中に頭から先にダイビングする姿は忘れ難い。この本もまた渋谷さんが頭からダイビングしていただいた賜物だと言っていい。感謝は尽きない。
二〇〇七年五月
(『吉本隆明全集36 2007〜2012』晶文社、2025年2月刊、721〜722頁』)
渋谷陽一の訃報を知った後ではまるで追悼文ようにも読めてしまう「あとがき」だが、たまたまネットで山川健一の「追悼文」を読むことができた。
僕は23歳、渋谷さんは25歳だった。
作家と「ロッキング・オン」の編集長の出会いといった感じではまったくなく、この間まで学生だったロックファン同士の付き合いが始まったーーという感じだった。
「俺のロック評論は、吉本隆明のロジックでロックを対象化しているだけだよ」と、いきなりコアな秘密を開示してくれた。
そして、こう言った。
「ユングの『心理学と錬金術』を読め。それからソシュールの言語論な。絶対に役に立つから。それで、『ロッキング・オン』に原稿を書いてくれ」
レッド・ツェッペリンが「天国への階段」で音楽の神を肯定したように、渋谷陽一はユングの集合的無意識を信じている人だった。
そして何よりも貴重なアドバイスは、こうだ。
「文芸誌の新人賞の効力なんてせいぜい1年しかもたないからな。急いでロックライクな小説を書け。時代のブーストが効 いているうちに、俺たちのようなロックファンに向けて立て続けに小説を書け」
兄貴分の渋谷陽一のアドバイスを、天邪鬼の僕が忠実に守ったのは、彼に同じ匂いを嗅ぎとったからだろう。NHKの FM番組にも、何度も呼んでもらった。打ち合わせも台本もないそのラフなスタイルを見て、これなら俺にもやれそうだなと思った。
初台にあった僕のマンションに遊びに来た時には、「少しは片付けろよ。ラジオで、山川君は無茶苦茶散らかった部屋に住んでます、ろくなものを食べてませんって言っちゃうぞ」と言われた。
初台にあったその仕事部屋のマンションには、鮎川誠、パンタ、それに渋谷陽一がよく遊びに来てくれていた。
僕が『an・an』のインタビューで好みの女性のことを聞かれたのを読んだ時にはひどく叱られた。
「おまえが髪の長い女性がいいとか優しい人がいいとか、どうでもいいよ。あまりにもくだらない。ああいうインタビューは今後二度と受けないように」
こちらが相談を受けることもあった。FMで人気DJだった彼にテレビ番組のキャスターをやらないかという打診があったのだ。どう思うかと聞かれ、即座に僕は答えた。
[https://x.com/sanpuhan/status/1948822614132351320/photo/1]
渋谷陽一に「急いでロックライクな小説を書け」と言われて書いたのが山川健一『さならの挨拶を』(『海』昭和56年8月号)だったのではなかろうか。[掲載誌が散逸して見つからない]
吉本さんの文芸時評『空虚としての主題』[雑誌『作品』創刊号(昭和55年11月)から1年間の予定で始められ7回目で掲載誌休刊後の8回から12回までガリ版で続けられた]の「物語を超えて」の回でとりあげられていた。
わたしたちはこういう[トルエンを吸った酩酊状態の=引用者注]描写のうちに、大げさにいえば滅多に出逢えないような、稀な輝かしい作品体験をしている。つづめていえば、描写が作品の物語の枠組を、真正面からのり超えて行く場面の体験なのだ。このいい方はもっと拡大して現在の文学作品が、物語性を真正面かのり超えてゆく現場の体験といってもいい。またその臨場感といってもいい。[中略]この作品では、物語の方が遅れてあとから「ぼく」のトルエン吸引者に特有な病的で薄弱で、萎えてしまった不安な判断や表象の行方を追いかけ、かろうじて追いつく。それが作品体験の実体なのだ。作品は筋書き的な要約を、作品自体によって拒絶できている。しかもけっしてはじめから物語を拒否してつくられているわけではない。たしかに、保護司や、庇護者ぶってもと恋人の早代子と同棲している早代子の教師村石に象徴される通念の倫理に、弱々しくトルエン吸引にひき籠ってしまう病者の倫理で拮抗しようとする「ぼく」の〈信念更生〉の空しく優しい物語を紡ぎ出そうとして、作品はつくられている。それにもかかわらず物語的な輪郭を要約したうえで作品に触れようとする読者の意図を拒否するだけのものを、この作品は実現している。[中略]わたしたちは作品の倫理として、「ぼく」という主人公の薄弱で優しいトルエン吸引者の病的な自己主張が、イメージと象徴となって溢れてくれるのを甘受する。そこにこの作品の物語性があることがわかる。「ぼく」はトルエンを吸収し、その妄覚に促されて夜中の海辺の美術館に侵入し、早代子の裸体画のまえにやってきて、絵から抜けでた早代子の幻影と語り合い、そして最後にトルエンをコップに注いて、今度は吸引するのではなく、ふたたび目覚めないために飲みほす。それで作品の物語はおわるのだが、作者は物語りを超えてゆくたしかな倫理で「ぼく」という主人公を設定している。見掛けは「ぼく」というトルエン吸引者の弱々しく優しい自己主張の倫理を、さりげなく埋めこんでいる作品なのだが、こんな鮮明でしかも作者がじぶんを超えようとする倫理のはてに造形された作品の主人公を。わたしたちはそうざらに見つけることはできない。
(吉本隆明「物語りを超えて」/『空虚としての主題1986年1月刊』福武文庫、215〜218頁)
前記「小説」と時代背景は数十年違えども破綻した家族関係が背景になっている映画作品を最近になって観た。実在した薬物依存症の女性の日記をもとに映画化された『あんのこと』(入江悠・監督、河合優実・主演、2024年6月公開)の主人公・杏は母親の借金を抱えながらホストクラブで働き、とある事件に巻き込まれて逮捕されたことから、深刻な薬物依存と差しのべられる更生の手立てとが乖離するような現実社会の深みにはまって二進も三進もできなくなったあげくに自死してしまう。
有無を言わさず面倒を見させられた幼児へさしのべる杏の命綱のような心優しい心遣いまでふみにじられてしまった非情な現実になすすべもなく壊れてしまう物語りの底が抜けた倫理のほころびは果てしない。
敗戦後80年になる日本の思想情況について《わが国では思想の根底が問われるときは、体制的か反体制的かが問題なのではない。思想がその原則を現実の場面で貫徹できる肉体をもっているかどうかが問題なのだ》としても、高度情報化の一途をたどる社会でその実体性が曖昧化しつつある「肉体」にかわって《批評の身体性》ともいうべき〈ロック魂〉をぶっつけたような小説がどこかで書かれたり、あるいはライブ演奏で弾けたりしているのだろうか。(2025年8月1日/5日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(43)あるいは軒端からの眺め��
「言葉の通り道があって、それを外れたら言葉が言葉として
の力を持たない。」(尹 雄大@ツイッター改めX)
これまで吉本さんを論じた本をほとんど読んでこなかったのに、Googleアラートで吉本さん関連情報のチェックだけはしてきている。かなり前に見かけたのが「思想家 吉本隆明を建築にしたら?(ChatGPT)|北原 武 - note」[思想家 吉本隆明を建築にしたら?(ChatGPT)|北原 武 - note」]というAI絡みのネット記事。吉本さんの思想を、1階層:「沈黙の広間」/2階層:母型の回廊/3階層:「言語のラビリンス」/最上階:「大衆の屋上」という建築構成に見立てられているだけでなく、タイトルに「言語未満の塔(The Tower of Pre-language)とあるように手で触れられるような物理的な建物化の試みになっていた。
吉本さんと「建築」といえば、第二次大戦敗戦後の〈身体〉を生き抜くような散文で書かれた「固有時との対話」という詩を読み解く〈キーワード〉の一つになっていたことが思い浮かぶ。
従来の検索キーワードを使ってサーチエンジンでヒットしたネット記事の内容をひとつひとつ調べたりしていた代わりに、AIを使ってーー例えば〈固有時との対話〉と〈建築〉に関連するネット情報などーー網羅的に調べたリソースを読み込んだレポートを作らせたりすることもできるようになった。
プロンプトに問いを入力後数分待ってAIが作成した八千字余りのレポートを読めたが、引用元も明示しながら文章化された手際の良さにあっけにとられそうな著作権はどうなるんだろう?
もし吉本さんが読まれるようなことがあったとしたら、「自由に見えるけど実は不自由な言葉」と言われるかもしれない。
如何なるものも自らの理由によって存在することはない しかもわたしはわたし自らの理由によって存在しなければならない 生存がまたとない機会であると告げるべき理由をわたしはもってゐなかった しかも既に生存してゐることを訂正するためにわたしの存在は余りに重く感じられた わたしの魂はすべての物象のなかに風のやうに滲みとほつてしまひ わたしの影もまた風の影のうちに一致した わたしはただありふれた真昼と夜とを幾何学の曲線のやうに過ぎてゆくだけであった ひとびとが実証と仮証とをうまく取ちがへてゐるその地点を!
(吉本隆明「固有時との対話」)
〈未だ書かれない余白を宿運のやうに背負〉う身体の存在の影としての〈建築〉あるいは〈空洞〉を、いま・ここで生きている現実に投影したらどのような場が生じるか。そこが自らの〈身体〉を踊らせるような〈余白〉になりうるだろうか。
言ひかへるとわたしは自らの固有時といふものの恒数をあきらかにしたかった この恒数こそわたしの生存への最小与件に外ならないと思はれたし それによってわたしの宿命の測度を知ることが出来る筈であった わたしは自らの生存が何らかの目的に到達するための過程であるとは考へなかつたのでわたし自らの宿命は決して変革され得るものではないと信じてゐた わたしはただ何かを加へうるだけだ しかもわたしは何かを加へるために生きてゐるのではなく わたしの生存が過去と感んじてゐる方向へ抗ふことで何かを加へてゐるにちがひないと考へてゐた
(同上)
まだ「固有時との対話」の英訳版はなさそうだが、物質的ではない作中の「建築」の訳語は何とすべきだろうか。「structure」や「framework」だと物理的な構造や制度のような肌触りになってしまうから、日本語の響きとしては具体的に触ることのできない〈〜道〉に近いような「architecture」が適確ではないだろうか。
著者自身が「解説 背景の記憶」で《詩はたぶん間違った表現なのだということだ。言い換えれば詩は詩を書くものの生の表現と無関係でもなければ関係でもない仕方で書かれてきている。生の多角性と無関係であり同時に全き関係であるような詩は可能か》と語られた文中の、「詩」を「庭」に、そして「書く」を「作る」に読み替えたくなるような作庭本の復刻版があった。
《デレク・ジャーマンの庭》を本で眺めただけなのだが、おそらく彼の生存の余白、あるいは生と死、または希望と絶望の間で交わされた〈対話〉の痕跡をとどめているのではないだろうか。
エイズの診断を受け、死が目前に迫るなか、原発を望む荒涼としたダンジネスの荒れ地でプロスペクト・コテージの庭を築いたのは単なる造園行為というよりーー過酷な自然を舞台にした死にゆく身体への抗いーー生を肯定する強い意志の表出、創造的なエネルギーの最後の発露だったにちがいない。
第5[フィフス=ルビ]クォーターにあるぼくの楽園は年ごとによくなっていく。
空青く
庭の日時計花壇は
横道を示す。
日の出を守り
日の入りを記し
西の地で。
ぼくの花壇は眠らない。
星座のもとに寝そべりながら、
時の調べを聞く花壇、
偉大な祖先の言の葉を、
ストーン・ヘンジをドルメンを。
花壇は笑う、そう、笑う
ウワサ話を囁[ささや=ルビ]いて。
賢いミソサザイ、
頭を傾[かし=ルビ]げて、
聞いている。
馬鹿は口先だけで生を歌い
あっという間に風に消える。
くだらない。
ほんとそうじゃない。
時計のゼンマイ壊れても、
針の電池が尽きるとも
時の砂は尽きはしない。
死の恐怖をも拒絶する。
カメラとともに立とうとも、
フィルムはついに解[と=ルビ]けていく。
死ぬよりほかになにもない?
生のラッシュはすぐ終わり、
再び見ようと待っている。
時は漏れて流れ出す
十二使徒が踊ってる。
(以下略)
(デレク・ジャーマン[著]ハワード・スーリー[写真]山内朋樹[訳]『デレク・ジャーマンの庭』創元社、2024年4月刊、72〜73頁)
荒涼たる地平のコテージを取り囲むように植物を育て、廃材や漂着物をアートとして配置する行為は季節の移ろいとともに変化し、無菌的な病室から離れたデレクの身体を躍動させる感情や思想を形にする場となったようだ。たとえばーー身体を通じて人間の初源生を極めようとするーー最上和子の舞踏の舞台みたいに。
見てのとおり、この庭は思ったよりも野生の庭だ。ぼくはこのやりかたを強くおすすめする。芝生を捨てて、棘[とげ=ルビ]のあるセイヨウイラクサや道端の草花をとり入れよう。たとえば、ブルーベルやナデシコ、オルキス・マスクラ、キンポウゲの群生ーーこうした繊細な見た目の花を(とはいえ、この辺りを歩き回ってもそんな植物は見かけない。7月はひどくて、ただフクシアの砂漠がひろがっているだけだ)。この本を読んだ人は庭の片隅でこの野生を試してみてほしい。きっと幸せになるだろう。
この夏、流木で覆った新しい椅子をいくつかつくるつもりだ。
蝶[ちょう=ルビ]の話に戻ろう。この庭にはクジャクチョウ、ヒオドシチョウ、ヒメアカタテハ、それからヨーロッパアカタテハの群れがやってくる。なかには怖がらずに指にとまる蝶もいるから、座って、息を殺してみて。やがて蝶は飛び立ち、家のまわりを素早く飛び回るので見失ってしまうかもしれない。マキバジャノメが草むらをあちこちへ吹き流されてひらひらと飛び、そして青い、青い蝶が‥‥‥。
(『前掲書』105頁)
デレク・ジャーマン亡き後の庭がどうなったのか知りたくてAIに調べさせたのだが、リサーチが終わったらレポートしますと言ったまま‥‥‥、詳細はわからなかったが存続していることだけは確からしい。たまたまシステムがトラブったのかーーなんだかAIに余白のまま放り出されたようなあしらわれかたになったが、身体的なけじめがつけられないAIならではの中途半端な放棄のしかたもアリだろう。残された余白で自らの身体を踊らせるようなことができればよいのだ。
明確なコンセプトによるジル・クレマンの《動いている庭》ときわめてプライベートな《デレク・ジャーマンの庭》とはまったく違った眺めのようで、いずれもメインとなる1・2年〜多年草の植栽が広がる庭の辺縁が[両著書収録写真を見る限り]はっきりしないーーおそらく初めから構想されていないのではないか。
日本の民家の庭から大名由来の庭園までのほとんどにおいて主立った眼目とされてきている[松などの]樹木や[自然な]岩石の類が排除されているというかーーあらかじめ入り込ませるような余地がない。世の東西における気候や風土の違いだけでなく、同じく自然観の相違によるのかもしれないが、庭と土壌を同じくする構造物としての住居との接続感にも身体的な感覚差が生じそうだ。
利己的な暮らしの農作業だけでなく料理や和裁など利他的な骨格も併せ持った民家暮らしぶりーーそんな祖父や実家の祖母の後ろ姿もずいぶん遠いものになってしまった。それぞれの家構えは違っていても、縁側に続く庭木や庭石から構成された軒端のあわいで「山川草木悉皆成仏」に連なるような道に家禽や家畜などもともに歩ませたりしていたわけだ。
動物の骨格は家の骨組みを連想させるが、家の梁とは異なり、骨はそれ自体で安定した構造物とはならない。生きている動物では、弾性のある繊維でできた靭帯で、それぞれの骨がつながっている。骨は筋肉を固定するポイントにもなっていて、体が休息しているときでも、筋肉は骨格を支えるのに十分な緊張状態を保っている。体を支える構造物である骨格は、また、神経中枢を保護するものでもある。頭蓋にすっぽり収まっている脳は、骨の壁によって衝撃から守られる。神経中枢は背に沿って延びる骨髄の中を走っているが、骨髄は、間隔があって柔軟性に富んだ脊椎の管に収まっている。脊椎が連結構造になっていることで、背を自在に動かせるだけでなく、骨髄から、体全体に情報を伝達する神経が枝分かれしている。神経中枢が骨格で保護されているのは、脊椎動物の特徴である。それ以外の動物では、タコやコウイカといったいくつかの頭足類だけが、同じ機能を果たす軟骨の「頭の骨」を持っている。
(ジャン=バティスト・ド・パナフィユー[著]パトリック・グリ[写真]『骨から見る生物の進化:EVOLUTION【コンパクト版】』河出書房新社、2017年11月刊、28/30頁)
取り出した何枚かの自作図面を見比べた棟梁は、これが“大黒柱”の位置が決まっていていいと選んだ他は見向きもされなかった。持参した手附金で材木を買わせてもらうとも言われた。まだ出来上がってもいない家の骨格を見通されているような気がした。
あれから半世紀以上が過ぎて独り住いになってみると家族構成に合わせて購入した建築敷地の造成前の田んぼことまでが思い返されたりする。
若くして結婚して子を授かり家まで建てたりすると、年取ってからの住まいのことなど考慮せずに、何もかも若気の至りみたいな勢いでやってしまったことに気づかされる。
30代半ばに県内での人事異動先の職場の同僚から、人生でするべきことを三つとも二十代で終えてしまってこの先何も残っていないね、などと声掛けされるほど“持ち家”が一人前の世間体の習わしとするような富山県人気質とは無縁だった。
田畑で作物作りする田舎の暮らしがもたらしてくれる何もかも捨てて、郊外で暮らす一介の賃金労働者になった気分だった。何もかも買って食べるようになって、米や野菜だけでなく漬物や豆腐などの加工食品まで埴生の暮らしとはいささか味が変わってしまった。なんとなくことの成り行きを象徴するようだった。母もなんだか不味くなったねと言ったりしたが、米や野菜を育てて調理して食べるところまでおそらく食材を吟味してきたであろう祖父は何も言わずに食べてくれていた。
幼い頃の田舎暮らしの記憶に、近所の冠婚葬祭などの仕出し料理に出かける祖父の後ろ姿がかすかに残っている。後妻と死に別れる前から日々の食卓も賄っていたようだから、ハレとケの料理をいつどこでどうやって習い覚えたのか、具体的なことはさっぱりわからない。おそらく明治中頃の大阪での丁稚奉公あたりに何かありそうだが、とにかく祖父の自分語りは聞いたこともなかった。
年季明けで出戻った郷里に近い村で三反百姓と商売を両立させるような民家を建てるまでになったようだが、どうやら鈍らせることのなかった料理の腕を誰かに伝えようなどとしなかったようだ。
植民地だった朝鮮総督府勤務中に33歳で殉職した一人息子にも教えていなかったのではなかろうか。おそらく確かな料理の腕を持ち帰った村の暮らしで近隣からの信頼も育まれ、何かと暮らしの便宜を図ってもらえたりしていたことであろう。いちがいもんで喧嘩早いところなども宥めすかされたりして、いいようにあしらわれていたような‥‥‥、おぼろげな幼い頃の記憶の切れ端から夏場の川釣り魚を料理してくれた無類の魚好きな姿が浮かび上がってるきたりする。
漁師と魚屋と動物学者は、こんにち、2万、5000種以上の魚を確認している。これは脊椎動物の半数近くに相当する。魚類の分布は水のある環境に限られるとしても(陸生の魚は存在しない)、その種類はきわめて多い。しかし、そのいずれもが、魚であると容易に見分けがつく。つまり魚とは、ひれと内骨格を持ち、水中で生きる動物である。動物学者にいわせれば、この定義は進化の歴史を反映していない。最も多い魚は、サケやオニカマスのような硬骨魚で、その特徴は骨の骨格を持つことである。しかし魚に似た別種の動物も存在する。魚と同じように生活しているが、体の構造と歴史を考えると、硬骨魚類とはとうていいえないのである。研究者たちは「魚」という名称を放棄しなければならなかった。現在の分類では、動物のカテゴリーとして「魚」はもはや存在しないのである。
「魚」の名称の消滅を理解するには、古生代初期の、脊椎動物のさまざまな系統の起源までさかのぼらなければならない。初期の脊椎動物は魚の姿をしていて、軟骨魚類と硬骨魚類というふたつの異なるグループの祖先であった。軟骨魚類にはこんにちのサメやエイが含まれ、骨ではなく軟骨の骨格を持つ点で他の魚と異なる。鱗[うろこ=ルビ]は象牙質でできていて、歯のようにエナメル質におおわれている。鰓[えら=ルビ]の裂け目[鰓裂]は直接外に開いており、鰓ぶたにおおわれていない。
(『前掲書』70頁)
自分も祖父の魚好きをひきついでいるような気がするが、その食べ方まではとうてい真似ができない。祖父が煮魚や焼き魚などを食べた皿にはまるで骨格標本のような姿しか残されていなかった。まるで猫がしゃぶり尽くしたみたいに。もし田舎から移住してきた郊外でご近所馴染みになったMの寿司との縁があったとしたらどんなによかっただったろうか、などと亡くなった後で思い返したりもした。
祖父は虚弱な孫に干したヤツメウナギを焼いて食べさせたりしたが、あれはウナギどころか偽の魚の味しかしなかったような記憶が残っている。まだ魚のほんとうの味がどんなものか見当もつかない年頃だったろうか。
祖父自家製の“黒作り”の初物食いは、いったいこれはなに?!‥‥‥だったが、ご飯にのせて食べたりしているうちに好きになり、やがて日本酒の肴にもってこいの一品になった。
新鮮なヤリイカを細かく切った身を、あらかじめ取り出して塩をしたイカ墨で和えれば作れるのだが、祖父みたいにやったことはない。好物なのを知っていた妻は“ホタルイカの沖漬け”などと一緒に時々買ってくれていたが、独り身になってからはーー減塩食を言い渡されているからだがーー買って食べたりしなくなった。
たまたまNHK・BS「六角精児の呑み鉄本線・日本旅」を観ていたら、富山地方鉄道で立ち寄った魚津の居酒屋では、女将さんがのどぐろ[アカムツ]のことを「神魚」と紹介していた。当て塩して焼いた鰭から先に食べると美味しいのよ、などと女将さんが講釈していたが、夏の鮎の塩焼きの食べ方に似ていなくもない‥‥‥、となんだか香る魚とも書くアユを食べたい気分になった。
おそらくご近所馴染みの寿司屋のカウンターに座ればいただけるであろう今日この頃だが、とてもひとりで出かける気になれそうもない。晩年の母がそうであったように、亡くなる前の妻もMの寿司の暖簾をくぐることを遠慮しがちになっていった。いつも家族一緒にもてなしてもらったハレの場だったから、老いて我が身を退かせるようになったのだろうか‥‥‥、老いた自分にもなんとなくあてはまるような気がしてきた。
いつのまにかあとを引き継いだように常連客となった娘夫婦の話では、大旦那もすでに引退されてしまい、あと数年で若旦那もお店をたたまれるらしいとのことだったが‥‥‥。
高屋敷〜高原町界隈からかけがえのない食文化の拠点が途絶えるような気がして‥‥‥残念至極。足繁く通っていた頃はこんなお店こそテレビの「情熱大陸」や「プロフェッショナル」で取り上げてもらいたものだなどと思ったりしたこともあったが、今さらそんなことはどうでもいい。
出前をオーダーしたことは数えきれないほどになるが、お店のカウンターで素材と対話したみたいに出される若旦那の四季の味わいの数々で豊かな時間をーー半世紀以上にわたってーー過ごさせてもらってきた。和食とは?、おいしさとは?、‥‥‥そんなことより何よりも〈料理し・食べる〉ことはーー自立して生きることーーそのものではないのか。
祖父の口から美味しいとか旨いということはほとんど聞いたことがなかったように思う。よい塩梅じゃとか、いい塩梅じゃなどと言いながら食べていたような記憶がある。
埴生の田舎暮らしで寒さを迎える頃になると決まって、畑で採れた蕪や白菜を使って、祖父は蕪寿司を、母は朝鮮漬けを仕込むのが習わしみたいになっていた時期があった。具に使う魚は鰤じゃなくて鯖だったようだが。
母は漬かり加減を見計らって食べごろにならないと卓袱台に出さなかったが、祖父はもう少し待ったほうがいいような漬かり加減のものからとり出してきて食べるのが常だった。というわけで祖父の蕪寿司は漬かり加減が最も美味しくなる頃に底をついてしまい、母の朝鮮漬けは漬かり過ぎて酸っぱくなるまで味わうことになるのだった。それで酸味やとろみを好むように育ったのかもしれない。
ちゃぶだいの上に飯がのった
煮付けた大根がのった
目刺しがのった
トマトがのった
ちゃぶだいの前に男が座った
女と子どもたちが座った
沈みかけた太陽と
遠い海と
隠れた権力者と
さまよい続ける兵隊が
ちゃぶだいをかこんでいる
指と爪の間に詰まった土をそのままに
女の子が飯をよそう
ちゃぶだいの畑で
言葉は物言わぬ種子
[中略]
日々の汚れた皿が
永遠の水にすすがれている
今日のささやかな喜びが
明日への比喩となる
永瀬さんのちゃぶだい
(谷川俊太郎「永瀬清子さんのちゃぶだい」)
自家製の漬物などは浅漬けから古漬けまですべて、それぞれ取り出した頃合いがとにかくちょうどよい加減として食べさせられてきたような気がする。
米だけでなくナスやキュウリやジャガイモやサツマイモそのほか収穫年の出来具合が良かったり悪かったりする食材も、それなりの調理で味を整えていただければそれで塩梅よしとするような食生活から暮らしの道筋をたどりはじめたのだ。
田畑で育てた食材を料理してちょうど良い加減の食事を保つことは、生きのびるるために身体的な稽古をしていることにもなるのではないか。[下線部傍点]
テレビやネットで見かけたりする食材の育ちそのほかを無視したような、ひたすら美味しさだけを追い求める食事のありさまは、身体にとって片手落ちな稽古にしかならないのではないか。(2025年8月29日記/9月2日Web公開)
続・本の一言:街道と民家(44)あるいは〈血〉と〈海〉のあいだに��
「ていうかお前/めっちゃ米炊くの/上手くない?
〈うめー〉
〈なー〉
魚焼くのも/上手いしょ」
「俺/炭焼き小屋の/息子なんで!
〈どやさ!〉
〈なるほど!〉
料理は/火加減!」
(吾峠呼世晴「第134話 反復動作」/『鬼滅の刃16 不滅』)
かけがえのないMの寿司では若旦那が食材と対話するような市場での仕入れからはじまって、お客の好みにあわせたみたいにーー舌や胃袋だけでなくときには懐具合までもーー訪れた時節を味わうような品々をいただいてきた。海の幸や山の幸はもちろんのこと、旨いものは旅をしないというが、内外各地の“初物”にもであえたり、おかげで高屋敷に住みついてからの食生活がより豊かなものになったような気がする。家族みんなで心躍るような満足感を味わえるひとときを繰り返し愉しんできた余韻は消えそうにない。
思いだすのは大旦那の大根の千切りの包丁さばきーー刺身の「つま」というより「けん」がふさわしいーーの見事だったこと。あれだけは真似ができないとつぶやく若旦那の姿など‥‥‥、変わりネタとしては、大根寿司とか昆布で〆た鯖の棒寿司とかも忘れられない。
食についてはいいことばかりでは済まされないように、なんとも首尾のよくないもてなされ方を味わった出来事もあった。
結婚式らしいことはしなかったのだが、双方の数少ない親戚に挨拶がてらの新婚旅行をしたときのこと。旭川を経て東京で会った従兄弟を誘って通りすがりの銀座の料亭でお昼の暖簾をくぐった。二階のお座敷に案内してくれた年配の着物姿の仲居さんから「ここはあんたたちのようなひとがくるところじゃないのよ」と開口一番‥‥‥、面食らった従兄弟は小声で「‥‥‥出ましょうか」などと腰を浮かせかけた。旅先で不自由しないようにと母から三十万円あまり懐にしていたから、大丈夫だから食べていこうと座らせた。
普段口にできないようなハレのお昼にするために入ったような料亭だから引き下がることなどしないで、仲居さんの言葉を聞き流すように運ばれてきた料理を黙ってたいらげた。煮豆のたぐいまで美味しくてーー田舎育ちの二人にとってーー老舗の割烹料理とはどういうものか一度は食べてみたかったのだ。
未熟性とは、私たち人間が「必ず持ちあわせていながら、けっして直視しようとしないもの」です。そして、この私たちが必死に背を向け続けている「自分のなかにある未熟性」こそが、実は、鬼滅の刃における「鬼」の正体であると僕は考えます。
鬼の始祖である鬼舞辻無惨の「血」を注入されると、人間は「鬼」に変貌します。「鬼」になった人間は、爆発的な身体能力とともに、不死性を獲得します。しかしながら、これは表面的な変化に過ぎません。人間が「鬼」となることによって生じるもっとも大きな変化は、その人間が持っていた幼稚性や未熟性(そこには往々にして、その人間が抱えていた無意識レベルのトラウマが含まれています)が強化され、前面に押し出されてしまうことです。
(名越康文「「鬼」は人間の「未熟性」の象徴である」/「第2章 鬼と鬼殺隊」/『「鬼滅の刃」が教えてくれた傷ついたまた生きるためのヒント』宝島社、2021年10月刊、37頁)
世間知らずで予約もしないで入ってきた“一見さん”の三人に対して仲居さんの老舗意識がーー敷居を跨ぐにはあなた方は若すぎるからもっと世間的に一人前になってからいらっしゃいーー言わせたのだろうが、帰ってから調べてみたら確かに京都のH作から暖簾分けした「板前割烹」ということだった。あれ以来、仕事での接待はしかたがないとしても、ふだんは割烹料亭を敬遠するようになってしまった。
一昨年と去年の入院時の病院食が喉を通らないような身体加減に困り果てていたが、退院後の半自炊生活でようやく食欲ももどってきたようで、ふつうの食生活ができるようになったことが大変ありがたいことにおもえる。
頭[精神科]に続いて心臓[循環器内科・心臓血管外科]と二年にわたる身体的異変で、〈食〉だけでなく日常的な立ち居振る舞いすべてができなくなって途方にくれたりすると、よく眠れてふつうに呼吸できること、食べられること、排泄できること、立って歩けるようになること、階段を上り下りできることなど、ひとつひとつができるようになるにつれーーそのありがたさに身体的自然も感じるがーー生老病死の辛さも稽古のように一歩一歩、着実に気を入れて前に進むしかない。そうすれば苦も自分に自然であることのありがたさを教えてくれているようだ。
やせ細った両脚のことだが、切開してバイパス用の血管を取り出した右脛の方がなんとなく太くなってきたようだ。足指を閉じたり開いたり“ぐーぱー”をやってみたりすると、握力は右に比べて左の方が弱い気がする。立ったりした時にふらつくようで不安定なこともある。
それで気がついたのだが、左右の足の親指をそれぞれ人差し指にくっつけるようにするとしっかり立てるようだ。下駄を履いたときなど、鼻緒を指の間に引っ掛けるだけにしたり、両指で鼻緒を摘むようにしたりしてみると、その違いがよくわかる。「みちのく山道」に乗ったりしても足指が突起物を掴むような握力がはたらくようだ。
鬼舞辻は血を注入して鬼を生み出すとき、「これでお前も日の光の下には出られなくなった。俺の気持ちがわかるだろう?」とは絶対に言いません。「お前は強いくなった。」「お前は人間を超えた」と言い続けるのです。
陸に上がって生活するようになった哺乳類は、もう二度と魚たちのように自由に海を泳ぎ回ることができなくなったわけですが、私たちが普段、その劣等感を意識することはありません。むしろ、自分たちは海の生き物より進化した生き物なのだと思い込んでいる。鬼舞辻の配下の鬼たちは、それと同じように、自分たちが「弱い」存在であることを知らない。唯一、鬼舞辻だけが、「弱い」ことを認識しているのです。
(名越康文「「弱さ」を基軸にした「悪」の可能性」/「第3章「究極の悪役」としての鬼舞辻無惨」/『前掲書』宝島社、2021年10月刊、126〜127頁)
術後数ヶ月で自転車に乗ってもいいかどうか、かかりつけ医に両手の握力を計られたことがあった。30にも届かなかくて握りこぶしもしっかりできない状態になっていた。
それで手指遣いにと触り始めたギターのピックを指先ではさむのではなく、親指を除く四指を握り、人差し指の第二関節の上にのせて親指で押すようにはさめば具合がよいことに気づいた。と同時に握りこぶしの秘訣もわかったのだ。
たとえば真言密教で結ばれる印のひとつである「蓮華拳」に似ていなくもない[参考:仏像の鑑賞は”手元”から!:密教の印を知ろう(Discover Japan)]。ピックを外した親指の先で人差し指の第二関節を押すように握れば、その下になる小指が肘をぬけて体幹とつながった握り拳になり、しっかり面が決まって正確にサンドバッグを打てそうな感じもするから不思議だ。家のどこにもサンドバッグなどぶら下がっていないから、手足をハの字とソの字に構えてシャドウボクシングの真似事で実際の感覚を試したりしている。
実際、手術しても薬物的な治療にしても、近代医学の治療の多くは、「部分」の治療をしたり強くすることは得意であっても、「全体」をコントロールすることは苦手です。
僕は自分のクリニックを開き、4年の間自分なりに必死に治療をやって、5年目に疲弊し倒れてしまいました。そこで僕は、いくら治療をしても、いやむしろ治療をすればするほど、人が「弱くなる」ということを体験しました。「治療は人を弱くする」というのは、その時に僕が得たーー矮小かもしれませんがーー一種の悟りです。どれほど効果的な治療であっても、人間を全体として捉えたときには「治療」というものは人間を弱くする。これは論理を超えた、僕の身体的実感だったのです。
そして鬼舞辻のやっていることは、そういう意味ではまさに「近代医学的治療」そのものであるように、僕には見えました。鬼舞辻の血によって、鬼は「部分的」には劇的に強くなりますが、「全体」として見たときには、恐ろしいほどに弱くなってしまうのです。
(名越康文「血の交換とドーピング」/「第3章「究極の悪役」としての鬼舞辻無惨」/『前掲書』宝島社、2021年10月刊、128〜129頁)
月に一回の通院と両手の指にあまる錠剤を服用する日々が続いていて、どうにも実感し難い術後の心臓の経過については六割ぐらいの回復状態というのが、最新の検査結果によるかかりつけ医の見立てだった。昨秋の退院の日に手術中のカラー画像を見ながら執刀医でもあったU田先生から説明を受けたときは、こんな状態の心臓がどうやって元に戻るのだろうかと不思議な心持ちだった。
あれから1年もたたないのに後期高齢者の自分に六割がたもの回復力があったなんて、なんだか身体自身が持ち合わせた自然性というより、神秘的な力を宿しているかのようなありがたさを感じる。
その前の年の精神病棟入院時あたりからだろうか。宗教的ではないが霊的な縁みたいな身体感覚がはたらくような場面に遭遇することもあった。
世間から隔離された病棟で身心ともに見境を失った修羅場のような朦朧状態で眠れず、なんとなく病室から廊下に出たところだった。その夜は開け放してあった閉鎖扉のドアチェックに隣室の年老いた患者がしきりにタオルを引っ掛けて何かをしようとしていた。デイルームで言葉を交わしたりすることのあるひとだったから、とっさに「どうしたの、何してるの」と声掛けしたら、そのひとは夢遊状態から醒めたみたいにタオルを外して首に戻した。「睡眠薬を飲んでもどうにも眠れず、さびしいようで‥‥‥」と言い残して自室に消えた。
鬼たちの抱えるさびしさは、その根源をたどっていけば、人間であれば誰しもが抱えている普遍的な感情に行き着きます。それは突き詰めれば、母親の子宮から出て、へその緒を切られたときに私たちの身体が実感したであろう、根源的な「さびしさ」です。よってそれは当然、主人公たち鬼殺隊の隊士にも共通しているものです。
しかし、鬼殺隊と鬼たちは、「じぶんたちが抱えたさびしさにどう対処するか」という対処法において、非常に対照的に描かれています。
(名越康文「鬼の躁的防衛、柱たちの解離」/「第2章 鬼と鬼殺隊」/『前掲書』宝島社、2021年10月刊、43頁)
十数年前に母を亡くしたときは「槽式躁」になったりするようなことはなかったのに、妻の場合に限ってどうして入院する羽目になったのだろう。〈躁的防衛〉だったのかどうか‥‥‥、いまだによくわからない。長らくおさまっていた過呼吸も夏場に来てぶり返したようだ。どんな身心の稽古がよいのやらどうにも見当がつきかねる。連日の暑さのせいか戻りかけていた食欲も減退気味で稽古不足なのかもしれない。こんなときこそ鮎の塩焼きでスパークリングワインを飲みたいもの‥‥‥、などとご近所馴染みのMの寿司をおもったりしていた。
それから数日経った昼前、通院から戻ったところへ娘がひょっこり顔を出した。通院日が前倒しになったことを知らせてなくて、電話にもラインにも出ないものだから心配してやってきたとのこと。異常がないことがわかって、すかさず「今から電話で予約できたら、Mの寿司へ行きませんか」ーーというなりゆきに。夕方迎えに来た娘夫婦の車で出かけたら季節の四品の八寸からはじまって、途中の一品に枝豆を添えて神通川育ちの鮎の塩焼きも目の前に。定番の寿司もいくつか握ってもらい、〆のなめこのお吸い物まできれいにたいらげられるなんて。デザートに呉羽梨の「幸水」が‥‥‥まるで夏バテの食欲も秋になったみたい。
おにぎりが好きでお茶漬けが好きで
チャーハンが好きでオムライスが好きで
おなかをこわしたときは白粥がいちばんで
近ごろは玄米のうまさにも目覚め
モロッコに旅したときは
炊きたてのごはんの湯気と香りを夢にまで見て
(代わりにクスクスで我慢して)
バリ島で棚田に出会ったときはほとんど涙ぐみ
どこだか忘れたけれど遠い旅先で
(パンだってきらいではないのですが)
持参のパウチのごはんをバスタブに浸し
祖父に聞いた日の丸弁当を思い出し
自分は地球人だがその中のアジア人で
またその中の日本人だとつくづく骨身にしみ
(矢野顕子の♪ごはんができたよ♪も好きで)
いつの間にか新幹線の窓から
四季折々の田んぼを目で探すようになり
「実るほど頭の下がる稲穂かな」
ということわざまで好きになってしまった
(谷川俊太郎「ごはんが食べたい」)
お米を研ぐときなど、ゆっくりやさしく円を描くようにすると美味しく炊けるようだ。薪の火加減として祖父母から伝え聞いた《はじめちょろちょろ中ぱっぱ、赤子泣くとも蓋とるな》がいまだに耳に残っている。今日この頃は炊飯器の蓋をする前に氷をひとかけ入れるのを忘れないようにするのも妻がしていたのを真似ているだけだ。妻は揚げ物用にといたころもにも氷を入れていたっけ。
この頃はずいぶん値上がりしたお米を食べさせられているが、パンなどに鞍替えする気にはならない。米へのおもいは、籾殻や米糠が匂い立つような郷愁をともなって、三反百姓のかたわら祖父が生業にしていた精米業をひきついだーー収穫期の精米作業場の忙しさに明け暮れて血もたぎるようなーー母の姿にたどり着いたりするのだが。そんな母の過労がたたったのか、廃業後の体の不調で医者に診てもらったら不整脈だったといっていたのを今頃になっておもいだした。
昨夏の緊急入院直後に循環器内科の担当医師からーー造影剤を入れて動画撮影された心臓の診断画像をディスプレイに表示しながらーー血液を送り出す弁のところで六割も血液が逆流していますね‥‥‥、この血管もずいぶん細くなっていますし、と説明されたときは黙ってうなずくしかなかった。血だけでなく気持ちまで逆流しているようだった。手術以外に手立てはないとしても、そこまでして独居住まいの老いぼれが延命してよいものやらどうやら‥‥‥、死に際に延命措置をしなかった母のことが思い出された。いのちを授けてくれた母からなんと言われるだろうかと。
この「生命の根源にして、同時に生命を死に至らしめる海」という存在は、そのまま母のイメージとつながります。慈しみ深く、優しさに溢れ、愛の根源たる母性、しかしそこに近づきすぎると同化され、自立を阻まれ、自分を見失ってしまいます。
そして「血」とは、先ほども述べた通り、私たちが体内に宿した「海」にほかなりません。「血」は、海から離れて陸上で生きる私たちが、今なお海から自立していない、独立していないことの証です。
私たちの身体をめぐる血液、体液の組成は、海水の組成に酷似しています。私たちは地上に上がったかのように見えて、実は海の水を体内に有しなければ生きてはゆけないのです。何億年もの歳月をかけて陸地に到達したものの、未だに海の支配を受けている。
(名越康文「血の交換とドーピング」/「第3章「究極の悪役」としての鬼舞辻無惨」/『前掲書』宝島社、2021年10月刊、130〜131頁)
『鬼滅の刃』の物語が始まって間もなく竈門一家が惨殺され、かろうじて生き残った妹の禰豆子の命乞いをする竈門炭治郎に向かって、鬼殺隊の水柱・富岡義勇が「生殺与奪の権を他人に握らせるな!!」と一喝するシーンが印象的だった。
さしずめ心臓・血管外科の手術台に横たわったことのある自分などは《まな板の上の鯉》みたいな状況から生き残ったようなものだ。
仮死状態から目覚めたみたいな痛みが続いた術後、ほぼ毎日のような採血その他の検査結果の「異常なし」に、手術で数時間余り途切れた時間を再び生き/生かされつつあることを確認させられているようだった。まだこの世に縁があった‥‥‥とのおもいがーーどうして?、なんのために生きのびるの?なんてことを不問にしたままーーあふれてきた。
「僕たち家族の/静かな暮らしを/邪魔するな」
「僕たちは/家族五人で幸せに/暮らすんだ//
僕たちの絆は/誰にも切れない」
(吾峠呼世晴「第29話 那田蜘蛛山」/『鬼滅の刃4 強靭な刃』)
那田蜘蛛山に攻め入った鬼殺隊に向かって叫んだ下弦の累が守ろうとしているーー配下の鬼たちで構成されたーー五人家族の「静かな暮らし」とはどんな関係のしかたで成り立っているのだろうか。鬼殺隊士の家族を惨殺しておいて守るべき家族関係なんてあるのか。いったいどんな倫理の均衡のもとに成り立つのだろう。
吉本 そういう気がします。つまりそれがどこからはじまるかということはたぶん、共同的な倫理と個的な倫理ーー共同性と個体性の摩擦面というようなものが倫理ですからーーが、外側の条件によってまったく乖離してしまう。まったく矛盾してしまうみたいなことが起こったときは、もうちがう次元で融和する、それ以外にないんじゃないかな。それはそんなに遠くない時期に起こるんじゃないかな。もっと簡単にいって社会的な通念のレベルと自分の実感的なレベルが、倫理的に矛盾している状態があるとします。その状態が極端になっていったときに、どこかで妥協が成立できる範囲内では、そうしていくでしょうが、できなくなるまで矛盾が著しくなったら、たぶん外側からの条件で、全然ちがうところに倫理的な水準が移ってしまう気が僕はしますね。そしてまた融和が成り立つ。矛盾もあるでしょうが、まあだいたいやっていけるみたいな融和です。二つの間でいくらちゃんばらしていても、このちゃんばらで解決がついたというふうにはいかないとおもいます。もっとちがう条件が、身体的な条件か、外側からやってきて、めちゃくちゃに条件が激変しちゃったために、思いもかけない次元でたぶんそれは解決されちゃう。
(吉本隆明 聞き手 島 亨「ハイ・エディプス論ー個体幻想のゆくえー」/『吉本隆明資料集191』猫々堂、2019年12月刊、91頁)
子供食堂や赤ちゃんポストなどの存続は消費社会における家庭人としての身体性が希薄化してきたこととどこかで通底しているのではないか。食べるために働くというより、何かを使うために働くというように。
老人医療や介護保険制度と同じようにその本質的な問題の解決というよりーーとりあえず限定的な給付可能範囲内でーー先送りしているだけなのかもしれない。
家族関係だけでなく職域や地域そのほかさまざまな組織の網の目から抜け落ちた先に何が待っているのか。いたるところにカメラや本人確認システムの網の目がはりめぐらされ、人間の無意識領域までも組織のマトリックスに管理されつつあるような高度消費社会にあって、頼れるのは老いつつある我が身だけ、不可能性としての身体性ーー日常を稽古化しながらーーを探り続けるしかなさそう。
吉本 そうだと思います。精神の働きの領域を自己幻想と対幻想と共同幻想というふうに三層に分ける考えとおなじようにいうと、身体の生理的な層と、身体と精神との両方にまたがっている層と、まったく精神の領域といいましょうか、独立して考えうるという領域、三つの分け方をしているとおもうんです。純粋に身体の動き方の領域があるんだというふうに考えるばあいに。純粋に身体の動き方だけの問題だというふうにいえる領域は、たぶん植物というものとの領域の重なりというもの、そういうことを想定しています。身体の病気、身体と心の病気が重なっている病気、精神だけの病気という分け方をすると、身体だけの領域の下層といいましょうか、そこでは植物の領域と接しているように思います。動物の領域も身体だけの領域といっているなかに、もうほとんど入ってしまっている。人間というのは、動物の中に全部入っちゃっていると考えているのかもわかりません。その下層では植物に接しているみたいにおもいます。その植物的領域がわりあいに成人期以後、多くなって、その比重が大きくなってということなんじゃないかとおもいます。
(『前掲書』59頁)
ここで大まかに分けられている層について、もっと考古的に細分化して自分の身体内の聲を聴くかのように探っていく、というのがさしあたっての身体的な稽古はじめということになるだろうか。なにが見つかってどのような身体操法に結びつくかは人それぞれの稽古しだい、とにかくやってみなければわからない。自立した日常を着込むような稽古が続けられるかどうかにかかっている。(2025年9月23日記/26日Web公開)
続・本の一言:〈対話〉と風向き
《なにか悪いことがあった時、ぼくはまずそれを受け入れる
そして徐々にその状況と和解する
良いことが起こると、ぼくは自失する で、混乱する
だって、そんなこと滅多にないから》ポール・サイモン
(小田嶋隆@ツイッター)
比嘉 加津夫 様
「猫々堂」の大事業を終えた松岡さんがほっと一息ついているであろう高知よりもっと向こう、海を隔てた那覇市の「脈発行所」から、どんな風の吹き回しなのか、やってきた封書を開けた戸惑いと喜び。
松岡さんがときおり寄稿されてきた地元紙『高知新聞』での扱われかたが気がかりだったところへ、『脈』105号で「『吉本隆明資料集』と松岡祥男」特集」を組まれるとのこと。
「待ってました、どんどんやってください」の気持ちは人一倍ですが、「松岡さんとの関わりを中心に書いて」のご依頼に、ハタと気づかされました。お前は松岡さんの人となりについて何にも知らないじゃないか。思わず「謝絶」の二文字がよぎりました。だって、数回の電話以外お会いしたことも、語れるような「交渉史」や秘匿すべき「エピソード」などないのです。購読していた吉本さん主宰の『試行』掲載広告を見て申し込んだ同人誌で〈松岡祥男〉を読むようになったのがそもそものはじまりです。
まず『同行集通信』に『風のたより』そして『怪傑ハリマオ』など同人誌上で拾い読み、商業出版された《単行本》を追っかけ、行間から高知で生まれ育ったリズム&ブルースが聴こえる6冊それぞれ固有の感性で彩られたページをめくってきた矢先に、猫々堂の《資料集》との出会いが待っていました。
そんな途上で、松岡さんの〈表現〉に出会ったときの〈身体感覚〉について触れていた藤井東「『論註日記』(松岡祥男)を読む」(『詩の新聞midnight press(季刊)』no.14.1993年12月刊)があり、それより前に吉本さんの「松岡祥男について」(跋文、松岡祥男『意識としてのアジア』深夜叢書社1985年11月刊)があり‥‥‥といったところです。
東京在住で人間そのものの生き方を根こそぎ問い直す書き手のほかに、とにかく書かれたものそのほか何でも読みたくなる書き手が高知からも現れるなんて!愛聴してきたジャズピアニストで言えば、一夜限りのステージの上手にセロニアス・モンク、下手にアーマッド・ジャマルの演奏に遭遇したみたいな「双手に華」の追っかけファンのひとりに過ぎません。〈購読〉を起点に東京ー高知ー富山を結ぶ〈読む〉三角形がかたちづくる架空の書棚に、吉本さんの著作書誌につづき、松岡さん編集・発行《資料集》の書誌をならべ、吉本さんや松岡さんの〈言葉〉に生涯縁のない人が圧倒的な現実を低次化するような居場所を探し、誰に頼まれたのでもない一方的な関わりかたをしてきました。ですから、同人誌暦豊かな『脈』主宰者のさすがな「執筆依頼」文面に誘われながらも、《吉本隆明資料集》と〈松岡祥男〉のあいだで言葉に窮したというのが、正直なところです。
これを機会に、大風呂敷を広げたようなサイト名も気恥ずかしい「隆明網(リュウメイ・ウェブ)」[サイト読者だけでなく、松岡さんや、京都の三月書房宍戸さんから多大な吉本著作資料情報をいただいております]の更新ログから、時系列で《吉本隆明資料集》アップデート記録を抜きだしてみましょう。
(1)鼎談・座談会�篇:第1集(2000年3月)〜第27集(2002年12月)
(2)吉本さん主宰の『試行』の「全目次・後記」及び「資料」:第28集(2003年2月)
(3)『試行』バックナンバーの一部復刻:第29集(2003年4月)〜第41集(2004年11月)
(4)初出・補遺篇[単行本未収録の著作・講演・対談・談話等を網羅]:第42集(2004年12月)〜191集(2019年12月)[それぞれ収録作品から選びとられた各集のタイトル名を省略]
(4ー1)吉本さんが「身体と心体について」書き継がれた「心的現象論」の未刊となっていた『試行』連載46回分を復刻収録
第56集:眼の知覚論・身体論
第59集:関係論
第65集:了解論 I
第68集:了解論 II
第72集:了解論 III
(4ー2)宿沢あぐり氏による新発見吉本作品収録書誌
第108集:「わたしの地名挿話」(1987年);「『林檎園日記』の頃など」(1988年)
第112集:「岸上大作宛書簡」(1960年);「「ずれ」を生きる良寛」(1992年)
第122集:「「未来元型」を求めて」 樋口和彦・吉本隆明(『プシケー』第8号[日本ユングクラブ会報]1989年6月25日発行)
第126集:「室生犀星」(東京・日本近代文学館・犀星忌講演・1988年3月26日『高原文庫』第3号1988年8月1日発行)
(4ー3)『吉本隆明資料集』第139〜191集/宿沢あぐり「吉本隆明年譜」(1〜24)分載収録年/月・年齢一覧
第139集:1[1924〜1950]零歳〜26歳
第143集:2[1951〜1959]26歳〜35歳
第146集:3[1960〜1962]35歳〜38歳
第149集:4[1963〜1966]38歳〜42歳
第152集:5[1967〜1970]42歳〜46歳
第155集:6[1971〜1974]46歳〜50歳
第158集:7[1975〜1978]50歳〜54歳
第161集:8[1979〜1982.4]54歳〜58歳
第164集:9[1982.5〜1985.9]57歳〜61歳
第167集:10[1985.10〜1987.10]60歳〜63歳
第170集:11[1987.11〜1989.10]62歳〜65歳
第172集:12[1989.11〜1992.4]64歳〜68歳
第174集:13[1992.5〜1994.8]67歳〜70歳
第176集:14[1994.9〜1996.3]69歳〜72歳
第178集:15[1996.4〜1997.12]71歳〜73歳
第180集:16[1998.1〜2000.1]73歳〜76歳
第182集:17[2000.2〜2001.4]75歳〜77歳
第184集:18[2001.5〜2002.11]76歳〜78歳
第186集:19[2002.12〜2004.3]77歳〜80歳
第187集:20[2004.4〜2005.3]79歳〜81歳
第188集:21[2005.4〜2006.9]80歳〜82歳
第189集:22[2006.10〜2008.4]81歳〜84歳
第190集:23[2008.5〜2009.5]83歳〜85歳
第191集:24[2009.6〜2012.3]84歳〜87歳
(5)別冊1:松岡祥男「ニャンニャン裏通り」(2019年12月)
収録書誌
ニャンニャン裏通り[初出:「猫々だより」第157〜167号連載7回分]
村上春樹『1Q84』をめぐって[初出:「怪傑ハリマオ」創刊号]
鎌倉諄誠さんのこと[初出:「怪傑ハリマオ」2号]
吉本詩にはじまる雑話[初出:「怪傑ハリマオ」3号]
「荒野のイエス」にあやかって[初出:「怪傑ハリマオ」4号]
二番煎じの話し[初出:「怪傑ハリマオ」5号]
北川透徹底批判[初出:「怪傑ハリマオ」6号]
北川透の頽廃[初出:「怪傑ハリマオ」7号]
「反原発」は正義か?[初出:「怪傑ハリマオ」9号]
芹沢俊介批判、その他[初出:「怪傑ハリマオ」10号]
あとがき
(6)別冊2:松岡祥男「吉本さんの笑顔」(2019年12月)
収録書誌
吉本隆明と沖縄[初出:「脈」81号]
ある日の吉本さん[初出:「脈」82号]
傲慢な加藤典洋[初出:「脈」83号]
中沢新一編著『吉本隆明の経済学』批判[初出:「脈」84号]
『「反原発」異論』をめぐって[初出:「脈」85号]
言葉の森の歌[初出:「脈」86号]
川上春雄さんのこと[初出:「脈」87号]
吉本さんの笑顔[初出:「脈」88号]
『最後の親鸞』について[初出:「脈」89号]
『アジア的ということ』をめぐって[初出:「脈」90号]
『全南島論』の射程[初出:「脈」91号]
『成吉思汗ニュース』の松岡俊吉[初出:「脈92号]
鶴見俊輔と吉本隆明[初出:「脈」93号]
「川上春雄宛全書簡」にふれて[初出:「脈」94号]
瀬尾育生「〈吉本隆明 1949ー1969〉のための改題」批判[初出:「脈」95号]
言葉の力を信じて[初出:「脈」96号]
北島正さんを悼む[初出「:脈」97号]
『追悼私記 完全版』に向けて[初出:「脈」98号]
「エリアンの手記と詩」について([初出:「脈」99号]
「情況への発言」の背景[初出:2011年洋泉社刊『完本情況への発言』解説]
根柢にあるもの[初出:2012年刊『蟹の泡1』(編集・発行/長谷川博之)所収]
吉本隆明さんと高知[初出:『高知新聞』2013年3月18日号]
「好きにやってください」[初出:2015年筑摩書房刊『吉本隆明<未収録>講演集』第4巻月報]
あとがき
全27集で参加者144名[第25集に収録した『菊屋まつり』フリートーク」の「事後承諾」による「掲載」にたいし北川透と瀬尾育生の2名によるクレーム1件あり]に及ぶ65本を収録した「鼎談・座談会篇」(1)を皮切りに、『試行』関連資料及び一部復刻(2〜3)と続き、未刊行「心的現象論」の復刻(4ー1)と新規一次資料の発掘(4ー2)だけじゃなく、今じゃ入手し難い単行本収録吉本〈対話〉資料の〈初出形〉へ往来できる新道が何本も拓かれ(4)、第139集から断続連載された「吉本隆明年譜」(4ー3)は宿沢あぐり氏がひとつひとつ現物にあたって書誌事項を確かめ、新たな考証と関連文献の参照を注記し、とにかく現物(一次情報)を典拠にしたいわゆる情報の情報(メタデータ)に頼らない画期的な二次情報化作業に拠る日録的な年譜になっている。
(1)〜(4)は吉本著作にたいする〈読者〉としての〈試み〉が成し遂げられた191冊であり、長期《資料集》購読者へのお礼として配布された(5)と(6)は〈表現者〉として、第113集と114集の発行のあいだ[2012年3月16日]に逝去された吉本さんの墓前に捧げられた2冊となっている。
(5)に未収録だが、松岡祥男「読捨ニャンニャン日録」(「怪傑ハリマオ」8号2011年12月20日発行)によれば、ほんとうは「猫々堂主人」というのは松岡家の猫の〈タマ〉[1998年5月18日〜2019年6月28日]で、《資料集》の封入作業などその手のことは松岡夫妻まかせ、ベンチに座っているだけで負けないダブルス・チームの監督みたいな眼差しを注いでいたようです。好物はエビだったようですが、本業のネズミ以外に庭の小動物や昆虫など、捕獲して得意げに見せたり、どのような春夏秋冬を過ごしていたのでしょう。日本海に沿う富山とちがって太平洋に面した高知の冬の寒さは〈タマ〉にとってやわらかかったことでしょう。松岡さんが〈対話〉形式で書かれる〈相の手〉をつとめたりするくらいですから、きっと《資料集》のテキスト打ち込み〈写本〉作業の日々の充実感も共有していたにちがいありません。
窓を[火共=アブ]る愛日 気 蒸すが如し
覚えず 書を抄して灯を灯すに至るを
誰か哀翁と此の喜びを同じくす
硯池浅き処 冬の蝿有り
(『江戸詩人選集 第5巻:市河寛斎 大窪詩仏』 岩波書店1990年7月刊)
たぶん犬は飼っても猫を飼ったことのないであろう市河寛斎(59歳/1807年)が詠んだ「冬温かし」の最終行に「蝿」ならぬ、南国土佐の「猫々堂」の作業PCの傍らで毛づくろいする〈タマ〉が透けて見えるようです。
《広く言えばこの一、二年、ぼくの感覚としては半年くらい前から
日本の天候を考えると風の向きや潮の方向が変わってきたような
気がする。日本の天候現象というのは以前と同じように考えちゃ
いけないんじゃないか。そういった変化のひとつの結果として今
回の震災があったと考えられると思う。》吉本隆明
(吉本隆明「風の変り目ーー世界認識としての宮沢賢治」[聞き
手 編集部]、『ユリイカ:詩と批評』青土社、2011年7月号)
今冬の富山は県内での1月の冬季競技を他県で開催するほど雪が降りませんが、江戸に生活の拠点をおいたまま隔年で越中・富山藩への出仕(43歳/1791年〜63歳/1811年)を繰り返さざるを得なかった寛斎は「雪中雑詩」、「客中記事」、「北海道中」など越中の厳しい冬の自然詠に向きあうように、「傲具詩」や「憶夕」そして「歳杪縦筆」で我が身の内的自然の衰えを詠み、その中間に骨董などの詠物詩を残している。詩作と稼ぎを両立させる〈不安定な安定〉を生きる道すがら、飛騨への旅路で遭遇した農婦の言葉に触発され「窮婦嘆」で富山藩を流れる神通川の洪水被害による農民の窮状を詠んでいるが、地勢的に上流で豪雨があればそれ以上に氾濫被害を繰り返したであろう常願寺川流域の窮状には触れていない。富山藩を致仕した寛斎の没後数十年経った「安政の洪水」で二年にわたって秋の収穫がなくなったり、日露戦争後の不況や人口増加による就職難に見舞われた明治三十年代は北海道への移住者が多く、「天井川にして、日本一の荒廃河川」(『山室郷土史』山室郷土史刊行委員会1993年)の氾濫で荒れた山室江口からも小樽そのほかへ渡ったとのこと。
日本が敗戦する直前、朝鮮半島[京城]から着の身着のまま引き揚げてきた一女一男の母子家族が、明治12年生まれの祖父が独り住まいしていた富山県の西の端(旧埴生村)の兼業三反百姓家で30年余り暮らし、長男の結婚を機に敷地や田畑を売り払い現在の山室[高屋敷]の家並みの端っこの田んぼを買い家を建て一家が移り住んだ。そんな界隈の散歩でひときわ目にとまった母屋のたたずまい。江戸時代から山室江口があった加賀藩の庄屋の家系の山崎家が大きな樹木の陰から見え、そこが『9.11の標的をつくった男』(飯塚真紀子著、講談社2010年8月刊)に詳しい「ミノル・ヤマサキ」の父・山崎常次郎の生家であると教えられたのは、人間存在の倫理的風向きを変えた2001年9月11日の《テロ事件》報道直後に訪れた引越し以来近所で馴染みの寿司屋のカウンターだった。
1886年9月2日山崎家の家督を継げない四男として生まれた常次郎は1909年23歳で自活の道を北海道ではなく、すでに五歳年長の三男鶴次郎の渡米先シアトルに求め、待ちうけていたのが人種差別など苦労の日々だったようだ。1911年東京出身の伊藤ハナと結婚した翌年に授かったミノル(1912〜86年)の建築家としてのその後が前掲書に綴られている。
いかに外地[朝鮮総督府勤務]での稼ぎが内地に比べて良いからといって、祖父が戦前の埴生村から送りだした一人息子が結婚生活5年目で殉職し、5歳と3歳の孫を引き連れ嫁が引き揚げてくることになるなんて思いもよらなかっただろう。発育不良で歩けもしない3歳男児が生きのびるなんて母のほか誰も信じていなかったと、後日近所の婆さんが当人に耳打ちしてくれた小学生の頃には、同級男児からよそ者ゆえのいじめが待っていたが、貧乏一家なりのひとり息子ということで近隣の大人たちからはわりとまともに遇された。いじめを避けるため同級生が行かないのを見越して進学した高校卒業時にはちょっとした手違いが。
会社より国の方が潰れにくいだろうし安定した稼ぎが見込める国家公務員試験を受け税務職の採用者名簿に載っていたにもかかわらず不採用になり、しかたなく金沢国税局に出かけて問いただしても要領を得ず一般職の名簿に回されてしまった。同行してくれた母から、片親で財産や名のある係累もないから‥‥‥と慰められ、みかねたクラス担任がせっかく斡旋してくれた税理事務所勤めもいろいろあって一ヶ月と持たず、菓子折りを携えた母に謝りに行かせたような不始末も。
高卒プー太郎の日々に東海・北陸各地からたらい回しされたように舞い込む一般職各種業務の面接案内など祖父は本など読むな公界を悟れが口癖でいっさい無視、けっきょく当時の住居から通勤可能な一件を選んで面接を受けることに。地方の国立大学の事務では傍系だった図書館の仕事を選んだわけだが、男子職員が居着いて欲しいということで東京の大学の2ヶ月間の司書講習に出張扱いで上京させてくれたり、今じゃ考えられない待遇だった。
引き揚げ児童の身の上を思いやられたのか、富山大空襲の夜に神通川原へ逃げた体験のある女性司書から目をかけられ、教育学部の某先生や、夜間短大に通った3年間では冬の下宿先だったお寺の幼稚園長先生から、地元では近所の遣り手婆さんから幾つか縁談が持ち込まれたり、豪雪の下宿時には老人しか男手がないということで近所の家長が屋根の雪下ろしを引き受けてくれたり、田植え時期や暮れの餅つきそのほか近所や親類縁者の手助けが欠かせなかったその裏で妬み嫉みなどの陰口もたたかれ。
農作業用の牛馬なども飼っていた専(兼)業農家のほか日常生活用品小売店や鋳掛け屋に大工その他自営業だけじゃなく在日家族の仕事も混じった狭い村の暮らしから、都市の郊外暮らしへと引っ越した頃には戦後日本の経済成長も頭打ちになり、引き揚げ里山・田舎暮らしの身体生活感が揺らぐ風向きにさらされて地産地消で賄ってきた生活過程を埋め合わせる外的自然観や内的自然観が変容するサラリーマン世帯暮らしに、話し言葉にも書き言葉にも行きつかないジャズ中心の音楽三昧から読むことにのめり込むように。
一年がかりの説得で納得してもらって売り払ってきた土地に戻りたいと責めたてられた時はなすすべもなかった祖父が引越し三年目の100歳の誕生日を前に亡くなった葬式では狭い自宅が町内の会葬者であふれ、その35年後に介護暮らしから身を引くように亡くなった母はセレモニーセンターの家族葬でみおくることに。花の四月だったがなぜか1960年代半ばの同じ頃に逝った実家の祖母の柳田國男『遠野物語』を読むきっかけにもなった昔語りまで思いだされ涙ぐんだ。
今日もテレビが伝える武漢発の新型コロナウィルス感染報道に、正月に遊びにいった折に祖母が語った「七草なずな、唐土の鳥が渡らぬうちに‥‥‥」が呼び覚まされ、春先の大陸からの黄砂飛来だけじゃなく、翼の間に毒を挟んだ妖鳥[姑獲鳥など]が日本に渡ってきてから落とすその毒も混じっていそうな風向きが、インド洋からアジア大陸経由で日本列島にまたがる気候を変容させ、祖母口伝で覚えた江戸期からの「お祓い言葉」に由来する季節感も薄らいでしまった。
洪水を繰り返し粗米しか育たないような常願寺川水域の大改修が1891年に、次いで用水合口化が1893年に実施され、その後も立山砂防事業として改修が積み重ねられたこの頃では田畑も潤い、鉄砲水の瀬先だった常願寺川縁を河川敷公園とした土手が好サイクリングコースになったり、立山山系を背景にクマやイノシシが下りてきていそうな雰囲気がなきにしもあらず。1969年の集中豪雨被害の3年後、幸いなことに高屋敷に住みついて50年余り豪雪で屋根の軒が折れたり台風で棟瓦が崩されたりしたぐらいだが、ここ数年は日本列島北から南まで地震や豪雨・土砂災害が顕著になり、阪神大震災やとくに東日本大震災以降の日本列島はどこに住んでいても表や裏といった二色刷りの温和な気候をときおり乱す自然災害といった認識を払拭するような天候現象の異変を知らせる風向きに。
吉本さんがどこかの講演で、気狂いじみたファンもそうでないファンもひとしく受けとめる発言をされていたようですが、ファンレターひとつ書いたことのないまま、習慣化していた「猫々堂「吉本隆明資料集」“ファン”ページ」更新作業が無くなってしまい、ただのファン、でもなく‥‥‥なんだか作業PCに向きあう椅子の座り心地もちがってきて、高知の猫々堂の松岡さんが二本指打法[鍵]で収集した吉本〈対話〉テキストを読み解くように打ち込み続けて成し遂げた《資料集》がカバーした吉本著作の歳月(1956年〜2011年)が、本棚に並ぶ『吉本隆明全集』(晶文社刊行中)の間を吹き抜ける風のように映えます。
これまでの歩みを折り返すいきおいで〈老い〉の坂道に抗しながら猫々堂を歩ませ、同人誌時代から培ってきた〈文学する身体〉が渾身で成し遂げた編集・発行作業と、それによって編みだされた『吉本隆明資料集』との間合いに、松岡さん固有の〈吉本隆明論〉がこめられています。話し言葉でもない、書き言葉でもない、なんの規範にもよらない思考の手足による未知の手探りが、未踏の一歩一歩を刻みつつあるようで、さまざまな数値で計測されるような擬似体感では読めず、読者それぞれ固有の〈身体〉感覚がそのページをめくらせてくれるようです。
引用とそれに対するコメントという形で書きはじめられた松岡祥男『論註日記:〈世界史〉と日常のはざまから』(學藝書林1993年10月刊)で日記の有効性を認め「そして、すぐに、これは声のない対話なんだとおもいました。」(前掲書「はじめに」)と語られた地平につらなる〈写本〉の領域に影を伸ばす猫々�堂『吉本隆明資料集』の立ち姿があり、松岡祥男詩集『ある手記』(1982年1月25日自家版)以来37年ぶりの自作冊子『ニャンニャン裏通り』と『吉本さんの笑顔』のあいだに、話し言葉にも書き言葉にもゆきつかなほんとうの「猫々主人」の〈身振り〉があるようです。
2020年2月12日
吉田惠吉 拝
昨年12月10日に逝去された比嘉加津男さんのご冥福をお祈りします。
続・本の一言:「ある編集者」のことなど
《ただ、わたしにも、対話のばあいに、課している戒律はある。〈じぶんを低くすること〉、〈相手をひき立てること〉。この戒律は、わたしの〈書いた〉ものでは、反対に〈確信のあることだけを確信をもって〉ということになる。》吉本隆明「あとがき」(『どこに思想の根拠をおくか:吉本隆明対談集』筑摩書房1972年5月25日刊)
吉本さんの『共同幻想論』(河出書房新社1968年12月5日初版)の序文[全24頁]に、本書執筆を試みた「この間の事情について、まえにある編集者の問いにこたえた記事がのこされているので、それを再録することにする。」に続く21頁におよぶ引用の注記に(『ことばの宇宙』67年)とだけ記され、「ある編集者」が不明なのがちょっと気がかりだった。
川上春雄編集『吉本隆明全著作集11』(勁草書房1972年9月刊)の解題には、「聞き手・編集部』による「対談」とあり、晶文社から刊行中の間宮幹彦編集『吉本隆明全集』第10巻(2015年9月刊)の解題では、「聞き手・編集部』による「インタビュー」となっている。また宿沢あぐり「吉本隆明年譜[1967〜1970](『吉本隆明資料集152』猫々堂2016年1月刊所収)での記載は、後者と同様であった。
『脈』88号(脈発行所2016年5月20日発行)掲載の松岡祥男「『最後の親鸞』についてーー吉本隆明さんのこと(9)」に併載された「吉本隆明対話リスト(1956〜1986)」の1967年(昭和42年)には、おそらく「聞き手の氏名」がないものとしてリストアップされなかったのだろうが、著者からご恵贈いただいた「吉本隆明対話リスト:1956年(昭和31年)〜1986年(昭和61年)」(2019年3月改訂)では「*表現論から幻想論へ(?)『言葉の宇宙』6月号→『共同幻想論』序」と記載され、当該年の「聞き手」不明のインタビューとして載せてあった。
吉本さんと親交のあった谷川雁の「テック」が出していた『ことばの宇宙』の第2巻第6号[1967年6月号]に「表現論から幻想論へー世界思想の観点からー」が掲載され、小田光雄の「吉本隆明『共同幻想論』と山口昌男『人類学的思考』」(『古本屋散策』(論創社2019年5月刊所収)に拠れば、そ当時の編集長が久保覚だったようだ。
「1968年に刊行された吉本隆明の『共同幻想論』には24ページにわたる長い「序」が付され、それが吉本へのインタビューをベースにして構成されていて、本論よりもそのことを記憶している読者はかなり多いのではないだろうか。[中略]吉本による『共同幻想論』のモチーフとコアが簡略に述べられ、また六十年代後半における『共同幻想論』に向けられた視線や理解の動向も浮かび上がる構成になっている。」と評したうえで、「聞き手」を明記せず「ある編集者」としかできないなんらかの事情を勘案し、川上春雄の「解題」での書誌的あつかいや「吉本の出版スタイル」を参照しながら、「もはやここで「ある編集者」=「聞き手」が久保覚だと断定してもかまわないだろう。」と「明記」されているではないか。
1989年夏のほんのひと時だが、吉本さんと講演会場の講師控え室で同室になったことがある。講座「吉本隆明・農業論」の2回目(7月9日)で、主催の世話役の女性に「吉本さんにサインを‥‥‥」と勧められるままにお茶をいただいた教室で、吉本さんは廊下側の座席に腰掛けられ、離れて反対の窓際に立たれた「編集者」とおぼしき人と、講演会場とはずいぶん違った「独り言」でも「対話」でもない口調で話されていた。連れ合いと居合わせた長岡技術科学大学の明るくなごやかな昼下がり、携えた一冊が『言葉からの触手』ではなく『共同幻想論』であったら、著者署名をお願いしながら件の「編集者」についてお尋ねできていたら、なんと応じていただけただろう。
*
2011年1月の「ラジオ版 学問のススメ:吉本隆明(思想家)」[ポッドキャスト:(その1)2011.01.04配信(その2)2011.01.11配信]でインタビュー[聞き手:蒲田健]に応じる吉本さんの肉声が今なお聞けるが、ほかに吉本さんのインタビュー音源のアーカイブなんてあるのだろうか。数ある吉本さんのインタビューの録音媒体の保存等について、立ちあった「編集者」はご存知なのだろうか。
青土社の《全対談集》や深夜叢書社の《インタビュー集成》から時を経て、このほど完結を迎えた猫々堂の《資料集》によって既刊本未収録の〈対話〉が数多く読めるようになった。
小林秀雄が「文章というのものは人間の手足みたいなものだろう。」と話している鼎談「文学と人生」その他を収録した『旧友交歓:小林秀雄対談集』(求龍堂1970年1月発行所収)巻末の「〈付〉戦後主要対談一覧(昭和21年ーー昭和54年)」に記された83件に、不明とされている戦前の対談を合わせたとしても、松岡祥男版「吉本隆明対話リスト」の収録件数にはおよばないであろう。
身体をはった文筆家としての吉本さんの〈時間〉との格闘の過程(表現)は書き(語り)下ろしにとどまることなく、ある時ある場所での〈時空〉の闘いとして、さまざまな対話(インタビュー)や講演(談話)が書き起こされてきている。
《ある指定された時期に、任意の寒々とした部屋で、あるいは多少の飲食と一緒にしつらえられた対談が、時間に耐える仕方みたいなものをかんがえさせる。対話は相対する者ふたりの間にあるのでもなければ、何れか一方にあるものでもない。ただかわされる言葉の緊迫と弛緩のゆれのあいだにある気がしてくる。もちろん「わたし自身」も緊迫したり弛緩したりするものとしての揺れの波形とおなじ次元におかれる。そして時間というものが理念としてみられた対話者を扇形に分散させるように流れ、おなじように、感性や表象や像[イメージ]としての対話者を、おなじ場所、おなじ位置、おなじ資質のところに固定して動かさないことを痛感する。》吉本隆明「あとがき」(『吉本隆明全対談集1』青土社1987年12月17日刊)
おそらく座談会やインビューを含めれば400件を超えるであろう吉本さんの�対話の全てが時系列で集成されたら、〈相対する者ふたりの間にあるのでもなければ、何れか一方にあるものでもない。ただかわされる言葉の緊迫と弛緩のゆれ〉が、即興演奏で時間に耐えるJazzミュージシャンが残したデュオやスモール・コンボによるライブ・コレクションを聴き通すかのように、感じとれることになるだろう。ところで著者(そして編集者)にとって対談とインタビューの違いとは?
《インタビューというのは、慣例ではあらかじめ何々の項目について意見を聞きたいという形で、申し込まれる場合と、即興的にはじまり、その場で出来上がった流れに沿って行われるばあいとある。うまくいかないで、改めて項目をくわえれて、手書きで答えを補足するというばあいもある。ここには何れのばあいも含まれているが、即応するように、どの形式よりも本音の言葉が生々しく含まれているといっていい。校正の過程で、くだくだしいその場の言い廻しを削り落として、できるかぎり判りやすく話の趣旨が露出するようにとこころがけた。でも即応性は消えていないと思う。インタビューの特色は、独白の要素がひとりでに意見(見解)のなかに入りこんでくることだ。しかもそのばあい対話という形式をはなれることができない。この特色のために、意外なほど編み目がこまかく、重たい手ごたえが生まれている。インタビューで問われるのは、知識よりも見識や叡智だといっていい。そして問う方と問われる方とが合作で見識や叡智はつくられてゆく。》吉本隆明「あとがき」(『世界認識の臨界へ:吉本隆明インタビュー集成』深夜叢書社1993年9月15日刊)
戦前の《手習い》からはじまった吉本さんの〈書く〉世界は、日本の〈敗戦〉体験を生きながらえる〈時間〉との格闘の過程(表現)をより深め、1960年代に入って〈情況的な課題と本質的な課題を裏づけながら提出することは、ここ六、七年来、わたしが意識的にやってきたこと〉として、『自立の思想的拠点』をはじめとした評論集に対応する『言語にとって美とは何か』や『心的現象論』が書き継がれ、〈この世界には思想的に解決されていない課題が総体との関連で存在しており、その解決はわたしにとって可能である問題を提起しているようにみえたという契機〉を生きとおした〈時間〉の闘いの枝流が、吉本さんの対談やインンタビューの奥底に流れていて、本流たる思想的過程に呼応している。
この読み(聴き)どころについては、「対談相手が変わっても、話題や論点がその場限りのものではなく、内在的な思想過程がその基底に脈々と流れていて、ひとつの大河をなしているからだ。だから、どんな小さなインタビューでも、ないがしろにすることはできないのだ。それは対話やインタビューに限らず、吉本隆明の〈全表現〉を貫く、著しい特徴」として、数ある対話のなかから選んで1冊の文庫本(『吉本隆明対談選』講談社文芸文庫)を編んだ松岡祥男の解説で強調されている。
とりわけその時々の現実の動きに対するに的確な情況判断と、その意識的問い直しによる考える根拠の持続が吉本発言を追いかけさせてやまない魅力の源泉だが、いつどこでどのように言葉で表現する身体的修練を積み重ねられたのだろうか。
《(1)足並みを揃えない(2)口並みを揃えない(3)すべてを疑えというのはマルクス流の言い草だが、わたしは消極的に、じぶんで確かめないことについては流布された言説を信じないくらいにしておきたい。》吉本隆明「あとがき」(『マルクスーー読みかえの方法:吉本隆明インタビュー集成』深夜叢書社1995年2月20日刊)
文筆家のみならず何事かを極めようとするものにとって言うは易しく、実践するにはずいぶん難しい稽古法だが、その技で鍛えた〈身体〉を術に自在な手足を養い、書き、話し、そして講演する〈姿勢〉が際立っている。
《講演を依頼されると、大抵はすぐ逃げることにしているが、それでも幾つかの依頼のなかで、どうしても行くことになる場合があった。その理由は二つある。ひとつは、まったく私的なもので、この人の依頼ならば、だまされても、誤解の評価をうけてもいいという契機がある場合である。もうひとつは、大なり小なり公的なものである。かって、戦争中から戦後にかけて、わたしは一人のなんでもない読者として傾倒していた幾人かの文学者がいた。かれらが、この情況で、この事件で、どう考えているかを切実に知りたいとおもったとき、かれらは、じぶんの見解を公表してくれず、沈黙していた。もちろん、それぞれの事情はあったろうが、無名の一読者としてのわたしは、いつも少しづつ失望を禁じえず、混迷にさらされた。もしも、わたしが表現者として振舞う時があったら、わたしは、わたしの知らない読者のために、じぶんの考えをはっきり述べながら行こうと、そのとき、ひそかに思いきめた。たとえ、情況は困難であり、発言することは、おっくうであり、孤立を誘い、誤るかもしれなくとも、わたしの知らないわたしの読者や、わたしなどに関心をもつこともない生活者のために、わたしの考えを素直に云いながら行こうと決心した。それは、戦争がわたしに教えた教訓のひとつだった。わたしは、まだ、この教訓を失っていない。》吉本隆明「あとがき」(『敗北の構造』弓立社1972年12月15日刊)
1956年11月23日の「「民主主義文学批判」戦後責任の問題をめぐって」(早稲田大学第3回早稲田祭・同実行委員会)から2009年9月22日の「宮沢さんのこと」(花巻市主催第19回宮沢賢治賞・イーハトーブ賞贈呈式)まで、まるで全国行脚したかのような、日本各地における吉本さんの講演記録が残されている。
350タイトルを超える吉本講演のわずか3本(1987年11月8日、1989年7月9日、1991年11月10日の長岡における農業論)にでかけて聴いたにすぎないが、それでもおだやかな導入からやがて熱のこもった佳境をぬけて質疑応答までの場の響きに魅せられた。用意周到に準備し、典拠とした「資料」を挙げ、模造紙をつないだ手書き「レジュメ」を背に、〈はなし〉のかなめにさしかかって興がのった〈ことば〉が渦巻く語り口があざやかに残っている。1960年代の富山市内で聴いたのだが、颯爽とした詩人の西脇順三郎(黒田講堂)や苦みばしった文芸評論家の平野謙(電気ビルホール)の話しぶりとはずいぶん違っていた。
農業論[二回目]の講演中に「ダイカキ」と聞こえた響きに、あぁ「代掻き」とその場で分かったが、吉本さんが1945年に大学とは別のところからの農村動員の要請により、埼玉県の大里村での農作業の時期がちょうど6月[宿沢あぐり「吉本隆明年譜」(1)」参照『吉本隆明資料集139』猫々堂2014年刊所収]だから、田植えにつらなる一連の作業として体験された可能性まで思いいたらなかった。宮沢賢治の農作業にも似て、吉本さんが「言葉」を紡ぎだされる手作業は、自身の「本」を編む作業姿勢でもあるようだ。
《本を編むのは毛糸を編むとか布を織るとか紙を漉くとかいうのとおなじにそれ自体がさまざまな作成の意図の集まりと重なりであろう。わたしにとってこの書物はなにを編んでいることになるのかと云えば言葉で〈初源〉への〈姿勢〉を編んでいるということになりそうである。〈姿勢〉ということにはさまざまな意味が含まれている。手や足の位置、気分のおきどころ、構え、予防、準備そして終了のあとの間合いなど、すべてが〈姿勢〉に関与している。『言語にとって美とはなにか』、『共同幻想論』、『心的現象論』の軌道のうえで外部からと内部からと、わたしを待ちうけていたものは、それらの軌道を動的に根柢的に揺さぶること(あるいは揺さぶられること)、展開すること、そして収斂させることなどの課題であった。〈姿勢〉はすべてそのことに関していた。わたしは気息を整えてさまざまの麓からひとつの課題へととりつこうとしてきた。ここには道すじが脇道や支道を生みという問題と、あまりに早急にモチーフに直通したために起った行き詰まりをたどり直すという問題と、そのままよそみせず、だが遅々としてすすまない本道の問題とが錯綜している。》吉本隆明「あとがき」(『初源への言葉』青土社1979年12月28日刊)
雑誌のグラビア写真などで見かけた吉本さんの書斎がなんだか独り稽古の道場のようで、そこで〈書く〉ことに取り組まれる息づかいや脈打つ響きをともなう〈身体〉像が、言葉で〈初源〉に向き合うさまざまな作業姿勢を集約しているようだ。言葉を武器に物事に立ちむかい、〈ほんとう〉と〈うそ〉の考え方がが交差し錯綜する場に〈体〉をあずけ、〈身〉をもって〈真〉に至る〈術〉で磨きあげた数々の書物が生みだされた。
そんな著者の「乱取り」ぶりが、〈編集〉という影の立役者を得て、見事に発揮された一冊が『重層的な非決定』(大和書房1985年9月20日刊)であろう。「そのときどきに起こった主題に対応する身体のこなし方をみようとすれば、わたしの理念と感性の本音は、この本のなかにいちばんあらわな形で書きこまれているのではないか。」(「あとがき」)とあるが、未知の読者がふと手にとりみずからの関心事にそうように読みはじめれば、言葉でどこまで〈身体〉を捌けるようになれるか、感性的な出稽古の受け皿となる多層性に満ちている。その一方では頭でっかちな読み手が増えたのか、ツイッターで「読書」を「インプット」などとつぶやかれるほどに〈現在〉は読書から遠ざかり、その身体性も見失われつつあるようだが。[下線部原文傍点]
晩年の小林秀雄とおなじように、多方面にわたる専門家との対話本として、「ただの便利屋みたいな気持ちにならぬよう自分なりに努力したのだが、さすがにおもうにまかせなかった。」と「あとがき」に記された『さまざまな刺激』(青土社1986年5月25日刊)において、「主観的にいえば、激しく動きまわり、さまざまな分野から未知の衝撃波を浴びようとして、こういう対談に進んで出かけていった」(同前「あとがき」)吉本さんの言葉による他流試合のあとで、「まだまだ身体の動かし方が足りないために、対話に応じて下さった諸氏の足手まといになった箇所もたくさんある。こんど未知の対話の旅をするときがあったら、これよりもっといい旅の記録をのこせるように、」(同前「あとがき」)さらに〈対話〉の技を高めた次なる《対話集》の達成をめざす稽古姿勢を未知の読者に向けられている。
《講演》にあたって「たぶんその殆どが事前に書く寸前といえるほど周到な準備がなされ」(「講演メモ」『言葉という思想』弓立社1981年1月30日刊)ていて、さらに数度の手を入れ著作として編まれたようだが、それが叶わない〈著者の没後〉にあっても、吉本さんの〈対話〉を探し求めて編集・発行し続けた「猫々堂」の《資料集》の存在が大きい。
『白熱化した言葉:吉本隆明文学思想講演集』(思潮社1986年10月刊)の背後に、『空虚としての主題』(福武書店1982年10月刊)を軸にして『悲劇の解読』(筑摩書房1979年12月刊)から『マス・イメージ論』(福武書店1984年7月刊)そして『ハイ・イメージ論 I〜III』(福武書店1989年4月〜1994年3月刊)におよぶ〈書かれたものとしての文学論〉が控えているように、『吉本隆明資料集』(猫々堂2000年3月〜2019年12月刊)には『吉本隆明全集』(晶文社刊行中)未収録の〈語られたものとしての文学・思想・情況論ほか〉が収められている。吉本さんが書き言葉と話し言葉による批評性の〈結合〉を試みられた格闘の息づかいやリズムがその〈身体性〉を浮かびあがらせ、双方の言葉を架橋する〈思想〉が〈発語〉する姿勢がきわだっている。(2019年11月25日)